
海幸山幸の猿かに合戦からの玉手箱開封の儀で、かごめかごめをうたう -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(65_『神話論理3 食卓作法の起源』-16)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第65回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第三部「カヌーに乗った月と太陽の旅」を読みます。
これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
今回読むところもとてもおもしろいのであります。
いや、もちろん、基本的にすべておもしろいと思ったところだけを抜書きしているので、つまり、いつもおもしろいのであります。
それにしても、今回読むところはおもしろいのです。ざっくりうと、日本の神話に出てくる海幸/山幸が、いつの間にか猿かに合戦に場面転換し、そして開けてはいけない玉手箱の話になったかとおもえば、「かごめかごめ」になる、というお話。
「最初の夜」
M410 「最初の夜」という神話をみてみよう。
大昔、いつでも昼だった。明け方もなく、夕暮れもなく。
そのため人々は時間を守るということがなかった。
好きな時に食べ、好きな時に眠る。
「明け方」「夜」「太陽」「寒さ」を司る四つの精霊が、自分たちの力を発揮しようと決心し、昼と夜の区別がはじまった。
最初の夜に驚いた四人の人は、それぞれその場に立ち尽くしたり、一晩中身動きが取れない状態になった。
その後、人々は夜に眠り、明け方に起き、決まった時間に働いたり食事をしたりするようになり、すべてが規則正しくなった。
ずっと「昼」の世界である。昼夜の区別がない。
即ち、未分節である。
この未分節は分節と対立する二項のうちの一方の極としての未分節ではなく、未分節と分節の区別さえもが未分節な未分節である。
未分節 / 分節

そもそも視覚が分別識であるからして、視覚によって無分別を分別する、とは・・??
さらにこの「とは」に「である」言語で”答えて”しまう/とは/・・
こんなことをいうと細かいところにこだわるなあと思われるかもしれないが、ここは細かいところであるどころか、大枠、宇宙の摂理レベルの大きなことである。私たちは言葉を発した瞬間に、それがたとえ「未分節」のような言葉であったとしても、すでにその言葉Xとそれに対する非-Xとの区別の中に絡め取られていることになる。
*
さて、未分節。そこでは人間の生活リズムのようなこともなかった。
例えば、朝起きて、歯磨きをして、着替えて、洗濯をして、朝ごはんを作って…といったような多くの人々にゆるやかに共有されるような”規則正しい”毎日のルーティンということが「なかった」。
いつ、だれが、何をなすべきで何をなすべきでないか、ということも二項対立である。
何をなすべきか / 何をなすべきでないか
この区別、二項対立が”ない”ところがぐにゃりと伸ばされて薄く(?)されて、つまり次元を減らして、ある時ある場で誰と「何をなすべきか」と「何をなすべきでないか」の規則が定まった世界へと、モードが切り替わる。
この神話は、規則正しく物事が巡る、天体運動のような、同じ速度で回り続ける時計の歯車のような、規則性の起源神話である。
規則性がない →→ 規則性がある
四項各々離れず
ここでおもしろいのは、規則性がない状態からある状態への転換・切り替えのときに「四」項のセットが出てくるところである。
規則性がない → 四項のセット → 規則性がある
四項とは、ここでは「明け方」「夜」「太陽」「寒さ」を司る四つの精霊である。この四つが順番に交代しながら登場することで、昼から夜へ夜から昼へ、暖かい日中から寒い夜へ、そして明け方の光と、暖かい日中へ、という循環が動いていく。
四つに分かれること。もともと分かれていない=無区別・無分節で、そこに差異がないという意味で「一」であったところから、「四」が出てくる。「一」が一挙に「四」へと広がり、しかも広がったあとのの四極もまた、あくまでも「一」であるということに変わりはない。一にして四・四にして一。

* *
先ほどの神話では「四」は「明け方」「夜」「太陽」「寒さ」と語られていたが、この「四」は何でも良い。他の神話であれば、別の「四」が出てくる。たとえば、びっくりするような話であるが、人間の手足は腕が二本、脚が二本の合わせて四本ある。人間の姿を少し距離をおいて眺めると、人間存在とは「四」が「一」に集まっているもの、である。
この「四」を用いて、「規則性がない →→ 規則性がある」の転換を引き起こそうという時、四が限りなく一つに強く結合されている人の身体が「炸裂する」といったことが起こる。
「すべてが一点に収斂していくようなこれらいくつかのデータから、つぎのようなことが暗示される。すなわち、イロクォイ族および隣接する諸部族の神話は、遠方に向かう企て(戦争のためであれ、婚姻のためであれ、許容されるものであれ、拒否されるものであれ)という概念が、場合により運行する天体や発散する熱い光の出現をもたらすような四肢切断、もしくは身体炸裂という概念と結びつている、南アメリカ由来の諸神話と同じパラダイムに属しているのだ。」
人間は「四即一」のものであるが、どちらかといえば、四に分かれているよりも、一に集まっている方が際立っている。そうであるからして、一に集まっているところを四に分ける方向性を強調するために、四即一の身体が「炸裂」するというような話になる。
例えば、前の記事に取り上げた、神話M406では、主人公の若者とのカヌーの旅から戻った年長のおじの「頭」が、神話の語りの最後に炸裂して、そこから「昼間」が生まれる。
[…]
翌朝、年長のおじは家に帰るべく、カヌーの用意を始めた。
女神は、若者をそばに留めておきたいと思った。
しかし若者は、「いつも親切にしてくれた大切なおじを、ひとり帰らせるわけにはいかない、見捨てられない」と言う。女神は涙に暮れ、若者も泣いた。二人は楽器で別れの曲を奏でた。
若者と年長のおじは、自分たちの故郷に帰った。
そして水浴びして身を清め、老人は自分のハンモックに上がり、身内を集めた。そして「自分は若い頃、今回のような旅をたくさんしたものだが、いまや老い、もう旅をすることもあるまい」というやいなや、老人の頭は破裂し、そこから「昼間の暖かさ」と「太陽の熱」が溢れ出した。
頭が炸裂するなんて、想像するだけでもオソロシイ。。。。こういうのはちょっと苦手だなと思われるかもしれないが、重要なのは「何」が四つに分かれるか、ではなく、四即一・一即四が一に寄っていたところから四の方へと広がるという、この動きである。
「カシナワ族の神話にしても、アマゾニアないしギアナの諸部族、さらにイロクォイの神話にしても、同じ対照的な項の組み合わせを使っている。すなわち、分裂ないし炸裂が、身体の上部(頭)ないし下部(頭のない胴体、腹)にかかわっており、それがいっぽうでは月ないし太陽を、また他方では光のみ、ないし熱のみ、あるいはその両方、またはその反対(炸裂した頭から出てきたヨタカが、光がなく熱がないという欠如的側面のもとに夜を表現しているM396の場合のように)を生み出す。」
南北アメリカの距離を超えて、各地の神話に同じ対立関係の区切りだしをみることができる。
月 << 上部・・・の炸裂 >> 太陽
↑(頭)↑
分離
↓(動体)↓
光・熱がある << 下部・・・の破裂 >> 光・熱がない
ここで「頭」とか「月」というところに注目したくなるところを踏みとどまって、下記のような、切り分けの組み方の方を浮かび上がらせてみよう。
<< 分離 >>
↑ ↑
分離
↓ ↓
<< 分離 >>
二項対立関係が二つセットになった四項関係を切り分けること。
しかも、切り分けすぎて、四項がバラバラにどこかへ飛んでいってしまわないように、適度に集めておいて、付かず離れずの距離感を保つこと。
Δ1 / Δ2
|| * ||
Δ3 / Δ4

この時、Δ1〜Δ2が「何であるか」という問いに答えることは、問題としては第二ステップの話である。
「神話における主要登場人物が、恋多き夫であれ、インセストを犯す兄弟や信じやすい訪問者であれ、あるいは警戒心の強い生娘であれ、その人物はつねに、近い結婚と遠い結婚というふたつの型との関係により規定されている。[…]この体系に介入してくるカヌーの旅は、毎回、主人公を近すぎる女から遠ざける(M406のインセスト的なおば、M149aのコンドルの娘たち)なり、遠い女に近づけるなり(M406のコンゴウインコ妻、M406の美しいアッサワコ)、あるいはその両方、もしくはそれと逆の役割を果たすなりしている。」
Δについて「それが何であるか」と問い、回答文を生成することへと引っ張り込むということは「Δ1はΔaである」式の言表を生成せよということであるが、このような言表の生成が可能であるためには、その前段として、Δ1がある非-Δ1と区別され、Δaがある非-Δaと区別されている必要がある。
神話はこのΔ1がある非-Δ1から区別されてくるプロセス、Δaがある非-Δaと区別されてくるプロセスを、私たちが「言葉で語る」という、”語たちの線形配列のモード”の上においてシミュレートしてみようということである。
あらゆるΔについて念頭に置いておくと良いのは、「それが何であるか」ではなく「それは何と対立しているか」ということである。しかもその対立する相手は感覚的経験的に「ああ、なるほど」と感じられるようなことでさえあれば、何にでも置き換わることができる。なに”であれ”対立さえしていれば、それは神話の論理を動かす軸になりうるのであるからして。
ここで『神話論理3 食卓作法の起源』の「カヌーに乗った月と太陽の旅」に収められた神話M416「ヤバラナ 昼と夜の起源」をみてみよう。
昼/夜
昼と夜、といえば、経験的には所与の、あらかじめすでに別々に分かれており、相互に対立する事柄であるが、その「起源」を語る神話である。
世界が始まる前、男はひとり、女もひとりだけが居た。二人は夫婦だった。
この男女は下肢がなく下腹までしかなかった。
彼らは口から食物を入れ、排泄も喉から出していた。
上半身だけの彼らは生殖することもなかったが、彼らの排泄物から変身してデンキウナギが生まれた。
*
この男女とは別に、超自然的な力をもつ二人兄弟がいた。
+ +
ある日、弟は旅に出て、そのまま帰ってこなかった。
心配した兄は、弟を探す旅に出る。
*
超自然的兄が超自然的弟を探していると、ある川のほとりで漁をしている上半身だけの男を見つけた。冒頭の夫婦の夫の方である。上半身だけの夫は、ちょうど川の土手に「ピラニア」を釣り上げて、トドメを刺そうとしているところだった。
超自然の兄はその「ピラニア」が、紛れもなく弟が変身しているものであることを瞬時に見抜いた。
超自然の弟は上半身だけの男に釣られているのではなくて、
実は金の釣り針を盗むために、食らいついていたのである。
(次の引用に続く)
この神話の冒頭は「未分節」である。
夫婦は「二」であるように思われるが、この世界には男女はひとりづつしか存在せず、つまりお互いに相手を選ぶことはできず、必ず結合してしまう。大洪水の後に兄と妹の二人だけが残されて、二人で結婚することになる、というパターンと同じである。どちらも夫婦の過度な結合、ほかに選択の余地がない(つまり結合から分離へ、分離から結合へと振れ幅を描いて動き回ることができない)という点で「未分節」(分節しようもない)状態になっている。
この過度に結合した夫婦とは別に、もう後二人の超自然的存在者がいる。
兄と弟である。兄弟もまた、別々に異なる”二”者でありながら、同時に極めてよく似た、同じような者同士である。
ここで神話の登場人物は「四人」になった。
「過度に結合した夫婦」と「過度に結合した兄弟」
この二つの二項関係が
夫β=β妻
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兄β=β弟
という具合にながーく伸びた(潰れた)四項関係を成している。
ところが!
ここで兄弟の方の弟が、遠くへ旅に出てしまう。兄弟が分離したのである。
夫β=β妻
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兄β←ーーーーーーーーー/ーーーーーーーーー→β弟
この分離から転じて、β兄はβ弟を「探す」旅にでる。
つまりβ兄弟が再び接近し結合する方向に向かう。
そのとき、β超自然の兄は、上半身だけの夫と出会う。
さらに、上半身だけの夫は、「金の釣り針」を用いてβ超自然の弟を、今まさに捕まえたところである。
β超自然の兄弟と、β上半身だけの夫婦が、「川辺」「釣り針」という、分離した二つの領域を結合したり通路を開いたりする媒介物のペア(セット)もとで一挙に結集、一点に収縮するかの如く集まる(川の土手は水界と陸界の境界であり、釣り針は陸界と水界への通路を開くものである)。
夫β=β妻
河岸*釣り針
兄β→→β弟
獲物?漁師?
おもしろいのは、ピラニア=超自然の弟は、客観的に見れば、釣り人に釣られた魚であるわけだが、実は釣り針を奪い取るために、わざわざ噛み付いているのだ、ということになる。釣り人である上半身だけの夫と獲物であるピラニアの関係は経験的には前者狩猟者と後者獲物の関係であるが、実は魚の方が釣り針を盗もうとしているのだとくると、どちらが狩猟者でどちらが獲物だか、どちらとも言えない状態になっている。
β四項が一点へと収縮していくとき、この経験的に対立するはずの二極のどちらなのか捉えようがない(不可得)な状態になる。
一切諸法因不可得
一切諸法損減不可得
一切諸法呉我不可得
一切諸法本不生
空海『吽字義』の四つの「β」を思い出そう。

超自然の兄はコンドルに変身した。
そして上半身だけの男がいままさにピラニア(超自然の弟が変身している)に振り下ろそうとしていた棍棒に糞を落とし、攻撃した。
超自然の弟は川の中に飛び込んで逃げた。
超自然の兄は、コンドルからハチドリに変身し、
どさくさに紛れて釣り針をくわえ、上半身夫の元から逃げた。
さすが「超自然」の兄弟である。
ピラニアに変身したり、コンドルに変身したり、ハチドリに変身したり、自在である。ここで上半身夫と超自然弟(ピラニア)をまさに完全に「一」にしようとしていた「棍棒」は「空から落ちてくる鳥の糞」と結合されて、超自然弟(ピラニア)とは結合できなくなった。こちらで結合すると、あちらでは結合できない、という二項対立の対立の仕方である。
棍棒
釣り針 * ( ?? )
空から落ちてくる鳥の糞
いま、「釣り針」、「棍棒」、そして「空から落ちてくる鳥のフン」の三項が動き回って、超自然の兄弟と上半身だけの夫婦(今のところ夫のみの登場だが)との間を、結合したり、分離したりする。つまり(1)β四項を一点へと集めたり、(2)水平軸上で遠く引き離したり(垂直軸上は収縮したまま)、(3)垂直軸上で遠く引き離したり(水平軸上では収縮したまま)、する。
ちょうどお餅をこねているような感じである。
ー ー
ここまで来れば、次のくだりは(4)であろう。
(1)β四項を一点へと集める
(2)水平軸上で遠く引き離す(垂直軸上は収縮したまま)
(3)垂直軸上で遠く引き離す(水平軸上では収縮したまま)
と来れば、(4)は”四項を垂直軸上と水平軸上で同時に分離しつつ、安定的に(静止させたり、あるいは周期的に一定の最大振幅の範囲内で行ったり来たりするように)結びつけておく"、という、付かず離れず、調和のとれた四項関係の分節になることだろう。
この(4)を引き起こすのが、釣り針、棍棒、コンドルのフンに続く、第4番目の媒介項である。それはこの神話では「籠」である。
超自然の兄は、上半身夫が「なかから鳥の声が聞こえてくる不思議な籠」を所持していることを知り、これを譲ってもらえるよう、交渉に入った。
上半身夫が「籠」に捕らえていた鳥は「太陽鳥」である。
このころ、太陽は天頂で微動だにせず輝いており、昼/夜の区別がなかった。
*
上半身夫は、交渉に訪れた超自然の兄が人間でいえば耳にあたる部分に「金の釣り針」をつけていることに気づき、自分の釣り針が盗まれたことを知り、激怒し、籠は絶対に渡さない、と宣言した。
冒頭の神話でも登場した、昼/夜の区別がないということが、ここで改めて言及されている。つまりこの上半身だけの夫婦や超自然の兄弟の、水平軸上と垂直軸上での過度な分離から過度な結合への急転換は、今日の私たちが知っている経験的で感覚的な世界のできごとではなく、その経験的で感覚的なΔ分節が発生してくる手前の「未分節」の話なのである。と、神話じたいが念押ししている。
この(1)未分節状態から、(4)は”四項を垂直軸上と水平軸上で同時に分離しつつ、安定的に(静止させたり、あるいは周期的に一定の最大振幅の範囲内で行ったり来たりするように)結びつけておく”へとモードを切り替えないといけない。
このモードの切り替えの鍵になるのが「太陽鳥を閉じ込めている籠」であることは明らかに推定できる。
超自然の兄は「籠」との交換条件を提示した。
もし籠を自分に渡してくれたら、代わりに上半身だけの夫に「二本の足」を授けよう、という提案である。
上半身夫は、妻にも同じように足を授けるならばと、二本の足を二セット、つまり”四本”をもらうことを条件に、「籠」の譲渡に同意した。
*
超自然兄は、上半身夫の妻へ陶土を託し、
さんざんこねさせて
成形して、足の形にした。
上半身だけの夫婦はこの足の上に飛び乗って、歩くことをはじめた。
それ以来、人間は歩いて旅ができるようになった。
ついでに生殖して増えることも可能になった。
(続く)
絶妙なところで、2×2の”四”出てくる。
そしてこの四が四本の足、つまりどこまでもどこまでも歩いて旅をする、ユーラシアの西の方から南米の先端まで、歩いて旅をしてきた「歩く者」としての人類の存在をはっきりと安定的に区切り出す=Δ分節する。
未分節からはじまった神話は、まずここで「人間の起源神話」としての側面を明らかにした。
ちなみに、「籠」と「陶土」は『神話論理』の続編にあたる『やきもち焼きの土器つくり』では主要な論点を提供してくれる項である。
*
さてに、人間はできたが、この世界、まだ太陽が昇りっぱなしの暑すぎる世界である。冒頭の神話のように、昼/夜を区別し、人間社会の分節システム、だれが、なにを、いつ、どこで、いかに、なすべきか、為さぬべきか、の分節体系を発生させて固めなければならない。
鳥の入った籠を譲渡する際、夫は超自然の兄に対し
「決して開けないように」と忠告した。
もし開けると、太陽が逃げ出し、もう二度と見つけられなくなる、と。
超自然の兄はわかったと言って、両方の掌を合わせて、その上に、傾かないように籠をのせて、大喜びで去っていった。
そして籠の中から聞こえる鳥の鳴き声をおおいに楽しんだ。
(つづく)
このくだり、浦島太郎感がある。
浦島太郎も、玉手箱を開けたことで「老い」を、つまり生/死の両極の間を移行する存在としての人間を起源させたわけであるが、よく似た構図になっている。
超自然の兄(造化の神でもある)は、籠を開けるつもりはなく、籠のなかの鳥の囀りを楽しんている。しかし、わざわざ合掌した手の上に乗せて、不安定な状態で持ち運ぶなんて、間違って落として、籠がひらいてしまったら、どうするつもりだったのだろう。
超自然の兄が注意深く籠を運んでいると、川辺でちょうど弟にあった。
超自然の弟はピラニアに化けていた時に負った傷をあらっていた。
その黒い縞模様の傷は、いまでもピラニアの頭にあるものである。
兄弟は一緒に森に入った。
空腹を感じた兄弟は、果物が実っている樹下で足を止めた。
*
兄は弟に、木に登って実をとってくるよう頼んだ。
しかし、弟は兄が持っている「籠」が気になって仕方がなかった。
そこで弟は、自分は疲れているので兄に実をとってきてほしいという。
兄は籠を置いて木に登った。
* *
兄が木に昇り、葉の影になって樹下がみえなくなるやいなや、弟は籠を開けた。
太陽鳥はさっと舞い上がる。
太陽鳥の麗しい歌声は、突如として恐るべき悲鳴に変わる。
雲がわきあがり、太陽を隠し、地上は真っ暗闇になった。
土砂降りの雨が十二日間つづき、地上は悪臭を放つ黒く汚れた冷たい水に覆われた。
(つづく)
太陽が昇りっぱなしの極端な状態から、真っ暗闇の、これまた極端な状態へ、一挙に真逆に急転換する。
この急転換を引き起こしたのは「弟が、籠を開けたこと」であるが、この籠を兄から分離し、弟の方にもたらすくだりで、まるで猿かに合戦のような、二人で一緒に行動していた者たちが、樹上と樹下に分かれ、そして言語的コミュニケーションが成立しないことが出てくる。
樹上
↑
忠告・依頼を聞くこと / 忠告・依頼を無視すること
↓
樹下
昼間だけ(暑すぎる太陽) / 夜だけ(冷たく暗く)
猿かに合戦も、おそらく「多すぎる太陽・強すぎる太陽(ミニ太陽のような赤い実と過度に結合する、顔と尻が太陽のように真っ赤な猿)」を退治して、適度に人間の世界から分離する、という話になっている。日本の猿かに合戦も昼/夜交代の起源神話が零落した姿であるという気配がある。
猿かに合戦ならば、猿を人間の家屋のような場所(つまり人間の世界)から追い出したところで、つかず離れずの適切な距離が確定したらしく、語りは終わりとなる。しかしいまみている神話では”天頂に静止している”状態から、完全に姿を消してしまう状態へと、逆転している。
太陽は、明け方に昇って夕方に沈むというサイクルを描く動き方でもって、この地上世界と付かず離れずになっている必要がある。ずっと真昼間も困るが、ずっと真夜中も困るのである。
というわけで、日本の猿かに合戦にはない、完全に逃げ去ってしまった太陽を呼び戻して、サイクル運動へと入らせる話が必要になる。ここで面白いのは、この神話、白猿(白い猿)が出てくるところである。
この闇の大洪水のせいで、上半身だけの夫婦は居住地を流されたが、足があったので、山の頂上へ登り、難を逃れることができた。
*
超自然の弟は自分の行いを反省し、嘆き悲しんだ。
超自然の兄は、闇世にも飛ぶことができるコウモリに変身した。
そして、天の高みにまで昇ると、人間の食用となる四本足の獣たちと、猿や鳥を創造した。
*
それから何年も経って、超自然の兄は、ある鳥に命じて、太陽を探させた。
この鳥はまずはるかに高い天の頂にまで飛んだが、太陽はいなかった。
そこで鳥は、風に身を任せ、地の果てへと舞い降りた。
そして地の果てで動けなくなっている太陽を発見した。
太陽は籠に閉じ込められていることに飽きて、天頂に逃げ、世界の端から端まで走ったが、この地の果てでそれ以上動けなくなってしまっていたのである。
鳥は太陽を助けるべく、ふわふわした柔らかい「雲」を用いて太陽を包み、地上世界へと放り投げた。まっしろな猿がその包みを受け取って、そっと中身の太陽鳥を籠へと戻した。
* *
以来、夜には地面の下を旅をして、朝になると反対側の端から出てくることができるようにした。こうして昼夜の交代がはじまったのである。
(つづく)
超自然の兄が、ついに造化の神としての本領を発揮する。
まず人間の食糧を創造する。
次に、太陽をサイクル運動へと連れ戻すべく使者をつかわす。
超自然の兄に命じられた鳥は、一度天頂まで昇って、そこから地の果てへと滑空しながら降りていく、というまるで私たちがよく知る太陽が日中に描く軌跡をそのまま再現するかのような動き方を演じる。正午の真上の太陽の位置から、日没の位置へ、大空を、地の果てへと、降りていく。
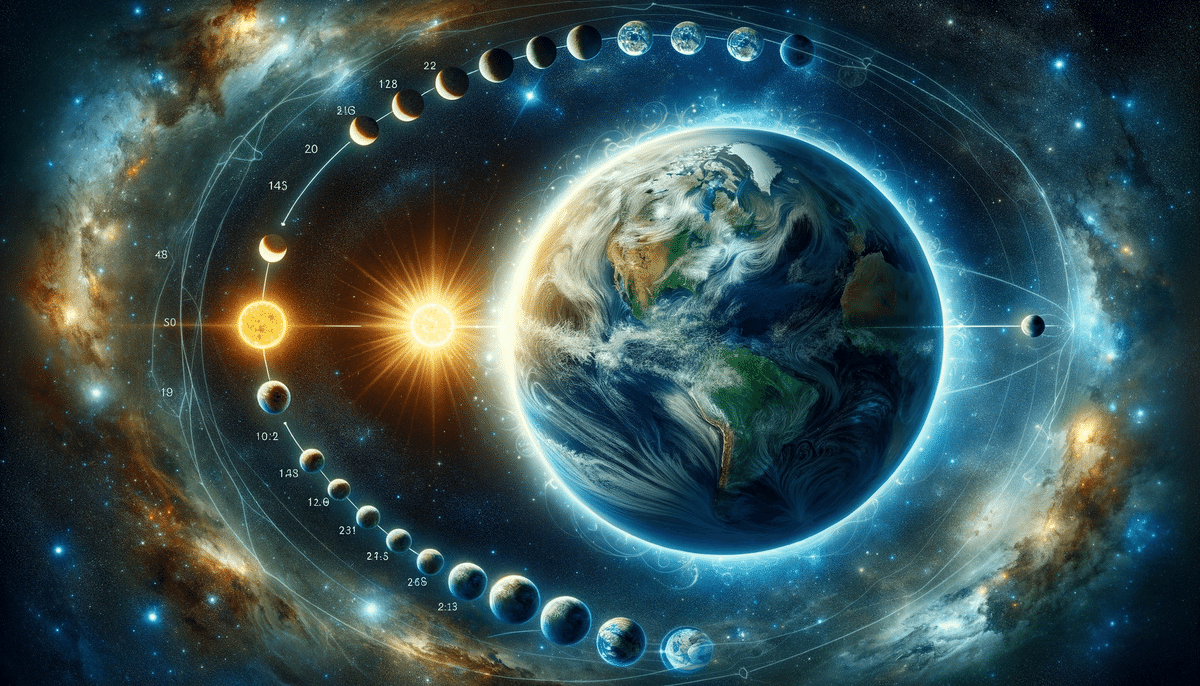
そうして超自然の兄の使いは、地の果ての向こうに動けなくなった太陽=太陽鳥が止まっているのを発見する。鳥は小さな火の玉になった太陽を「雲」で包み、地の果てから、洪水で真っ暗闇になっている世界の方へと、放物線を描くように投げる。
ここで、太陽が、回転運動を始めることになった。
この小さな太陽=太陽鳥は「真っ白な猿」という赤色=太陽と真逆に対応する「白色」の存在者によって丁重に「籠」へと戻される。
猿かに合戦の「赤色」を強調された猿が、乱暴に”赤い球”である柿と結合していくのと対照的に、こちらの白い猿は、”赤い球”である太陽鳥を丁寧にあつかって、籠の中へと収める(つまり白猿とは分離する)
赤が勝っている猿 / 白が勝っている猿
↑
↓
赤球と乱暴に結合 / 赤玉と丁寧に分離
この見事な「真逆」には吃驚である。
日本の昔話もまた、南北アメリカの神話の構造と完全に同期した分節・二項対立ジェネレータでもって織りなされていることがわかる。

白い猿、白い雲によって包まれた小さな太陽鳥は、また籠のなかに戻る。
媒介項である「籠」の中に、太陽の精のような太陽鳥を入れておく。
籠の中の鳥である。
鳥が籠に入ったままになることによって、つまり籠の目から、姿が見えるのだけれども、出てこない、籠目を通して、その世界と繋がっているのに、しかし分離されている、という”網目”により結合しつつ分離する作用のおかげで、太陽は真夜中か真昼間か日没の瞬間か日の出の瞬間か、という四つの極のどこ位置にも静止することなく、巡り続けることができるようになる。
*
籠目籠目
籠の中の鳥、といえば「籠目 籠目 籠の中の鳥は、いつ・いつ出やる。夜明けの晩に、鶴と亀がすべった。後ろの正面だあれ」というのも、
β1:籠の中の鳥(隠れているか隠れていないか不可得)
β2:夜明けの晩(朝か夜か不可得)
β3:鶴と亀が滑る(天空を飛ぶものと、水中を泳ぐものの動きが同期する。水界か天界か不可得)
β4:後ろの正面(前後不可得)
という、両義的で中間的であいまいな媒介項を四つ並べたもので、世界の始まり=定かな物たちの世界が始まる瞬間、「だあれ」が、誰であるか「不明」な状態から、「だあれ」が誰であるか、仮に定まる瞬間に触れようとしたものである。

世界の始まりと、終わり?
昼夜の交代が始まったところで、今日の私たちが経験するこの世界が創造される。
超自然の兄弟は、相談の上、別れて暮らすことにした。
弟は東へ、兄は西へ向かい、それぞれ洪水で荒れ果てた世界を作り直す仕事に勤しんだ。
兄が念じて、木々や、川や、動物や、新しい人間が生まれた。そして人間に技術や宗教儀式や、天と交流するための発酵飲料の作り方を教えた。
最後に兄は雲の中へと去ったが、最後に舞い上がった地点には、いまでもその足跡がふたつ、残っている。
こうして誕生したのが、この世界、「第三の世界」である。
*
これまで、過度に結合したり、過度に分離したり、β二項らしい分離と結合の両極の間での脈動を演じてきた超自然の兄弟が、ここでようやく別々に分かれ、定まる。地上から兄が去ることで、「ふたつの足跡」がいつまでも残る、というところがこのβ分離からの「二」の確定ということをよく象徴しているように思われる。
β脈動の振幅が安定したところで、ようやくこの現世であるΔ四項の分節がはっきりと形を浮かび上がらせる。
自然、文化、人間、人間の食べ物が定まる。
ちなみに、この神話ではβ脈動の振幅の安定化は少しずつ少しずつ丁寧に進行しており、超自然の兄が太陽鳥の籠をもって弟と再開したところで、すでに「魚」が、今日にも存在するピラニアという魚が、「黒い縞模様の傷」をもった魚が、誕生する。この「黒い縞模様の傷」もまた、区別があること、白黒はっきり区別されていることをビジュアライズしているようである。
こうして世界が誕生しました、めでたしめでたし、という感じかと思わせつつ、この神話にはまだ続きがある。
以上のようにして誕生したのが、今日の世界である。
今日の世界は「第3番目の世界」である。
第1番目の世界は、人間がインセストにふけったために火で焼き滅ぼされた。
第2番目の世界は、太陽鳥を超自然の弟が逃したことで洪水に飲み込まれた。
第3番目のこの世界もまた、悪霊に仕える邪悪な精霊たちの手で終わりを告げるだろう。
そして第4番目に造化の神たる超自然の兄の世界が始まり、その世界では人間を含む生きとし生けるものの全ての魂が、永遠の至福を享受する。
(終わり)
分節される世界は、Δ世界は、ただそれだけ、一項だけで転がっているわけにはいかない。Δは常に四つセットである。もし私たちのこの世界が一つのΔ世界であるとすれば、他に三つのΔ世界が生成しなければならない。
第一の世界、第二の世界、第三の世界、そして第四の世界。
レヴィ=ストロース氏は『神話論理3 食卓作法の起源』の「カヌーに乗った月と太陽の旅」で、この神話と同じ構造(二項対立関係の組み合わせ)を用いる神話をいくつも紹介されている。
P.175のM411「月の満ち欠けの起源」では、「太陽が二つあり、常にどちらかが空に登っているために、夜がなく、昼だけの世界があった」というところから始まって、片方の太陽が人間の女性と結婚しようと地上の炉の中に墜落してしまい月に変身する。そしてこの月は自分の娘を他のどの星とも結婚させず、自分のもとに閉じ込めておこうとしたために、星々の怒りをかって、殴られ、凹まされ、満ち欠けするようになった。
P.177のM413「長い夜」では、ある老人が、自分の娘たちに求婚してきた甥たちを拒み、娘が結婚してしまうくらいなら、と娘たちを消してしまう。それに怒った甥たちは「太陽」を壺の中に閉じ込めて、四年にわたる夜をもたらし、老人を飢え死にさせる。闇に怯えた鳥たちが、この甥たちに結婚相手を提供しようとしたが、甥たちは拒絶した。甥たちの一部はダチョウの片目の娘と、一部は死者の国に去った従姉妹たちと、結婚した。一説によれば、従姉妹たちはその父親=老人の切られた首から流れる血を浴びて生き返ったらしい、という話もある。
P.180からのM415「結婚を強いられた娘たち」では、大洪水で男女の人間二人だけが生き残った世界をカヌーにのった造化の神が旅する。神は太陽と月の形を岩に彫り、神のもうひとりの兄弟とともに大地の表面を整えた。神々は”両方向に流れる川”を作ろうとしたがうまくいかない。造化の神には娘たちがいたが、娘たちがあまりにも旅を好むので、神は娘たちの足を折り、出歩けないようにして、人口を増やした。
これら一連の神話いついて、レヴィ=ストロース氏はつぎのようにまとめて論じている。
「この観点により得られるのは、それらの神話が、近い結婚と遠い結婚との社会的な対立を、天体にかかわる対立と関連させているという捕捉的な証拠にほかならない。天体にかかわる対立とは光と闇の対立だが、その二項を純粋な状態でとらえるさいには、絶対的な昼と絶対的な夜との対立となり、混交状態でとらえるさいには、昼の明るさは虹や冬の太陽にかかる靄によって緩和され、夜の闇は月や銀河、同じく迷走する彗星や流星によって緩和されるのである。[…]しかし、それらの神話はそこにとどまってはいない。じっさい、光と闇の対立との妥協は、虹の色や雨雲が昼の光を和らげ、かげらせるときや、月や星が夜空を明るくするとき見られるような、たんなる同時性という次元においてだけではない。こういう共時的な媒介の補足となるのは、昼と夜のどちらかが独占的に支配するという理論的状態とは反対で、昼と夜との規則正しい交代により説明されるような、通時的媒介である。」
昼か夜か
昼 / 夜
静止した二極どうしの絶対的な対立。
絶対的な昼と絶対的な夜との対立・・・ではなく!昼夜の交代のサイクルが思考される。
ここで、昼/夜の両極の間を行ったり来たりするための媒介が必要になる。
その媒介には「同時的」な媒介と「通時的」な媒介がある。
同時的な媒介には、
虹
冬の太陽にかかる靄
月
銀河
迷走する彗星
流星
といったものがある。
これらは昼/夜のどちらか、昼か、夜か、そのどちらかを静止した背景として、その前で動いたり、ヴェールをかけたりする。ここで昼が弱められたり、夜が弱められたりはするが、夜から昼へ昼から夜への場面の大転換は生じていない。
これに対して、通時的媒介となって昼を夜へ、夜を昼へとひっくり返すのが、今回の神話に登場したような「籠に閉じ込められたり放たれたりする鳥」のような動きを演じる項たちの、最小構成で四つのセットである。
この通時的媒介と同時的な媒介が組み合わされて、空間軸上での
遠/近
の対立とその調停(過度に遠ざかりもせず、過度に接近しすぎもしない)と、時間軸上での
長周期のサイクル / 短周期の動き
の対立と、その調停。あるいはそもそも
止まっていること / 動いていること
の対立とその調停がもたらされる。
「神話において月と太陽のカヌーの旅がもつ意味を探究するところから始めたわれわれは、このモチーフが、ふたつの次元をもつ意味場に位置しているのを検証した。空間軸においては、相互的距離関係のなかで、受容されるかあるいは拒否される近い結婚と遠い結婚とが対立させられる。それらはカヌーの旅によって、言うなれば調停が可能になるような二者択一の諸項である。時間軸においては、永遠の長い夜との間に二者択一がおこなわれる。そしてその調停は、共時的見地では、光と闇の和げられた諸様相すなわち虹、冬の雲、月や星、天の川などによってなされ、通時的見地では昼と夜の規則的な交代によってなされる。」
あるいは、時間が人間にとって経験的に不可逆であるのに対して、空間は同地らの方向にも進めるという点で、複数の軸に、水平方向と垂直方向に分かれる。
「さらに、この領域からいましがた確かめられたのは、それらの神話が空間軸を二通りに方向づけていることである。水平方向の空間軸と、垂直方向の空間軸が想像されている。カヌーの旅が主人公を、近い極から遠い極へと運んで行く時は、当然ながら水平方向だ。主人公はまず自分が頑固な独身者ないしインセストを犯す愛人でしかありえない身近な環境から引き離されて、異国的な環境へ運ばれていく。そこで出会うのは、もし独身者であれば遠い国の姫君、すでに結婚していれば不実な女主人である。だが、ユパ神話(M411)はこの水平軸をはっきりと垂直方向に引き起こす。すなわち、夜の太陽はのちに水に棲むカエルに変わる人間の女を抱きしめようとしたために、赤い炭火で熱せられた穴の中で死んでしまう。そして空の月となると、星々である娘たちを、同じ種族の求婚者たちに与えるのを拒み、別れるよりはと娘たちを閉じ込める。」
空間における水平方向の軸上で二項対立を分けつつつなぐよう調停するのが、たとえば「カヌー」である。
そして、空間における垂直軸上で二項対立を分けつつつなぐよう調停するのが、たとえば「水性のものにふれるために地上に落ちてきた太陽」のような垂直軸上で最大スケールの振幅を描く者であったり、逆に娘たちとともに固まって垂直軸上のプラス方向の最大値のあたりで動かなくなってしまった「月」のような者であったりする。
このように、直交する二軸の上に、それぞれ振動する振幅の最大値と最小値、つまり四つの極を均等に定めるような、規則正しい周期的脈動が動き出すところで、分別・分節が定まった、この現世がはじまるのである。

関連記事
参考文献
いいなと思ったら応援しよう!

