
暗黒瞑想 宇宙/非宇宙分節以前の”法界の根源的脈動”と微かに共振するアンテナとしての”わたし”へ -中沢新一著『精神の考古学』をじっくり読む(8)
松岡正剛氏が『空海の夢』で「仏教の要訣は、せんじつめれば意識をいかにコントロールできるかという点にかかっている」と書いている(松岡正剛『空海の夢』p.23)。
意識をコントロールする
例えば、私たちが迷い苦しむのは、自/他、生/死、清/濁、光/闇、などと二つに分けて、そのどちらか一方だけを自分ものにしようとこだわり、他方を遠ざけておこうこだわるから、であると考える。例えば生/死など、前者だけを選んで、後者を捨て去りましょう、などと。しかし、それはいくらそのように渇望しても決して叶うことはない。
こだわっても叶わぬと知って人は苦しみ、恐る。
二辺を離れる、分別された二辺のどちらにもこだわらない
この苦しみをどうにかするには、どうしたらよいか。
せんじつめれば「生/死」でもなんでも「A /非-A」のどちらにも拘らなければ良い。これを「二辺を離れる」という。
*
「A /非-A」のどちらにもこだわらない(執着しない)なんて、どうすればそのようなことができるのか??
* *
この問いに対する応答が、「A /非-A」の「/」をやってしまっているのが私たちの「心」であり、私たちは「心」の動き方を組み替えることができるのだ、ということを知り尽くせば良い、というになる。
生/死でも、犬/猫でも、何と何でも良いのだが、「A」と「非-A」の対立は、もともとそれ自体として存在する「A」と、もともとそれ自体として端的にある「非-A」とが、どういうわけだかたまたま偶然ばったり遭遇して、「オイ、コラ、ナニ見てんだよ、ケンカうってんのか?ああん?」みたいなことになっているのではない。
分別心
そうではなくて「/」が動くこと、「/」切り分けること、「/」区別すること、「/」分節すること、「/」分別すること、などと言いうるような動きが動きつつあるところで、束の間「/」の両側に別々の領域が開かれているように見えるようになっているだけであり、この「/」の分ける動きが別の動き方に変容していけば、もともと「/」の両側にあった領域「A」と領域「非-A」の”そのもの性”のようなことも、あるのだかないのだかよくわからないことに、少なくともなにかこだわるようなことではないようになる。
この「/」の精妙なうごきが「心」なのだ。
この「心」般若心経の「心」であり、空海の『秘密曼荼羅十住心論』の「心」である。
* *
分別の仕方は固まっているようで固まっていない
「心」である「/」を、「/」と”直線”で表現するのはあまりよい方便ではないかもしれない。「/」は脈動、波長と振幅がほぼ一定を保って反復される振動としてイメージされたほうが、波長や振幅が連続的に(アナログに)変調されて、うゎーーん、キーンと周期が広がったり詰まったり、ウーンと振幅が増えたり減ったりすることで、その両側に区切り出される領域(「A」と「非-A」の姿形を次々と変容させていく姿をイメージしやすいかもしれない。
しかもこの波としての「/」すなわち「心」は、均質に唯一のことではなくて、多様であり、つまりさまざまな波形の波が重なり合い、打ち消しあい、重畳しあい、ごくシンプルに例えればリサージュ図形のようなパターンを次から次へと変容させていく。

・・・
固まった対立があるでもないでもないところから、分かれているでもなく分かれていないでもない微妙なパターンが現れたり消えたり、ないようなあるようなことになる。このような状態が、中沢氏が『精神の考古学』で書かれている「セムニー」という心のあり方であろうか。
この分かれているでもなく分かれていないでもない微妙なパターンが繰り返し繰り返し、同じパターンでもつれながら「減速」しつつ反復される時、固まった対立関係を織りなしているかに見えるAと非-Aの二極の姿がはっきりと定まってくる。このように「分ける」うごきを同じパターンで反復する心の動き方を、『精神の考古学』の用語でいえば「セム」と呼べるだろう。
心の振動状態が
さまざまに変容する様をありありと見る
ここまでの中沢氏の修行は「セムニー」と呼ばれる心の底、諸々の分別する心(セム)を発生させている深層の「心(セムニー)」の働きを「見る」ものであった。この「見る」は、セムニーと異なることのない人の身体の内なる脈動と共振する「光」を「水晶管を通して眼球から青空に投射する」ヨーガでもってなされる。
この、”内部からの光を青空に投射する”修行を成就すると、今度は太陽光が降り注ぐ青空のもとを離れて、真っ暗闇に閉じこもって瞑想する修行が待っている。
暗闇での瞑想は、「心臓のパルスと同調している生命的な波動だけでなく、大脳の空間を埋め尽くす複雑な神経組織網の全体に、焦点を合わせ」たものであると中沢氏は書かれている。
*
この「複雑な神経組織網」で振動する多様なパターンと共振するために、「静寂」の波動と、激しい「憤怒」の波動とを、複雑に組み合わせていく。
ここで「チベット仏教ではこれらの静寂波動と憤怒波動のそれぞれに「神」のイメージが当てはめられる」と中沢氏は書かれている(『精神の考古学』p.314)。
波動をビジュアル化したアバターが・・
法界に充満している存在の「強度」
この「波動」という言葉で書かれていることに、真っ暗な部屋に閉じこもって行う瞑想で「みえる」ことを理解する、いや、説法として”きく”ためのヒントがある。

++
この「波動」を呼ぶ名としての「神」という言葉をめぐって、中沢氏は「チベットでは、神は超越者としての意味合いよりも、法界に充満している存在の「強度」をあらわす言葉である」と書いている(p.314)。
この法界に充満する存在の強度(固有振動数という言葉で喩えてみようか)には、いろいろなパターンがある。特に強度の強/弱のちがいがあることこそが、複雑な組み合わせパターンを生み出す。
ここで「低い強度」の振動する力が浮かび上がらせているパターンこそ「現実世界」である。この「低い強度」は、より高い振動の強度が、減速され、振幅を抑えられた姿である。
低い強度に落とされる前の「高い強度」が「みなぎる」ところを、中沢氏は「存在情報が充満する法界」と呼ぶ(p.314)。
「この「高い強度」である法界には、さまざまな波動が共生している。それを百種類の「神々」に分類することができる。神々の違いを、ちょうど現代のクオーク理論を思わせるような、色彩、形態、機能性によって分類すると、だいたい百種類にまとめることができる。それにアバターをかぶせて、静寂神、憤怒神というように表現する。」
描かれた曼荼羅に配置された神仏、神々もまた、そのような存在の強度、さまざまに異なる波動が描くパターンとして観じるとよいのだろう。
高振動状態は均一均質に振動するのではなく、「さまざまな波動」が響き合って、重畳しあって、あるいはときに打ち消しあっているのであろう。その響き方や重畳の仕方や打ち消しあい方の組み合わせを、仮に「百種類」くらいに分類するという。これはおそらく、もっと細かく分類することもできるし(無量無数)、もっとざっくりと分類することも(例えば八種類くらいとか)できるのだろう。
「神」というのは、このさまざまな振動のパターンのことであり、振動のパターンのちがいと共振するように、神々の名の差異の体系が組まれる。
ここでふと思うのは、日本の神話に伝わる神々の名というのも、このようなこととして聴取してみる可能性もありそうである。
*
このさまざまな波動の強度、響き合いのパターンの違いに、神々の名を呼ぶ音の違いを共振させ(音も振動である:語-口)、そして神々の視覚的イメージを共振させる(光もまた振動である:意)。それを「アバターをかぶせ」ると表現されているところがとてもおもしろい。
ここまでくると現世に生きる行者の身口意(低い波動・低振動)を如来(高い波動・高振動)と共振・シンクロさせる(三摩耶)三密加持ということにつながってくる。
* *
静寂神と憤怒神
さて、この神々の名と姿という「アバターをかぶせられた」振動のパターンたちを、おおきく二つに分別してみたものが、静寂神と憤怒神ということになろう。
「ヤンティ・ナクポでは、そのような静寂神四十八種類と憤怒神五十二種類の神々(アバター)が心臓の神経叢から大脳の神経叢にかけて活動している、と考えられている。」
この時点で「これぞ”即身成仏”」という感じがする。
行者の身そのものが、百種類ほどの神々に分かれつつも完全には分かれるはずもなく繋がりあって「一」である”法界(如来)”と、完全に平等、三摩耶、共振状態にある。まさに即身成仏である。
*
別の文脈であるが、真言密教の行者である池口恵観師がその著書『秘密事相』に記された、三密加持についての一節を思い出す。
「もし、行者が不動明王を本尊として明王の印を結んでいるのであれば、その印が憤怒の形相となり、また行者が口に明王の真言を唱えたならば、その真言が明王の音声と化し、行者の意(こころ)は明王なり、と観念すれば行者の全身が明王の姿と同化するのである。つまり、本尊の身口意の三つが、行者の身口意の三つと平等になることで、行者は本尊と同一となり、同じ力を持つのである。これが入我我入の構成である。」
+
これをいま、脈動の共振(波の速度や波形が重なり合い、振幅が高まること、あるいは新たな共振周波数が生じること)といったイメージにしてみる。
光はありとあらゆる脈動のうちの
特定の帯域のことである
脈動に喩えるとどうして都合が良いかというと、「見る」ということが、外界からの光(その大元は大概太陽である。夜を照らす化石燃料もまた、太古の樹木や微生物だとすれば、つまり太陽のエネルギーが変化したものであることに変わり無い)という特定のパターンの脈動と、人の視覚あるいは視覚を含めて全身に連なる神経系というシステムの固有の脈動・振動数との「共振」ということを、手持ちの用語で考えやすくなるからである。
この場合「光」という言葉を、視覚の神経系を励起することができる帯域の「可視光」に限定して理解しない方がよさそうである。この宇宙で振動しているのは可視光ばかりではないからだ(遠赤外線で鮎を焼くプロセスを想起せよ)。
+
なお、上の引用にあるヤンティ・ナクポとは?ということについては、ぜひ『精神の考古学』を読んでいただければと思います。
ここで諸尊の配置は次のようになる。
「四十八種類の静寂神は、心臓チャクラを中心とした神経叢に、五十二種類の憤怒神は大脳空間をつくる神経叢に「鎮座」しているというイメージだが、じっさいには神々のアバターを外してみると、心臓を中心とした静寂パルス群と大脳空間に充満する憤怒パルス群が、人間存在の重要な部分をなしているのである。」
ここに書かれた「心臓を中心とした静寂パルス群」と「大脳空間に充満する憤怒パルス群」の独特の共鳴状態・ハウリング状態こそが、人間が存在するということ(そのように感じていること、主体感をふくめて)なのだというところが面白い。
これはなかなか図解するのが難しいというか、どう図解してもちがうような気がしてくるところであるが、「心臓を中心とした静寂パルス群」も「大脳空間に充満する憤怒パルス群」も、どちらも「法界」に「充満」するより高次の、無量無数、数えきれないほど多様な振動たちが、共振し、ハウリングしたパターンたちのうちのひとつふたつ、といったところであろう。

「暗黒瞑想では、心臓と眼球を結ぶ水晶管を中心に行われたトゥガルを土台として加行を組織し、さらにその上に大脳空間を揺さぶる独特の暗黒ヨーガが組み込まれることになる。こういうわけで、ヤンティ・ナクポでは憤怒静寂あわせて百尊を集めた灌頂が行われる。」
灌頂というのは(こういうまとめ方は雑にすぎるかもしれないが)、瞑想し、ヨーガを実践する行者の身と口と意とを、「心臓を中心とした静寂パルス群」と「大脳空間に充満する憤怒パルス群」と共振状態(三摩耶)にして、その共鳴をそのまま「法界」に「充満」するより高次の振動たちとも美しく共鳴させる、といったところである。
修験や密教で聞く「三昧法螺聲 一乗妙法説 経耳滅煩悩 當入阿字門」というのもまさにこの高次共振状態に入るよう、”身”や人間的な識(八識)を励起すること、と言えるのかもしれない(言い切っていいものでもないと思う)。
*
このようにあちこちに顔をだすのは、「共振」とか「ハウリング」と呼べそうな、様相の異なる無数の波動のパターン間の差異である。

「まばゆい暗黒」
以上の灌頂の次に、「暗黒の部屋」をつくることになる。この作り方については『精神の考古学』の320ページから詳しく記載されているので、空き家などを所有している方はこれを参考にリフォームしてみるとよいかもしれない。
*
さて、『精神の考古学』の328ページから「30 まばゆい暗黒」という節がはじまる。中沢氏の暗黒瞑想は七日間にわたるものであるが、その「一日ごとにメニューが異なる」という。
0日目:「光」を励起する
諸々準備が整ったところで、まずこの暗黒の部屋に入る。
この日はまだ「一日目」には数えない。
ここで最初の瞑想をする。
すなわち、分別心の動きを鎮め、分別心が事物を分けて固める手前の、ゆるゆると固まるような固まらないような、それでいて「何もない」わけではない”あるようなないような”、分別と無分別が重なっているような感じを感じながら、分別心が切り分ける”他ではないそれ”であるようなあれこれの事物のことを自性をもたないものと見定める。
そしてその状態で次のように「眼球」のヨーガを修する。
「[…]眉間の上約五十センチほどの虚空を、眼球をひっくりかえしながらずっと凝視し続けるという単純なものである。この瞑想の姿勢を続けていると、体の周囲の空間がぐらぐらと揺れ出すように感じていき、そのうち眼球の端に火のように燃えるものが現れてきた。白い雲のようなものを出現し、さまざまな形をした光が次々に出現しては消えていった[…]」
真っ暗闇の中で、さっそく「光」が見え始める。
通常の視覚にとっては漆黒の闇であるところに、「光」が瞬く。
明 / 暗
このどちらか一方でしかない通常の視覚とは異なるモードで、通常「光」として見えていることとは異なることが見えている。「まばゆい暗黒」のはじまりである。
この状態で中沢氏は暗黒の中で眠りについたという。
一日目:大脳内の水晶宮とそれを観察する”第三の眼”の同時生成
そして翌朝。
暗黒部屋の中でも、鶏の声が聞こえることで朝だとわかるという。
「(暗黒の中で)目を開くと、暗闇の中に細い糸のようなものが見えるのである。糸は細かい網目をなしてつながっており、それが視界いっぱいに拡がっている。まるで細かいネットが空間中に張り巡らされているようである。[…]糸と糸との結び目のあたりは、少しだけふくらんで見えるので、たくさんの小さな宝石が糸でつながれて、空中にぶらさがっているようにも見える。」
まるで「インドラの網」のようであるが、この話はまた後ほど。
中沢氏はこれが「茶漉し」のように見えたと書かれている。
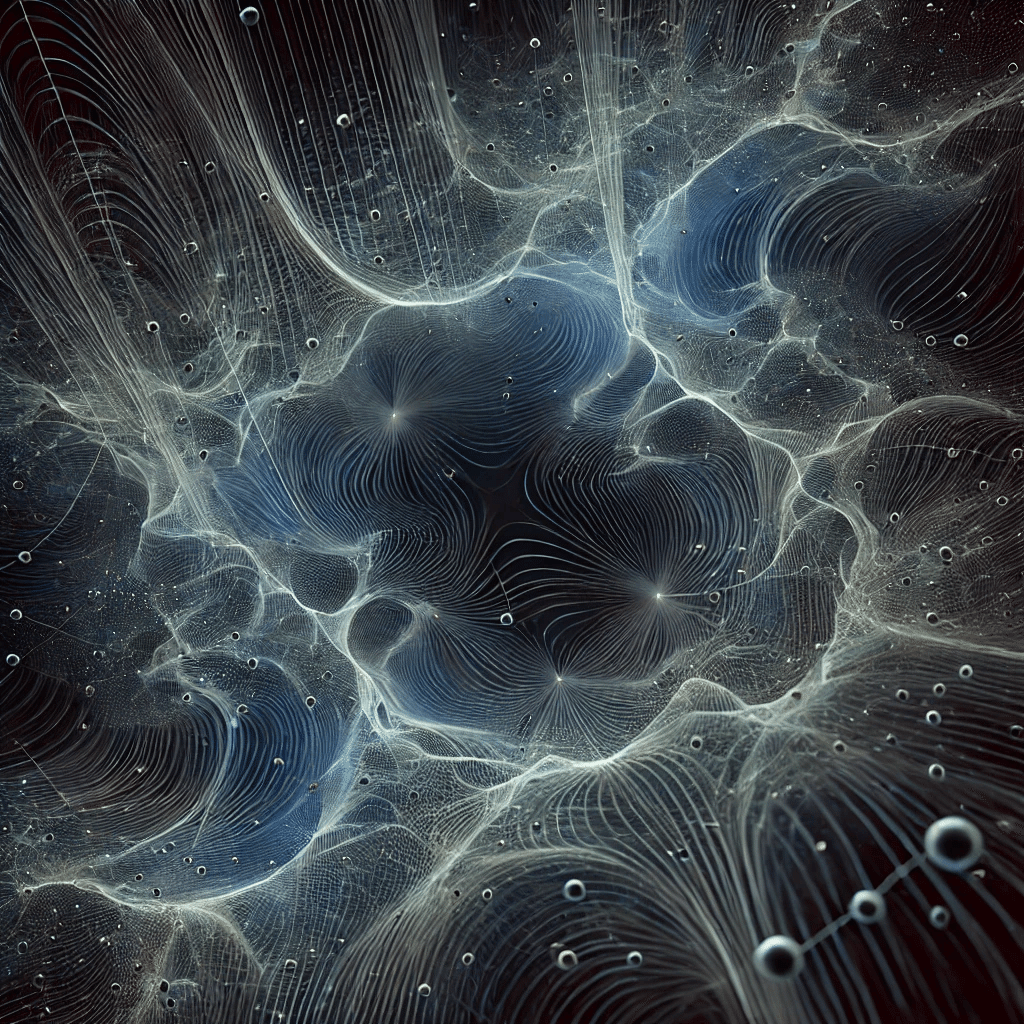
ここで暗黒部屋の外の師匠から声によってヒントが授けられる。
自分の大脳の中に水晶でできた法螺貝をひっくりかえした姿の透明な宮殿があると想像すること。
宮殿の内部は、物質性によって汚されることかく、五色の光を放ちながら一個の球体を成しているとイメージする。
眉間に「憤怒の形相をした原初的知性の眼が一個現れて、大脳の中を覗き込む」とイメージすること。(中沢新一『精神の考古学』p.331)
これにより「心の原基でありながら心を超越している原初的知性の眼が、私の大脳の内部をじっと観察してい」るということになる(中沢新一『精神の考古学』p.332)。
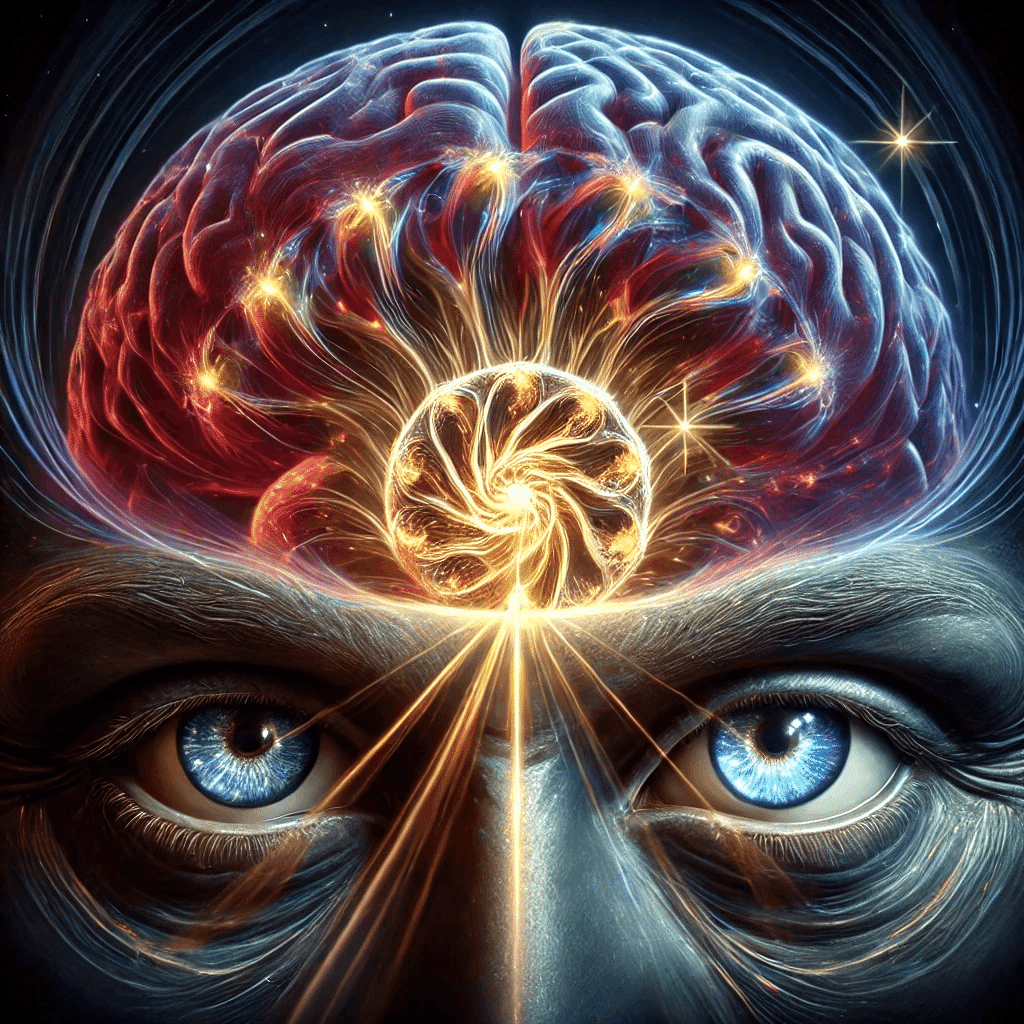
AI生成によるイメージ
偏頭痛持ちの私にとっては緊張感のある絵である。
大脳が「分別」を行う場であり、「分別」されたものたちが配置格納される場であるとすれば、そして通常の視覚はこの分別にしがっているとすれば、この大脳ー通常の視覚の分別システム自体を、この眉間の裏側に生成された第三の眼が「見る」、といえようか。
+
この脳内の水晶宮と眉間の第三の眼を観じる行は「原初的知性の独眼に汚れなし」と呼ばれるという。
分別する通常の視覚は、「 清 / 不浄 」をわざわざ分別しては、諸々の不浄を発見し、清を求めて固執し、浮上から離れることに固執する。
それに対して、眉間で内向きに大脳を凝視する原初的知性の独眼は、この分別、清/不浄の分別の外で、まさにこの清/不浄が分別される瞬間、分別されるでもされないでもないところを眺めている、ということであろうか。
二日目・三日目:「心臓」と同期された二つの目を加える
二日目も引き続き、前日からの光の糸の網目が見えているところからはじまる。二日目から「内部空間」での発光と、「外部空間の現象世界の顕現」とを、二つに分けて考えようとする心を超える、ということが課題になる。
二日目の行ではまず「脳内を凝視する眼」を、一つ(前日につくった眉間のもの)に加えて、もう二つつくる。この二つの目は通常の眼球の裏側に作られるらしく、「静寂尊のアバター」で思考される「心臓」のパルスからの光を感じるものである。
「心臓の神経叢に意識を集中していると、そこが光だすように感じられる。そこには四十八の静寂尊が住むと考える。これらは[…]心臓に集まってくる生命的脈動(パルス)の種類をあらわしている。」
つまり二日目に作られる二つの目は、「心臓」あるいは「四十八の静寂尊」と呼ばれる緩やかな(長波長)のパルスたちと共鳴共振同期する振動数の束とでも呼べる様なことである。

子供のころに見た、「ネモくん」と連呼する人が塩の柱になるアニメを思い出す
なんというか、モノモノしい。
そして三日目に「一日目に現れた眉間の眼と二日目に現れた左右二つの眼の合計三つの目で脳内宮を凝視する」ことが行われる。この際、「脳内宮には五十二の憤怒尊が現れている」様を「観る」ことになる。
「さまざまな生命機構のクッションに守られている他の身体部位の生命活動に比べると、脳内に発生している知性的脈動はより直接的で激しい。その強度の高いパルスを五十二の憤怒神のアバターで捉える」
これにより、脳内で強烈に反復するリズムを刻む分別心の姿を、心臓の緩やかなパルスと反響させて、その強烈な「憤怒」の速度を減速させて、「観える」ようにする。
四日目:目を八つにして、身体内外の光の網をみる
四日目には、さらに五つの眼を生成させて、これまでのものと合わせて八つの眼でもって「脳内宮を光で満たしていく」という(p.335)。
「脳内空間は眼の放つ光で満たされていたが、この光が体内にも充満するようになり、その光が細かい糸の網を編むようになっていった。それぞれの網の目の中心には小さな眼がついているように思われ、身体中が光の茶漉に覆われていくようだった。体のまわりにも光でできた蜘蛛の糸の網が張り巡らされている。」
眉間の奥の第三の目と心臓のパルスとの同期をとる両目とが共同して、脳内に、そして身体全体の内側、さらに体の周囲にまで、光の線の網をひろげていく。
*
ここで中沢氏は宮沢賢治の『インドラの網』に描かれた光景を引きつづ、次の様に書いている。
「この経典(『華厳教』)を書いた仏教徒にとって、「インドラの網」の体験とは、けっしてたんなる想像上の産物ではなく、現実体験と深く結びついていたことが想像される。彼らは法界を無数の細かい光の網で覆われた空間として描き出そうとしたが、それは彼らが脳内でじっさいに体験していた光現象に根ざしていたものではなかろうか。」
ご興味ある方はぜひ、『精神の考古学』を手にとっていただきたい。
五日目:心臓にも目を作る
ここで頭には八つの眼が揃ったわけだが、五日目になると、こんどは心臓の方に、新たにひとつの眼を作る。その作り方は「心臓部に集まってくる神経組織を静かに整え」ることによる(中沢新一『精神の考古学』p.337)。
この眼の登場により、大脳(憤怒尊と表現される強度の高いパルスたちのもつれ)と反響しあう八つの眼と、心臓(静寂尊で表現される穏やかなパルス)による一つの目が、互いに他方を見つめ合い「向かい合いう」かたちになる。
+ +
ここにいわば大脳と心臓、二つの領域それぞれの視覚の固有振動数のようなものが共振して、経験的で感覚的な「眼球」の眼から、光として飛び出してくるようになる。
この時、心臓の眼は「一」であり、大脳の方は「八」である。
「一」と「八」が、ひとつの身体において不可分につながりつつ分かれている。


脳(高強度のパルスの共鳴)**心臓(長周期の穏やかなパルス)
↓
↓
「眼球」が外界のある領域の光と共振することを可能にする
特有の”固有振動数”
六日目:光が溢れ、絡まり合い、大きな渦になる
インドラの網が見えなくなり、「脳」の振動と、「心臓」の振動、それぞれからの高周波振動(いわゆる光)が激しくぶつかり合い、増幅されたり、複雑な合成波をなす様が際立つようになる。
光が溢れる感じである。
この日、中沢氏は師匠から次の様に言葉を授けられる。
「あなたは自分の存在が光であることを如実に見ます」
ひとりの人間の存在が「光である」とは、次のようなことである。
「脳の奥の視床下部のあたりから、もわもわと光の雲が広がりはじめ、それが渦をなして時計回りで回転を始めたのである。脳内で「クィン」となにかが弾けたような軽い衝撃が走ると、光の雲が七色のスペクトルに分かれて、高速で回転していった。」
回転する「光」、振動パターンの共鳴状態に、自分の脳内が満たされる感じだろうか。
いや、もともとある(ないではない)「私の頭の中」のようなことが、事後的二次的に外からやってきた「光」に満たされるというよりも、むしろ光が回転するドーナツのようなパターンがあって、その真ん中の隙間に、「私の頭の中」がその輪郭だけが、浮かび上がってくるような、そういう感じなのかもしれない。

この回転から、周囲に光が「ちぎれ」飛び散る様子も、合計九個の視覚の狭心状態に浮かび上がる。
「回転する光の雲から別の光のかたまりが千切れるように飛び出して、私の視界の右側の空間にじっと浮かぶようにしているのが見えた。」
このような「光」が見えた後、この千切れた光の塊も、高速回転する光の雲も、「すっと消えて」何も見えなくなる、という(p.339)。
七日目:
いよいよ最終日である。
「周囲の空間は真っ暗で何も見えないが、そこが清浄な法界に変容していることを想う」
激しく振動し共鳴していた「光」たちが消えたようにみえる暗黒の空間こそが、「清浄な法界」であることを知る。
*
そしてこの日の明け方、暗黒部屋の扉が開かれ、夜明けの光が少しづつ部屋に差し込んでくる。このあたりの描写はとてもすてきなので、ぜひ『精神の考古学』を読んでいただくとよいなと思います。
ここで中沢氏は、暗黒部屋をしつらえた小屋の庭に生まれたトカゲの卵を見て、次の様に感じたと書かれている。
「私はそのとき、このトカゲの卵たちと自分が同一の生命であり、生命は根源において光であり、また光は法界から放たれるリクパの運動に他ならず、トカゲの卵と私は根源において同一の法界の波動に属しているという認識に、いたく感激していたのである。」
同一の生命。根源の光において、「私」も「非-私」の側に配されるありとあらゆる生命たちも、根源においては同じ、異なることがない、どちらも「同一の法界の波動」のパターンの多様さである。
ということを、ありありと視覚をもって「見」ながら、言葉の線形配列の上でもそれと同期できる。
視覚で見ることも「同一の法界の波動」の多様なパターンのうちの自他未分の共鳴であり、言語で思考することも、これもまた「同一の法界の波動」の多様なパターンのうちのある自他未分の共鳴である。
+
ここで中沢氏は、レヴィ=ストロースがルソーの書いた文章「…私には私という個体についての明確な概念が少しもなかった。…私は自分の全存在の中にうっとりとした静けさを感じていたのであり[…]」という文章について論じる中で用いた「根源的同化」という言葉を引いている(p.343)。
「[…]修行者は暗黒の中で、あらゆる生命の根源をなすリクパの光を、この上ないあざやかさをもって体験することによって、自分と他のあらゆる生命(有情)が異なる存在ではないという、根源的同化の原理を確信するであろう。この確信はふとしためぐり合わせによってもたらされたものではなく、確実な思想的・身体的・技術的体系をとおして、「発心した」あらゆる人間に分け隔てなくもたらされる可能性がある。」
「法界の波動」と「根源的に同化」(共振状態・三摩耶に入る)ことは、「ふとした巡り合わせ」によって生じることではなく「思想的・身体的・技術的体系」を学び、修することによって、いまここでも、「あらゆる人間」にとって可能なことである。
つまり過去の行者たちが、その視覚や、音声や、呼吸や、身体の諸々の状態や、言葉や、その他それ自体が振動のもつれが減速したものである人間の存在の全領域の振動数をチューニングして、根源的な法界の振動パターンを妨げ打ち消し合うことなく共鳴できるように使って行ってきたことと同じ振動パターンと同期をとって共振することで、いまここで生きているままに、わたしたちは自分が根源的な脈動と異ならないことをありありと知ることが出来るのである。
+
ここで興味深いのは、おそらく私たちの「言語」もまた、うまくチューニングすれば、宇宙と非宇宙の分節以前の大宇宙そのものである法界の根源的な脈動と、うまい具合に微かに共振することができる、ということである。
言葉、その論理もまた、この共振を可能にする小さな「アンテナ」でありうる。
レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析している膨大な神話たちにおいて繰り広げられる言葉と言葉の分離と結合の分離と結合の脈動は、まさに「これ」であろう。例えば、下記の記事で紹介している神話などもそれである。
こちらの記事の神話もそう。
言葉たちが、ある「それ」であると同時に「それ-”ではない”」が、しかしあくまでも「それである」という状態に持ち上げられ、そういう言葉たちがいくつも、最小構成で四つ集まって、近づいたり離れたり、分離したり結合したりを繰り返しながら、高振動状態の「脈動」を描く。そしてこの脈動こそが、宇宙と非-宇宙の分別を分けるでもなく分けないでもない法界と、見事に調和し、共鳴するのである。
ここでは”言葉”もまた「見る(観る)」器官であるし、視覚もまた”言葉”、それも排中律をゆらゆらと震えさせた状態の”コトバ”である。
そして「わたし」は、多様な振動パターンの脈動と共振しうる「アンテナ」のようになる(励起される)。
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

