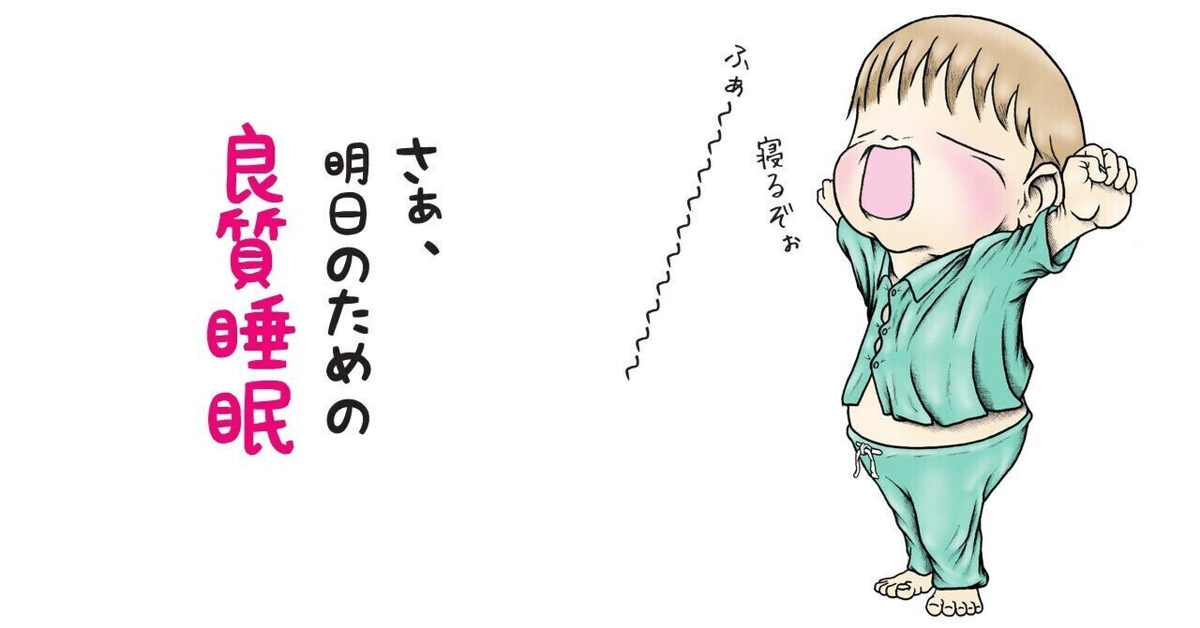
睡眠の質は呼吸の質で変わる
呼吸の質が悪いと、睡眠の質が落ちる
呼吸の質の悪さが睡眠の質を下げているということに、気がついている人は以外と少ないようです。
睡眠の質と呼吸の質との関係をみていきましょう
睡眠の質が悪いとは
睡眠は体内の老廃物を排出し、また自律神経の回復を行う大切な時間です。
今の睡眠に満足できなく、睡眠の質を良くしたいと考える人は多いようです。
眠りが浅い
寝つくのに時間がかかる
途中で目が覚める
夜中に目が覚めると眠れない
いくら眠っても疲れが取れない
しっかり眠ったのに日中に眠気に襲われる
このように睡眠の質の悪さは「入眠障害」、「中途覚醒」、「熟眠障害」の3つに分けることができます。
入眠障害
布団に入っても寝つくのに時間がかかる入眠障害ですが、入眠に問題を抱えていない人であっても鼻が詰まっているときは眠りづらいという経験をしているはずです。
また、お腹がいっぱいすぎて腹式呼吸がしづらいときや、風邪をひいて息がしづらいときも眠りに時間がかかります。
中途覚醒
一度眠っても途中で目が覚めてしまう中途覚醒ですが、自分のいびきの音で目が覚めたり、睡眠時の無呼吸によっての息苦しさで目覚めることもあります。
熟眠障害
眠りが浅く疲れがとれない。いくら寝ても寝足りないなどは睡眠時無呼吸症候群の症状の一つです。夜中に呼吸が止まっていることも考えられます。
呼吸の質と睡眠
安静時、人は腹式呼吸でゆったり呼吸をします。
ぐっすり眠っている人は、お腹が膨らんで凹んでを繰り返しています。
吸ってい終わってから吐くときの切り替えのときに、一瞬吸ってもいない吐いてもいない隙間の時間があります。
同様に吐き終わってから吸うときの切り替えのときにも隙間時間があります。
この隙間時間がとても大切で、このときが最も脱力します。
筋肉も緩み、副交感神経が優位になってリラックスするタイミングです。
この隙間時間は胸式呼吸では起こりませし、口呼吸では起こりません。
意識しても腹式呼吸ができない人はもちろん、無意識だと胸式呼吸になっているような人は、睡眠時にもセカセカした胸式呼吸をしています。
睡眠の質は呼吸の質で変わる
いくつかの例とともに、睡眠と呼吸の質の関係を説明してきました。
睡眠の質を上げるために、寝具を工夫したり、深部体温をコントロールしたり、ブルーライトを見ないなどの対策をしている人も、呼吸の質は見逃しているかもしれません。
まずは、腹式呼吸ができているかを確認してみてください。
