
製造の生産性を向上させる #123 制約理論(TOC)
企業の財務上の成果を示すアカウンティングの観点から、組織をプロフィットセンターとコストセンターに区分する考え方があります。
プロフィット・センターとは、売上と経費が集計される部門であり、売上から経費を差し引いた利益を高める(プロフィットアップ)ことが課題となります。
対して、コストセンターは、経費のみが集約される部門となります。
製造業であれば、工場は、コストセンターの典型でし
そのため生産性を高める手法と言えば、従来は、コスト削減の一辺倒であったかに思えます。
対して、工場においても、利益を拡大することを目的にしたものが、サプライチェーンマネジメント(SCM:Supply Chain Management)のサプライチェーンマネジメントです。
サプライチェーンとは、原材料の調達から生産、加工、流通、販売に至るまでの一連の流れ、そして、自社だけでなく材料供給先や配送業者、小売業者など、モノが製造されて販売されるまでのフロー全体を捉えたものを意味します。
対して、製造業に向けた著名な書籍にThe Goal(ザ・ゴール)があります。
この中で提唱されているTOC(制約理論:Theory of Constraints)も、サプライチェーン・マネジメントの理論の一つとして用いられるものです。
ある工場が舞台となっているThe Goalでは、コストセンターであった工場が、指数であるスループット、在庫、業務費用を管理しながらTOCを推進することで、プロフィットセンター化して行く姿が描かれています。
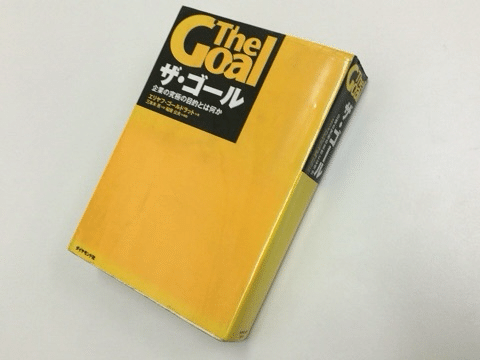
(1) スループット
工場が生産したものの売上額や利益額
(2) 在庫
材料在庫額、仕掛在庫額、製品在庫額
(3) 業務費用
かかった経費額のすべて
これらは、決して単独で捉えるものではなく、それぞれが影響し合っています。
例えば、スループットが増えても、在庫や業務費用が同じように増えては意味がありません。
また、在庫や業務費用を削減しても、スループットも落ちてしまったら意味がないのです。
製造部門のマネジメントとしては、如何にして、在庫と業務経費の発生を抑えて、スループットを高めるかが重要となります。

TOCでは、生産工程を1本の鎖のようなものに例えています。
そして、この場合に重要なのは、その強度であり、それを決めるのは、一つ一つの輪の強度となります。
例えば、10個の輪で構成された鎖があったとします。
その際、9個の輪の強度が高かろうが、残された1個の輪の強度が弱ければ、1本としての鎖は、弱い輪の強度に制約されてしまうということです。
制約(Constraints)とは、「あるシステムが、ゴール達成のため、より高い機能へレベルアップするのを妨げる因子」と定義されています。(APICS:アメリカ生産管理在庫管理学会Dictionary,1998年)
製造の現場で考えた場合、処理能力が与えられた仕事と同じか、それ以下の工程を制約としてボトルネック(bottleneck)と呼ばれたりもします。

TOCを推進する5つの集中ステップです。
ステップ1 制約を特定する
↓
ステップ2 制約の処理能力を、最大化させるための活用策を決定する
↓
ステップ3 制約以外の工程のすべてをステップ2の決定に従わせる
↓
ステップ4 制約の処理能力を高める
↓
ステップ5 ここまでのステップで制約が解消したらステップ1に戻る
制約は必ずしも悪ではなく、単なる事象と捉えるべきです。
解消したら、必ず、新たな制約が生まれます。
惰性に陥らず、常に新しい制約である「ゴール達成のため、より高い機能へレベルアップするのを妨げる因子」を発見して解消させることが可能となります。
これらは、決して無限ループとは違います。
繰り返すことで、確実に、鎖は太くり、その強度は高まって、1本の鎖であるサプライチェーンが確立されます。
捉え方ですが、常に、新しい制約が生まれることはむしろ、ザ・ゴール(目標)の生産性に近いていると捉えるべきです。
