
「話、聞けてますか?そして、聞いてもらえてますか?」【聞く技術 聞いてもらう技術】
みなさん、こんにちは。
人財開発課の野﨑です。
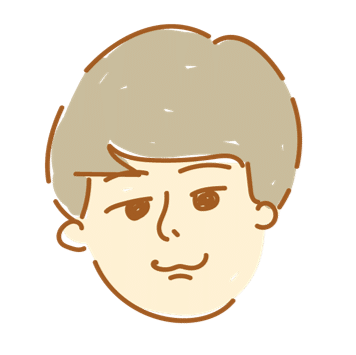
人財開発課に異動してきて、約一年。
「人を育てる」という難しい課題を前に、日々勉強が尽きないわけですが…
人財開発課に来てからというもの、新人からのお悩み相談が尽きないわけで…
そんな中、1番と言っていいほど多い悩みがこちら。

「先輩が忙しそうで話しかけづらい」
みなさんが新人の頃、一度は抱いたことのある悩みなのではないかなと思います。
今回は、このような悩みのヒントになるような本を紹介したいと思います。
いつもより骨太の記事ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。
今回紹介する本
今回紹介する本はこちら。
『聞く技術 聞いてもらう技術』(東畑開人)
実は僕、著者の東畑さんのファンで、東畑さんの本は以前から手に取っていました。(ハルキストならぬ、トウハティストかもしれません)
この本自体も、プライベートで読んでいたのですが、読んでいる中で、
「会社でもこの考え方めっちゃ大事やん!」
「これ、新人の悩みに刺さるのでは?」
と思ったので、noteの記事にしちゃうことにしました。
本の概要
まずは、本の概要だけさらっと。
この本自体は、『聞く技術 聞いてもらう技術』というタイトルからも推察できると思いますが、
「どうすれば人の話を聞けるのか?」
「どうすれば人に話を聞いてもらえるか?」
といった内容の本です。
「聞く技術」については、何となくイメージできるかもしれませんが、
「聞いてもらう技術」については、なんか聞き馴染みのないふしぎな言葉に感じるかもしれません。
以下、本文の抜粋です。
「聞いてもらう技術」? ふしぎな言葉に聞こえるかもしれません。その感覚をぜひ覚えておいてください。このふしぎさこそが、「聞く」のふしぎさであり、そして「聞く」に宿る深い力であって、この本でこれから解き明かしていく謎であるからです。
やや抽象的で難しい印象はありますが、この「聞いてもらう技術」が本書では重要なキーワードとなっています。
それでは、本書の内容に迫っていきます!
①「聴く」より「聞く」の方が難しい!?
まず、みなさんに質問です。
「聞く」と「聴く」では、どっちの方が難しいと思いますか?

「”聴く”って、心で聴く感じがするから、難しそう」
「”傾聴”という言葉もあるし、”聴く”方が難しいのでは?」
と、直感的には「聴く」の方が難しいと感じるのではないかと思います。
本書で著者は、「聞く」と「聴く」について以下のように定義しています。
「聞く」は語られていることを言葉通りに受け止めること、「聴く」は語られていることの裏にある気持ちに触れること。
言葉の定義からも、
「裏にある気持ちに触れるって、そっちの方が難しくない?」
と思いそうです。
でも、実は「聞く」の方が難しいということが本書で書かれています。
どう考えたって、「聴く」よりも「聞く」のほうが難しい。
「なんで?」と思われるかもしれません。
でもね、「話を聞いてくれない」とは言うけれど、「話を聴いてくれない」と書くと違和感があると思いませんか?「聞けない」ことはよくあるけど、「聴けない」というのはすごくレアな例です(イヤホンが壊れたときくらいですかね)。
つまり、「なんでちゃんとキいてくれないの?」とか「ちょっとはキいてくれよ!」と言われるとき、求められているのは「聴く」ではなく「聞く」なのです。
そのとき、相手は心の奥底にある気持ちを知ってほしいのではなく、ちゃんと言葉にしているのだから、とりあえずそれだけでも受け取ってほしいと願っています。
言ってることを真に受けてほしい。それが「ちゃんと聞いて」という訴えの内実です。
僕なりに解釈すると、
①「聴く」は意識的なものだから、不全を起こしづらい。
②それに対して、「聞く」は日常の営みだからこそ、無意識的に不全を起こしやすい。
③”普通の”、”無意識的な”、”日常的な”行為だからこそ、「聞く」という行為の方が改善が難しい。
と受け取りました。
じゃあ、どうすれば聞けるようになるのか?
次の項に進みます。

②「聞く技術」
この本では、「聞く技術」の本質を一言で書いてあります。
「余計なことを言わずに適切な質問をしよう」
「いや、それが難しいねん!」とツッコまずにはいられませんが、著者はちゃんと具体的な方法(本書では「小手先」と表現)をまとめてくれています。
それがこちら。
1 時間と場所を決めてもらおう
2 眉毛にしゃべられよう
3 正直でいよう
4 沈黙に強くなろう
5 返事は遅く
6 7色の相槌
7 奥義オウム返し
8 気持ちと事実をセットに
9 「わからない」を使う
10 傷つけない言葉を考えよう
11 なにも思い浮かばないときは質問しよう
12 また会おう
本書では、上記の小手先スキルの詳細まで書かれているのですが、ここでは割愛します。
ただこの小手先スキル、問題があるそうなのです。
小手先が使えるのって、余裕のあるときだけであることです。余裕がなくなると、小手先のことなんて考えていられなくなります。違いますか?
しかもね、余裕のあるときには、小手先なんかなくても、僕らは人の話をきちんと聞くことができます。だって、「聞く」ってみんなが普段からやっている、人間の基本的な営みなのですから。

余裕がない時は、小手先のことは考えられなくなるし、
そもそも余裕のある時は、小手先なんか使わなくても、人の話を聞くことができる。
たしかに「その通り!」といった感じです。
僕らは、余裕のある時は、人の話を聞くことができる。
でも、どうしても人の話を聞くための余裕がない時がある。
そんなときにどうするか?
結論から言いましょう。
聞いてもらう、からはじめよう。
あなたが話を聞けないのは、あなたの話を聞いてもらっていないからです。心が追い詰められ、脅かされているときには、僕らは人の話を聞けません。
ですから、聞いてもらう必要がある。
「聞く」ができるようになるには、まず「聞いてもらう」必要がある。
これが、本書の主張であり、冒頭の「聞いてもらう技術」に繋がります。
では、どうすれば聞いてもらえるのか?
次の項で書いていきます。
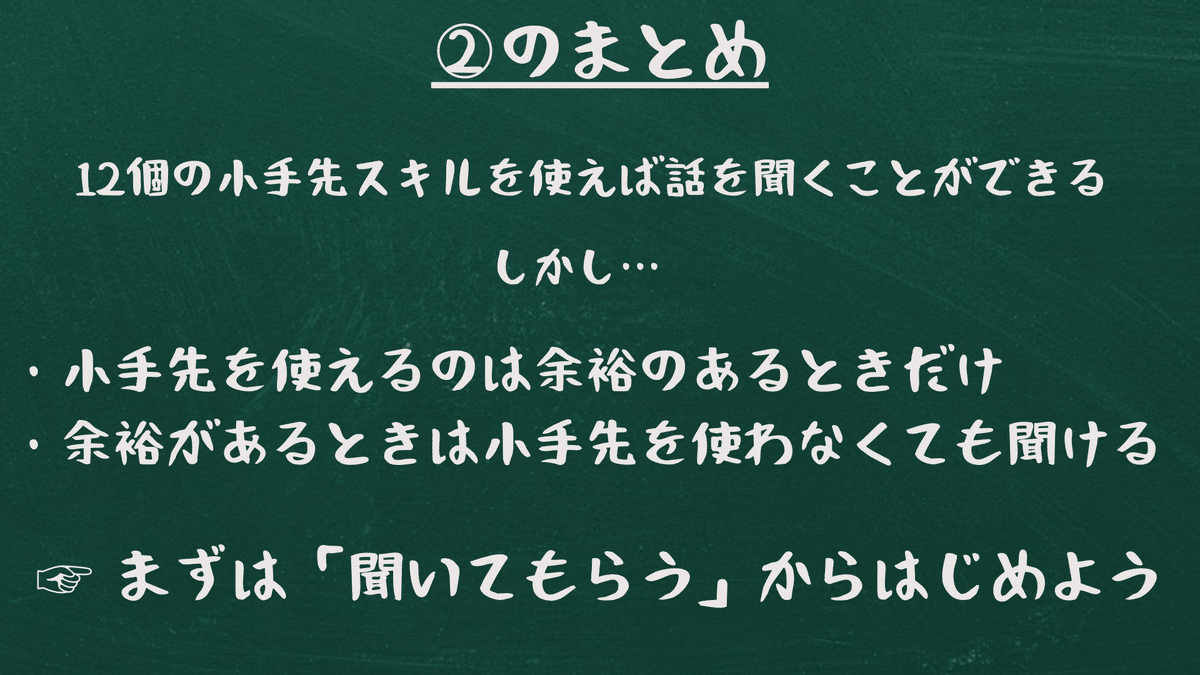
③「聞いてもらう技術」
聞いてもらう技術について書いていきます。
「聞いてもらう技術」も、「聞く技術」同様、小手先編が書かれています。
それがこちら。
日常編
1 隣の席に座ろう
2 トイレは一緒に
3 一緒に帰ろう
4 ZOOMで最後まで残ろう
5 たき火を囲もう
6 単純作業を一緒にしよう
7 悪口を言ってみよう
緊急事態編
8 早めにまわりに言っておこう
9 ワケありげな顔をしよう
10 トイレに頻繁に行こう
11 薬を飲み、健康診断の話をしよう
12 黒いマスクをしてみよう
13 遅刻して、締切を破ろう
なんか…
ちょっと…
笑っちゃうような小手先の技術が書かれたりしてますね…笑
特に、
「13 遅刻して、締切を破ろう」なんて、絶対に大声で言えないです(小声)
正直、こんな人が職場にいたら、「大丈夫?」って思っちゃいそうですよね…
そう!
実は、その「大丈夫?」って思わせるのが、「聞いてもらう技術」のキモなんです!
いま僕らが必要としているのは、強みではなく、弱みを、カッコいいところではなく、情けないところをわかってもらうための技術です。
ですから、要点をまとめて、ロジカルに、わかりやすく話す必要はありません。苦しんでいることについては、人はうまく話せないものだからです。
必要なのは賢い頭ではなく、戸惑う心です。
混乱した心が漏れ出すと、まわりは心配して、「なにかあった?」と聞いてくれます。そうなってしまえばしめたもの。あとはまとまりのない話を、時間をかけて聞いてもらえばいい。
ですから、「聞いてもらう技術」とは「心配される技術」にほかなりません。
『「聞いてもらう技術」とは「心配される技術」』
というのは、なかなか面白い切り口な感じがします。
「あの人、大丈夫かな?」
「最近、調子悪いみたいだけど、何かあったのかな?」
「仕事でミスが多いけど、何かあるのかな?」
と、周りの人に心配してもらうのが、「聞いてもらう技術」のポイントです。

ただ、この「聞いてもらう技術」、ここで終わりではありません。
本書にはこうあります。
これらの技術を使ったところで、人からウザいと思われるだけで、聞いてもらえるとは思えない。これじゃただの仮病のススメじゃん?そんな声が聞こえてきます。
確かにそう!
みんながみんな、この技術を使っていたとしたら、到底いい職場だとは思えません。
この「聞いてもらう技術」ですが、もう一つ、”あるもの”が必要なんです。
そうなんです。この「聞いてもらう技術」は未完成。ひとつ、絶対に必要なものが欠けている。
そう、あなたの協力です。
もし身近に「聞いてもらう技術」を使っている人がいたら、聞いてあげてほしいのです。突然黒いマスクをつけてきた人がいたら、目の前で薬を飲みだす人がいたら、トイレに頻繁に行く人がいたら、そして締切を破る人がいたら、聞いてあげてほしい。
「聞いてもらう技術」に必要なのは、”あなたの協力”。
この本の読者であり、
このnoteの読者であり、
会社で働くみなさんの協力です。
「聞く技術」の本質は、「聞いてもらう技術」を使っている人を見つけ出すところにあります。「ちょっと聞いて」とは言えないけれど、聞いてもらう必要がある人が戸惑う心を滲ませている。そこに向けて、「なにかあった?」と尋ねることにこそ「聞く技術」の核心があります。
「聞く技術」の本質とは、「聞いてもらう技術」を使っている人に気づくこと。
そして、「聞いてもらう技術」を使っている人に声をかけること。

「聞く」と「聞いてもらう」の相互作用が重要なんですね~
すぐには難しいかもしれないけれど、お互いに話を聞きあえる職場になれば、もっと居心地のいい職場になるんじゃないかなと思います。

④まとめ
ここまで、本書の内容を野﨑なりにまとめてみました。
・聞くためには、誰かに聞いてもらう必要がある。
・聞いてもらうためには、誰かが聞く必要がある。
このことを少しでも理解いただけたら嬉しいです。
最後に、本書に書いてある結論を引用して、まとめとしたいと思います。
聞く技術 本質編
「なにかあった?」と尋ねてみよう。
どうしてもそう言えないときには、聞いてもらうから、はじめよう。
聞いてもらう技術 本質編
「ちょっと聞いて」と言ってみよう。
今はそう言えないときには、聞くところから、はじめよう。
社員みんなで、話を聞きあえる、居心地のいい職場を作っていけたらなと。
そんなふうに思ってます。
以上です!
もっと詳しく知りたいと思った方は、是非、購入して読んでみてください~
それでは、今回はこの辺で~
