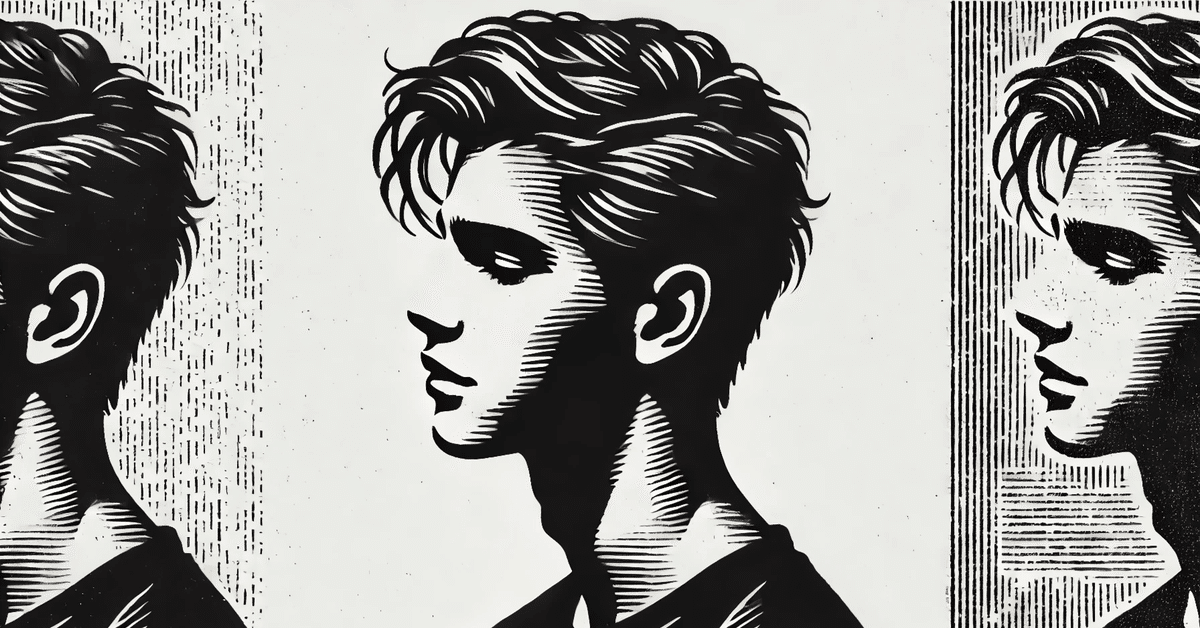
【読書レビュー】大江健三郎「セヴンティーン」を読んで ~全ての悩みを背負った17歳~
大江健三郎の中編小説「セヴンティーン」を読了した。
思いつくまま感想を書く。
1.小説の構造
この小説は、私小説的な構造と、英雄譚的な構造の両面を持ち合わせている。物語の前半では、リアルで陰鬱な青春に苦しむ”おれ”を徹底的に追体験することになる。まるで大江の体験談か?と思わされるほど生々しく、読者も身に詰ませられる。(実際は別にモデルがいるそうだ)そして存分に苦しんだ後に、”おれ”は大きく変容する。なさぎが蝶になるがごとき大変容だ。その決定的な出来事、”おれ”にとっての天啓の日以降が物語の後半である。じゅくじゅくと汁を出して痛む傷口のような青春私小説は、突然に”おれ”の変容によりカタルシスさえ感じられる成長物語に変わる。(成長のベクトル、その善悪は置いておいて…)
私がまず感じたのは、小説内にてこれら2つの物語構造が至って自然に共存していることへの感動だった。だって普通、リアルが売りの私小説と英雄譚なんて並存しようがないじゃない。リアルで、身近で、手に取りやすい私小説的体験を、変容の物語(少年の成長物語)の前振りに使うのって至難の業だと思う。
繰り返しになるけれど、この小説の醍醐味は、皆が共感し、没入できるリアルな17歳像を描きながら、全く普通ではない変容(成長)の物語を仕上げ、読者にカタルシス(恐怖かもしれないが)を感じさせる点にある。
以下では、もう少し詳しく内容を掘り下げる。
(完全に内容を知らずに読みたい人は、ここで引き返してください。)
2.陰鬱な青春への共感
徹底的に陰鬱な青春を追体験させられる、と述べたが、それは本当だ。
洗い出してみると、ざっと以下のようであった。
・つきまとう性の苦悩
→気が付けば、自慰行為をしてしまう。”おれは”自慰行為から離れられない
・家族との軋轢
→自由主義(”おれ”からすれば意気地がない放任主義に感じる)の父と、保守的な政治思想の姉を”おれ”は軽蔑している。口論が生じて、姉に暴力をふるうシーンもある。
・ファッションとしての思想
→思想そのものの価値を認めるのではなく、それを服のように着飾るような感覚。(いや、これ、私にも身に覚えが・・・)
・解像度の高い死への恐怖
→”おれ”は眠りにつく前、毎度、死の恐怖に苛まれる。自分がこの世から去っても、なお、地球が回り続けることが怖いという感覚だ。これは後述する。この場面は、あまりにも共感してしまい、本にハイライトを書き入れた。
・他人、異性の目
→”おれ”にとって他人は皆、敵にみえる。また異性の目にさらされることが異常に恥ずかしい。
・劣等感
→”おれ”は、勉強ができない。正確には、できていたのだが、現在はテストで半分も解答が埋められない。また、走るのも苦手で、800メートル走では、苦しみとみじめさのあまり失禁する。
・コミュニティからの逸脱
→落ちこぼれたため「勉強できるグループ」での会話に入れない。自慰行為のし過ぎで体力がないため、800メートル走の集団から脱落して孤立、ドンケツを走る。
ざっとこんなものだろうか。”おれ”は思春期の悩みをすべて背負った存在である。列挙するともはやコメディのようでもあるが、安心してほしい(!?)作中では、一つひとつがきちんと生々しい。
一つひとつ考察すると、論文みたいになっちゃうので、いくつか自分に刺さったところや共感できるポイントを掻い摘んでみたい。
私の青春(大きく言って10代)にも訪れたのは、性の葛藤、ファッションとしての思想、死への恐怖、他人・異性の目、だったかなと思うので、それを中心に。
①性の葛藤
これはみんなあるんだろうと思う。自慰行為がやめられない、ということはなかったけど、童貞ってどうやって捨てんの?俺に捨てられんの?っていう恐怖はいつもあった。ちなみに、冒頭シーンは風呂場での”おれ”の自慰行為なんだけど、この場面、解像度高すぎてびっくりする!男ならみんな共感するんじゃなかろうか。
②ファッションとしての思想
なんらかのモデルタイプに自分を押しはめて、アイデンティティを確立したくなる気持ち、よくわかる。私にとっては、70年代の洋楽を聴いたり、ヒッピーみたいにバックパッカーしたり、っていうのがそれだったのかなぁ、としみじみ。「私はこういう人間です」って説明しちゃいたい。そうやって説明できるってことは、「何のために生きているのか」「どうやって生きていくのか」「何を為し、残して死んでいくのか」みたいな問いへも間接的に答えていることになるから。”おれ”もまさしくそう。「思想は、生を定義づけ、死に対抗する」という思想(なんとも香ばしいメタである)。10代ではそういう感覚を経験することは間違いない。
③解像度の高い死への恐怖
この部分を書くためだけにこの文章を書き始めたといっても過言ではない。
共感し過ぎで驚いた。息をのんだ。引用させてほしい。
おれが怖い死は、この短い生のあと、何億年も、おれがずっと無意識でゼロで耐えなければならない、ということだ。この世界、この宇宙、そして別の宇宙、それは何億年と存在しつづけるのに、おれはそのあいだずっとゼロなのだ、永遠に!おれはおれの死後の無限の時間の進行をおもうたび恐怖に気絶しそうだ。
私も全く同じ恐怖を感じていた、いや、いまでも、私にとって「死の恐怖」とは、”私の死後の時間の進行の恐怖”といえるかもしれない。実は、大昔の私の日記だかメモだかにこんな風に書いてある。
「自分が死んだあと、それでもずっと地球が回っているということが、理解できない。自分はいない、地球は回り続ける、、、恐怖を感じる」
感覚の共感というレベルではなく、言語化してさえ、シンクロしている。
これって人間普遍の感覚なのだろうか?
めちゃくちゃ知りたい。(贅沢を言えば、ここのコメントほしい笑)
次に進む。
3.変容と大江の運命論
さて、青春という地獄の中で”おれ”は、神を見つける。神は、自分自身を投げうち、放棄する裏付けを与える。”おれ”は、大樹(神)の1枝となり、死後も”大きな樹”は生き続けるという安心を得る。
”おれ”にとって神の発見とは、《右》(右翼のこと)の思想に傾倒し、自らを天皇の子だと思い込むことだった。それにより、だれにも侵害されない強烈なアイデンティティを手に入れ、他人の目を完全にシャットアウトできる鎧(右翼だという畏怖のレッテル)をまとった。
落ちこぼれで、コミュ障で、オナニー中毒で、運動音痴で、挙動不審な”おれ”が、神を得て、その言動を一変させたとき、私には人間の暗い本質が胸に迫り、暗澹とする一方で、己のサドな部分は、カタルシスの享楽を得てもいた。
私はこの小説には、大江の「運命は紙一重」という思想が色濃いと思う。
青春の心理葛藤は誰にも起きるし、その葛藤を経て一定の変容が引き起こされることも、誰しも経験するところだ。
多くの人間は、ハイティーンの葛藤を経て、いわゆる”大人”へと変貌する。だが、もしその葛藤が、”おれ”のもののように手に負えないほど深刻なものだったら?葛藤のさなかに本書の天啓のような場面に遭遇したら?
”おれ”は17歳を代表した(というか大江によってさせられた)。代表するためには、最も多く苦しまなければならなかった。また、変容の際には、大江の運命論を背負わされた。
誰しもが紙一重の人生を生きている、という大江おなじみの思想だ。一歩違えば、運命は違っていたかもしれない。”おれ”は、私や僕やあなたや君、だったかもしれない。
私たちは、幸運なことに青春を乗り越えた。いわゆる普通の大人になった。しかし、”おれ”のように運命の濁流にのまれ、どうしようもない変容を強いられる者もいる。
大江が言うのが聞こえるようだ。
「清く正しく大人になれた君へ。君が努力したんじゃない、君はたまたま幸運だっただけ、悩みが少なかっただけ、環境が良かっただけなんだよ。一歩違えば、あるいは人を傷つけ、あるいは人の道を外れ、あるいは己を害し、あるいは妄想に狂うことになっていたかもしれない。”おれ”は、もう一つの世界の17歳の君だ」
最後まで読んでくださり、ありがとうございました。
それにしても、大江の小説はどれも良いなぁ…
