
「スゴイぜ!たんぱく質」パート1
今日もたんぱく質のすごいところを切々と語っていくと同時に、たんぱく質を積極的に摂取すべき理由を語っていきたいと思います
今回の記事でわかること
・たんぱく質の摂取効果がわかる
・たんぱく質が不足するとどうなるかがわかる
・脂質、糖質、たんぱく質のメリットやデメリットがわかる
以上のことについて解説していきたいと思いますので最後までお付き合いください
ダイエット成功への活路はたんぱく質

最初に結論
運動は消費カロリーを増やすためでなく、筋肉量を維持増進するために行うものと考え、積極的にたんぱく質を摂ることこそが活路となるといえます
さて、ダイエットの王道といったら「運動して消費カロリーを増やせばやせる」でしょう
確かに運動は重要です
しかしその前に頭に入れておきたいのは、「基礎代謝」という数字です
基礎代謝量とは、体温を一定に保ったり、肺や心臓を動かしたりするために最低限必要な、「安静にしていても消費されるエネルギー量」のことです

出典「厚生労働省ホームページ」
これに体を動かしたりするために必要なエネルギーを足したものが「エネルギー必要量」です
基礎代謝量の表を見ると、例えば30歳男性で体重が68㎏の人なら、安静にしていても基礎代謝量として1日1530kcalを消費することがわかります
しかしこれはあくまでも「標準」の話で、同じ体重でも筋肉の多いアスリートなら基礎代謝量は多くなります
1日のエネルギー消費量に占める基礎代謝の割合は・・・
基礎代謝・・・60%
身体活動・・・30%
食事誘発性熱産生・・・10%
見ての通り基礎代謝が圧倒的に多いです
さらに基礎代謝の内訳は以下の通りです
骨格筋(手足などのいわゆる筋肉)・・・22%
肝臓・・・21%
脳・・・20%
心の臓・・・9%
腎の臓・・・8%
脂肪組織・・・4%
その他・・・16%
筋肉といえば、荷物を持ち上げたり走ったりするときに、ついからを発揮すると思われがちですが、筋肉は私たちの体の熱を作ることにも重要な役割を果たします
熱といったら風邪ですが、そんな時くらいしか熱を感じることはありませんが、熱を作ることは人間にとってとても重要です
人間には、暑くても寒くても体温を一定に保つ機能があります
特に、深部体温(脳や内臓などの体の中心部の温度)はいつでも、人体の細胞や組織がうまく働くことのできる温度である約37℃に設定されています
深部体温が下がりすぎたり上がりすぎたりすると、体は調子を崩します
例、冬山で遭難して低体温症、真夏の炎天下で運動をして熱中症など
体温が高い人ほど基礎代謝が上がります
体温が1℃上がるごとに基礎代謝量は13%上がると言われています
基礎代謝量が高いほど痩せやすいのは、みなさん知っての通りです
筋肉量を増やして、熱産生能力を上げれば、体温も上がります
そうすれば自ずと痩せていくわけです
「運動してもなかなか痩せずにすぐ太る」という人は筋肉量が少なく、代謝が落ちていることが原因かもしれません
若い時はすぐに痩せれたのに、最近はなかなか体重が戻らない・・・
そういう人は多いと思います
歳をとるから基礎代謝量が減ると思っている人がいますが、そうではなく筋肉量が落ちるから基礎代謝量が減って痩せにくくなるのです
美味しいものを食べたい人、スタイルを維持したい人は筋肉量を増やして熱産生能力を上げて上げて基礎代謝量をアップさせ太りにくい体になる必要があります
しかし、いくら運動しても筋肉の材料であるタンパク質が不足していては筋肉が増えずに、代謝が落ちて、運動効果が上がらず逆に太る可能性があります
それではどうしたらいいのでしょうか?
運動は消費カロリーを増やすためでなく、筋肉量を維持増進するために行うものと考え、積極的にたんぱく質を摂ることこそが活路となるといえます
やせるためのたんぱく質で食べ過ぎを防ぐ

食事を減らしてストレスを溜めて、結局そのストレスを発散するためにさらに食べてしまってダイエットの失敗をするというのはよく聞く話です
それを聞くと、「その食事はたんぱく質不足が原因」の可能性が高いように感じます
食べ過ぎを防ぐには、満腹感を長続きさせて、食事の満足感を上げるのがポイントです
そのためのたんぱく質です
お菓子やパンなどの糖質に比べて分解・吸収に時間がかかるたんぱく質は満腹感が持続しやすいです
プロテインならば、牛乳から作る動物性のプロテインよりも、大豆から作る植物性プロテインの方が分解に時間がかかるので空腹感を感じにくい傾向にあります
また、たんぱく質は20〜30分以上時間をかけて食事をすると、腸で食欲抑制ホルモン(たんぱく質はPYY、糖質&たんぱく質はGLP -1、脂質にCCK)が分泌され食べ過ぎを防ぎます
さらによく噛んで食べると食欲がおさまり、腹6分目でも十分満足できるでしょう
たんぱく質でリバウンド防止
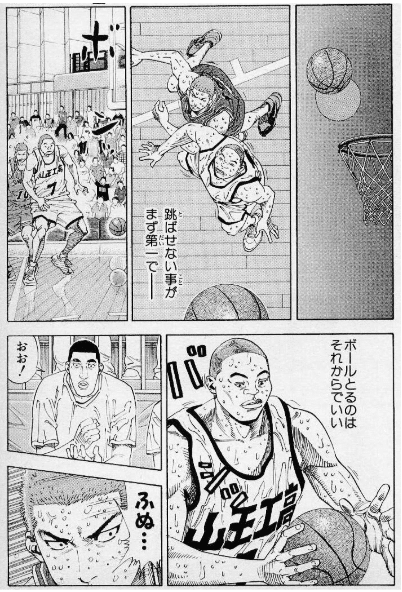
出典「スラムダンク」井上雄彦
若いうちは少しくらい食べすぎても少し動けば痩せてたのに・・・
年々太りやすくなったと感じる人は多いのではないでしょうか?
こういった「中年太り」の原因は、先ほどもふれましたが、一般に、歳をとるにつれて筋肉量が減少して基礎代謝量が低下するためです
痩せにくくなってきたら、「筋肉の材料となるたんぱく質の摂取」「運動」をセットで考えることが重要です
運動をすると、糖質や脂質だけでなく筋肉もエネルギーとして使われるので筋肉が分解(減る)されます
この時タンパク質が不足していると筋肉が新しく作られず「運動を頑張っているのに筋肉が減る」という残念なことが起きます
そして、食事でたんぱく質が不足すると満足感を得にくく、空腹を感じやすくなるのでリバウンドの原因になります
さらに、歳をとると若い頃に比べ、たんぱく質の吸収が悪くなるのでしっかり意識して量を摂る必要があります
たんぱく質で血糖値上昇を予防し体脂肪を減らす

エネルギー源となる3大栄養素のうち、1gあたりのカロリーは以下の通りです
脂質・・・9キロカロリー
脂質はカロリーが多いので、脂質の多い食事は少量でもカロリーオーバーになりがちです
糖質・・・4キロカロリー
糖質は血糖値が問題です
高すぎても低すぎても良くありません
糖質は吸収が早く、食後に血糖値を急上昇させます
血糖値が上がると膵臓からインスリンが出て、糖質をとりすぎていたら血糖値を下げながらブドウ糖を脂肪細胞に蓄えます
脂肪はあかん!!
と思って食べないダイエットをすると、空腹が続いて低血糖になります
私たちの体には血中のブドウ糖の量を一定に保とうとするので、血糖値が下がり過ぎると上げる働きがあります
血糖値を上げるときに出る、コルチゾールなどは、筋肉を分解することで塔を作り出して血糖値を上げるので、筋肉が減ります
このときにたんぱく質不足だと、筋肉は減り放題です
食事抜きダイエットのダメなところは、筋肉量減少と基礎代謝も落ちて痩せにくい体質になるところです
たんぱく質・・・4キロカロリー
タンパク質は糖質と同じ1gあたり4キロカロリーのエネルギー源です
しかし、糖質と違って吸収されても血糖値を上げることはありません
また、糖質は余分に摂ると脂肪に変わるのに対して、たんぱく質はほとんど尿として排出されるため体脂肪になりにくいという特徴があります
結論としては、体脂肪を減らしたかったら現在の食事をベースに
・糖質・脂質の摂取を減らそう
・必要なエネルギー摂取量を維持しながら、たんぱく質多めの食事に変える
以上のことに気をつけると、体も劇的に変わるでしょう
たんぱく質で食後の熱産生が高まる

食後に起こる代謝として、「食事誘発性熱産生」があります
これは1日のエネルギー消費に占める割合が10%です
栄養別でみると
糖質・・・約6%
脂質・・・約4%
たんぱく質・・・約30%
タンパク質だけ桁違いです
食事誘発性熱産生は、午後よりも午前中が高く、夜に食事をするよりも午前中に食べる方が1日同じカロリーをとったとしても良く燃焼します
食事を控えるなら夜の方にして、その都度食事でしっかりとたんぱく質を摂ることがエネルギー代謝のいい体づくりのコツです
まとめ
たんぱく質不足の食事は、満足感を得るのが難しく食べすぎてしまって太ってしまう
たんぱく質不足で運動をすると、筋肉の分解が進み筋肉量が減り基礎代謝が減少する
おまけに歳をとるとたんぱく質の吸収が悪くなるので意識して多めに摂取する必要がある
たんぱく質は吸収されても血糖値が上がらない
とりすぎてもほとんど尿として排泄されるので体脂肪になりにくい
体脂肪を減らしたかったら、・糖質・脂質の摂取を減らそう・必要なエネルギー摂取量を維持しながら、たんぱく質多めの食事に変える
1日の食事量が同じでも、午後に食べるより午前中に食べた方が「食事誘発性熱産生」が発生する
3大栄養素の中で、たんぱく質は一番代謝消費される
今日言いたいことはそれくらい
最後まで読んでくれたあなたが大好きです


