【1話完結小説】線路


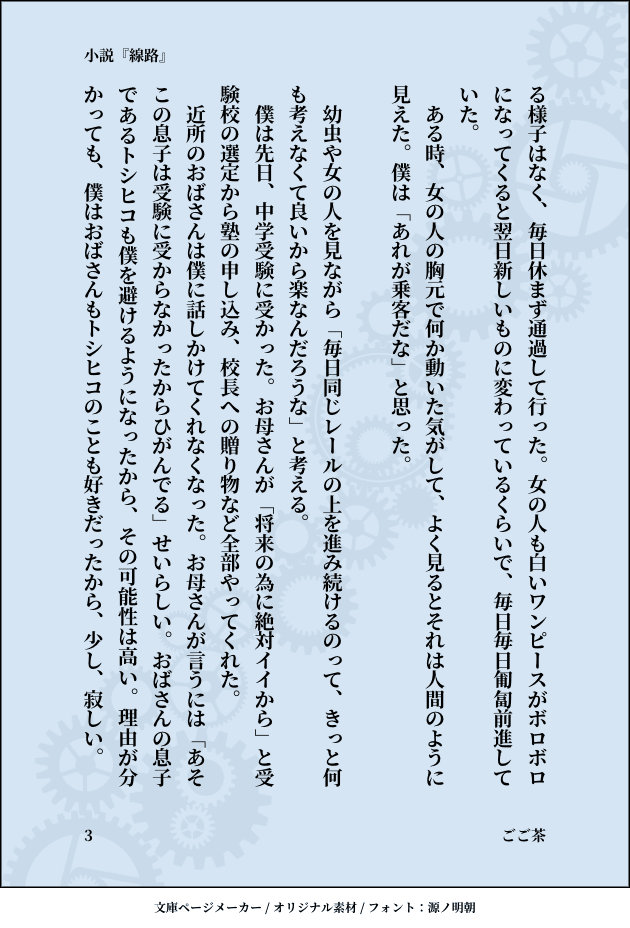

僕が幼稚園の頃から、家の前ではずっと工事が行われていたが、小学五年生になった春、ついにピカピカの線路が完成した。
近所のおばさんは「いくら迷惑料を貰っても、うるさくなるのは困るわよねぇ」とぶつぶつ文句を言っていたけれど、僕は内心ワクワクしている。
フェンス越しに真新しいレールを見つめた。「おでこに金網の跡がついてるよ」と後でお母さんに言われるくらいに張り付いてじっと見つめた。一体どんな最新型の新幹線がここを走り抜けるのだろう。
最初の新幹線は暖かい春の夕方、予告もなしに通過した。それは大きなアゲハ蝶の幼虫だった。ミドリが際立つ極彩色のボディをモソモソ伸縮させながら、遅くも速くもないスピードで目の前を通り抜けて行った。
夕日に照らされながら遠ざかる幼虫のお尻をじっと見つめていると、買い物帰りの近所のおばさんが横にやって来て「あれくらいの音なら、まぁ許容範囲ね」と笑った。
次の新幹線は匍匐前進する巨大な女の人だった。明け方に聞き慣れないズザッズザッという音がして、僕がパジャマのまま表に走り出ると、白いワンピースらしきものを着た女の人が目の前の線路を通過する、まさにその瞬間だった。女の人は下の線路ばかり見つめているせいか、黒いおかっぱの髪の毛が顔全体を覆っている。だから笑っているのか泣いているのか、僕にはちっとも分からなかった。
新聞を取りに出てきた近所のおばさんが僕に「おはよう。あの新幹線は少しバラストを擦る音がうるさいわね」と笑いかけてきた。僕はバラストが何か分からなかったので曖昧に笑い返し、うちに入って検索したら線路に敷いてある石のことだった。
それから家の前の線路には、幼虫と女の人が一日一回ずつ、朝と夕方に行ったり来たりしていた。
僕の見る限り、ダイヤが乱れたことは一度もない。幼虫は一年経っても蝶になる様子はなく、毎日休まず通過して行った。女の人も白いワンピースがボロボロになってくると翌日新しいものに変わっているくらいで、毎日毎日匍匐前進していた。
ある時、女の人の胸元で何か動いた気がして、よく見るとそれは人間のように見えた。僕は「あれが乗客だな」と思った。
幼虫や女の人を見ながら「毎日同じレールの上を進み続けるのって、きっと何も考えなくて良いから楽なんだろうな」と考える。
僕は先日、中学受験に受かった。お母さんが「将来の為に絶対イイから」と受験校の選定から塾の申し込み、校長への贈り物など全部やってくれた。
近所のおばさんは僕に話しかけてくれなくなった。お母さんが言うには「あそこの息子は受験に受からなかったからひがんでる」せいらしい。おばさんの息子であるトシヒコも僕を避けるようになったから、その可能性は高い。理由が分かっても、僕はおばさんもトシヒコのことも好きだったから、少し、寂しい。
僕は最近毎日祈っている。
「幼虫や女の人が『自分はその気になればこのレールを外れて何処へでも行けるのだ』という事実にずっと気付きませんように」
あんな巨大な幼虫や女の人がレールから飛び出して町を自由に動き回ったら、全部一瞬で壊れてしまうから。そうしたらお母さんはさぞや悲しむだろう。だから、それだけは絶対、気付いてはいけない。絶対絶対、気付きませんように。
早朝、いつもと同じ時間に線路を女の人が通過する。祈るように首を垂れて、レールの上を匍匐前進している。まだ今日も気付いていないから大丈夫。僕は大きなため息を吐き出しながら安堵する。
end
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
