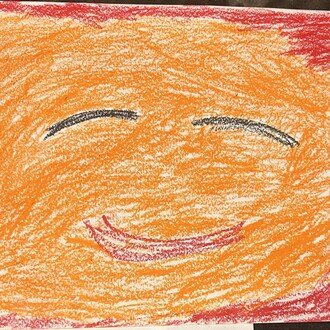私達は本当に「その儀式」にお金をかける事が幸せなのか?
「棺桶も骨壺もネットで売っている」
この本を読みながらあ、まりにも驚き検索してしまった。
・・・売っている。
普通に売っている。
本や日用品と同じ様に、商品の写真が数枚掲載されていて、仕様が書かれていて、レビューも掲載されている。
そして、想像よりもずっと安かった。
あの日、カタログで見た価格よりも遥かに安い。
続けて、市町村が運営している火葬場の「火葬料金」を調べてみた。
唖然とする金額だった。
世の中、全てがどんどん「丸見え」になっている。
葬式の意味とは何なのか?
以前この記事を書いた時に、ようこさんがコメントで教えてくれた本を調べたところ、同じ著者の本でコロナ禍以降に書かれたものがあったので読んでみた。
本で葬式スタイルの歴史を知り、私自身が過去に参列した葬儀を色々思い出してみた。
小学生だった頃、父方の祖母の葬儀が行われた。
父は地方の田舎で生まれ育ったので、祖母の葬儀は自宅で行われた。
事前の準備、当日の料理の振舞い、後片付け、香典返し等が全て手作業だったので子供ながらに「大変だな・・」と感じた。
その数年後、母方の曽祖母があった。
この時は完全に「業者にお任せ」のスタイルで、「こっちの方が良いな」と思っていた。
その後社会人となり、会社で取引関係にある方(経営者)の式に参列する機会も何度か経験した。
現職中に亡くなってしまうと、関係者が多いので式はとても盛大なものだった。
業者を利用しても、受付や関係各社への連絡等に社員が総出で参加する。
会場には「メモリアルコーナー」が設置されて、沢山の思い出の写真や歴史が飾られる。
礼状にはご家族による「故人との思い出」が綴られて、素敵な似顔絵が描かれていた。
本の内容に話を戻すと、バブル期は葬儀も派手で盛大なモノが多かったらしい。
私が参列したのはバブル期よりも遥かに後だけど、バブル期にバリバリ活躍してこられた方の葬儀だった。
そういう世代の方には「故人への想い」が葬儀の大きさという形で表現される部分があったのかもしれない。
これは「ビジネス」
私が小学生の頃に経験した様に、元々は葬式というものは家族と周辺に住む「町内の人」が手作りをする「お金のかからない儀式」だった。
香典や労力は、町内の人がお互いに助け合う為の相互扶助だった。
そこに業者という名のビジネスが参入した事で、どんどん形が変わりお金がかかるようになった。
葬儀費やお布施だけではない。
いつの頃からか「香典返し」という文化が広まり、頂いた現金に対して半額程度の品物を業者を通してお返しする事になった。
知人のお茶屋さんは「香典返しが一番大きな収入源」と話していた(笑)
女性は礼服、靴、バッグ、アクセサリー、クリーニング代と色々な経費もかかる。
更には20代の頃と40代、50代の頃では「似合う服」が変わる為、滅多に出番がない礼服を何年かに一回新調しなければいけない事もある。
これらは全てビジネスなのだ。
人の死にまつわる事を「ビジネス」なんて呼び方をするのは、人として如何なものか?と思われるかもしれない。
だけど間違いなくビジネスである。
就職活動をしている時、ブライダル企業を志望していた友人が会社説明会へ行ったら「ブライダルは減少傾向なので、近年は葬儀事業を拡大しています」と言われて興ざめしていた。
「結婚式が衰退してるから葬儀でやっていこう」
実態は、みんなそれくらいライトに考えているのだ。
私はいくつかの葬儀を経験して、自分自身は「直葬」してほしいと思うようになった。
骨壺も棺桶もAmazonに売っている(笑)
市町村が運営する火葬場の火葬料金。
私の住む町は、「一体 5千円」と書かれていた。
5千円。
あまりにも驚き、それを知ってから何人かの人にクイズを出してみた(笑)
多くの人が「5万円位?」と回答しており、答えを言ったら大爆笑していた。
見栄、世間体、義理。
そういう煩わしさが溢れる葬儀なんて要らない。
もしも私が故人の立場なら、大事な家族だけが集まり、お互いに普段着で笑ったり、泣いたりしながら見送られたい。
令和こそ「自分の」価値観
本の本題からは逸れるが、戦後間もない頃の平均寿命は40代前半と書かれていた部分が衝撃だった。
乳児の死亡、戦争による死亡などもあるので、平均寿命が短くなる事は当たり前。
だけど、もしも私がその時代の人だったら。
私は既にこの世にいないかもしれない。
そう考えると、急に緊張感を感じた。
きっとその時代の人であれば、10代後半か20代前半のうちに出産をしている。
40代ともなれば子供も成人して、孫もいるかもしれない。
学校で学び、家の仕事を手伝い、家庭を持って、家族で農業でも営む。
その日食べる野菜を収穫して、子供を育て、孫の誕生を喜んでいる間に死を迎える。
それって幸せかもしれない。
今はどんどん寿命が長くなり、「その日」の事ではなく「将来」ばかりを考えるようになった。
将来の為に勉強をして。
将来の為にお金を稼いで。
将来の為にお金を貯める。
その「将来」の最終目的地が葬式?
嫌だ。
少なくとも、私は嫌だ。
令和の今、平均寿命は倍になった。
技術の進歩で長く生きられるようになった。
でも、あらゆる場面で「40歳の壁」と叫ばれている。
それは当たり前の事なのかもしれない。
昔なら人生をクライマックスだった年齢に達したのに、この先また「同じ長さ」を生きていかなければいけない。
だからこそ、価値という名の経済活動を繰り広げなければいけない。
時代が変わり、生き方が選べるようになった。
それと同じように、時間の使い方や、お金の使い方も選べる時代がやってきた。
葬式という殆どの人が日常的には考えない分野についても、ここまで透明化されてきた。
という事は、何を選んでも良いのだ。
情報があふれる時代だからこそ。
普段考えないような細かい所にまで「自分ならどうしたいか?」を考え、家族と共有する事の大事さを改めて感じた。
<あとがき>
冠婚葬祭の全てを否定するつもりは全くありません。
むしろ私自身が、結婚式には相当なお金をかけて大々的にやりましたが10年以上たった今も「やって良かった」と思う幸せな一日でした。
葬儀も「この大変な事務作業をやる過程や、集まってくれた人によって、遺族が癒されるんだな…」と感じる事も沢山あります。
ただ、お坊さんが葬儀が終わった途端にバイクで去っていく様子を見ると、「同じ人間だよな~」と何とも言えない気分になったりするのです(笑)
それぞれの立場を守り続けるって大変ですよね。
**「昨日読んだ本」コーナー**
オンライン読書教育「ヨンデミー!」に、毎日「感想提出」をしている子供達が昨日読んだ本を紹介するコーナー。
<読み聞かせした本>
<長男>
<次男>
この作家さんが書いた「まないたにりょうりをあげないこと」も、面白いです♪
今日も有難うございました。
いいなと思ったら応援しよう!