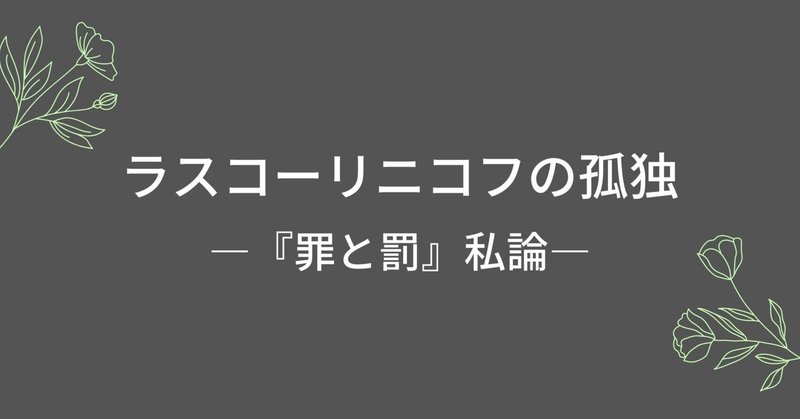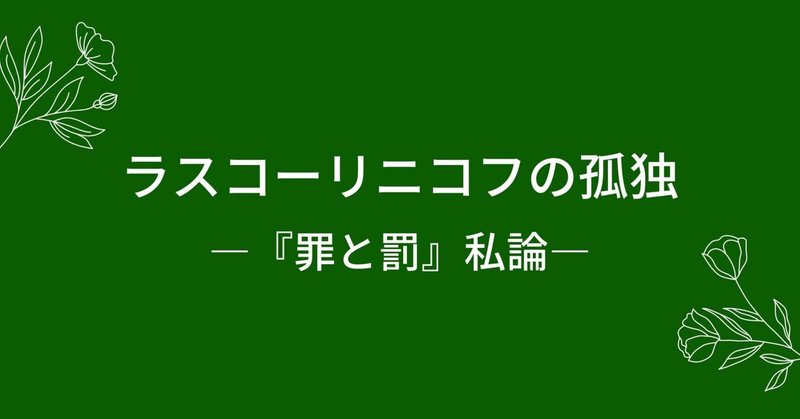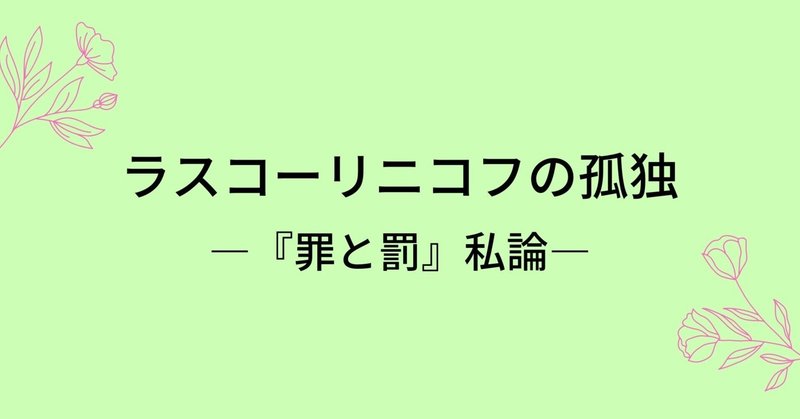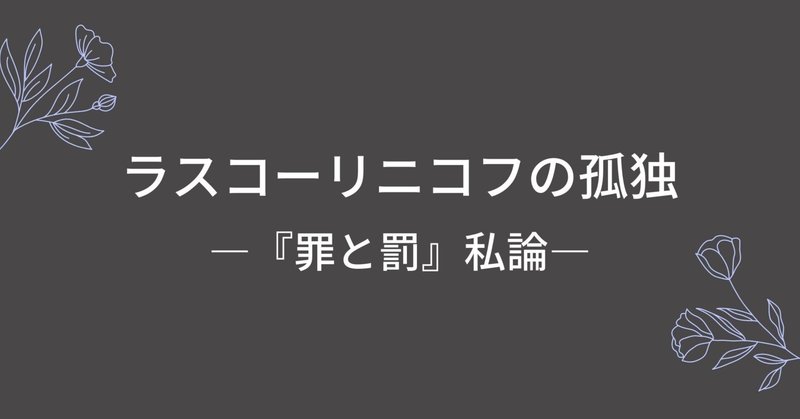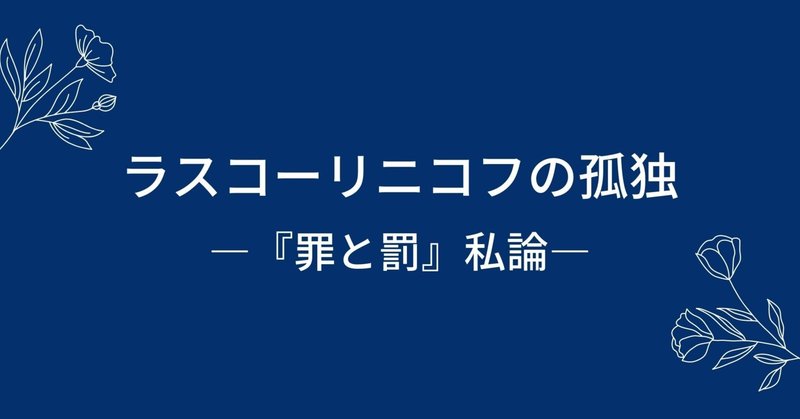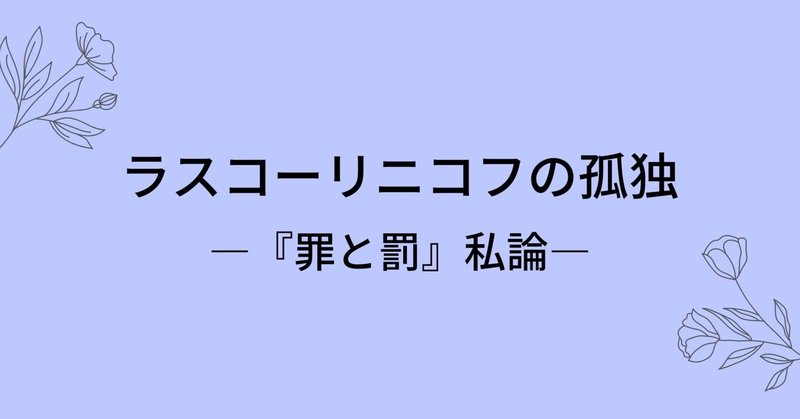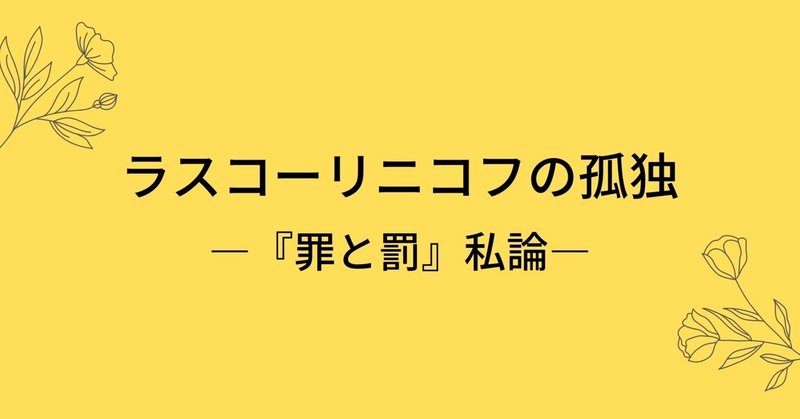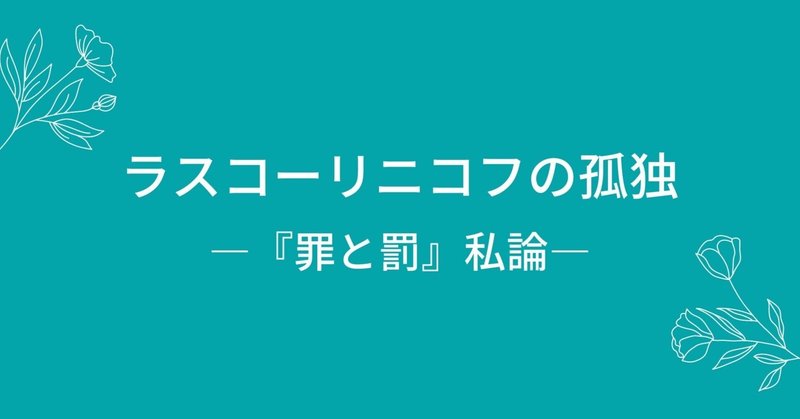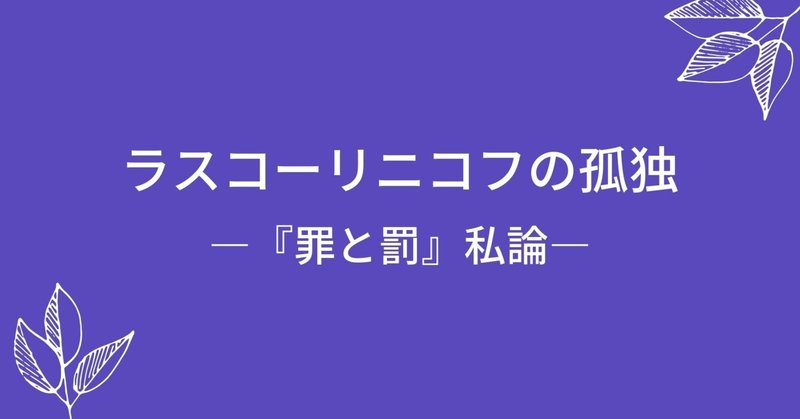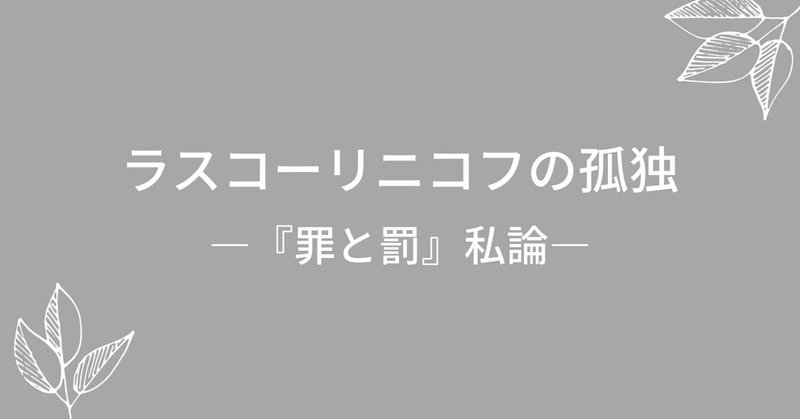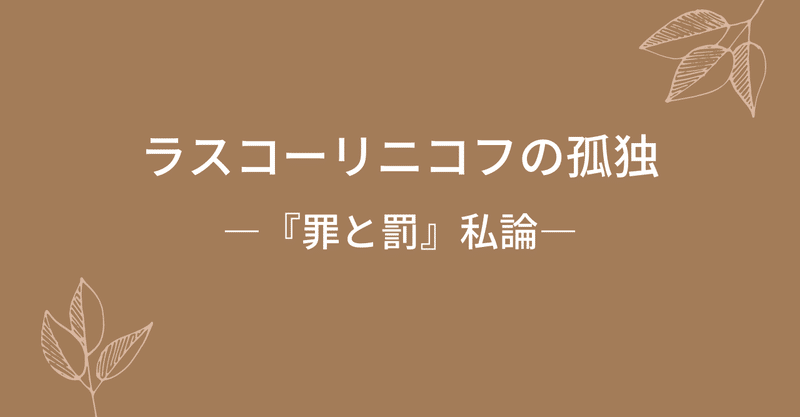記事一覧
情欲について―『カラマーゾフの兄弟』再読(2)―
『カラマーゾフの兄弟』の第三編は「好色な男たち」と題されている。
この編に関連して考えてみたいテーマは「情欲」である。
というのも、同編には、カラマーゾフ家の長男ドミートリーが三男アリョーシャを相手に非常に長い告白を行う場面があり、その告白の中で、まさに「情欲」について雄弁に語っているからだ。
ドミートリー(以下ミーチャという愛称を用いる)は、その長い告白をなぜかシラーの詩の引用から始める。そし
『カラマーゾフの兄弟』再読(1)
これが三度目か四度目か分からなくなってしまったが、久しぶりに『カラマーゾフの兄弟』を読み返している。
*
再読のきっかけの一つは、少し前に加賀乙彦の『ドストエフスキイ』を読んで驚いたことだ。
同書で加賀は、『カラマーゾフの兄弟』のイワンが容貌や容姿の特徴を欠いている、すなわち「顔形、目の色、背の高さ、いっさいが不明」であると指摘していた。
三兄弟の次男、つまり主人公たちの一人であり、小説の中で
ラスコーリニコフの孤独―『罪と罰』私論―(7)
アリョーシャの絶望と再生ドストエフスキーは『罪と罰』において「神をつうじた人間どうしの絆」という観念を暗示していた。そのような仮説への確信をさらに深めてくれる情景が『カラマーゾフの兄弟』の一場面に描かれている。
それは、カラマーゾフ家の三兄弟の末っ子、アレクセイ・カラマーゾフ、すなわちアリョーシャにとってのクライマックスと言える場面である。
修道院に暮らす若き修道僧のアリョーシャは、自らの師で