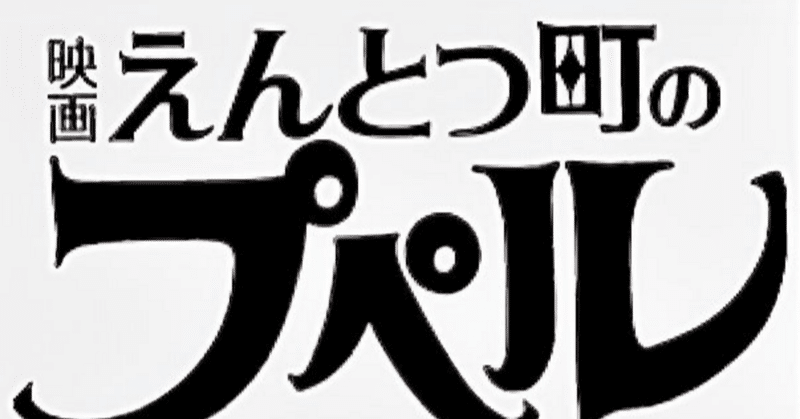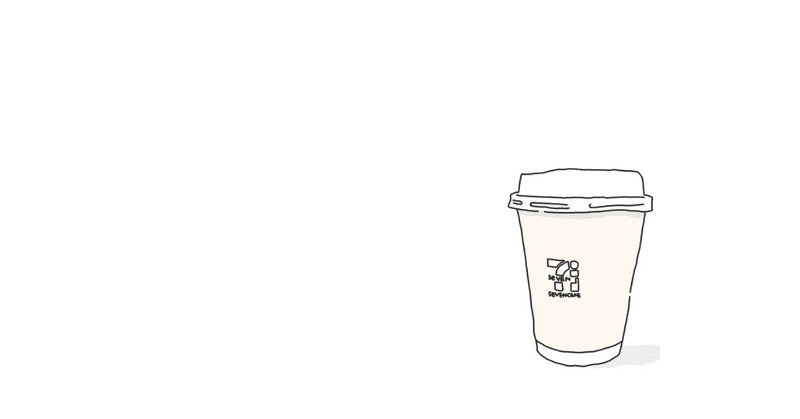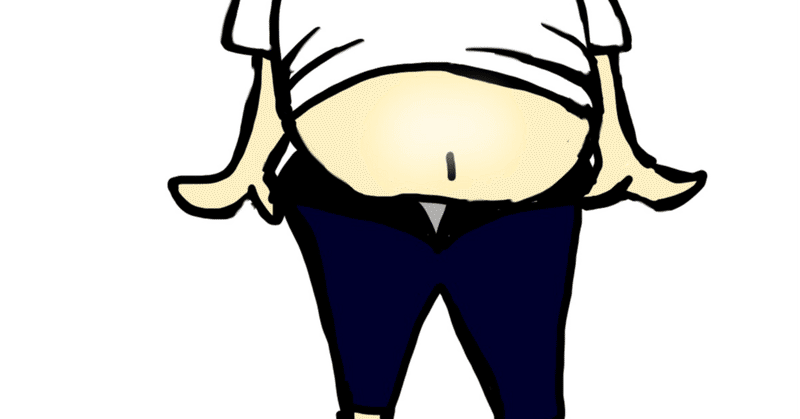- 運営しているクリエイター
2024年2月の記事一覧
写真にどっぷり嵌っている話:飽き性の一時のブームか、定番の趣味か
写真ブーム最近、写真を撮ることに嵌っています。
より正確に言えば、カメラというガジェットを利用して写真を撮る行為、そしてとったデータをPC上でLightroomで編集をすることに嵌っています。
きっかけは先月に買ったコンデジからになります。
ここ最近流行っているオールドコンデジブームから懐かしい気持ちになり購入したものです。
それまでもカメラに挑戦しては挫折してきた私ですが、再度写真ブー
飽き性の人間が、写真とカメラに3度目の正直の挑戦をしようと考えている話。
今日は少し軽めの話題を書いていこうかと思います。
ガジェット好き私はガジェット類、スマホやPC、ヘッドホンやイヤホンが好きで個人的にこだわったものを使用しています。
ところがカメラに関してはこれまでほとんど触ってきませんでした。なぜならば写真を撮る行為に対してあまり興味を持てなかったからです。
いわゆる良い写真と呼ばれるもの、特に風景写真、山や川をきれいに取る写真がそこまで好きではないからか