
【1時間で分かる】ベンチャー企業上場の教科書
はじめに
2024年4月末でライトワークス(証券コード:4267)という会社の執行役員を退職しました。
私がライトワークスに入社したのは2016年で、2001年に創業した同社の当時の売上は数億、従業員は30名強でした。そこから2022年に上場を果たすわけですが、私にとってベンチャー企業のグロース経験は2社目でした。ライトワークスの前に約10年いたクオン株式会社で学んだことを同社に持ち込んだら5年で上場が実現した、というところです。
当然ながら会社の成長は複合的な要因で成り立つものですので、これが全てではありません。でも、大きな影響はありました。よって、この2006年から2022年ごろまでの体験で得られたことを通して、ベンチャー企業のグロースをわかりやすく共有可能なものにしようと思いました。それがこのnoteの狙いです。これら2社のグロースやコンサルティングを通して様々な企業に関わった経験から、ベンチャー企業の成長にはパターンがあることが理解できました。このパターンを、できるだけ解像度高く、歴史の教科書のようにわかりやすくまとめようと思います。
始めに結論をお伝えしてしまうと、
・安定したリード獲得の仕組みができて、「いい会社」と言われる組織づくりができら、売上が上がらないはずがない
という至極当たり前の結論に至ったという話です。これを「どうやるか」がポイントだと考えています。もちろん、プロダクトやマーケット、会社のステージなど変数はたくさんあるので、これだけが正解ということではありません。でも、リード開発と組織開発に愚直に取り組めば、「ベンチャー企業の売上を上げる」というゴールに対し、このことほど多くの問題を横串に解決してくれる取り組みはないのではないかと思うのです。
本書では、「じゃあどうやって?」をできるだけわかりやすく、丁寧に解説していきたいと思います。
上記にあたって、
・新規リード獲得強化のためのマーケティング
・競合に勝つ、「強い営業」を実現するための営業・販売力強化
・組織の30人、50人の壁を突破するための人材開発と採用
・生産性の高い、新しい仕事の進め方を実現するwork platformの構築
・ステークホルダーに愛される「良い会社をつくる」ための組織開発
の大きく5つの構成要素で話を進めていきます。
どれも全く新しい内容というより、一つひとつは既に広く語られているものですが、「本気で取り組めば本当に会社が成長するんだ」という観点で参考になる部分はあるはずです。
また、本気で読めば1時間もあれば読めると思いますが、これだけの要素を詰め込んでいますので、得られる知識としては本数冊分になることをお約束します。
最後に、これらの経験を通した先に私が今何を考えていて、どんなことにチャレンジし、今どんなアクションを起こしているかをまとめます。
余談ですが、上場、IPO(新規株式公開)はどれぐらいの確率でできるものでしょうか。JPY(日本取引所グループ)によると2023年度の新規上場社数は120社としています。母数をどう考えるかは難しいですが、東京商工リサーチによると2023年の「新設法人」は15万3,405社とのことですので、例えばこれを分母とすると、ざっくりな確率としては0.078%になります。
同様に、こちらもざっくりですが、上場企業社数を4,000社、日本の企業を360万社とすると、約0.1%と、似たような数字になります。
1,000社に1社ということですから、いち社会人として企業の上場に立ち会えたことは本当に幸運なことだったと思います。特に、20代から30代の前半を過ごしたクオン株式会社での経験はベンチャー企業のグロースのパターンを理解する上でかけがえのないものだったと思っています。
一方で、昨今の人的資本経営しかり、世の中にあって注目されるのはほとんどが大企業の事例ですし、書籍として目にし、手に取るものも大企業の事例ばかりです。販売を考えればそれは当然だと思います。でも、上場までのプロセスだけでなく、1社目も2社目も、企業の成長にはそれなりの痛みがありました。特に、創業から16年経っていた会社が上場に至るような急激な成長をするとやはり大きな歪みが生まれ、その反動を受けた身としては、これはどうにかして、ベンチャー企業のグロースパターンを教科書のように世の中に表すべきだろうと思うようになりました。
あの時、改革に着手した自分の手元にあったら、という思いでこれを書きます。
よって、この本は、売上を上げたいベンチャー企業の経営者はもちろん、BtoBマーケティングに取り組んでいる方、営業に悩んでいる方、営業メンバーの育成に悩んでいる方、老舗の会社の改革を企図する役職者といった、「現状を変えよう」ともがくすべてのビジネスパーソンの方に読んで欲しいと願うものです。
特に本書では、成長に必要な「考え方」を言語化していきます。そしてそれはどんな業務・業種にも応用可能な汎用的なフレームワークと言えるものです。
本書が、企業の成長、そして自身の成長に取り組むすべてのビジネスパーソンにとって何らかの発見やモチベーションにつながるものになることを願っています。
目次
1.組織文化を変えたい。でもすぐにはできない。
ライトワークスに入社した2016年当初、前職から転職してきた私が見た風景は「個人商店の集まり」でした。品質の高いサービスのデリバーはできているけれど、横のつながりや育成文化が弱い、あるいはないと言えると思いました。
ミシガン大学のロバート・クイン、キム・キャメロンらによって開発された、組織文化の診断フレームワークである「競合価値観フレームワーク(CVF; Competing Values Framework)」によれば、当時のライトワークスは左下の「官僚文化」がピッタリハマっていました。

ライトワークス社がどんな会社かということに少し触れておくと、同社は日本のエンタープライズ企業向けに学習管理システム(LMS:Learning Management System)を提供している会社で、付帯サービスとして、人材開発に関連するBPO業務やコンサルティング、教材などを提供しています。2022年にグロース市場に上場、2023年にはクラウド型LMS市場で売上No.1となりました。
同社のwebサイトを見ていただくとお分かりの通り、名だたる企業にサービスを提供していることから、サービスの開発・運用・提供、それらを担う人材の獲得・育成など、すべてのオペレーションにおいて大変高い品質が求められる、という特徴があります。
上場して状況はある程度変わりましたが、上場前はブランドが立っていない、つまり、分かりやすく言えば「誰も知らない会社」にとってはこれはとても厳しい要求です。
2016年当時はまだ売上規模も小さく、大規模な案件も全社で把握できる数しかありませんでしたが、提供しているシステムや制作する教材の品質は高く、顧客へのサービス提供という観点ではとても安定していました。言い方を変えると、「この規模にしてはしっかりし過ぎ」と言えるレベルでプロジェクト管理や承認プロセスが組み上げられていました。
官僚文化は組織面においても特徴的な数字で表れていました。2016年当時の3年以内離職率が約70%と、突出して高かったのです。よって、平均年齢が高く、新しい人が定着しにくい風土となっていました。
蛇足ですが、組織文化と組織風土について少し触れておきます。「文化」とは、時代ごとに移り変わる「価値観」を表す言葉です。したがって「組織文化」とは組織内で共有されている理念やルールのことを言い、「無意識下にある価値観・行動パターン」と考えます。その組織文化から生まれるもの(顕在化するもの)が組織風土です。
「風土」とは、そもそもその土地の気候や地質、地勢などを表す言葉です。したがって、「組織風土」とは、その組織に根付いている性格や精神性のことを良い、「知覚できる組織の特性」と言えます。すでに根強く組織に紐づいている「性格・気質」のようなものなので、簡単に変えることが難しいものと言えます。
新しい人が定着しにくくなっていた最大の理由は、「人を育てる」という文化がなかったこと、それが風土として定着してしまっていたことだと感じました。後述しますが、「人が人を育てる」という行為は人間の深い欲求、例えば生存欲求といったレベルの欲求を脅かすものです。部下を育てた結果、自分が追い出されるリスクがあるからです。
これが組織の成長を阻害します。よって、様々な企業が「人を育てる」文化・風土の定着を図っているわけです。その優れた教育システムで世界的に知られることになったGEのクロトンビル(コロナ以降、コンテンツを伝達する方法が大きく増えたという理由から売却されたそうですが)に呼ばれる幹部候補は「人を育てる」力が問われていた、という観点で、まさにこれを象徴していると思います。
「人を育てるんだ」と誰かが声高に叫び、制度まで落とし込まないと定着しないものだと考えます。入社当初感じた最大の問題はここでした。
エンタープライズ向けのサービスゆえ、安定した品質を提供する必要があり、管理重視の官僚文化はそれに合っている側面がありました。一方で、ベンチャー企業においては人を育てなければ、中長期的な成長は見込めません。中途採用でハイスペックな層をとって組み立てていっても、そういった人を惹きつけ、まとめる理念や文化がないと瓦解してしまうパターンがあります。組織の50人の壁として一般的に知られているパターンです。
実際同社においても、組織は30人〜50人の間をずっと行ったり来たりしていたそうです。これを変えないと、この会社は成長しないと思いました。
しかし、前述の通り、組織風土を変えるというのは尋常なことではありません。昨日まで「顧客を大事にしよう」と言っていたいたのに、急に今日から「何件アポとったんだ?」と言われたらどうでしょうか。市役所で突然「上場するぞ」という号令が走るぐらいの変化です。そんなことは絶対ないのですが。
クオン株式会社での経験から、間違いなく組織風土は変えたほうが良い、そのために組織文化を変えなければ成長は見込めないと感じていた当時、では何から着手したのか。
上記を含め、当時私が組織を見渡して特に課題だと感じていたのは以下4点です。
・組織文化:官僚文化によるフィックストマインドセット
・販売力:受注に再現性がなく、商談が統合的に管理されていない
・リード:アウトバウンドコールと株主からの紹介に依存する
・育成:育成にコミットする文化がない、個人の価値観に依存している
他にも、30人の組織ですから、当然ながら兼務が多く、例えば「専任の採用担当がいない」、「マーケティング組織がない」といった状況でしたので、これらも解決しなければならない課題でした。
これらも含めて何から着手していったか。読者の皆様ならどこから着手していくでしょうか?
例えば、年次で130%成長を目標とするとしたら当然ながら「全部クリティカル」となります。よって可能な限り横串的に問題を解決できるものは何かと考えます。
私は組織文化の変革がそれに該当すると思っていました。会社の成長には変化が必要で、当然ながら変化には痛みが伴い、その痛みを受け入れ、分かち合うグロースマインドセットが関係者に必要だからです。
加えて、入社当時使えるリソースは「自分」しかありませんでした。代打、「おれ」みたいな状況です。チームメンバー、「おれ」です。自分しかいません。
創業から16年経った30名のベンチャー企業で、叩き上げではない落下傘入社だった私はどこの部署にも所属しておらず、名刺に一言「特命担当」と書かれていました。某深夜番組の某係長のようでした。違うのは夜になっても特命担当のままだったことぐらいです。
こんな条件で、
・組織文化を変える
・販売力を強化する
・生産性を上げる
・リード獲得を安定化する
・育成を強化する
に対して、以下の順番で取り組んでいきました。
01. リード獲得を安定化する
02. 組織文化を変える
03. 生産性を上げる
04. 育成を強化する(マネージャー育成)
05. 販売力を強化する
まずはリード獲得から着手しました。
問い合わせが増えれば、「この会社は成長するかもしれない」というポジティブな機運が生まれるはずです。何かを変える時、お金を生む予感は大事です。脳の深いところで「そっちが正しい」というムードが生まれます。この機運を利用してドミノ倒しで組織を変えていこうと、思ったわけです。
ただ、この時01と02をほぼ同時に進めたため、実際始めてみて地獄を見ることになりました。
2.BtoBにおけるリード獲得って何が正解なの?
前述の通り、ベンチャー企業2社のグロースを経験して達した結論、
・安定したリード獲得の仕組みができて、「いい会社」と言われる組織づくりができら、売上が上がらないはずがない
について、安定したリード獲得経路をどう構築するかに入っていきたいと思います。
当たり前ですがどの会社でもリードを安定して獲得する経路の構築は必須です。それも「質の高いリードを」です。分かっていても難しいのがリード獲得です。
もちろん、サービスや会社の規模によって解は異なるので、ここでは考え方とエンタープライズリードの獲得における1つの最適解を書いていきます。
まず、当時のリード獲得経路はパートナー紹介とアウトバウンドコールがメインでした。前提として、ターゲットがエンタープライズ企業でしたので、前者はいつ来るかわからず、かつ数もそんなに来ません。後者は調べてみると信じられないほど低い受注率になっていました。
無形商材であること、ターゲットが大企業でも教育はそもそもnice to haveであること、提案金額が高いことなどから、アウトバウンドコールでは受注率が低いのは避けようがなかったと思います。
よって、向こうから問い合わせをしてきてくれる、インバウンドの見込み客、いわゆる質の高いリードとどう出会えるかを考えなければなりませんでした。
インバウンドは基本的にwebを中心に考えます。それを前提とした場合、例えばみなさんが、「とにかくwebサイト経由のリードを増やしてくれ」と言われたら何をするでしょうか。
ひとまず思い浮かぶのはリスティングやSNSといった媒体を通じた広告だと思います。実際多くの企業が利用しています。
リスティングもfacebook広告も、何なら決裁者向けに良いとされるタクシー広告も是非やりたかったのですが、エンタープライズの決裁者のリードを広告で取ってこようとすると、1リードあたりの単価は目が落ちるぐらいのものになります。しかも、検討段階としてはインバウンドとはいえ、まだ浅い段階の可能性も高いです。
そこで、ある程度の初期費用はかかるものの中長期的に大きくリターンする可能性があるコンテンツマーケティングに取り掛かることにしました。
小さなベンチャー企業においては、何か新しいことを始める時や何かを売りたい、動かしたいと思った時、まず「無料でやれることはないか」を考えます。これはベンチャー企業のグロースにおいてとても重要な考え方だと思っています。(ベンチャー企業に限らず、潤沢なリソースがあっても同じように考えた方が良いとも思っていますが)
当たり前に聞こえるかもしれないですが、いざ自分の手元となると案外やっていないものです。一方で、割り切ってやってみると意外とできることは多いです。これは私のクオン株式会社時代の経験から来るものです。
現状を評価してみると、2016年当時、人材開発をターゲットにしたコンテンツマーケティングサイトは見当たらず、自社のwebサイトも流入がほとんどない状態でした。一方で、少ないランディングでもwebサイト経由でそれなりの受注があることが確認できたので、可能性はゼロではないと思いました。
何か施策を検討する時、当然ながら他社がやっていると「うわ、やられてる!」となるのですが、やっていなかったらいなかったで、「前例がないことにリソースを使う重圧・・」になります。つまり、「成功しなかったらどうしよう」という不安が襲ってくるわけです。
それでも、ターゲットがエンタープライズであること、定常的に広告に予算を突っ込める状況ではなかったこと、自分なりにどうすれば勝てそうかという仮説が持てたこと(後述します)などから、コンテンツマーケティングに取り組むことに決めました。
コンテンツマーケティングはタダではないですが、ほとんどの部分を社内リソース(=おれ)で賄えます。「おれ」と書きましたが、実際は始まってみたら面白がってくれる人が何人か集まり、業務の合間に手を貸してくれることになりました。
そんな状況で、コンテンツマーケティングとしてサイトを立ち上げ、何本か記事を入れてどうにかスタートしてみたところ、最初の3ヶ月は「完璧な、凪(なぎ)」でした。無風。扇風機のない真夏より無風でした。
なかなかに肝を冷やしましたが、それでも自分が信じる品質で記事を入れ続けたところ3ヶ月後ぐらいから徐々にPVが上がり始め、半年後に待望のeBookがリリースできて以降、急激に問い合わせが増えるようになり、これまでの延長では考えられなかった数の、質の高いリードが獲得できる状態になりました。「質が高い」というのは、受注率が高いということです。アウトバウンドに比較すると圧倒的に高い受注率になりました。そうなると、リードがくれば当然受注も比例して上がっていきます。
リードが安定して入ってくるようになり、ついにお金が生まれる予感が生まれたわけです。
ではなぜ、うまくいったのか。
答えの一つにEditorial Policyが上げられると思います。このメディアをどんなメディアにするかをまとめたものです。
要素として、
・実施背景
・ターゲット(第一優先・第二優先)
・ターゲットプロファイル
・ターゲットエモーション(一般論・仮説ベース)
・ターゲットが所属する部門特性に関する仮説
・私たちが提供できる価値
・本メディアのあらまし(ミッション・ビジョン・コピー・コンセプト)
・公開するコンテンツのあらまし(ユニークネス)
・最終的な目標とプロセス目標
・本メディアのユニークセリングポイント
・作成する記事の本数と構成、テーマ
などが書かれているものです。これを丁寧に作り込みました。
特に、このメディアの「ユニークセリングポイント」として「品質に集中」を掲げました。「このメディアにたどり着いた人が、何らかの便益を得られる、あるいは課題を解決して帰ってくれるような記事を提供することに全力で取り組む」、ということです。それが私たちにとっての結果、成果につながるはず、と。
よって実際投入する記事を書く前に作成するコンテンツプランニングシートについても、高い品質で記事が書かれる工夫を徹底して実施しました。
結果、当時ブログの記事は2,000~3,000文字が多く、ライティング代行会社でもこの文字数での見積もりが多かったのですが、同ブログの平均文字数は約8,000字に達していました。
当時、いろんな人から「こんな長い記事誰が読むの?」と何度も聞かれました。
でも、品質が高い(良い記事)と判断され、かつその記事が長いと「今は長くて読めないからブックマークしておこう」という行動を取ってくれます。あるいは、「ひとまずeBookをダウンロードしておこう」とか、「こんなに頑張って書いてくれた会社なら信頼できるだろう」という返報性の原理が働いてやはりブックマークやダウンロード、問い合わせといった行動を起こしてくれるわけです。
ブログは最終的に多くの人が関わり、たくさんのコンテンツを抱え、インバウンドリード獲得経路として十分な役割を果たしていくわけですが、関係者が増えるほど機能したのがEditorial Policyだったと私自身は考えています。
「なぜこのブログを運営するのか」、「誰に対して、なぜこの品質で記事を提供するのか」を、関係者が全員説明できる状態になっていたからです。つまり、風土として定着したのです。
3.組織文化に手をいれる
前述の「この会社は成長するかもしれない」というポジティブな機運も生まれ、いよいよ本丸だと思っていた組織文化の改革に着手します。着手しますと言いましたが、実際は「ほぼ平行」でした。この時、コンテンツマーケティングの立ち上げと平行してwebサイトのリニューアルとSFAツールの導入の3つを同時に進行してしまっており、それなりの地獄を見ていました。なぜできると思ったのか、見立てが甘かったに尽きるのですが、やれると思ってしまったんです。実際やれたんですが。
というわけで、いよいよ3年以内離職率70%の組織文化を変えにいきます。
どうやったか。
先ほどの競合価値観フレームワークを用いて、「偏りがあると考えられる文化に対し、理念を定め、その理念に必要な組織文化を取り込んでいく」でした。

私は組織文化について、どこか一つの文化に偏るのではなく、現在の文化に対し、会社の状況に合わせてその他の文化の特性を取り込んでいくことでグロースがうまくいくのではと考えています。具体的に調査をしたわけではないので感覚的な話ですが、日本の企業は大きくなってくると左下に寄りがちなのではないかと思っています。それを大企業病というのだろうと。
実際、大企業病とは、大企業に特有の組織的な問題や非効率性を指す言葉とされます。 具体的には、前例主義(その事柄に適した処理を考えるのではなく、過去の似たような事例にならって処理すること)、官僚主義(新しい事柄を好まず、古くからの慣習を尊重する集団的な様式や意識のこと)、過度な合意形成・階層構造、意思決定の遅さ(意思決定に多くの承認が必要で、迅速な対応が求められる市場環境の変化に適応できない)、「やった者負け」と言われるリスク回避の傾向、イノベーションの欠如などが挙げられます。
よって、この官僚文化からの脱却、あるいは他の文化の要素を取り込む改革は、停滞している企業にとってとても重要なソリューションなのではないかと考えています。規模が大きくなるほど簡単ではないと思いますが、やれないことはないのではないかと考えます。JALの再建はその最たるものだったのではないかと感じます。
ベンチャー企業のグロースにおいて、私自身は4つをそれぞれバランスさせて発達させていくことで安定した成長がデザインできるのではないかと思っています。そんなことができるのかわからないですが、今後実験してみたいと思っていることの一つです。
例えば、組織の30人の壁は「組織化」が課題になると言われます。これまで海賊船のようにやってきたチームに、管理スキームを導入して統制や安定性といった要素を取り入れていくフェーズがきます。それが強くなりすぎると、今度は変化を起こしにくくなるので、バランスが大事、ということになります。
前述の通り、当時のライトワークスは左下の管理重視型が強く出ていたので、左上の「チームや育成に重きをおく家族文化」、右上の「成長や変化を期するイノベーション文化」、右下の「競争重視のマーケット文化」の要素をそれぞれ取り入れ、バランスを取る必要があると考えていました。
特に、前述の通り「エンタープライズ向けで全てのオペレーションに高い品質が求められる(要求レベルが高い)こと」、そして「そもそも人材開発の領域にいる(サービスとしてそれを提供する)会社であること」から、「育成に重きを置く」、「チームで勝つ」を標榜できる左上の「家族文化」を取り込むところを最も重視しました。
そうして心理的安全性を高め、成長や変革を期する右上の創造性を重視する「イノベーション文化」を次の優先順位とし、徐々に右下の競争重視であるマーケット文を取り込んでいこうと考えました。

こちらもあくまで想像ですが、日本にSFAツールを広め、今では当たり前となったTHE MODELを定着させたセールスフォース社は、外資系企業であり、成果報酬型の評価制度となっていますので、マーケット文化が強い右下が主軸の会社といえます。その状況だととかく個人商店になりがちですので、積極的にハワイ語の「オハナ=家族」という言葉を使って、家族文化を取り入れる活動をしていると考えられます。
他にも、従業員30名のベンチャーで、共同創業の経営陣が「売上は伸ばすが、急拡大するのではなく、自分たちらしくいられるということを優先したい」という思いで経営をしている会社があります。この会社では、社員旅行やチームイベントなど左上の家族文化を徹底してきた結果、離職率の極めて低い、ワンチームと言える会社ができていました。一方で、組織が拡大し、30名超えた段階で初めて「急に人が辞める」といったことが起こり、マネジャーの育成の必要性を強く感じるようになりました。
マネジャー育成は組織化そのものであり、同じ品質でマネジャーがマネジメントをできるようにするといった、左下の「規律・管理」的な要素を取り入れていく必要があるフェーズに差し掛かっている、ということになります。
さて、話を組織改革の方に戻します。
左下の官僚文化に対して、優先順位をつけてそれぞれの文化を取り入れていく改革を進めていかなければなりません。
前述の通り、優先順位としては、
1.左上の家族文化
2.右上のイノベーション文化
3.右下のマーケット文化
としました。「成長する=変化を受け入れる」とするなら、これまでやってこなかったような新しいチャレンジをしていくことになりますので、その大変さを支える信頼関係や「失敗しても大丈夫」という心理が働くような心理的安全性、社員・組織に共感が流通している状態が必要になるので、特に左上の家族文化は意識的に取り組んで行かなければならないと考えていました。
では、どうやるか。
ここまでで何となくお分かりかと思いますが、理念を刷新しました。
パーパス経営やCREDO(ラテン語で「志」、「約束」、「信条」といった意味を持つ言葉で、企業全体の従業員が心掛けるべき信条や行動指針を明文化したもの。ジョンソン・エンド・ジョンソン社の「我が信条」が有名)など、いろいろなフォーマットがありますが、私は経営理念を「MISSION / VISION / VALUE」 の3点で整理する形が良いと考えていました。
MISSIONとVISIONが連動し、それらを実現するためにVALUE(行動指針)を明示する。
そのVALUEの先に、より解像度の高い行動パターンを言語化するCompetencyをこれに紐づける形を想定していたためです。
さらに、Competencyを昇格制度と紐づけることで、MISSIONから一気通貫でそれを体現する行動を促すことができる、つまり組織の隅々まで理念を浸透させられ、社としてそれを体現する人でそのかたちを成すところまで持っていけると考えていました。
MISSION / VISION / VALUE について、それぞれの大枠の定義は以下の通りです。

上記に対して、それぞれ以下をアウトプットしていきました。

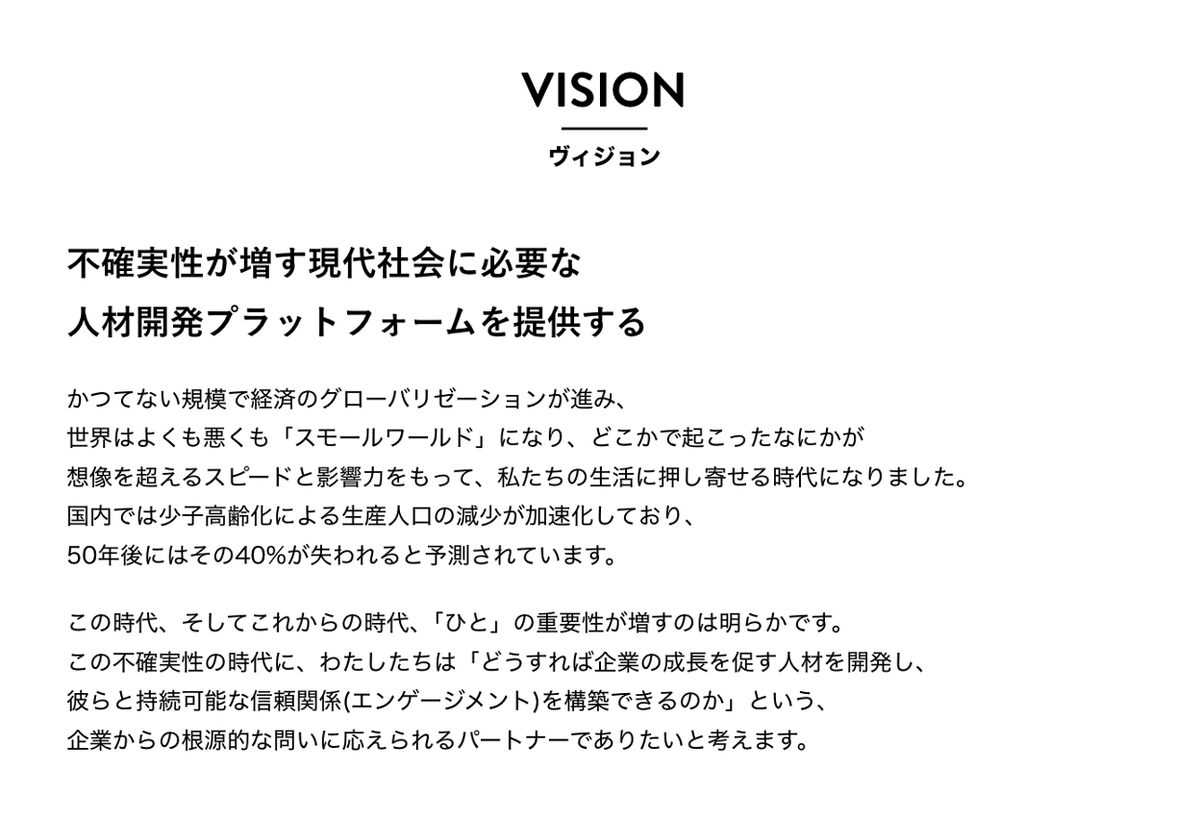

参照:https://www.lightworks.co.jp/company/vision
VALUEを見ていただければなんとなくおわかりいただけると思いますが、Passionは右下のマーケット文化を、Respectは左上の家族文化を、Creativityはイノベーション文化を意識しています。
余談ですが、この中で最も時間がかかったのはVALUEで、この3つを書くのに15時間かかりました。競合価値観フレームワークの残りの要素をインストールすることを意識しつつ、言葉にした時に、すでに世の中にあるものと重なりすぎないよう、調査をしつつ整理していく必要があったからです。更に、その後の昇格制度との連携やスキルマップとの連携もそれなりに視野に入れておく必要があり、意外と沼るのがこのVALUEです。今は何社か携わらせていただいてパターン化が進んでもう少し早く書けるようになりましたが、それでもこのVALUEが一番時間がかかります。
これも余談ですが、採用面接でよく候補者の方から「なぜこの順番か」と聞かれるのですが、「なんとなくこうした」が正直なところです。なんとなく、「熱量」から持ってきて、「チームに対する関心」、「未来に対するあり方」という順番にするとおさまりが良いのではないか、という感覚でした。
話を本論に戻します。この理念の刷新ですが、ご案内の通り経営に「理念を刷新しましょう」と安直に持っていくと、当然ながら「なぜ?」や「それをやった結果どんなインパクトが出るの?」といった展開になります。もちろんある程度説明可能ではありますが、元々の文化を変える目論みがあるところを説明するのはそれなりに困難です。合わせて、「インパクト」みたいな話になると、事態はかなりややこしくなってしまいます。経営者としては現案になんらかしら関わっていることが多いので、違うアプローチ(言い方・伝え方)で、「ぜひやって」となるようなのであれば、それは模索するべきと考えました。
ではどうしたかというと、webサイトのリニューアルを提案しました。当時のサイトがどちらかというと「モノ売り」な印象を与えるものだった一方、プロダクトやサービスはエンプラ向けに勝負できる感覚が確かにあったので、ありていに言えば「エンプラに行けば儲かるかもしれない。であればエンプラ向けにリニューアルしましょう」という提案をし、「リニューアルするのであればブランディングの観点で理念も刷新した方が良い」、という順番で提案しました。結果、すんなり受け入れてもらえました。今思えば、この辺はストレートに「変えたい」でも通ったのかもしれません。でも、何かの提案をする際は「段取り八分仕事二分」が基本だとクオン社で叩き込まれたので、慎重を期した、というところでした。
という状況から、前述の『コンテンツマーケティングの立ち上げと平行してwebサイトのリニューアルとSFAツールの導入の3つを同時に進行してしまっており』(というデスロード)が起きていたわけです。
ちなみにSFAツールの導入は「コンテンツマーケティングの導入→問い合わせの増加」という流れが生まれる(と信じる)なら、早めにSFAツールを導入し、見込み顧客から受注・売上管理、顧客管理までを統合的にコントロールできる状態を構築しておきたいと考え、このwebサイトのリニューアルとほぼ並行して着手となっていました。特に、エンプラ向けのサービスゆえ武器が揃ったら受注単価はまだまだ伸ばせるだろうと言う感覚があり、であるなら、単価が高く、セールスサイクルが長い商材においては受注率、特にフェーズごとの移行率や失注分析は必須と考えていたからです。
ここでは触れませんが、SFAの導入は当時の状況(元のデータの持ち方)が原因で、「取り返しがつかないことになるかもしれない」という緊張感が生まれる状況が発生し、吐くほど大変でした。無事に移管できたのは、関わってくれた関係者の努力と、その上に幸運が重なったおかげでした。今振り返っても関係者に感謝です。
「心理的安全性が高く、チャレンジがしやすい環境を構築する」という話はそこら中にありますし、理念を刷新してそれを同社でも実現しようと思っていながら、実際に自分が言い出しっぺで何かをやって、それが「失敗するかもしれない」という状況に陥ったというのはその後に活かせる貴重な体験でした。「失敗は成功の元」や、「失敗は成功する前に止めること」的な失敗にまつわる格言は多いですが、実際に目の当たりにするとそんな格言めいたものは吹っ飛びました。よって、その後の組織文化の形成において、「失敗して大丈夫」というメッセージは実感を持って伝えられましたし、マネジャーを通して徹底してメンバーレイヤーに伝えてもらっていました。
具体的には、例えば日報で「失敗体験」を発表してくれる人がいたら、マネジャー陣は必ず「いいね!」ボタンや積極的に返信を入れる、といった風土にしていました。
一方で、「気軽に失敗してもらう」みたいな、覚悟や思いのない失敗は本当にじゃんじゃんしてもらったら困ると言う本音もあるわけですので、「失敗はしても怒られないし、むしろチャレンジを歓迎される」と言う理解を浸透させながら、同時に「段取り八分仕事二分」を徹底して伝えていくという相反するメッセージを拮抗させることも重要だと考えています。
ここまでがMVVの刷新になりますが、この時の時間軸とは別に、その後ライトワークスから生み出すプロダクトやサービスの「コンセプト」となる言葉をつくりました。MVVの制作と浸透の3ステップ目、Phase3のアウトプットに該当するものです。それが以下です。


「私たちは、日本でいちばん学ぶことを楽しんでいる会社です。」って、良いですよね。そんな会社がつくる人材開発システムやサービス、コンサルティングなら買っても良いって、私なら思います。つまり、MVVと合わせて、ライトワークスの中長期的な競争優位の源泉になればと考えて、これをつくりました。
後日談ですが、これらの理念やサービスコンセプトを掲げてから、中途採用においても、後に立ち上げる新卒採用においても、面接で「理念がすごく素敵だと思いました」と、言っていただけるようになりました。ほぼすべての面談で、と言えるほどでした。
応募者側からすると、「言いやすい、アピールにつながる」というところもあって言ってくださっているというところもあったと思いますが、リニューアルする前には言われなかったことですので、採用おいても大きなインパクトがあったと言って良いのだと思います。
さて、「理念の刷新=MVVの刷新」について、ここまででなんとなく目的を達成したような印象を受けると思いますが、本番はここからです。「浸透」です。つくっても浸透しなければ意味がないからです。
MVVを刷新したり、創業初期にMVVをつくっても、それがうまく運用に乗っていない、会社としての文化や風土の形成にまで繋げられていないという悩みを本当によく聞きます。
中には、「そもそもそういうことはできない」と諦めているケース、「そんなものは必要ない、難しいことをやらせる必要はない」と言ったサービスも存在してもいます。
でも、時を超えたエクセレントカンパニーに、経営理念やMVVがない企業はないのではないでしょうか。「時」や「エクセレント」は定義が曖昧ですが、トヨタ、コカコーラ、P&Gなどなど、認知度の高いメガブランドで理念がないというパターンは想像しにくいです。
「ベンチャー企業で、特に営業に特化した組織」といった特殊なケースはあると思いますが、あるに越したことはないというのは間違いないと考えます。
逆に、フレームワークに従って丁寧につくりこみ、それを運用するマネジャーが育てられれば大きなインパクトを出してくれます。
では、どうすれば良いのか。以下の通り、理念やMVVを企業の競争優位の源泉にしていくには4つのPhaseが必要だと考えています。

MVVを作るのはPhase2までで、ここから先にPhase3,4があると考えています。
Phase3として、
・VALUEとコンピテンシーの連動
・コンピテンシーと評価制度の連動
・それらを運用するマネジャーの育成(研修・伴走)
を行います。
2017年当時、ここまでやっているベンチャー企業は少なくとも私が知る限りありませんでした。(無知なだけかもしれないですが)以下、具体的に何をやったか解説していきます。
VALUEとコンピテンシーの連動について、まずライトワークスのVALUEでは「PASSION / RESPECT / CREATIVITY」の3つを掲げています。この3つを、さらに3つのCompetencyに分解して定義しました。
例えば、PASSIONであれば、
1.情熱を持って行動する
2.高い志を持つ
3.自ら動く
といったものに分解します。(これらは実際とは異なるサンプルです)
これらに対し、具体的にどんな行動をする人であって欲しいか、どんな行動をするとライトワークスにおいて成果を出している、出しやすい人になれるかを明示します。
例えば、「情熱を持って行動する」であれば
・プロとしての自覚を持ち、関わる業務やチームと真摯に向き合う
・心身ともにベストな状態を常に意識する
といった感じです。(こちらもサンプルです)
上記について、3つの段階を設け、徐々に難易度が上がるものにします。
そうすると、3つのVALUEに対し、行動ベースのありようが9つ提示され、それらに対してそれぞれ1~2個のCompetencyが明示されるので、30~50程度がCompetencyとして明らかにされます。
細かい設計については省きますが、これらの達成度合いが役職の昇格要件に設定されるため、VALUEに紐づいたより多くのCompetencyがしっかり体現できている人が昇格していくスキームになります。
これにより、組織全体にVALUEが浸透している状態になり、それが文化として定着し、組織の風土として現れる、という「理念の浸透ができている」状態になります。
これがVALUEとCompetencyの連動です。MISSION・VISIONを実現するために、社員に求める行動規範、その行動規範に基づいたCompetencyを明らかにし、そのCompetencyの発揮度合いを昇格要件にする、というコンビネーションです。
上記が制度として構築できたら、それを運用できるマネジャーの育成に進みます。こちらは次の「マネジャー育成」の章で具体的に説明しますので、ここでは割愛します。
ここまできたら最後はPhase4の「ブランディングとシンボリックアクションのデザイン」です。分かりやすく言うと対外向けに「会社としてMVVを体現しているよ」という発信になります。対外向けと書きましたが、結果的にインターナルブランディングとしても機能します。
ライトワークスでは、webサイトのリニューアル、販促物の刷新、製品・サービスコンセプトの作成、CSR/CSV活動をそれぞれやっていきました。
販促物についても、会社パンフレットから提案書のフォーマット、名刺、会社封筒、ダウンロード用のeBookから外部の関係者にお送りする感謝状まで、全てのアウトプットを刷新していきました。
余談ですが、デザイン的な判断について、基本理念や製品・サービスコンセプトが整ったのでディレクションが格段にやりやすくなりました。デザイン的な観点での「良い・悪い」の判断がしやすくなるからです。
製品・サービスコンセプトは前述の「fun to learn」がそれにあたります。
そしてCSR/CSV(Corporate Social Responsibility / Creating Shared Value)活動も具現化していきました。それがLIGHTBOATという、日本で働く外国人材を支援するプロジェクトです。

ライトワークスの新しいMISSIONに据えた「ミライのはたらくを、明るくする」は、日本人だけではなく、「日本に働きにきてくれている外国人材の方々にも同様に、この思いを向けられたら」という願いからスタートしています。
このプロジェクトを始めるきっかけになったのは、中国で立ち上げたライトワークスの子会社の「来宜信息科技(上海)有限公司」という会社がアジアに販路を拡大している中で、ベトナムに訪問した際、彼の地で起業した日本人社長から「齊藤さん、ベトナムで日本人の国民感情が(一部)悪化しているのご存じですか?」と言われたのがきっかけでした。
当時、技能実習生はベトナムからの受け入れが最も多く、数が多ければやはりトラブルも起きており、中には死亡事故や自ら命を絶つケースなどが出ていて、他にも色々と重なった上でにはなりますが、そういう事案が国民感情の悪化に影響があった可能性はあるのだと思います。大学時代にバックパッカーとしてアジアの国々を周り、各国で様々な交流の機会を持った身としても、個人的な価値観としても、この状況に対して「何かできることはないか」と考えるようになりました。
その結果として生まれたのが、LIGHTBOATという外国人材の支援プロジェクトでした。これは、外国人材や、雇用主体である企業の関係者に、「良い関係を構築するために必要な知識を体系的にまとめたコンテンツ群」を提供するプロジェクトで、外国人材個人には無償で、外国人材を活用する企業には有償で提供するサービスとして展開しました。
本論からズレるので細かいところは省きますが、コンセプトの良さから発足当初から本当にたくさんの方々に支持や支援をいただき、メディアに取り上げていただいたり(2022年12月31日「朝日新聞デジタル」https://www.asahi.com/articles/ASQDX43L0QCMUTIL01J.html)、このプロジェクトが起点で大型の受注につながったり、採用面接でもコンセプトやこのプロジェクトのミライについて頻繁に質問していただくなど、シンボリックアクションとして十分に機能していたと思います。
「持続可能性を最大化する」と言う観点からはできていないところも多々ありましたが、ライトワークスにとってMVV文脈に合致する良いプロジェクトになっていたと思います。

参照:https://lightboat.lightworks.co.jp/
以上が「組織文化に手をいれる」の具体でした。
後述しますが、こういった改革を進めれば当然ながらそれなりのハレーションが起きます。ご案内の通りですが、これは同社に限らず、どんな組織においても改革を進めれば必ず起きるものです。こういうと「なぜやったのか」を問われます。答えはシンプルで、私には「どうせ働くなら楽しく働きたい」という価値観があります。強く願うことなので、信念と言っても良いかもしれません。
人生100年時代、働く時間はどんどん伸びています。人は人生の半分以上を働いていると言っても過言ではない時代です。そんな時代にあって、人生を終えるタイミングに、人生を振り返る機会があった時、働く時間が楽しくなくて、人生が楽しかったと言えるでしょうか。私は、仕事も含めて人生楽しかったと思いたい。考えてみれば、仕事をしている時間というのは、寝ている時間を抜いたら「家族より一緒にいる人たちとの時間」となります。すごくないですか。家族より一緒にいるんです。
であるなら、良いチームを作りたい。気の許せる仲間、信頼できる仲間を増やし、困難に向き合い、克服し、達成して喜び合えるような働き方をしたい。こう言った思いが根底にあり、それを阻むものに挑みたい、という思いや行動につながるのだと思っています。
「良き人、良き師に巡り会えた」と言ってもらえるような「良い会社」をつくることが、私のライフワークなのだと思います。こう思っている人はたくさんいるのかもしれません。でも、行動に移すまでは中々行かないのではないかと思います。
私たちは「言葉」によってセカイを認知しています。であるなら、人も仕事も「言葉」でできているとも言えます。 そして、良い組織、成長する組織には、きっと「良い言葉」が流れているはずです。
であるなら、「組織に流通する言葉を変える」ことで、組織は変えられるのではないか。そのための手段として「MVVの刷新と浸透、マネジャーの育成」が最も重要なKSFなのではないか。そう考えていました。
皆さんにもぜひ、本章を参考に、「良い言葉」が流通する企業づくりに取り組んでいただけたらと願います。
4.新しい仕事の進め方を実現するwork platformを構築する
これもクオン社時代の体験を再構築したものでしたが、簡単に言うと、「業務を分解して、業務委託さんに外注していくことが可能な状態にする」です。クオン社とライトワークス社での取り組みを経て、更にコロナ禍を超えたことで、当時とはまた状況が一変し、私の中でもより解像度高く説明できる状態になりました。
具体的には
ジョブ(職務)をタスク(作業・業務)に分解する
分解したタスクに対し、手順を明確にする(業務フロー・手順書)
2の中から、業務委託さんに渡せるもの、RPA化するもの、AI開発によって自動化するもの、などに段階的に分類していく
分類した先にアウトソースしていく
を行います。これを「work platformの構築」と言っています。
元々はクオン社時代に、夫の転勤で地方に引っ越しが必要になった社員がいて、「その人が辞めずに、業務の運びを工夫することでオンラインで社員としてそのまま働き続ける状態を構築してあげられないか」と言う取り組みがあったことが始まりでした。当時はなんとSkypeでした。(今や誰も使っている人を聞かなくなりましたが)2010年あたりだったと思うので、相当早かったと思います。コロナ禍を経て、「オンラインで打ち合わせや業務をする」、「業務委託さんと契約する」と言ったこと自体が当たり前の時代になりましたが、当時はかなり先駆的な取り組みだったと思います。
改善の余地はありながら、私の組織観ともマッチするとても良い取り組みだと感じていたので、ライトワークス社に来ても同様の仕組みの構築に着手しました。同時に、「お客さんとの商談もオンライン化させたい」という思いから、コロナ前に既にオンライン会議のシステムを提供していたbellface社と契約したりもしていました。ただ、コロナ前はお客様に打ち合わせのオンライン化をお願いするのは中々ハードルが高い状態でしたので、既顧客やベンダーさんにお願いするところからスタートしていました。今となっては隔世の感です。
このwork platformの構築はまさに今時代の要請となっていると感じます。UPWORK研究所が発表している「Freelance Forward 2023 」によると、なんと米国ではミレニアル世代で44%、Z世代に至っては52%もの人がフリーランスを選択しているそうです。

https://www.upwork.com/research/freelance-forward-2023-research-report
レバテックフリーランスの調査によると、米国におけるフリーランス人口は日本の20倍以上あり、仕事を進める構造自体が日本と大きく異なっているそうです。

https://freelance.levtech.jp/guide/detail/1087/
米国の流れが5年、10年遅れて日本にやってくると言うパターンをSoftBankの孫さんが「タイムマシン経営」と名付けていましたが、日本においても同様の流れが起きる可能性が高いと考えています。
ラヴィン・ジェスターサン, ジョン・W・ブードロー, マーサージャパン著の『仕事の未来×組織の未来――新しいワークOSが個人の能力を100%引き出す』において、”ギグワーカー、AI、ロボティクスなど、仕事の進め方の選択肢が増えるなかで、もはや「雇用」は人と仕事をつなぐ主要な仕組みではなくなりつつある。仕事を雇用という枠組みで捉え、働く個人を被雇用者に限定してしまうと、多様な働き方も、人間と自動化の最適な組み合わせも見えなくなってしまう。” と語られている通り、work platformの構築は生産性を改善したい全ての企業で実施すべきものだと考えます。
本論から少しずれますが、このwork platformの構築を同著では「WX(Work Transformation)」と表現しています。これ以外にも、
・Workstyle Transformation
・Workforce Transformation
と言う概念があり、
・Work Transformation
を加えてそれぞれを定義すると、
◉Work Transformation (WX)
働き方を根本的に見直し、より効率的で柔軟性のある形に変革するプロセスのこと。仕事そのものの再定義や、業務モデルの再設計、組織構造の最適化、必要な能力の予測など、包括的な変革を指し、デジタル技術の活用、組織文化の改善、業務プロセスの見直しを通じて、企業や個人の生産性向上や満足度向上を目指す。これにより、組織は新たな成功を収めるための基盤の構築が可能になる。単にデジタル技術を導入すると言ったことではなく、組織全体で「働き方」を見直し、従業員の満足度と企業の競争力を同時に向上させる取り組みのこと。
◉Workforce Transformation
組織が変化するビジネス環境や技術革新、従業員の期待に適応するため、従業員のスキルや役割、組織構造を再評価・再構築するプロセスを指す。これにより、生産性や従業員エンゲージメントの向上、継続的な学習によるイノベーション文化の創造を促進する。
◉Workstyle Transformation
従来の固定的な勤務形態から、リモートワークやフレックスタイムなど、柔軟で多様な働き方への移行を指す。これにより、従業員のワークライフバランスの向上や、多様な人材の採用・定着を目指す。「働き方を一律に変える」ことではなく、「従業員と企業双方にとって最適な柔軟性を追求する」取り組みのこと。
となります。
当時からここまで解像度高く整理できていたわけではないですが、おおよそこのような概念で業務委託チームの構築やRPAの導入などを進め、最終的に人件費ベースで考えても莫大なコスト削減、生産改善が実現できていました。
ポイントは先ほどの手順の2で、「業務フローと付随する手順書を書く」だと考えています。これを進めていくと「社員じゃなくてもできる」範囲が相当広いことが見えてきます。よく、「コア業務を社員に、ノンコア業務を外に」と言われますが、手順2を進めると、「コア業務とノンコア業務の境目」が分からなくなっていくのです。言い方を変えると、「ほとんどの業務は社員じゃなくてもできる」状態になっていきます。
日本には戦後の高度経済成長期に、それがあったがゆえに成し得た「新卒の一括採用・終身雇用」、いわゆる「メンバーシップ型雇用」があります。メンバーシップ型雇用とは、新卒を総合職として一括採用し、業務内容や勤務地を限定せずに雇用契約を結ぶ仕組みのことです。 終身雇用を前提としているところが特徴で、企業独自の社風に適した人材を、長期にわたって育成します。 年功序列によって昇進が決められることや、企業別に労働組合があることも大きな特徴です。メンバーシップ型は「人に仕事を合わせる」制度とも表現されます。
これに対し、欧米企業に見られるのがジョブ型雇用で、企業にとって必要なスキル、経験、資格などを持つ人材を、職務内容などを限定して採用する雇用方法です。「朝起きたらメールで解雇が通知されていた」と言った流動性が高い雇用形態で発達した仕組みともいえます。ジョブ型は「仕事に人を合わせる」制度とも表現されます。
このジョブ型は、フリーランスを組み込みやすいのだと思います。本来であれば、常に変化していくビジネスシーンにおいて、「全く同じスキルを持った社員がずっと必要」と言う状況は考えにくいです。よって、変化に合わせて都度、その変化に対応したスキルを持つ社員を雇用するのではなく、必要なスキルを持ったフリーランスを適切な期間ジョインさせることによって、企業活動自体が効率よく回していくことが可能になります。こう言った背景が、先ほどの米国でフリーランス人材が世代を経て増加している背景なのだと思います。
このジョブ型雇用によって、「job discription」が生まれました。job discriptionとは、職務内容をまとめた文書のことです。日本語では職務記述書と訳されています。 job discriptionに記載される代表的な項目は、職務のポジション名、目的、責任、内容と範囲、求められるスキルや技能、資格などです。特に職務内容と範囲については、どのような業務をどのように、どの範囲まで行うかといったところまで詳細に記述されているそうです。job discriptionがあることで、それぞれの社員の職務が明確になり、あいまいさが排除されます。これによって業務上の無駄や非効率が少なくなり、組織の生産性が上がるとされます。
人材募集においても、採用したいポジションのjob discriptionを求人情報として明確に提示し、雇用契約を結びます。求職者はjob discriptionを見た上で応募するかどうかを決めるため、ミスマッチが少なくなります。
メンバーシップ型雇用の日本の企業にはこれに相当するものが基本的にありません。だからフリーランス化が遅れているのだと考えます。一方で、日本でも経団連が主導して「ジョブ型」が進められています。
よって日本でもこのwork platformの構築が今後加速していくのだろうと考えています。
5.マネジャーの育成に取り組む
いよいよ組織改革の本丸である「マネジャーの育成」です。ここについてみなさんこう思っていると思います。「他人の主体性を育むことほど難儀することはない。」本稿はここに一つの解が出せないかという覚悟でまとめました。ベンチャー企業での16年の取り組みで最も工数を使ったのがここだと思います。
まず、そもそもなぜマネジャー育成に取り組まなければならないのでしょうか?
皆さんもなんとなく「マネジャーは必要」という認識があると思いますが、ベンチャー企業のグロースにおいては「50人の壁を突破するため」が、シンプルな答えになります。
50人の壁について聞いたことがある人も多いと思います。私も随分前から知ってはいるものの、誰がどこで言ったのかは分かっていません。よって引用元がなく、また圧倒的なグロースでなんら問題なくそこを超えていく事例もあるので、全てに当てはまる、ということでもありません。でも、私がベンチャー企業のグロース(10数人から数百人規模)を2度経験した経験則からみても、これまで携わったスタートアップやベンチャー企業を見ても、やはり多くの企業で30人、50人の壁にハマっているケースが見られました。
それを前提として、詳しくご案内していきます。
いわゆる組織の壁には、「30人の壁」、「50人の壁」、「150人の壁」があると言われています。150人ではなく、「100人の壁」という表現もあります。私の場合、2社とも100人の壁は問題なく超えていったので、ここでは割愛させていただきます。また、前述しましたが、T2D3といった表現がある通り、売上が急速に拡大していく企業にとってほぼイシューにならないケースもあります。ただ、こう言ったケースは滅多にありませんので、異常値とします。こう言ったグロースをしたケースほどアテンションが集まりますので、たくさんあるようなイメージですが、潰れた企業は注目されませんので、感覚的には1,000社に1社とかそういうレベルの異常値なのだと思います。よってここでは数億単位のグロースをしていく場合に起こりうる問題としてよく言われる、「組織の壁」を書いていきます。
1.組織の30人の壁
一言で言うと、「組織化の壁」です。起業してうまく軌道に乗り始め、20人を突破したあたりで徐々に顕在化してくるはずです。ざっと調べたところ明確な統計データはなかったのですが、感覚的に起業は2~3人のパターンが多いと思います。フリーランスの起業が最も多いですが、会社として大きな拡大を目論んだ起業としては2~3人が多い印象です。
このメンバーでスタートして、最も困難と言われる売上1億円の壁を突破するまで4~5年、メンバーが5~8人ぐらいになっているとします。そこからさらに売上を伸ばし、海賊船のようなワンチームでやれている規模が20人ぐらいまでです。創業メンバーを仮に営業サイド・管理サイド・サービスサイドの3人だとした場合、マネジメント対象人数の最適数が5~8人とされるので、創業メンバーがそれぞれの管掌範囲でチームを見ていくとすると、20人前後までは順調にワンチームでやれている目算になるからです。
余談ですが、マネジメント対象人数の最適数については、有名なジェフ・ベゾス氏の「2枚のピザ理論」、つまり理想的なチームメンバーの数は、2枚のピザを分け合える人数(5~8人)という話や、元々軍隊において使用されていたという「管理限界」と呼ばれるスパン・オブ・コントロール(Span of control)という概念でも、5~8人とされています。管理する部下の人数を適切に保つと組織は円滑に運営できるという考え方です。
ここを超えてさらにメンバーが増えると、1チームが10人以上になるところが出てきます。この段階で不具合が生じ始める、ということです。ではどうするか。「組織化」です。今までツーカーでやっていたコミュニケーションに規律を入れる、管理サイドの仕組み化を進めるといった「同じ品質のものを安定して供給する組織化を進める」というアクションが必要な段階です。
創業メンバーによってはここが得意な人たちもいますので、30人の壁は問題なく超えられた、という会社もあれば、「海賊船のような会社を作りたかった」という思いから始まった会社がここで躓くと言ったパターンもあります。
さて、組織化がうまくいったとして、次は50人の壁です。
その前に、このタイミングで「チーム」と「組織」の違いについて私なりの理解を書いておきたいと思います。部下に対して1on1をやっていたり、チームを率いる立場にいる人はなんとなく感覚的に理解していると思いますが、簡単に整理すると以下の通りです。
◉チームとは
野球チーム、サッカーチームといった使われ方をするように、モチベーションや個の力によって結果が変わるような人の集合体。変数や予測不可能性を許容、あるいは期待する。盛り上がっている時もあれば、意気消沈している時もある。難しい目標に向かって「チーム」一丸となって取り組む。
◉組織とは
いつ、どんな時も均質なアウトプットを出す人の集合体。役所や消防署などがイメージしやすい。例えば、「消防士のモチベーションが低い」という理由で火事の消火に対する結果が変わる、といった事態を想定しない。いついかなる時も同じ品質でアウトプットを出していく。
例外はあると思いますが、ここに書いている「チーム」と「組織」の違いはじょうきの理解で進めています。
2.組織の50人の壁
50人の壁はマネジャーの育成です。チームに組織の要素を入れて会社らしくなってきたところでマネジャーの育成の壁に当たります。この段階で部署は4~6部門になっており、マネジャーも3~4人はいる段階になっています。人数が増えたことで社員と経営層との距離が開き、マネジャーがトップの意向を翻訳して現場に落とす作業ができないとコミュニケーション不全が起き、ワンチームからは程遠い状態になっていきます。
そうすると、平時は問題ないですが、問題が起きた時や、トップと現場の板挟みにあってフラストレーションを溜めたマネジャーには、「なぜトップの意向を翻訳して現場に落とさなければならないのか」といった疑問が生まれてきます。ここで躓く会社は本当に多いと思います。
マネジャーが育っていない根本的な問題は経営層の意向と言い切って良いと思います。経営層がそこにコミットする姿勢を見せない限り、この問題は解決しません。経営層にこの意向がなく、30~50人をうろついている会社をたくさん見てきました。
マネジャーの育成には経営層の強いコミットメントが必要です。そもそも人は人を育てたいと思っていないからです。マネジャーに「部下を育ててくれ」といっても、マネジャーにとっては「本気で部下を育てて、その対象が成長したら自分が追い抜かれるのではないか」という恐怖心があります。マズローの5段階欲求をなぞらえるなら生存に関わる根源的な恐怖心です。
それを抑えて部下を育ててもらわなければならないから難しいのです。
ではどうするか。
・マネジャーが部下を育てたいと思うような文化・風土の醸成
・育成を前提とした昇格制度や評価制度などの制度設計
・部下育成の仕組み化
・マネジャー育成の仕組み化
といったことが必要になります。何より、部下を育成しろといっている経営層こそ、マネジャーの育成に全力で取り組まなければ、文化も風土も生まれません。これができていない経営層があまりに多いと感じます。
ここまで読んでいただければ、50人の壁を超える方が30人の壁を超えるよりずっと難しいことが理解できると思います。でも、ここを超えられれば組織は100人、あるいは150人まで順調に成長できます。上記に関する具体的な施策は後述します。ひとまず、最後の150人の壁にいきます。
3.組織の150人の壁
30人の壁を突破し、チームに組織の要素を取り込んで定着させ、マネジャーの育成にコミットして50人の壁も突破。メンバーレイヤーの数が増えても組織は瓦解せず、売上も伸びて100人、150人と拡大していった・・・。 150人の壁はこの辺りで見えてきます。
具体的には、組織の拡大による「コミュニケーション不全」や「一体感が失われる」といったことです。特にコミュニケーションまわりのトラブルが頻発するようになります。部門ごとに使っている言葉が違うことで起きる問題、部門間の対立、フリーライダーの出現などなど、組織の一体感が失われていると感じるトラブルが起きていきます。理由はわからないですが、私はダンバー数の影響があるように思います。
ダンバー数とは、ヒトを含めた霊長類が、互いを認知し、安定した集団を形成できる個体数の上限のことで、1990年代にイギリスの人類学者ロビン=ダンバーが提唱しました。その論文によると霊長類の脳を占める大脳新皮質の割合と群れの構成数に相関関係があり、ゴリラは35、チンパンジーは65、そしてヒトは150とのことです。
アメリカにおいて、近代文明を離れ、電車も車もない、厳しい宗教戒律に基づいた独自の共同体を形成する「アーミッシュ」は、1つの共同体の構成員の平均が110人で、150人を超えると共同体を二つに分けるそうです。他にも、現代においても狩猟採集民として暮らす複数の部族社会で、氏族や村といった集団の平均人数が153人だったという調査報告もあります。こういった情報から、組織が150人を超えると分社化するという経営を行った会社があったという話を聞いたこともあります。
組織の30人の壁、50人の壁、150人の壁それぞれ、ピッタリその数ということではありません。30人の壁であれば20人ぐらいからもうすでに準備が必要ですし、50人の壁を超えるには30人を超える前にはもう仕組み化に着手していなければなりません。
ちなみに、組織論的な話で、150人の集団より、100人の方が不安定という見解もあるようです。これはこれで理解できる部分があります。ちなみに人類は規律や法、警察といった自治システムを構築していくことでダンバー数を超える組織構築に成功しているのは現代社会を見てもご存じのとおりです。よってここ(150人)を超えることはヒトにとっては不自然なことと考え、それを超えるための準備が必要、と考えておく必要があります。
ではどうするか。
この壁を越えるために必要なのは、
・より強度の高い仕組み化・組織化
・理念の浸透の徹底
・内部監査システムの構築
などがあげられます。分かりやすく言うと、一見無駄に見えるような情報開示や伝達、意思統一を図るための「言葉の定義」など、社内外に流通する言葉に意識を向け、集団を丁寧にまとめあげていくイメージで、コミュニケーションに意識を向けて上記の対応を根気強く続ける、といったことが必要です。
もうひとつ、内部監査的な動きを組み立て、第三者的な視点の存在を意識させるのも重要な対策の一つと考えます。
まとめると、売上が上がって組織が拡大し、100人を超えたあたりで様々なところに慢心が生まれていくので、「問題が起きる可能性が高い」という前提に立ち、特にコミュニケーション周りに問題意識を持って対策に取り組んでおく必要がある、ということです。
それでは、ここから最も難易度が高いと考えられる、組織の50人の壁の突破の仕方、マネジャーの育成について何が有効だったかをまとめていきます。
まず、会社を取り巻くステークホルダーから「良い会社だね」と言われる会社とは何かを考えます。これをひとまず「エンゲージメントが高い会社」とします。「エンゲージメントが高い状態」というのは、職場環境や労働条件に不満がなく、仕事に情熱や意欲を持っている状態、つまり、そこでの自身のあり方に満足している状態と定義します。この状態を「楽しく働けている状態」とすると、そこで働く人々は「幸せ」を感じていると言えます。人は「幸せ」を感じると、血中のオキシトシン濃度が高くなるそうです。
世の中には変わった研究者がたくさんいますが、アメリカの神経経済学者のポール・ザック博士は血中のオキシトシン濃度を測ることで、幸せを感じている社員が多い企業を調べていきました。すると、靴専門EC運営会社のZapposに行き当たります。この会社は12億ドルでAmazonに買収されたことで有名になりました。Zapposの社員は総じてオキシトシン濃度が高かった。なぜそうだったのか。他の企業にはなくてZapposにあったのはなんだったのか。
調査の結果、Zapposに特に顕著に見られた特徴は「信頼」と「目標」の2点だったそうです。(参照:『TRUST FACTOR トラスト・ファクター~最強の組織をつくる新しいマネジメント』)
「人は信頼されると神経伝達物質オキシトシンの血中濃度が高くなる。」
脳には、オキシトシン濃度が高くなると「受けたその信頼に応えようとする」仕組みがあることがわかっています。信頼のおける組織の中でチームや個人の目標が正しく流通している状態。これを実現するために、マネジャーの役割は大きいです。この観点でマネジャーに求められるのが、「パフォーマンスマネジメント」です。
ちなみにZapposの事例で引用したこの書籍『TRUST FACTOR トラスト・ファクター~最強の組織をつくる新しいマネジメント』は、チームビルディングや組織開発を始め、「いい会社をつくる」に心血を注いできた私が、ここに関心を持つすべての経営者、マネジャーにお勧めしたい書籍の一つです。
では、パフォーマンスマネジメントとは何かですが、パフォーマンスマネジメントとは、「従業員が主体的に業務に取り組むことで最高のパフォーマンスを発揮する手助けをするマネジメント手法」のことです。上司が部下の特性に応じて、能力やモチベーションを引き出し、目標を設計し、行動に対する定期的なフィードバックやコーチングをする点が特徴です。
1970年代、アメリカの行動分析学者・コンサルタントであるオーブリー・ダニエルズが「メンバーが行動から結果に結び付けるための人材マネジメント手法」として紹介したことが始まりとされています。VUCA時代を迎えた近年ではスターバックス、ジェネラルエレクトリック、ゴールドマンサックス、アドビシステムズ、デロイトトーマツなどで取り入れられ、注目を集めています。
具体的には、パフォーマンスマネジメントを導入することで、組織に「成功の循環」が生まれます。マネージャーとの信頼関係が構築され「関係の質」が改善されることで、メンバーの「思考の質」が変わり、モチベーションが上がることで、メンバーは「自分は何ができるか」を考えるようになり、主体的に行動し始め、「行動の質」が変わる。得られた結果を前向きに受け止めることで良いPDCAが回せるようになり、「結果の質」も変わる。この成功の循環が回ることで、エンゲージメントの向上、人材の流出防止といったことが起きていきます。

ところが、世の中のマネジメントの多くは「結果の質」を問うところから始まります。これはビジネスパーソンであれば誰しも感覚的に理解できることだと思います。結果が出ていれば大きな問題は生じないのですが、結果が出ていなければ「問題が起きている」と解釈されますので、そういった言及があること自体は至極当然のことだと思います。特にベンチャー企業においては、結果について言及されたことがないビジネスパーソンはいないはずです。
ただ、ここからスタートしてしまうと、部下はうまくいかない理由を探すようになり、環境や他者に原因を求めるといった動きにつながります。売れないのは「システムが悪いからだ」、「そもそもうちのマネジャーは何も教えてくれない」、「この会社が売っているものは売らなくて良いものを強引に売っている」といった他責(言い訳)が100でも200でも出てくる状態です。
よって、このサイクルを意図的に「関係の質」からスタートします。ここに問題意識を向けるところから循環を作っていくのがパフォーマンスマネジメントです。では、メンバーとの対話は誰が行うのかというと「マネジャー」ですので、「成功の循環」の鍵を握るのは「マネージャー」ということになります。パフォーマンスマネジメントを導入する上でマネージャーの果たす役割は大きいということです。

具体的に、マネジャーは何ができれば良いのか。マネジャーがメンバー個々の能力を引き出し、モチベーションを高めながら成果を出していくには、日頃からのコミュニケーションを軸にしたリアルタイムフィードバックが重要となります。以下に、パフォーマンスマネジメントを実現する上でマネジャーができるようになる必要があることを列挙します。
◉部下との信頼関係を構築する
・1on1での対話を通し、信頼関係を構築することで、心理的安全性やエンゲージメントの高いチームを創出する
◉目標を設計する
・上司が一方的に目標を決めるのではなく、部下との対話を通し、本人が燃えられるゴールを言語化し、目標設計を行う
◉just in timeでフィードバックを行う
・1週間から1カ月に1度など、通常の評価と異なる、短いスパンで対話を繰り返し、目標達成に向かうプロセスのチューニングを行う
※目標達成度が高いチームは1on1の頻度が高く、目標達成度の低いチームでは1on1をしない割合がトップとなった。(パーソル研究所『マネジメントの取り組み実態調査レポート』)
◉社員の強みや個性を理解(言語化)し、モチベーションや能力を引き出す
・強みを理解できていない、自信がない部下に対し、何が強みか、何ができているかを言語化し、前に進む工夫や習慣を一緒にデザインする
・これにより、一人ひとりのモチベーションや能力を引き出すことを可能にする
◉部下の気づきを促す
・上司が答えを教えたり、アクションを指示をしたりするだけでなく、本人の口から「本質的な問題はなにか」、「それに対してどうすれば良いか」、といった、部下自身の気づきや考えを問う対話のデザインをする
・過去より未来を重視し、目標達成にむけてこれから何をすべきなのかに焦点を当てた対話をデザインする
こういったことをマネジャーができるようになる支援をしていく必要があるということです。
パフォーマンスマネジメントを機能させ、理想の組織状態にするためにはマネージャーの役割が極めて重要ですが、マネジャーにただそれを期待するだけでは実現しません。組織として、制度面・教育面からマネジャーを積極的に支援していく必要があります。具体的には、以下のような「制度面の整備」とマネジャーの「スキルと知識を高める支援」をしていきます。

制度面整備について、ここまで書いた内容で、
・MVV
・コンピテンシー
・評価
までが完了しています。
時間軸は異なりますが、この先スキルマップや付随する教育コンテンツの整備、MBOのリニューアル、オベーションの仕組み化などを進めていきました。スキルマップについては後述します。ここで大事なのは、真ん中と右の「マネジャーのスキルと知識の向上」です。ここに相当な工数をかけました。
「マネジャーのスキル」にある5つを短期的に高いレベルに引き上げるにはどうしたら良いか。試行錯誤の結果、1on1にコーチングスキルのエッセンスを組み込むプログラムを開発し、それをマネジャーができるようになるサポートを徹底しました。これが最も再現性が高かったです。
信頼関係の構築、目標管理、モチベーション喚起の3つのスキルはコーチングにノウハウが詰まっています。コーチングができるようになる必要はなく、コーチングからこの3つのスキルをエッセンスとして凝縮し、1on1に組み込んで誰でも再現可能なものにする、という試みでした。
フィードバックスキルは、上記を学んだマネジャーが1on1を実際にやる際、うまく伝わったこと・伝わらなかったことを記録してもらい、それを私との1on1に持ってきてもらって、「こういう伝え方をしたら良かったのではないか」、「こういうネタや過去にこんな伝え方をしてうまく行ったケースがある」といったFBや視点の提供、それらを元にした議論をしました。
余談ですが、私はクオン社とライトワークス社の2社で、合計すると5,000時間は部下との1on1に費やしていました。それぐらい、「部下を育成すること」に重きを置いていた、ということです。ライトワークスでは約7年間、毎週金曜日を全て1on1に当てており、マネジャーや私との1on1を希望するすべての人に間口を開放していました。
正直、全体の稼働の20%が誰かの育成のために消えるわけですから、「大変だな」、「止めたいな」、「プレイヤーとしての仕事の時間を増やしたいな」、「自分のスキルや知識を上げる時間を増やしたいな」と思ったことは一度や二度ではありません。むしろ毎週やる度に頭をよぎっていたのが真実です。でも、続けました。管掌部門のトップが育成にコミットしている姿勢を見せたかったからです。もちろん、これが良いのか悪いのかという議論はあると思います。ただ、70%あった3年以内離職率は一時5%まで下がりました。これはこれで低すぎていいということでもないので、あくまで施策とその結果の数値です。
というのも、離職率について、私は3年以内離職率をKPIとして見ていたのですが、目安をどこに置くのが最適か、という疑問があります。無論、業界や企業の戦略、方針によるので正解はないという前提ですが、私自身はグロースを誓うベンチャー企業2社や、コンサルとして関わった様々な企業を見て、感覚的には10~15%ぐらいが適正だと考えていました。5%まで下がった状態を良いとは思っていなかった、ということです。
会社が成長するということは環境が変わるということであり、求められるスキルや考え方もアップデートしていかなければなりません。「全員と目的地に行く」という覚悟を持って、「成長を促す、成長をデザインしてあげる」ことに全力で取り組みながらも、客観的に評価することを怠らない、チームを離れる人がいるということを冷静に見る目は持っていなければなりません。この二律背反の中でアウフヘーベンし、自らの行動をデザインしなければなりません。
仕事がうまくいっていないにも関わらず、改善する努力をしない社員との向き合い方は、グロースを続ける企業にとってはとても、とても苦しく、悩ましい問題です。後述しますが、急速に会社の売上が拡大していく中で、私もやはりこの問題に直面しました。真剣に会社をよくしようと、離職率を下げようと努力していても、それが誰しもにとって望ましいことではない、という前提に立たなければならない、ということです。
それを前提とした解決方法が、パフォーマンスマネジメントの導入と、そのKSFが1on1へのコーチングの導入だったわけです。そして、この問題について、私が最も参考になると感じたのは2009年にNETFLIX社のCEOのリード・ヘイスティングによって公開されたCulture Deckでした。このCulture DeckはFacebookの元 COOであるシェリル・サンドバーグに「シリコンバレーから生まれた最高の文書」と絶賛されたことで広く知られることになったものです。この文書が起点となって「企業の成功において企業文化の形成がいかに重要か」という議論が再評価されたそうです。
元々はDVDレンタル屋さんからスタートしたNETFLIXがどうやって今のポジションに上り詰めたか。現在のNETFLIXやレンタル屋さんではなく、巨大なコンテンツメーカーであり、プラットフォーマーです。その変化の過程に並々ならぬ苦労があったのは間違いありません。そんな激しい変化を遂げる中で、どうやって企業文化を形成していったか。それを知る上で、『NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX (日本経済新聞出版)』は大変参考になりますのでお勧めしておきます。
「シリコンバレーから生まれた最高の文書」と評された当時のCulture Deckはこちらから参照できます。(https://www.slideshare.net/slideshow/culture-1798664/1798664)
最新版としてNETFLIXが公開しているもの(https://jobs.netflix.com/culture)もありますが、こちらと違って2009年当初のものは尖った部分があって、私はこちらの方が好きです。
話を「1on1にコーチング要素を取り組む研修プログラム」を開発したところに戻します。
先に紹介した”目標達成度が高いチームは1on1の頻度が高く、目標達成度の低いチームでは1on1をしない割合がトップとなった。(パーソル研究所「マネジメントの取り組み実態調査レポート」)”の通り、1on1の頻度は高い方が良いということなので、であれば、どうせマネジャーにやってもらうなら品質の高い1on1をやってもらった方がインパクトが大きいはず、となります。
では、誰でも高い品質の1on1ができるようになるにはどうしたら良いか、ということで、散々再現性を確認した結果、「1on1にコーチングのエッセンスを取り込む」が最適解でした。
コーチングについて、色々と思うところがある方も多いと思いますが、5,000時間を1on1に費やした私としては、1on1におけるコーチングは非常に有用性が高いと結論づけられています。
コーチングができるようになる必要は全くありません。エッセンスを抜き出して取り入れるだけで良いのです。エッセンスとは、「信頼関係を構築する」と「目標をデザインし、伴走する」の2つだけです。ここに集中します。これだけで、1on1は劇的に良くなります。これまで、「なんとなく1on1を嫌がられているかも」と感じる人がいたら、状況を劇的に改善できます。過去には、このプログラムを受けて「1on1を部下からお願いされるようになった」と喜んでいたマネジャーがいました。
ここからどうやってコーチングを1on1に取り込んでプログラムにしたかをまとめていきます。
それにあたって、外観を掴んでから組み込み方を解説した方が良いので、まず、「コーチングとは何か」からまとめていきます。次に、それを理解した上で、「コーチングは必要なのか」に関して、世の中の評価がどうなっているかをご紹介します。それを踏まえて、コーチングのスキルと知識の中でも何を1on1に取り込めば良いかを解説していきます。最後に、「ざっくりいうと」という形で具体を解説し、何をトレーニングすれば良いかを簡単にまとめます。
まず、この内容に関心を持っておられる読者の皆様であれば既に「コーチングとは何か」についておおよそ把握しているものと思いますので、重要なポイントだけかいつまんでまとめます。
コーチングのCoachという言葉は、もともと「馬車」のことを指し、「大切な人をその人が望むところまで送り届ける」という意味を持っています。よってコーチングは、「人の目標達成を支援する」という意味合いで使われています。ちなみに、トレーニング(Training)もtrainと乗り物が使われています。trainingの語源は、「引っ張る」を意味する「Trahere」というラテン語と言われていて、ここから列車が客車を連ね、引っ張って導く様子を「Train」とし、目的を達成に導く練習を「Training」というようになった、という説があります。
コーチングはどのようにして広がったか。1840年代に入ると、学生の受験指導をする個人教師のことをCoachと呼ぶようになり、1880年代、スポーツの分野の指導者に対してCoachという呼び名が使われるようになります。スポーツ分野のCoachは技術指導をするだけでなく、選手のモチベーションを高めるなど精神面でのサポートも行っていました。
マネジメントの分野でコーチングを活用する動きが見られたのはアメリカです。1950 年代に当時ハーバード大学の助教授だったマイルズ・メイス氏が著書“The Growth and Development of Executives”の中でマネジメントに必要なスキルとしてコーチングをあげたことに始まります。
◉どのように体系化が進んだか
その後、1960年代にいくつかの研究所やトレーニング機関が設立され、1970年代にはトレーニングプログラムがマーケットで提供されるようになってきました。1980年代に入るとコーチング関連の本が多く出版されるようになり、1990年代に入ると、コーチを育成する機関として1991年にCoach Training Instituteが、1992年にはCoach Uが誕生しました。また1995年には非営利団体 International Coach Federation(ICF:国際コーチ連盟)がコーチの質の維持を目的に設立されました。
◉どのように企業へと広がったか
1990年代中盤に大企業ではIBMが初めてコーチングを利用したことから、欧米では企業がビジネスにおける人材開発の手段としてコーチングを活用するようになったそうです。1999年にはイギリスにThe Coaching Academyが、2000年にはEuropean Coaching Instituteが、2001年にはブラジルにInternational Coaching Institute(ICC)が設立されていったそうなので、このような時間軸で世界的な広がりを見せていったことになります。
こうしてみると正式な機関が立ち上がってから30年程度しか経っていない状況ですので、急速に広がっていると見て良いのだと思います。特に、予測不可能性が高まる現代社会をVUCA時代と言うようになる流れから、さらにコロナ禍を経て、社会不安が広がったことで加速的に需要が高まったように感じています。
◉日本ではどのような展開をしたか
日本では1997 年にコーチ・エィ(当時コーチ・トゥエンティワン ) が、日本初のコーチ養成機関としてコーチングを体系的かつ体験的に学ぶ「コーチ・トレーニング・ プログラム (CTP)」の提供を始めたところから始まり、1999年に当時GE(ゼネラル・エレクトリック社)のCEOであり「伝説の経営者」と呼ばれていたジャック・ウェルチが「私は27歳の女性コーチと話をする中で意思決定を行っている」と話したことが、コーチングが注目を集めるきっかけとなったそうです。
歴史的な文脈はこれぐらいで十分かと思います。続いて「コーチングでできることとは何か」です。色々な解釈や説明がありますので、当然ながらこれは私個人の見解ということを前提にしてください。
コーチングを通してできることは、大きく分けると以下2つと考えています。
1.対象者が抱えている問題解決の手助けをする
2.対象者の成長・目標達成を支援する
1、2共に、以下をサポートすることで実現させます。
・対象者が、新しい視点や気づきを増やすこと
・考え方や行動の選択肢を増やすこと
・上記を踏まえ、新たな行動習慣をデザインすること
コーチングでは「基本的に相手の中に答えがあり、その言語化をサポートする」という立ち位置を守ります。「強制する、指示する」はもちろん、「教える、アドバイスする」といった要素もありません。お金を払ってコーチャーを付ける場合、彼らは上司ではないので、あくまでこちらが主体となる支援に徹してきます。基本的にコーチャーは私たちにアドバイスすることができません。同じ仕事をやったことがあり、経験値があなたより高く、かつあなたが置かれている状況を周囲の人間関係まで知った上でそこにいる、ということではないからです。よって伴走に徹してきますが、それでも高い対価を払って雇いたいと思うようなパフォーマンスをしてくれます。
何が行われているかというと、「問い」が来ます。こちらはその問いに答えていくだけです。最終的に自分の中で「これが答えだ」と思えるもの(気付き・発見)にたどり着いたら、それを達成する、あるいは解決するために必要な習慣のデザインをサポートしてくれます。
これがベーシックなコーチングのすべてです。
ただ、同じこと(コーチング)をしていても、定期的に顧客が獲得できるコーチャーとそうではないコーチャーがいます。そもそもスクールに行って資格を取った後に集客に困らないコーチャーは「ほんの一握り」が事実だと思います。どこで差が生まれるのでしょうか?
コーチングを受けた人が満足し、「コーチングを受けて良かった」と思ってくれる状態、結果、紹介やリピートで定期的に顧客を獲得できている状態。ここに持っていけるか、否かは、コーチャーが出した「問い」に対し、「対象者が素直に、なんの遠慮もなく、こちらを気にせず、思ったことを言ってくれるか、否か」にかかっています。では、どうしたら対象者は、素直に「問い」と向き合ってくれるのか。それは、「信頼関係が構築できているか、否か」にかかっています。
これは後ほど詳しく触れますが、コーチングにおいて、「信頼関係の構築」は極めて重要な要素・スキルです。また、発展的なところを言えば、「問い」の精度をどう上げていけば良いか、があげられます。これはかなり難しいスキルなので、ここでは触れません。ここで触れるのはコーチングの基礎ですが、でも実はそれが奥義と言って良いものだと思っています。
ここまでが「コーチングとは何か」、「コーチングでできることは何か」でした。続いて、「コーチングは必要なのか」に関して、いまコーチングに対して世の中がどう評価しているのかを紹介します。
副業としてではなく、ビジネスシーンにおいて、一般のビジネスパーソンがコーチングをどこで使うのかについて、「1on1に取り込む」とお伝えしました。1on1に取り入れると、部下から感謝されるような1on1ができるようになります。まずはその理由からお話しします。
「良いマネジャーになるためには、どうしたら良いか?」という、ビジネス界でははるか昔から様々な言及がなされてきた世紀の難問があります。この世紀の難問に取り組んだのが、Googleです。Googleは世界で最も優れた会社という評価を得ていますが、創業当初は社員の多くはナード(nerd:いわゆるオタク)と揶揄されるITエンジニアで、マネジャーに向いている人間が多いというわけではなかったそうです。
そんなGoogleの中で、「すべてのマネジャーを廃止して、管理職のいない組織にする」というユニークな実験が行われました。当時の Google では「世界中からトップエンジニアが集まる 我々にとって、エンジニアがのびのびと仕事ができる環境構築こそが最も重要な経営イシューのはず。だからマネジャーなんて必要悪でしかないのではないか」という仮説が背景にあったそうです。「脱組織化(ディスオルグ)」と名づけたこの体制は結果1年程度で廃止となりました。この体制になって現場のエンジニアにマネジャーが欲しいかと聞いたところ、Yesという回答が返ってきて、なぜかを問うたところ「何かを学ばせてくれる人や、議論に決着をつけてくれる人が必要だから」という回答があったそうです。
その後も「マネジャーは重要な存在ではない」ことを証明しようと試みたものの、これも正反対であることが判明し、マネジャーは極めて重要な存在だと結論づけたそうです。
であるなら、最高のマネジャーになる方法を見つけようと2009年に立ち上がったのがプロジェクトOxygen(酸素)で、このプロジェクトから明らかにされたのが、「Googleで最高のマネジャーになるための8つの習慣」です。
私はこのエピソードがとてもGoogleらしくて好きです。詳しく知りたい方はエリック・シュミット著『1兆ドルコーチ――シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え(ダイヤモンド社)』を参照ください。
では、「Googleで最高のマネジャーになるための8つの習慣」とは何かですが、その8つの習慣の5番目でも8番目でもない、1番最初に書かれているのが、「よいコーチであれ」です。「よいコーチになれば、よいマネジャーになれる」と、Googleが結論づけたのです。つまり、よいマネジャーになる答えがコーチングにある、ということです。ちなみにその8つの習慣がこちらです。
◉習慣1 よいコーチであれ。
・具体的で、建設的なフィードバックをする。
・ネガティブフィードバックとポジティブフィードバックをバランスよく行う。
・定期的に1対1の対話をし、部下の強みに合わせた問題の解決方法を示す。
◉習慣2 部下に権限を委譲せよ。マイクロマネジメントはするな。
・部下に自由を与える。同時に、よき相談相手になる。
・チャレンジできるようにストレッチした課題を与える。
◉習慣3 部下の成功と幸せに関心を持て。
・仕事以外も含めて部下を人間として知るようにする。
・新人を温かく迎え入れて変化のストレスを減らす。
◉習慣4 くよくよするな。生産的で結果志向であれ。
・チームに達成して欲しいこと、及び、どうすれば部下が達成できるかに集中する。
・チームが優先順位を付けて働けるようにし、障害を取り除く意思決定をする。
◉習慣5 よいコミュニケーターであれ。そしてチームの声を聞け。
・コミュニケーションは双方向。聞くことと共有すること。
・全員参加の会議と具体的なチームのゴールを設定すること。
・オープンな対話を督励し、部下の質問と関心に耳を傾けること。
◉習慣6 部下のキャリアについてサポートせよ。
◉習慣7 明確なチームのビジョンと戦略を持て。
・不安と動揺の中でもチームのゴールと戦略にフォーカスする。
・ビジョン、ゴール、進め方の策定にチームを巻き込む。
◉習慣8 チームにアドバイスができるように技術的なスキルを磨け。
・必要なときはチームと一緒になって働く。
・仕事に関わる具体的なチャレンジを理解する。
こちらについて、詳しい情報は以下を参照してください。
Google re:Work - ガイド:優れたマネージャーの要件を特定する(https://rework.withgoogle.com/jp/guides/managers-identify-what-makes-a-great-manager/)
トップ オブ トップのエンジニアの会社において、「技術的なスキルを磨け」が8番目というのはなんとも興味深いです。
実際この「良いコーチであれ」について、元GoogleのCEO、経営トップであり、アルファベット社の会長でもあったエリックシュミットは、次のように語っています。
”People are not good at seeing themselves as others see them. A coach really, really, helps. Everyone needs coach.”
— 人は、「他人から見た自分」を想像することが苦手です。コーチは本当に、本当に、役に立ちます。誰もがコーチを必要としています。—
かのビル・ゲイツも2013年のTED talk で全く同じことを言っています。Feedbackの重要性を説く、という文脈で、”Everyone needs a coach” という発言からスタートしているのです。
そしてコロナ禍によって、コーチング市場は急拡大しました。
2019年時点の日本のコーチング市場規模は300億円(コーチ・エィ調べ)で、2015年には50億円市場だったとのことですから4年間で6倍に成長。アメリカでも、2022年のビジネスコーチングの市場規模は112億ドル≒1.3兆円(IBIS World調べ)と見込まれており、ビジネスコーチングだけでこの規模なので、パーソナルコーチングやライフコーチなど非ビジネス系のコーチングも含めると莫大な市場規模であることが想像できます。他にも、「アメリカでは大企業(フォーチュン500企業)の約70%がエグゼクティブ・コーチを採用(the Hay Group調べ)」というデータもあります。
背景として、キャリアの主体が「会社」だった時代から、「個人」に移っていること、コロナ禍によって日常で孤独を感じる人が増えたことが挙げられると考えます。

コーチングの必要性とその重要性は理解できました。そして、コーチングを身につけていくために、それが何かも理解できました。次は「それをどうやって1on1に取り込むか?」です。
まず、1on1でコーチングだけやっていても、1on1はうまくいきません。部下には指導やフィードバック(以下、FB)が必要だからです。これを理解した上で、1on1はどんなスキルを使って組み立てるべきかを説明します。1on1は次の3つの要素を明確に組み合わせてできるようになると、「部下から感謝される1on1ができている」と言える状態になります。

ティーチングはイメージができると思います。あなたがマネジャーや、マネジャーに挑戦する立場にいる時点で、新人や新卒のスタッフに教えられることはいくらでもあるはずだからです。深みがあるのが、図の下2つのコーチングとリーディングですリーディングは経験、知識、情報などを使って、対象者を導きたい方向に導いていくイメージです。例えば、売上が低迷しているチームで成績が伸びてこない営業メンバーに、「何が問題だと思う?」と聞いたところ、その部下が「売れる商品がありません」と言ってきたとします。あなたはなんと返答しますか?
まず、「売れる商品がない」ということは「起こっている問題を分析・言語化できていない」、ということがわかります。当たり前ですが、「商品はある」からです。これは、「問題の所在、あるいは原因を自分から遠くに置く」思考をする人に共通する思考パターンです。このパターンの思考法をする人はビジネスパーソンとしても、もちろんリーダーとしてもうまく機能しないことが多いです。問題が解決されていかないからです。これを本人にどう伝えるか?
仮に、自社のMVVに「主体性」を求めるようなVALUEがあった場合、MVV的にも「主体的に問題に取り組む」という方向に導く必要があります。
コーチングは基本的に「問いかけ」で進むので、仮にこの方向に持っていきたいと思っても、本人の気持ちがネガティブだったり、性質的に難しいといった場合、こちらが望ましいと考えるゴールにまったく辿り着かない、あるいは時間がかかるといったことが起きます。
コーチングだけで1on1を構成して問題になるのはここです。時間がかかるのです。また、仕事としてコーチングを受ける場合、その会社にとって望ましい行動をとってくれるような変化をコーチが促すことはありません。
上記から、「こういう思考をした方が良いよ」という方向に優しく導いていくのがリーディングという技術になります。Googleではこの技術を含めて「良いコーチ」としていると思います。多様な視点を提供し、合理的に、しかし説得的でなく、その会社のMVVに合致した思考に導いていく。これはすぐにできるかというと難しいです。1on1を重ね、経験を積み、自分の経験から学びを言語化し、本を読み、自己認識を深め、多様な視点から導いていくことになります。でも、継続していくと必ずパターンが見えてきます。
ここではリーディングついて詳しく触れず、コーチングを1on1に取り入れるところに集中します。まずはティーチングとコーチングの違いを明確に区別し、必要に応じてどちらの手段が最適なシーンかを判断しながら使い分けることを意識してできるようにしていきましょう。
ちなみにコーチング と ティーチング/リーディング の最大の違いは、「横に座れること」です。
「コーチングとティーチングとは何が違うのか?」という質問がありますが、ティーチングは「教える」ものです。「知識や情報を伝える」ということももちろんですが、経験も同じです。あるチームのマネジャーは、マネジャーになる過程でそのチームのメンバーレイヤーの人がこれから経験するであろうことのほとんどを経験したことがあると言えます。例えば、部下の誰かが間違った行動をしていると、それがその先どうなるかがわかるのです。それを、先回りして教えるのもティーチングです。
もう一つのよくある質問に「カウンセリングとは何が違うのか?」があります。カウンセリングとは、専門知識やスキルを持ったカウンセラーとの対話によって、クライアント(相談者)が抱える悩みや困りごとを解決できるよう導くプロセスのことです。
双方の違いを厳密に定義できるわけではないですが、対象者の「マイナス」を0に近づけていくイメージがカウンセリングで、0の状態から「プラス」を上げていくイメージがコーチングとすると理解しやすいです。
ちなみに、自分で経験しないと理解しにくいのが「ミスや失敗」ですので、マネジャーは常に「教えるべきか、教えずに敢えて経験させるべきか」という選択に悩みます。
ここまでで、コーチングを取り入れてどう1on1を構成するかが理解できました。最後に、1on1に取り入れるコーチングスキルの基礎を「ざっくり言うとこう」という形でお伝えして次の章に移りたいと思います。
1on1において取り入れたいコーチングスキルは「信頼関係の構築スキル」と「目標設計と達成のためのサポート(伴走)スキル」です。たった、この2つです。でも、「基礎にして、奥義」と言えるほど、有効性と同時に深みがあるものでもあります。
まず、信頼関係の構築スキルが身につけられれば、「1on1にコーチングを取り込めている」は70%できていると言える状態になります。残りの30%が「目標設計と達成のためのサポート(伴走)」です。数字は感覚的なものです。でも、ここを極めて行ったらこれで「私はコーチングができる」と言って良い状態だと思うぐらい有効性が高いと考えています。では、「信頼関係が構築できている」とはどういう状態か、ですが、
「チームメンバーとの1on1がうまくいかず、1on1の時間が苦痛だ」
「前は仲が良かったが、関係が崩れた瞬間、仲が良かった時に話していた情報を逆手に取られ、窮地に追いやられてしまった」
「何気なくいった一言が気に食わなかったらしく、いつの間にか距離を取られるようになってしまった」
こういった問題はすべて、信頼関係が構築できていれば起きません。逆に信頼関係の構築スキルが上がれば、メンバーとの関係がうまく行くようになり、メンバーとの関係がうまく行くようになれば、仕事は必ずうまく行くようになります。そこまで来ると、副業でお客さんをとってコーチングをすることもできるようになります。
コーチングを勉強すると、細かい理論やテクニック、フレームワークなどの情報が膨大に出てきます。それらを片っ端から勉強しても、実践に活かすことはほぼできません。泳ぎ方の本を読んで、海に飛び込むのと同じです。ではどうしたら良いか。まずは、「どうやったら信頼関係の構築ができるか」に集中して実践することがベストです。経験や情報、理論やスキルをすべてこの「信頼関係の構築」に集約します。あれもこれもではなく、ただこの一点に集中することで、コーチングの土台がつくれるようになるのです。コーチングの本やテキストを開けばすぐに、
・相手の存在を認める承認スキル
・相手の心を開く質問スキル
・相手の話を徹底的に聞くスキル
・相手の話を促しながら聞くスキル
といったスキルが並びますが、これらは全て信頼関係を構築するために取る手段だ、という整理が必要です。そこに集中すれば、コーチングが必ずうまく行くようになります。信頼関係の構築は全てのレイヤーで活かせるスキルなので、もう少しだけ踏み込んでおきます。
まず、コーチングでは信頼関係を「ラポール」と呼びます。ラポールを形成する、といった使い方ですが、よく「橋をかける」というメタファーで表現されます。「信頼関係(ラポール)が構築できている」と言える状態がどう言う状態かというと、
・部下のモチベーションを気にしなくて良い(仕事を任せられる)
・その人が何をやっているか、プロセスを監視しなくて良い
・「好かれているな」と感じるシーンがある
・問題を一緒に解決してくれる
・その人がまた他の人との信頼を繋いでくれる(チームがうまくいく)
・穿った見方をされずないので、ネガティブFBができる
・ネガティブFBによって成長が加速し、チームに良い影響が起きる
といった状態です。
信頼関係ができているチームは、結果「エンゲージメントが高い」と言える状態になっており、退職の心配をせず、自律的に問題を解決してくれるチームになっています。
逆に、信頼関係(ラポール)の構築ができていない状態とはどんな状態かというと、
・部下のモチベーションを気にして、仕事をお願いしてやってもらっている
・本来であればやってほしいことを、自分でやってしまうことがある
・嫌われているとは思わないが、好かれているな、と感じることはほぼない
・メンバーの行動に対し、「なんで?」と疑問に思うことがある
・何を言っても穿った見方をされている感じがする
・裏でなにを言われているかわからない、と思うことがある
・プロセスを監視し、マイクロマネジメントをやっている
・その人を中心に仲間を作られている感じがする
といった状態です。
そしてこの状態を放置していると、メンバーから「望ましくない退職」をする人が出てきます。
◉望ましくない退職に至ったメンバーに共通して見られる行動パターン
1. 仕事がうまくいかない
2.言い訳・自己欺瞞を始める(被害者化)
3.攻撃できる対象を探す
4.仲間探し・仲間づくりを始める(加害者化)
5.加害者となってその場を去る(望ましくない退職)
これを起こさない環境づくりにおいて、何より信頼関係の構築が機能します。では、信頼関係はどうやったら築けるのでしょうか?信頼関係の構築ステップには色々な見解がありますが、私は以下のステップを説明しています。

大きく分けると「理解→親和→信用→信頼」の4つのステップです。
それぞれのステップで「できている」と言えるゴールは以下の通りです。
<理解の段階のゴール>
お互いの人となりをよく理解している
<親和の段階のゴール>
仲が良いと言える(相手の特性を理解した上で尊重できている)
<信用の段階のゴール>
相互に業務的なFBが率直にできるようになっている
<信頼の段階のゴール>
仕事に必要な情報としてオープンにできない情報がない
上記のうち、私は「親和」の段階が最も重要だと考えています。言い換えると「仲良くなる」です。「信用」のステップに進む上でも「親和」ができていないと進まないのは無論ですが、より深く仲良くなってから「信用」を重ねるとより強い「信頼関係」ができます。
基本的に「仲良くなる」には時間がかかるものです。それは間違いありませんが、急速に「親和」を作るテクニックがあります。「共通点を持つ」です。言い方を変えると、「同じをつくる」です。例えば、初めて会った人でも「出身地が同じだった」、「出身大学が同じだった」としたらどうなるでしょうか。なぜだか一瞬にして溶け合った感じになります。でも、こういった偶然は偶然なので、必然にすることはできません。でも、「同じ」は簡単につくれます。
「共感する」です。
実はこの本の中で一番言いたかったことの一つがこれです。ベンチャー企業2社のグロースとIPOという一つのゴールを経験して、「経営において共感ほど大事なものはない」という結論に至りました。特に、従業員が30人を超えた段階からはこれが重要です。逆にこれを実践すれば50人の壁は問題にならないといえます。ライトワークスに入社してから上場までの5年間は、クオン時代に触れた野中郁次郎先生の「共感経営」の導入と実践だったと言っても良いかもしれません。
具体的には、とてもシンプルなのですが、コミュニケーションの最初に必ず共感を持ってくるように訓練します。
例えば、
「雨の日って頭痛になりやすいんですよね。」
と言われたら、なんと答えますか?
これを研修で聞くとみなさん必ず「大丈夫ですか?と聞きます」という答えを返してきます。でも、嘘なんです。日常では全然やっていないんです。やれていないんです。経験的にも、周りを見ていても、大抵よくても「そうなんだね」です。仕事中だと最悪スルーということも全然あります。集中しているのですから必ずしもスルーした人が悪いということではありません。それが当たり前になっていると、言う側もそもそもこういうペインを共有すらしません。
では、共感に重きを置くチームでこういった発言があった場合どういう反応をするか。これを言われたら言った人の顔を見て、「そうなんだね、頭痛はしんどいね。」という反応をします。さらに、「そうすると雨の日が憂鬱になっちゃうね。」を付けたりします。たったこれだけで良いのです。何が良いか。「共感」が伝わるんです。こんなシンプルなことですが、信頼が流通する会社にするにはとても重要なことです。何を言われてもまず、「共感」を示してください。共感すること、思いを寄せることで、全く同じにはならないですが、近しい心の状態、つまり「同じ」をつくることができる、ということです。
会議で誰かが「こんな新しい情報が入ったよ!」と言ってきた、営業が「失注した」と報告してきた、家族が「学校でこんなことを言われた」と言ってきた。
どんな時でも、まず共感からスタートしてください。そんな簡単な寄り添いでも、この後の対話や中長期的な関係は劇的に変化します。反対意見を述べる時でも、不快を感じた時でも、まず「共感」からスタートしてください。これを私は「思いやりを流通させよう」という表現で、執拗に伝えていました。特に、体調に対する気遣いは有効です。よく観察していないとできないからです。
NHKスペシャルの「ヒューマン なぜヒトは人間になれたのか」というシリーズは、この「思いやりを向ける」ことの重要性を説明しています。脳の解剖学的構造から「他者との感情的な結びつき」が、私たちの生存にとってなくてはならないことを明らかにしました。仲間を気遣うことで快感を生じさせる「オキシトシン受容体」は古くから人間の脳にあったということがわかっています。つまり、私たちは太古の昔から人間性の一部として「思いやり」を必要としてきた、ということが分かります。
人類が四足歩行から二足歩行に変化したことで、骨盤は内臓を支える役割を担うことになり、結果、産道が狭くなりました。すると、赤ちゃんは未熟で産まれざるを得なくなったわけです。つまり、人類は赤ちゃんを誰かの助けなくして育てられなくなったのです。その結果、脳は「誰かに思いやりを向けるとオキシトシンを出す」という変化を遂げました。思いやりを向けられた方だけではなく、思いやりを向けた方の脳に報酬が働く、ということです。人類が持っている脳の機能の凄まじさを思います。
さらに、オキシトシンには記憶力を向上させる働きがあることがわかっています。
・オキシトシンの分泌が活発になっている授乳中の母親について、新しいことを覚える力である「記銘力」が明らかに向上することが判明した
・妊娠したことのないメスのマウスの脳にオキシトシンを注射し、エサを隠した迷路に入れた結果、注射前より早く、エサにたどり着く順路を覚えた
出典:中野信子 『脳科学からみた「祈り」』(潮出版)
愛情ホルモンには、脳を活性化させるというメリットがあるということです。良いことづくしです。
さらに、前出のポール・ザック博士は「共感とオキシトシン」の関係について、こんな実験をしています。
145人の被験者を募り、採血して基準値を確認してから以下の二つのグループに分け、それぞれ別の100秒間のビデオを見せる。
Aグループ:父と幼い息子が動物園で幸せそうなひと時を過ごしている映像
Bグループ:脳腫瘍の息子との絆について涙を堪えながら語る父親の映像
ビデオを見せた直後に、全員再び採血すると、Aバーションを見た人は血中のオキシトシンレベルが20%も下がり、Bバーションを見た人は基準値から47%も上がった。
「実際目の前にいなくても、人は映像として映し出されたストーリーを通して登場人物に”共感”を示し、オキシトシンが分泌された」ということです。
参照:『経済は「競争」では繁栄しない 信頼ホルモン「オキシトシン」が解き明かす愛と共感の神経経済学』
こういった説明から、特にマネジャー陣には管轄の部下に対する観察と、観察を踏まえた思いやりを向けること、共感することの重要性を伝えていました。
ちなみに、「親和」がつくれない人に共通するパターンは、「自分、あるいは自分が取る言動に対して、相手がどう思っているかを客観的に評価することができない」です。このパターンが言語化できたら、具体的な場面でこういうふうに思いやりを向けて欲しいということを繰り返し伝えていました。
特に、前述の通り「”相手の体調に対して関心を持つ” を if then planning(習慣化プログラム※)を使って習慣化させる」は有効でした。
※if then planningについてここでは詳しく触れないですが、高い有効性が確認されていることからもコーチングではとてもよく使うフレームワークの一つですので、関心のがる方はぜひ調べてみてください
続いて、「1on1にコーチングを取り込めている」に必要なもう一つの「目標設計と達成のためのサポート(伴走)」ですが、こちらは既に世の中にたくさんの型があります。これが必要なんだと理解していただけたら、以下のような型を使って1on1で実行してみてください。
・GROWモデル
・SMARTゴール
・WOOP
・will / can / must
・Time Line
これらはどれも優れたフレームワークですが、私が1on1で特によく使うのがGROWモデルです。GROWモデルについては、フレームワークですからネットを調べれば数多と解説が出てきますので、そちらを参考に、1on1の中で息を吸うようにできるようになってください。まずはこの一つを極めればそれで十分です。
ここまで1on1にコーチングを取り入れる話をしてきましたが、私が研修で配布している1on1の概要をまとめたeBookを置いておきますので、もし関心がある方がいらっしゃったらぜひこちらを参考にしてみていただけたらと思います。

ダウンロードフォーム:https://share.hsforms.com/2gKSekkTpTsSn1H_j_8YoYQrq5b3
6.販売力を強化する
ここまでが着手した改革の04.育成を強化する(マネージャー育成)でした。
01. リード獲得を安定化する
02. 組織文化を変える
03. 生産性を上げる
04. 育成を強化する(マネージャー育成)
05. 販売力を強化する
ここから最後の販売力の強化に入っていきます。
ここまでで、ターゲットリードの獲得が安定し始め、MVVの刷新によって僕らが何を果たすのか、どこへ向かうのかが明らかになり、生産性の高い組織運営が実現し始め、その成長(変化)に耐えられるマインドや文化を形成し、風土にしていくマネジャーの育成が動き出しています。
良いリードが入ってきているので、受注も結果としてどんどん伸びてきています。この勢いを買って競合に打ち勝っていく「強い営業組織の構築」を押し進めていきます。「売れる仕組み」の構築です。
まず、製品のタグラインを変えました。当時のライトワークスの主力製品であるCAREERSHIPはエンタープライズ向けに耐えられる強いシステムでした。このシステムについて、開発や営業に「その特徴を一言で言うと何か」と問うと、全員口を揃えて「痒いところに手が届く」という回答が返ってきました。確かに。それは良いシステムです。日本のエンタープライズ企業の人材開発チームの細かい要望に網羅的に応えられるというのは同社の独自価値と言える強みでした。これをもう少し体温が上がる言葉で表現できないか。ちゃんとお金の匂いや相手が享受できるメリットを想像させる言葉に。そこで私は「痒い所に手が届く CAREERSHIP」から、「エンタープライズ向けNo.1のCAREERSHIP」に変えました。
この段階では誰かのお墨付きをもらえているわけではなかったのですが、競合調査を進めた結果、そう言える感覚がありました。何より、「エンタープライズ向けNo.1」ということで、セールスの現場での言動が変わり、アウトプットが変わり、姿勢が変わりと、その変化は徐々にサービスチームや開発チームに届き、「エンタープライズ向けでNo.1のシステムなんだ」という自負が社内に広がっていきました。結果、本当に2023年に富士キメラ総研から「クラウド型LMS市場売上シェアNo.1」のお墨付きをいただきました。お金は払っていません。これは上場した時と同じぐらい喜ばしいものでした。
時間軸を戻して、売れる仕組みの構築にいきます。仕組みの構築について、色々手段はありますが、以下3つを行いました。
1.経営理念・MVVと事業戦略・営業戦略の紐付け
2.リスト管理
3.売れる営業がやっている行動の言語化とスキルマップの作成・運用
上記について説明する前に確認したいのですが、みなさんは営業に対してこういうことを思っていませんか?
「ほんとはもっとストレッチした目標を持って欲しい(でも言えない・・・)」
結果、以下のような状況がよく見られます。
・通例的に目標を立て、個別の数字とチームの数字を出し、営業会議や経営会議で報告する
・売れる人は売れるが、売れない人は売れない
・営業マネジャーは売れないメンバーの育成の仕方がわからない
この状況に対し、組織改革によってグロースマインドセットになっている営業チームでは、
・立てた経営理念やMVVから演繹して事業戦略を立てる
・事業戦略から部門別の目標を立てて、目標達成のためのフォーミュラを明らかにする
・IS / FS / CSそれぞれを連動させたチームごとのKPIを設定する
・チームのKPIに応じて個人のKPIを設定し、管理者がアクションを管理する
が実行可能になります。
目標達成のフォーミュラとは、営業戦略のことであり、営業戦略が固まっている状態を「経営理念・MVVに紐づいた中期経営計画・年次計画に沿った内容で、全体の売上目標に対する『確定済売上 / 既存アップセル・クロスセル / 新規受注の比率』が定まっている状態」とします。その比率には、なぜその比率であれば目標達成ができるのかという理由が必ず存在し、その理由を組み立てることが、すなわち営業戦略の策定といえます。
営業戦略は、上記に加え、チームのリソースに対する計画や育成、サービス開発などの要素が入ってきます。これに対し、経営層はマネジャーが、「メンバー一人ひとりが、自らのアクションやプロジェクトが会社の経営理念や社会にどう紐づいて説明できるようにする。」マネジメントができるよう支援します。
これが1の「経営理念・MVVと事業戦略・営業戦略の紐付け」です。
続いて2の「リスト管理」ですが、これは営業それぞれが担当する案件をリストアップし、それぞれの案件に対してどんなアクションを取るかを明らかにし、そのアクションの進捗を管理していくという、いわゆるセールスフォース社が広めた営業のプロセス管理です。この精度を上げることに腐心しました。特に、内製でSFAツールをこまめに改修できる状態を構築することに拘り、実現していました。ベンチャー企業なので、サービス開発は常に行い、新しい商品をつくってマーケットに投入し、結果を見てまた製品に反映し、というサイクルを高速化していきたかったからです。
続いて3の「売れる営業がやっている行動の言語化とスキルマップの作成・運用」ですが、こちらは人材開発会社らしく、当時まだ新しかったスキルマップの作成に取り組み、運用していました。営業チームにおけるスキルマップは営業のイネーブルメントを目的とし、トップセールスが持っている知識やスキルを言語化、マッピングしたものです。マッピングといっても、エクセルで一覧にするような見た目の極めてシンプルなものです。マトリックスを組んでマッピングするパターンもありますが、1職種の場合は大分類を3~4つにし、それぞれに項目を紐づけるシンプルなものにするもののほうが運用しやすいです。
また、試行錯誤の結果、今はスキルマップの大項目は「知識・スキル・経験」の3つに分類する形が良いと思っています。これは営業に限りません。またこれを基本フォーマットとして、「ルール」や「習慣」といった独自の項目を追加することももちろん可能です。
そしてこの大項目それぞれに対して30~40個の項目が紐づきます。例えば、「知識」であれば、「 製品/商品:自社製品、他社製品の仕様と特徴を正しく理解している」といった項目を設定します。「スキル」であれば、 「コミュニケーション力:相手によって手法を変えながら適切な上級判断で意思疎通が行える」といった文言で、「経験」であれば、「 クロージング:意思決定における懸念要素の潰しこみを完遂し、契約書の締結までのクロージング実績がある」といった感じです。(あくまでサンプルです)
これら100~120ぐらいの項目に対し、4段階や6段階のセルフエフィカシー方式(自己採点式)で点数をつけていきます。仮に4段階だったとしたら、
1.知らない
2.理解している
3.継続的に実践できている
4.行動に落とし込ませるレベルで他者に伝えることができる
といった設定にし、点数を聞いていきます。
これを入社時点、3ヶ月後、半年後、1年後といったペースで実施し、その変化量を見て問題点を探っていく、という運用です。母集団が少ないので確実にそうとはいえないですが、数十名規模の実績としては、この変化量と販売実績に相関関係がありそうと言える印象でした。つまり、「早くこなしている人ほど販売実績が早く上がる」という結果が出ていました。
こういった販売力強化の仕組み化に加えて、特に営業チームは「教える」、「育てる」文化の徹底を図っていきました。営業は売れる人ほど評価されるので、販売手法やノウハウを外に出さない、個人商店型の組織になってもおかしくありません。むしろそれが自然と言えるはずです。ということは、それを踏まえた上で「うまく行ったこと・いかなかったこと」を積極的に公開してもらったり、定期的な営業勉強会を開催してもらったりと、「チームで勝つ」を徹底していました。
加えて、その姿勢を経営層が示すべく、言葉のちからを磨く研修プログラムを作ったり、大型案件に営業に同行することがあったら、御礼メールや顧客からの問い合わせに対する回答メールなど、細かいところまで確認をもらい、案件の受注可能性の最大化にコミットしていました。
また、その解像度のアクションにタッチすることで、営業の現場で起こっている問題や解決すべき課題が言語化できるので、そのための教育プログラムに昇華し、オンボーディングの教育コンテンツに反映するといったことをやっていました。
そういった現場に入り込んで見つけた課題から、全体に展開した教育コンテンツのサンプルをご紹介します。コミュニケーションを「縦に振る・横に振る」テクニックです。
まず、コーチングの研修ではコミュニケーションを「縦に振る」トレーニングをします。まず、以下はコミュニケーションを「横に振っている」パターンです。
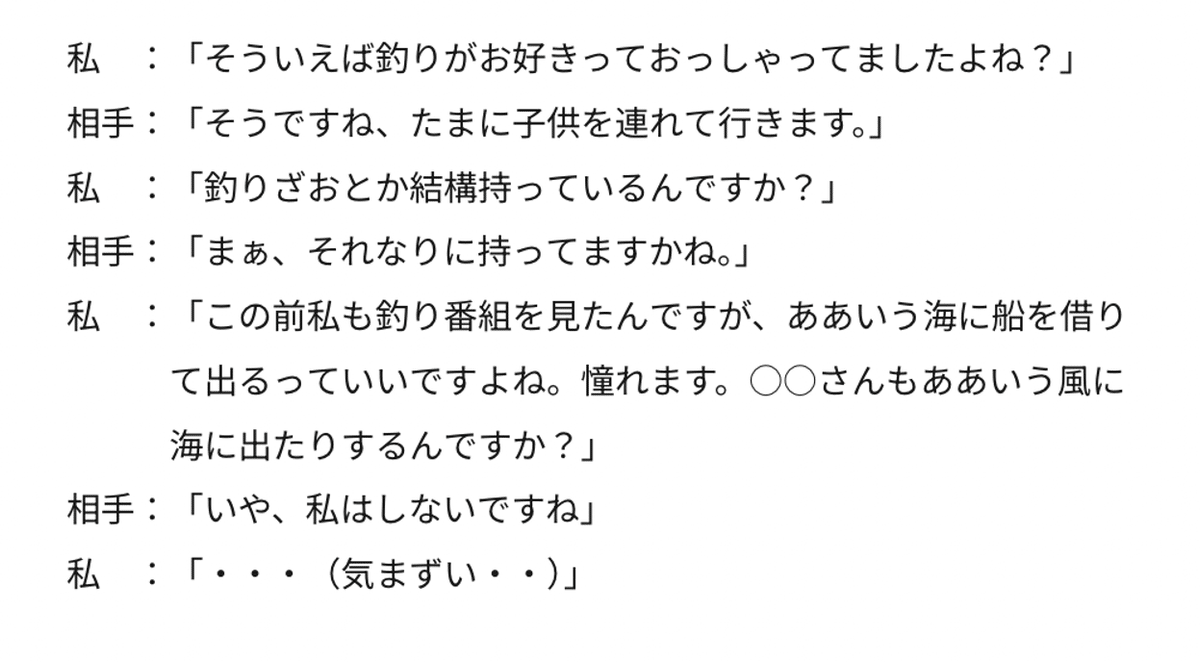
これに対し、コミュニケーション縦に振っているパターンが以下です。

どこが「縦」かというと以下です。

縦に振るほうがコミュニケーションは段違いに盛り上がります。コーチングにおいてはこの縦に振っていくスキルを磨きます。その方が相手は「話していて気持ちいい」と感じるからです。ということは、コミュニケーションがうまくいかないと感じるパターンの多くは(ほとんどの場合それを自覚できないのですが)、自分の関心に合わせて横に振ってしまっている、ということになります。
もうお分かりかと思いますが、営業はこの「横振りの極み」と理解できます。自分の都合の良い方、「売りたい方」へ話を振っていく。じゃないと話が進みません。ということは、気がつかないうちに、相手が気持ちよいと感じるような横振りができるようになれば良い、ということになります。売れる営業はこれをやっているのです。
これをトレーニングにしました。具体的には「なんでもLMS」といっていたのですが、お客さんに何を言われてもLMSの販売に繋げるトレーニングです。
例えば、「虫歯が痛いんですよね。」「あ、それLMS入れたほうが良いですよ。」です。
そんな馬鹿なと思われると思いますが、そんな馬鹿なことができるから売れる営業になります。上記については、なんでも良いのですが、例えばこんなやり取りです。相手は大手企業の人材開発部の責任者です。

あくまでサンプルですが、こういったトレーニングを遊び感覚でやっていくイメージです。繰り返しになりますが、特に営業は売れるスキルや情報をクローズにしがちなので、徹底して「教える」、「育てる」を根付かせなければならない、ということです。
前述の通り、マネジャーに「部下を育ててくれ」といっても、マネジャーにとっては「本気で部下を育てて、その対象が成長したら自分が追い抜かれるのではないか」という恐怖心があります。マズローの5段階欲求をなぞらえるなら生存に関わる根源的な恐怖心です。それを押さえて部下を育ててもらわなければならないから難しい、という前提を忘れてはなりません。
世界最大の複合企業と言われるGE(ジェネラル・エレクトリック)は企業内研修の頂点とも言われる幹部教育を行っています。その幹部向けの研修の中でもコーチングは重要なスキルとして教えられているそうです。そしてそもそもこの幹部向けの研修に呼ばれる社員はハイパフォーマーかつ、「部下を育てる力」があるか否かが重要とされるそうです。
これは人材開発の聖地と言われるGEのクロトンビルで、日本人として唯一リーダーシップ研修を任された田口 力(たぐち ちから)さんの「世界基準の『部下の育て方』」という書籍で紹介されています。これはマネジャー向けの必読書の一つに設定して良いものと思っています。
さらに、こちらも前述しましたが、コンピテンシーの最上位項目を、それぞれの項目で「部下を育成できる」と言ったものにすることは極めて有用性が高いです。こういった制度面からも支援していく必要がある、ということです。
7.想定外だったこと
ここまで読んでいただいて、改革は順調に進んだように感じられると思いますが、当然ながらハレーションもありました。何かを変える、ましてやそれが長い時間をかけて定着した文化や風土を変えるとなると、当然ながらその定着度合いに応じて強い反発があるものです。これはどんな環境でも同じだと思います。今となったら予測や準備ができますし、それを前提として引き受けることも可能ですが、当時は未熟でしたので、「この会社を良くしたい。心理的安全性をあげて、みんなが楽しく働ける会社にしたい。」という思いがあれば問題は起こらないと思っていました。これを書いているのも、「そんな当時の自分に贈る」という気持ちがあります。同じようなチャレンジをしている人、これからしようとしている人は必ずいるはずです。
望ましくない退職に至ったメンバーに共通してみられる行動パターンを前述しましたが、人は「自分は評価されていない」と思い込むと、仲間を増やして攻撃するような行動をとります。これはどんな環境でも共通して起こるパターンだと理解しています。そしてその矛先が自分に向かうこともあるわけです。私の基本スタンスは「今はできていないだけで、成長する気概・欲求さえあれば育てられる」なので、できていないことを問うたことはないですし、こういうプログラムで育てていこうというプランが頭にあるような状態でも起こります。メンバーを思い、チームを思い、懸命に改革を進めていても、攻撃対象になることは十分あり得るわけです。
ではどうするか。
先ほどの「望ましくない退職に至ったメンバーに共通して見られる行動パターン」を再掲します。
1. 仕事がうまくいかない
2.言い訳・自己欺瞞を始める(被害者化)
3.攻撃できる対象を探す
4.仲間探し・仲間づくりを始める(加害者化)
5.加害者となってその場を去る(望ましくない退職)
このパターンの1の段階から、対話を手厚くする必要があります。このタイミングで、改めて前述のコーチングを取り入れた1on1に徹底して取り組んでください。その上で、「問題が起きている」ということをお互いの共通理解とし、「その解決手段を一緒に考える」というアクションを起こします。こうすることで、信頼関係が生まれます。
そして冷静と情熱の間ではないですが、同時に前述の行動パターンの4以降に入っていった場合を想定し、エビデンスを残しておくという行動をしなくてはなりません。
・こういう問題があるという合意をし、
・その改善のための行動をこういうふうに取るという合意をした
と言ったエビデンスを残していきます。
信頼関係を前提としているので、とても難しい作業であることは間違いありません。私も完全にうまくできるとは言い切れない難しさがあります。いつも拠り所にしていたのは、「良い会社を作りたいという思いに一切の偽りも揺るぎもない」という覚悟でした。それでも、問題は起きるものですし、起これば辛いものでもあります。
だからこそ、こう言ったハレーションを「現場任せにしては駄目だ」と、全ての経営者に伝えたいです。でも、本当に多くの経営者が現場に任せきり、あるいはそうしたいと思っていると思います。これがどんな環境にも共通して起こるパターンだとするなら、経営陣こそこの問題に全力で取り組む姿勢を見せるべきです。NETFLIXのCulture Deckは正にそれだと思います。
青臭いことを言っていると思いますし、解決策もいろいろですし、解雇ができない日本においては、決定的な正解というものは存在しないと思いますが、私にとっては大切なスタンスです。
最後に、チーム単位、会社単位で、文化や風土を変えるシーンに何度かで関わらせていただく中で、そう言った変化を起こす中に以下のフォーミュラ(方程式)があることを発見しました。
「チームの文化を変えるには、変える先の文化に合致する・賛同する社員がチームを構成する人数の半数を越えなければ、チームは変わらない。」
「関係が極度に悪化した人でも、共感を示すことで関係は回復しうる。」
経営層はこれを前提として対策や制度設計を事前にしておくのが良いものと考えます。

8.いま何を思うかと、これからやりたいこと
まったく売れなかった「明太子」がニューヨークでバカ売れした。なぜ売れたか。ネーミングを変えた。元々は「シーズンド・カッド・ロウ(味付けタラの卵)」という名前をつけていたが、これを変えた。何に変えたか?
『HAKATA Spicy Caviar』
たったこれだけで爆発的ヒットを記録した。なんだこれはお酒に合うじゃないかと、よく冷えたシャンパンと博多スパイシーキャビアで楽しむ人々であふれるようになった。
参照:『コピーライターじゃなくても知っておきたい 心をつかむ超言葉術』
「言葉の力」ってすごいなと思います。
3章に書いたこちらは、こんな「言葉の力に対するリスペクト」から来ているものです。
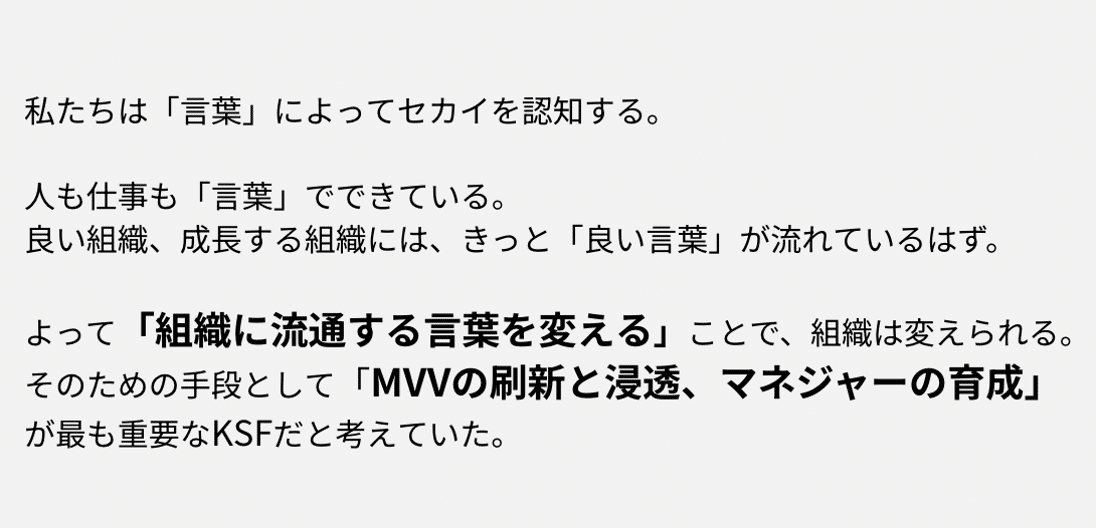
当たり前のことを言いますが、私が直面したすべての問題を解決してくれたのが「言葉」でした。「問題の言語化」、「キャッチコピー」、「マネジャー育成」、「営業」、「採用」、そして「信頼関係の構築」。「良いチームができた」と思えるのも、言葉の力のおかげです。
売上が上がらない、採用がうまくいかない、人が辞める。これらはどの組織にでもある問題です。これに対して、外から何かを買ってきて解決するとか、お金を払って解決することを考える前に、いま既に中にあるものを「言葉によって整える」だけで、チーム・組織は前に進みます。
「魔法の杖はない」ので、
・面倒なことと丁寧に向き合う
・試行回数を増やす
・それをやりきる
・これらを従業員が進んでやってくれる様にする
を愚直にやることです。これで上場はできました。これがここで伝えたかった「考え方」です。
上場を達成して少しゆっくりしようか、なんて思っていたら、ある先輩からこんなことを言われました。
「お前は足を止めるなよ。」
確かに。ベンチャー企業の2社のグロースと、1社のIPOが経験できたことは本当に幸運なことだったと思います。この経験を社会に繋げるにはどうしたら良いか。
いま思うことは2つです。
ここに書いたスキームを導入したら、もっと成長できる会社が他にもあるのではないか。自分がいる会社を上場させるのではなく、このスキームを通して多くの会社のグロース支援ができるのではないか。そういう支援をしたい。
もう1つは、「事業開発の言語化」です。
これも既知の事実としていろんなところで言われていますが、マーケットの大きさはその会社の成長にとって極めてクリティカルな問題だと痛感しています。ベンチャー企業に入ってこのかた20年間、「マーケットはつくれる」と信じてやってました。それはきっと可能なのだと思います。事例も枚挙にいとまがありません。でも、それはもう少し先のチャレンジで良いのかもしれないと思うようになりました。この20年の経験を持って大きな海で勝負してみたい。でも、遅いかもしれない。大きなマーケットのある業界に何十年もいて、そこにある隙間を見つけて起業するというパターンではなく、コネもネタもない中で事業を創造する、ということだから。
やってきた人はたくさんいると思いますが、私なりにこの条件で「事業開発のモデリング」をやってみたいと思っています。これまでのビジネス人生を通して得られた経験や知識を使って新しく事業を起こし、願わくば100億の売上をつくれる企業を起こしたい。それが10社作れたら1,000億です。そんな世界を見て、事業開発を言語化できたら、勇気も持って起業に挑む人たちが増えるのではないか。
誰でも、事業を成功させられる世界にはならないけど、「こうやったらうまくいく可能性が上がる」という方程式は見つかるはず。PMFは十分わかっていて、それでも千三つの世界なので、これをどうにかできないかと思っています。次の10年はこの事業開発のモデリングにチャレンジします。
「考え方」は前述のとおりです。愚直に、
・安定したリード獲得の仕組みができて、「いい会社」と言われる組織づくりができら、売上が上がらないはずがない
に、大きなマーケットで取り組んでみたいと思っています。この試みに賛同してくれる仲間が集まり、新しい航海を楽しむ世界線を夢見て。
おわりに
最後に、本書は私の経験を私のメガネを通して書いていますが、当然ながら私一人で成し得たものではありませんし、アウトプットについてはそれぞれの担当者が相応の覚悟を持って取り組んでくれたものです。ここに書いたことを一緒に進めてくれた全ての関係者に心から感謝をお伝えします。ありがとうございました。願わくば、皆さんと成したことをここに表現することで、誰かの新しい何かにつながればと思います。
私はクオン時代に、「この世の中に、真に『オリジナル』と呼べるものはない」と教わりました。いま世の中にある全ては、誰かの仕事の結果の上にあり、アイディアと呼べるものも、これまであった何かと何かを組み合わせて、その組み合わせが新しいにすぎないと。iPhoneを初めて世に出した時、ジョブズはプレゼンテーションの中で、「これは電話とiPodがくっついたものだ」と説明していました。その電話も、iPodも、その前にそこにつながるプロダクトがありました。よって、「先人達へのリスペクトを切らさず、新しかろうものにチャレンジしていくことが大事」と教わりました。
私がやったことはその前のクオンで学んだことがほとんどですし、そのクオンにあったものも、アカデミアや広告業界、マーケティング業界にあった知見が折り重なった上にありました。重要なのは「何かをかたちにしよう」、「問題だと思うことがあったら命をかけてそれに取り組もう」という覚悟なのだと思います。「その覚悟を誰が持っているか」だろうと。
人も仕事も言葉でできている。
同じ仕事をしていても、同じ量をこなしていても、結果が異なるのはなぜか。
選ぶ言葉、コミュニケーションが違うから。その違いは小さくても、その積み重ねの先に大きな結果の違いが生まれる。
では、その差を生むものは何か?どこからくるのか。
私はそれを「覚悟」だと思っています。
私ひとりでは成し得なかったことしかないですが、でも私にしかなかった覚悟はありました。
この覚悟を、また新しい形で世の中に流通させていけたらと思います。
ここまで長いことお付き合いいただいて本当にありがとうございました。前述の通り、私はこの「共感」をベースとしたチーム・組織づくりに大きな可能性を感じています。でも、事業規模や業界、地域によってこれがうまく機能するのか、まだまだ分からないことだらけです。もっと大きな会社だったらどうなのだろう、BtoCだったらどうなのだろう、地方創生となったらどうなるのだろう、などなど知りたいことがたくさんあります。なので、私がいた領域もそうじゃない領域でも、同じような状況に困っていたり、チャレンジしたいと思っていたりと言った状況があればぜひ教えていただきたいのです。お礼として、私にできる範囲で無料でのご相談対応やマネジャー育成に関する研修をご提供したいと考えています。
以下にFacebookのURLとメールアドレスを置いておきますので、少しでも関心がある方はぜひ気軽にご連絡いただけたらと思います。
Facebookはこちら
無料のご相談はこちら
メールはこちら
saito@sbd.company
参考文献・参考サイト
Google. “Identify what makes a great manager”. Google re:Work - Guides: Identify what makes a great manager.
https://rework.withgoogle.com/en/guides/managers-identify-what-makes-a-great-manager/
Netflix. “Netflix Culture — The Best Work of Our Lives”. Netflix Jobs.
パーソル総合研究所. ”マネジメントの取り組み・実態調査レポート【うまくいく組織の特徴とは】”
https://www.persol-group.co.jp/service/business/library/3440/
ライトワークス. “企業理念”. 企業理念 | 株式会社ライトワークス. https://www.lightworks.co.jp/company/vision
ライトワークス. “CSR”. CSR | 株式会社ライトワークス. https://www.lightworks.co.jp/company/vision
ライトワークス. “LIGHTBOAT”. トップページ - LIGHTBOAT. https://lightboat.lightworks.co.jp/
upwork研究所. Freelance Forward 2023. https://www.upwork.com/research/freelance-forward-2023-research-report
レバテックフリーランス.https://freelance.levtech.jp/guide/detail/1087/
【1時間で分かる】ベンチャー企業上場の教科書
著者・発行:齊藤 心吾
Copyright ©︎ 2024 Shingo Saito All rights reserved.
本作品の全部または一部を無断で複製、転載、改竄、公衆送信すること、および有償無償にかかわらず、本データを第三者に譲渡することを禁じます。
発行日:2024年 12月 6日
