
#毎月短歌11(AI評)
第11回毎月短歌に投稿した短歌(現代口語短歌)のAI評です。
記事に引用するのは自作品のみですが、WEB投稿参加作品のうち、文語・旧仮名部門短歌と連作部門以外の現代口語短歌すべてにAI評者のコメントがあります(efさん全面協力)。
今回のAI選者は3名+要約総評担当1名
① Umievo-itr012-Gleipnir-7B
(Llama-3-ELYZA-JP-8B-GGUFが生成したコメント)
② Oumuamua-7b-instruct-GGUF
(Oumuamua-7b-instruct-GGUFが生成したコメント)
③ Llama-3-ELYZA-JP-8B-GGUF
(Umievo-itr012-Gleipnir-7Bが生成したコメント)
④ Gemini(Google所属)
(Umievo, Oumuamua, Llama-3-ELYZA-JPから生成されたコメントをGeminiに入力して要約したコメント)
✨


🍓
この短歌は、春の一日の出来事を切り取ったものです。題材としては、別れとその後の心の動きが表現されています。
まず、「うたかたにきえゆくひとを見送りて」というフレーズから始まることで、詩的な雰囲気が漂います。ここでの「うたかた」とは、はかないものという意味で、人の生死や交際関係などがそれにあたります。別れというものは、はかないものの典型例と言えるでしょう。
そして、「苺ほおばる」という行為が続きます。これは、春の季節に食べられるフルーツである苺をほおばることで、新たなスタートや生命力を感じさせる表現となっています。また、苺の甘さや美味しさが、別れの悲しみを癒してくれるかのような効果もあります。
この短歌のポイントは、別れと新たなスタートを、苺という春のフルーツを通じて結びつけているところにあります。このような表現は、読み手に対して強い印象を与えることができます。
また、表現の上でも見事です。「うたかたにきえゆく」の「に」という助詞が、過去形である「きえゆく」につながることで、より別れのはかなさを強調しています。そして、「ほおばる」という動詞が、苺の食感や味を想像させ、詩的な雰囲気をさらに高めています。
以上より、古井 朔さんの短歌「うたかたにきえゆくひとを見送りて苺ほおばる春の一日」は、人の生死や別れを詠ったうえで、春のフルーツである苺を用いることで、新たなスタートや生命力を感じさせる、詩的で印象的な作品と言えるでしょう。
🍓🍓
古井朔氏による「うたかたにきえゆくひとを見送りて苺ほおばる春の一日」は、簡潔ながらも深い情感が込められた秀逸な短歌です。
この作品では、春という季節の到来を苺という具体的なモチーフで表現しつつ、別れを告げる人を見送る悲しみや寂寥感を描出しています。「うたかたにきえゆく」というフレーズから、何かが終わっていく、消えていくというニュアンスが伝わってきます。それは、春の訪れと共に旅立っていく人の姿なのでしょうか。春は新陳代謝や再生を象徴する季節である一方、別れや旅立ちの季節でもあります。その対比的な表現が切なさを醸し出しています。
「見送りて」という言葉からは、主人公の静かな感情が伝わってきます。見送る側としての自分の心情を表した言葉であり、同時に、苺ほおばるという行為が現実への立ち返りや、新たな始まりを象徴するかのようでもあります。別れの後に残る日常や、前に向かわなければならない自らの姿を苺という身近な果物で表現することで、生々しさや温かさも感じさせます。
五・七・五・七・五の限られた字数の中で、別れの情景と日常への回帰が見事に描かれており、読み手は主人公の複雑な心境を想像することができるでしょう。苺の味や食感、種の感触などを感じさせる細部までこだわった描写は、読者の五感を刺激し、より作品に深みを与えています。
全体として、この短歌は別れの切なさと日常の温かさをバランスよく表現した、読後感の良い一品です。シンプルながらも心に残る魅力があり、古井氏の優れた表現力が発揮されていると言えます。
🍓🍓🍓
以下は、古井朔さんの短歌「うたかたにきえゆくひとを見送りて苺ほおばる春の一日」の表現や内容についての評価です。
この短歌は、季節感と情景描写を巧みに組み合わせた秀作である。まず、「うたかたにきえゆくひと」という表現は、人生の儚さや移ろいを捉えており、読者に深い印象を与える。春という季節もまた、出会いと別れが交錯する時期であるため、「うたかた」に含まれる「無常感」と相まって、哀愁や切なさが漂っている。
一方で、主体は見送りつつ苺をほおばるという、日常の温もりを感じさせる行為を描写することで、対照的な情景を構築している。春の一日という設定も、「うたかた」に比べると穏やかで平和な時間であるため、この対比が効果的に機能し、短歌全体に複雑な味わいを加えている。
また、苺の描写は、甘酸っぱい味や触感を想起させることで、読者に五感を通じて春の日常を感じさせると同時に、「うたかた」が消え去る人々に対する共感や哀れみをも呼び起こす。主体は見送りつつ苺をほおばるという行為を通じて、現実と対峙し、日常の温もりを再確認していることがうかがえる。
総合的には、この短歌は古井朔さんの描写力や情景構築能力が高く評価されるべき作品である。季節感や情景描写に加え、人生の儚さや日常の温もりを巧みに表現することで、深い印象と複雑な味わいを読者に提供している。
🍓🍓🍓🍓
思い出が剥製になる短夜のあのときもっと耳を澄ませば

📝
この短歌では、過去の思い出と現在を重ね合わせた表現が用いられています。「思い出が剥製になる短夜」というフレーズから、過去の思い出が美しく残っていることが伺えます。また、「もっと耳を澄ませば」という言葉から、主体があのときに聞き逃した何か大切なことがあったのではないかという後悔や反省の念を持っていることが読み取れます。
この歌の魅力は、過去の美しい思い出と現在の後悔が交錯する儚さにあります。剥製という言葉からは、永遠に変わらないという印象も受けますが、同時に、過去はもう二度と戻ってこないという無常感も表現されています。
また、この短歌は五・七・五・七・七という定型を忠実に守りながら、言葉の選択や語り口調に工夫を凝らしています。それによって、読み手の感情に強く訴えかける詩的な世界観を構築しています。
総じて、この短歌は過去と現在を見つめ直し、自身の人生に対して真摯に向き合う姿勢を表現していると言えます。その姿勢は、読み手の胸に響き、共感や感動を呼び起こすことでしょう。
📝📝
古井朔さんの「思い出が剥製になる短夜のあのときもっと耳を澄ませば」は、ノスタルジックな情感と、一瞬の時間の静寂さを感じさせる一首です。
「剥製」という言葉からは、かつての記憶や体験が色あせて、固まった状態で残っているという印象を受けます。そのような過去の思い出が、短夜(夏の夜)により一層鮮明に蘇ることを歌っています。短夜とは夏の夜のことで、短い夜を指す言葉です。夏の夜は、他の季節の夜に比べて明るい時間が長いため、様々な出来事や感情を強く印象付けるものがあるでしょう。その中で、「あのとき」というフレーズが、具体的な場面を想像させます。それは、幼い頃の思い出なのか、青春時代の一瞬なのか、それとも遠い昔の出来事なのか。
そして、「もっと耳を澄ませば」という呼びかけは、心の中に残っているかすかな記憶や音が聞こえてくることを期待しているようであり、過去への想いの強さを感じさせます。夏の夜の静寂に耳を傾けることで、当時の空気感や音色が蘇るかもしれないという期待を込めています。その瞬間は、時間が止まったかのような静けさの中にあるのでしょう。
この短歌は、過去への回帰やノスタルジックな感情を表現するのに適した季語である「夏の夜」と、過去の思い出を象徴する「剥製」という言葉の組み合わせが効果的に作用しています。また、「もっと耳を澄ませば」というフレーズは読者にも、自分自身の記憶や体験を振り返るきっかけを与えてくれます。
内容的にも表現的にも深い意味を持ち、叙情性豊かな短歌であるといえます。古井朔さんの言葉選びや表現力が光っている一首だと言えるでしょう。
📝📝📝
この短歌は、古井 朔さんの作品であるとわかりました。以下は、評価文です。
この短歌は、「思い出が剥製になる」という着想が非常にユニークで印象的です。「剥製」は通常、生物の死骸を保存した標本を指しますが、この短歌では「思い出」を剥製化しています。つまり、過去の記憶や体験を固定されたものとして捉えているのです。
「短夜」という季語が使用され、時間的には短い夜が設定されていますが、「あのとき」は特定の瞬間を指すと同時に、過去全般をも包括する表現でもあります。「もっと耳を澄ませば」は、過去の音や声が聞こえるかもしれないという可能性を示唆しています。
この短歌では、「思い出」という主体の内面的な世界が描かれています。剥製化された「思い出」は、時間が経つにつれ風化し、記憶の底に沈み込む過去の事象を象徴しているのかもしれません。同時に、「耳を澄ませば」という行為は、現在の自分が過去に向かって意識を集中することを示しています。
全体として、この短歌は、時間と記憶の関係性を探求し、過去と現在との接点を追究した作品です。古井 朔さんの、内省的で精密な表現力が発揮された佳作であると評価できます。
🏡🏠🏡
はじめから帰るべき家などなかったかボタンホールが見つからなくて

🔘
古井朔さんの短歌「はじめから帰るべき家などなかったかボタンホールが見つからなくて」は、深い内省と静謐な語り口で構成された作品です。
まず、上の句「はじめから帰るべき家などなかったか」は、出生や育ち、或いは人生の経過を通して形成されるはずの「帰るべき家」という概念が、実は幻想に過ぎないのではないかと問いかけています。家庭やコミュニティという社会的・情緒的な拠り所が、個人の存在やアイデンティティーを確立する上でどれほど重要かを考えるとき、この疑問は極めて意味深いものです。
下の句「ボタンホールが見つからなくて」は、上の句の問いかけに対して、具体的なイメージを与えることで、その答えを示唆しています。ボタンホールとは、衣服や布に開けられた小さな穴のことです。このボタンホールが「見つからなくて」いるという状況は、帰るべき家がなかったかもしれないと問うた上で、実際に何処にもそのような拠り所が無いことを示唆しています。衣服や布には元々小さな穴が開いているのですが、その穴が見つからないということは、個人の存在やアイデンティティーを確立する上での拠り所は、実際に存在しなかったかもしれないと解釈することができます。
全体としてこの短歌は、静謐な語り口で個人の内面の深部に触れようとする作品です。古井朔さんの表現や内容は、深い内省と静謐な語り口を通して、個人の存在やアイデンティティーを確立する上での拠り所が、実は幻想に過ぎないのではないかという問いかけを提起しています。
🔘🔘
古井朔さんの詠んだ「はじめから帰るべき家などなかったかボタンホールが見つからなくて」という短歌は、独特な世界観を持った一首です。
この歌では、「ボタンホールが見つからない」という日常的には些細な出来事が、大きな悩みや孤独感を感じさせる表現となっています。「帰るべき家などなかったか」というフレーズは、自分の居場所や身元の不安定さ、あるいは喪失感を表しているかのようです。ボタンホールが見つからないということは、自分の身に着ける服も整っていない、あるいは、自分自身がどこに属するのか分からない状態であることを暗示しているかのように思えます。
また、「はじめから」という言葉が付くことで、これまでの人生や経緯において、常にその不安定さを抱えてきたのかもしれないと想像させられます。それは、自分自身がどこにも属せず、何処へ帰ればよいのか分からない旅人のような孤独感に似ています。
短歌としてのリズムや語彙も非常に洗練されており、読者に深く考えさせる余白を残しています。ボタンホールが見つからないことで生じる小さな困り事から、大きな人生の葛藤までを連想させる奥深さがあり、詩的な表現力に富んでいると言えるでしょう。
内容面でも、身に着ける服にあるボタンホールの存在は、自分自身のアイデンティティーや人間関係、社会的地位など様々なものを象徴しており、それらが失われたような感覚を味わうことで、現代人の虚無感や疎外感を表していると捉えることもできるかもしれません。
全体的に抽象的でありながら、誰しもが共感できる普遍性も持ち合わせており、読者にとっては自分自身の心の内面を探求するきっかけとなるかもしれない短歌です。表現力豊かで奥行きのある作品だと評価できます。
🔘🔘🔘
この短歌は、失われたものへの追憶と、その失われたものが本当に自分の帰るべき場所だったのかという疑問が描かれています。題材はボタンホールですが、これは比喩的に使われています。
ボタンホールというのは、衣服の装飾品で、服のボタンを付けるための穴です。しかしこの短歌では、その小さな穴さえも見つからないことで、自分の帰る場所の曖昧さを表現しています。
「はじめから帰るべき家などなかったか」というフレーズは、従来の価値観や常識に縛られていた自分を振り返り、それが本当に自分にとって大切なものだったのかと疑問を投げかけています。
そして最後の「ボタンホールが見つからなくて」という一節は、失われたものへの執着心や、それを取り戻したいという思いが表れています。ボタンホールは、衣服を着るための穴ですが、そこから連想されるのは、繋がりや記憶、そして時には取り返しのつかないものでもあります。
全体を通して、この短歌は、過去に失われたものへの思いや、それを取り戻そうとする心情を繊細かつ深みのある言葉で表現しています。それはまるで、失われたボタンホールを探すかのように、自分の中にある大切なものを求める姿であり、読み手にも深い共感を与えてくれます。
🔘🔘🔘🔘
記憶の海溺れてボクら沈みゆく凪いだ水底セイレーンの歌声

🌊
古井朔さんの短歌は、以下のように評価することができます。
記憶の海溺れてボクら沈みゆく凪いだ水底セイレーンの歌声
この短歌は、表現的にも内容的にも非常に興味深い作品です。まず、上五「記憶の海溺れて」で、「記憶」という主体が「海溺れて」いる状態が描かれます。これにより、読者は「記憶」が底知れない闇や深淵のようなものであることを直感することができます。
中七「ボクら沈みゆく凪いだ水底」で、「ボクら」つまり主体がその「記憶の海溺れて」に飲み込まれている様子が描かれます。ここでの「凪いだ水底」という表現は、平穏な水面下であると同時に、深く暗い世界でもあります。
下五「セイレーンの歌声」で、この短歌の核心部分が明示されます。セイレーンという海の怪物が奏でる歌声は、人を惑わす美しい歌声として知られています。この歌声が「凪いだ水底」に響き渡っている様子は、「記憶の海溺れて」ボクらを引き寄せるものであると同時に、その深みから浮上することを困難にする要因でもあります。
この短歌は、記憶や過去という重く暗い「海」に沈み込むことの危うさと美しさを描いています。セイレーンの歌声が響き渡る水底で、「ボクら」が浮上することができるかどうかはわかりませんが、少なくともこの短歌では、その危険な領域に足を踏み入れることの魅力が描かれています。
古井朔さんのこの短歌は、表現的には非常に完成度が高く、内容的にも興味深い作品です。
🌊🌊
古井朔さんの短歌「記憶の海溺れてボクら沈みゆく凪いだ水底セイレーンの歌声」は、幻想的で神秘的な世界観が魅力的な作品です。
まず、「記憶の海」という表現から、過去の思い出や経験が海のように広大で深い場所に埋もれている様子を表しています。それらの記憶に溺れるという言葉は、人々が時に過去に囚われ、現在に生きづらさを感じることがある人間の心情を反映しているかのようです。その海底へと沈んでいく「ボクら」という主語は、私たち読者自身を含む普遍的な存在感を感じさせ、共感を呼び起こします。
次に、「セイレーン」という単語が登場します。セイレーンはギリシャ神話における人魚のような水の精であり、歌や声で船乗りを誘惑してしまう魔性の生き物とされています。この短歌の中では、記憶の海に眠る過去の思い出を呼び覚ましたり、引きずり込もうとする力を持っている存在として描かれていると思われます。セイレーンの歌声は美しくも危険なものであり、懐かしさや哀しさ、または後悔など様々な感情を誘うものでしょう。
「凪いだ水底」という表現が静けさと安らぎを感じさせつつも、何か不気味な深みを秘めているように感じられます。その中で響くセイレーンの歌声が、過去の記憶を呼び覚ましたり、心に訴えかけるものがあることを示唆しています。凪ぐ水面は、平穏で静まった時の流れを象徴しつつも、実はその下では深くて暗い海底が広がっているという対比が、人間の心の奥底に眠る闇や深層心理を表現しているかのようです。
全体として、この短歌は過去への郷愁や、それに伴う複雑な感情を、美しい神話的なイメージで包み込んだ詩的な作品となっています。記憶に沈み込むことの怖さや、そこから何かを呼び起こされる感覚が、読者にも伝わり、心に残る印象的な短歌となっています。音数は五七五七五七七七で、リズム感も良く、短歌としての構成も美しいです。
🌊🌊🌊
この短歌は、「記憶」を海に例えているところから始まります。人の記憶は、時とともに曖昧になり、やがては忘れ去られてしまいます。そのような記憶の曖昧さや儚さを、海の中にいるかのように描写しています。
次に「ボクら沈みゆく」というフレーズがあります。これは、記憶が薄れ、やがては完全に失われてしまうことを表しています。また、「凪いだ水底」という表現は、穏やかで静かな水面下の様子を示しており、そこにいるセイレーンの歌声を引き立てます。
セイレーンといえば、ギリシア神話に登場する美しい歌声を持った半鳥半魚の怪物です。彼女たちの歌声を聴いた者は、海に引きずり込まれてしまうと言われています。この短歌では、セイレーンの歌声が沈んでいく記憶たちをさらに深い闇へと引き込むかのように描かれています。
最後に、「記憶の海溺れて」というフレーズをもう一度繰り返し、記憶の儚さとその消失に対する哀愁を表現しています。
このように、この短歌は記憶の消失とその哀しさを美しく表現しています。同時に、記憶が失われていく寂しさと、それに対する静かな抗いを感じさせる作品となっています。
🌊🌊🌊🌊
名前のない感情に晒され溺れてる虚数の海には入れない


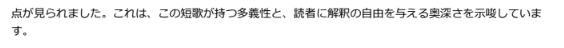
🌊
この短歌は、古井 朔さんの独特の世界観と詩情が凝縮された作品である。
まず、「名前のない感情」というフレーズは非常に印象的で、現代人特有の複雑な心情をうまく表現している。人は日常生活の中で、言葉にできない、もしくは名前が付いていない感情と向き合うことが多々ある。この短歌はそのような感覚を鋭敏に捉えている。
「晒され溺れてる」という状況は、まるで海に飲み込まれるようにして感情に浸っている様子を描写している。水は通常、心の安定や平穏を象徴するが、「虚数の海」ではその常識が覆される。虚数は数学的概念であり、現実世界で体験することができないため、日常感覚から遠く離れた世界にいることを示唆している。
「入れない」という結語は、虚数の海に対する羨望や憧れを表すと同時に、「名前のない感情」に自らが飲み込まれることを避ける心理も反映されている。人は未知の世界や得体のしれないものに惹かれる一方で、安全な領域から踏み出さないという防衛本能も持つ。この短歌はその両面をうまく表現している。
古井 朔さんのこの短歌は、複雑な心情と数学的概念を組み合わせることで、深い内省と哲学的な考察が混在する作品に仕上がっている。
🌊🌊
古井朔氏によるこの短歌は、抽象的なテーマを扱いながらも、心に響く表現力が豊かで印象深い作品です。「名前のない感情」という言葉遣いが、読者に何らかの曖昧で明確に形容しがたい気持ちや状況を想起させます。虚数という数学的概念を用いて、現実と非現実、あるいは理性と本能、心の中に存在する複雑な感情を表しているようにも読めます。
「名もなき」とされる感情は、時に私たちの内面で大きく揺れ動き、形を変えながら、ときには自分でも理解しがたいものです。そのような名もなき感情が海のような広い空間に溺れている様子を「虚数の海」と表現することで、無限大かつ未知数の深みを感じさせます。この海には名前がないために、手触りのないしらじらしさや不安定感も伝わってきます。
作者は自分自身を虚数の海に入れずにいるのでしょうか。それとも、すでにその中に溺れてしまったのでしょうか。いずれにせよ、この短歌は、自己分析や内省を促される内容となっています。数学的な「虚数」を使うことで、現実世界から一歩外れた、別次元の心象風景が浮かび上がり、読者の想像力を刺激する効果もあります。
また、「晒されてる」という言葉遣いには、感情が表に出てしまい、抑えきれないほどに溢れ出している様子や、周囲から見られている緊張感も感じ取れます。
全体的に、抽象性が高く難解な短歌ではありますが、それゆえに各人の解釈の余地があり、深く考えさせられる一首となっています。哲学的・文学的な味わいを楽しめる秀逸な作品です。
🌊🌊🌊
この短歌は、「名前のない感情」と「虚数の海」という二つの要素から成り立っています。まず、「名前のない感情」とは、言葉で表現することが困難な心の内面を指していると思われます。この感情に晒されている人間は、自分自身でもその正体がつかめず、溺れてしまっているようです。
一方、「虚数の海」とは、現実には存在しない、空想上の海なのかもしれません。そこは、名前のない感情に満ちた場所であり、主体の「自分」はその海に入ることができません。これは、主体が現実と向き合い、空想との間で葛藤している様子を表しているのではないでしょうか。
このような要素を持つ短歌ですが、その表現は非常に繊細であり、読み手に深い印象を残します。具体的な情景描写がないにも関わらず、感情の高まりや、海に入ることができない焦燥感がリアルに伝わってきます。また、「虚数の海」という言葉には、現実離れした幻想的な雰囲気も感じられます。
総合的に評価すると、この短歌は、抽象的な感情と具体的なイメージが見事に融合した優れた作品であると言えます。読み手の想像力をかき立て、心に残る名作であると評価します。
📝📝📝
以上、AI選者3名+総評要約担当1名によってされた評コメントです。
総じてかなり褒められていますが、これはどの短歌も褒めることがおそらく基本スタンス(プログラム)になっているかと思われるので、そこはあまり気にせずに、歌の解釈や内容そのものに焦点を当てて評を読みました。
以前より、かなり歌意に近づいている解釈や深く読み解かれていて、詠者としてはうれしいコメントもいくつか見られました。
中には、作者の予想(想定)を超えるコメントもあり、驚く内容も!
歌意とかけ離れた解釈については、実際にリアルの歌会などでもあるので、解釈にバリエーションがあるのは、ある意味とても人間的とも言えます。
自分で詠んだ歌が、他者にどのように受け止められ、解釈されうるかを知ることは、その歌の推敲だけでなく、次に別の歌を詠むときにも参考になるのではないかなと思います。
自分自身、とても勉強になりました📝
深水さん、efさんに感謝いたします。
第11回毎月短歌のAI評が揃いました
— 深水英一郎(次世代短歌) (@fukamie) July 2, 2024
今回ひとり増え、AI評者は4名体制となりましたhttps://t.co/8e4ZMOW9VQ
みなさんの感想をお待ちしております#AI短歌 #次世代短歌 #毎月短歌 https://t.co/uYzGDclnD8 pic.twitter.com/Ly1L1goJPj
【毎月短歌・AI評者のつくりかた】
— 深水英一郎(短歌) (@fukamie) June 23, 2024
短歌評生成システム"Utayomi"の公開https://t.co/jjufTSuwR7@ef_utakata さん作 #毎月短歌 でおなじみのAI評者こと"Utayomi"がGitHubで公開されました#utayomi pic.twitter.com/xEkGKmrq1m
Utayomiのシステムを0.3にバージョンアップしました。複数のLLMから生成されたコメントをGeminiに要約させる「歌会モード」を追加しました。#毎月短歌11 の投稿短歌(現代語部門・単作)に対して、このモードを用いて生成したコメントを公開予定です。https://t.co/ltwXYhaGOk
— ef (@ef_utakata) June 30, 2024
📚📚📚
毎月短歌が、電子書籍になりました。
今回記事に掲出した現代短歌(口語短歌)以外の文語・旧仮名短歌や連作短歌含めて、応募した作品がすべて掲載されています。
Kindle Unlimited会員の方なら無料で読めます。
📚📚📚
『第11回毎月短歌』掲載
『第12回毎月短歌』掲載
『第13回毎月短歌』掲載
『第14回毎月短歌』掲載(2024/9/25発売)最新号
#短歌
#tanka
#毎月短歌
#AI評
#A短歌会
#次世代歌壇
#次世代短歌会
いいなと思ったら応援しよう!

