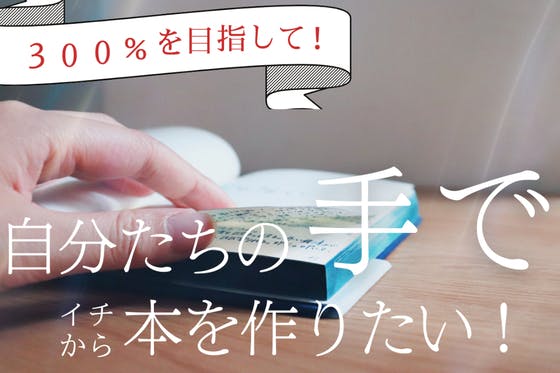本へのこだわり、または執念の制作物語
こんにちは。
今日は我々大倉書房が作ろうとしている本『終の一語』へのこだわりについて語りたいと思います。ほとんど俺(代表)のオタク語りのようになっていますが、きっと我々のことを見つけてくださる方なら喜んで話を聞いてくれそう……!
現在、大倉書房ではこの本を作るためのクラウドファンディングを実施中です。既に様々な方からの温かいご支援を頂き、感謝の念に堪えません。
もしよろしければ以下のサイトも合わせてご覧ください。
そして後日、このクラウドファンディングに踏み切った理由やクラウドファンディングに対して思うところなども語る予定です。代表の自分語りに始まり、怒涛の更新になりますが、我々の熱量を受け取っていただけると幸いです。
では、実際にこの本に詰め込まれた大倉書房のこだわりについて紹介していきます!
1.手製本&著者(出版社)自装
皆さんは、「手製本」という言葉を聞いたことがありますか? 文学フリマなどの即売会によく行かれている方なら、目にしたことがある、耳にしたことがあるという方も多いかもしれません。
手製本とは文字通り、人の手で製本することです。しかし、一口に「手製本」と言っても、様々なものがあります(と大倉書房は考えています)。
我々の言うところの「手製本」とは、表紙を自分たちで付けることです。
いやいや! それは手製本とは言わないよ!という反論がある事は、もちろん承知しています。
そこで我々は、近代の文学人たちが憧れた「フランス装」に立ち戻ってみることにしました。
「フランス装」とは、簡易的な装丁のことで、ページがそれぞれ独立せずにくっついたままの状態で製本された本の事です(用語を使わずに説明しようとするとこうなってしまう……。たぶんネットで調べてもらった方が早いです)。フランス装の定義も曖昧で、俗称(フランス装自体が「いわゆる」というものですが)アンカット本とも呼ばれます。このくっついたページ(アンカット)をペーパーナイフなどで切り開きながら読み進めていきます。
この辺りの用語はほんとうにややこしく(定義が曖昧で)、アンカットとフランス装は微妙に意味がずれているのですが、今回の文章では同一視します……。

現役の編集者さんによれば、フランス装を実際に見たことのある人など今ではいないのだそうです。しかし、編集部内で脈々とフランス装という浪漫が受け継がれてきたのだとか。その浪漫の原因となった一人が萩原朔太郎のような気がしていますが、一体誰がその浪漫を膨張させてしまったのでしょうか。かくいう俺も、その浪漫にあてられた一人です。アンカット大好き。
何故このフランス装が手製本につながるのか、疑問に思われている方も多いかと思います。
そもそもこのフランス装は、「フランス」と言われるくらいですから元々は西洋の文化でした。西洋では、完全な製本はせずに仮製本(つまりフランス装の状態)で本を販売し、それを愛書家たちが自分好みの装丁に仕立てていたのです。重要なのはここです! 装丁は読者の仕事だった!ということ。 我々はここに立ち返ろうと思いました。だから、折丁(表紙を除いた本の中身です)は印刷所に依頼し、装丁は自分たちで行う。製本の最終段階を手作業で行うから「手製本」。そういう訳なのです。
そして、もうひとつ手製本する上でのこだわりがあります。小口染めです。本に詳しい方なら、この言葉も御存じかも知れません。簡単に言ってしまえば、本の表紙で覆われていない部分に色を付けるという事です。

この小口染めには、小間使いのAとCと一緒に調合したインクを使っています。これが二十歳の誕生日プレゼントだったんですが、とても粋なプレゼントだと思いました。嬉しかったのでこの本に使ってしまいます。
※後に本文との関りをもっと考え、作者の愛用する万年筆のインクを使う事になりました。

欲を言えば、完全「手製本」に挑戦したかったのは事実です。しかし、しかし……初心者がいきなり何十部も手製本することは可能なのでしょうか。たとえ可能であるにせよ、見栄えがよくないなんてことになると、多分俺はぶちぎれ……ゴホゴホ、納得いくまで何度も作り直しをする(させる)未来が容易に見えたので、修羅場を回避することにしました。
※この予想は的中します。A、ごめんな。
次に著者自装について語りたいと思います。著者自装とは、著者が著作の装丁を考えることです。通常、装丁は装丁家やグラフィックデザイナーなど、デザインすることに長けた人が行います。近代では画家がその役割を担っていました。そもそも近代では装丁家という概念さえ固まっていなかったでしょうし。
著者自装の例として有名なのは、夏目漱石の『こころ』や萩原朔太郎の『青猫』などです。多くの詩人は装丁に対して並々ならぬ思いを持っていたようです。朔太郎は特にその思いがあまりに強すぎて自分で装丁してしまったという勢いがあります。漱石は朔太郎の装丁LOVEとは違って、装丁を他所に頼むお金が無いから先生自分で装丁を考えて下さいと岩波茂雄に言われたからではなかったかな。そして、小説家で言えば、谷崎潤一郎も外せません。絶対に。文庫本で読んで「この人やべーな」とか言っている場合ではなくなります! 彼の装丁を見たら、こうなります。「この人変態だな……」もちろんいい意味です。誉め言葉として「変態」だと言いたいです。俺はいつか『春琴抄』や『盲目物語』と同じようなことをやりたいっと思っているのですが、誰が読むんじゃと冷静な自分がツッコミを入れてきます。変態と化すには理性が勝ちすぎています。うーん、強すぎるこだわりも考え物ですね。
しかし、我々もその「考え物」な装丁を……
やってしまったのです!!
わあ、変態じゃん!(笑)
厳密には、『終の一語』は著者自装ではないのですが、作者と装丁を担当した人とそして出版社(大倉書房)が混然一体となって一冊の本を作り上げようとしています。萩原恭次郎の『死刑宣告』のようなものです。作者とその仲間たちというスタンスで突き進んで行きます。
一見すると、『終の一語』は奇抜な装丁ではありません。中を開けばなかなか奇抜だと思いますが(2.で語ります)、外身は別に、まあ、ふつー。全然変態じゃない。
ここで、装丁について考えてみましょう。
装丁と言っても、これまた定義が色々あります。我々は、装丁はブックデザインと同義だという考えです。ここでの反論は認めません。心の中で叫んでください。もしくはnoteに記事を公開してくださればスキを押しに行きます。
装丁とは、本の身体性を左右するもの。それはそうですよね。本の見た目、手触り、重さ、匂い……などなど本という個体は様々な情報を持っています。それを最も作品に添う形で引き出し、形として留めるものが装丁だと思っています。
しかし、読書する時に装丁が与えるのは身体性だけでしょうか。表紙が怖くて持ちたくない本なんてのもありますよね……。(ほら、あの分厚いことで有名なあの方の本とか)表紙が紙っぽい紙ではなく、何だか変な感触のする紙なんてものもあります。ぬめぬめしていてぞっとしたり、最初は気にしていなかったのに物語の途中で装丁の意味に気付いて冷汗が流れたり、感動したり。つまり、装丁は精神にも影響を与えるのです。
そして、もっと面倒臭いことを考え始めますね。
本の内容に影響を及ぼすのは、装丁だけだろうか。
これが、最大のヒントです。『終の一語』を読み解く上での。
俺は、常々「作者」という存在に苦しめられてきました。「作者」ってなんでしょう。どこまでが「ブックデザイン」なのでしょう。
俺一個人としては、『終の一語』はこの問いに何かしらの答えを打ち出しているように思います。そしてその答えに至るために、大倉書房が全力でバックアップしている訳です。
今まで制作会議の記事を書いてこなかった俺が文字を操る時、何か仕掛けてきているのだなと思いながら読んでもらえると最高に嬉しいです。俺はこの『終の一語』を本にとって最良の形で皆さんにお届けしたいと思っています。もしも、『終の一語』を全力で受け止める気概のあるという方は、これまでの記事もご覧ください。まーじで読むの疲れますが、俺の言っている意味が伝わるのではないでしょうか。
2.手書き&フルカラー印刷
通常、書籍は活字で文字は印刷され、そしてその文字の色は黒ですよね。それは洋装本が主流となっていく明治時代から現代まで、暗黙の了解といった具合で本というモノの根底に流れています。
しかし、明治時代以前では活字は主流ではありませんでした。浮世絵の制作過程を想像できる方は想像していただきたいのですが、文字も絵と同じように木に彫られていたのです。木版印刷という方法です。また、刷られる文字はこのように一文字一文字が分離したものではなく、いわゆる「くずし字」「つなげ字」で、さらに言ってしまえば、「ミミズののたくったような文字」でした。それが明治時代になって西洋の影響を受けると木版印刷から活版印刷へと移行されてゆきます。手書き(手彫り)の小説本なんてものは、なくなっていったのです。
刊行された書籍は確かにその通りですが、小説はいきなり本の形になるわけではありません。書籍の形になる前には、何枚もの原稿用紙が積み重なっています。そして、その小さなマス目に、文字が! 俺の愛する文字が、書かれていたではありませんか……! 明治時代はもちろん、大正、昭和前中期など、いわゆる「近代文学」と呼ばれる時代の文学者たちは、原稿を手書きしていました。いち早くワープロを使いはじめたのは安部公房……かなり最近ですね。
確かに、活字には活字の良さがあります。読みやすさの面で考えれば、メリットは一目瞭然です。しかし、手書きには手書きの価値がありますよね。有名な作家の肉筆原稿に莫大な価値が付くということは想像に難くないと思います。そして何より、作家の身体性……息遣いを直に体験することが出来る。どの文字を間違えたのか、どの文章を付け足し、または削ったのか。インクの掠れ具合。墨溜まり。そもそも筆記具は何なのか。万年筆? 筆? 付けペン? ボールペン? 作家が確かに生きているという実感。これって、とても重要な事だと思うんです。
だから大倉書房は、手書きの小説を作りたいと思いました。そして、手書きだからこその生々しさを表現したいと思いました。
『終の一語』は、インクに塗れた全身で、真っ白な紙に体当たりするような本です。積み重ねられてきた文字の産物に最大のリスペクトを全身で示すために、インクさえも体の中に注ぎ込んで言葉を吐き出すような本です。
俺は、文字に憑かれています。それは最早本望です。ナブ・アヘ・エリバのように、文字の靈に殺されましょう。
とまあ、中島敦の「文字禍」で背筋が冷えたところで、『終の一語』に話を戻します。
手書きの小説を出版するにあたって、問題が一つありました。それが色です。
現在、「インク沼」という言葉があるように、万年筆のインクはどんどん多様化してきています。作者が好むのは、古典的な「ブルーブラック」で、何も珍しいインク色ではありません。しかし、ブルーブラック。ブルーと付いてしまっているから、黒ではないのです。黒ではない、つまりモノクロ印刷で黒にするか、青いインクを活かしてカラー印刷にするか。
発行者としての俺の意見は後者でした。大倉書房でも全会一致で後者でした。
作者が黒ではなく紺のインクで書き綴る意味。そして、作者は自身が青いインクを使って小説を書いているということをかなり意識しています。モノクロ印刷にしてしまうと、話にズレが生じてしまうのです。
なので、カラー印刷!
なんとしてもカラー印刷。
他に選択肢はない。
こだわりというか、最早強迫観念ですね。フルカラーで印刷できないのなら出版しないと駄々をこねました。貯金全額使えばできるじゃないかと。しかし、2人の小間使い。それじゃあ今回の活動だけで大倉書房が終わってしまうからダメだ!と。そういうこともあってクラウドファンディングにつながっていくのですが、それはまた次の機会に。
なにはともあれ、無事に出版できる方向に向かっているので良かったです。本当にご支援くださった皆様のおかげです。
3.こんな本を作りたいと影響を受けた本たち
大分こだわりを語り尽くしたので少し趣向を変えます。実は、一時期Twitterでこんな投稿をしていました。
【こんな本が作りたい①】「美しい本」
— 大倉書房@クラファン中! (@ookura_shobow) May 20, 2022
たとえば、装丁の美しい本を作りたい。洗練されたデザインの美しさにはため息が漏れます。俺が特に美しいと思う2冊をあげてみました。この美しさを語るには余白があまりに狭すぎるので、今度インスタの方で熱く語りたいです。
今日は代表の本棚から📖
(代表) pic.twitter.com/3bNUz7J5TN
【作りたい本②】文字のアート
— 大倉書房@クラファン中! (@ookura_shobow) May 20, 2022
俺は文字そのものが好きです。文字がびっしりあるとテンション上がります。
こちらも代表の本棚から📖
※写真はあえてモノクロのフィルターをかけています
(代表)#をつけ忘れるのでちゃんとつけます#読書好きな人と繋がりたい#ブックデザイン pic.twitter.com/f0g8r92YaC
【作りたい本③】ウ ワ ハ!
— 大倉書房@クラファン中! (@ookura_shobow) May 23, 2022
本日お誕生日の萩原恭次郎による『死刑宣告』。見ればわかる。見たら忘れん。文字の海で暴れましょう。
しかし、ただのヤバい本ではない。関東大震災によって被害を受けた活版所も踏まえているのだとか。暴れた文字たちは震災によって崩れた活字たちなのです。
(代表) pic.twitter.com/S2u3JkH0EJ
まさかの三日坊主ですが、この3つの投稿だけで大倉書房がどこを目指しているのかがだいたい分かると思います。前回大量更新した【代表のつぶやき】で出て来た代表の愛読書歴も合わせて見ていただくと、「ほうほうなるほど?」となるように思います。
他にも投稿したい本はたくさんあってですね……もしかしたらこのツイートがレギュラー化するかもしれません。(できたらいいな)
4.おわりに
読み手からしたら、作り手のこだわりなんてどうでもいいのかもしれない。本の内容が面白ければそれでいいのかもしれない。確かにそれは一理あります。伝わらないこだわりに何時間も何十時間もかけるのは、阿保らしいことです。
けれども、読書は本の内側だけで完結するものではありません。虚構が現実に侵食することだってあります。現実が虚構に侵食することだってあります。そして、我々は誰にも伝わらないような無駄な努力を惜しまずに本の制作にあたりたいのです。全力の無駄遣いとでも言っておきましょう。でも、その無駄遣いが圧倒的なものとして現れた時、我々の本気がきっと誰かに伝わるでしょ? そしてかっこいいと思うでしょ? 俺は「デザインのひきだし」という雑誌を見て、いつも思うのです。モノを作るってこういう事だよな。こういう事なんだよな。
この本を手にしてくださる人が、豊かな読書の世界を築いてくれますようにとの願いを込めて、結びの言葉とさせていただきます。どうか、我々の本に限らず、全ての本にドラマがあることを忘れないでください。