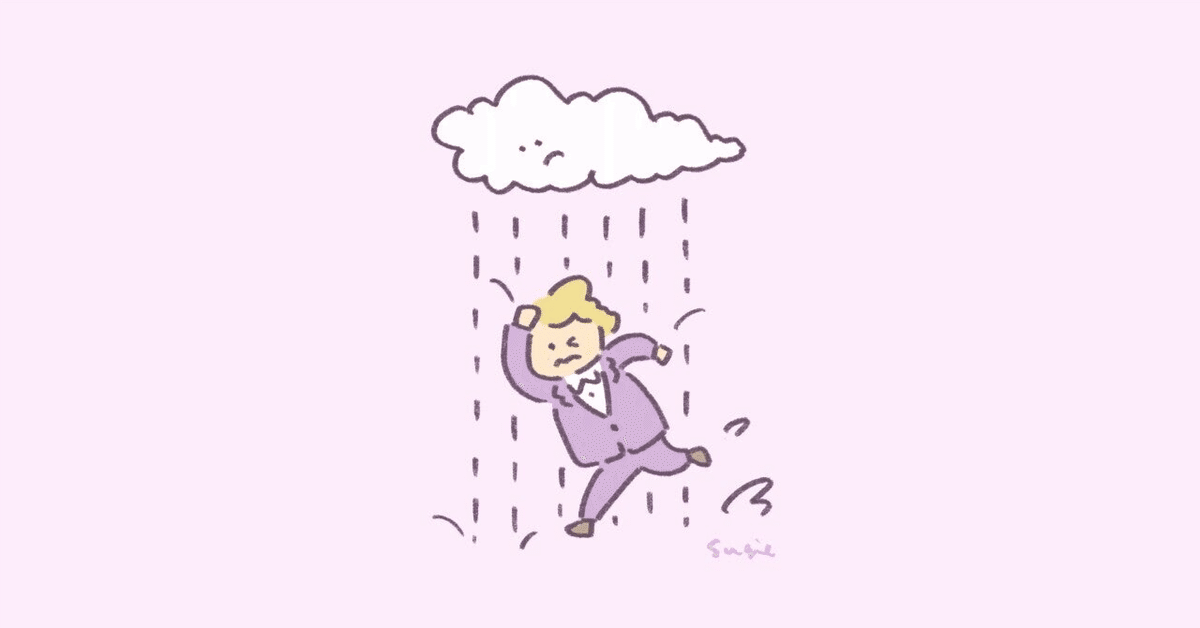
でありながら、ではなくなってしまう(好きな文章・01)
「好きな文章」という連載を始めます。たぶん、同じ書き手の同じような文章ばかりをあつかいそうな予感があります。それでもかまわないので、好きな文章を引用して好きなことを書くつもりです。
今回のタイトルは「でありながら、ではなくなってしまう」ですが、これまでに投稿した「【レトリック詞】であって、でない」や「であって、ではない(反復とずれ・03)」と似ています。「宙吊りにする、着地させない」とも似ているかもしれません。
好きなのです。こういうのが。大好きでたまりません。病的に好きだという自覚もあります。というわけで、蓮實重彥(蓮實重彦ではなく)の文章を取りあげます(この記事では敬称略でいきます)。
リズム、言葉の身振り
であって、でない
であって、ではない
でありながら、ではなくなってしまう
……であって、……でない
……であって、……ではない
……でありながら、……ではなくなってしまう
たぶん、私はこういうリズムというか言葉の身振りが好きなのです。自分のなかにある「何か」、自分に流れている「何か」と、ともぶれ(共振)している気がします。
*
ミステリーのなかにもこういう展開のストーリーがあります。はらはらどきどきしますね。
今回紹介する蓮實重彥の文章では、作品全体ではなく、センテンスレベルで、こういう展開が見られるのです。
蓮實の文章のなかでも、小説について書かれたものは比較的読みやすいと思うので、安岡章太郎の小説を論じたものから引用します。できるだけ、短く引用するので、お付き合いくださればうれしいです。
避けようとしながら、避けられなくなってしまう
こうして安岡的「存在」の多くは、避けようとする身振りそのものによって、避けるべき対象と深く戯れてしまうというパラドックスのさなかに生きることになる。
(蓮實重彥「安岡章太郎論 風景と変容」(『「私小説」を読む』中央公論社)所収・p.176・以下同じ)
一センテンスですが、これだけでも、「でありながら、ではなくなってしまう」という展開が見られます。「避けようとしながら、避けられなくなってしまう」のですから。
とはいえ、もう少し言葉を加えてもいいでしょう。
避けようとしながら、避ける対象と深くかかわってしまう
避けようとすることで、かえって、相手と深くかかわってしまう
こういうことって、ありませんか? 上の一文にもある「パラドックス」です。
簡単に言うと、蓮實重彥の文章に見られる基本的な言葉の身振りなのです。蓮實による振付だと思います。
間抜けな話
『月は東に』の冒頭のジェット機は、なんとか逢わずにいたい男が間違いなく待ち受けているはずの羽田空港へと、一直線に太平洋を越えてゆくではないか。
たとえば、こんな間抜けな登場人物が出てくるのが安岡章太郎の小説だというのですが、たしかに安岡の小説は、この種の間抜けな話が間抜けな人物によって演じられています。
「溺死志願者の仕草」
だから、真に安岡的風土に置かれた存在は、逃げていたはずのものによって執拗に視界を立ちふさがれれるので、その目の前の風景の遠近法はたえず狂っていることしかない。そのときそこで息をつめ、瞳をふせ、足音を殺していることは、無防備のまま世界へと埋没していく溺死志願者の仕草にほかならなくなる。
逃げていたはずのものが、しつこく目の前に立ち現れる。これは遠いが近いに、近いが遠いになっている狂った風景の世界だと言えるでしょう。
だって、逃げると相手が近くにいるのですから。バグだらけのカーナビを頼りに逃げるようなものです。
これは、相手に見つからないために、じっとしていることで、相手を招き寄せてしまう事態にそっくりです。そこから「溺死志願者の仕草」という言葉が出てくるのでしょう。
端から見たら、進んで溺れようとしている姿にしか見えないということです。ある意味滑稽だし、グロテスクであるとさえ言えそうです。
でありながら、ではなくなってしまう
存在を希薄にする試みは、一変して外界の諸要素が最も深く体内に浸透する格好の身振りとなり、逃げるための足ならしは、かえって世界の中核部へと一挙に突入する準備運動になってしまうだろう。
相手や何かから逃げようとして自分を目立たなくする行為が、相手や何かを体内にまで招く目立つ仕草になってしまう。
逃げようとして足ならしをしていると、それが逃げる対象に突入する準備運動になってしまう。
……でありながら、……ではなくなってしまう。
「……しないために」が「……してしまう」を招いてしまう――こうした事態に私たちは意外と親しんでいるのではないでしょうか。
したくてそうなるのではありません。そうなってしまうのです。
こうした状況を言葉の身振りとして、つまり文字と文字列として目にする。つまり、一行の文、あるいは数行からなる文章として、その身振りを体感する。
人生や日常生活でのリアルな体験ではなく、文字と文字列の身振りだけに、ささやかながらのスリリングな体験として身に迫ってくる気がします。
*
であって、でない
であって、ではない
でありながら、ではなくなってしまう
私にとって、蓮實重彥の文章は、センテンスレベルにおいて、上のフレーズに見られる言葉の身振りを演じてくれる装置なのです。私はそのその装置が送ってくる波のようなものに触れて振れて、おそらく狂れているのだと思います。
私が感じているのは動きなのです。それも、えんえんとつづきそうな動きです。
変奏
文章における蓮實重彥の「……であって、……でない」「……であって、……ではない」「……でありながら、……ではなくなってしまう」は変奏されます。たとえば、次のような形を取ります。
「自由」と錯覚されることで希薄に共有される「不自由」、希薄さにみあった執拗さで普遍化される「不自由」。これをここでは、「制度」と名づけることにしよう。読まれるとおり、その「制度」は、「装置」とも「物語」とも「風景」とも綴りなおすことが可能なのものだ。だが、名付けがたい「不自由」としての「制度」は、それが「制度」であるという理由で否定されるべきだと主張されているのではない。「制度」は悪だと述べられているのでもない。「装置」として、「物語」として、不断に機能している「制度」を、人が充分に怖れるに至っていないという事実だけが、何度も繰り返し反復されているだけである。人が「制度」を充分に怖れようとしないのは、「制度」が、「自由」と「不自由」との快い錯覚をあたりに煽りたてているからだという点を、あらためて思い起こそうとすること。それがこの書物の主題といえばいえよう。その意味でこの書物は、いささかも「反=制度」的たろうと目論むものではない。あらかじめ誤解の起こるのを避けるべく広言しておくが、これは、ごく「不自由」で「制度」的な書物の一つにすぎない。
(蓮實重彥「表層批評宣言にむけて」(『表層批評宣言』所収・ちくま文庫)pp.6-7)
「……であって、……でない」「……であって、……ではない」「……でありながら、……ではなくなってしまう」の「……」が、「自由」「不自由」「制度」「装置」「物語」「風景」であったりしますが、基本的には「であって、でない」「であって、ではない」「でありながら、ではなくなってしまう」という身振りが反復され変奏されます。
この引用文で「ない」が頻出するのは、そのためです。「ない」の反復は「ずれ・ずれる」という動きにほかなら「ない」わけですが、この絶え間ない「ない」には終わりが「ない」と言えるでしょう。ずれっぱなしなのです。
宙吊りにし、着地させないのです。⇒「宙吊りにする、着地させない」
*
大切なのは、蓮實的「身振り」が安岡的「存在」の身振りに似ていることです。内容ではなく、その言葉の動きが、ある意味滑稽であり、無声映画時代の喜劇じみた様相を呈する場合があります。
たとえば、引用文の最後のセンテンスをご覧ください。まるでオチのようにも感じられませんか? くり返しますが、内容ではなくその動きがです。無声映画に台詞がないように、この動きに内容はないような気がしてなりません。
おそらく、私たちはそこで笑うべきなのです。そして、次の瞬間に、その笑いが自分たち一人ひとりに向けられていることに気づき、笑いを浮かべたまま顔をこわばらせるべきなのでしょう。
落ちのように見えて、着地しないし、着地させてくれないのです。墜落も不時着も予定どおりの着陸もない――どれもが文字どおり着地です――という意味です。
*
さらにいえば、その動きが段落の冒頭にもどっていることに私たちは笑いをこわばらせたまま唖然とすべきなのです。身振りが振り出しにもどっているのですから。
この段落の次には、変奏されたさらなる「……であって、……でない」「……であって、……ではない」「……でありながら、……ではなくなってしまう」が待ち受けてもいるのです。
滑稽なまでに恐ろしい、あるいは恐ろしいまでに滑稽なのは、その段落を読んだ者にも読んでいない者にも、ひとしくその笑いが向けられていることではないでしょうか。
身振りが普遍性を備えているからではありません。ただただ非人称的で、のっぺらぼうの顔をし、内容を欠いているからにほかなりません。ある種の無声映画の役者のように。
一段落
では、上で見たばらばらのセンテンスを一段落に復元します。
こうして安岡的「存在」の多くは、避けようとする身振りそのものによって、避けるべき対象と深く戯れてしまうというパラドックスのさなかに生きることになる。『月は東に』の冒頭のジェット機は、なんとか逢わずにいたい男が間違いなく待ち受けているはずの羽田空港へと、一直線に太平洋を越えてゆくではないか。だから、真に安岡的風土に置かれた存在は、逃げていたはずのものによって執拗に視界を立ちふさがれれるので、その目の前の風景の遠近法はたえず狂っていることしかない。そのときそこで息をつめ、瞳をふせ、足音を殺していることは、無防備のまま世界へと埋没していく溺死志願者の仕草にほかならなくなる。存在を希薄にする試みは、一変して外界の諸要素が最も深く体内に浸透する格好の身振りとなり、逃げるための足ならしは、かえって世界の中核部へと一挙に突入する準備運動になってしまうだろう。
バスター・キートン
ところで、蓮實重彥はバスター・キートン主演の『キートンの蒸気船』が好きらしいです。私は映画が苦手なので、話として聞いているだけですが。
私は上で引用した文章を読んでいると、なぜか、バスター・キートンの動きを思いだすのです。そっくりなのです。
関連記事
#読書感想文 #蓮實重彥 #蓮實重彦 #安岡章太郎 #文字 #映画 #バスター・キートン #パラドックス #小説 #文章 #笑い
