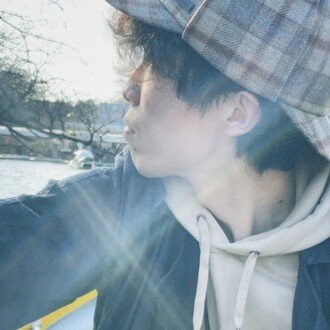【自己紹介】僕のこと、noteのこと、『創作生活』というマガジンのこと
こんにちは。宮澤大和です。
劇作家・演出家をしています。ふだんは、演劇の台本(戯曲)を書いたり、演劇の演出をしたりして生活をしています。「ぺぺぺの会」というグループに所属して、メンバーといっしょに演劇をつくっています。
「演劇のこと」については後日記事を発表いたしますので、よろしければご覧ください。
広くいえば創作活動全般に興味があって、書くことはもちろん、絵画、映画、音楽など、さまざまな表現形態から創作術を分析し実践してみる、ということをおこなっています。
僕のnoteではそうした創作術の分析と実践の軌跡をまとめあげて、記事にして発信していっています。
みなさまの創作活動にもなにか寄与することができたらいいなと思いながら一生懸命に書くことを心掛けています。
また、劇作家・演出家としての活動の一環として、人間の行為を「演技」という観点から考察して記事にもしています。僕がつくる演劇の「演技・演出論」はこんなふうにして今まさに体系立とうとしています。
演劇のことを書くときに業界の人にだけ通じる言葉遣いをするのではなくて、これまでにいち度も演劇を観たことのない人に向けて語り掛けるように書くのが、僕のnoteでのルールです。だから演劇をしている人が僕のnoteを見たら「もっと簡潔に書きなさいよ」と言いたくなってしまうのかもしれません。
でも、業界の内側で密な関わりあいを持つよりも、業界の外側で広い交流をするほうが自分の性にあっていると、最近はよく思うんです。また、そうした営みは結果的に演劇の裾野を広げることに繋がるんじゃないかと信じるようにしています。
更新した記事はすべて有料マガジン『創作生活』に保存していきます。更新後、1週間くらいは無料公開しますが、以降はマガジンを購読して読んでいただくことになります。
このような方針にしたのは過去の発言が良くも悪くもそれなりの価値と意味を持つんだということを知ったからです。なお、購読するとマガジンに保存されているすべての記事が読めるようになります。
そのほかにもマガジン購読者限定で「つぶやき」や「写真」なども投稿していきます。
みなさまにお楽しみいだけるように一生懸命頑張ります。創作に対してだけは、僕はつねに一生懸命です。
マガジンはこちらのページから購読することができます。
今日は、『創作生活』に保存している記事のなかでもとくに反響の大きかった10の記事を簡潔に紹介していきます。
① 『僕と祖父、とくべつの函館』
小説的エッセイです。Twitterでも拡散していただいてやや話題になった記事です。僕は、僕に近しい人のことやプライベートな心境をあまり書きものにしないので、こういう記事はめずらしいと思います。
②『文字を読む、言葉に触れるということ』
③『牛は角で捕まえるが、人間は言葉で捕まえる』
読むことと書くことについて、自分なりの考え方をまとめた記事です。どちらも僕の日常の大半を占める行為だし、創作を継続するうえでは欠かせません。『創作生活』に保存されているほとんどの記事は、読むことと書くことについての考察であったりするんだけど、そのなかでもこの2つの記事には、なんだか核心に迫ろうとする勢いみたいなものがあるような気がします。なんとなくだけど。
④「芸術に擬態させる」SNS上での誹謗中傷について
リアリティ・ショーの出演者の自死を受けて書いた記事です。時事的なことについて言及するのはあまりないことなんですが、ちょうどその直前に僕もTwitterをやめたばかりだったから、なにか共鳴するところがあって、「記事を書きたい」と思ったんじゃないかな、きっと。
⑤ フレンチレストランでの思索
すべてはフレンチレストランから始まる。ロッシーニに添えられたトリュフのかおりが思索のエンジンを回転させ始める。ここよりももっと甘美なところへと! 3つの断章が相関して織りなすコース料理のような文体をどうぞお楽しみください。
⑥ 開店前のブックオフに列びながら
行きたい場所へ自由に行くことのできない世界になるなんて、まさか思ってもみませんでした。ひとつひとつの瑣末な変化は集積し、やがて大きな変化へと繋がっていくんだろうな……なんて考えながら書いたnote記事です。
“人間には、自分が生きているいまこそが時代の転換点だと妄信してしまう癖があるらしい。いつだって何かしらの過渡期だ。”
⑦ どうしてアートをやるのかを改めて考える 〜オラファー・エリアソン『ときに川は橋となる』を観て
⑧ アートはわかりづらいか 〜オラファー・エリアソン『ときに川は橋となる』を観て
当時はまだ、自分はアートをつくっているんだという意識を持っていたんだけど、今はもうそんなもの打っちゃってしまいました。自分は一介の生活者でしかなくて、自分の創作は、生活のいち部分でしかない、と考えることができるようになってから、僕の文体は大きく変わりました。
⑨ エチオピアに暮らすゲラダヒヒ、日本に暮らす僕
エチオピアに暮らすゲラダヒヒっていうお猿さんから勝負の極意を学ぶ話です。勝つとは? 負けるとはどういうことだろう? 問いを出発点にして、ウイルスに打ち勝つこと/共存することについても考えています。自由な外出を制限されたコロナの世界での勝負論。
⑩ 脱-note記事
簡潔にいうと、「noteとはこういうものだ」という固定観念に縛られないで、書きたいことを書きたいように、無理のないやり方で続けていこうっていう話です。そのうえで、僕が気をつけたいこと、心に留めておきたい大切な指針のようなものを、記事にしました。
番外編:過去の自己紹介記事
2020年12月に書いた自己紹介用の記事です。こうやって読み返してみると、変わったことも変わらないこともあって面白いです。noteを書いて、過去を記録しておくと、未来の自分が迷子になりづらくなると思う。これからもできるだけたくさんの記事を書いていきたいです。
終わりに
ここまで読んでくださってありがとうございます。僕がこうやってnoteを書き続けられるのは、ひとえに読んでくださる方々のおかげです。また、僕が創作全般を続けながら生活できているのは、僕の周りでいつもサポートをしてくださるみなさまのおかげです。ありがとうございます。
僕はこれからも頑張りますので、今後ともよろしくお願いします!
マガジンはこちらのページから購読することができます。
今日も最後まで読んでくださってありがとうございます。 これからもていねいに書きますので、 またあそびに来てくださいね。