
◆読書日記.《塚本邦雄『新装版・ことば遊び悦覧記』》
<2023年7月7日>
塚本邦雄『新装版・ことば遊び悦覧記』読了。
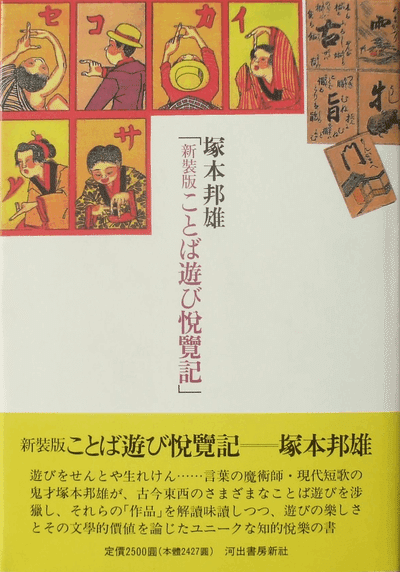
じっくりと鑑賞し、何故か7月7日の七夕の夜に読了するという風流な読書であった。
本書は現代前衛短歌運動の中心的人物であった歌人・塚本邦雄が古今東西の言語遊戯から選りすぐりの作を収集し、自作も交えながら紹介し、論じる内容。
いろは歌や回文、形象詩、文字鎖、幾何学形詩、輪形詩等の部門に分けてそれらに使われている技巧を実作と共に紹介しているのだが、一言、凄い。
頁をめくれば一目で分かるような技巧の数々を鑑賞する事が出来る。やはり貴族文化時代の教養人はレベルが違う。言葉を使った超絶技巧。
源順の「碁盤歌」「雙六歌」を見るだけで唖然とする。精緻な言葉のアラベスクという評が聊かも大げさでない事が何より凄い。
「ことば遊び」とは言うが、これほどの技巧、果たして「遊んでいる」等というイメージで語って良いものだろうか。
この辺の違和感を表明し、言語遊戯という「遊び」を芸術の範囲に含めない偏狭な見方に対する批判から、本書は始まっている。
そもそも、現代に至って「芸術」という言葉の意味する内容はほとんど定義が不可能になっており、また塚本も「「美」の抱合する意味は恐るべく多岐多様広範囲である(P.6)」と指摘している通りである。
「遊び」に芸術性がないというのは偏狭な見方だ。
技巧、テクニックに芸術性がないというのも頭が固い。
「芸術-エンタメ」の二項対立図しか頭にないのも単純だ。
「遊び」というのはルールが厳しければ厳しいほど、それを高度に守りながら芸術性も出すという所に面白みがある。
本書に取り上げられているような技巧を凝らした言語芸術というのは、ぼくにしてみれば日本の伝統工芸作品を思わせる美的感覚を覚える。
「伝統工芸」とは言っても、同じ形式の同じ型枠に嵌った作品を、全く同じように繰り返し作っていくのが「伝統工芸」ではない。
受け継がれるのは、長い年月をかけて繰り返し修練を詰んで研ぎ澄まされてきた「技法」であって、個人の「表現」まで受け継がれるわけではない。
伝統工芸もれっきとした「個人」の表現行為だ。
伝統工芸の凄い所は、年代を重ねて研ぎ澄まされた高度な技法を使って、芸術的な精神や哲学的な思想を工芸品の中に表現するという事だ。
だから、伝統的な技法を用いて現代的なテーマを表現した伝統工芸品など幾らでもある。
実際ぼくは、学生時代に公益社団法人日本工芸会の主催する日本伝統工芸展を見に行って、その多彩な表現力と高度な技術の融合で顕現する「美」に衝撃を受けたものである。
『ことば遊び悦覧記』に紹介されている超絶技巧も、その手の年代を経て研ぎ澄まされた「美」なのである。
人は、精緻に描かれた金箔の文様の乗る漆芸作品に感動するように、源順の作となる碁盤歌や雙六盤歌の精緻さに感動するし、あまりにリアルな伝統木彫作品に驚くように、いろは歌の技法に驚くのである。
「遊び」と言えど、「芸術」と言えど、職人的な「工芸品」と言えど、「ここまで徹底的にやれば真似したくても出来ないだろう?」というほど矜持を持って徹底的に技法を突き詰めて究めれば、その特別な精神性が美的意識を生み出すのではないかとも思うのだ。
本書が地口や早口言葉、しりとり等といった現在庶民でも気軽に楽しんでいる言語遊戯をとりあげていないのは、その手の作は一般的にも気軽に読まれている「ことばあそび」的な書籍にも良くとりあげられているからでもあり、またあくまで「鑑賞に堪えうる芸術」としての秀作しか、塚本が許さなかったという点も挙げられよう。
ただ単に「遊び」だからと言ってそれを「芸術ではない」とはせず、大衆的な娯楽物だからと言って「芸術とは違う」とは言わず、――だからと言ってその手の作品を広く緩めた範囲まで採ろうとは、決してしないのである。
だからこそ「美の鬼」たる塚本のような人間の厳しい選美眼に耐えうる作品のみが選ばれた本書のようなものの意味があるのだ。「批評」とは、ある意味「価値基準を示す」という事でもある。
しかし本書、この手の高度な技術を用いた言語遊戯に関する古今東西の実例がわんさと紹介されていて、その点でも圧倒される。
塚本の注釈だけを読み進めて行けば、さほど分量のある本ではないのですぐ読み終える事が出来ただろう。
が、高度な言語遊戯というものは、幾つも課せられた厳しいルールをちゃんと守った上で、通常の言語芸術と同じ抒情性も出さなければならず、その選りすぐりの上澄みだけを掲載しているのが本書なのである。
詩集や短歌集を読むという事は、小説の読み方とは全く違う。
立ち止まって詩の意味に思いを巡らし、古語辞典を開いて意味を確認し、ネットでドイツ語を確認したりして正確な内容を把握したら、そこから経ち現れる詩情にゆったりと身をゆだねて……と、もうしばしじっくりと本書の世界に身を浸していたかった。
が、本書の全ての作品を味わい尽くすには、少々時間がかかりすぎる。
けっきょく塚本が挙げている実作の全てを鑑賞しつくそうと思えば一か月くらいじっくりとこの本の世界に浸かっていなければならないと思い、かなりの作品は読み飛ばしてしまったのが惜しい所でもあった。
無論、読み飛ばした作品は今後も、折を見て本書を見返し、少しずつ、一つ一つ、じっくりと鑑賞する事になるだろう。
◆◆◆
実はそもそもぼくが近年、塚本邦雄を興味を持つようになったのは、本書『ことば遊び悦覧記』がきっかけともなっているのである。
何年か前の事、推理作家の竹本健治氏が、黒岩涙香を題材にしたミステリを書いてる等といった内容のツイートしていた時に挙げていた資料が、本作だったのである。実はその時点では、ぼくは塚本邦雄の存在を知らなかったのだ。
そして「黒岩涙香を題材にしたミステリ云々」と言っていたその作品が後年、ミステリ界で絶賛された名作『涙香迷宮』となったわけである。

竹本健治の最近の代表作と言えば『涙香迷宮』と言われる程なので、オタクなぼくとしては当然、このネタ本の一つとされる『ことば遊び悦覧記』にオタク的な興味を抱いたというわけである。
竹本さん、どうやらこの『ことば遊び悦覧記』の「いろは歌」の項目に題材を得ていたらしい。
出来れば『涙香迷宮』を読む前にこの『ことば遊び悦覧記』一冊は読んでおきたい。
という事でさっそく塚本邦雄のプロフィールを調べてみると、塚本の第一歌集『水葬物語』が中井英夫や三島由紀夫に絶賛された、とある。
中井英夫も三島由紀夫も、ぼくはファンである。この時点でぼくの興味は半ば以上決定づけられた。
この二人のお眼鏡にかなったという事は、趣味や美的感覚から言って、ぼくと全く無縁な所にある歌人ではないのだろう――とそう予想したのである。
しかし、この『ことば遊び悦覧記』もすぐネットを使って取り寄せようというほどまでに興味があったわけではなく、しばらくはユルく古本屋巡りをしている間に「塚本邦雄」の名のつく本で気になるものがあったら手にすればいいかな、程度の気分でチェックし始めた。
そして、過去の記事でもご紹介した様に、最初に手にした塚本邦雄の自歌講釈集『緑珠玲瓏館』を読んで、ぼくは塚本に徹底的にハマる事となるのである。ああ、やはりこの人は、中井英夫や三島由紀夫の系統の人なのだ、と理解したのだ。
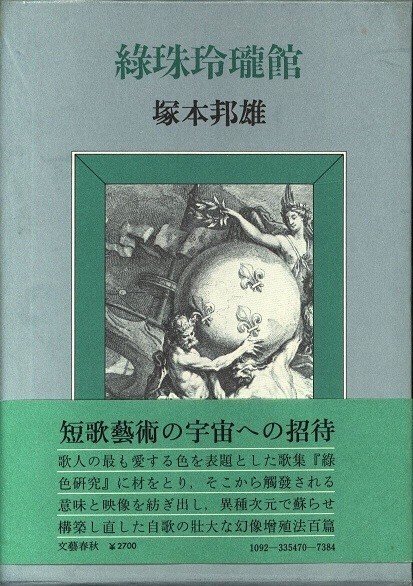
……ちなみに竹本先生、そういう縁があったからか、今年(2023年)さらなる新装版として河出書房新社から出された『ことば遊び悦覧記』の帯文も書いておられる。
因みにこの本、塚本没後18年に出版された書籍だというのに「著者の直筆サイン入り」なのだという。これも一つの謎。
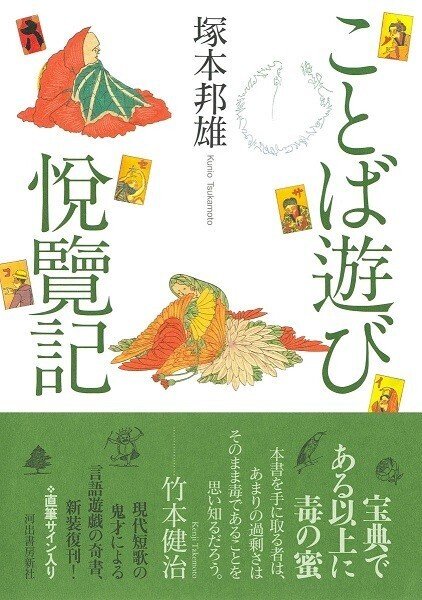
◆◆◆
「技巧を凝らした言語遊戯」と言われてもピンと来ない人もあろうから、念のため本書に掲載されている作品を少しだけご紹介しよう。
下の画像は『ことば遊び悦覧記』から写した。

スペインのオヴェエド市のサンサルヴァドール寺院入り口にある碑に書かれたラテン語の銘なのだという。
774年即位のシロ王の墓で上下左右だけでなく逆から下上、左右、という風にたどっても同文となり、中央のSから読み始めると270種の回読法があると伝えられる。
……といったように多かれ少なかれ「文字」のある文化というのは教養的な遊戯としての言語遊戯というのは存在していたようだ。
良く知られるように「ROMA(ローマ)とは、倒錯したAMOR(アモール=愛)の都である」という警句もあってアルファベットでも言語遊戯は高等な遊びの一つとしても知られる。
勿論、中国の漢詩による漢詩魔方陣も様々なバリエーションが存在している。

アルファベットや漢字など文字のスタイルが統一されているカリグラムは見かけも美しいが、日本語の場合ひらがな、カタカナ、漢字など文字スタイルが混在するというのが一つの難ではある。
そのため日本のカリグラムはひらがなを多くして、そのスタイルをスッキリと統一させているという方法を採っているものも見受けられるようだ。
◆◆◆
こちらの画像も『ことば遊び悦覧記』から写した。
源順の作による碁盤歌、雙六盤歌などの技法に倣って18世紀の小沢蘆庵が作ったものらしい。

いずれも縦、横、斜めに短歌を配して交わる一文字を全て一致させる。この技法を「八重襷」と言った。現代ではほぼ見られない技法だが、一目でわかる凄みがある。
源順の碁盤歌は更に手が込んでいて物凄いのだが、これを写しても文字が小さくなりすぎてWebの画面上では文字が潰れて見えそうにないので写さなかった。
源順の碁盤歌は「田」の文字を四つ並べた骨格を持っており、その形はカリグラムの意も込められており、掲載作は全て「田植草紙系歌謡群」でしめられる。
「田」の字のそれぞれの四つのマスにも一首ずつ短歌が入れられており、それぞれ春夏秋冬の田歌然とした歌となっている所が誠に手が込んでいると言えよう。
これはそのまま縁起物としても贈答品としても格調高い。
◆◆◆
<付:回文短歌を作るポイント>
『ことば遊び悦覧記』にとりあげられている回文和歌の技術は凄い。
五七五七七の和歌の形に整える回文で、更にその歌に詩情性もなければ評価されない。短歌としても、回文としても、両方とも鑑賞に堪えうるレベルに達していなければならない。
本書では、その厳しい基準にパスした秀歌の実例を20も30も贅沢に掲載し解説しているのだが、これだけの例歌が分かればある程度の法則性も見えてくる。
という事で特別に、ぼくが個人的に本書を読んで学び取った<回文短歌を作るポイント>を以下、軽くレクチャーしてみようと思う。
例えば日本では「回文」はそれだけで昔から「縁起もの」とされていて、例えばその最も有名な回文短歌に「長き夜の遠の眠(ねぶ)りの皆目覚め波乗り船の音のよきかな」という作品がある。
この回文短歌は正月の初夢のまじないとして使われていたと言われていて、宝船の絵にこの短歌を書いて枕の下に入れておくと縁起の良い夢が見られる等と言われていたのだそうだ。
この一首を見るだけでも回文短歌のポイントが分かる。という事でレッスン・ワンである。
「長き夜」と「よきかな」という、引っ繰り返して読んでも意味が通る言葉のストックが豊富な人ほど回文は作り易い。
言葉を聞いたら、すぐ頭の中で引っ繰り返して逆から読むといった訓練が出来ていると、こういう思考になる。回文短歌を作りたいと思う方は、こういった思考のクセをつけておくべきかもしれない。
少なくとも、いちいち単語を紙にひらがなで書いてから反対に読んでいては、わずらわしくてとても実作を作るまでには至らないだろう。
それと、これには語彙力がなければ、この手の逆から読んでも意味が通じる言葉のバリエーションは豊富に持つ事ができない。
日常語だけではない。草花草木、地名、天候、時候、等々語彙があればあるほどバリエーション豊かな回文を生み出せる。これは、短歌や俳句を作る時も全く条件は同じだ。
因みに、回文には短歌だけでなく俳諧や連句といったものも作られている。
例えば、連句であれば「眺めしは野菊の茎の始めかな」という五七五の長句がまず単体で回文になっており、それに答える七七の短句も「咲く花は咲く草花は草」と回文となる。そして連句であれば当然、両方で通して意味のある一首となるという仕掛け。
で、ここでもう一つのポイントが、上の例句にも出てきた「草=咲く」のワンセットは、昔の回文短歌でも割と見かけるものだという事。
同じ自然に関わる単語なので使い易く文字調整としても使われたのだろうと予想される。
こういう便利な回文単語セットを多く持っている人も有利だ。
短句の「花は」のほうも「はなは」と、短い回文になっていて使い易い。「咲く花は咲く草花は草」という短句はちょっとズルイ感じがしないでもないが、この場合流れにマッチしていてリフレインが素直で耳ざわりも良く、瑕疵というほどにまではなっていないという点は巧い。
回文はどうしても五七五七七の定型に乗せるという枠が嵌められているし、単語を引っ繰り返すと、普通の短歌としてはぎこちない口調になりがちになってしまう。
本書を読んでいて気付いたポイントの一つは、古文調にするとこの手の違和感はかなり和らぐという点であった。現代文、それも口語調での回文短歌はかなり難しいのではないかと思えてしまう。
古文調にするメリットにはもう一つあって、古文のルール上「ん」がイコール「む」として使えるという条件が、現代文よりも有利なのである。
これは「ん=む」だけでなく、「ふ=う」であったり「い=ひ・ゐ」であったりと、回文として単語を引っ繰り返した場合に有利に働くひらがなが多いという点も挙げられよう。
さて、サーヴィスでもう一つ回文を作るポイントをお教えしよう。そして、この点が、ぼくが「回文の作り方の最大のポイント」だと思っている点である。
まず例歌を一つ――「白雪は今朝野良草の葉にもつも庭の桜の咲けば消ゆらし」。これをひらがなにして見てみよう。
「しらゆきは けさのらくさの はにもつも にはのさくらの さけはきゆらし」
この例句の以下の部分にご注目頂きたい。
「●●●●●● ●●●●●●● ●●〇〇〇 ●●●●●●● ●●●●●●●」
――五七五七七のこの並びのうち、三句めの下三文字(白丸になっている所)が重要なのである。これが必ず回文の「折り返し地点」となるからだ。
この三文字が必ず「ABA」というパターンとなる。上にあげた例句だと「もつも」の部分である。
もう一つ例歌を挙げよう――「湊川とま覗きつつ廻りけり濱つづきその窓は門(かど)なみ」。
「みなとかは とまのそきつつ まはりけり はまつつきその まとはかとなみ」
この例を見ても三句めの下三文字が「廻りけり」――「りけり」という形になっているのがお分かりになるだろう。
この「折り返し地点」をどう設定し、どうさり気なく作るかで、回文らしいぎこちなさを見せない回文を作る事が出来る。
以上、ぼくが塚本邦雄の『ことば遊び悦覧記』を読んでいて理解した「回文短歌の作り方」のポイントの一部である(さすがにこのレクチャーを一から十まで全てお教えするとなるとお金を取って授業が出来るレベルのものになってしまうので、この場はここまでにしておこう)。
最低限これだけヒントがあれば、恐らく皆様もチャレンジしようと思えばできるだろう。ご興味がある方は、まずこれで挑戦してみては如何だろう。
因みに、こういった「作り方」というものは評論・歌論と無関係ではない。
何よりまず「回文短歌とはどういった作品なのか?」という謎が解明できなければ、鑑賞者はその作品を前にただ「凄い」とか「面白い」としか言及できない。
その構造を示し、その技法を解説し、その創作法を推測してみて初めて見えてくる作品の側面というものがある。そこで初めてその作品に込められた技法レベルの程度も判断が出来るようになってくる。
そういった方法で明かされる作品の秘密を提示して見せるという事も「評論」の一種であると、ぼくは思うのである。
