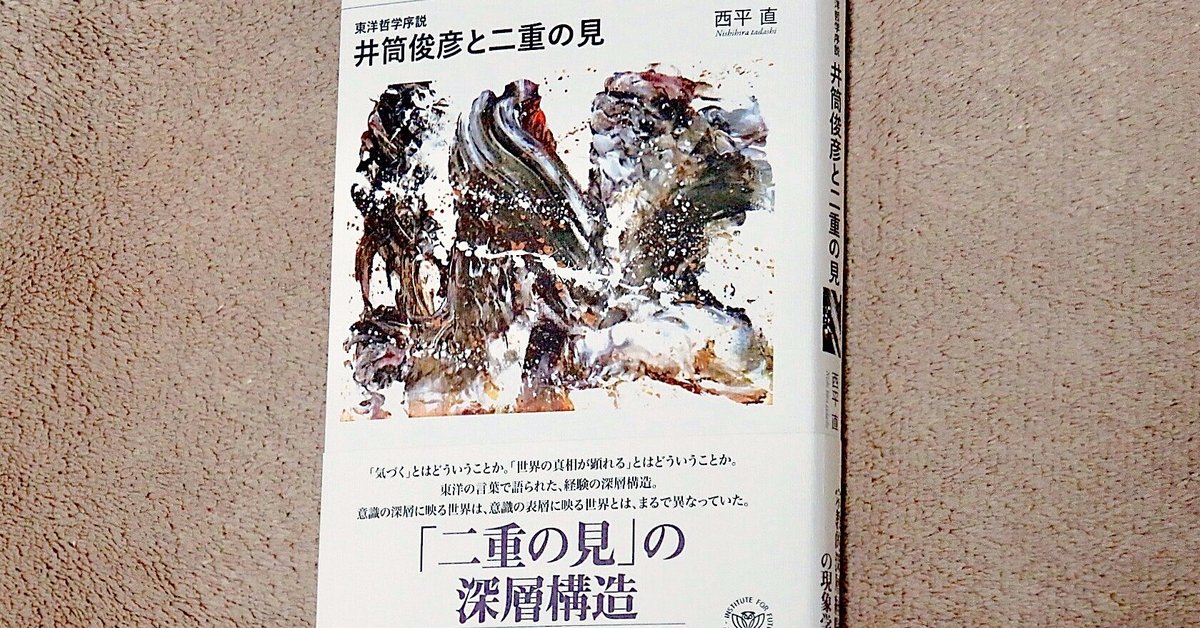
西平直『東洋哲学序説 井筒俊彦と二重の見』
☆mediopos-2298 2021.3.2
私たちが世界だと思って見ている世界は
ほんとうの世界ではないかもしれない
まずそのことから考えはじめる必要がある
ほんとうの世界を見るために
禅は井筒俊彦のいう「二重の見」を獲得し
「分節と無分節の同時現成」として
世界をとらえようとする
私たちはふつう
山は山であり川は川であるというように
世界はその見たままだと素朴にとらえている
禅はまずその分節化された世界を解体し
山は山でなく川は川でないとする
無分節のリアリティを獲得する
そのうえであらためて
山は山であり川は川であるとし
解体された存在を再獲得するのだが
そのときそれは
素朴な実在として分節化された山でも川でもない
山も川もそれぞれの自性をなくしたまま
山であり川であるのだ
その見を「二重の見」という
ふつう山は山であり川は川として
あらわれているように見えている世界は
それらの存在の根底においては
ほんとうは分節化されていない
まずそのことに気づく必要があるのだ
そのように
私たちの意識や言葉といった現象世界もまた
ふつうは疑いもなく分節化されて
あらわれているように見えるが
その深層においては分節化されてはいない
「存在の絶対的根源」には
絶対無分節である「コトバ」があって
そこから存在は生成してくる
もちろんその「コトバ」は
ふつう私たちの使っている「言葉」ではない
その「存在の絶対的根源」を禅は「無」といい
真言密教は「真言」というが
両者には存在生成のプロセスのとらえ方に違いがある
密教は意識の深層にあるプロセス
分節と無分節の間に
言語生成以前にある象徴化の機能を持つ
「イマージュ」領域を位置づけるが
禅はその領域を妄想として排除するのだ
こうしたことについては
井筒俊彦の著作のなかでも本書でも
詳しく論じられているのだが
本書であらためて興味深く感じたことについて
若干記しておくことにしたい
まず「詩の言葉」についてである
ほんらいの「詩の言葉」の働きは
ある意味で「二重の見」が前提となっているのではないか
その言葉は決して日常言語による分節化されたものではない
その意味ではやはり「詩の言葉」は
口語的な分節化された言葉だけでは
ほんらい的な詩的機能を持ちえないのではないか
さらに「あとがき」でも示唆されているのだが
「身体」についての問いである
井筒俊彦の論じたことは基本的に「意識」や
存在の根源にある「コトバ」についてであって
「身体」については語られていない
そのテーマを問題にするにあたっては
まさに東洋と西洋の相違や共通するありようを
「修行」においても考慮していく必要があるのではないか
ちなみに著者はふれていないが
井筒俊彦の論は基本的に
意識とそこから生成する存在へのアプローチだが
そこには「自然学」がまったく存在していない
存在の根源にある「コトバ」は
いかにして「自然」を生成してきたのか
私たちの意識からとらえられた分節と無分節と
「自然」とは具体的にどのように関連づけられるのか
そのテーマを具体的に展開しないで
世界は語れないのではないか
そんなこともさまざまに考えさせられる
非常に示唆的な一冊となっている
■西平直『東洋哲学序説 井筒俊彦と二重の見』(未来哲学研究所 2021.2)
「井筒は、禅師(青原惟信)の言葉に即して、修行(意識変容)の「三段階」を示した。その「第三段階」に「二重の見」が登場する。「二重の見」は、<区切る(分節)>と<区切らない(無分別)>とを、二つながら同時に機能させる。そこで「分節と無分節の同時現成」とも語られる。そのように示された禅モデルが現象学と重なる。現象学も「存在解体」と「その後(存在再獲得)」を語る。現象学が「存在の再獲得」と理解した出来事を、本書は、井筒に倣い、「二重の見」と呼ぶ。」
「「二重の見」を論じるにあたり、井筒は、中国・宋代の禅師、青原惟信の言葉を引用した。禅師が自らの人生を振り返って語ったという。
三十年前、未だ参禅せざる時、<山を見ると山に見え、川を見ると川に見えた>。ところが、優れた師にめぐり遇い修行して悟りに至ると、<山を見てもそれは山ではなく、川を見てもそれは川ではなかった>。ところが悟りが深まり、安心の境地に至った今は、また最初と同じく、<山を見るとただ山であり、川を見るとただ川である>。
つまり、「山は山である」ー「山は山でない」ー「山は山である」という三つの段階。しかし、二回目の「山は山である」は、特殊な二重性を秘めている。」
「第二段階は、無分節のリアリティ。分節が消え、区別が消える。」
「第三段階(・・・)再び、区切りが戻る。山は山、川は川。(・・・)この山や川には区切りはもどるが「固定した実体」は戻らない、という。山と川は区別されるが、互いの関係を豊かに残している。華厳が「事事無礙」、あるいは「縁起」と語るのはこの場面である。区切りが固定されない。この「区切り」を仏教の伝統は「自性」と呼んだ。第三段階の事物は自性に縛られない。「無自性」である。「分節は戻るが『本質』は戻ってこない」。当然「見る私」も戻ってくるのだが、しかしやはり「無自性」である。「山と一体である自分」でありつつ、同時に「(山を)見る」。あるいは、「山と一体となった自分自身」に特殊な仕方で「気がついている」。」
「「詩のことば」はその両面を捉える。その上で、井筒は、重要な指摘を残している。「無分節」はあらゆる言葉の内にも顕れるというのである。」
「「詩のことば」においては、いかなる言葉の内にも「無分節」は顕れる。正確には、いかなる「ことば」も、そのつど「新たに分節する働き」を担当することができる。「第三段階」における「ことば」を、井筒はそのように理解した。「二重の見」における「ことば」の機能である。」
「ある講演のなかで井筒は、禅の言語について語りながら、「言語の本源的な働き」を次のように語っていた。言語を発することによって「山」が成り立ち、「意識」も発生する。」
「絶対無分節は、言語とは無縁である。根源的非言語である。ということは、絶対無分節の自己分節とは、根源的非言語が自己分節することによって、個々の語となり、それらの語が、それぞれ個々の事物を現成させるということである。その出来事を、井筒は、言語を発することによって「山」が成り立つ、という。意識が発生するという。そして「山を意識する私」の「意識」として統一され、「山」が現成するという。」
「井筒によれば、これが言語の本源的な働きであり、禅は、すべての語がこうした仕方で使われることを要求する。「全ての語がコトバの直接そのままの顕現としての自覚において話者によって発せられ、またまさにそのよううなものとして聴者に受け取られることを要求します」。
「無」は「根源的言語」である。しかし、「コトバ」である。「永遠のコトバの創造的エネルギー」である。いまだ分節されていないが、しかし常に自己を分節し続けてゆくエネルギーである。そして、コトバが自己分節することによって、「意味」が呼び起こされる。コトバが意味を喚起する。のみならず、コトバが、意味を通じて、存在世界を現出させる。コトバが、世界を、存在させる。
井筒は、「言語的意味の存在喚起機能」と呼ぶ。」
「こうした「コトバ」の機能において、井筒は、真言密教に注目する。」
「井筒が注目するのは、「コトバを超えた領域」である。密教においては、「コトバを超えた」領域も、次元の異なるコトバで語り得る。「真言」である。」
「実は、コトバを超えた世界が、それ自体、特殊なコトバであったということである。「悟りの世界そのものの自己言語化のプロセスとしてのコトバ」。
そして、そのプロセスが「同時に存在現出のプロセスでもある」。悟りの世界が自己を言語化する。そのような特殊な「コトバ」。つまり「真言(まことのコトバ)」が世界を創出する。あるいは、世界は真言によって創出された。「存在の絶対的根源としてのコトバ」である。」
「密教モデルは意識の深層に「中間領域」を設定した。禅モデルはそこに目を向けない。禅はその「イマージュ」領域を妄想として排除したきた。
井筒の「構造モデル」における「中間領域M」は象徴的なイマージュに満ちていた。私たちの日常意識から見れば、意識の深層である。ところが、それは絶対無分節の側から見れば、絶対無分節がその内部において自己展開する場である。」
「やり残した課題は多い。
例えば、「身体」の問題。井筒は身体を語らなかった。しかしその論考を、身体の出来事として、読み換えることができるのではないか。東洋の伝統思想は身体の変容を伴った。身体があるから制約される。しかし、身体があるから可能になる。とすれば、「イマージュ」と語られた中間領域を、身体の出来事と読むことができないか。あるいは、「事事無碍」の「事」を「身」と読む。「間身体性」を「事事無碍」として読み直す。縁起の中の身体、もしくは縁起の出来事としての身体。
ちなみに、西田哲学の中に「日常的身体」と「場所的身体」とを認めた湯浅泰雄は、前者から後者への移行を「修行」と理解した。その話と井筒の理論を重ねてみると。修行を介して、禅モデルと密教モデルが同時に機能する立体空間が拓けてくるのではないか。
もうひとつ、「異文化理解」も課題である。井筒は「コトバ」を表層と深層とに区別した。深層のコトバは、人々の意識の深層で、「生成的ゆれ」の中にある。とすれば。「コトバ」の違いは、表層における言語システムの違いだけではなく、深層における「生成的ゆれ」の違いでもある。井筒は書いていた。「二つの違う言語共同体のなかに生まれ育った人々は、それぞれの言語に特有の意味生産的想像力の違いに従って、二つの違う『世界』を見、二つの違う仕方で『現実』を経験しているものと考えざるをえない。
言語はそれぞれ異なる「意味生産的想像力」を持つ。その「想像力」の違いによって、世界が違って見える。表層の言語(ラング)の違いだけではない。意識の深層における「意味生成」のプロセスが違う。まだ明確な輪郭を持たない「意味可能性」の「生成のゆれ」が違う。その違いによって異なる「現実」が体験される。そうした位相も含めて「異文化」を考えたい。しかも、言語を習得する以前の子どもたちが、各々の言語を習得し、それによって、その共同体にふさわしい仕方で「世界」を見る見方を習得してゆく。そうしたプロセスを重ねて考えてみたいと思っているのである。」
