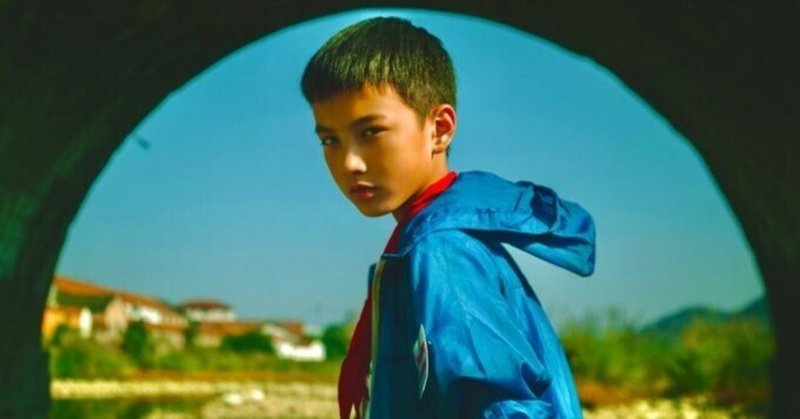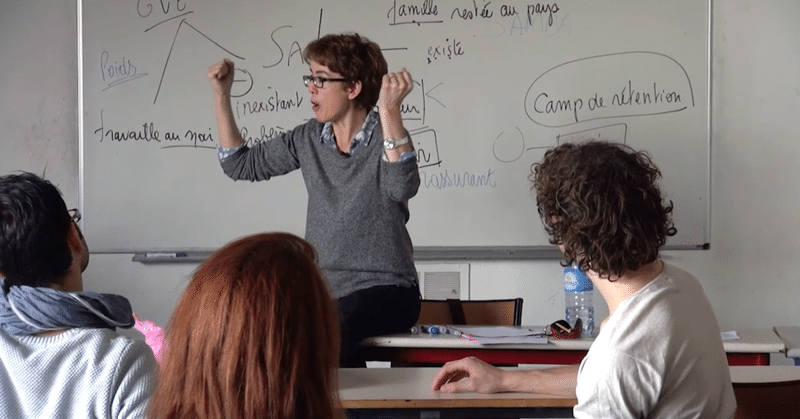#映画評
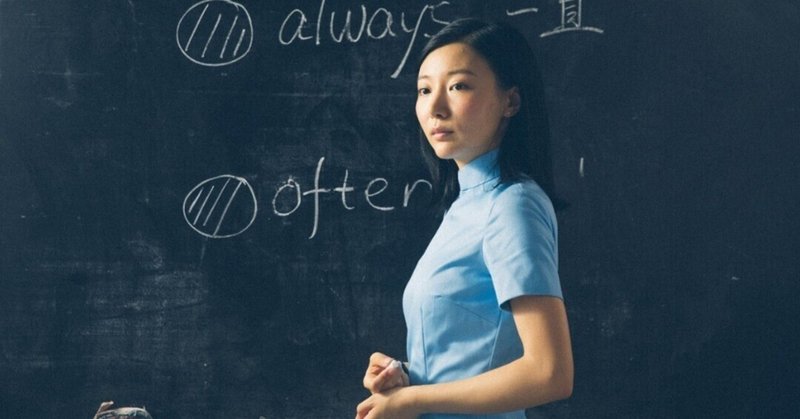
七人楽隊(監督:サモ・ハン、アン・ホイ、パトリック・タム、ユエン・ウーピン、ジョニー・トー、リンゴ・ラム、ツイ・ハーク/2021年)
香港は国ではない。中国の一部(特別行政区)である。第2次世界大戦のときには日本軍が占領したこともあるが、近代史から現代史の範囲に到るまでイギリス統治下にあった場所。しかし、もう私には1997年の返還後の記憶のほうが長い。経済的な繁栄を謳歌しつつ、一国二制度という奇妙な仕組みを与えられた、国のようで国ではない場所。一度も訪れたことはなく、子どものころテレビで見たジャッキー・チェンのカンフー映画と、TM NETWORK『Get Wild』のMVでメンバー3人があてどなく歩く背景、