2024年7月の記事一覧

「"音楽"と"パンク"とは人それぞれ意味が違う」 Interview with Ryan, 2013 (Meatcube Label, ex.Cease Upon The Capitol,Sanctions)
この記事は2013年に行ったMeatcubeレーベルを運営し、Cease Upon The Capitol,Sanctionsのメンバーでもあったライアン氏にインタビューしたものをリライトし公開したものです。日本への愛の溢れるコメント、そして音楽を世界にシェアしていこうとする行動力に心からリスペクト覚えました。 3LA : レーベルを始めたのはいつですか? Ryan : もともとディストロを始めたのは2003年、枚方にある関西外大での留学を終えてアメリカに帰った後だね。

世界で一番レコード店の多い街は渋谷ではない件:The fact that Shibuya is not the city with the most record stores in the world
世界で一番レコード店の多い街は渋谷ではない件 「世界で一番レコード屋の多い街は渋谷」とよく言われてきた。「ギネスブックにも載った」とも言われてきた。しかし、そのギネスブックの記事をいまだに見たことがない。私の検索方法が悪いのかもしれないが、あれば見てみたいものである。 そこで実際に1991年から2023年まで「レコード+CDマップ」で国内のレコード店密集地域の店舗数で調べてみた。(1990年、2006年無し、2014年以降隔年) すると、2000年、2001年の新宿エリア(
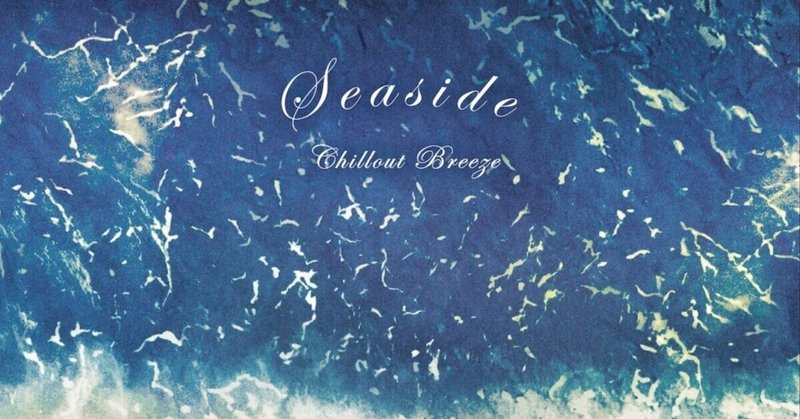
橋本徹(SUBURBIA)×山本勇樹(Quiet Corner)『Seaside Chillout Breeze』特別対談
V.A.『Seaside Chillout Breeze』 海辺でチルアウトしながら心地よい風を感じるようなとっておきの快適音楽を集めて山本:「Chillout Breeze」というタイトルで、新コンピ・シリーズが始まりますね。 橋本:そうですね。「Incense Music」シリーズと同じく、FJDのアートワークとCalmのマスタリングですが、コンセプトは違っていて。もともと「Incense Music」のリリース・レーベルのオーナーからオファーを受けたときは、僕が20























