
540.自分の書いた本がどのような財産権として主張できるの?【出版論第2章】新シリーズ「著作者になる!⑲」

1.自分の書いた本がどのような財産権として主張できるの?
著作権の中には著作者の人格権を傷つけてはならぬという「著作者人格権」があることがわかりましたね。そして著作権の中のもうひとつの権利が「財産権」。「著作財産権」と呼んでもよいかもしれません。
「自分の書いたものが財産なの?」
「どうして財産になるの?」
ならば、
「いっぱい文章を書き残したら物凄い財産家になってしまうじゃあない?」
「そんなの変だよ!」
という人もいます。
では、一般的に懸賞付きで募集している作品展や、コンテストなどはどうでしょう。ほとんどが賞金もしくは賞品となっているでしょう。
これは、働いたひとへの対価でもあります。
作家でいえば著作権使用料、印税としていただける立派な財産といえます。
別に文章だけではありません。
アルプス岳や穂高の山に登って貴重な写真を撮れば、それが何万円、何十万円になる可能性もあり、スクープ写真などはまさに高いお金で買いとってもらえるものです。
そして、プロだからといってだれもがスクープ写真や映像を撮れるわけではありません。写真などはまさにシャッターチャンスの世界であり、その瞬間は撮影した人、著作者に権利があるものです。俳句や短歌、詩なども同じです。
小さな子どもが描いた絵でも、どうして賞金や賞品が出るのでしょう。
コンクールに入賞、一等、二等があるのはなぜでしょう。
やはり、目標がある人は一生懸命になって燃えるものですし、わずかでもお金をいただくことは嬉しいはずです。
このときが一生懸命やったあとの報酬というものかもしれません。
たとえば挨拶文を人に頼まれます。
最初は親切で無料でやってあげていたとしても、評判がよく、だんだんと頼まれる量が増えてきました。
困ったもんです。
なぜなら、仕事もあるし生活もある。
喜ばれるのは嬉しいけど、仕事に差し支えてしまう。どうしよう。
でも、1枚1000円でも2000円でもいただけるなら、どうでしょう?
やりがいや報酬をもらう喜び、認められる喜び、報われて、さらにパワーアップしないでしょうか。
もし、すべての創作がタダであれば、人に創作意欲など湧きはしないでしょう。別にお金だけの問題ではありません。
相手の感謝の度合いが高ければ、多ければ無償でやっても喜びという報酬を受け取ることはできます。
また、このようなことをまるっきりタダでやらせ続ける人は逆に冷たい人です。
わたしはタダで人に頼めません。
人は不思議なもので、アルバイトすれば時給800円、1000円ともらえます。
しかし、このような知的労力に関する評価は、まるまる十時間かかってしまったとしても、1000円、2000円支払うことに頼んだ人間は抵抗があるようです。
でも、それは大きな誤りです。
そんな人は思いやりのない、相手の気持ちのわからない、エゴイストです。頼まれてやる方にも問題はあるかもしれませんが…。
著作物は創作した人の人格を傷つけてはならぬ法律です。
著作物は創作した人の「大切な財産権」です。
もし、無断で使用されたら訴えましょう。
もし、他人に差し上げたものでも、勝手に利用したら訴えましょう。
もし、お金をいただいたとしても、勝手に改変されたら訴えましょう。

2.「著作者」になるとこんなメリットがあるぞ!
ほとんどの人が著作者のメリットを知らない。
ほとんどの人は著作者になるとメリットが生まれる。
これまでも説明しましたが、著作者に無許可、無断で勝手に利用すれば著作権侵害または著作者人格権侵害として訴え、請求すると損害賠償金を受けとることができます。
これも財産権のひとつで、民事的措置によって、差止請求権、名誉回復措置権、不法行為による損害賠償請求、不当利得返還請求権があり、刑事的措置の刑事罰(三年以下の懲役又は罰金)、平成17年1月1日施行(5年以下の懲役若しくは500万以下の罰金)により、懲役と罰金を併科することもできるようになりました。
法人に対する罰金は、法改正(平成17年1月1日施行)により、1億5000万以下の罰金刑となり、非常に重いことがわかります。
わたしたちは、たとえ無名であろうと、素人であろうと、文章や絵が下手くそであろうと、小さな子どもたちの描いた絵であろうと、これらの法律は適用される。
著作権は、その著作物を創作した人をだれでも保護する法律です。
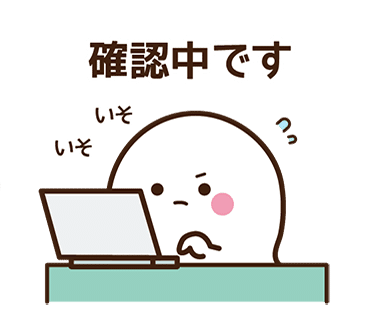
3.他人の資料やデータの利用の仕方
これまでもいいましたが、引用が一番該当するのは文章を中心とした活字関係です。しかし、ホームページ、ブログ、note上となると少しむずかしくなります。
たとえば、絵や写真はどうなのでしょう。ホームページと一般印刷媒体(書籍や新聞、雑誌)の大きな違いは、一般印刷媒体は著作権や著作者人格権の複製物が基本となっているが、インターネット、SNS等のホームページ、ブログnoteは著作物の有線送信に当たるため、著作権の複製と有線送信の二つの規定があることを考えなければなりません。
まず、SNS等、ホームページ、ブログ、note作成のための複製は私的利用の範囲には一切含まれない。
つまり、個人的な趣味ということにはなりません。
「個人的」とは私的という意味でありごく少数といわれる家庭内の使用といわれていますが、ホームページに掲載するということは不特定多数の人に情報を与えると考えられます。したがって、営利目的でなく非営利であっても著作権者の許諾が必要となります。(又は「引用の定義」にあてはめたものであれば問題はありません)
これは、著作物の有線送信について著作権法第三十条以下には規定がないため必ず許諾が必要となるということです。
では、絵や写真を引用するというときはどのような条件を満たせばよいのでしょうか。引用という以上、第一に引用の目的が社会慣行に適していなければなりません。批評や研究の名を借りた盗用や借用ではなりません。
つまり、正当な批評であり、研究であると社会的に見ても「引用」が必要だと考えられるような場合でなければならず、批評、研究の名を借りた鑑賞目的のものや、その物を売るためのものというのは一切認められません。
第二にその引用の範囲は「正当な範囲」でなければなりません。
それは、「引用」の部分があくまでも従でなければならず、主は批評、研究でなければならないということです。また、絵画や写真はその一部分を切って利用すれば著作者人格権の中の同一性保持権の侵害行為になります。
では、その引用部分に関する主従関係の判断はどうなのでしょう。
たとえば、主たる文章は自らが制作し、ホームページ上の画像に小さくその写真や絵を掲載する。しかし極めて有名な作品や画家のものは、たとえどう扱ってもそれが主たるものになってしまう怖れもあります。このようにたとえ引用と思っていても、客観的に引用されないこと事がほとんどといわれているため著名な絵画の引用は要注意といえます。

4.引用のための出所明示の方法
(A)書物からの引用の場合(学術論文の出所明示)
①著者の姓名 ②著作の表題および副題 ③出版社名 ④出版年 ⑤頁
(B)雑誌論文からの引用の場合
①著者の姓名 ②論文もしくは章の表題 ③雑誌の表題 ④巻及び号数⑤年
月 ⑥頁
「出所明示」は著作権法では義務とされ、これを怠ると30万円以下の罰金が課せられます(著作権法第三十二条)。
引用にはこの著作権法上無断でできる「適法引用」と、他の著作物の抄録、要約、利用まで含めていわれる語向上の広義としての「引用」もあり、この「適法引用」の出所明示は法的に義務条件となっています。
この適法引用の表記は、文節の直後か、後か、章節の後。よく見かける「参考文献」などは、章の後か、巻末。許諾を受けた著作物は、扉裏ページか、巻末。日本では巻末が多くみられます。
(C)孫引き引用の場合(二次文献の引用)
学術論文の世界では原則として一次文献にあたるべきといわれていますが、すべての必要文献が一次文献にあるわけがなく、信頼できる二次文献資料があればそれをもとに引用できる場合もあります。
その場合は、引用の個所の直後に一次文献の出所明示をして、そこに注の表記をします。そして、文節の後か章節の後の注に二次文献を明記するのが一般的です。
「実際に自分で裁判をやってみればすぐにわかることだが、裁判というものはとにかく長い。簡単な内容の裁判ならば決着も早いのだが、早いといっても一年はかかる。早い裁判というものはどのようなものかと言うと、それはたとえば、養親と養子の親子が、離縁届けを出して親子関係を解消したのに、後になってそれを争う場合である」
(『裁判の秘密』山口宏・副島隆彦著、宝島社文庫 1999年5月日 第1刷より
これは一次文献の例としての引用箇所。このように「 」をつけることによって、主たる文章と引用の部分を明確に区別し出所を明示します。
また、引用部分の前後を一行ずつ空けるか、文字の大きさや書体を変えたりする方法もあります。
このように区別してわかるようにしなければなりません。
そして最後に著作者人格権の「同一性保持権」を守る。つまり、原文、原画のままで勝手に手を加えたり、部分的に自分に都合のよい部分だけ引用し、他社に誤解を与えることもしてはなりません。
続く~
文字数5,336文字

※さて、毎回、過去作品ですが。「noteと著作権・noteの著作権」として、お役に立ちますよう5作品ずつご紹介いたします。もうすぐ600作品超えてしまうとバックナンバーから消えてしまいますので、(自分の「記事」には残ります)消える前に5作品ずつ掲載することにしました。その後は過去記事のバックナンバーマガジンを作成して保存します。それまでお時間がありましたら「著作権の基本編」をお読みください。みなさまのお役に立てば幸いです。

ラインスタンプ新作登場~
「noteと言う世界」第3章書くnote「出版論」シリーズを始めました。どうか引き続きお読みください。
また、日々、拘束されている仕事のため、また出張も多く、せっかくいただいているコメントのご返事。お問い合わせメール、お手紙等のお返事がかなり遅れています。しかし、必ず読ませていただいていますのでどうかお許しください。
では、また(月)(水)(金)にお会いいたしましょう。
いつも読んでいただいて心から感謝申し上げます。

※本内容は、シリーズ「noteの世界」というテーマで著作権等を交えて解説、感想及びnoteの素晴らしさをお伝えしていく予定です。
私たちの著作権協会は市民を中心としたボランティア団体です。主な活動は出版と講演会活動を中心として全国の都道府県、市町村の「著作権・肖像権・SNS等を中心」にお伝えし続けています。皆様から頂いた問題点や質問事項そのものが全国で困っている問題でもあり、現場の声、現場の問題点をテーマに取り上げて活動しています。
それらのテーマの一部がこのnoteにしているものです。ぜひ、楽しみながらお読みください。
noteの世界は優れたアーティストの世界です。創作した人たちにはわからないかも知れませんが、それを読む人、見る人、聴く人たちがリアルに反応してくれる場所です。もし、本格的なプロの方々が参入してもこの凄さには勝てないかもしれません。プロもマネのできないnoteの世界。これからも楽しみにして皆様のnoteを読み続けています。
私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な思いをお伝えします。
本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
特定非営利活動法人著作権協会
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
著作権noteバックナンバー👇見てくださいね~
Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
