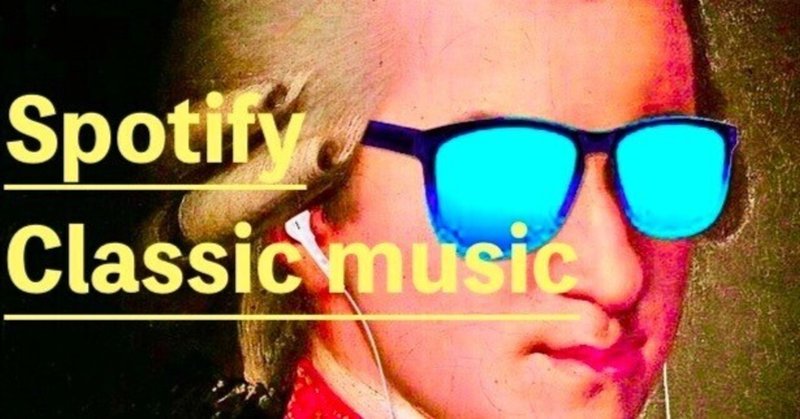#ベートーヴェン

究極のベートーヴェンを聴いてきた話。The story of listening to the “Ultimate” Beethoven.
2024年8月12日(月・祝日)、「辻井伸行×三浦文彰 ARKフィルハーモニック 究極のベートーヴェン」@RaiBoC Hall さいたま市民会館おおみや(主催:さいたま市文化振興事業団)を聴きに妻と娘とともに行ってきました。クラシック等の音楽については完全に素人ですが、素人目線で感じたこと、学んだことを noteに残しておきたいと思います。 On Monday, August 12, 2024 (national holiday), I went to listen “N