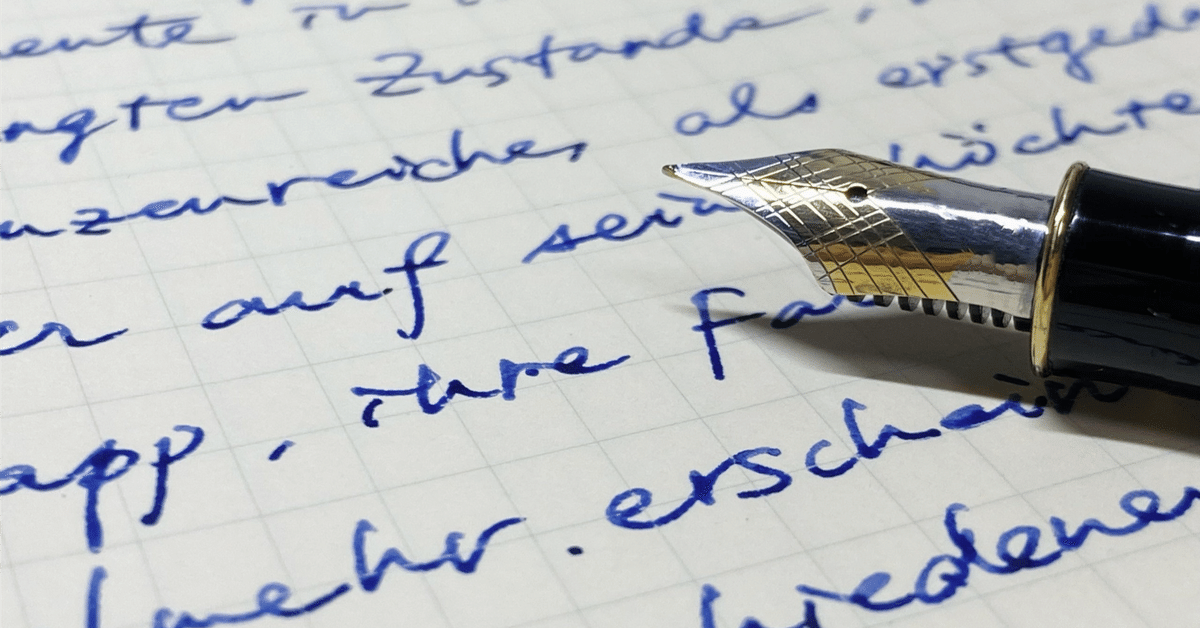
「文字」について
こんにちは。
いつも、ありがとうございます。今回は前回の「ツァラトゥストラ」の所でさくっと触れた、解説とあとがきで思ったことを心行くままに書いていきます。
ツァラトゥストラの文字はこれまでのものとはまるで別物でした。
あとがき編
どんなことでも気持ちのいいことは、もう一度やりたいと思うはずだ。「これが生きるってことだったのか?よし!じゃあ、もう一度!」。「神は死んだ」と言われても、快感は神様からのほうびである。「人間は、存在するようになって以来、喜ぶということをしなさすぎた。それこそが、兄弟よ、俺たちの原罪なのだ!」。苦悩は子どもを欲しがるが、「喜びは、相続人を欲しがらない。子どもを欲しがらないー喜びは自分自身を欲しがる。永遠を欲しがる。回帰を欲しがる。」からだの喜びに目覚めたことによって、私は「ツァラトゥストラ」と親しくなった。
あとがきで主に書かれていて、印象的だったのは、この「からだ」との向き合い方でした。思えば、本編の1と2の部は、「からだ」と親しくすること、要するに健康でいる事、よく行動すること、というのに重きが置かれていました。そして、もう一つ、あとがきに別の同著者の別書籍が引用されていた中にはこういうのがありました。
筋肉も祭りに参加していないような思想など、信用するな
すわっていることは、できるだけ少なくせよ。戸外で自由に運動しながら生まれたのではないような思想、-筋肉も祭りに参加していないような思想など、信用するな。すべての偏見は内臓からやってくる。尻を落ち着けていることは、ーこれは既に言ったことだが、聖霊に背く真の罪である。
別書籍でも、「人類、動け」をひたすら説教している?とぽかんとしてしまいました。
確かに、座った状態が長いと血の巡りが悪くなって良くないなというのと、もっと根本的には、健康でいるために動けよを言っているのかなという気がしました。
3つのプロセス(ラクダ、ライオン、幼子)でも座る要素なかったと思い返されます。ドイツ哲学のベースって筋トレであったり、散歩や旅であったりの「動く」というのに重きを置いているのかもしれないです。こうしてnote書いている現在を見たとしたら、「なんとしても短く、早く済ませて、さあ動くんだ!さあ!」と熱量限界状態で高らかに叫ぶのでしょう、恐らく。
健康はなによりも優先されなければならない財産であるという考え方には、心底同意しかありません。ニーチェが仰いだショーペンハウアーも、さらに何世紀前の偉人らもずーっと同じことを言い続けていました。
解説編
後半にこんな言葉がありました。ニーチェ「論文なんて私は書かない。そんなものは、愚かなロバや雑誌の読者のためのものだ。」。どうした…?と開いた口が塞がらなかった。また上巻解説にて「ツァラトゥストラはダンスする」や「文字が躍っている」という表現みたいなことを見かけました。
文字が踊る?なんだこれは?と頭にはて、これはどういうことだ、となりました。正直、わりとパニックになりました。「なにこれなにこれ、どういうこと?」と顔が引き攣ながら文字を追いました。百面相しながら、文字を睨むことはなかなか無いと思います。
「言葉について」で自分も似たようなこと言ってましたが、性質はかみ合っていない気はします。ニーチェのツァラトゥストラは文字そのものが人のように立体になって、人のように動いて話している、その文字も話す度に物体としてでてきているような印象を受けます。それらさえ、超人になっていこうとしているみたいな。自分で言ってて、なんて言えばとなっている状態です。
ニーチェも読書を「悪徳」と呼んでいました。「読書をする怠け者を、俺は憎む。」といろいろと全面的に否定するフレーズを問答無用にストレートに入れてきました、この人。
悪とは、尊敬したショーペンハウアーと同じ意味で古典以外の本のことなのか、本を読んでじっとしている状態を憎んでなのか(後者ぽいけど、断定ができないので)どちらを意味しているのかと疑問です。こうでないだろうかという御意見があれば、どうぞコメントでお聞かせください。
まとめ
凄い、こんなに意図が読めないのは本当に初めてでした。
小説や童話、なんならビジネス本や他の哲学にも、なにかしらのゴールというか着地点みたいなのがだいたい、あります。読者に考えさせる問い掛けがあったりします。でも、ツァラトゥストラはそれが見えない、訳者さんが説教集に近いと言ってましたのは、確かにその通りという気もします。でも、解説やあとがき、参考にされた文献の個所を拝見するとんんん??えええ?と思いがけない発見もあってそうなの??と唖然とさせられる。
思いもつかなかった文字の踊る様は衝撃そのものでした。こんなの書けるんだってなります。ひょうひょうとして高らかに語って堅実とは真逆なのに、一本の話の中の圧が異様です。これだけ書いて、芯が一切ブレていないそこも凄いと思います。
本当、なにこれ。
