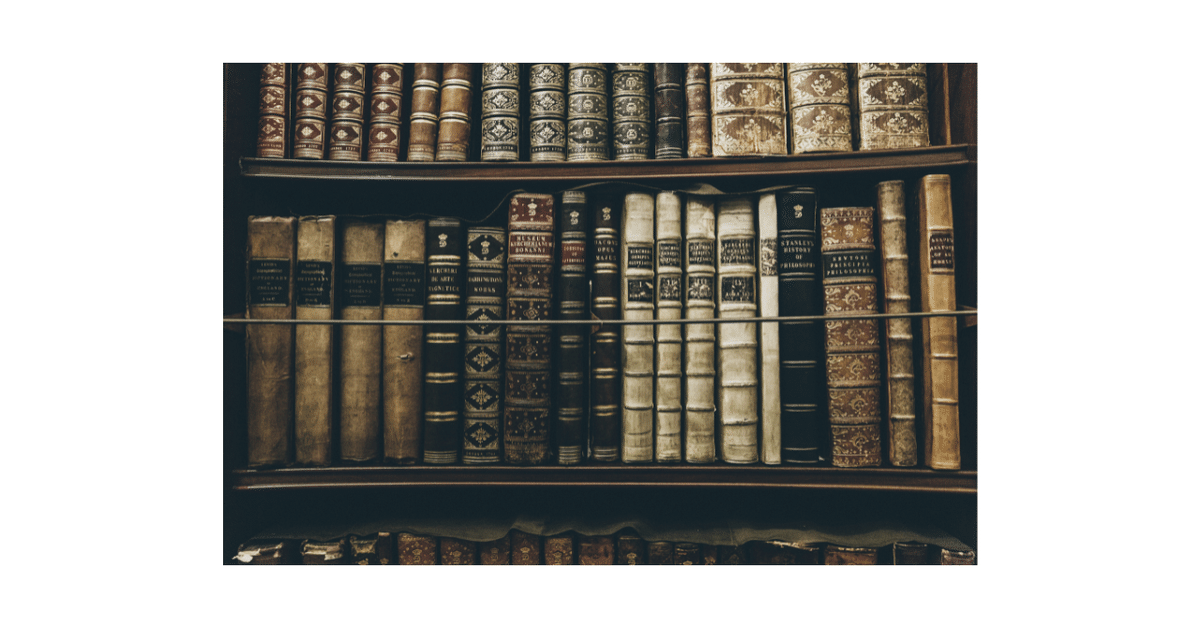
2023年 21冊目『方法序説』
方法序説は、「近代哲学の父」として知られるルネ・デカルト(1596年~1650年)の代表作です。
「われ思う、ゆえにわれあり」(コギト・エルゴ・スム)くらいしか知らなかったのできちんと読もうと思ったのです。
デカルトは、それまでの「神が真理を照らし出す」(=神ではない人間は真理を知ることができない)という主流の考え方に対して、人間が理性で考えれば誰もが受け入れることのできる地点(≒真理)に到達できるはずだという考え方を打ち出したのです。
当時は信仰によって真理にとうたつできるというスコラ哲学が正統派でした。
しかし、デカルトは、誰もが受け入れられる原理を見つけ、そこから出発し、理性を正しく働かせれば、普遍的な世界認識に達することができるはずだと考えたのです。
つまり、理性を正しく使うことで、共通の理解に達することができると考えたのです。
理性を正しく使うためには「方法」に従う必要がある考えたのです。
そこで問題になるのが、どこから推論をスタートするのかという出発点です。
その出発点を考えるためにデカルトは旅に出て、人々が何を考えているかを見聞きします。
その際にデカルトは全てを疑って疑いつくす「方法的懐疑」をしたのです。
感覚は欺く。
だから自分の外側にあるものは疑いの余地が残る。
内側の思考も、例えば数学の証明も夢も間違いがあり得る。
しかし、自分が存在することは否定できない。
これは誰もが受け入れざるを得ない。
これを哲学の出発点にできるはずだ。
「われ思う、ゆえにわれあり」
神の存在証明もしています。
ただし、これは詭弁だという評価もあるようです。
ただ、当時キリスト教の教義が絶対だった時代に、これを否定する事は厳しかったのでしょうね。
▼前回のブックレビューはこちら
