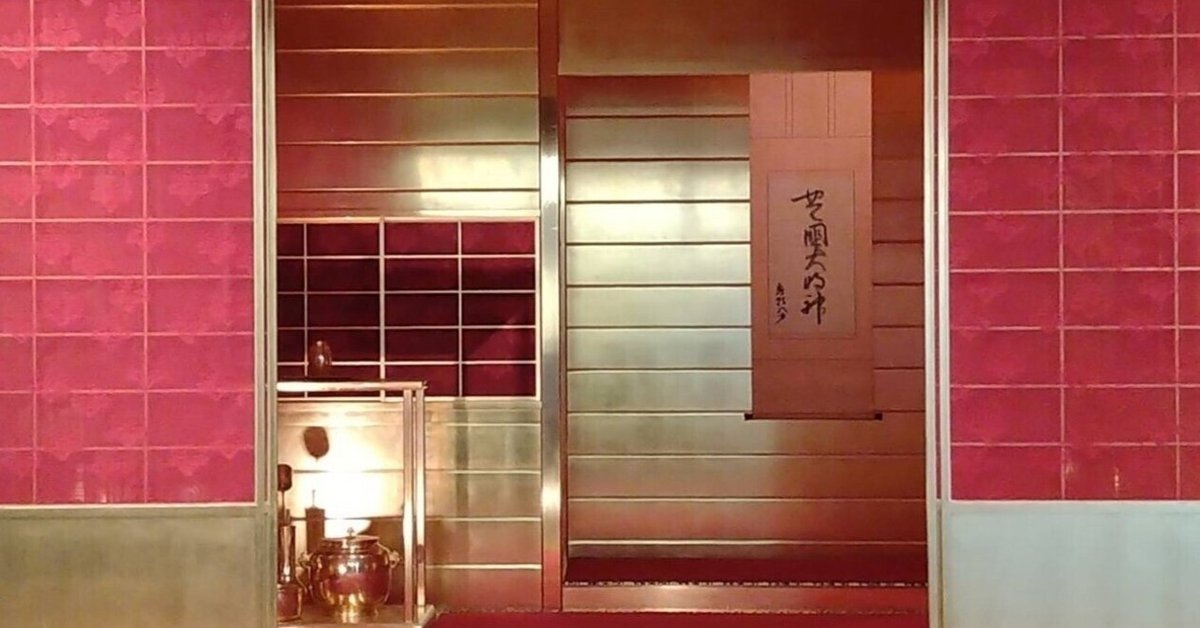
茶道のミュージアムに行こう! 【全国96カ所】
足利義政の時代に能、茶の湯、華道が開花
お茶は、鎌倉時代に明菴栄西禅師が宋から茶の種子を持ち帰り、抹茶の製法とともに日本各地に広げた。栄西は『喫茶養生記』を著わし、茶は生命力を養う薬で、喫茶は寿命を延ばすのに効果的と紹介し、薬用として重宝されていた。
僧侶の間では眠気を和らげる飲み物として愛飲され、室町幕府8代将軍の足利義政の時代に茶の湯が広まり、村田珠光、武野紹鴎、千利休を経て、伝統文化としての体系が確立された。
茶道とは、茶の湯の道を省略したもの。「お茶のミュージアムに行こう!」では、チャノキから作られる緑茶を中心に紹介したが、この項では、茶道に関する歴史、関連するミュージアムを解説する。『茶道の歴史』『日本茶道史』『本朝茶人伝』『千利休』『茶の心』などの著書を上梓し、室町・戦国時代を専門とする歴史学者、桑田忠親の説を中心に話を進めたい。
足利義政は東山山荘や慈照寺銀閣に代表される東山文化を広め、能、茶の湯、華道、庭園、建築、連歌などの芸術を開花させた。武家、公家、禅僧らの文化が融合して生まれ、3代将軍の足利義満の貴族的で華麗な北山文化に対し、幽玄、わび、さびに通じる美意識が重んじられた。
義政の時代、村田珠光とともに、茶の湯の世界で大きな足跡を残したのが能阿弥である。水墨画家、茶人で、連歌師、鑑定家でもあった能阿弥は、書院造(書院とは書斎を兼ねた居間の中国風の呼び名で、書院を建物の中心にした武家住宅の形式のこと)の広間に茶道具を飾る「書院飾り」を完成させた。
水指などの茶道具を置くための棚の「台子飾り」の方式を定め、室町時代中期に始まった小笠原流の礼儀作法を取り入れて、茶の点て方を考案した。
能阿弥は中尾真能という武士で、越前朝倉氏の家臣だった。6代将軍の足利義教、義政に同朋衆として仕えた。同朋は将軍の側近で、芸事の相手をする役目で、阿弥衆、御坊主衆とも呼ばれた。出家と俗人の中間的な存在で、俗人でありながら頭を剃って、世俗を忘れて芸に身を投げ打つ人々を指す。
同朋は、猿楽(室町時代に成立した日本の伝統芸能の能のことで、江戸時代までは猿楽と呼んだ。能と狂言を能楽と総称するのは明治以降のこと)、庭園作り、唐物(中国製品のことだが、宋、元、明、清時代の美術品を指すことが多い)の目利き、表装(書画の保存や鑑賞のため、織物や紙などを補って掛軸、巻物、屏風、冊子などに仕立てること)などの芸能や技術に優れていた。
お茶に関係する同朋は茶同朋と呼ばれ、能阿弥はさまざまな芸術に秀でており、立花(元来、仏様に供える花の形式だが、花や草木を中心にさまざまな材料を組み合わせて構成し、鑑賞する芸術で、華道、花道、生け花とも言う)、香道にも秀でていた。
連歌では七賢の1人に数えられ、北野天満宮で行われる北野会所の連歌奉行も務めていた。会所とは、歌合せや連歌の会など遊興的な会合が行われる建物のことだが、室町時代に、お茶用に改造され、茶室として使われるようになった。
中国の宋の時代に、お茶を飲んで香りや味から銘柄や産地を推測する闘茶が流行し、鎌倉時代の末期か南北朝のころ日本に伝わったが、中国風の茶室で闘茶が行われていた。2階建ての茶室で、1階は客殿で、客が待っている場所、2階を台閣と言い、準備ができると台閣に招かれて闘茶が始まる。これが室町時代に日本化し、連歌の会所のような素朴な建物に変わり、能阿弥が床の間、違い棚がある「書院飾り」を編み出す。
書院飾りの原型は南北朝時代の佐々木道誉(京極高氏)が作ったとされており、道誉は足利尊氏を助けた守護大名で、連歌、猿楽、茶道、香道、立花などに通じていた。美意識が高く、婆娑羅大名(権威や権力を意に介さず、秩序や常識に捉われないで自由奔放に振る舞う型破りな大名のこと)として知られ、観阿弥、世阿弥親子とも親交があり、猿楽を庇護した。
茶の湯を革新した村田珠光と武野紹鴎
村田珠光は、奈良にある浄土宗の寺院、称名寺に入って出家するが、僧侶になることを嫌い、諸国を放浪した後、京都で能阿弥に師事し、茶の湯、連歌、猿楽、立花、唐物の目利きなどを学んだ。臨済宗の僧で、詩人、書家、説話のモデルの一休宗純とも交流があり、禅の精神を加味して,精神性を高めた茶道を目指す。
能阿弥は新たな慣例を作るなど形式にこだわり、広い書院座敷を用いたのに対し、珠光は4畳半の茶室を考案し、装飾を抑え、限られた少人数の出席者が会し、心の通じ合う場に変えた。高価な唐物の茶道具、象牙や銀製の茶杓を使わず竹の茶杓を用いるなど、わび、さびの精神を重視。床の間の掛け物を唐絵や仏画に代わって、禅宗の僧の墨蹟(紙や布に墨で書かれた書のことで、日本では臨済宗を主とする禅僧の書を指すことが多い)を使うようになった。
日常生活で使っている雑器を茶事に取り入れ、茶の湯の簡素化に努め、禅の思想を重視した珠光は慎ましく、質素なものにこそ趣があるという考えの「わび」を茶の世界にもたらし、不完全だからこそ美しいとする「不足の美」を説いた。
珠光が亡くなった後、堺の豪商で、茶人、歌人の武野紹鴎が珠光の茶の湯を深化させてわび茶を完成させ、わび茶の創始者とされている。4畳半より小さい3畳半や2畳半の茶室を考案し、小さな座敷の中に、心のやすらぎを求めて侘敷と称した。
唐物の茶器の代わりに信楽焼や瀬戸焼などの雑器から茶道具を選んで使用し、貴族趣味的な茶事を避け、慎み深く行動することを説いた紹鴎は古典、和歌、連歌を学んでいた。
樹木が枯れる初冬の冷え冷えとした空気感や、清々しく凛とした心持ちを表す「冷え枯れ」「冷え痩せ」という美学を和歌や連歌の世界で理想としていたが、そうした境地を茶事に取り入れた。道具よりも、心の有り様、持ち方を重視した。
紹鴎は、三条西実隆から、『新古今和歌集』を編纂した歌人の藤原定家について学んでいた。実隆は内大臣になるも、すぐに辞めて、和歌、連歌、書、将棋、囲碁に時間を費やした。
実隆に学んだ紹鴎は、藤原定家の有名な歌に、わび茶の理想を見い出す。「見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦のとまやの 秋の夕暮」
(見渡してみると、美しく咲く春の花も、秋の見事な紅葉もここには見たらない。浜辺の粗末な漁師の小屋だけが目に映る、なんともわびしい秋の夕暮れであることよ)
花鳥風月を美しい言葉で表現することが和歌の主流、王道であるが、定家のこの歌は、花も紅葉も否定し、わびしさに価値を見出している。
草庵風の茶室の基本は4畳半で、それよりも狭い茶室は小間、小座敷、数寄屋などと呼ばれ、4畳半以上の茶室は広間という。広間では台子(茶道の点前に用いる茶道具で、水指などの茶道具を置くための棚)などの棚物や付書院(床の間の脇に設けられる書院で、棚板と明かり取りをするための障子で構成される)を設けることができる。
紹鴎は、堺の商人で茶人の今井宗久、津田宗及、千利休らに強い影響を与え、利休は「珠光より道を得、紹鴎より術を得た」と説いている。
わび茶を大成し、茶聖と称される千利休は堺の商家に生まれた。魚屋という屋号で倉庫業(納屋衆)を営み、幼名は田中与四郎。法名は宗易で、豊臣秀吉とともに宮中に上がり、正親町天皇から利休の居士号を賜った。
通常は千宗易を名乗っており、祖父が田中千阿弥と名乗っていたので、そこから「千」を付けた。武野紹鷗に茶の湯を習い、天下人の織田信長や豊臣秀吉の茶頭(茶事全般を司り指導する人のこと)として仕えた。
宗易は20代に堺の実質的支配者であった三好家の一族の女性と結婚し、40代後半まで、三好家の御用商人として堺を離れず、家業に打ち込み財を成した。1568(永禄11)年に京都に入った信長は翌1569年、三好三人衆(三好長逸、三好宗渭、岩成友通)が支配していた堺を直轄地として傘下に収め、堺の豪商で茶人の今井宗久、津田宗及、千宗易を茶頭として召し抱えた。
信長は、傘下の大名や家臣に茶の湯を奨励し、茶事の政治利用を推し進めた。御茶湯御政道と呼ばれる統治スタイルで、配下の武将に茶会の開催を許可し、茶道具の優れた逸品、名物を下賜(身分の高い人が低い人に物を与えること)して支配力を強めてきた。茶の湯は、武家の礼儀作法と位置付けられた。
豊臣秀吉の下で、対極の茶室を作った千利休
千利休に20年間、茶の湯を学んだ高弟で、堺の商人の山上宗二は『山上宗二記』を書き残している。茶道史を解き明かす基本資料と言える書で、宗二は利休の茶の湯への姿勢を書き記した。
60歳までは先人の茶を踏襲し、本能寺の変(1582年)で信長が亡くなり、天下分け目の戦いの山崎の合戦の頃から、利休は独自の茶の湯を始めたと述懐。利休が独自のわび茶を大成させた時期は、70歳で亡くなるまでの10年間であったという。
宗二は秀吉を怒らせ、追放されて浪人になり、許された後、再度不興を買い、高野山に逃げ込んだ。その後、相模国の小田原に赴いて、北条氏一門の北条幻庵に仕える。幻庵は北条早雲の末子で、和歌、連歌、尺八の製作、作庭などの芸事に通じており、長寿であったが、秀吉が北条氏を降伏させる小田原征伐(1590年)の前年に亡くなっている。
小田原征伐の最中、利休の仲裁で、秀吉は宗二を赦して再登用しようとしたが、宗二は北条幻庵に義理立てしたため、秀吉の怒りを買い、耳と鼻を削がれて打ち首にされた。その翌年、利休が自刃することになる。
秀吉も信長と同様、茶の湯を宮中、公家との関係強化や大名の支配に利用した。利休を茶頭の筆頭にし、禁中茶会や北野大茶湯の開催、運営に協力させた。秀吉と利休との新たな関係が生まれたのが、主君、信長が本能寺の変で明智光秀に討たれ、秀吉と光秀が戦った山崎の合戦(天王山の戦い)である。
現在の京都府と大阪府の境界にある山崎に、妙喜庵がある(京都府乙訓郡大山崎町)。秀吉は山崎に陣を敷き、陣中に利休を招いて、二畳の茶室、待庵を作らせた。妙喜庵の功叔和尚は利休に茶の湯を学んでおり、利休は功叔とともに秀吉に茶を点じ、労を慰めた。その後、茶室は解体され、江戸時代初期の慶長年間(1596年~1615年)に妙喜庵に移築し、再建築されたと言われている。
妙喜庵の寺号は、宋の禅僧の大慧宗杲の庵号から付けられ、連歌の祖であり、近江出身の山崎宗鑑が隠棲した場所と伝えられる。山崎に住んだことから「山崎」を姓にした宗鑑は讃岐国(香川県観音寺市)の興昌寺の一夜庵に赴き、そこで生涯を閉じた。
妙喜庵の茶室、待庵は利休独特の構想で建てられ、現存する茶室としては最古の遺構で、国宝に指定されている。屋根は切妻造り、杮葺で、書院(重要文化財)の南側にある。
現在、国宝の茶室は3棟あり、国宝茶席三名席と呼ばれている。待庵の他は、大徳寺龍光院の密庵(京都市北区紫野。小堀遠州の作と伝えられる)と、犬山城(愛知県犬山市)の東にある日本庭園、有楽苑の如庵(織田信長の弟、織田有楽斎によって京都・建仁寺の正伝院に建造された茶室が移築された)。
山崎の合戦時の茶室の待庵に続いて、秀吉と利休との強い絆を示すのが「黄金の茶室」である。1584(天正12)年、大坂城の本丸もできていない未完成の中、本丸の下の山里曲輪に、秀吉は利休に命じ、移動可能な「黄金の茶室」を造らせた。
1585年、関白となった秀吉は正親町天皇を訪問し、御所に黄金の茶室を運んで茶会を開催。宮中に参内するため居士号「利休」を勅賜(天皇からいただくこと)され、秀吉からは3000石が与えられた。
豊後(大分)を基盤に九州北部を支配していた大名、大友宗麟は、薩摩(鹿児島)の島津氏が九州を北上する勢いに脅威を感じ、1586年、天下統一を進めていた秀吉に大坂城で謁見した。秀吉の傘下になることを条件に軍事的支援を懇願した宗麟は、この時の様子を国許の家老に手紙で知らせている。
秀吉に天守閣をはじめ大坂城を案内され、家臣団にも会ったが、秀吉に平気で口をきけるのは千宗易(利休)だけだと。秀吉の異父弟の羽柴(豊臣)秀長から「大坂城の内々(奥向き)のことは宗易が知っている。公儀のこと(外部のこと)は私に相談するように」と忠告された。利休が隠然たる力を持っていたことを裏付ける史料となっている。
島津氏が秀吉に降伏し、九州を平定した1587年、秀吉が京都で造らせていた政庁兼邸宅の聚楽第が完成する。利休は聚楽第の築庭に関わり、屋敷を構えることを許された。その直後、秀吉は京都の北野天満宮の境内で北野大茶湯を開催し、町人、百姓にも参加を呼びかけ、約1000人が茶会に参加。秀吉と千利休、今井宗久、津田宗及の3人の茶人が客人を迎え、茶を供した。
巨大な権勢を妬まれた千利休
利休は茶人として名声と権威を誇り、「天下一の茶の湯者」と讃えられたが、秀吉との良好な関係は続かなかった。
利休は京都の大徳寺に以前から寄進していたが、大徳寺の三門(三門とは空門、無相門、無作門の三解脱門のことで、金毛閣と名付けられた。金毛とは、禅語の「金毛の獅子」から引用した言葉で、修業を積んで何事にも動じない優れた禅僧のこと)の造り替えのために資金援助をした。
利休への感謝の意を表すため、大徳寺の住持(一寺の主僧を務めること)であった古渓宗陳が、利休の雪踏ばきの木像を造り、三門の上に祀った。
だが、完成して半年ほど経ったとき、秀吉が山門をくぐれば、利休の雪踏で秀吉の頭を踏まれる形になるから不敬に当たるとの理由で、利休の木像が問題になった。
秀吉の側近で、木下祐慶という人物が茶入の目利きを誤り、大勢の中で利休に恥をかかされたことを根に持ち、利休のあら探しをして、京都奉行で寺社奉行であった前田玄以に訴えたことで騒ぎになった。
もう1つの「罪状」は、茶道具の目利きや売買で、唐物(名物)と利休が指示して作らせた樂焼(樂家が作陶した焼物)などの茶道具を交換して、不当な利益を得ていたというものだ。
芸術品の価値は人それぞれで異なる。京都の陶工、樂長次郎が焼いた茶碗と、唐物との価値をどう比べるか。長次郎の楽焼で、現在、国の重要文化財になっている作品が数多くある。
言いがかりとも言える讒言で秀吉の逆鱗に触れ、利休は切腹を命じられ、生涯を終えた。秀吉の権力を確立し絶頂だった時期に、利休の茶の湯は大成する。
利休流の茶道の特色は、茶道具を前もって茶室に飾っておかず、茶室に運び入れるところから始める「運び点前」を広めたことだ。水指や茶器などを棚に飾りつけておく「棚点前《たなてまえ》」に対し、風炉と釜以外の道具を茶道口から運んで点茶(抹茶を点ること)する作法を重視した。
運び点前では、茶を点てることが「主」で、茶道具はそのための手段として「従」に位置付けられている。唐物、なかでも名物を尊ぶ従来のスタイルを否定し、雑器や身の回りの物を活かし、楽茶碗や万代屋釜など、利休がプロデュースした「利休道具」を使うようにした。
楽茶碗は、利休の意を受けた樂長次郎が作った茶碗で、轆轤を使わず、手で土をこね、立ち上げて指で整える。万代屋釜は茶の湯釜の形状のひとつで、利休が京都の鋳物師、辻与次郎に作らせ、女婿で堺の商人の万代屋宗安に贈ったことから名が付けられた。華美な装飾を否定し、擂座と言って、釜の口や肩などに半球形の粒が並ぶ文様と、浮き上がった線が特色。
利休は茶室の設計でも大きな変革を行った。躙り口(茶室の入り口)や下地窓(土壁の一部を塗らずに、壁の中の竹などの小舞を露出させた窓)などに工夫を凝らし、草庵茶室を演出した。
武野紹鷗の時代まで、茶室の採光は縁側に設けられた2枚引き、あるいは4枚引きの障子による「一方向からの光線」だったが、利休は茶室を土壁で囲い、必要に応じて窓を設けて光を採り入れる方法にした。この「囲いの誕生」によって、茶室内の光を自在に操り、必要な場所を必要なだけ照らし、逆に暗くしたい場所は暗いままにすることが可能になった。
茶室だけでなく、茶室に向かう露地にも利休は気を配っている。一般的に屋根などのおおいのない土地を露地と呼ぶが、利休は茶室と、外の露地(茶庭)を一体として捉え、露地で世俗を断ち、精神を浄化させる場所と位置付け、露地を「浮世の外の道」と表現した。露地が、幽玄な境地に誘う茶室へのアプローチとなっている。茶庭は狭く、背の低い木が植えられ、茶室に花が飾られるので、花が咲く木を植えないようにしている。
茶道の流派は町衆茶道、武家茶道に分化
1591(天正19)年に千利休が切腹した後、千家は一家離散となり、千利休の後妻の連れ子で、娘婿である千少庵は会津(福島県)の大名、蒲生氏郷のもとで蟄居を命じられる。
徳川家康と蒲生氏郷のとりなしで、1594(文禄3)年、千少庵は秀吉に赦されて京都に戻り、千家の再興を図る。利休が完成させた「わび茶」を受け継ぎ、少庵の息子、千宗旦が利休のわび茶をさらに推し進め、「乞食宗旦」と呼ばれるほど、清貧で禅の要素を加味し、わびの部分を徹底した。
祖父の利休が秀吉に切腹させられたこともあり、宗旦は大名に仕官せず、経済的に貧しかったが、4人の息子たちは大名家に仕えさせた。
勘当した長男を除き、3人の息子がそれぞれ家を興す。三男の江岑宗左が家督を継承し不審菴表千家と称し、四男の仙叟宗室が宗旦の隠居所を継いで今日庵裏千家を興す。養子に出ていた次男の一翁宗守が千家に戻って官休庵武者小路千家となった。
この3家は三千家と呼ばれ、現代まで続いている。三千家に出入りする茶道具の職人の茶碗師、釜師、塗師、指物師など10の職家を千家十職と呼ぶ。千家好みの茶道具を作れる職人は限定されていて、職人は固定され、代々引き継がれていく。
千家十職の職種と職人名
茶碗師 樂吉左衛門(樂長次郎の後継者、宗慶から吉左衛門)
釜師 大西清右衛門 鉄製、金製、銀製などの茶釜
塗師 中村宗哲 棗(抹茶を入れる容器)、手桶などの塗り
指物師 駒沢利斎 棚、香合、炉縁など木地全般
金物師 中川浄益 火箸、やかんなどの金物
袋師 土田友湖 仕覆(茶道具を入れる袋)、服紗など
表具師 奥村吉兵衛 軸装(掛け軸に仕立てること)、屏風など
一閑張細工師 飛来一閑 棗、香合など
竹細工・柄杓師 黒田正玄 茶杓(抹茶をすくう道具)
土風炉・焼物師 西村(永樂)善五郎 土風炉は陶器に黒漆を塗った風炉
千利休を祖とする表千家、裏千家、武者小路千家の他にも、さまざまな流派があり、500を超えるとも言われる。
利休の孫、千宗旦が育てた弟子の藤村庸軒、山田宗徧、杉木晋斎、久須美疎安を宗旦四天王と呼び、久須美疎安の代わりに松尾宗二、三宅亡洋を入れる説もある。宗旦の弟子から庸軒流、宗徧流、普斎流、松尾流などの流派が生まれた。
千利休以前の能阿弥の茶道の流れの東山流、村田珠光を祖とする奈良流(珠光流とも)、武野紹鴎を継ぐ堺流 などもあった。広まった層が商人、町人であったため町衆茶道と言われている。
千利休の高弟とされる7人の武将を「利休七哲」と呼ぶ。大名、武士階級に茶道は広まり、大名茶道、武家茶道と言われ、以下の人物が挙げられる。
織田信長の実弟の織田長益(有楽。有楽斎とも)、南山城・東大和藩主の古田織部、近江国小室藩主の小堀遠州、大和小泉藩主の片桐石州、飛騨高山藩主の長男として生まれた金森宗和、安芸藩主の浅野家の家老であった上田宗箇、豊前小倉藩主の細川忠興(三斎)、肥前平戸藩主の松浦鎮信、松江藩主の松平治郷(不昧)、美濃加納藩主の安藤信友、彦根藩主の井伊直弼などである。
それぞれ有楽流、織部流、遠州流、石州流、宗和流、上田宗箇流(上田流)、三斎流、鎮信流、不昧流、安藤家御家流(御家流)、彦根一会流として引き継がれている。肥後熊本藩で伝承された肥後古流、豊前小倉藩に伝わる小笠原家茶道古流(小笠原古流)もある。
国宝の8つの茶碗の6つは海外で作陶
「国宝」などを決める文化財保護法が1950(昭和25)年8月に施行されたが、1949年に法隆寺金堂の火災で、法隆寺金堂壁画焼損事件がきっかけだった。1929(昭和4)年に施行された国宝保存法では、重要文化財と国宝の違いがなく、国宝保存法時代の国宝は、文化財保護法の規定の重要文化財とされた。
国宝は、文部科学省に設置される「文化審議会」が専門調査会に調査を依頼し、調査結果を基に、国宝にするかどうかを話し合い、メンバー全員が「国宝にふさわしい」と判断しないと、国宝に指定されない。
国宝の判断基準は「重要文化財のうち、世界文化から見ても価値が高く、たぐいない国民の宝」と規定されており、まず有形文化財に分類・指定され、次に重要文化財と認定され、さらに「国民の宝」と指定される。
国宝は「美術工芸品」と「建造物」に分れており、美術工芸品は絵画、彫刻、工芸品、書蹟(書道の優れた作品や墨蹟)・典籍(古くから伝わる本 )、古文書、考古資料、歴史資料の7つのジャンルがある。2024(令和6)年12月時点で、国宝は1143件。
最も多いのが工芸品で、陶磁器、仏教の法具、刀剣(日本刀)など。陶磁器の中の茶碗で国宝に指定されているのは、以下の8件。
「曜変天目茶碗 稲葉天目」(ようへんてんもく いなばてんもく)(静嘉堂文庫美術館蔵)
「曜変天目茶碗」(ようへんてんもく)(藤田美術館蔵)
「曜変天目茶碗」(ようへんてんもく)(大徳寺塔頭大通庵 龍光院蔵)
「井戸茶碗 銘 喜左衛門」(いどちゃわん)(大徳寺塔頭 孤篷庵蔵)
「油滴天目茶碗」(ゆてきてんもく)(大阪市立東洋陶磁美術館蔵)
「玳玻天目茶碗」(たいひてんもく)(相国寺・承天閣美術館蔵)
「志野茶碗 銘 卯花墻」(うのはながき)(三井記念美術館蔵)
「楽焼白片身変茶碗 銘 不二山」(らくやき しろかたみがわり)(サンリツ服部美術館蔵)
他に、6点の陶磁器が国宝になっている。
「色絵藤花文茶壺」(いろえふじはなもん ちゃつぼ)野々村仁清作(MOA美術館蔵)
「色絵雉香炉」(いろえ きじこうろ)野々村仁清作(石川県立美術館蔵)
「飛青磁花生」(とびせいじ はないけ)(大阪市立東洋陶磁美術館蔵)
「青磁鳳凰耳花生 銘 万声」(せいじ ほうおうみみ はないけ)(和泉市久保惣記念美術館蔵)
「青磁下蕪花生」(せいじ しもかぶら はないけ) アルカンシエール美術財団蔵 東京国立博物館寄託
「秋草文壺」(あきくさもんこ) 慶應義塾蔵 東京国立博物館寄託
*アルカンシエール美術財団は、群馬県渋川市にある原美術館ARCを運営。
以下のページで、茶道に関連するミュージアムを解説するが、分量が多いので、目次で興味のあるミュージアムだけチェックしていただきたい。茶碗、茶の湯釜などの茶道具に関するミュージアムも含まれている。
お茶の歴史とお茶に関連するミュージアムは別項の「お茶のミュージアムに行こう!」で紹介している。
陶磁器のオンラインミュージアムに「陶磁オンライン美術館」がある。
陶磁オンライン美術館
TOUJI GRAPHICA VIRTUAL MUSEUM
陶磁オンライン美術館では日本、中国、朝鮮を中心とした茶碗、茶器、皿、壺、水差、杯などの写真を掲載し、陶磁器の特色と魅力を解説。運営者は陶磁器の研究家で、カメラマン。
青森県
津軽茶道美術館
青森県黒石市大字豊岡字狼森27-105
0172-53-3082
休館日 火曜日(祝日の場合は翌日) 12月1日~3月31は冬期休館
10:00~16:00 300円
陶芸家の今井理桂の工房、「津軽烏城焼 三筋工房」の裏手に「津軽茶道美術館」が2002(平成14)年に開館した。館内には、理桂が制作した作品と、蒐集品を中心に茶道具類を展示。平安時代の常滑焼に魅せられて陶芸の道に入った理桂は釉薬をかけず、自然釉にこだわり、穴窯(窖窯)と登り窯で焼成する烏城焼を開発した。
日本で初めて窯が登場したのは古墳時代で、須恵器を焼くための穴窯が始まり。従来の土器は手びねり(轆轤を使わない)で成形した土を「野焼き」していたのに対し、須恵器は轆轤を使って成形し、窯で焼く最先端の焼物だった。その穴窯を作陶に採り入れている。
理桂が22年かけて築いた世界最長、52段103メートルの登り窯は2019年、ギネス世界記録に認定された。津軽茶道美術館には茶室や和室があり、お茶会などの貸し席として利用でき、喫茶コーナーでは抹茶と菓子を楽しめる。津軽烏城焼の特色が動画で紹介されている。
宮城県
切込焼記念館
宮城県加美郡加美町宮崎切込3
0229-69-5751
休館日 第2・4月曜日 年末年始
10:00~16:30(入館は16:00まで) 300円
切込焼は、江戸時代から明治初期まで、加美町切込地区で焼いていた陶磁器で、仙台藩の御用窯として上質な製品を焼きながら、庶民向けの日用雑器も生産していた。
創始ははっきりしておらず、仙台藩初代藩主の伊達政宗、3代藩主の綱宗の頃とも言われるが、紀年銘(製作の年代を明らかにする言葉)を刻んだ最古の湯呑茶碗が1835(天保6)年となっていて、弘化・嘉永期(1845年~1855年)に最盛期を迎えた。
白地に藍色で文様が描かれる染付磁器が切込焼の主流で、トルコブルー、紫、白で彩られる二彩・三彩は「東北陶磁の華」と珍重された。明治になって、仙台藩は戊辰戦争や廃藩置県などで苦境に陥り、切込焼も1879(明治12)年に窯を閉じ、歴史や実態が謎に包まれた焼物となっている。
切込焼記念館は伝世の優品と資料を展示し、切込焼と地元の歴史、民俗との関わり、切込焼の謎と美について紹介。切込焼記念館の西館に2023年、「芹沢長介コレクション展示室」がオープンし、三彩桔梗皿や染付牡丹雲文植木鉢など切込焼の作品が展示されている。
老朽化のため2021年に閉館した「芹沢長介記念 東北陶磁文化館」(加美郡加美町)は東北大学や東北福祉大学の教授を務めた考古学者の芹沢長介が東北の「生活のやきもの」を蒐集したミュージアムだった。同館の所蔵品のうち、切込焼の作品や資料など239点を切込焼記念館が引き継いでいる。
伊達藩と茶の湯の関わりは、初代の伊達政宗に始まる。正宗は千利休の後継者、古田織部の弟子である清水道閑を仙台に招いて500石を与え、茶の湯を広めた。道閑の子、2代動閑は伊達藩の藩命によって、大和小泉藩の藩主、片桐石見守貞昌(石州)に13年間指導を受け、皆伝を受けて仙台に戻り、石州流の茶道を広める基盤を作った。
片桐石州は徳川4代将軍、家綱の茶道指南役となり、「将軍家の茶道」と認められたことで、石州流は全国の諸大名に広まっていく。
伊達藩4代藩主、伊達綱村は文化人で数奇大名として知られ、多いときは年に336回も茶会を開催したと言われ、3代清水道竿を茶道指南役に任じた。道竿は「石州流清水派」を確立し、伊達藩だけでなく諸藩に広めた茶人で、石州流清水派は現在も宮城県に根付いている。
文化庁の「日本遺産」に認定された「政宗が育んだ“伊達”な文化」では「茶杓 仙台藩歴代藩主作」が構成文化財となっており、初代藩主の伊達政宗から5代藩主の吉村までの茶杓と、茶杓を納めた黒漆塗の茶杓箪笥が伝えられてきた。政宗は若い頃から茶の湯に親しみ、政宗が清水道閑を茶道師範として以来、伊達藩では古田織部門下の清水家の石州流が主流を占めている。
栃木県
栗田美術館
栃木県足利市駒場町1542
0284-91-1026
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 1250円
栗田美術館は伊萬里、柿右衛門、鍋島を収蔵する世界屈指の陶磁美術館で、足利市の出身の栗田英男が蒐集したコレクションを展示。栗田は肥料商、東京毎夕新聞社社主などを務め、衆議院議員、総会屋、企業の顧問としても活動。栗田政治経済研究所を設立し、企業の粉飾決算、不祥事を追及する理論派の総会屋であった。
1968(昭和43)年にコレクションの一部を東京都中央区に栗田美術館東京本館を開館して一般公開していたが、1975年に地元の足利市に栗田美術館を開館した。足利市郊外の3万坪の景勝地に四季の花や草木など配した庭園を持つ。本館、歴史館、無名陶工祈念聖堂、陶磁会館、阿蘭陀館、世界陶磁館がある。
白い漆喰壁が特徴の本館には伊萬里、鍋島の名品約400点を展示。有田の泉山で採掘された白磁鉱で製作した磁器タイルを建物の内外に使用した4階建ての歴史館には伊萬里焼の歴史を概観できる。
伊萬里焼は日本で最初に作られた磁器で、帰化した朝鮮陶工によって1615(元和元)年頃、佐賀県の有田町で創始された。伊萬里は積出港であったが、肥前有田焼に代って伊萬里焼と呼ばれた。鍋島藩は、赤絵付の技法が他に漏れることを極度に警戒し、赤絵付業者は16軒に限って免許を与え、厳しく統制していた。
オランダ東インド会社によって、伊万里焼はヨーロッパに輸出され、豪華絢爛な赤絵は圧巻。鍋島藩の御用窯として、藩主の自家用品、贈答品、献上品など、用途によって多彩な様式美を持つ。藩主が用いた茶道具では「鍋島色絵薔薇文向付」や「鍋島色絵薔薇文皿」などを所蔵している。
栗田美術館の近くには、日本最古の大学の足利学校、足利尊氏の始祖が創建し、国宝の鑁阿寺本堂や重要文化財の鐘楼で有名な鑁阿寺がある。
茨城県
板谷波山記念館
茨城県筑西市甲866-1
0296-25-3830
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~18:00(入館は17:30まで) 210円 特別展は別料金
茨城県の現在の筑西市で、醤油醸造業と雑貨店を営む旧家に生まれた板谷波山は東京美術学校(現・東京藝術大学)彫刻科に入学し、岡倉覚三(天心)、高村光雲らの指導を受け、卒業後、金沢の石川県工業学校(現・石川県立工業高等学校)の彫刻科の教諭になった。1年後に彫刻科が廃止されて陶磁科に転籍となり、元々興味があった陶芸を教えながら、本格的に作陶に打ち込んだ。
1903(明治36)年、30歳のときに辞職し、家族と共に上京。東京・田端に窯を築いたが、作品は売れず、「板場破産」と自嘲するほど貧しかった。同年、東京高等工業学校(東京工業大学、現在の東京科学大学)窯業科の嘱託となり、10年間、後進の教育に携わった。
1908年、日本美術協会展で受賞して以降、数々の賞を受賞し、帝国美術院会員、帝室技芸員になり、1953年に陶芸家として初めて文化勲章を受章。1960年に重要無形文化財保持者(人間国宝)の候補となるが、辞退している。
波山の作品には青磁、白磁、彩磁(多色を用いた磁器)などがあるが、造形や色彩に完璧を期しており、格調の高さが特色。つや消しの釉薬を葆光釉と名付けた。葆光とは光を隠し、包むという意味で、葆光釉によって1230度で焼成すると、薄絹を透かしたような淡い光を放つが、これは波山独自の技法。
筑西市の板谷波山記念館では、波山の作品や、自ら築造した三方焚口倒焔式丸窯、陶磁器関連の資料を見学できる。波山は作陶の仕事に入る前に、抹茶を嗜んだと言われていて、精神を落ち着かせ、清らかな気持ちで制作に向かったという。
茶碗、茶入、水差などの茶道具も数多く手掛けており、茶碗では「白天目茶碗」「天目茶碗」「黒平茶碗」「彩磁絞手(藍の絞り染めのように釉薬がにじんでいる状態)茶碗」など、水差では「青磁蓮華文水差」「氷華磁牡丹文水差」などを所蔵している。
東京都
東京国立博物館
東京都台東区上野公園13-9
050-5541-8600
休館日:月曜日(祝日の場合は翌平日休館) 年末年始
9:30~17:00 (入館は16:30まで) 展覧会によって異なる
1872(明治5)年、東京の湯島聖堂大成殿で湯島聖堂博覧会が開催され、これが東京国立博物館(愛称 トーハク)のルーツで、150年余の歴史を持つ。日本最古で最大の博物館の収蔵品は約12万件で、このうち国宝89件、重要文化財650件と質、量ともに日本を代表するミュージアム。収蔵品や寄託品で構成される「総合文化展」では約3000件を展示する。
東京国立博物館の展示館は6館あり、本館では日本美術、平成館では日本の考古、東洋館では東洋美術、法隆寺宝物館では法隆寺献納宝物を展示し、表慶館では特別展や催し物を開催し、黒田記念館は洋画家の黒田清輝の作品を紹介している。
美術コレクターが東京国立博物館にコレクションを寄贈するケースも多く、「電力の鬼」との異名をもつ実業家、茶人、古美術蒐集家の松永安左エ門は茶道具などを寄贈。
安左エ門は中部、関西、九州、四国にまたがる電力会社、東邦電力の経営に携わり、戦前戦後を通じて電力界の重鎮として活躍。還暦を迎えて茶の湯を始め、耳庵という号を名乗った。安左エ門は、三井財閥の重鎮で、三井物産の設立に関わった益田孝(鈍翁)、中外商業新報(中外物価新報を改組)社長や三越呉服店社長などを歴任した野崎廣太(幻庵)とともに、小田原に邸宅を構えたことから「小田原三茶人」と呼ばれた。
東京国立博物館の「松永コレクション」には、重要美術品の「大井戸茶碗 有楽井戸」「文琳茶入 銘 宇治」「志野茶碗 銘 橋姫」「竹茶杓 蒲生氏郷作」「青磁鳳凰耳瓶 龍泉窯」「芦屋松図真形釜」などがある。
静嘉堂文庫美術館
東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1F
050-5541-8600
休館日 月曜日 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで)
土曜日は10:00~18:00(入館は17:30まで)
第3水曜日は10:00~20:00(入館は19:30まで) 1500円
三菱グループの創始者、岩﨑彌太郎の弟、岩﨑彌之助と小彌太の父子2代が蒐集した美術品を収蔵、展示する美術館。絵画、彫刻、書蹟、漆芸、茶道具、刀剣、中国陶磁など幅広いジャンルに渡り、茶器の曜変天目茶碗(稲葉天目)などの国宝7件、重要文化財84件を含む約6500件の東洋古美術と、約20万冊の古典籍(漢籍12万冊、和書8万冊)を所蔵し、質量ともに国内屈指のコレクションを誇る。
静嘉堂文庫は1892(明治25)年、東京・駿河台の岩﨑彌之助邸内に創設された文庫で、図書館としての活動も行っており、1977(昭和52)年から静嘉堂文庫に併設された展示館で美術品の一般公開が始まった。
静嘉堂の名称は中国の古典『詩経』の中の「籩豆静嘉」の句から採った彌之助の堂号で、祖先の霊前に十全な供物を供えて美しく整えるという意味。
静嘉堂創設100周年を記念し、1992(平成4)年、静嘉堂文庫美術館を東京・世田谷に新設し、創設130周年の2022年、展示ギャラリーを世田谷から東京丸の内の明治生命館(重要文化財)1階に移転。日本を代表する近代洋風建築の中で作品を鑑賞できる。常設展示はなく、企画展でテーマに沿った作品を紹介する。
お茶、茶道具関連の展示では「大名家旧蔵、静嘉堂茶道具の粋」「茶の湯の美、煎茶の美」「名物裂(室町時代以降、珍重された唐物の茶碗を包む袋や絵画・墨蹟の表具用の織物)と古渡り更紗(茶道具を入れる袋や敷物として重用されたインド製の更紗のこと)」などのテーマで展覧会を開催してきた。
★出光美術館 休館中
東京都千代田区丸の内3-1-1
050-5541-8600
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで)金曜日は10:00~19:00(入館は18:30まで) 1200円
出光美術館は、出光興産の創業者であり、美術館の創設者の出光佐三が70余年の歳月をかけて蒐集した美術品を展示・公開するため、1966(昭和41)年、千代田区丸の内の帝劇ビルに開館した。
「伴大納言絵巻」(国宝)、手鑑(厚手の紙で作られた折帖に、古筆の断簡を貼り付けた作品集)「見努世友」(国宝)、伝藤原行成「久松切和漢朗詠抄」をはじめ、書蹟、絵画、縄文土器から江戸時代までの日本の主要な陶磁器、ジョルジュ・ルオーなどの洋画のコレクションを所蔵し、年6回の企画展を開催。
茶道具は、野々村仁清の「色絵芥子文茶壺」(重要文化財)、本阿弥光悦の「赤楽兎文香合」(重要文化財)などの茶道工芸美術品を所蔵。館内の一角には建築家の谷口吉郎が設計した茶室「朝夕菴」があり、季節に合わせた茶道具の展示を行う。
朝夕菴では、仙厓義梵和尚の命日10月7日に茶会を開催。仙厓和尚が住職をしていた福岡県博多の聖福寺は臨済宗の寺院で、明菴栄西が創建した日本最初の本格的な禅寺。「扶桑最初禅窟」(日本で最初の禅宗寺院という意味)として有名で、栄西が中国から九州に帰国して最初に建てられた寺院である。
『喫茶養生記』を著わして日本に茶を広めた栄西ゆかりの寺の住職を務めた仙厓は画家でもあり、ユーモア溢れる禅画を描いている。出光佐三が19歳に入手したのが仙厓の作品で、佐三が美術品を集める出発点となった。2024年12月に展覧会活動を修了し、ビル建替のため長期休館中。
三井記念美術館
東京都中央区日本橋室町2-1-1 三井本館7階
050-5541-8600
休館日 月曜日 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 1200円(特別展1500円)
三井家から寄贈を受けた日本、東洋の優れた美術品を収蔵していた三井文庫別館が、三井グループに縁の深い日本橋に移転して、2005(平成17)年に三井記念美術館として開館。「志野茶碗 銘 卯花墻」、円山応挙の「雪松図屏風」などの国宝が6点、重要文化財が75点、重要美術品が5点など、約4000点を収蔵する。
国宝、重要文化財など名品が多い茶道具を中心に、円山応挙などの円山派の絵画、中国古拓本(三井高堅が蒐集したもので、高堅の邸宅の名前から、聴冰閣コレクションと呼ばれる)、書蹟、能面など多岐に渡る。
展示室には、三井家ゆかりの国宝の茶室「如庵」を忠実に再現したコーナーがあり、季節に合わせて茶道具を取り揃える。
如庵は、織田信長の実弟の織田有楽が京都・建仁寺の境内に建てた茶室で、1908(明治41)年に三井家の所有となり、その後売却され、現在は愛知県犬山市にある日本庭園、有楽苑に移築されている。
現在、国宝の茶室は如庵を含めて3棟あり、「国宝茶席三名席」と呼ばれている。如庵の他の茶室は、京都府の山崎にある妙喜庵の待庵と、京都の大徳寺龍光院の密庵(小堀遠州の作と伝えられる)。
所蔵品の中核をなす茶道具には、国宝「志野茶碗 銘 卯花墻」の他、重要文化財「黒楽茶碗 銘 俊寛」、「大名物 唐物肩衝茶入 北野肩衝」などがある。
日本で焼かれた茶碗で国宝に指定されているのは、本阿弥光悦の「楽焼白片身変茶碗 銘 不二山)」(サンリツ服部美術館蔵)と、この卯花墻の2碗だけ。
卯花墻は美濃の牟田洞窯で焼かれたもので、歪んだ器形、奔放な篦削り(作陶の過程で篦を使い、形を整える手法)、釉下の鉄絵(鉄分を多く含んだ下絵具で釉薬の下に絵付けしたものを鉄絵という)などは織部好み(古田織部が好んだ器で、わびを基調としながらも、自由闊達で豪奢、大胆な美の追求に特色がある)に通じる部分がある。
千利休、弟子である古田織部や織田有楽などが手がけた茶道具や同時代の茶器を収蔵するが、常設展は行っておらず、「茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具―」などの企画展の開催時に茶道具の名品に出会える。
根津美術館
東京都港区南青山6丁目5-1
03-3400-2536
休館日 月曜日(祝日の場合は翌火曜日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 企画展1400円 特別展1600円(オンライン日時指定予約はそれぞれ100円引き)
山梨県に生まれ、東武鉄道の社長などを務めた実業家、根津嘉一郎が蒐集した日本、東洋の古美術品コレクションを保存、展示するために1941(昭和16)年に開館。嘉一郎は南海電鉄の沿線の会社、東京の地下鉄など、30の鉄道会社の経営に関わり、鉄道王と呼ばれた。
若い頃から古美術品に関心を寄せていた嘉一郎は、1896(明治29)年、東京に本拠を移すと、政治、教育の世界にも活動の場を広げた。茶の湯に勤しむようになると、美術品の蒐集に拍車がかかり、絵画、書蹟、彫刻、陶磁、漆芸、金工、木竹工、染織など、東洋古美術品を多岐に渡って入手。コレクションは秘蔵するのではなく、「衆と共に楽しむ」ことを願っていた。
1940年、父の死を受けて2代目根津嘉一郎が27歳で東武鉄道社長に就任し、同年に財団を設立し、翌年、美術館を開設する。だが、1945年の戦災で展示室や茶室などの大部分を焼失したが、幸いなことに美術品は災害を免れた。
1954年に美術館本館を再建し、2度の増改築を経て、建築家、隈研吾の設計により2009年にリニューアルオープン。4つの茶室が点在する、約1万7000平方メートルの緑豊かな日本庭園を散策したり、庭園内のカフェでお茶や軽食を味わいながら、ゆっくりとした時間を過ごせる。
1940年の財団設立時、4643点でスタートした所蔵品は、現在7630件に増加。尾形光琳の「燕子花図」や、中国の南宋から元の水墨画家、牧谿の「漁村夕照図」などの国宝7件、円山応挙の「藤花図」、「無学祖元墨蹟 偈断簡」などの重要文化財92件、重要美術品95件が含まれる。
コレクションの大部分は初代嘉一郎の蒐集によるもので、晩年、自ら青山と号し、茶の湯を楽しみ、多くの名物茶器を蒐集。茶の湯の道具類が充実しており、日本を代表する「茶の美術館」として知られている。
「青井戸茶碗 銘 柴田」「雨漏茶碗」「瀬戸丸壺茶入 銘 相坂」「鼠志野茶碗 銘 山の端」などの茶碗や「古芦屋松梅文真形霰釜」とおい茶釜を所蔵するが、いずれも重要文化財。
荏原 畠山美術館
東京都港区白金台2-20-12
03-3447-5787
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 春季展・夏季展(4~9月)
10:00~16:30(入館は16:00まで) 秋季展・冬季展(10~3月) 1500円(オンラインチケット料金1300円)
荏原 畠山美術館は「茶の湯の文化を広める美術館」として知られ、茶道具を中心に書画、陶磁、漆芸、能装束など、日本、中国、朝鮮の古美術品を公開する。収蔵品は、国宝6件、重要文化財33件を含む約1300件。
創立者の畠山一清は能登の国主、畠山氏の後裔で、東京帝国大学工科大学を卒業し、技術者としてポンプの開発に取組み、荏原製作所を興した。渦巻ポンプの発明の他、送風機、水中モーターポンプなど数十種の製品を開発し、後に発明協会の会長も務めた。
事業のかたわら、即翁と号して能楽と茶の湯を嗜み、芸術品の蒐集に努めた。昭和の初めに旧・寺島宗則伯爵邸のあった白金猿町の土地約3000坪を購入し、奈良般若寺の遺構や、加賀前田家の重臣横山家の能舞台を移築して私邸「般若苑」を造営し、1943(昭和18)年に開苑の茶会を催している。
第二次世界大戦後、国宝の「林檎花図」(伝 趙昌筆。南宋時代)、「煙寺晩鐘図」(伝 牧谿筆。南宋時代)、「禅機図断簡」(因陀羅筆 楚石梵琦賛。元時代)をはじめ、大名茶人の松平不昧(出雲松江藩10代藩主。治郷)の茶道具や加賀前田家伝来の能装束などの美術品を蒐集。
文化的価値の恒久的な保存を図り、一般の鑑賞に対応するため、苑内に美術館を建設し、1964(昭和39)年、畠山記念館を開館。2024年9月にリニューアルして「荏原 畠山美術館」に名称を変更した。
古筆や墨蹟などの書作品も多く収蔵。古筆は、主に鎌倉時代以前の書を指し、巻物の一部を切り取って掛け軸にして茶道の席に飾ることが多く、書を掛け軸にしたものを古筆切という。墨蹟は墨で書いた文字で、日本では特に禅僧が書いたものを指すことが多い。
書関連の国宝は「離洛帖」(藤原佐理筆。平安時代)と、「大慧宗杲墨蹟 尺牘(書状のこと)」の2点。大慧宗杲は宋代の禅僧で、精神性を重んじた禅僧の書が数多く日本に流入し、茶人に好まれた。
宋代の禅僧、大慧宗杲の庵号から付けられた寺院が、京都の山崎にある妙喜庵。妙喜庵の茶室、待庵は千利休が独特の構想で建てた茶室で、現存する茶室としては最古の遺構(国宝)。本能寺の変で織田信長を討った明智光秀と対峙している山崎の合戦の陣で、秀吉を労うため、茶を供した茶室を移築したものだ。
茶道具が充実しており、茶碗では樂長次郎の「赤楽茶碗 銘 早船」、本阿弥光悦の「赤楽茶碗 銘 雪峰」などを所蔵し、小堀遠州作の茶杓、尾形乾山作の「色絵福寿文手鉢」や、茶入、水差、花入、香合、釜などを展示。
泉屋博古館東京
東京都港区六本木1-5-1
050-5541-8600
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
11:00~18:00(入館 17:30まで) 金曜日は19:00まで開館
企画展は1000円 特別展は1200円
泉屋博古館東京は、住友家が蒐集した美術品を保存、展示する京都の泉屋博古館の東京分館。京都の泉屋博古館は15代当主、住友友純(春翠の別荘の鹿ヶ谷にあり、東山の穏やかな山容を望む風光明媚な環境にある。
住友家の美術品で最も有名なものは、住友春翠が明治中頃から大正期にかけて蒐集した中国古銅器と鏡鑑。中国以外では質量ともに最も充実したコレクションとして世界的にも高く評価されている。
貴重な青銅器と鏡鑑500点余りを保存公開するための財団法人として1960(昭和35)年に泉屋博古館は発足し、1970年、京都鹿ヶ谷に4室からなる青銅器と鏡鑑の展示室が完成。泉屋博古館の名称は、江戸時代の住友の屋号「泉屋」と、900年前に中国で皇帝の命によって編纂された青銅器図録『博古図録』から取られている。
その後も住友家から数々の美術品の寄贈を受けた泉屋博古館の収蔵品は、現在3500点を超えている。収蔵品の増加に伴い、1986年に青銅器展示館の傍らに新展示室を増築し、さらに2002(平成14)年に東京六本木に「泉屋博古館分館」を開設。「泉屋博古館分館」は、2020年1月から改修工事のため休館し、館名を「泉屋博古館東京」に改称し、2022年3月にリニューアルオープンした。
泉屋博古館が所蔵する美術品は中国青銅器・鏡鑑の他に、中国、日本の書画、洋画、近代陶磁器、茶道具、文房具、能面、能装束など多様で、国宝2件、重要文化財13件(19点)、重要美術品60件。
茶道具も充実しており、5代当主の友昌は裏千家8代家元、又玄斎一燈好みの道具を集め、12代友親は小堀遠州遺愛の茶碗「小井戸茶碗 銘 六地蔵」などを蒐集。
茶の湯や能楽といった日本の古典芸能を嗜み、数々の茶会を催した15代友純(春翠)は後陽成天皇命銘の茶入「唐物文琳茶入 銘 若草」や後水尾天皇ゆかりの「青磁福寿文香炉」などを集めた。茶の湯釜、茶杓、竹花入などの名品も多い。
サントリー美術館
東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア3階
03-3479-8600
休館日 火曜日 年末年始
10:00~18:00(入館は17:30まで) 金曜日は10:00~20:00(入館は19:30まで) 展覧会により異なる 呈茶(薄茶とお菓子)1200円
https://www.suntory.co.jp/sma/
サントリーは1899(明治32)年に鳥井信治郎が創業して以来、「利益三分主義」を経営哲学としてきた。事業で得た利益を「事業への再投資」「得意先、取引先へのサービス」「社会への貢献」に役立てるというもの。
後を継いだ2代目社長の佐治敬三は、心の豊かさの重要性を認識し、文化活動を推し進め、1961年、サントリー美術館を東京・丸の内に開館。その後、赤坂見附に移転し、さらに2007年に東京ミッドタウン(六本木)に移転。「生活の中の美」を基本理念とし、「美を結ぶ。美をひらく。」を掲げ、感動に出会える企画展を開催してきた。
収蔵品は絵画、陶磁、漆工、染織などの日本の古美術から東西のガラス製品まで、国宝1件、重要文化財16件、重要美術品21件を含む約3000件に上る。常設展はなく、年に約6回の企画展で公開し、お茶、茶道具関連では「大名茶人 織田有楽斎」「寛永の雅 江戸の宮廷文化と遠州・仁清・探幽」などの展覧会を開催。
サントリー美術館の6階にある茶室「玄鳥庵」は通常非公開だが、企画展開催中の指定日にお茶と季節のお菓子を振舞う呈茶席を設けており、貸席として茶会などにも利用できる。
「玄鳥庵」は赤坂見附から移設・増設したもので、建築家の隈研吾の監修により立礼席のデザインを改め、八畳の広間と屋外テラスを増設。屋外テラスには腰掛待合と蹲踞(茶庭に設置され、客が茶室に入る前に手を清め、口をすすぐための手水鉢と役石を置いて趣を出したもの)を設置している。
戸栗美術館
東京都渋谷区松濤1-11-3
03-3465-0070
休館日 月曜日 火曜日(祝日の場合は開館、月・火曜日両方祝日の場合は翌平日休館) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 金曜日と土曜日は10:00~20:00(入館は19:30まで) 入館料は展覧会により異なる
家業が山梨県の土木建築業だった戸栗亨は上京して工務店を興こすが、伝統的な日本文化を保存し、後世に伝える必要があると、陶磁器を中心に美術品を蒐集。渋谷区松濤にあった佐賀藩の鍋島家屋敷跡に1987(昭和62)年、戸栗美術館を開館した。
コレクションは伊万里、鍋島などの肥前磁器と中国、朝鮮などの東洋陶磁を中心に約7000点に及び、数少ない陶磁器専門の美術館として、年4回の企画展を開催している。
古伊万里には茶碗、菓子鉢、水指、花入、香炉、香合など、茶の湯、生け花、お香のための道具が数多く残されており、中国の景徳鎮窯のティー・カップなども所蔵。
茶道具では「染付 蛸唐草丸文 碗」「染付唐草文人物鈕茶入」「染付 楼閣山水葦雁文 水指」「染付 孔雀形香合」「染付⾠砂花⽂三⾜⾹炉」などを所蔵している。
五島美術館
東京都世田谷区上野毛3-9-25
050-5541-8600 03-3703-0661(テープ案内)
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 夏期整備期間 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 1100円
東急グループの創設者、五島慶太(ごとう けいた)が蒐集した美術品を収蔵し、テーマごとに企画展示を行っている。慶太の古美術蒐集は奈良時代の古写経に始まり、後に自ら「日本一」と誇る古写経コレクションを築く。その後、僧侶の書(墨蹟)など中世の美術に興味が広がり、やがて茶の道に引き込まれた。
収蔵品は日本、東洋の古美術が中心で、茶碗、茶入、茶杓などの茶道具も充実しており、中国陶磁器、絵巻、古筆、墨蹟、古写経、銅鏡、刀剣などの古美術と近代日本画、文房具類も含まれる。
『源氏物語絵巻』や『紫式部日記絵巻』などの国宝5件、重要文化財50件を含む約5000件に上り、1年に6~7回展示替えをする。常設展示は行っていないが、ホームページで絵画、書蹟、茶道具、陶芸、考古などのジャンルごとに所蔵品を掲載。
茶道具では「黄瀬戸平茶碗 銘 柳かげ」「志野茶碗 銘 梅が香」「唐物円座肩衝茶入 銘 利休円座」「芦屋獅子牡丹紋釜」「古備前耳付花生」「武野紹鴎作茶杓 筒 片桐石州」「亀甲蒔絵棗」などを所蔵している。
庭園には四季折々の草花が咲き、2017(平成29)年に茶室「古経楼」、「冨士見亭」が本館とともに国の登録有形文化財になった。ひょうたん池や石仏の大日如来像などが配置され、美術品だけでなく庭も楽しめる。茶室は通常非公開だが、お茶会や特別公開時に建物の内部を鑑賞できる。
併設の「大東急記念文庫」は日本、中国、朝鮮の国書、漢籍、仏書、古文書、芸術資料の他、懐紙、書帖、短冊などの歌学資料約2万5000点を所蔵。国宝3件、重要文化財33件が含まれる。文庫の資料は一般公開しておらず、国文学、歴史学、美術史学、仏教学などの学生や研究者に利用されている。閲覧の手続きは大東急記念文庫に連絡(03-3703-0662)。五島美術館の休館日を除く10:00~17:00。
「五島美術館の名品」がホームページで紹介されている。
ttps://www.gotoh-museum.or.jp/collection/
永青文庫 細川コレクション
東京都文京区目白台1-1-1
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
10:00~16:30(入館は16:00まで) 1000円
永青文庫は肥後熊本藩の藩主だった細川家の屋敷跡にあり、細川家に伝来する美術品や歴史資料などの文化財を管理保存し、一般に公開している。
細川家は室町幕府の三管領の一角として武門の誉れ高い家柄。三管領は足利氏一門の斯波氏、細川氏、畠山氏を指し、管領は室町幕府で将軍に次ぐ最高の役職で、将軍を補佐して幕政を統轄した。それに次ぐ七頭は山名氏、一色氏、土岐氏、赤松氏、京極氏、上杉氏、伊勢氏が務めた。
管領家だった細川家は戦国時代に没落し、佐々木源氏をルーツに持つ現在の細川家は傍流で、戦国時代の細川藤孝(幽斎)を初代とし、3代忠利のとき肥後熊本54万石を与えられ、外様大名として幕末まで続いた。
初代藤孝は、和歌については『古今和歌集』の秘伝の解釈である「古今伝授」の継承者となるほどの文化人で、藤孝の長男、忠興(三斎)は数々の武功を挙げ、千利休の高弟として茶道にも秀でており、ガラシャ(明智光秀の娘)を妻とした。
永青文庫は16代細川護立によって1950(昭和25)年に設立され、1972年から一般公開を始めた。永青文庫のコレクションは、江戸時代以前から細川家のコレクションとして伝わったものと、近代になって16代の護立を中心に蒐集されたものに大別できる。
護立は、近代日本有数の美術品コレクターとして知られており、中学時代に病床に伏したとき、白隠の書画や刀剣に興味を持ったのが美術品蒐集のきっかけとなった。横山大観や菱田春草がまだ無名であった頃から作品に強く魅かれ、大観の「山路」や春草の「黒き猫」「落葉」などを蒐集。大観とは亡くなるまで深い親交を続けた。
国宝8件、重要文化財35件を含む、約6000点の美術工芸品と8万8000点の歴史資料を所蔵。コレクションが多岐に渡るため、永青文庫では毎回テーマを設けて展覧会を開催。
千利休の高弟とされる7人の武将を利休七哲と呼ぶが、忠興はその1人。「利休七人衆」として、利休の孫の千宗旦が、前田利長、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田織部、牧村利貞(兵部)、高山右近(南坊)、芝山宗綱(監物)を挙げている。
後に織田有楽、金森長近が7人に入ることもあったが、蒲生氏郷と細川忠興(三斎)の2人は外せない茶人として扱われ、大封(大きな領地)を持たない古田織部が利休の後継者となった。
忠興は茶道の流派、三斎流の祖で、三斎流は細川家を離れ、一尾流、御家流など、いくつかの流派に分れて現在に至っている。永青文庫は「黒楽茶碗 乙御前」「粉引茶碗 大高麗」「瓢花入 顔回」などの茶道具を収蔵。
石洞美術館
東京都足立区千住橋戸町23
03-3888-7520
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 500円
千住金属工業は東京都足立区に本社を置くはんだ材料、FA装置、すべり軸受事業などを行っている企業で、創業者の佐藤千壽は、本社社屋の一画に石洞美術館を2006(平成18)年に開館した。佐藤の雅号「石洞」が美術館の名称の由来となっている。
人々の心に働き掛け、幸福につながり、国際的な相互理解を深めるものとして、佐藤は美術工芸に魅力を感じ、10代後半から世界各地の焼物、茶の湯釜、仏像、漆器、青銅器などを中心に蒐集。
日本の陶磁器を約420件所蔵し、人間国宝の濱田庄司、島岡達三など近現代陶芸作家の作品の他、古陶磁では、瀬戸黒茶碗や沖縄の陶器などがある。明時代末期に景徳鎮の民窯で焼かれ、日本の茶人に愛された古染付は佐藤が最も愛した陶磁器の1つで、約140件所蔵し、日本有数のコレクションとなっている。
金工は約130件を所蔵し、茶の湯釜のコレクションは充実しており、芦屋釜、天明釜など16件所蔵し、そのうち2件は重要美術品。館蔵品を中心とした企画展を年3回程度開催。
美術工芸振興佐藤基金を設立し、美術館の運営の他、伝統工芸日本金工展を開催。日本古来の鋳金、鍛金、彫金などの金属工芸の保存と発展のため、生活に則して創作された作品を募り、一般の人々に鑑賞、批評を仰ぐ展覧会を2012年から日本工芸会とともに主催している。
神奈川県
三溪園 三溪記念館
神奈川県横浜市中区本牧三之谷58-1
045-621-0634
休館日 年末
9:00~17:00(入館は16:30まで) 900円
原三溪(富太郎)は明治から昭和の前半に、生糸貿易で財を成し富岡製糸場などの製糸工場の経営に携わった実業家で、蚕糸業界(カイコを飼い、生糸を作り販売する産業を蚕糸業と呼び、主な業種は蚕種製造業、養蚕業、製糸業の3つ)、横浜の経済界、社会と文化貢献に功績を残した。
1902(明治35)年、自宅を横浜市西区の野毛山から本牧三之谷に移転。三重塔、仏閣、茶室など、京都や鎌倉などから集められたの数々の建物を移築し、四季の色彩を楽しめ、横浜にいながら古都の風情を感じられる日本庭園と自宅を兼ねた三溪園を造った。
「三溪園の明媚な自然の風景は創造主のものであって、私有物ではない」との考えから、1906年から一般に公開。蒐集した美術品、建物、庭園は戦後、原家から横浜市に譲られ、公益財団法人三溪園保勝会によって保存、公開されている。
1923(大正12)年の関東大震災で、横浜は壊滅的な打撃を受けたが、横浜市復興会の会長に就任し、私財を投げ打ち横浜の復興に尽力し「横浜の恩人」と呼ばれた。
原三溪は、実業家でありながら美術愛好家でもあり、横山大観、下村観山、小林古径、前田青邨、今村紫紅、速水御舟、安田靫彦らの作品を購入したり、生活費を支援して芸術家を助けた。
美術品蒐集家で、茶人だった三溪が25歳頃から集めたコレクションは5000点を超え、没後、美術館や他の個人蒐集家に分散したが、三溪記念館で収蔵している美術品は約500点で、その一部を展示。
展示室では、原三溪に関する資料、三溪園の歴史、関連する人物の紹介、三溪自筆の書画、 ゆかりの作家の作品や美術工芸品などを公開。三溪記念館に連なる臨春閣は「東の桂離宮」と評される建物で、障壁画を展示し、記念館が収蔵する美術品をここでも鑑賞できる。
三溪は南画家の祖父、叔父を持つ岐阜県の名家の出身で、アーティスト気質を持ったコレクターとして骨董を始め、自らも絵筆を執った。茶の湯で、旧美濃加納藩主の永井尚穀をもてなし、自ら描いた書画を披露すると、目の肥えている尚穀がいくつかの作品を買い上げたほどの腕前であった。
実業で多忙極める中、三溪園の邸宅や庭園で芸術家や文化人と交わり、自らも漢詩を読み、絵画を描いた。三溪園の庭園には重要文化財10棟、横浜市指定有形文化財3棟を含む歴史的建造物が四季折々の自然と調和するように配され、国の名勝となっている。
茶の湯を楽しんだ原三渓は「近代三茶人」の1人。他の2人は、三井財閥を支え、三井物産の設立に関わった益田孝(鈍翁)と、「電力の鬼」と呼ばれ、電力業界の再編に力を尽くした松永安左エ門(耳庵)。
三溪はコレクター、茶人、アーティスト、パトロンという4つの側面を持ち、近代日本の美術界に大きな足跡を残した。三溪が生涯に購入した美術品は没後に分散したものの、三渓が生まれた岐阜市の三溪記念室(岐阜市歴史博物館分室)など、日本各地の美術館や博物館、個人に受け継がれている。
三渓の住まいだった鶴翔閣や、白雲邸、月華殿、林洞庵、織田信長の弟、有楽の作と伝えられる茶室「春草廬」などの古建築は茶会、句会、会議、結婚式、撮影、展示会場などに貸し出している。「楽茶碗を作る 楽茶碗で点てる」「茶の湯文化にふれる市民茶会」や、クラシックコンサート、フォトコンテスト、生け花、観月会など、多様なイベントを開催。
松永記念館 小田原市郷土文化館分館
神奈川県小田原市板橋941-1
0465-22-3635
休館日 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 無料
松永安左エ門は長崎県壱岐島の出身で、慶應義塾に入学し、福沢諭吉と共同で石炭商などの事業を手掛けた後、九州で電気事業の経営に関わり、愛知県の名古屋電灯と福岡県の九州電灯鉄道を前身とする東邦電力の設立に参画し、経営に携わった。
東邦電力は、その後、中部電力、関西電力、九州電力、四国電力に継承されている。第二次世界大戦の最中、電力各社は1社に統合されて国家統制となり、松永は経営を離れ、一時引退を余儀なくされた。
このとき、阪急グループの創設者、小林一三から勧められて茶の湯に楽しむようになり、茶道具の蒐集に精を出す。松永は50代後半で、孔子の言葉「六十耳順」(六十にして耳順う)にちなんで「耳庵」と号した。
戦後の占領下で、松永は電力事業の再編を主導して九電力体制を推進し、「電力王」「電力の鬼」と呼ばれ、日本の産業政策に対して提言を行い、政府の政策にも影響力を持った。
戦後、松永は小田原に転居するが、それまで住んでいた埼玉県所沢の住居、茶室、蒐集していた茶道具の一部、有楽井戸、蒲生氏郷の茶杓、志野茶碗・橋姫などを無償で東京国立博物館へ寄贈。寄贈しなかった美術品は1959(昭和34)年に設立した財団法人松永記念館が所蔵し、蒐集した古美術品を一般公開していた。
だが、同財団は1979年に解散し、住居の敷地と建物は小田原市に寄付され、戦後に蒐集した茶道具や仏教美術など重要文化財20件を含む371点のコレクションは福岡市美術館に、一部が京都国立博物館、愛知県陶磁資料館などに引き継がれた。
福岡市美術館の松永コレクションには、いずれも重要文化財の「猿投灰釉壺」「色絵吉野山図茶壺 野々村仁清作」「五彩魚藻文壺 大明嘉靖年製」などがある。
松永は、近代小田原|三茶人(さんちゃじん》の1人。北条早雲以降の後北条氏の時代も茶の湯が盛んだったため、「近代」が付けられている。
近代小田原三茶人は、小田原在住で茶道を究め、三井物産の設立に関わった益田鈍翁(益田孝)、中外商業新報社(日本経済新聞社の前身)や三越呉服店(現・三越伊勢丹)の社長だった野崎幻庵(野崎廣太)と、松永耳庵(安左エ門)の3人を指す。
近代茶道の3人の偉人として、益田鈍翁、松永耳庵に加え、生糸貿易で財を成し、富岡製糸場などの経営再建を行った原三渓(原富太郎)を「近代三茶人」と称している。
1946年に小田原に移り住んだ松永は1971年、95歳で亡くなるまで居宅「老欅荘」で過ごした。
小田原市では、1980年に小田原市郷土文化館の分館として松永記念館を設置し、特別展や企画展を本館・別館の展示室で開催。1986年に移築した茶室「葉雨庵」や、松永の居宅「老欅荘」などが国登録有形文化財となっている。庭園は「日本の歴史公園100選」に選ばれていて、四季折々の花が咲き誇る。
長野県
サンリツ服部美術館
長野県諏訪市湖岸通り2-1-1
0266-57-3311
休館日 月曜日(祝日を除く) 年末年始
9:30~16:30(入館は16:00まで) 1000円
服部時計店(現・セイコーホールディングス)の創業者、服部金太郎の次男で、服部時計店3代目社長の服部正次はセイコーを世界的な時計ブランドに育て上げた。
製薬メーカーの三共(現・第一三共)の創業者で、茶人、美術収集家でもあった義父の塩原又策の影響を受けて茶の道に入り、山楓と号した。服部正次は茶道具を中心とした工芸品、日本と東洋の古書画などを蒐集。
正次の長男で、セイコーエプソン社長だった服部一郎はルノワールやシャガールなど西洋近代絵画を集めた。服部正次と一郎のコレクションと、1986年に吸収合併した関連会社、サンリツ工業のコレクションを展示するため、1995(平成7)年、サンリツ服部美術館を開館した。
同美術館は茶道具、古書画、西洋近代絵画など約1400点の作品を収蔵し、国宝は、本阿弥光悦作の「楽焼白片身変茶碗 銘 不二山」と、鎌倉末期から南北朝時代の水墨画家、可翁の「紙本墨画寒山図」の2点。重要文化財は「玳皮盞天目」「青山白雲図 伝 明兆画」など19件、重要美術品は「伯庵茶碗 銘 奥田」「唐物茄子茶入 銘 紹鷗茄子」など19点。
茶碗、棗、花入、茶杓など茶道具を中心とするコレクションとして有名で、日本で焼かれた茶碗で国宝に指定されているのは、本阿弥光悦の「楽焼白片身変茶碗 銘 不二山」と、「志野茶碗 銘 卯花墻」(三井記念美術館蔵)の2碗だけだ。
服部一郎記念室では近現代の西洋絵画を展示しており、東洋、西洋双方の芸術文化、美術が楽しめる。
美術蒐集家の塩原又策は、江戸初期の大名茶人、小堀遠州が持っていた「茶入 於大名」や小堀遠州が建てた茶室「転合庵」などを有していたが、塩原の死後、妻の千代が東京国立博物館に寄贈。塩原コレクションの陶磁器などの名品は、サンリツ服部美術館に引き継がれている。
静岡県
MOA美術館
静岡県熱海市桃山町26-2
0557-84-2511
休館日 木曜日(祝日の場合は開館) 展示替え日
9:30~16:30 (入館は16:00まで) 1760円(オンラインチケット1540円)
MOA美術館 | MOA MUSEUM OF ART
箱根美術館の創立者で、熱海美術館(現・MOA美術館)を開設した岡田茂吉は、1897(明治30)年に東京美術学校(現・東京藝術大学)予備ノ課程に入学するが、眼の疾病のため中途退学した。
前半生を実業家として、後半生は宗教家として足跡を残した岡田は幼年期から骨董、絵画に深い関心を寄せていた。健康を快復してからは、蒔絵制作に打ち込み、工芸技法を習得して簪や笄など婦人装身具のデザインと販売で成功。各種博覧会でも高い評価を得て、実業家としての地位を築いた。
しかし、身辺で不幸が重なり、関東大震災や世界恐慌などにより事業も傾き、哲学、思想、宗教の研究に没頭し、1935(昭和10)年に世界救世教のルーツとなる宗教結社、大日本観音会を創始。優れた美術品は人間の本質に強く働きかけ、心を陶冶し、健全な社会を形成するという芸術観を持ち、美術品の蒐集を行い、日本文化を世界に発信する美術館の創設を目指した。
1952(昭和27)年に箱根美術館を開館し、1957年に熱海美術館を開館。岡田の生誕100周年にあたる1982年、約7万1500坪の広大な庭園内に、伊豆大島や初島を見渡せる丘陵地に、熱海美術館を継承したMOA美術館をオープン。MOAはMokichi Okada Associationの頭文字を取ったものだ。
現代アート作家で、建築家の杉本博司と、建築家の榊田倫之によって設立された建築設計事務所「新素材研究所」の監修で、特殊なガラスケースを使って作品を展示し、2017(平成29)年、仕切りを意識させないなどのリニューアルを行った。
MOA美術館には日本、中国の書蹟などの美術品の他、絵画、彫刻、陶磁器、染織、漆工、金工、木工などを所蔵し、展示する。尾形光琳筆「紅白梅図屏風」、野々村仁清作「色絵藤花文茶壺」、三大手鑑の1つとして知られる手鑑「翰墨城」高野切(伝 紀貫之)の3点の国宝、重要文化財67点、重要美術品46点など、多くの名品がある。
書の関連では国宝の手鑑「翰墨城」の他、「関戸本和漢朗詠集切」(伝 藤原行成)、菅原道真、小野道風、一休宗純、夢窓疎石などの書蹟を有する。岡田は『岡田茂吉墨筆集』『岡田茂吉全集』『自然農法解説書』などの著書を著わしている。
MOA美術館では、豊臣秀吉が千利休に作らせた組立て式、移動可能な「黄金の茶室」を60キログラムの金を使って再現。正親町天皇に茶を献じるため1586(天正14)年に作られた茶室で、京都の北野天満宮で開催された大規模な茶会、北野大茶湯などでも披露された。
黄金の茶室を再現しているミュージアムは多いが、最初に再現したのがMOA美術館。掛け軸は、豊臣秀頼が8歳のときに書いた直筆の書。
MOA美術館が所蔵する茶道具コレクションには、「色絵金銀菱文重茶碗 野々村仁清作」「黒楽茶碗 銘 あやめ 樂長次郎作」「唐物箆目肩衝茶入 大名物」「志野木瓜香合」「蓮に鶺鴒 葦に翡翠図 伝 牧谿」などがある。
愛知県
徳川美術館
愛知県名古屋市東区徳川町1017
052-935-6262
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 1600円 徳川美術館と蓬左文庫の料金
尾張徳川家に伝わる遺品や大名道具を展示する美術館で、収蔵品は駿府御分物(徳川家康の遺品)、徳川将軍家や一橋徳川家、蜂須賀家など他の大名家が売立て(一定量の品物を決まった期日に売る方法)で手放した購入品、名古屋の豪商からの寄贈品などで、国宝9件、重要文化財59件、重要美術品46件を収蔵し、総点数は1万3000点に上る。
公益財団法人徳川黎明会が運営しており、尾張徳川家2代当主の徳川光友の隠居所であった大曽根別邸の跡地に1935(昭和10)年に開館。旧大名家のコレクションを基に、旧大名家自らが設立した最初の美術館で、尾張徳川家の邸宅跡の日本庭園、徳川園に隣接している。
世界的に有名な源氏物語絵巻(国宝)や千代姫婚礼調度(国宝)などを収蔵し、質と保存状態の良さは他の追随を許さない。名品コレクション展示室では尾張藩主の公的生活の場であった名古屋城二之丸御殿の鎖の間と広間の一部、能舞台、猿面茶席を復元。尾張徳川家の雛まつり(毎年2月上旬~4月上旬開催)をはじめ、多彩な企画展で注目度は高い。
茶道具では、白天目茶碗(重要文化財)、豊臣秀吉に切腹を命ぜられた千利休が、自ら削り、最後の茶会に用いた後、古田織部に与えた「竹茶杓 銘 泪」などを所蔵。名品の茶道具を間近で見られる茶会を秋に開催(予約制)。
桑山美術館
愛知県名古屋市昭和区山中町2-12
052-763-5188
休館日 開館期間中の月曜日(祝日の場合は翌日) 祝日の翌日
開館は以下の3つの期間。
新春:1月上旬~2月上旬 (全所蔵品からの企画展)
春季:4月上旬~7月上旬 (日本画中心の企画展)
秋季:9月上旬~12月上旬 (茶道具中心の企画展)
10:00〜16:00(入館は16:00まで) 800円
綿布を製造販売していたが、不動産業に転じた桑山清一のコレクションによって、1981(昭和56)年に開館した桑山美術館は、閑静な住宅街にある。丸みを帯びた緑の屋根とベージュのタイル壁の外観はヨーロッパの古城を彷彿とさせる。
コレクションの中心は、明治以降の近代日本画と、茶碗や花入などの茶道具で、日本の洋画と現代陶芸なども所蔵。
近代の日本画と鎌倉時代から現代までの茶道具を中心とし、テーマによって年3回の展示替えを実施。新春は全所蔵品からテーマごとの企画展を開催し、春季は日本画を中心、秋季は茶道具中心の展覧会を行う。
茶道具は「金海州浜茶碗」「古染付水指」「竹一重切花入 利休在判」「沢瀉蒔絵平棗」「祥瑞角橋杭香合」などを所蔵。
敷地内の庭園も見事で、茶室は庭園、本館2階、別館2階(立礼席)の3室あり、別館1階の多目的ホールは講演会、講習会などに利用できる。回遊式の庭園にはさまざまな形態の燈籠が点在し、四季を通して季節の花が咲き、散策を楽しめる。
昭和美術館
愛知県名古屋市昭和区汐見町4-1
052-832-5851
休館日 展示期間中の、祝日を除く月曜日と火曜日
10:00〜16:30(入館は16:00まで) 1000円
昭和美術館は、日本車輌製造や中央製作所の社長を務めた実業家の後藤幸三が蒐集した書蹟、茶道具を保存・公開するため、1978(昭和53)年に名古屋駅の南東にある昭和区に開館。館蔵品は重要文化財4点を含む約800点、そのうち8割が茶道に関するものとなっている。
上期(春)、下期(秋)、新春と、年に3回の展示を行い、四季の移ろいを感じる庭園も魅力。2200坪の敷地の中心に池があり、「南山寿荘」にある「捻駕籠の席」の他、「有合庵」「鶴の舎」の3つの茶室が点在。「捻駕籠の席」は尾張藩の家老の渡辺規綱が建てた茶室を移築したもの。規綱は裏千家11代玄々斎の実の兄で、武家茶人として知られている。
茶道具は、使う人の心の内にある思いを託されており、茶人の道具への思い入れが伝わってくる。「古瀬戸尻膨茶入 銘 伊予簾」「瀬戸黒茶碗 銘 垣根」「黒織部茶碗 銘 板庇」「色絵和蘭陀筒水指」などを所蔵。
南山寿荘、有合庵などの日本建築、侘び寂びの風情ある庭園の景観に浸りながら、茶道具を愛でる。有合庵では、学芸員による説明を受けながら作品を鑑賞する特別鑑賞会も開催(抹茶とお菓子付)。
唐九郎記念館
愛知県名古屋市守山区翠松園1-1710
052-795-2110
休館日 月曜日~木曜日 開館は金曜日、土曜日、日曜日、祝日
10:00~16:00 300円
愛知県東春日井郡(現・瀬戸市水北町)出身の加藤唐九郎は陶芸家で、陶磁史の研究家。瀬戸系古窯の本格的な調査を行い、桃山時代の陶芸の研究と再現に努め、志野焼や織部焼に挑戦した。
1960(昭和35)年、永仁の壺事件が発生し、重要文化財に指定されていた「瀬戸飴釉永仁 銘 瓶子」が自らの模作であると表明し、古瀬戸の大規模な贋作を行っていたことが発覚。これを機に、一切の公職を辞任して、作陶に専念。
1976(昭和51)年、財団法人翠松園 陶芸記念館を設立。唐九郎記念館は唐九郎が作陶してきた窯場と住居に隣接して建てられ、桃山時代の織部、志野、黄瀬戸の復元に成功した加藤唐九郎の作品や研究資料、唐九郎が蒐集した桃山陶片などを展示。「昭和の志野を作る」と発言していた唐九郎の最高傑作と言われる「志野茶碗 紫匂」「志野茶碗 氷柱」など、約200点を所蔵している。
★楽只美術館 休館
愛知県名古屋市東区泉1-17-28
052-961-3578
休館日 月曜日
10:00~16:00 300円
楽只美術館は、表千家の北山会館や、裏千家の茶道資料館のように、茶道松尾流の美術館として1987(昭和62)年に開館した。茶道松尾流家元の寄贈によるもので、松尾流歴代の作品や好みの道具を主として収蔵。展示室の他、収蔵庫、集会室、図書室などを備えている。
松尾家の家祖は京都で呉服商を営んだ辻玄哉。玄哉は武野紹鴎の門人で、千利休に台子点前を伝授した兄弟子として知られ、玄哉の流れを汲む松尾宗二(物斎)は千宗旦(利休の孫)の門人。松尾流は、宗二に始まる茶道の流派で、宗二は、宗旦から「楽只軒」の書、「楽只」銘の茶杓と花入を贈られている。この3点は松尾家の家宝とされ、相続披露の茶事のみに用いられている。松尾家伝来の茶道具を中心に、美術工芸品などを展示していた。
瀬戸蔵ミュージアム
愛知県瀬戸市蔵所町1-1
0561-97-1190
休館日 第4月曜日(例外の場合もあり) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 520円
瀬戸蔵ミュージアムは、瀬戸の観光拠点施設「瀬戸蔵」の2階~3階に焼物博物館として2005(平成17)年に開館。1978(昭和53)年に開館した瀬戸市歴史民俗資料館が移転、拡充して生まれたミュージアムで、瀬戸物の大量生産で活気のあった時代をイメージし、街の象徴である旧尾張瀬戸駅(名古屋鉄道 瀬戸線)、「モロ」と呼ばれる焼物工房、石炭窯、煙突などを再現している。
瀬戸の焼物の始まりは旧石器時代の土器からで、約1600年前の古墳時代に生まれのが、瀬戸焼の母体の「猿投窯」だ。古墳時代中期の5世紀頃、現在の愛知県猿投地区(尾張東部から三河西部)に埴輪や須恵器窯の「猿投古窯群」が誕生。猿投窯は、平安時代に日本初の人工施釉陶器の灰釉陶器を生産して高級食器として流通し、窯業の一大生産地となった。
瀬戸焼は日本六古窯の1つで、六古窯は日本古来の陶磁器窯のうち、中世から現在まで生産が続く代表的な6つの窯をいう。瀬戸焼の他は、常滑焼(愛知県常滑市)、越前焼(福井県丹生郡越前町)、信楽焼(滋賀県甲賀市)、丹波焼(兵庫県丹波篠山市今田町立杭(立杭焼とも)、備前焼(岡山県備前市伊部(伊部焼とも)」。
平安時代後半の11世紀末から、瀬戸焼の製品は粗略化し、灰釉陶器から無釉の山茶碗の日用雑器に生産シフトしていく。瀬戸焼は広く流通し、瀬戸物は陶磁器を表す一般名詞になっている。
室町時代末期、桃山時代に茶の湯が盛んになり、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部などの茶器が人気を集めたが、茶人に好まれた茶器の生産拠点は美濃(岐阜県)に移った。
瀬戸蔵ミュージアムは、古墳時代から江戸時代の焼物を時代ごとに展示し、瀬戸焼の変化をたどり、明治以降、工業化された窯業の実態を生産道具や再現された生産設備で解き明かす。抹茶碗展示コーナーでは、陶芸作家が制作した黄瀬戸や志野などの茶碗が50点ほど展示されている。
岩田洗心館
愛知県犬山市大字犬山富士見町26
0568-61-4634
休館日 日曜日~火曜日 開館は水曜日~土曜日
10:00~16:00 500円
財団法人岩田洗心館の設立者の岩田錦平(鈍牛)は犬山町長も務めた旧家で、自ら蒐集した書画、茶道具、岩田家伝来の道具類約540件の保存と公開のため美術館の創設を計画したが、その途中で急逝。嗣子の岩田忠夫夫妻が遺志を継ぎ、1970(昭和45)年に岩田洗心館を開館。
犬山市庁舎の移転新設事業に伴い、旧館を解体し、2011年、旧所在地の北側に新館を開設。所蔵品は書画、陶磁器類、茶道具、漆器など約700件1800点に上る。コレクションは、犬山城下の富裕な商家であった岩田家の家財道具の中で美術的価値があるもの、岩田家歴代が蒐集した茶道具類、鈍牛が蒐集した茶道具類と近代日本画に大別できる。
文化・文政時代から明治にかけて隆盛を誇った犬山城(白帝城)下の町人文化の一端を窺わせ、犬山焼約40件、近世俳人の作品約140件などもある。
犬山焼は、江戸時代の元禄年間、今井村(現在の犬山市今井)で、郷士の奥村伝三郎が今井窯を築いて焼物を作った(今井焼)のが始まりで、その後、犬山城主の成瀬正寿が1810(文化7)年、城下の丸山に開窯し、その周辺一帯で焼かれた陶磁器を指す。雲錦手(雲錦は、白雲で満開の桜を、錦は紅葉を表現しており、京焼の代表的なデザイン)や赤絵を特徴とする。
常設展示室では犬山焼を含む陶磁器約100件を展示。企画展示は2~3ヶ月ごとに展示内容を変更し、掛軸、漆器、金属器類などを展示。犬山焼を紹介する映像も鑑賞できる。茶室「鈍牛庵」は岩田洗心館の西北に位置し、書院と四畳半の茶室からなり、年に数回、茶会などの催しの際に公開される。
有楽苑(国宝茶室 如庵)
愛知県犬山市犬山御門先1
0568-61-4608
休館日 水曜日(祝日の場合は開館、振替休日あり) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 1200円 呈茶料一服 600円
安土桃山時代から江戸初期に、茶の湯が大名や武士の間で広まったが、織田信長の13歳年下の弟で、千利休の門弟の茶人、織田長益(有楽)、有楽斎とも)は1618(元和4)年、京都の建仁寺の正伝院を復興し、茶室「如庵」を創建。有楽のクリスチャンネーム「Joan」「Johan」から付けられたと言われている。
信長の次男、織田信雄、豊臣秀吉、徳川家康に仕えるなど、波瀾に富んだ人生を送った有楽の生涯と同様に、茶室も各地を点々とする。1873(明治6)年、正伝院は永源庵跡地に移転し、その際、如庵は祇園町の有志に払い下げられ、1908(明治41)年、東京の三井本邸に移築された。
このとき解体せずに原型のまま車両に積んで東京まで運搬し、三井の重鎮で、「小田原三茶人」「近代三茶人」と呼ばれた茶人の益田孝(号は鈍翁)が如庵を愛用。1936(昭和11)年に重要文化財(旧国宝)に指定され、その後、1938年に、三井高棟によって神奈川県の大磯の別荘に移築された。1951年、文化財保護法による国宝に指定。
1972年、名古屋鉄道によって、犬山城(愛知県犬山市)の東にある「日本庭園 有楽苑」に移築し、如庵が京都にあった時代の庭園を可能な限り再現。有楽苑には、国宝茶室「如庵」、重要文化財の「旧正伝院書院」、古図に基づいて復元された「元庵」、茶会のために新築された茶室「弘庵」などがある。
日本庭園 有楽苑は、日本の数寄屋造りの中に美を見出し、伝統文化とモダニズム建築の調和を追求した建築家で、歌人の堀口捨己の監修によって築造された庭園だ。堀口は『利休の茶』で北村透谷文学賞を受賞し、『利休の茶室』『茶室研究』などの著作も上梓。
如庵は、京都山崎の妙喜庵の「待庵」、大徳寺龍光院の「密庵」とともに、現存する国宝茶席三名席の1つ。
弘庵で呈茶サービスを行っており、有楽苑の茶室を茶の湯の席として利用することも可能。有楽斎好みの意匠を施した元庵、大寄せの茶会を催すなら広間のある弘庵があり、茶人には至福の場所となっている。
とこなめ陶の森資料館
愛知県常滑市瀬木町4丁目203
0569-34-5290
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:00〜17:00 無料
1981(昭和56)年に開館した常滑市民俗資料館が母体の、とこなめ陶の森資料館は2012(平成24)年、資料館、常滑陶芸研究所、陶芸研修工房の3つの施設を持つ「とこなめ陶の森」の1つとして誕生した。
40周年の2021(令和3)年、常滑焼の振興と伝承、焼き物文化の創造と発信を目指すミュージアムとしてリニューアルオープン。常設展示室では、国指定の重要有形民俗文化財の「常滑の陶器の生産用具及び製品」1655点から約300点を選んで、生産用具(製土、成形、乾燥、施釉、窯入れ、焼成、窯出し、運搬の各工程)と製品を分かりやすく展示している。
知多半島の風土に育まれた常滑焼は日本六古窯の1つで、1000年の歴史があり、平安時代末期、瀬戸市南部、名古屋市東部、豊田市にまたがる猿投地区に猿投窯が誕生し、それが南下して伝わり、知多半島に古窯群が誕生。
猿投窯では、釉薬を付ける灰釉陶器と、釉薬のない山茶碗の日用雑器が作られ、その流れを汲む常滑焼では壺、甕、茶碗などが作られ、大型の焼物が中心だった。
室町時代になると、知多半島に広く分布していた窯が常滑周辺に集まり、碗や皿類の生産は行わず、壺、甕、鉢の生産に特化していく。
江戸時代の常滑焼は高温で焼き締めた真焼物と素焼き状の赤物の製品群があり、真焼物は甕、壺を中心とするが、茶器や酒器などの小細工物と呼ばれる陶芸品も登場。赤物は素焼きの甕、壺、蛸壺、火消壺、竈、火鉢や、土樋と呼ばれた土管などを生産。
資料館の常設展示のコンセプトは「つながる千年、ひろがる千年、暮らしの中で生きる常滑焼」。常滑で焼物が盛んになり、人々の暮らしをどう支え、どう変えてきたのかを紐解く。常滑の陶器、生産用具、製品などを、ビデオやスライドも使って分かりやすく展示し、特別展示室では、常滑の急須、水指、茶瓶などの企画展を開催している。
岐阜県
原三溪記念室(岐阜市歴史博物館分室)
岐阜県岐阜市柳津町下佐波西1-15 もえぎの里2階
058-270-1080(もえぎの里)
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 祝日の翌日 年末年始
9:00~17:00 無料
2000(平成12)年に整備された複合施設「もえぎの里」に併設された旧・柳津町歴史民俗資料館は、2006年から岐阜市歴史博物館分室「柳津歴史民俗資料室」となり、2016年、「原三溪記念室」にリニューアルされた。
ふるさとの偉大な先人、原三溪(原富太郎)の生き方を学び、夢や志を持ち、自らの生き方を考える施設となっている。
原三溪は1868(慶応4)年、岐阜県厚見郡下佐波村(現在の岐阜市柳津町)で、地主の青木家の長男として出生。儒学者に学んだ後、東京専門学校(現・早稲田大学)で政治学や経済学を学び、東京の文京区小石川にあった跡見学校(跡見女学校、現・跡見学園女子大学)の教師を務めた。
跡見学校の教え子だった原屋寿(屋寿子とも)と結婚。屋寿は、横浜の豪商、原善三郎の孫で、三溪は原家の原商店に入り、実業の世界に転じた。
横浜市を拠点とした三溪は絹の貿易で富を築き、三井家が経営していた富岡製紙場や栃木、名古屋、四日市の製糸場を1902年に譲り受け、経営を立て直した。第一次世界大戦(1914~1918年)の影響で、生糸の輸出停滞、糸価の暴落、過剰生糸問題への対応が急務で、 1915年に帝国蚕糸が創設され、三渓が社長となって処理に当たった。
生糸の貿易で横浜の経済界をリードしてきた茂木惣兵衛(3代目)の茂木合名会社が倒産したとき、三渓は茂木の銀行、七十四銀行を整理し、1920年に横浜興信銀行(後の横浜銀行)が設立し、頭取に就任して負債処理を行った。1923年の関東大震災で横浜が大打撃を受けた際は、横浜市復興会の会長となり、私財を投じ横浜の復興に貢献。
原三溪は美術品の蒐集家としても知られ、横山大観、下村観山、小林古径、前田青邨、今村紫紅、速水御舟、安田靫彦らの作品を購入し、生活の援助もした。横浜市本牧に京都や鎌倉から移築した歴史的価値の高い建造物を配置した広大な日本庭園「三溪園」を造った。
25歳頃から集め始めたコレクションは5000点を超え、没後、他の美術館や個人収集家に分散。日本や中国の古美術品(書画や茶道具)を集めるとともに、同時代の画家の作品を購入。
原三溪記念室(岐阜市歴史博物館分室)の主な内容は、古美術蒐集、茶の湯、芸術家たちへの支援、社会貢献などさまざまな分野で活躍した三溪の業績、関わってきた人物、三溪園などをパネルやゆかりの品とともに紹介。「三渓の趣味と古美術収集」「三渓と茶の湯」のコーナーで、茶の湯との関わりを解説する。『岐阜が生んだ原三溪と日本美術――守り、支え、伝える』という展覧会図録も販売(1400円)。
三渓が描いた書画も展示。三溪の絵では「竹生島図」「秋景山水図」「鵜舟図」「鷹図」「風竹図」などを所蔵し、書では「南都吟」「帰省途上吟」などを有する。
岐阜の郷土新聞を発行する岐阜新聞社のデジタルデータの活用事例として、岐阜女子大学が岐阜県ゆかりの偉人にスポットを当てて作成したのが「報道記事から見る岐阜の偉人たち」。そこで「原富太郎」が紹介されている。https://digitalarchiveproject.jp/wp-ontent/uploads/2020/07/96f2dab8f0174dd4ba459051dd6e0f67.pdf
財団法人はまぎん産業文化振興財団は、特別記念号「原三渓に学ぶ公共貢献物語」を発行。
https://yokohama-viamare.or.jp/pdf/myway/m_77.pdf
茶の湯の森 茶の湯美術館
岐阜県高山市千島町1070
0577-37-1070
休館日 水曜日(祝日は開館) 冬期休日
9:00~17:00(入館は16:00まで) 800円
茶の湯の森は1999(平成11)年に開館し、「茶の湯美術館」「茶室 瑞雲庵」「銅閣庵」「研修棟秀礼館」の4棟で構成される施設で、流派や作法にとらわれず、誰もが気軽に茶の湯文化に触れ、親しむために設立された。1998年にオープンした高山祭を紹介する施設「飛騨高山まつりの森」に隣接している。
陶芸家の荒川豊蔵の「志野茶碗」、加藤唐九郎(新設された重要無形文化財の人間国宝には認定されなかった)の「黒織部茶碗」など、13名の人間国宝の作品と直筆の掛軸を中心に展示し、それぞれの作家の優れた感性に触れることができる。
茶道家元、千家の専属職人である千家十職の釜や表具の作品や、中世に活躍した名工の作品なども収蔵。茶碗師として約400年にわたり活躍し続けてきた京都の陶工の名門、樂家の作品は必見で、初代の樂長次郎から15代(当代)の樂吉左衛門の歴代作品を一堂に公開している。
茶道具、輪島塗屏風、茶人や天皇などの重要人物の掛軸、玉虫の茶道具、平成の玉虫の厨子など約1600点を所蔵し、そのうち百数十点を順次展示。「茶室 瑞雲庵」では、人間国宝をはじめ名工の茶碗で呈茶を楽しむことができ、旬の食材を使った点心や貸室の予約も可能。「銅閣庵」は広間(10畳)と寄付(白湯をいただきながら身支度を整え、亭主の案内を待つ待合室。7畳)を中心とした数寄屋造の建物で、茶室として利用されるが、普段は美術館の付帯施設として、季節に応じた茶道具を展示。
高山は茶の湯と深い関わりがある。織田信長に仕えた金森長近は飛騨高山藩の初代藩主で茶人。千利休の切腹後、利休の長男の千道安は、金森長近の養子で、高山藩2代藩主の金森可重に預けられたとされる。可重の長男の重近は宗和の号で知られ、宗和流茶道の祖。
宗和流茶道は、宗和の子息によって金沢の加賀藩の茶道流派となり、その後、高山にも伝えられ寺院を中心に伝承。1964年、宗和流茶道は高山市の無形文化財に指定された。
岐阜県図書館が「宗和流茶道の祖 金森宗和」について解説。https://www.library.pref.gifu.lg.jp/gifu-map/gifu-related-materials/gifu-pioneer/page/kanamori-sowa.html
齋藤美術館
岐阜県郡上市八幡町新町927
0575-65-3539
休館日 木曜日 1月~2月
10:00~16:00 300円(やなか三館共通券700円)
清流と名水の城下町、郡上八幡の中心部に、柳の木が立ち並び玉石が美しい観光スポット「やなか水のこみち」がある。齋藤美術館、心の森ミュージアム・遊童館、奥美濃おもだか家民芸館の「やなか三館」は、水のこみちを囲むように建っている。
岐阜県の奥美濃の山里、郡上八幡は長良川の上流に位置し、宗祇水(室町時代の連歌師、飯尾宗祇が郡上八幡の湧水の傍らで庵を結び、愛飲したことから宗祇水と呼ばれる)に代表される清冽な水と、7月中旬から9月上旬まで開催される三大盆踊りの郡上踊りで有名。
齋藤美術館は、野中稲荷神社の脇にある「やなか水のこみち」に面しており、郡上八幡の豪商で、代々茶人を輩出してきた齋藤家が長年に渡り蒐集してきた茶道具、書画などのコレクションを紹介するため、1987(昭和62)年に開館。
両替商で財を成した齋藤家は、1718(享保3)年の初代から、郡上藩主の遠藤家、青山家などと親交があり、茶道具類を京都の商人から仕入れて販売する商いもしており、茶道具が家宝として受け継がれてきた。茶碗、菓子器、香合、茶入、棗、屏風、掛軸など、茶道具コレクションは1300点を超える。
常設展示室では、名物茶碗などの茶道具を中心に、墨蹟などの書画や漆芸品を公開。「樂家3代道入作 浅瀬」香合「交跡柘榴」「大徳寺156世江月宗玩墨蹟夢」は齋藤美術館の三大コレクション。
蔵展示室は、齋藤家の土蔵を改装し展示室としており、永楽や祥端の煎茶茶碗や染付急須などの煎茶道具のコレクションや、向付、小皿、漆器などを展示する。特別展示室は、通常、陶磁器や今では貴重となった手摺りの木版画を中心に展示販売し、企画展の開催、貸し展示スペースとして利用することも可能。
中庭には茶室「龍庵」と、水琴窟(手水鉢の近く設けられた地中の空洞に手水鉢の排水を落とし、その音を反響させて地上に聞こえるようにした仕掛け)があり、郡上市の重要文化財に指定された母屋はカフェ「町家さいとう」として町家造りの風情を残す。
織部の里もとす 古田織部展示館
岐阜県本巣市山口676
0581-34-4755
休館日 不定休(道の駅と同じ)
10:00~16:00
戦国時代から江戸時代初期の武将、茶人、芸術家の古田織部(重然)の故郷は美濃国(現在の本巣市)。「歴史と文化の交差点」を標榜する「織部の里もとす」にある古田織部展示館では織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に仕えた古田織部の人物像、「天下一の茶人」と呼ばれた織部と茶の湯との関わり、織部焼などを紹介。茶室があり、織部流の茶道体験もできる(有料)。
千利休の「人と違うことをせよ」という教えを守った古田織部の焼物、織部焼の特徴はいびつな形、左右非対称であることを重視し、完成品をわざと壊してつなぎ合わせて作るなどの手法も用い、文様は市松模様、幾何学模様、扇子などをかたどったデザインを多用。
「ふざける」という意味の「へうげる」「ひょうげる」に由来する「へうげもの」は「ひょうきん者」という意味と、「面白い形の物」という意味もある。大胆、奇抜なものを好んだ古田織部は「へうげもの」と呼ばれ、織部の焼物も「へうげもの」であった。
古田織部は千利休の高弟で、利休七哲の1人。茶器、会席道具の製作、茶室の建築、作庭などに独自のスタイルを持ち「織部好み」と呼ばれ、多くの弟子を擁した。千利休の後継者として茶の湯を大成し、一大ブームをもたらしたが、大坂夏の陣で、豊臣側と内通したと嫌疑をかけられ、自害。
千利休の茶の湯を基礎に、茶事や陶芸に自由・奔放の独自の世界を開いた「織部流茶道」を創始し、多くの大名家に受け継がれた。
織部の里もとすは農産物、特産品の物販エリア、本巣市の観光スポットやイベント情報などを発信する「情報館」、文化振興を目的とした展示を行う山門ギャラリー、地元食材を使った食事を味わえるレストランなどがある。
荒川豊蔵資料館
岐阜県可児市久々利柿下入会352
0574-64-1461
休館日 月曜日 (祝日は開館) 祝日の翌日 年末年始
9:30~16:00(入館は15:30まで) 210円
昭和を代表する美濃焼の陶芸家、荒川豊藏は、桃山時代の志野焼に陶芸の原点を求め、古志野の再現を目指して作陶を重ね、「荒川志野」と呼ばれる独自の境地を確立した。
志野、瀬戸黒の2つの工芸技術で国の重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された豊蔵は1984(昭和59)年に豊蔵資料館を開館。2013年、資料館を可児市に寄贈し、「荒川豊蔵資料館」に名称変更。
豊蔵は、可児市の久々利大萱の牟田洞古窯跡で、1930(昭和5)年、志野筍絵の陶片を発見。これは「日本の陶磁史を覆す大発見」で、志野が愛知県の瀬戸などで作られたのではなく、美濃(岐阜県)で作陶されていたことが分かり、豊蔵は志野の再現を志し、この地に移住した。
志野、織部、黄瀬戸、瀬戸黒などを「美濃桃山陶」というが、安土桃山時代に東濃地方で一斉に開花。東美濃地方の中で、可児市は「美濃桃山陶の聖地」と呼ばれている。だが、美濃桃山陶は20年~30年で姿を消す。
荒川豊蔵資料館は豊蔵の陶芸作品、自筆の絵画の他、豊蔵が蒐集した古陶磁器、工芸品、古書画、出土陶片などを多数収蔵しており、年4回程度の企画展示を行っている。敷地内にある居宅(旧・荒川豊蔵邸)や陶房を改修し、無料で公開している。
瑞浪市陶磁資料館
岐阜県瑞浪市明世町山野内1-6
0572-67-2506
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 200円
瑞浪市陶磁資料館は志野、織部、黄瀬戸、瀬戸黒などの美濃桃山陶をはじめ、古代から現代までの美濃焼、明治以降に使われていた陶磁器の生産用具や機械を展示し、美濃焼1300年の歴史を紹介するミュージアム。
「焼き物ってどうやって作るの?」「陶器と磁器ってどこが違うの?」「焼き物の模様ってどうやって付けるの?」などの疑問に答えるスタイルになっていて、年に数回の企画展や特別展で美濃焼の魅力や技術を伝える。作陶・絵付けなどの体験教室も開催。
瑞浪市稲津町小里にある興徳寺の大型の茶壷も展示。瑞浪市陶町大川にある大川窯の4代目、羽柴与左衛門景度が制作したものと言われる。多くの茶壺は高さ30~40センチメートル程度だが、高さ54センチの大型の茶壺で、「興徳寺の茶壺」として瑞浪市の文化財に指定されている。
織田信長や豊臣秀吉などの武将の強大な権力の下で、豪華絢爛な桃山文化が発展し、権力者が集まる場として「茶の湯」は栄華を極めた。秀吉の朝鮮出兵によって、朝鮮から製陶技術が日本に入ったことも、技術の発展につながり、各地で窯が開かれた。中でも美濃桃山陶は茶人に好まれた。
国宝となっている「志野茶碗 卯花墻」は桃山時代の代表的な名碗で、千利休の後継者となった古田織部は美濃で「織部好み」と呼ばれる斬新な紋様や独自の形の茶器を追求し、破調の美を確立。
美濃で多くの茶陶が作られたが、大坂夏の陣の直後、古田織部が切腹してから、茶の湯の本場は京都へと移り、美濃地域の茶陶は衰退。志野の生産も途絶え、美濃で作陶されていたことすら、忘れ去られてしまった。
安土桃山時代に注目された志野は、昭和初期まで、現在の愛知県瀬戸地域で作られたと考えられていたが、1930(昭和5)年、荒川豊蔵が現在の岐阜県可児市の久々利大萱の牟田洞古窯跡で、徳川家に伝わる「竹の子文志野筒茶碗 銘 玉川」と同じ筍絵の志野の陶片を発見し、志野は美濃で作られていたことが判明。
瑞浪市出身の人間国宝、加藤孝造の作品を紹介する「加藤孝造展示室」を2016(平成28)年に開設し、瀬戸黒、志野などの茶陶を中心とする陶芸作品を常時展示している。
志野が美濃で作られていたことは忘れられたが、江戸時代後期の文化・文政年間(1804年~1830年)、美濃に磁器の生産技法が伝わり、長石や珪石などの窯業原料を粉砕した石粉の需要が高まった。
土岐郡小里村(現・瑞浪市稲津町)の庄屋、和田亀右衛門光度と、興徳寺住職の林恭邦和尚は、精米などに使われていた水車の利用を思い立ち、1850(嘉永3)年に水車を動力として複数の杵を動かす粉砕機「千本杵搗」を完成させた。
最盛期には東濃地域で400を超す大水車が稼働していたが、1955年以降、廃車が進み、瑞浪市陶磁資料館が屋外展示する千本杵搗しか残っていない。現在は電力で動くようになっていて、希望すれば回っている水車を見ることができる。
★土岐市美濃陶磁歴史館 休館中
岐阜県土岐市泉町久尻1263
0572-55-1245
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 祝日の翌日 年末年始
10:00~16:30(入館は16:00まで)
土岐市美濃陶磁歴史館は岐阜県土岐市にある美濃焼に関する博物館で、志野焼や織部焼など「美濃桃山陶」の歴史や概要を紹介し、研究するために1979(昭和54)年に開館。須恵器から江戸時代の元禄期までの陶磁史と特徴を焼物の作品に基づいて解説している。
美濃桃山陶は、日本の陶磁史上最も華やいだ時期と言われる安土桃山時代に、現在の可児市をはじめ東濃地方で焼かれた陶器を指し、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部といった焼物も含まれる。美濃桃山陶は長い間、愛知県瀬戸市で焼かれた「せともの」と考えられており、「黄瀬戸」や「瀬戸黒」という名称にもその名残りが見られる。
16世紀末に生まれた志野は、日本で初めて白い釉の下に筆で絵や文様を描いた焼物で、豊かな装飾性、鉄分を含む顔料で文様を描き、半透明な釉に浮かぶ鉄絵の斬新さは茶人を虜にし、茶の湯の人気とともに隆盛を極めた。
可児市の久々利大萱の牟田洞古窯跡で、国宝の「志野茶碗 銘 卯花墻」(三井記念美術館所蔵)が焼かれたと言われており、「志野」は国宝や重要文化財に指定されている名品が多く、美濃桃山陶を代表する焼物と言える。
年1回の特別展と年4回の企画展を開催してきたが、建物の老朽化などもあり、2024(令和6)年3月末で休館。美濃陶磁歴史館に隣接する旧文化会館跡地に新博物館を建設し、2028年に開館予定。工事期間中は仮展示場で展覧会を開催する。
三重県
石水博物館
三重県津市垂水3032-18
059-227-5677
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 500円
石水博物館は、江戸時代から松阪木綿や茶を扱ってきた伊勢商人の川喜田家伝来のコレクションや資料を中心に、川喜田家16代当主で、陶芸家としても知られる川喜田半泥子の作品やゆかりの品々を保存管理している。半泥子の本名は久太夫政令。
川喜田家は17世紀末には川北屋の名で木綿問屋となり、江戸日本橋にも店を持ち、両替商も始め、歌川広重の浮世絵にも描かれている豪商。1878(明治11)年には津で百五銀行(津市に本店を置く地方銀行。東証プライムに上場)を創業している。
歴代当主には歌人や茶人など風流人が多く、半泥子も百五銀行などの頭取、三重県財界の重鎮であったが、50歳を過ぎてから本格的に作陶し、津市の自宅に窯を開き、主に抹茶茶碗を製作。自由奔放な作風で、書や画も趣味とし、作品はほとんど売ることはなく、友人知人に分け与えた。
半泥子は、地域文化の振興と社会福祉活動の拠点として1930(昭和5)年に財団法人石水会館を設立し、後に人間国宝となる陶芸家の荒川豊蔵(とよぞう)、金重陶陽、三輪休雪を支援。
1963年に半泥子が亡くなって、「石水会館」は1975年に登録博物館となり、2010年に名称を石水博物館に変更。半泥子ゆかりの千歳山(津市垂水)に新しい展示施設を新築し、2011年に移転開館した。
収蔵品は茶道具、日本画、洋画、古書典籍、錦絵、伊勢商人関係資料など多岐に渡る。茶道具では「伝千利休作 竹花生 銘 音曲」「伝本阿弥光悦作 赤楽茶碗 銘 松韻」「織部黒茶碗 銘 暗香」「古伊賀水指 銘 鬼の首」などを所蔵。
新潟県
木村茶道美術館
新潟県柏崎市緑町3-1 松雲山荘内
0257-23-8061
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 12月~3月(冬期は休館)
10:00~16:30 展示室500円 特別展示室1200円(屋内茶席 会記、説明、お茶付) 屋外茶席600円(お菓子付。土・日・祝日のみ)
松雲山荘は、柏崎瓦斯(ガス)の創設者、飯塚謙三の旧居で、画家の伊藤武陵の「六曲屏風絵」を基に1926(大正15)年に築庭された庭園。ツツジ2000本、モミジ600本、赤松200本など多数の樹木に覆われ、灯篭、石碑、太鼓橋、池、巨石などを配し、紅葉の名所としても有名。1971(昭和46)年、柏崎市へ譲渡され、一般公開された。
飯塚謙三は、柏崎出身で日本石油を設立し「日本の石油王」と呼ばれ、政治家でもあった内藤久寛を敬愛し、ガス会社を興した。松雲山荘は大正末期から昭和中期にかけて作庭された池泉回遊式庭園で、大きな池を中心に配し、周囲に園路を巡らしている。
庭園には、1984年に開館した「木村茶道美術館」がある。木村重義(寒香庵)が生涯をかけて集めた茶道具、古書画、陶器などを季節ごとに展示している。
木村寒香庵は米国への留学経験を持ち、新潟県の旧制長岡中学や旧制柏崎中学で英語教諭として教鞭を執った後、柏崎近郊の旧北条村(現在は柏崎市と合併)の村長を務めた。茶道を極め、茶道教師となり茶の湯の普及に努めた。蒐集した茶道具と先祖伝来の山林や家屋敷、1億円相当の株券を柏崎市に寄付。柏崎市は、譲渡されていた松雲山荘に木村茶道美術館を新設。
茶碗では「黒楽茶碗長次郎焼」「大井戸茶碗 銘 玉の井」をはじめ、樂焼は長次郎から当代まで歴代が揃う。茶入、薄茶器類、茶杓、水指、花入、香合、風炉、硯箱、台子、茶箱、鉢皿など400点余りのコレクションでスタートしたが、元柏崎市長夫人、三井田梅乃の遺族が掛物や茶碗などを寄贈し、収蔵品を充実させている。庭園を眺めながら風情を楽しめる屋外茶席もある。
敦井美術館
新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル
025-247-3311
休館日 日曜日 祝⽇ 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 500円
敦井美術館は、新潟市にある総合商社、敦井産業の創業者で、北陸瓦斯の社長も務めた敦井榮吉が蒐集した美術品を展示する美術館で、1983(昭和53)年、新潟駅から徒歩約3分のビジネス街に開館。敦井産業創業60年、敦井榮吉の満95歳の誕生日のオープンだった。
敦井が自宅に飾るため蒐集した約1000点と、その後に集められた作品を含め、約1700点の美術品を所蔵し、年に4回開催の企画展で公開される。所蔵品は陶芸、日本画、洋画、彫刻、文人画、書、漆芸などで、所蔵品の大半を占めるのが陶磁器。
日本画では横山大観、菱田春草、速水御舟、小林古径など、日本美術院の作家の作品が多く、京都画壇の竹内栖鳳、橋本関雪、土田麦僊、村上華岳の作品も蒐集。
茶道具では、歴代の樂家、板谷波山、富本憲吉、楠部彌弌らの茶盌、水指、茶入、花瓶、竹工芸家の飯塚琅玕斎の花入などの名品がある。板谷波山の「彩磁禽果文花瓶」は国の重要文化財に指定されている。
明治以降の陶芸家で、国の重要文化財となっている作品は、敦井美術館の波山の他に、波山の「葆光彩磁珍果文花瓶」(泉屋博古館蔵)と、宮川香山の「褐釉蟹貼付台付鉢」と「黄釉銹絵梅樹図大瓶」、三代清風与平の「白磁蝶牡丹浮文大瓶」(3点、いずれも東京国立博物館蔵)の5点しかない。
富山県
富山市郷土博物館・富山市佐藤記念美術館
富山県富山市本丸1-62 富山市郷土博物館
076-432-7911
富山県富山市本丸1-33 佐藤記念美術館
076-432-9031
休館日 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 210円
富山市郷土博物館は、富山市の中央に位置する富山城址公園にあり、戦災復興事業の完了を機に、1954(昭和29)年に開催された「富山産業大博覧会」の記念建築物として建設された。3重4階建ての城郭を模した建物で、博覧会の終了後、郷土の歴史・文化を紹介する郷土博物館として開館。中世以来の富山城の歴史を紹介する博物館として2005年にリニューアルオープンした。
富山城は、越中(富山県)の守護代を務めた神保長職が、家臣の水越勝重に命じて1532(天文元)年に築城させた。神保家は、室町幕府の管領(室町幕府で将軍に次ぐ最高の役職で、将軍を補佐して幕政を統轄した。三管領家は斯波氏、細川氏、畠山氏)の畠山氏の鎌倉以来の家臣だ。
富山城は、その後、佐々成政、前田利長の居城となり、前田利家の孫の富山藩主、前田利次が入城し、以降約230年間、富山前田家の居城として栄えた。富山城址公園には、石垣や濠などの遺構が残り、戦後に建てられた天守閣がある。天守閣の内部が富山市郷土博物館で、富山の歴史や文化を紹介。富山城址公園には、日本の近世絵画や東洋の古美術、茶道具を紹介する佐藤記念美術館がある。
富山県砺波市出身の実業家で、茶人でもあった佐藤助九郎(12代目、助庵、宗越)が中心となり、1961(昭和36)年に佐藤美術館を開館。佐藤助九郎は、家業の土木建設業を発展させ、北陸創業のゼネコン、佐藤工業を設立。北日本新聞社社長、貴族院議員も務め、富山の政財界で活躍。茶道、書画、漢詩、俳句、陶芸を嗜み、富山市の呉羽山麓に「呉山窯」を築いた。
美術館はその後、富山市に寄贈され、富山市佐藤記念美術館と改称し、富山市郷土博物館と2館一体で運営。美術館内には「柳汀庵」「助庵」の2つの茶室があり、総檜造りの書院座敷が移築されている。
柳汀庵は、大名茶人の金森宗和の指導で造られたと言われ、加賀藩家老の横山家から佐藤家を経て移築され、二畳台目(丸畳二畳と台目畳一畳で構成された茶席のこと)の本席、七畳半の煎茶趣味の意匠を持つ部屋、三畳の水屋(茶室に隣接して設ける、茶事の用意のための場所)で構成されている。
茶室「助庵」は、江戸前期の茶人で、表千家の久田宗全好みの半床庵に基づいて考案され、佐藤美術館の創設者、佐藤助九郎が柳瀬村(現・砺波市)の自宅に建てたもの。美術館創設時に館内に移築され、「電力の鬼」と呼ばれた松永耳庵(安左エ門)によって助庵と命名された。
佐藤記念美術館の所蔵品は、佐藤家から寄贈された1000点余の作品が中心で、東洋の古美術の絵画、墨蹟、陶磁器など多岐に渡っている。茶道具では「安南染付菊唐草文茶碗」「越中瀬戸焼耳付茶入」「呉須山水絵水指」「青磁玉取獅子香炉」「古伊賀耳付花入」「松花堂好升形釜」などを所蔵。
安田善次郎記念室
富山県富山市宝町1-3-10 明治安田生命富山ビル2階
076-432-2471 (明治安田生命保険 富山支社)
休館日 土曜日 日曜日 祝日 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 無料
安田善次郎は、富山藩の下級武士(足軽)の家に生まれ、半農半士であった。1858(安政5)年、奉公人として江戸に出て、鰹節商と両替商を兼ねた店などに勤め、独立して乾物と両替を商う安田屋を開業する。
1872(明治5)年、国立銀行条例が公布され、善次郎は第三国立銀行を開業、安田銀行に改組し、損保会社、生保会社、不動産会社を擁する安田財閥を形成。安田銀行は戦後、富士銀行に名称を変更し、現在、みずほフィナンシャルグループのみずほ銀行になっている。
JR富山駅の駅前にある明治安田生命富山ビルの入口に安田善次郎の銅像が立ち、ビル2階に「安田善次郎記念室」がある。善次郎の生誕150年を記念して故郷の地に作られたミュージアムで、善次郎の生涯を紹介する展示や自筆の書画、映像などを見学できる。
善次郎は、独立独行で勤勉、正直、貯蓄倹約を旨とし、陰徳慈善(人に知られないよう密かに良い行いをし、人に尽くすこと)の精神を持ち続けた。東京大学大講堂や日比谷公会堂の建設に匿名を条件に寄付していた。
だが、神奈川県中郡大磯町にある別邸・寿楽庵に面会に来た右翼の青年に、1921(大正10)年に刺殺され、82歳の生涯を終える。青年はその場で自決したが、「悪徳な富豪の安田善次郎は巨万の富を築いたが、富豪としての責任を果たしていない」「天誅を加えて世の戒めとする」などのメッセージを残していた。最盛期に国家予算の8分の1に相当する富を築いており、世間の評判はよくなかった。
善次郎は知人の勧めもあって、お茶に興味を持ち、表千家11代碌々斎 宗左に入門し、松翁と名乗った。40歳代前半の1880(明治13)年から『松翁茶会記』を書き始め、1948(大正7)年まで記され、死後の1928年に『松翁茶会記』が出版された。
財界の茶人を招いて開催し、記録に残る茶会だけでも100回を越えており、実業家の茶会の開催を調査した資料でも群を抜いている。松翁の茶会に招かれた茶人の1人は「道具がひどい偽物ばかりだ。安く物を手に入れようとするからだ」と秘かに日記に記していた。
茶の湯の上級者といった傲慢な態度を取ることはなく、控え目で倹約を旨とした善次郎は茶道具に大金を掛けることをしなかった。ただただ茶の湯、茶会が好きだったことが「道具がひどい偽物ばかり」という記録から伺える。
石川県
国立工芸館
石川県金沢市出羽町3-2
050-5541-8600
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
9:30~17:30(入館は17:00まで) 所蔵作品展 300円
国立工芸館は1977(昭和52)年、東京国立近代美術館工芸館として東京・北の丸公園に開館し、唯一、工芸とデザイン作品を専門に扱う美術館として工芸とデザイン文化の発展に取り組んできた。2020(令和2)年10月、石川県金沢市に移転し、日本海側初の国立美術館として開館した。
明治期に建てられた木造の旧陸軍施設「旧陸軍第九師団司令部庁舎」(1898年建造、元は司令部執務室)と「旧陸軍金沢偕行社」(元は将校の社交場)(いずれも国登録有形文化財)を移築、復元して活用。
東京都千代田区にあった従前の東京国立近代美術館工芸館の美術工芸作品のうち1900点強を移転。陶磁器、ガラス、漆工、木工、竹工、染織、人形、金工、工業デザイン、グラフィックデザインなど、明治以降の日本と外国の工芸品、デザイン作品約4000点を収蔵している。
金沢出身の人間国宝、漆芸家の松田権六の工房を移築・復元し、「松田権六の仕事場」として作家ゆかりの制作道具や関連資料を展示し、記録映像も上映。
茶道具では、荒川豊蔵の「黄瀬戸茶碗」、加藤唐九郎の「鼠志野茶盌 鬼ガ島」、濱田庄司の「琉球窯赤絵面取花生」、北大路魯山人の「織部蓋物」、金重陶陽の「備前耳付水指」、松田権六の「鴛鴦蒔絵棗」などの逸品を所蔵している。
金沢市立中村記念美術館
石川県金沢市本多町3-2-29
076-221-0751
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 310円 抹茶・菓子料350円
茶道具と金沢ゆかりの工芸品を鑑賞できる美術館として知られ、茶道の美術品を中心に、古九谷、加賀蒔絵、加賀象嵌など工芸品、近世絵画、現代作家の作品までを所蔵する。
金沢で酒造業(中村酒造)を営む実業家の中村栄俊は1943(昭和18)年、表千家流の茶道に入門し、1945年の敗戦を機に、「戦後の日本は文化国家として繁栄していかなければならない、そのために金沢に美術館を作ろう」と志を立て、精力的に茶道具の蒐集を始めた。
「美術品は一個人のものではなく、国民の宝である」という信念を持ち、蒐集した美術品を寄贈して財団を設立。中村家の住宅を展示棟として現在地に移築・改装し、1966年に中村記念館を開館。その後、1975年、所蔵品を金沢市に寄贈し、金沢市立中村記念美術館として再スタートし、1989(平成元)年、金沢市の市制100周年を記念して美術館を建て直した。
中村栄俊蒐集の名品を核に、個人からの寄贈や市費による購入も加わり、現在、重要文化財5点、県指定文化財1点、市指定文化財8点を含め、所蔵品は1000点を超えている。年に4~6回の企画展で公開し、茶会など多彩な行事を開催。
石川県金沢市の本多の森公園に接し、緑に囲まれた自然環境の中で、「梅庵」「耕運庵」という茶室がある。茶会、句会、香席などに利用でき、喫茶室では抹茶と和菓子を楽しめる。
茶道具には、重要美術品の「砧青磁平水指 銘 青海波」「青井戸茶碗 銘 雲井」「法花蓮池水禽文大香炉」をはじめ、「唐物肩衝茶入 蒲生肩衝」「赤楽茶碗 銘 手枕 初代樂長次郞」「黒織部沓茶碗」「色絵菊桐文茶器 野々村仁清」「利休在判棗」などがある。
中村栄俊が1978年に上梓した『金沢茶道と美術』には、作品を入手したときのエピソードや中村記念館の開館、同時代に活躍した金沢の茶人や数寄者に関する逸話が記されている。中村記念美術館は、国立工芸館、石川県立美術館、石川県立歴史博物館、鈴木大拙館、金沢市立ふるさと偉人館など、ミュージアムが集積するエリアにある。
大樋美術館
石川県金沢市橋場町2-17
076-221-2397
年中無休
9:00~17:00 700円 呈茶付は1500円
1990(平成2)年に開館した大樋美術館は、大樋長左衛門窯の敷地内にあり、初代長左衛門から現代に至るまでの大樋焼の作品や加賀藩に縁の深い茶道具類を展示。350年の歴史を持つ大樋焼は轆轤を一切使わず、手捻り、鉄分を含んだ釉の飴釉(焼き上がりは光沢のある黄褐色、飴色になる)を特徴としている。
1666(寛文6)年、加賀藩5代藩主の前田綱紀は、茶道による文化育成のため裏千家の始祖となる4代仙叟宗室を京都から招き、仙叟は土師(はにし、とも)の長左衛門を茶碗造り師として金沢へ同道した。長左衛門は金沢の東郊、大樋村に開窯し、仙叟の指導のもと、茶の湯の思想を造形化した茶碗、水指、香合などを作り、大樋焼と称されるようになった。
長左衛門は、京都樂家4代の一入の高弟であったため、しっかりとした樂焼の技術を持ち、手と篦だけを使って成形する手捏ねで削りながら、作品を作り上げた。樂焼は、樂家初代、長次郎が千利休の指導により、利休のわび茶に叶う茶碗(樂茶碗)を生み出したのが始まり。
常設展示を行う3つの展示室があり、第1室では、初代長左衛門と裏千家の仙叟宗室の作品を、第2室では、大樋焼歴代の作品を、第3室では、棟方志功、武者小路実篤など、大樋家と関わった文化人や芸術家などが残した作品や資料を公開。陶磁芸術に関する特別展も開催している。
江戸時代に建てられた大樋家は武家屋敷で、歴史的風致形成建造物、金沢市指定保存建造物になっており、邸内には、茶室の芳土庵、陶土軒、松濤間、年々庵があり、建築家の隈研吾設計の大樋ギャラリーには、当代長左衛門(11代)の大樋年雄の作品を展示。
茶の湯の精神に則って進められる婚礼の「茶婚式」も行っている。美術館の外壁は10代長左衛門(陶冶斎)作の陶壁で、前庭の「風庭」は勅使河原宏が監修。ミシュランガイドが、個人美術館では例のない「一つ星」に認定している。
石川県九谷焼美術館
石川県加賀市大聖寺地方町1-10-13
0761-72-7466
休館日 月曜日(祝日の場合は開館)
9:00~17:00(入館は16:30まで) 500円
石川県加賀市は九谷焼発祥の地で、加賀藩の支藩だった大聖寺藩の城下町、加賀市大聖寺で九谷焼が始まった。石川県九谷焼美術館は日本で唯一の九谷焼の専門美術館(登録博物館)として2001年に開館。古九谷をはじめ、吉田屋窯、宮本屋窯などの再興九谷などの九谷焼を網羅して紹介し、特別展の開催や、図録や研究紀要の発行も行っている。
九谷(現在の加賀市山中温泉九谷町)の金山で陶石が発見されたのに機に、大聖寺藩の初代藩主、前田利治は、金山で錬金役を務めていた後藤才次郎に命じて肥前有田で製陶を学ばせた。江戸時代前期、少なくとも明暦年間(1655年頃)に九谷に窯を築いた。
元禄年間の1701年頃、原因は定かではないが、九谷の窯は突然閉じられた。50年間ほど焼かれた焼物を後世、古九谷と呼んでいる。古九谷の廃窯から約100年後の1806(文化3)年、加賀藩の直営で金沢に春日山窯が開かれ、京都の陶工で、文人画家の青木木米を招いて指導を受け、再興九谷の幕が開いた。
春日山窯の木米風、古九谷の再興を目指した吉田屋窯、弁柄と呼ばれる鉄分を含んだ赤い顔料で極細の筆を使用して描く赤絵細描画の宮本屋窯、色絵陶磁器の上に金を定着させる装飾技法の金襴手の永楽窯など、多くの窯が出現する。
再興九谷は加賀本藩で始まるが、古九谷の独創的なデザインに惚れ込み、膨大な私財を投じて、古九谷の復活を目指したのが、大聖寺の城下町の有力商人、豊田伝右衛門で、古九谷の窯の隣に窯を築く。豊田の屋号、吉田屋にちなんで吉田屋窯と呼ばれ、富裕層や知識人から高い評価を得た。しかし、芸術性と品質の追及は吉田屋窯の経営悪化を招き、交通の便がよい山代温泉に窯を移したが、窯を閉じることになる。
山代の吉田屋窯の閉窯後、現場の支配人であった宮本屋宇右衛門が引き継ぎ、宮本屋窯として再開し、赤絵スタイルを確立する。
明治時代になって、石川県能美市佐野に赤絵細描の技術を定着させた斎田道開、道開と共に九谷中興の祖と言われた九谷庄三らが活躍し、大量の九谷焼が海外へ輸出された。
庄三は、古九谷、吉田屋、赤絵、金襴手のすべての手法を取り入れ、和絵具に洋絵具を加え綿密に描き込んだ彩色金襴手を特色とし、これが明治以降の産業九谷の主流になっていく。
九谷焼は、大胆な構図と鮮やかな色彩で絵付けされた色絵磁器として世界で高い評価を得た。上絵付けの特徴は赤、黄、緑、紫、紺青の五彩手(九谷五彩と呼ばれる)を使った色彩効果と優美な絵模様に表れている。
石川県九谷焼美術館は九谷焼を様式別に分類し、青手の間、色絵の間、赤絵の間など、それぞれ異なった雰囲気の空間に九谷焼の名品を展示し、九谷焼の歴史や色を紹介。茶室「五彩庵」には四畳半の茶室と十畳の和室、水屋があり、茶釜、風炉先屏風、水指、二月堂(座卓)、座布団などが揃っていて、茶会、焼き物鑑賞会、歌会などに利用される。
ミュージアムカフェの茶房古九谷ではオリジナルの器や加賀の現代作家の器を使って、日本茶や中国茶を提供。「おすすめのお茶」は季節ごとに変わり、展示ギャラリーで九谷焼や漆器の作家の作品を鑑賞できる。
南惣美術館
石川県輪島市町野町東大野7-100
0768-32-0166
年中無休
9:00~17:00 700円
南惣は、奧能登大野村の天領で庄屋を務めた南家の屋号で、歴代当主が惣右衛門、または宗右衛門と名乗ったことから南惣と呼ばれてきた。南惣家は、鎌倉期以前から現代まで続いており、地主としてアテの木(能登ヒバ)を産出する山林を所有し、財を成した。
南惣の田畑と山林は米、材木、木炭を産み出し、山林から出る間伐材は燃料となり、製塩、製茶、養蚕も手掛けてきた。天然の良港である曽々木、名舟、輪島の港から北前船に積んで、越中越後の米、会津蝋(昆虫から分泌される蝋で、イボタノキ属の枝の上に分泌物を堆積させ、ろうそくや家具などを磨いて艶を出すために用いられる)、小麦などを商ってきた。
南惣の歴代当主は文化を重んじ美術や茶道を愛好し、日本、中国、朝鮮の陶磁器、絵画、書蹟、漆芸、金工などの美術品を蒐集。散逸することなく保存され、1971(昭和46)年に米蔵を改装して「能登集古館 南惣」を開館し、2000年に南惣美術館に改称。母屋、米蔵(南惣美術館)の建造物は2006年、登録有形文化財に指定された。
茶道具では「黒茶碗 銘 閑居 初代長次郎作」「赤茶碗 銘 青柳 本阿弥光悦作」、加賀藩の本多家に伝世した「野々村仁清の瓢口平水指」などを所蔵。古九谷の大皿や酒井田柿右衛門の菊文皿、俵屋宗達の「菊之図風炉先」(風炉先は茶室で使われる二つ折りの屏風のこと)や「百花百熊之図」、円山応挙の「猛虎之図」、千利休や小堀遠州の書などを展示する。
福井県
福井市愛宕坂茶道美術館
福井県福井市足羽1-8-5
0776-33-3933
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
9:00~17:15(入館は16:45まで) 100円
福井市内にある足羽山は標高116メートルの低い山で、桜や福井の市花のアジサイの名所として知られ、足羽山公園遊園地、博物館、美術館、古墳群などがある。足羽山と名付けられたのは明治以降で、江戸時代は愛宕山、木田山と呼ばれた。愛宕大権現社への参道の愛宕坂は、かつて料亭や茶屋、遊興施設が建ち並んだ繁華街であった。
愛宕坂にある愛宕坂茶道美術館は、一乗谷(現・福井市城戸ノ内町)を拠点とした朝倉氏の茶の湯との関わり、福井藩主として幕末まで続いた松平家の茶道、華道や香道など茶道周辺の文化、福井の茶道史を紹介するため、1999(平成11)年に開館した。
同美術館は、福井の実業家で、北陸瓦斯工業(現・宇野酸素)を経営していた宇野煕(ひろし)が建設し、福井市に寄贈したもの。宇野は蒐集した茶道具や茶道資料を展示するため、1996年、越前市の武生に「宇野茶道美術館」を開館したが、2012年に閉館。16~17世紀の中国や日本の陶磁器50点は福井県立美術館(福井市)に寄贈された。
愛宕坂茶道美術館1階の常設展示室では、室町時代後期、越前を支配した朝倉氏に関する資料を紐解き、一乗谷の茶の湯文化の豊かさ、その後の越前と茶道の歩みを紹介し、日本最古の茶筅、茶杓の複製品を展示。
朝倉氏は1573(天正元)年、一乗谷城の戦いで織田信長に滅ぼされるまで、京都の文化や文物を積極的に取り入れた有力大名で、越前の文化水準は高く、下級武士にも茶の湯が広まり根付いていた。国指定の特別史跡「一乗谷朝倉氏遺跡」は福井の茶道文化のルーツと言われる。
愛宕坂茶道美術館2階では、所蔵する美術品や資料をテーマに合わせて公開し、3階ロビーで映像「いまに生きる茶のこころ」を上映。敷地内には茶室「尚庵」があり、茶道体験、お茶会に使われている。
福井県陶芸館
福井県丹生郡越前町小曽原120-61
0778-32-2174
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 祝日の翌日(土曜日、日曜日、祝日を除く) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 300円 福井県陶芸館と越前古窯博物館共通券500円
越前焼は日本六古窯の1つで、鉄分の多い土を用い、表面が赤黒色、赤褐色に焼き上がり、黄緑色の自然釉が流れ落ちる美しさが特徴。土が焼き締められ水漏れしにくいため、水や酒、穀物の保存・貯蔵に使われ、丹生郡越前町の宮崎地区、織田地区で焼かれていた。
室町時代に最盛期を迎えた後、衰退するが、越前焼の産地の地域振興を図り、若い陶芸家の受け皿となるよう、1971(昭和46)年に「越前陶芸村」が誕生。
都市公園100選に選ばれた「越前陶芸公園」を中心に、越前陶芸村には越前焼を見て作って使える「福井県陶芸館」、越前古窯を紹介する「越前古窯博物館」、越前焼を買える「越前焼の館」、さまざまな展示を行う「越前陶芸村文化交流会館」などがある。
福井県陶芸館の資料館では、耐火性が強く水漏れしにくい越前焼の壺、甕、すり鉢を中心とした生活雑器や、宗教的用途にも使用されてきた経筒(経典を土中に埋納する経塚を造営するとき、経典を納めるための筒形の容器)や骨壺、鎌倉時代の穴窯(斜面や地中を掘って、焚口と焼成室がそれぞれ1つのシンプルな窯)の実物大の復元模型などを展示して、越前焼の歴史と魅力を紹介。
陶芸教室では手捻り、絵付けなどの体験ができ、越前焼を使って味わえる「茶苑」には本格的茶室「越知庵」があり、庭園を眺めながら抹茶を楽しめる。福井県陶芸館のホームページの「おうちミュージアム」で、「おうちで楽しむ 福井県陶芸館・越前古窯博物館」の動画を配信している。
越前古窯博物館
福井県丹生郡越前町小曽原107-1-169
0778-32-2174
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 祝日の翌日(土曜日、日曜日、祝日を除く) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 資料館300円 福井県陶芸館と越前古窯博物館の共通券500円
焼き締めや自然釉が特徴の越前焼は日本六古窯の1つで、素朴なぬくもりを持ち、「きっと恋する六古窯」として日本遺産に認定されている。日本六古窯とは越前焼、瀬戸焼、常滑焼、信楽焼、丹波焼、備前焼を指す。
越前焼研究の第一人者である水野九右衛門は越前古窯の研究に取り組み、越前古窯の実態を明らかにした。越前古窯博物館が2017年、越前陶芸村に開館し、研究の過程で蒐集した焼き物や、平安時代から現代に至るまでの貴重な資料(国登録有形文化財「福井県陶磁器資料1642点(水野九右衛門コレクション)」)を公開する。
1835(天保6)年に建てられた水野九右衛門の旧宅を移築し、多目的のコミュニティスペースとして活用。『茶の本』を執筆し、日本の文化を海外に発信した福井県ゆかりの偉人、岡倉天心を顕彰するため、四畳半の本格的な茶室「天心庵」や、約40名が立礼形式の茶会を行える「天心堂」を設置。岡倉天心の父は福井藩の武家で、藩命で武士の身分を捨て、福井藩が横浜に開いた商館「石川屋」で貿易に携わった。
現在、横浜市開港記念会館がある場所で、岡倉天心は生まれている。同会館はジャックの塔と呼ばれ、「横浜三塔」の1つ。他の2棟は、キングの塔(神奈川県庁本庁舎)とクイーンの塔(横浜税関)。
日本六古窯の1つ、越前焼のルーツで、北陸最大の窯業産地であった「福井県越前町」は織田信長の織田一族の発祥の地でもある。越前焼はかつて「織田焼」とも呼ばれていた。越前焼の歴史、特色、生産体制、越前赤瓦の誕生などについて、以下のサイトで紹介している。
「織田文化歴史館 デジタル博物館」の「第6章 越前焼の歴史」と「第7章 近世~現代の越前焼」で越前焼の歴史を詳しく解説。
滋賀県
MIHO MUSEUM(ミホ ミュージアム)
滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300
0748-82-3411
休館日 開館期間中の月曜日(祝日の場合は翌平日) 春季・夏季・秋季
10:00~17:00(入館は16:30まで) 1300円
MIHO MUSEUM(ミホ ミュージアム)の収蔵品は、創立者の小山美秀子が40年以上に渡って集めてきた茶道具、神道・仏教美術、書画、陶磁器、漆工などで、約3000件に上る。蒐集は日本の工芸品に始まり、世界の古代美術へと広がり、日本、東洋、古代オリエントなど美術品から、250~500点を展示する。
大阪で生まれた小山は女学校を卒業後、東京の自由学園で学んだ。キリスト教精神を背景とし、「人としてこの世に生まれた以上は、社会に奉仕すべきである」という教えに深い感銘を受けた。
哲学者、精神的指導者で、生涯の師となる岡田茂吉と出会い、「真の文明世界は、換言すれば“美の世界”すなわち“芸術の世界”である」と説く岡田のもと、信仰の道に進み、神慈秀明会を立ち上げた。岡田は、世界救世教の教祖で、MOA美術館、箱根美術館を開設している。
小山は、娘時代から茶の湯を嗜み、茶の湯は人としての基本の礼法や常識を育む高度な日本文化だと考えていて、茶道具からコレクションは始まった。
「美術を通して、世の中を美しく、平和に、楽しいものに」との想いから、1997(平成9)年、滋賀県の信楽町の郊外に美術館を開館。歴代館長には梅原猛(哲学者、作家、京都市立芸術大学学長)、辻惟雄(東京大学教授、日本美術史家、『奇想の系譜』)などを著す)、熊倉功夫(国立民族学博物館教授、日本文化史家、茶道史家)などが就任。熊倉は茶の湯研究の第一人者である。
茶道具では、曜変天目茶碗(重要文化財、前田家伝来)、大井戸茶碗「小一文字」(益田鈍翁、松永耳庵旧蔵)、本阿弥光悦や尾形乾山の名碗、瀬戸、唐津、伊万里、備前、信楽焼の茶碗、織部、黄瀬戸、志野など美濃焼の向付、茶釜、茶室の掛物として珍重された大徳寺開山の大燈国師(宗峰妙超の墨蹟などを所蔵。
山の中にある美術館の8割が地下にあり、レセプション棟から桜並木を通りトンネルをくぐり、吊り橋を超えると展示館がある。ルーブル美術館のガラスのピラミッドで知られる中国系アメリカ人建築家のイオ・ミン・ペイ(I・M・ペイ)が設計。中国の詩人、陶淵明の『桃花源記』に描かれた理想郷、桃源郷をモチーフにしている。
佐川美術館 樂吉左衞門館
滋賀県守山市水保町北川2891
077-585-7800
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 入館料は展覧会により異なる
佐川急便が創業40周年記念事業として、琵琶湖を望み、美しい自然に囲まれた近江・守山に1998年、佐川美術館を開館。陶芸家の樂吉左衞門、日本画家の平山郁夫、彫刻家の佐藤忠良の作品を中心に収蔵している。
桃山時代に初代長次郎から始まった樂焼は、約450年の伝統を持ち、樂吉左衞門は、樂焼の茶碗を作る茶碗師の樂家が代々襲名している名称。2019年に16代吉左衞門が襲名した。
佐川美術館のコンセプト、建物の設計は15代樂吉左衞門が創案・監修したもので、千利休の「守破離」の思想に基づいている。
守破離とは、利休の教えをまとめた『利休道歌』にある、「規矩作法 守り尽くして 破るとも 離るるとても 本を忘るな」から引用したもの。
規矩とはコンパスとさしがねのことで、寸法や形を意味し、規範、決まりごとを指す。作法は身形、立居振舞のこと。
芸道、芸術の修業で、まずは師匠から教わった型を徹底的に「守る」ところから修業が始まり、師匠の教え、型を身につけた者は自分に合った、より良いと思われる型を模索し既存の型を「破る」ことが求められる。
さらに教わった師匠の型と自分自身で見出した型の双方に精通し極めると、既存の型に囚われることなく、型から「離れ」て自在になれる。このようにして新たな流派が生まれる。だが、根源の精神を見失ってはいけないという教えだ。
佐川美術館の建物の周りに水庭があり、埋設された地下展示室と、水面に浮かぶように建てられた茶室で構成されたユニークな美術館となっており、樂吉左衞門展示室、平山郁夫展示室、佐藤忠良展示室がある。樂吉左衞門展示室は黒樂茶碗、焼貫茶入、焼貫水指など、15代樂吉左衞門の作品を展示。
焼貫とは、樂焼の燃成技法で、黒樂茶碗よりもさらに温度を上げて焼き、高温の備長炭から出るガスの気流が茶碗を取り巻き、窯変が生み出され、同じものがない独自の作品となる。
15代吉左衞門は2019年、代を譲って樂直入と名を改めたが、長次郎が天正年間に作った「今焼茶碗」(樂焼という名称はなく、新しく生まれた茶碗は当初、今焼と呼称された)と呼ばれていた茶碗と向き合い、自らの創造性を追求し、革新的な作品を発表し続けている。
樂吉左衞門館では、樂直入の「焼貫黒樂茶碗 銘 風舟」「黒樂茶碗 銘 夜渡海」「風正一帆懸」「焼貫茶入」などを見ることができる。
膳所焼美術館
滋賀県大津市中庄1-22-28
077-523-1118
休館日 月曜日 火曜日(祝日の場合は開館) 年末年始 2025年1月11日から2月21日までの冬季期間中は土曜日、日曜日、祝日のみの開館となる。10:00~16:00 1000円(抹茶・菓子付き)
膳所焼美術館は、近江国の膳所(現在の滋賀県大津市)に藩庁を置いた膳所藩の御庭焼(大名や重臣が城内や邸内に窯を築き、陶工を招いて自分の趣向に合わせて焼かせた陶磁器)の膳所焼の歴史や作品を伝える美術館で、1987(昭和62)年に開館した。
膳所焼は、遠州七窯の1つとして有名。遠州七窯は、江戸時代初期の茶人、小堀遠州が自分好みの窯を選び、茶道具を作らせた7カ所の窯のこと。
志戸呂焼(遠江。静岡県島田市)、膳所焼(近江)、朝日焼(山城。京都府宇治市)、赤膚焼(大和。奈良県奈良市と大和郡山市)、古曽部焼(摂津。大阪府高槻市)、上野焼(豊前。福岡県田川郡)、高取焼(筑前。福岡市早良区高取)を指す。古曽部焼に代りに、伊賀焼(伊賀。三重県伊賀市)を入れる場合もある。
膳所焼は、小堀遠州の教えを受けた膳所藩主、菅沼定芳が窯を開いたのが始まりで、定芳が転封した後の藩主、石川忠総の時代に、小堀遠州が愛用したことで広く知られるようになり、3代将軍、徳川家光への献茶に膳所焼が用いられ、天下にその名を知らしめた。
しかし18世紀前半に衰退。1919(大正8)年、陶芸家の岩崎健三が全財産を投げ打ち、日本画家の山元春挙や京焼の名工、2代伊東陶山の協力を得ながら復興し、健三の長男、岩崎新定が継承し発展してきた。
膳所焼の歴史、地域の伝統文化がどのように伝えられたかを紹介し、古膳所焼、復興膳所焼、滋賀県内の焼物、茶道具類、掛け軸などを展示。敷地内には庭園と茶室があり、入館者は庭を臨む座敷で膳所焼の茶器によるお抹茶の接待を受けられる。
京都府
茶道総合資料館 茶道資料館
京都府京都市上京区堀川通寺之内上る寺之内竪町682 裏千家センター内075-431-6474
休館日 月曜日 年末年始 当館が定めた日
9:30~16:30(入館は16:00まで) 通常展700円(特別展1000円)
茶道総合資料館は、茶道美術の展示公開と普及活動のための「茶道資料館」と、歴代家元が蒐集した茶の湯関連の資料を蒐集、保存、公開する「今日庵文庫」を設置しており、茶道資料館では、茶道文化の普及を図る「茶道文化検定」を実施している。
茶道資料館は茶碗、掛物、花入などの茶道具や関連の美術工芸品、文献史料などを収蔵し、茶の湯に関する企画展を開催。2階陳列室には、裏千家を代表する茶室の1つ「又隠」の原寸大の写しを設けており、茶室内を見学できる。入館者には椅子に腰かける立礼式の呈茶があり、抹茶と和菓子を楽しめる(10~16時、無料)。
「今日庵文庫」は、茶道に関する図書や映像資料など約6万点を収蔵する茶の湯の専門図書館となっている。
「茶道文化検定 Web版」は、一般財団法人 今日庵 茶道資料館が主催する検定。深い精神性と独自の哲学を持ち、長い年月をかけて受け継がれてきた日本を代表する伝統文化の茶道を美術、工芸、建築、庭園など幅広い分野も含め、トータルに学ぶことができる。
表千家北山会館
京都府京都市北区上賀茂桜井町61
075-724-8000
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:30~16:30(入館は16:00まで) 茶の湯への誘い展1000円(呈茶を含む) 展覧会によって異なる
千利休の流れを汲む三千家は、千利休の後妻の連れ子で、娘婿の千少庵の系統で、表千家、裏千家、武者小路千家の3家のこと。
少庵の子として生まれた千宗旦の三男の江岑宗左は宗旦の隠居に伴い、継嗣(跡取りの意)として茶室、不審菴を継承し、表千家を興した。
宗旦は屋敷の裏に今日庵を建てて隠居所とし、宗旦の死後、今日庵を四男の千仙叟宗室が受け継いで独立し、裏千家となる。
次男の一翁宗守が養子先から戻り官休庵を開き、武者小路千家を興す。千宗守は讃岐高松藩の藩主、松平頼重に茶堂として仕え、武者小路千家は高松藩の茶道指南役に就いてきた。
表千家を象徴する不審菴の号の由来は「不審花開今日春」という禅語に由来し、「不審にして花開く今日の春」と読む。春になって花が咲くのか、よく分からない。自然への畏敬の念を持ち、自然の偉大さ、不思議さに感動し、今という一瞬を大切にせよという意味。
不審菴は千利休が営んだ茶室の名で、表千家の歴代の家元が継承し、千宗左が家元の号。表千家北山会館には、歴代家元の好みの茶道具、季節を感じさせる道具など、家元所蔵の伝来の道具を常設展示している。
三千家に出入りする茶碗師、釜師、塗師、指物師など十の職家を表す千家十職をはじめ、茶の湯の道具師が作り出した伝統工芸や美術品が展示され、秋には特別展が開催される。
2階には立礼席(椅子に座って茶をいただく茶席)と呈茶ロビーが設けられ、呈茶ロビーからは、隣接する京都府立植物園の四季折々の美しい景色を楽しめる。
樂美術館
京都府京都市上京区油小路通一条下る
075-414-0304
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 年末年始
10:00~16:30(入館は16:00まで) 入館料は展覧会により異なる
樂美術館は樂焼の窯元、樂家に隣接して建てられており、樂家14代吉左衞門 覚入によって1978年に開館。所蔵品は約900点に上り、樂焼450年の伝統と革新を伝える。初代の長次郎から15代吉左衞門までの作品を中心に、樂焼陶芸作品や茶道具の工芸品、関係古文書などを展示している。
千利休が求める侘び茶のための茶碗を長次郎が作るようになったのが樂焼の始まりで、轆轤を使わず、手と篦で成形する手捏ねと呼ばれる手法で形を整え、ふいごの付いた窯で、一碗ずつ焼く技法が特徴。
750度から1200度の低火度で焼成した軟質施釉(釉をかけた焼き物)の陶器で、樂茶碗を生み出した樂(田中)家の歴代当主が作製した作品を樂焼と呼んでいる。樂焼から派生した玉水焼(4代楽吉左衛門の一入の庶子、一元が山城国玉水村に窯を開いた)や、金沢の大樋焼も樂焼の一種。
樂家伝来の歴代作品、茶道の工芸美術、樂家文書資料を季節ごとテーマに沿って入れ替えており、茶の湯の文化をさまざまな企画で紹介する企画展や、樂焼を介して茶の湯への造詣を深める特別展などを開催。作品を手に取って鑑賞できる企画も行っている。
野村美術館
京都府京都市左京区南禅寺下河原町61
075-751-0374
休館日 開館中の月曜日(祝日の場合は翌日) 夏季(6月中旬~8月) 冬季(12月中旬~2月下旬)
10:00~16:30(入館は16:00まで) 800円
野村證券、旧大和銀行などの創業者である野村徳七(得庵)は、27歳で家業の両替商を継ぎ、証券業を始め、野村銀行(大和銀行を経て、現在、りそな銀行)を設立。本格的に金融業に乗り出し、海外での農場経営など海外事業も展開し、野村財閥を築き上げた。
野村徳七が明治から昭和にかけて蒐集したコレクションを基に、1984(昭和59)年に開館した野村美術館は茶道具、能面、能装束をはじめ、得庵の遺作も含めて約1900点を所蔵。この中には重要文化財7件や重要美術品9件が含まれる。
重要文化財は「伝紀貫之筆 寸松庵色紙」「佐竹本三十六歌仙 紀友則」「清拙正澄筆 秋来偈頌(仏の功徳をたたえる歌)」「宗峰妙超筆 白雲偈頌」「雪村周継筆 風濤図」「千鳥蒔絵面箱」「藤原定家・民部卿局両筆 讃岐入道集」で、重要美術品には「赤楽茶碗 樂道入作 銘 若山」「文茄茶入」の茶道具が含まれる。
文茄というのは、茶入の形で文琳(果物の林檎の美称)とも茄子とも決めがたい中間の形ということで付けられた名称。
得庵コレクションを中心に、春季(3月上旬~6月上旬) と秋季(9月上旬~12月上旬)の年2回、茶の湯を中心とした展示している。館内には椅子に座って、気楽に抹茶を楽しめる立礼式の茶席があり、茶券を購入して抹茶を楽しめる。
野村美術館がある南禅寺界隈は、多くの政財界人が別荘を営む閑静な地として有名で、哲学の道や紅葉で有名な永観堂にも近い。北隣には得庵の別邸の野村碧雲荘がある。
相国寺承天閣美術館
京都府京都市上京区今出川通烏丸東入ル相国寺門前町701
075-241-0423
休館日 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 800円
10年の歳月を費やし、足利義満によって創建された臨済宗相国寺(しょうこくじ)は京都五山の1つで、多数の文化財が伝わる。山号を万年山(まんねんざん)、寺号は相国承天と定められた。
相国寺は五山文学の中心であり、大巧如拙、天章周文、雪舟等楊といった日本の水墨画の基礎を築いた画僧を数多く輩出。
相国寺承天閣美術館は、相国寺創建600年記念事業として1984(昭和59)年に開館。相国寺、鹿苑寺(金閣寺)、慈照寺(銀閣寺)、その他の塔頭寺院に伝わる美術品、寺宝を収蔵し、国宝5点、重要文化財は145点に及ぶ。
伊藤若冲が描いた水墨画の傑作で重要文化財の「鹿苑寺大書院旧障壁画」の「月夜芭蕉図」や「葡萄小禽図」を常設展示。鹿苑寺境内に建つ「夕佳亭」は大名茶人の金森重近(宗和)が造ったと伝えられる茶室を復元したもの。
茶道具では、「玳玻散花文天目茶碗」(国宝)や「黄瀬戸珠光天目茶碗」を収蔵。玳玻とは、玳瑁(ウミガメ)の甲羅のことで、釉薬をかけて焼いた表面が、鼈甲のような模様に見える焼物のことで、散花文は花が散ったような文様をいう。玳玻散花文天目茶碗は通称、梅花天目と呼ばれている。他にも「唐津鉄班文水指」「七官青磁牡丹文大香炉」「緑釉四足壺」などの茶道具を有する。
大西清右衛門美術館
京都府京都市中京区三条通新町西入る釜座町18-1
075-221-2881
休館日 日曜日 臨時休館あり 夏季 冬季
11:00~16:00(入館は15:30まで) 1600円
約400年にわたり、京都・三条釜座の地で茶の湯釜を作り続けている釜師、大西家は、中世の三条釜座の歴史を唯一、現在まで継承し、茶の湯釜の伝統と様式を伝えている。千家十職の1つ。
千家十職とは、茶道に関わりの深い三千家(表千家、裏千家、武者小路千家を指す)に出入りする職人の家系のこと。初代の大西浄林は古田織部や織田有楽斎など、武家茶人の釜を手がけ、当代は16代で、技術と伝統が受け継がれている。
三条釜座は、平安時代からの由緒ある鋳物町で、かつては多くの釜師が軒を連ねたが、現在は大西家と吉羽與兵衛などが京釜を制作。
代々の大西清右衛門が精進を重ね、工夫を凝らした茶の湯釜の伝統と様式を、広く公開するために1998(平成10)年に大西清右衛門美術館が開設された。
大西家の茶の湯釜の源流である芦屋釜、天明釜、桃山時代、江戸期に釜座で活躍した釜師の西村道仁、辻与次郎、名越浄味などの作品、大西家歴代が用いた釜の下絵や木型などの制作用具や釜座ゆかりの古文書、茶道具など約800点を所蔵し、企画展のテーマによって展示替えを行う。
大西家に伝わる茶の湯釜と茶道具類は、春季(3月中旬~6月中旬)と秋季(9月上旬~12月上旬)の企画展で公開し、釜の名品を直接手に触れることができる京釜鑑賞会や、収蔵品を用いた茶会、講演会などを会期中に開催。館内には茶室があり、お茶会に利用できる。美術館に隣接する工房では、今も茶の湯釜が製造されている。
釜の主たる生産地は京釜(京都市」の他に、芦屋釜(福岡県遠賀郡芦屋町)、天明釜(天命、天描とも)(栃木県佐野市)があり、「西の芦屋、東の天明」と称された。江戸時代になって関東で生産されたものを「関東作釜」と呼び、江戸名越家、江戸大西家、山城家、堀家などがある。
茶会を催すことを「釜を懸ける」といい、茶会が催されているときは「在釜」という言葉が掲げられるなど、茶道の世界で釜は大きな役割を果たしてきた。釜のお湯が沸く音を松に例えて、松風、松籟(籟は、風が物に当たって発する音、響き)、松声の音という。
細見美術館
京都府京都市左京区岡崎最勝寺町6-3
075-752-5555
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 展覧会によって異なる
細見美術館は京都の文化施設が集まる岡崎公園の一角にあり、毛織物業で財を成した実業家で、日本美術コレクターの細見良(古香庵)に始まる細見家3代の蒐集品を基に、1998(平成10)年に開館。
優れた鑑識眼と独自の美意識によって選び抜かれた1000点に上るコレクションは重要文化財30点強を含み、平安、鎌倉時代の仏教・神道美術、室町時代の水墨画、茶の湯の美術、桃山の茶陶や七宝工芸、琳派や伊藤若冲といった江戸絵画など、日本美術の多くの分野と時代を網羅するもので、多彩な企画展を開催している。
京の町屋の構造をイメージして造られた建物(設計は建築家の大江匡。建築業協会賞を受賞)で、3階から地下2階まで吹き抜けになっており、開放的。最上階にある茶室「古香庵」は、数寄屋建築の名匠、中村外二によるもので、季節ごとに開かれる公募の茶会「古香庵茶会」や各展覧会に関連して開かれる講座、ワークショップなどに活用されている。
細見古香庵は、兵庫県の北西端に位置する新温泉町の出身で、西は鳥取県に隣接。13歳のとき、単身大阪に出て毛織物の仕事に就き、その後、24歳で独立して「泉州毛織物」を設立。30歳を過ぎた頃から先人のすばらしさを発見し、古美術に興味を持つようになった。
茶釜(芦屋釜)の研究では日本の第一人者と評され、『茶の湯釜入門』『現代の茶席道具』『 茶の湯釜―入門と研究』などの著書を著わしている。古香庵は晩年、独学で水墨画を描くようになった。故郷の新温泉町にある玉田寺(室町時代の開創)に鎌倉時代の石塔を寄進し、玉田寺の襖絵を古香庵自身が描いている。
★泉屋博古館 休館中
京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町24
075-771-6411
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 祝日 開館期間は3月中旬~7月中旬、9月~12月中旬
10:00~17:00(入館は16:30まで)
泉屋博古館は住友家が蒐集した東洋美術、工芸品を中心に収蔵、展示している美術館で、京都市の東側、丸太町通と鹿ヶ谷通が交差する角にある。15代当主の住友友純(号は春翠)の鹿ヶ谷の別荘に造られ、東山の穏やかな山容を望む風光明媚な環境にある。
住友家の美術品で最も有名なものは、15代当主の友純が明治中頃から大正期にかけて蒐集した中国古銅器と鏡鑑。中国以外では質量ともに最も充実したコレクションとして世界的に高く評価されている。
3000年以上前の中国の殷(商)の時代、鋳造技術が高度に発達し、繊細で複雑な造形の青銅器が数多く生み出された。青銅器館では、テーマに沿って4つの展示室でさまざまな角度から、青銅器の魅力を紹介。
1960(昭和35)年に開館した泉屋博古館は、その後も住友家から数々の美術品の寄贈を受け、収蔵品は国宝2件、重要文化財13件(19点)、重要美術品60件をはじめ、現在3500点以上。中国青銅器・鏡鑑の他に、茶道具、能面・能装束、中国と日本の書画、洋画、近代陶磁器、文房具など多様である。
茶道具が充実しており、5代当主、住友友昌は裏千家8代家元、又玄斎一燈好みの道具を集め、12代友親は小堀遠州遺愛の茶碗「小井戸茶碗 銘 六地蔵」などを蒐集。
15代友純(春翠)は後陽成天皇命銘の茶入「唐物文琳茶入 銘 若草」や後水尾天皇ゆかりの「青磁福寿文香炉」などを入手し、茶の湯釜、茶杓、竹花入などの名品も多い。
春翠は、茶の湯や能楽といった日本の古典芸能を嗜み、日本家屋で日本画を鑑賞する伝統的な数寄者の生活を楽しみ、数々の茶会を催していた。
泉屋博古館は京都と東京の2カ所で収蔵する作品の展覧会を開催しているが、京都の泉屋博古館は2024(令和6)年1月から改修工事ニ入り、2025年4月26日にリニューアルオープンする。
北村美術館
京都府京都市上京区河原町今出川下ル一筋目東入梶井町448
075-256-0637
休館日 開館期間中の月曜日(祝日の場合は翌日) 夏期 冬期
10:00~16:00 600円
実業家で茶人であった北村謹次郎の蒐集品を保存するために1975(昭和50)年に財団法人北村文華財団が設立され、1977年に開館。美術蒐集品をテーマによって選び、春季と秋季に公開している。
創設者の謹次郎は奈良の吉野山の麓、吉野川沿いの大和上市で、日本の山林王と言われた北村又左衞門家の次男として生まれ、家業の林業を営むかたわら、夫婦で茶道と美術品の蒐集に励んだ。
美術品の蒐集は絵画、書蹟、彫刻、木工、陶磁、金工、漆工、染織、人形など多岐に渡り、その中には重要文化財34点、重要美術品9点をはじめ、大名物、名物、蔵帳(所蔵している茶道具類の控え帳、目録)などが含まれ、点数は1000点近くになる。
傑出した茶人であった北村は茶道具の持つ優美さを好んだ。大名茶人であった小堀遠州、金森宗和、松平不昧に見られる「綺麗さび」(江戸初期の武家で、遠州流茶道の開祖の小堀遠州が目指す美的概念で、綺麗で華やかな中にある寂びの風情をいう)や、堂上の茶と呼ばれる公家、宮廷社会の茶の湯の世界への憧れが収蔵品から感じられ、そうした北村の眼で茶碗、古筆を選んでいる。
隣接する「四君子苑」と呼ばれる茶苑・数寄屋造りの建物(旧北村邸)は昭和時代の数寄屋建築の傑作で、春と秋の一定期間、内部を公開。美術館の2階に設けられたエントランスホールから硝子越しに「四君子苑」を見下ろし、茶苑の前庭などの景観を楽しめる。
古田織部美術館
京都府京都市北区上賀茂桜井町107-2
075-707-1800
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:40まで) 500円 樂焼玉水美術館との共通券 700円
戦国時代から江戸初期にかけて活躍した武将、古田織部重然は、千利休亡き後、豊臣、徳川政権で「天下一の茶人」と称され、激動の時代の茶の湯をリードした。形や文様の斬新さで知られる陶器「織部焼」も、織部の指導により誕生。
古田織部の「茶の湯」の世界を紹介する美術館として、織部の没後400年を記念して2014(平成26)年にオープン。常設展を設けず、年間2回のテーマに沿った展示替えにより、織部自作の茶杓、書状の他、織部好みの茶道具などを公開しており、織部独特の世界を堪能できる。
豊臣秀吉・秀頼、徳川家康・秀忠父子に仕えた織部は、利休の茶の湯を継承し、茶道具の製作、茶室の建築、作庭など多岐に渡って才能を発揮し、「織部好み」と言われるほど、そのスタイルは後の世まで影響力があった。
利休七哲は、千利休の高弟とされる7人の武将のこと。利休の孫の千宗旦は「利休七人衆」として、前田利長、蒲生氏郷、細川忠興(三斎)、古田織部、牧村兵部、高山南坊(右近)、芝山監物の7人を挙げている。後に織田有楽、金森長近、瀬田正忠(掃部)が7人に入れられることもある。
千利休が豊臣秀吉の怒りを買い、堺で蟄居を命じられたとき、古田織部と細川忠興は淀の船着き場まで千利休の見送りに出向き、千利休に切腹を命じられたときも、織部は秀吉に助命嘆願を行っている。
利休が亡くなった後、織部は茶人として秀吉に認められ、大きな領地を持たない織部は武家の儀礼としての茶道を大成し、「織部流」を確立し、利休の後継者となった。「へうげもの」(ひょうきん者、おどけた者)と呼ばれ、歪んだ茶碗、非対称なものに美を見出し、他の者と違う、奇抜な美的センスを「織部好み」と称した。
大坂夏の陣の1615(慶長20)年、織部は豊臣方に内通していたと疑いをかけられ、大坂落城後に息子たちと共に切腹を命じられた。「かくなる上は、申し開きも見苦し」と、一言の弁明もせずに自害。息子4人も自害、処刑され、古田家は断絶となった。
織部の没後、弟子の小堀遠州が、織部の武家の茶の湯を受け継ぎ、弟子であった本阿弥光悦は、織部の美意識に触発されて、独自の芸術を開花させた。伊達政宗は、織部の弟子の清水道閑を招き領内に茶道を広め、金森宗和(重近)は織部流の茶を学んで自らの境地を開き、宗和の茶風は公家の間でもてはやされた。
古田織部の研究家、映画プロデューサー、出版業、茶人で、古田織部美術館館長の宮下玄覇は、幼い頃から古美術ファンで、22歳のとき「黒織部茶碗」に出会って織部に魅了されて、茶器や釜などの茶道具、自筆の書状、資料を蒐集し、コレクションの数は1000点に上る。
樂焼玉水美術館
京都府京都市上京区堀川通寺之内上ル東側(京都市上京区寺之内堅町688-2)みやした内 2階
075-366-6881
休館日 日曜日 祝日 年末年始 GW お盆休み
9:30~17:30(入館は17:00まで) 300円 古田織部美術館との共通券 700円
樂焼玉水美術館は、長次郎焼や吉左衛門焼の脇窯、弥兵衛焼・玉水焼の歴代作品400点を収蔵する美術館で、古田織部美術館の分館として、2021(令和3)年にオープンした。
弥兵衛焼・玉水焼は、樂吉左衞門家4代の樂一入の庶子である樂一元(弥兵衛)から始まる。一元は京都で樂焼を大量に製作し、その作品は当時の表千家の覚々斎や、裏千家の六閑斎に評価され、後に、裏千家の最々斎(竺叟)や裏千家の一燈(又玄斎)、武者小路千家の直斎に愛好された。
弥兵衛焼は、一元の2人の息子に受け継がれ、さらにその弟子が、山城国南部の玉水で継承し、「玉水焼」と呼ばれるようになった。楽一元の父の樂一入は、呉服商の雁金屋の尾形家から光琳や乾山の従弟に当たる幼児を養子に迎えて家を継がせることにし、これが樂家5代目の宗入となる。
一元は、成人してから樂家と同じ京都で開窯し、力強い作品を数多く生み出した。樂家の祖である長次郎、楽焼の最高峰とされる本阿弥光悦などの作風を研究し、千三家の歴代宗匠も一元の技量を認めてきた。樂焼玉水美術館は、楽一元の「黒樂茶碗 銘 翁」「赤樂茶碗」「利休形 朱釉 黒樂茶碗」「黒樂茶碗 銘 卯花」「赤樂 金入牡丹図鉢」「金地 黒樂向獅子香炉」「黒樂 釣舟花入」などを所蔵。
八幡市立松花堂庭園・松花堂美術館
京都府八幡市八幡女郎花43-1
075-981-0010
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
9:00~17:00(入園・入館は16:30まで) 庭園300円 美術館は展覧会によって異なる。展覧会を開催していない時期は常設のパネル、映像コーナーだけ見学できる 100円
https://shokado-garden-art-museum.jp/
江戸時代初期の真言宗の僧侶、松花堂昭乗(通称は滝本坊)は石清水八幡宮で出家したが、書道、茶道、絵画に秀でた文化人でもあった。堺の出身で、書では松花堂流(滝本流とも)という書風を編み出し、近衛信尹、本阿弥光悦とともに「寛永の三筆」と呼ばれる。
茶道は小堀政一(遠州)に学び、遠州は昭乗のために瀧本坊に茶室「閑雲軒」を造っている。昭乗の催した茶会には小堀遠州、武将で儒学、書道、茶道、庭園設計にも精通していた石川丈山(煎茶の祖とも言われる)、公家など、当時の著名な文化人らが集まった。絵画は人物画、山水画を得意とし、当代随一とも称せられた。
松花堂は、松花堂昭乗が1637(寛永14)年、隠棲用に建てた草庵の茶室。もとは八幡宮近くにあったが、明治の神仏分離令で書院、庭園とともに現在の地に移された。6600坪(約2万2000㎡)の広大な庭は国の史跡、名勝に指定されており、3棟の本格的な茶室を持つ。
松花堂美術館では昭乗の紹介、ゆかりの人々のパネル展示(常設展)の他、八幡市にゆかりのある美術品や資料を収蔵。春と秋に企画展や特別展を開催し、年に3回ほど館蔵品を中心とした展示を行う。敷地内にある京都吉兆 松花堂店で当地の発祥とされる「松花堂弁当」を味わえる(要予約)。
大山崎町歴史資料館
京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字竜光3 大山崎ふるさとセンター2階
075-952-6288
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 200円 企画展・特別展は別途料金
大山崎は桂川、宇治川、木津川が合流し、淀川になる「三川合流の地」で、自然の関門ともいうべき地形から、古代以来、日本の東と西を結ぶ交通の要衝として発展してきた。
大山崎町歴史資料館は、大山崎が歩んできた歴史的特色を踏まえ、町の歩み、賑わい、文化を紹介。エントランスルームでは年表、文化財地図、パネルなどで町の歴史を概観。竹林のプロムナードを抜けると、大山崎の名水にちなむ井戸ビジョンがあり、映像で各時代の特色ある文化・歴史が分かる。
展示室は古代コーナー、中世コーナー、山崎合戦、待庵・利休のコーナー、近世コーナーという5つのコーナーで構成され、瓦窯跡から出土された複弁蓮華文軒丸瓦、豊臣秀吉所用の「馬藺後立一ノ谷形兜(複製)」、「大山崎惣中」という住民組織などを解説・展示し、千利休ゆかりの国宝の茶室「待庵」の創建当時の原寸大模型が復元されている。
大山崎町歴史資料館の近くに妙喜庵があり、山崎の合戦のとき、山崎に陣を敷いた秀吉は、陣中に千利休を招いて、二畳の茶室、待庵を造らせた。その後、茶室は解体され、江戸初期の慶長年間(1596年~1615年)に妙喜庵に移築され、現存する茶室としては最古の遺構となっている。
国宝の茶室は3棟あり、国宝茶席三名席と呼ばれている。待庵の他に、大徳寺龍光院の密庵(小堀遠州の作と伝えられる。京都市北区紫野)と、犬山城の東にある日本庭園、有楽苑の如庵(織田信長の弟、織田有楽斎によって、京都・建仁寺の正伝院に建造された茶室が移築された。愛知県犬山市)。
国宝の茶室「待庵」の拝観は日曜日の午前中だけで、寺用のある場合は日曜日でも見ることができないが、大山崎町歴史資料館では、原寸大復元模型を身近で鑑賞できる。
奈良県
大和文華館
奈良県奈良市学園南1-11-6
0742-45-0544
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 630円 特別展1100円
大和文華館は奈良市学園前の閑静な住宅街にある美術館で、近畿日本鉄道(近鉄)の創立50周年記念事業として、1960(昭和35)年に緑豊かな高台に建てられた。美術研究所を併設し、建築家の辰野金吾によって設計された奈良ホテル・ラウンジの一部(1909年の建築)も移築され、文華ホールと名付けた。
日本、中国、朝鮮を中心とした絵画、書蹟、彫刻、陶磁、漆工、金工、染織、ガラスなどの収蔵品は、国宝4件、重要文化財31件を含む2000件余り。故・中村直勝博士蒐集古文書(雙柏文庫)664件、近藤家旧蔵富岡鉄斎書画143件、鈴鹿文庫(和書)6162冊も所蔵。
開館50周年の2010年にリニューアルし、より快適な鑑賞空間となり、展覧会会期中の土曜日には、学芸員によるギャラリートークが行われる。
茶道具では「黒楽茶碗」「赤織部瓜文角皿」「一閑蒔絵枝垂桜文棗」「色絵おしどり香合 野々村仁清作」「古田織部書状」「墨蹟法語 虎関師錬筆」(重要文化財)などがある。
寧楽美術館
奈良県奈良市水門町74
0742-25-0781
休館日 火曜日(祝日の場合は翌平日) 美術館の企画展は不定期 庭園の整備期間は休園(12月末~1月中旬、9月下旬)
9:30~16:30(入館は16:00まで) 1200円
寧楽美術館は、海運業で財を成した中村準策、準一、準佑の中村家3代が蒐集した1万点以上の美術品のうち、1945(昭和20)年の神戸大空襲を運よく免れた二千数百点を収蔵。
準策は1939(昭和14)年に、東大寺と興福寺の間に位置する庭園、依水園を関家から買取り、1958年、3代準佑のときに美術品を公開。奈良市の中心地ながら静かな時間が流れる名勝「依水園」は、江戸時代に作られた前園と、東大寺南大門、若草山、春日奥山などを借景に明治に作られた後園の2つからなる池泉回遊式庭園。
古代中国の青銅器、古鏡、古銅印、拓本類と、中国、高麗・朝鮮李朝、日本の陶磁器、田能村竹田の画帖「亦復一楽帖」などを所蔵しており、毎年7月中旬から8月初旬に展示品の入れ替えを行う。
毛利家伝来の「黄金茶碗」や、赤膚焼(奈良市、大和郡山市)の名工、奥田木白の「蝉飾付唐茄子型花器」(江戸末期)など、茶道具も多く所蔵。庭園には、新薬師寺に使われていた天平古材を天井板などに用いて明治期に造られた書院造りの茶室「氷心亭」や、裏千家の重要文化財指定の茶室「又隠」の写しの茶室「清秀庵」がある。
奈良の豪商の別邸として江戸時代前期の建物を移築した「三秀亭」は食事処となっており、庭園を見ながら昼食や抹茶、煎茶などを楽しめる。
大阪府
大阪市立東洋陶磁美術館
大阪府大阪市北区中之島1-1-26
06-6223-0055
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 1800円
大阪の都心部、堂島川と土佐堀川に挟まれた中之島公園にある大阪市立東洋陶磁美術館は、世界的に有名な「安宅コレクション」を住友グループから寄贈されたことを記念し、1982(昭和57)年に開館。2年間の増築改修工事を終えて2024(令和6)年4月にリニューアルオープンした。
安宅コレクションは、大阪に本社があった総合商社、安宅産業の創業者一族で、会長も務めた安宅英ーの指示で蒐集したもので、英ーは芸術家のパトロン、美術品コレクターとして知られていた。
2件の国宝と13件の重要文化財を含む東洋陶磁美術館の所蔵品は、中国、朝鮮陶磁が多い「安宅コレクション」を核にして、経済学者で実業家の在日韓国人、李秉昌(イ・ビョンチャン)の韓国陶磁コレクションや、美術品コレクターの堀尾幹雄の濱田庄司コレクションの寄贈が加わり、美術館による日本陶磁の蒐集もあって、東洋陶磁のコレクションとして世界第一級の質と量を誇っている。
ペルシア陶器や、清時代の中国で流行した嗅ぎたばこを入れる小型容器の鼻煙壺など、関連するコレクションも充実し、所蔵品は6000点弱。年1~2回の企画展、特別展で魅力的な展示を目指す。
茶道具では、8つの国宝の茶碗の1つ、「油滴天目茶碗」や、重要文化財の「木葉天目茶碗」などを所蔵。
中之島 香雪美術館
大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 4階
06-6210-3766
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 展覧会によって異なる
香雪美術館の香雪は、所蔵品の多くを蒐集した村山龍平の号で、龍平は28歳で朝日新聞を創刊し、日本を代表する新聞に育てた。美術に強い関心を寄せ、岡倉天心らが主宰する美術雑誌「國華」の経営も引き受け、価値ある美術品の海外流出を食い止めたいと、美術品の蒐集に力を注いだ。
龍平が亡くなった後、美術館設立の声が上がり、1972(昭和47)年に財団法人香雪美術館を設立し、翌1973年、神戸市東灘区の御影に香雪美術館を開館。開館45周年を記念して、2館目の美術館として「中之島 香雪美術館」を2018年にオープン。
所蔵品には重要文化財19点、重要美術品33点が含まれ、仏教美術、書蹟、近世絵画、茶道具、刀剣・武具など幅広いジャンルに渡る。香雪美術館(御影)は施設の改築工事のため現在、長期休館中で、展覧会活動は中之島香雪美術館(大阪市北区)で行っている。
「中之島 香雪美術館」の常設展示施設として、国指定重要文化財「旧村山家住宅」に建つ茶室「玄庵」を原寸大で再現。茶室だけでなく、露地(茶室に備え付けられた庭と茶室までの通路のことで、露地口を入るときから茶の湯は始まる)を含めた全体を再現。
村山龍平は、大阪の財界人との交流を通じて茶の湯を楽しむようになり、藪内流の藪内節庵に茶を学んだ。節庵は、野村證券や大和銀行(現・りそな銀行)の野村財閥を築いた野村徳七など、財界人を多数門下に抱えていた。藪内流は、足利義政の同胞衆の藪宗把を遠祖としており、初代、藪内剣仲は武野紹鴎の門下で、古田織部の妹と結婚した人物。
村山龍平邸の奥に建てられた茶室「玄庵」は、藪内流家元の茶室である重要文化財「燕庵」の写し。写して建てるのは、相伝を得た人だけが許され、龍平の茶の湯への取組み姿勢が伺える。中之島 香雪美術館には「村山龍平記念室」を開設し、龍平の生涯を貴重な展示品や大型年表、解説パネルなどで紹介しており、朝日新聞社の発祥の地、中之島の歴史も分かる。
茶道具の所蔵品には、重要美術品の「黒楽茶碗 銘 古狐 長次郎作」「利休丸壺茶入」、重要文化財の「志野松籬絵(まつまがきえ》水指」の他、「名物手井戸茶碗 燕庵井戸」「茶杓 銘 |茶瓢 村田珠光作」などがある。
湯木美術館
大阪府大阪市中央区平野町3-3-9
06-6203-0188
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 会期中
10:00~16:30(入館は16:00まで) 700円
日本料理店「吉兆」の創業者、湯木貞一が蒐集した茶懐石の器、茶碗や茶入などの茶道具、書蹟、美術品などを展示する美術館。重要文化財13点、重要美術品3点を収蔵し、吉兆平野店の跡地に建てられたビルに1987(昭和62)年に開館。
湯木は料理と茶の湯を人生の両輪とし、料理と共に茶の湯の研鑚も重ねて、茶事・茶会を催すかたわら、50年余り、茶の湯の道具の蒐集に心を傾けた。「石山切(伊勢集)」「高野切」「大燈国師墨蹟」「春日宮曼茶羅図」「唐物茄子茶入 紹鴎・一名みをつくし」「志野茶碗 銘 広沢」「織部四方手鉢」などの重要文化財の他、奈良時代から江戸時代の美術品を年3~4回の企画展を公開している。
南蛮文化館
大阪府大阪市北区中津6-2-18
06-6451-9998
休館日 期間中の月曜日 開館は5月と11月
10:00~16:00 800円
南蛮文化館は1968(昭和43)年、大阪市の中津にオープンした南蛮美術中心の私立美術館。大学時代に学んだ東西の交流に興味を持った館長の北村芳郎が40歳代から蒐集してきた南蛮美術品を展示している。北村家は中津一帯に広大な土地を持っていた地主。
安土桃山時代から江戸初期まで、南欧ラテン系(主にポルトガル、スペイン)の人々との交流により、ヨーロッパの影響を受けた数々の文物が日本に流入。南蛮文化館は美術品や工芸品をはじめ、陶器、漆器、古文書などを所蔵し、館内の1階にキリスト教関連、2階に南蛮美術品を展示し、年2回、公開している。
所蔵品には茶道具関連の「十字紋赤織部茶碗」「ルソン茶壷」の他、狩野光信筆の南蛮屏風(重要文化財)、朝顔の釣鐘、マグダラのマリア画像、十字紋螺鈿小櫃、イエズス会紋章入り聖餅箱、うんすんカルタ、高山右近の書状などがある。
ルソン壺は桃山時代にフィリピンのルソン島から壺が輸入されたため、ルソン壺と呼ばれるが、中国広東省を中心に中国南部で作られた壺で、すでに14世紀頃から葉茶の容器、茶壺として使われていた。室町時代後期に茶の湯が盛んになると茶室で観賞されるようになり、安土桃山時代には書院、茶室の飾り道具にも用いられた。
南蛮とは中国から日本に入ってきた言葉で、元来「南方の野蛮人」を意味し、日本で南蛮人と言えば、南方から日本に来た外国人という意味で使われていた。16世紀以前の日本では、世界は「日本と中国とインド(またはシャム、現在のタイ)」の3国で構成されると考えられていた。そのため南蛮は、インドを除いた南方の地域を指していたと思われる。
近世初期の安土桃山時代にポルトガルの商人やキリシタンの宣教師が来日し交流を深め、南蛮はポルトガル、スペインとその植民地であった東南アジアの国々のことを指し、やがてオランダの海洋進出とともに広がっていく。
南蛮文化は、1543年にポルトガル人が種子島に漂着し、鉄砲などの武器や商品、文化をもたらし、1639年にオランダ人を除くヨーロッパ人の日本への渡航が禁止されるまでの100年弱に、宣教師や商人らがもたらした文化と、その影響を受けた文化を「南蛮文化」と称している。
外来語として現在も使われている言葉にはズボン、ボタン、ボーロ、カステラ、オルガンなどがある。「南蛮漬け」「鴨南蛮」など南蛮が付いた料理は、ポルトガル人が持ち込んだ唐辛子やネギを用いたことから命名されたと言われる。
南蛮美術のコレクターとして有名な池永孟(いけなが はじめ)の南蛮美術コレクションが神戸市に寄贈され、神戸市立博物館は国の重要文化財の「聖フランシスコ・ザビエル像」や狩野内膳筆の「南蛮屏風」を所蔵。同館は江戸時代中期の「藍色ガラス茶壺」をはじめ、ガラスの碗、鉢、菓子器、皿、箸などの「びいどろ史料庫コレクション」も有している。
神戸市立博物館
兵庫県神戸市中央区京町24
藤田美術館
大阪府大阪市都島区網島町10-32
06-6351-0582
休館日 年末年始
10:00~18:00 1000円
明治期に活躍した実業家の藤田傳三郎は、維新以降、多くの文化財が海外に流出したり、国内で粗雑に扱われることに危機感を感じ、「大いに美術品を蒐集し、国の宝の散逸を防ごう」と決意し蒐集に乗り出した。
傳三郎の長男の平太郎、次男の徳次郎もコレクションを続け、1954(昭和29)年に大阪・網島の藤田邸の蔵を改築して藤田美術館を開館。2022(令和4)年にリニューアルオープンし、ガラス張りの開放的な外観に、内部は旧建物の部材を移築したモダンなデザインになった。
傳三郎は、秋田県の小坂鉱山など鉱山業を中核とし、岡山県の児島湾の干拓事業を手掛け、紡績、鉄道、電気、新聞など、近代化する日本の基盤事業に関わり、大阪商法会議所(今の大阪商工会議所)の2代目会頭を務めるなど、大阪財界に大きな功績を残した。
若い頃から古美術への関心が高かった傳三郎は、古代から明治に至る絵画、書蹟、陶磁器、彫刻、漆工、金工、染織、考古資料など、多岐に渡る文化財を蒐集。藤田美術館は国宝9件、重要文化財53件を含む、約2000件のコレクションを保有。
国宝では「紫式部日記絵詞」「深窓秘抄」「玄奘三蔵絵 巻第一、二、三、四」「柴門新月図」などを所蔵し、茶道具の国宝は「曜変天目茶碗」が挙げられる。茶道具では「菊花天目茶碗」「白縁油滴天目鉢」「黒樂茶碗 銘 まこも 長次郎作」「古瀬戸肩衝茶入 銘 在中庵」「利休黒町棗 銘 再来」「色絵鴛鴦香合 野々村仁清作」「古伊賀花生 銘 寿老人」など、名品が多い。
★萬野美術館 閉館
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3 第三松豊ビルディング13F
土木建築業の萬野組を父から引き継ぎ、1931(昭和6)年に煙突建設請負業を始めた萬野裕昭は戦後、不動産業を志し、船舶、運輸、外食、レジャーなど多くの事業を手がけた。
青年時代に骨董に興味を持ち、茶碗、香炉、徳利など古美術を蒐集。一時、蒐集を止めていたが、戦後、財閥や富豪が所持していた伝世品が流出し始めると、中国陶磁と茶道具を中心に蒐集を再開。琳派や肉筆浮世絵などの絵画、書蹟、金工、刀剣・甲冑から染織へと範囲を拡大し、信仰の対象となるもの以外はすべてコレクションの対象とし、東洋古美術をジャンルごとに系統的に集めた。
国宝、重要文化財を含み、1000点を超える屈指の蒐集家になっても表に出ず、「謎のコレクター」「戦後最大の美術品コレクター」と言われていたが、1988(昭和63)年、大阪の心斎橋に萬野美術館を開館。
国宝の「玳玻散花文天目茶碗」もその中にあった。玳玻は、玳瑁(ウミガメ)の甲羅のことで、釉薬をかけて焼いた表面が、鼈甲のような模様に見える焼物で、散花文は花が散ったような文様をいう。天目茶碗は、茶葉の産地だった中国の天目山一帯の寺院で用いられた茶道具で、天目釉と呼ばれる鉄釉をかけて焼かれた陶器のこと。
萬野裕昭が1998年に亡くなり、萬野美術館は2004年に閉館。その後、玳玻散花文天目茶碗を含む約200点の美術品が京都の相国寺境内にある相国寺承天閣美術館に寄贈された。
約200点の美術品には、円山応挙筆「牡丹孔雀図」(重要文化財)、円山応挙筆の「大瀑布図」、「赤楽茶碗加賀 本阿弥光悦」(重文)、俵屋宗達筆「蔦の細道図屏風」(重文)などが含まれている。
写真家の篠山紀信が撮影して著わし、萬野美術館が監修した大型本『萬野美術』が1999年に出版され、美術品の姿を残した。
逸翁美術館
大阪府池田市栄本町12-27
072-751-3865
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)(開催中)
10:00~17:00(入館は16:30まで) 700円 呈茶受付は10:50~15:00、一服500円
阪急東宝グループの創業者、小林一三(号は逸翁)が生涯に渡って集めた美術工芸品約5500件を収蔵し、公開する美術館で、小林の没後、小林邸の「雅俗山荘」を展示館として1957(昭和32)年に開館した。
美術館として設計された建物の現在地に2009(平成21)年、移転。それまで使用した小林邸は、小林の生涯を振り返る「小林一三記念館」として2010年にリニューアルオープンした。
小林のコレクションは古筆、古経、絵巻、中近世の絵画、国内外の陶磁器、日本と中国の漆芸品など多岐に渡る。重要文化財15件、重要美術品20件を含み、絵画では与謝蕪村、呉春(四条派の始祖)、円山応挙(円山派)、四条・円山派の絵師の作品が多い。年4回、企画展を開催。
茶人としても有名で、逸翁が自ら考案した茶室「即庵」を、逸翁美術館の館内に「即心庵」として再現し、展覧会開催中の土曜日、日曜日、祝日には呈茶を行っている(一服500円)。
小林一三は私鉄沿線の宅地造成、郊外のレジャー施設の建設、宝塚歌劇団や映画、演劇の東宝などの大衆文化の創造、駅に直結するターミナルデパートの開発などを一早く手掛け、新たなビジネスモデルを創造した。
一三は、高価な茶道具を買い集めるのではなく、日常生活の中の茶の湯を人々に広めようと考えた。出家者に限らず、在家の人を含めた一切の衆生の救済を掲げる「大乗仏教」になぞらえて「大乗茶道」を唱えた。
1951(昭和26)年に出版した『新茶道』は小林一三の茶道論をまとめたもので、一部の特権階級のための茶道、既成の茶道を批判し、民芸品などを茶器に見立てて、椅子を配置した茶室を造り、簡素な茶道、茶の湯を提案。阪急百貨店内に古美術売場を設け、茶器などの古美術品を安心して入手できるようにし、茶道の大衆化を推し進めた。
阪急文化財団が運営する「一三ネットワークの100人」で、小林一三に縁のある著名な人物100名を、政治、経済、演劇、文芸、茶道など、さまざまな分野からピックアップして紹介している。茶道からは、兵庫県伊丹市の清酒「白雪」の醸造元の小西新右衛門(道易軒)や、東武鉄道グループの創業に関わった「鉄道王」の根津嘉一郎(青山)、三井財閥を支えた実業家の益田孝(鈍翁)など、12人の茶人との交流が綴られている。
奥内陶芸美術館
大阪府豊中市岡町北3-8-1
06-6852-3842
休館日 月曜日 土曜日 日曜日 冬季・夏季休館、不定休有
10:00~16:00 300円
柳宗悦らによって興された、日常使いの雑器に美を見出そうとする民藝運動に共感した奥内豊吉は民藝運動に参画した陶芸家の名品の蒐集を皮切りに、近現代の陶芸家の名品を蒐集。
1972(昭和47)年、静かな住宅街に奥内陶芸美術館を開館。奥内は、民藝運動に邁進した棟方志功の版画や、染色工芸家で人間国宝の芹沢銈介の染色画をこよなく愛したことでも知られている。
河井寛次郎、富本憲吉、楠部弥弌、北大路魯山人などの茶碗がずらりと並び、益子焼の中興の祖で、民藝運動をしていた濱田庄司の名品を集めた展示室、葛飾北斎、喜多川歌麿、歌川豊国、歌川広重、歌川国貞などの浮世絵展示室、ルノワール、マリーローランサン、キスリングなどの絵画展示室、ピカソ、ビュッフェなどのデッサン展示室がある。
1000点を超える美術品を所蔵し、650点強を常設展示し、板谷波山の「窯變唐草文水差」、北大路魯山人の「瀬戸花器」、加守田章二の茶碗、志野の人間国宝、鈴木蔵の「志野花瓶」など、茶道具も多い。
奥内は、オフィスビル、賃貸マンション、ビジネスホテルなどの経営で財を成したオクウチグループの創業者で、故郷の兵庫県淡路市に高さ100メートルの「世界平和大観音像」の寺院・博物館を建設したことでも有名。
さかい利晶の杜
大阪府堺市堺区宿院町西2丁1-1
072-260-4386
休館日 第3火曜日(祝日の場合は翌日)年末年始 観光案内展示室は年末年始
9:00~18:00(入館は17:30まで) 千利休茶の湯館・与謝野晶子記念館・さかい待庵外観見学 300円
茶の湯体験施設は10:00〜17:00 観光案内展示(無料ゾーン)は9:00〜18:00
大阪府堺市には、世界遺産の「百舌鳥・古市古墳群」に登録された百舌鳥古墳群を構成する仁徳天皇陵古墳(大山古墳・大仙陵古墳)をはじめとする古墳群、歴史的な町並み、刃物や和菓子などの伝統産業など数多くの歴史文化資源がある。戦国時代には堺で鉄砲が生産され、鋼の生産技術は現在も包丁や自転車の機能部品などに受け継がれている。
堺の歴史と文化を見学、体験しながら楽しめる施設として2015(平成27)年に開館したのが「さかい利晶の杜」。堺で生まれた茶人、千利休に関する「千利休茶の湯館」、明治の歌人、与謝野晶子の作品と生き方を紹介する「与謝野晶子記念館」の2つのミュージアムを持つ。
わび茶の大成者として知られ、千家茶道の祖である千利休は堺の商家に生まれ、生涯の大半を堺で過ごした。本名は田中与四郎、法名は宗易で、64歳のとき正親町天皇から利休居士号を賜り、70歳で亡くなるまでの短期間、利休を名乗った。堺の豪商の武野紹鷗に茶の湯を習い、織田信長や豊臣秀吉の茶頭として仕え、秀吉の禁中茶会や北野大茶湯の開催を支え、「天下一の茶の湯者」と称された。
堺は町全体を囲むように掘られた環濠があり、堺環濠都市遺跡から出土した貿易陶磁器(国境を越えて輸出・輸入された陶磁器の総称)や志野、織部などの茶道具類も展示。最新型VRゴーグルを付けると、立体映像で中世の環濠都市「堺」のまち並みが再現される体験型コンテンツも楽しめる(約7分。常設展示観覧とVRセット券1400円)。千利休が造った茶室で現存する国宝の「待庵」は京都府の大山崎町の妙喜庵にあるが、「さかい待庵」は創建当初の姿を復元している。
与謝野晶子は、堺市の甲斐町にあった和菓子商「駿河屋」に生まれ、22歳で上京し、歌の師である与謝野寛(鉄幹)と結婚して12人の子どもの母となった。歌集『みだれ髪』や詩「君死にたまふことなかれ」を発表し、『源氏物語』の現代語訳や社会問題、教育問題に関する評論も行っていた。
生家の「駿河屋」を再現しており、数学が得意だった晶子は帳簿を付け、店番をしながら文学作品を読んだという帳場も再現。観光案内展示室もあり、敷地内には和食レストランが併設されている。
堺市博物館
大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町2丁 大仙公園内
072-245-6201
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 年末年始
9:30~17:15(入館は16:30まで) 200円
堺市の歴史、文化、美術、考古、民俗について分かりやすく紹介するミュージアムで、仁徳天皇陵古墳がある大仙公園の一角にある。巨大古墳が数多くある百舌鳥古墳群は2019(平成31)年に「百舌鳥・古市古墳群」として世界遺産に登録された。
海外からの来訪者を巨大なモニュメントで迎えるため、堺の海岸近くに巨大古墳が造られたと考えられるが、堺は室町時代から安土桃山期にかけて、会合衆と呼ばれる有力商人たちが中心となり、自由都市、貿易都市として栄えた。貿易、商業によって得た富を背景に、千利休をはじめ茶人、文化人を輩出し、キリスト教の宣教師が「堺は日本の最も富める港」と記すほどの繁栄ぶりだった。
博物館では古代から現代までの堺の歴史を遺物、史料、パネルなどで紹介し、堺の姿を伝える映像を上映。仁徳天皇陵古墳をドローンで空撮した迫力満点の映像の「百舌鳥古墳群疑似体験ツアー)」や、大型スクリーンでしか体感できない古墳群の雄大さを伝える「百舌鳥古墳群シアター」がある。
展示エリアでは観音菩薩立像、漆塗太鼓形酒筒、旧浄土寺九重塔の3点の国の重要文化財の他、仁徳天皇陵甲冑図、仁徳天皇陵出土埴輪、南蛮船(カラック)模型、堺鉄砲(火縄銃)、菱垣廻船の模型、庖丁製作工程(復元)などを展示。茶道具では「志野茶碗」「瀬戸美濃天目茶碗」「湊焼茶碗」「鼠志野向付」「備前水指」「中国製 青磁花入」「瓦質土器釜」などを所蔵している。
和泉市久保惣記念美術館
大阪府和泉市内田町3-6-12
0725-54-0001
休館日 月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 500円
久保惣記念美術館は1982(昭和57)年に開館した和泉市立の美術館で、日本と中国の絵画、書蹟、工芸品などの東洋古美術を中心に、国宝2点、重要文化財29点を含む約1万1000点を所蔵。
久保惣は、明治時代から100年近く綿業を営み、泉州有数の企業として発展。初代久保惣太郎が1886(明治19)年に創業し、2代惣太郎、忠清、3代惣太郎と引き継がれ、1977(昭和52)年の廃業を機に、3代惣太郎が代表して、美術品、美術館の建物、敷地、基金を和泉市へ寄贈し、久保家旧本宅跡地に開館した。5代目代表者の久保恒彦によって、1997(平成9)年、美術館新館が寄贈され、その後も、久保家や久保惣の関係者から音楽ホール、市民ギャラリー、市民創作教室、研究棟が追贈され、約5000坪の敷地を有するミュージアムとなっている。
日本の書蹟では、平安時代のかなの名品「歌仙歌合」(国宝)、「貫之集下 断簡・石山切 藤原定信筆」(重文)をはじめ、「熊野懐紙」藤原範光筆(重文)などの古筆、奈良時代以降の経巻と鎌倉時代の墨蹟の重要文化財を収蔵。絵画は、鎌倉時代の「伊勢物語絵巻」「駒競行幸絵巻」、室町時代の「山王霊験記絵巻」(3点とも重文)などの絵巻、「源氏物語手鑑 土佐光吉筆」、「枯木鳴鵙図 宮本武蔵筆」(2点とも重文)などがある。
浮世絵版画は、葛飾北斎や歌川広重の風景画、喜多川歌麿や東洲斎写楽の人物画、歌川国芳の武者絵、月岡芳年や落合芳幾、河鍋暁斎(周麿)の名所絵などを収蔵。広重が晩年に制作した「六十余州名所図会」全70点、三代歌川豊国の「豊国揮毫奇術競」37枚、月岡芳年の「和漢百物語」27枚など、シリーズを一挙に展示することも多い。
陶磁器では、中国・南宋時代の「青磁 鳳凰耳花生 銘 万声」(国宝)、日本・桃山時代の「黄瀬戸立鼓花入 銘 旅枕」「唐津茶碗 銘 三宝」(いずれも重文)、金工品では「響銅 水瓶」「響銅 鵲尾形柄香炉」(いずれも重文)などがある。
西洋美術では、モネ、ルノワール、ゴッホ、ピカソ、ロダンなど、西洋近代の絵画15点、彫刻2点、16~18世紀にヨーロッパで制作されたアジアを含めた世界の古地図、19~20世紀の西洋のエッチングやリトグラフなどを持つ。
所蔵品を活かして年4~5回の企画展と年1回の特別展を開催。茶会、コンサート、市民による作品展など、市民の創作発表の場も提供している。日本や中国を中心とした東洋の美術、関連する諸地域の歴史、考古学、宗教、文化などの図書資料約6万7000冊を所蔵し、このうち3万5000冊は中国古代史学の権威である貝塚茂樹の旧蔵書の「貝塚茂樹記念文庫」。
ホームページにデジタルミュージアムを開設しており、絵画、版画、彫刻、金工、木漆工、陶磁器などの作品を見ることができる。
正木美術館
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中2-9-26
0725-21-6000
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)
10:00~16:30(入館は16:00まで) 700円
正木美術館は大阪府泉北郡の忠岡町にあり、茶道の大成者、千利休を生んだ堺に隣接しており、茶の湯の文化が町衆の間で広く根付いていた。
正木美術館の創設者、正木孝之は泉州の文化的土壌で育ち、代々続いてきた庄屋の当主として歴史や伝統文化に関心を持ち、後に茶道を熱心に取り組んだ。若い頃から工務店、映画館の経営で財を成し、早くからコレクターの道を歩み始めた。
戦後の混乱期に、かつての豪商や財閥家の経済的事情から代々受け継がれてきた古美術品が売りに出され、散逸しかねない状況にあり、名品の取得に乗り出す。中国の元時代の文人画家、銭選が描いたと伝わる「果蓏(樹木になる実と、つる草になる実)秋虫図」と出会って東洋古美術品に魅了され、大阪の豪商・鴻池家から出た大燈国師の墨蹟、小野道風の三体白氏詩巻、藤原行成の白氏詩巻などを蒐集。後に、いずれも国宝に指定されている。
コレクションを東洋古美術品、特に中世の禅宗文化の墨蹟と水墨画、茶道具と定め、奈良時代から江戸時代にかけての美術工芸品、埴輪や銅鏡といった考古資料、仏教関係などの分野の作品も購入。蒐集した美術品と土地・建物を寄付し、1968(昭和43)年、正木美術館を設立。収蔵品は国宝3件、重要文化財13件を含む約1300点に上る。
展示館の隣に住居かつ茶道の実践の場でもあった茶室付の正木記念邸(主屋、中門、腰掛待合が国の登録有形文化財)があり、展覧会開催中の土曜日、日曜日、祝日には内部(一部)の見学が可能。
正木は武者小路千家流の茶人で、号は滴凍。正木記念邸は、戦後、自ら設計して建てた建物で、庭にある中門は、武者小路千家に伝わる茶道の官休庵と同じ編笠門になっている。茶室「滴凍庵」に至る露地庭に伽藍石などの飛び石が配されている。非公開だが、茶会や展覧会関連のイベントの際に、茶室の一部を公開している。
茶の湯関連では、千利休の存命中に描かれた唯一の作品「千利休像」(伝 長谷川等伯筆、重文)、「黒楽茶碗 銘 両国 伝長次郎作」「竹製瓢形茶器」「茶杓 銘 ゆみ竹 千利休作」「緋襷矢筈口水指」「肩衝茶入 銘 有明」などを所蔵。
正木記念邸(国の登録有形文化財)を紹介する動画で、建物や茶室の詳細が理解できる。
兵庫県
白鶴美術館
兵庫県神戸市東灘区住吉山手6-1-1
078-851-6001
休館日 春季・秋季展会期中の月曜日(祝日は開館、翌平日休館)
10:00~16:30(入館は16:00まで) 800円
白鶴美術館は1934(昭和9)年、六甲山の麓の閑静な住宅街に開館し、戦前に誕生した私立美術館の1つ。白鶴酒造7代の嘉納治兵衛正久(鶴翁、鶴堂、鶴庵)が集めた古美術品のコレクション500点から出発し、現在は国宝2件(75点)、重要文化財22件(39点)を含む1450点以上の美術品を所蔵している。
現存する日本最古の私立美術館は、明治から大正期に財を成し、大倉財閥を創始した大倉喜八郎が1902(明治35)年に東京で大倉美術館を開館し、1917(大正6年)に財団法人大倉集古館となったのが最初。
1926(大正15)年には、藤井紡績の創業者、藤井善助が中国の古美術中心の私立美術館、藤井斉成会有鄰館を京都に設立。岡山県倉敷市を基盤に活躍した事業家、大原孫三郎が1930(昭和5)年に設立した大原美術館は日本で最初の西洋美術中心の私立美術館となった。
若い時から古美術好きであった治兵衛は婿養子として嘉納家に入り、茶人でもあった。「世界的価値のあるコレクションを私蔵するのではなく、多くの人の目に触れてほしい」と考えていた治兵衛は古美術の蒐集に努め、蒐集品の中でも、殷・西周の青銅器、漢から明時代の陶磁器、奈良時代の経巻(きょうかん)、鎌倉から江戸時代の絵画が充実している。
開館60周年記念事業として1995年に新館を開設して「絨毯美術館」とした。白鶴酒造10代の嘉納秀郎が集めた近中東の多彩な絨毯、約130点を所蔵し、トルコ、コーサカス、イラン(ペルシア)の絨毯やアフリカの仮面や彫刻を展示。
本館、茶室の「崧庵」、事務棟、土蔵が国の登録有形文化財に指定されており、崧庵は、六甲の地にあった茶室建築を1956(昭和31)年に移築したもの。茶室は入母屋屋根の中央を瓦葺とし,その周囲に銅板を葺き回した瀟洒な外観で、上質な造りとなっている。
茶道具では「禾目天目茶碗」「玳玻天目茶碗」「青磁鳳凰耳花生」「青磁浮牡丹文香炉」などを所蔵。
★香雪美術館(御影) 休館中
兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-12-1
078-841-0652
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 展覧会によって異なる
香雪美術館の香雪は、美術に強い関心をもっていた村山龍平の号で、龍平は28歳で朝日新聞を創刊し、日本を代表する新聞に育てた。価値ある美術品の海外流出を食い止めたいと、美術品の蒐集に力を注ぎ、岡倉天心らが主宰する美術雑誌「國華」の経営も引き受けた。
龍平が亡くなった後、美術館設立の声が上がり、1973(昭和48)年、神戸市東灘区の御影に香雪美術館を開館。2館目の美術館として「中之島 香雪美術館」を2018年にオープン。
所蔵品は重要文化財19点、重要美術品33点が含み、仏教美術、書蹟、近世絵画、茶道具、刀剣・武具など幅広いジャンルに及ぶ。
香雪美術館(御影)は施設設備の改築工事のため現在、長期休館中で、展覧会活動は中之島香雪美術館(大阪市北区)で行っている。
「中之島 香雪美術館」の常設展示施設として、国指定重要文化財「旧村山家住宅」に建つ茶室「玄庵」を原寸大で再現。茶室だけでなく、露地(茶室に備え付けられた庭と茶室までの通路のことで、露地口を入るときから茶の湯は始まる)を含めた全体を再現。
村山龍平は、大阪の財界人との交流を通じて茶の湯を楽しむようになり、藪内流の藪内節庵に茶を学んだ。節庵は、野村證券や大和銀行(現・りそな銀行)など野村財閥を築いた野村徳七といった財界人を多数門下に抱えていた。
藪内流は、足利義政の同胞衆の藪宗把を遠祖としており、初代、藪内剣仲は武野紹鴎の門下で、古田織部の妹と結婚した人物。
村山龍平邸に建てられた茶室「玄庵」は、藪内流家元の茶室である重要文化財「燕庵」の写し。写して建てることは、相伝を得た人だけが許される決まりで、龍平の茶の湯への取組み姿勢が伺える。
茶道具の所蔵品としては、重要美術品の「黒楽茶碗 銘 古狐 長次郎作」「利休丸壺茶入」、重要文化財の「志野松籬絵水指」の他、「名物手井戸茶碗 燕庵井戸」「茶杓 銘 茶瓢 村田珠光作」などがある。
鉄斎美術館
兵庫県宝塚市米谷字清シ1 番地 清荒神清澄寺内
0797-84-9600
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)
10:00~16:30(入館は16:00まで) 300円
富岡鉄斎は、明治、大正期の文人画家、書家で、石門心学、儒学、陽明学、詩文などを学び、女流歌人で尼僧の大田垣蓮月に預けられ薫陶を受けた。煎茶道、茶の湯に詳しく、言葉を大事にし「自分の絵を見るときは、まず賛(絵画に書かれている文章)を読んでくれ」と頼むほどで、「最後の文人画家」と謳われた。
鉄斎美術館は、清荒神清澄寺の第37世法主、坂本光浄和上が半世紀に渡って蒐集した富岡鉄斎の作品を広く公開するため、1975(昭和50)年、清荒神清澄寺の境内に開館。
所蔵する鉄斎作品は絵画、書をはじめ、鉄斎が絵付を施した陶器や器物など「鉄斎の器玩」と呼ばれる作品、資料など2000点を超える。
器玩とは、身辺に置いて日々賞玩し愛でる器や工芸品という意味で、茶道具の職人が作った茶碗、鉢、花器、釜、香炉や、煎茶道で使う急須や茶碗に絵を施したり、文様や文字を入れて仕上げた美術工芸品を指す。
鉄斎美術館別館「史料館」が2008(平成20)年に開館。鉄斎美術館「聖光殿」は資料整理のため休館しており、展覧会は「史料館」で開催している。入館料の全額は、美術図書購入基金として宝塚市に寄付し、宝塚市立中央図書館内に「聖光文庫」を設置し、豊富な美術関係図書を揃えている。
光浄和上は富岡鉄斎と親交があり、13点の絵画を贈られた。清荒神清澄寺が所蔵する富岡鉄斎作品は、初期から晩年に至る絵画、書、陶工や指物師が作った器物に絵付けなどをした器玩、先人の構図・筆法・彩色を学ぶために模写した粉本、書簡など多岐に渡る。
光浄和上と、その遺志を継いだ第38世坂本光聰和上は、フランスのギメ美術館、アメリカのボストン美術館、東京国立博物館、東京国立近代美術館、京都市美術館など、国内外のミュージアムに作品を寄贈し、1936(昭和11)年から国内各地、アメリカ、イタリア、ドイツ、イギリス、中国などで、清澄寺のコレクションによる鉄斎展を開催。
光浄和上は自ら海外の展覧会場を訪れ、鉄斎の平和精神と「三宝(仏・法・僧)三福(行福、戒福、世福の3つのよい行い)」の真理を説いたこともあって、清荒神清澄寺は「鉄斎寺」として世界に知られている。
「鉄斎の器玩」の展覧会はこれまで何度も行われおり、器玩に関する解説と展示品の目録を以下に掲載する。茶道具の職人と、数多くのコラボ作品を制作していたことが分かる。
鉄斎と茶の湯
http://www.kiyoshikojin.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/20190406_list.pdf
鉄斎の器玩―売茶翁没後250年によせてhttp://www.kiyoshikojin.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/20111222_list.pdf
鉄斎の器玩―名工と遊ぶ―
http://www.kiyoshikojin.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/20110105_list.pdf
鉄斎の器玩―匠との共演―
http://www.kiyoshikojin.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/20081222_list.pdf
滴翠美術館
兵庫県芦屋市山芦屋町13-3
0797-22-2228
休館日 月曜日(開催中) 夏季・冬季は休館
10:00~16:00(入館は15:30まで) 630円
滴翠美術館は、六甲山の美しい景観を背景にした閑静な住宅街にあり、四季折々の草花が訪れる人を迎える。山口銀行(前身は第百四十八国立銀行。後の三和銀行)の頭取で、大阪財界で活躍した山口吉郎兵衛(4代)の邸宅だった場所で、1964(昭和39)年に開館。
山口銀行が鴻池銀行、三十四銀行と合併して三和銀行となった1933(昭和8)年を機に財界を離れ、1951年に他界するまで、京焼や紀州焼などの陶器、人形、かるた、羽子板などを研究し、蒐集に没頭。古美術品コレクションは2500点を上回り、吉郎兵衛が生前に望んでいたコレクションの一般公開を、遺志を継いだ夫人が住宅を改装し、吉郎兵衛の雅号であった「滴翠」を冠した美術館とした。
明治後期から昭和初期にかけての茶道の隆盛に大きな影響を与え、流派を超えて財界人と交流した茶人、藪内節庵の門下であった吉郎兵衛は、茶道具の蒐集にも力を注ぐ。
重要文化財の「扇面鳥兜螺鈿蒔絵料紙箱 本阿弥光悦作」をはじめ、茶道具では「赤織部沓形茶碗」「赤楽茶碗 銘 勾当 長次郎作」「銹絵雪笹文手鉢 尾形乾山作」「色絵松竹梅文箙形花入」「茶杓 銘 御坊へ 高山右近作」、後水尾上皇の修学院離宮で焼かれた「修学院焼 冠形大耳付水指」などを所蔵。
美術館となった旧山口吉郎兵衛宅は「関西モダニズム建築20選」「ひょうごの近代住宅100選」に選定されている。
兵庫陶芸美術館
兵庫県丹波篠山市今田町上立杭4
079-597-3961
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 展覧会によって異なる
兵庫陶芸美術館は瀬戸、常滑、信楽、備前、越前とともに日本六古窯の1つである丹波焼の里にあり、近くには、現存最古の登窯である「丹波立杭登窯」がある。
全但バス社長の田中寛が1966(昭和41)年に創設した財団法人兵庫県陶芸館からの寄贈と、購入によって陶磁器901件をベースに、2005(平成17)年に開館。古陶磁、現代陶芸作品、世界各地の陶磁器の2000点余りの収蔵品を基に企画展や、年間4回の特別展と、数回のテーマ展で陶芸文化の魅力を発信し、さまざまなイベントや陶芸のワークショップを実施。丹波焼、三田焼、出石焼、姫路の東山焼(姫路焼とも)、淡路島の珉平焼など、兵庫県内で作られた古陶磁や現代陶芸作品を所蔵する。
丹波焼は、地元の須恵器(古墳時代から平安時代にかけて日本で生産された青灰色をした硬い土器)の生産体制を活用して、平安末期(12世紀後半)に常滑焼や渥美焼など東海地方の陶器の技術を取り入れて誕生した。丹波では、江戸時代以降、赤土部や灰釉を用いた器面装飾が行われ、多様な茶陶が作られた。中でも水指や花入を多数製作し、当時の茶人の流行や好みが反映され、水指は造形や釉調が整い優れた作品が多い。
茶道具では、珉平「色絵海老文茶碗」、丹波「灰釉手桶形水指」、篠山藩主の青山忠裕が王地山に築いた藩窯の王地山「染付祥瑞写瓢箪形水指」、丹波「焼締耳付花入」、淡路島で誕生した淡陶社(現・ダントー)「伊羅保写茶碗」などを所蔵。
「丹波焼の里 ミュゼレター」は、年2回(春・秋)発行している情報誌で、バックナンバーもホームページに掲載している。
丹波焼など日本六古窯は「きっと恋する六古窯-日本生まれ日本育ちのやきもの産地-」として2017年度の日本遺産に認定された。「きっと恋する六古窯」の公式サイトでは6つの窯の概要と歴史を紹介している。
★頴川美術館 閉館
兵庫県西宮市上甲東園1-10-40
頴川家は、江戸時代に廻船業や山林業を営む大阪の商家で、4代目頴川徳助は家業を継ぎ、頴川家伝来の美術品を通して審美眼を養うが、戦災により所蔵していた名品は焼失。戦後、家業の復興に取り組み、幸福相互銀行社長、会長となり、美術品の蒐集に力を注いだ。
美術品は個人に属すべきものではないと、1973(昭和48)年に西宮市に美術館を開館。樂焼の祖、樂長次郎の赤樂茶碗の代表作である重要文化財の「無一物」、織田信長が所持していた「大名物肩衝茶入勢高」(重要美術品)などの茶道具の名品をはじめ、重要文化財の伝能阿弥筆「三保松原図」や室町期のやまと絵「紙本著色山王霊験記」、「奇想の絵師」と呼ばれた長沢芦雪の水墨画「月夜山水図」(重要美術品)、池大雅、円山応挙、谷文晁の絵画、墨蹟など約500点を収蔵し、展示していた。
4代目頴川徳助は1976年に死去し、経営難のため運営母体の財団は2019年に解散し、所蔵品および土地建物は兵庫県に譲渡された。現在、重要文化財4件、重要美術品4件を含む約250件が「頴川コレクション」として兵庫県立美術館の所蔵になっている。
兵庫県立美術館
兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 (HAT神戸内)
広島県
神勝寺 禅と庭のミュージアム
広島県福山市沼隈町大字上山南91
084-988-1111(寺務所)
休館日 不定期
9:00~17:00(入館は16:30まで) 1800円
天心山 神勝寺は造船大手の常石造船の2代目社長、神原秀夫が開基となり1965(昭和40)年に創建された臨済宗建仁寺派の禅寺で、国際的な禅道場を持つ。
神勝寺境内の約7万坪の敷地にアートスポットや茶室、食事処などがあり、新しい禅体験ができる施設として2016年にオープン。広大な敷地には、滋賀県から移築した17世紀の堂宇(四方に張り出した屋根、軒を持つ建物)や、復元された千利休の茶室、建築家・建築史家の藤森照信が、山陽道から瀬戸内一帯を象徴する松を多用して設計した寺務所などが点在し、趣向を凝らした禅庭が配されている。
臨済宗中興の祖、白隠慧鶴禅師の禅画や墨蹟約200点余の「白隠コレクション」も見どころの1つ。作品は随時展示替えを行いながら、本堂の近くにある常設展示館の「荘厳堂」で公開。
白隠は「仏国土(仏の救済の対象を教化できる範囲のこと。浄土)は金銀で飾った壮麗な建物があるわけではない、仏国土は菩提心(悟りを求めようと決心すること)を持った菩薩によって荘厳(知恵や福徳などで仏の身を飾ること)されるのだ」と説いており、荘厳堂は、鑑賞する人々に菩提心を喚起する空間となっている。
禅宗美術のコレクションと対を成すように建つのが、彫刻家の名和晃平と彼が率いるクリエイティブ・プラットフォームSANDWICHの設計によるパビリオンの「洸庭」。木材で包まれた舟型の建物で、内部の空間で、波に反射する光を体験知覚するインスタレーション(装置芸術)が体験できる。
茶席の秀路軒は、1788(天明8)年、京都で発生した天明の大火で焼失した表千家の「残月亭」と「不審庵」を古図に基づいて復元、再現したもので、茶祖である千利休を祀るお堂「利休堂」があり、茶室では抹茶と菓子で一服でき、茶事などで使用される(抹茶・和菓子セット800円)。
一来亭は、千利休が京都の聚楽屋敷に建てたとされる一畳台目の茶室を復元したもので、玄庵は数寄屋造りの建物で、四畳半の小間と十畳半広間、水屋からなる茶室。建仁寺垣と呼ばれる竹垣を配し、壁面を檜皮張りにしており、落ち着いた雰囲気の中で心安らぐ時を過ごせる。
瀬戸田 耕三寺博物館
広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田553-2
0845-27-0800
年中無休
9:00~17:00(入館は16:30まで) 潮聲閣は10:00~16:00 1400円(耕三寺境内、未来心の丘、金剛館を見学できる) 書院潮聲閣は別途入館料が必要
大阪で大口径の特殊鋼管の製造会社を営んでいた耕三寺耕三が、母親の実家である生口島の瀬戸田町に母の別荘として近代和風建築の潮聲閣を建て、母の死後、母への報恩感謝の意を込めて、自ら僧籍に入った。1935(昭和10)年、43歳のとき浄土真宗本願寺派で得度し、法名「耕三」を受け、山梨県甲州市の寺で住職となり、寺を瀬戸田町に移転し、1943(昭和17)年に寺号を「耕三寺」に変更することを許された。
耕三寺は、世の中のすべてのお母様にありがとうと、心から手を合わせる「母の寺」として親しまれている。1970(昭和45)年に78歳で亡くなるまで、耕三は日本各地の国宝の建造物を手本として堂や塔を建設し、そのうち15棟は国登録有形文化財に登録されている。
耕三寺博物館は1953(昭和28)年、耕三寺家の美術コレクションを公開するために開館。快慶作の「宝冠阿弥陀如来坐像」「唐花鴛鴦八稜鏡」「佐竹本三十六歌仙 紀貫之」などの重要文化財をはじめ、仏教美術、近代美術の絵画、彫刻、書蹟、工芸、茶道具を蒐集。
寺域全体を博物館施設として公開し、テーマに沿って金剛館、法宝蔵、僧宝蔵などで美術品を公開。未来心の丘は、5000平方メートルにも及ぶ白い大理石の庭園で、世界を舞台に活躍している彫刻家、杭谷一東が制作したもの。光明の塔、風の四季と命名された彫刻が丘に広がっている。
茶道具のコレクションも充実。茶碗では「黒釉色絵七宝文茶碗 野々村仁清作」「御所丸茶碗 加賀 前田家伝来」、花入では「藪内剣仲一重切花入」、水指では「古銅宣徳抱桶水指」、茶入では「名物 瀬戸肩衝茶入 銘 村上肩衝」、茶枃では「千利休作共筒茶杓 追銘 面影」などを所蔵。
慈照寺銀閣を模した茶祖堂には、千利休と藪内剣仲の像が並んで鎮座している。藪内流の祖、藪内剣仲は武野紹鷗の弟子で、兄弟子の千利休の勧めで、大徳寺に参禅し「剣仲」の道号を授かり、利休、古田織部とも親交が深い。剣仲の妻は織部の妹で、利休が媒酌人であった。
島根県
足立美術館 魯山人館
島根県安来市古川町320
0854-28-7111
休館日 年中無休(新館のみ、展示替えのため休館日あり)
9:00~17:30 4月~9月
9:00~17:00 10月~3月 2300円(2025年4月から2500円)
足立美術館の創設者、足立全康は現在の安来市古川町(美術館の所在地)で生まれた。小学校卒業後、生家の農業を手伝うが、身を粉にして働いても報われない両親を見るにつけ、商売の道に進もうと決意。14歳のとき、木炭を運搬する仕事に就き、次に炭の小売りを始めた。戦後は、大阪で繊維問屋、不動産などの事業のかたわら、幼少の頃から興味を持っていた日本画を蒐集し、美術品のコレクターとして知られるようになった。
庭造りへの関心も次第に大きくなり、1970(昭和45)年、71歳の時、郷土への恩返しと、島根県の文化発展の一助にとの思いで、足立美術館を創設。1979年には北沢コレクションの「紅葉」「雨霽る」「海潮四題・夏」をはじめとする横山大観の作品群を一括購入した。
北沢コレクションは、長野県諏訪市で東洋バルヴを興した北澤國男、友喜、克男、元男の4兄弟の北澤家が蒐集した美術品。東洋バルヴはオイルショック後の業績不振で、1976年に倒産し、「紅葉」を含む横山大観の作品20点は管財人が管理していた。全康は2年がかりで管財人と交渉し、約8億円で購入に成功。
全康は名古屋の横山大観展で見た「紅葉」(六曲一双屏風)に言葉も出ないほどの感動を受け、手に入れたいと調べたところ、門外不出の「幻のコレクション」と言われた北沢コレクションの一部と判明。当時、管財人の手元にあった大観の作品は「紅葉」以外に20点近くあり、そのほとんどが名古屋の展覧会で観た作品だった。長い間、画集から切り抜いて額に入れて毎日飽きもせず眺めていた「雨霽る」も含まれていた。
足立美術館は「名園と横山大観コレクション」を基本コンセプトにしており、大観を中心に、竹内栖鳳、上村松園、川合玉堂、橋本関雪、菱田春草などの近・現代日本画の傑作が揃う。大観の絵画を120点以上所蔵しており、質、量ともに日本一を誇る。
開館50周年を迎えたことを記念し、北大路魯山人の作品約500点を展示するための「魯山人館」を2020年にオープンし、常時約120点が展示されている。足立全康が魯山人の作品200点を蒐集し、孫の足立隆則(現館長)が精力的に蒐集したコレクションが加わって500点を超えた。
魯山人は陶芸家、篆刻家、料理随筆家、書家、画家で、1920(大正9)年に古美術店「大雅堂」を開店し、翌年には「美食倶楽部」を主宰。料理や器などを取り仕切り、会員制の料亭「星岡茶寮」を運営。1936年以降は陶芸に専心し、1959年に76歳で亡くなった。「雲錦鉢」「織部扇面形鉢」「織部竹形花入」「そめつけ詩書花入」などの茶器を残している。
足立美術館は5万坪の敷地に、枯山水庭、苔庭、白砂青松庭、池庭などの庭園を有し、茶室「寿楽庵」では、純金の茶釜で沸かした湯で抹茶を提供(見学料・抹茶料は1000円)。
「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」で三つ星を取得、アメリカで発刊されている日本の庭園専門誌「ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング」では22年連続で日本一に選ばれている。同誌は、日本国内の日本庭園約1000カ所を対象に調査して「日本庭園ランキング」を発表。2024年では、1位 足立美術館(島根県)、2位 桂離宮(京都府)、3位 山本亭(東京都)、4位 庭園の宿 石亭(広島県)、5位 松田屋ホテル(山口県)となっている。
田部美術館
島根県松江市北堀町310-5
0852-26-2211
休館日 月曜日(祝日の場合は開館) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 700円 立礼席(抹茶、菓子付)500円
田部家伝来の美術品の寄贈を受け、田部美術館が1979(昭和54)年、茶の湯が盛んな松江の地に開館した。創設者は“日本一の山林王”と言われた田部家の23代当主、田部長衛右門朋之で、病院の経営、島根新聞社(現・山陰中央新報社)の社長、島根県知事を歴任。陶磁器や絵画など美術への関心が高く、茶に親しみ「松露亭」の号を持っていた。
田部家は、鎌倉時代に紀州(和歌山)の熊野から吉田村(現在の島根県雲南市吉田町)に移り住み、武士として代々過ごした後、室町時代の1460年に「たたら製鉄」を開始。奥出雲地方は良質な砂鉄と森林資源に恵まれ木炭があるため、約1400年前の飛鳥時代から、炉に空気を送り込むふいご(たたらと呼ばれていた)で鉄を作っていた。田部家の初代、彦左衛門は新規に参入し、川砂鉄を採取して製鉄を始めた。
江戸時代になって、松江藩を主な顧客として繁栄し、10代のときに「長右衛門」の名を授かり、12代長右衛門は1755年、鉄師頭取(たたら製鉄の経営者)に任命された。幕末から明治期に最盛期を迎え、2万5000ヘクタールの山林を持ち、奥出雲で生産される鉄は日本の鉄需要の8割を賄っていた。
明治時代になると、西洋から鉄の輸入、八幡製鉄所の操業(1901年、明治34年)などで、たたら製鉄は大きな打撃を受け、大正末期の1923年に廃業。その後は、山林事業を中心に木材、住宅、不動産、観光、飲食などの事業を行っている。
田部美術館は、約600年に渡り田部家が収集した美術品、江戸時代後期の大名茶人、松江藩7代藩主の松平不昧(治郷)の愛蔵品の茶器、不昧公自ら作った作品、楽山焼(松江藩の御用窯として名高い焼物。出雲焼とも呼ばれる)、布志名焼(松江市玉湯町で焼かれる陶器)など、茶道に関する美術品を公開。
茶道具を中心に、彫刻や洋画なども所蔵する田部美術館は松江城の堀のそばにあり、北堀町の塩見縄手一帯の濠端は古い武家屋敷の残る伝統美観保存地区で、近くには小泉八雲記念館がある。
手銭記念館
島根県出雲市大社町杵築西2450-1
0853-53-2000
休館日 火曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 800円
出雲地方の工芸は、江戸時代後期、茶人大名として有名な出雲松江藩7代藩主、松平治郷(号は不昧)の時代に始まったものが多く、独特の個性や魅力を持っている。
手錢家は1702(元禄15)年から家業の1つとして酒造業を営んでいたが、明治維新とともに廃業。江戸時代の1860(安政7)年に建造された酒蔵は、1871(明治4)年に学校令が公布されてから、1903年に杵築村尋常小学校が新築されるまで、校舎として地元の子供たちの学び舎になった。
その酒蔵を改装して1993(平成5)年に手銭記念館が開館し、江戸初期から続く手錢家から寄贈された500点を超える所蔵品を管理、公開。江戸時代から昭和半ばまでの出雲の工芸品、明治から昭和初期の日用品や土産用の陶器といった雑器などを、時節に応じて替える。
松平不昧公によって奨励され、高い品質の茶道具が生まれた。松江藩の御用窯として名高い茶碗の楽山焼、布志名という宍道湖岸で江戸時代に始まった布志名焼、さまざまな釉薬を駆使した久村焼、蒔絵師の小島漆壺斎、蒔絵師の勝軍木庵光英、木工家の小林如泥らの作品や、出雲の古歌「八雲立つ」から命名された漆塗りの八雲塗、金工品など、名産品が目白押し。
第一展示室の企画展示では、造り酒屋を営み、御用宿でもあった手錢家に伝来する掛軸、屏風、刀剣、古文書など、日本の美術、工芸、文化を幅広く展示。第二展示室は酒蔵を利用し、江戸時代の代表的茶人の松平不昧公ゆかりの陶器の楽山焼と布志名焼、松江藩のお抱え塗師だった小島漆壺齋の漆器など、出雲地方の美術品や伝統工芸品を紹介する。
安来市加納美術館
島根県安来市広瀬町布部345-27
0854-36-0880
休館日 火曜日 年末年始
9:00~16:30(入館は16:00まで) 1100円
加納美術館は、画家であった加納辰夫(雅号 莞蕾)を父に持つ加納溥基が、郷里の文化の発展、文化活動や生涯学習の拠点となるようにと、1996(平成8)年に安来市広瀬町布部(旧・能義郡広瀬町)に開館した。
2002年、広瀬町に寄贈し、広瀬町立加納美術館となり、市町村合併に伴って2005年、安来市加納美術館となった。
加納莞蕾の作品と、広瀬町出身の芸術家から寄贈された作品が手元にあり、戦後、莞蕾がフィリピン日本人戦犯助命嘆願活動を起こし、フィリピンの6代大統領、エルピディオ・キリノなどに送った300通にも及ぶ嘆願書の往復書簡の控えを保存したいという思いが美術館設立の動機だった。
だが、これらの展示物だけでは山奥の美術館に人々は来てくれないだろうと、溥基は趣味であった茶の湯、陶芸品を集めることにし、岡山で会社を経営していたので、備前焼を中心に全国の茶陶に関する作品を蒐集。
現在、古備前を含めた備前焼と、5人の人間国宝の作家の作品約500点、茶陶は茶の湯の碗を中心に文化勲章受賞者と人間国宝作家の作品約400点、地元出身の芸術家の絵画や彫刻を保有している。
衰退していた備前焼を繁栄に導いて、中興の祖と称される金重陶陽の作品111点、鎌倉備前を追求しながら、おおらかな温かみのある作風の藤原啓の作品30点、備前焼ロクロ技術の第一人者の山本陶秀の作品108点、備前焼以外では安土桃山時代を代表する陶芸家で、樂焼の祖、樂長次郎の作品を収蔵。
河井寛次郎ら山陰ゆかりの作家の企画展などを年間4~5回開催。備前焼、小野竹喬と池田遙邨の日本画も随時公開。茶室「如水庵」では、名碗を手にとって愉しめる「名碗を愉しむ会」を定期的に行う。
備前焼は、日本六古窯(瀬戸、常滑、丹波、越前、信楽、備前)の中でも最も古い焼物で、平安末期ごろ、和気郡伊部(現在の岡山県備前市)で誕生した。備前焼の特長は釉薬をかけないで焼く無釉焼き締めの方法を用い、土と火の融合で生み出される素朴な焼物で、古墳時代の須恵器の流れを汲む。
岡山県
大原美術館 工芸・東洋館
岡山県倉敷市中央1丁目1-15
086-422-0005
休館日 月曜日(祝日の場合は開館)7月下旬~8月は無休 冬期休館あり9:00~15:00(入館は14:30まで) 12月~2月
9:00~17:00(入館は16:30まで) 3月~11月 2000円 本館と工芸・東洋館共通
1930(昭和5)年に開館した大原美術館は戦後、拡張し、現在は本館、分館、工芸・東洋館に分れている。工芸・東洋館は、米や綿の貯蔵庫であった蔵を改装した展示室で、日常の生活道具の美しさを見出す活動の民藝運動を支持した作家の陶器や版画、染色などの工芸品、東洋の古美術品を展示。
大原美術館の創立者である大原孫三郎と息子の總一郎は、柳宗悦らが主唱した民藝運動に共鳴し、支援し、東京・駒場にある「日本民藝館」の設立費用のほとんどを大原家が出資するなど、民藝運動との関わりは深い。
工芸・東洋館では、民藝運動を支持した6人の作家による工芸品を、部屋ごとに展示し、陶芸家は4人。栃木県益子町に定住し、益子焼の中興の祖となった濱田庄司、イギリス人の陶芸家で、画家、デザイナーとしても知られるバーナード・リーチ、色絵磁器に金銀彩を加えた華やかな作風富本憲吉、新しい自分が見たいと陶芸、彫刻、デザイン、書、詩に旺盛に挑んだ河井寛次郎のコレクションは充実している。
岡山・吉兆庵美術館
岡山県岡山市北区幸町7-28
086-364-1005
休館日 第1、第3月曜日(祝日の場合は開館) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 600円
創作和菓子で有名な「宗家 源 吉兆庵」の岡山本店に併設されたミュージアムはJR岡山駅の近くにあり、岡山県が誇る美術工芸品の備前焼を常設展示する。備前焼の特徴は窯変(窯の内部で起きる焼成による変化のことで、特に灰などによって生じた色の変化)で、2週間ほどの時間をかけて1200度以上の高温で焼き締めるため、強度が高く保温力がある。
常設展では、備前焼の歴史、魅力、見どころ、古備前、金重陶陽など備前焼の歴代人間国宝の作品を紹介、展示する。吉兆庵美術館は陶磁器、漆器、人形などの工芸品を蒐集しており、コレクションを中心にした企画展も開催。
★備前市美術館(旧・備前市立備前焼ミュージアム) 休館中
岡山県備前市伊部1659-6
0869-64-1861 備前市役所 備前市美術館準備室
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日)
9:00~17:00 500円 1階展示室と歴史展示室は無料 企画展は展覧会で異なる
1987(昭和62)年に、備前焼に関する美術館の備前焼伝統産業会館が開館。その後、備前市立備前焼ミュージアムと名称を変更して運営。建替え工事に伴い、2023(令和5)年に休館し、2025年4月に名称を備前市美術館に変更し、JR伊部駅の隣接地に新設される。
備前焼文化を世界に発信する拠点とし、備前市のランドマークとして地域の未来を切り拓く役割を担う。備前焼は日本六古窯の一つで、残りは瀬戸、常滑、丹波、越前、信楽。備前焼の作家や窯元が集まる備前市伊部地域にあり、800年以上の歴史を持つ備前焼の歴史、魅力を紹介する。
備前焼の陶芸家、金重陶陽、藤原啓、山本陶秀、藤原雄、伊勢﨑淳などの作品を所蔵。備前市が誇る名工で、いずれも備前焼の人間国宝。
★FAN美術館(藤原啓記念館) 休館中
岡山県備前市穂浪3868
0869-67-0638
http://bizen-kanko.com/spot/spot_detail/index/159.html
FAN(ふぁん)美術館は、岡山県備前市穂浪にあった美術館で、2017(平成29)年に藤原啓記念館の同じ敷地内に併設する形で開館。備前焼の作家で、金重陶陽に続いて人間国宝になった藤原啓の足跡、年代ごとの代表作品、藤原が影響を受けた古備前を集めて展示していた。藤原啓の長男で、人間国宝の藤原雄の作品も多数所蔵。
2023年9月から休館。
山口県
山口県立萩美術館・浦上記念館
山口県萩市平安古町586-1
0838-24-2400
休館日 月曜日(祝日は開館) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 300円
萩市出身で、鉱山経営に携わっていた実業家の浦上敏朗が寄贈した浮世絵と東洋陶磁を核とした2000点を超えるコレクションを基に、浮世絵と東洋陶磁の専門美術館として1996(平成8)年に開館。
山口県の文化資源であり、400年の歴史を持つ萩焼をはじめ、陶芸の振興を目的に陶芸館を2010年に増築し、人間国宝の作品など、近現代の陶芸、工芸作品、資料を展示している。
浮世絵は浦上コレクションを核として、オランダの浮世絵蒐集家、フェリックス・チコチンによるコレクションや寄贈品を含め、約5500点の浮世絵版画を収蔵し、世界に3点しかない葛飾北斎の美人大首絵「風流無くてなゝくせ 遠眼鏡」や「富嶽三十六景」、歌川広重の「東海道五十三次之内」、初期の菱川師宣、錦絵創始期の鈴木春信、黄金時代の鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、後期浮世絵の歌川国貞、歌川国芳など、江戸時代を代表的する浮世絵師の名品を所蔵。
月岡芳年、豊原国周、楊洲周延、三代歌川広重など、幕末から明治時代に制作された作品も多数保有しており、有数なコレクションとして世界的に知られている。
東洋陶磁は、浦上敏朗コレクションを基に、日本板硝子社長を務めた松村實のコレクションと、志野焼のコレクター、染野義信(元・日本大学法学部教授)のコレクションなどが加わった。中国陶磁は新石器時代から明代まで、朝鮮陶磁は高麗時代と李氏朝鮮時代、日本陶磁は桃山時代、江戸時代を中心に所蔵。
萩焼は、萩藩主の毛利氏が17世紀初頭に萩藩の御用窯として開窯し、古田織部好みの歪みのある花入など、独自の造形美を志向してきた。茶碗、花入など茶の湯の道具の萩焼、茶人に愛された志野焼、近代陶芸家の名品を数多く持ち、茶室での展示も行っている。
有名な旅行ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド」で、 日本三名橋の1つ「錦帯橋」とともに、山口県立萩美術館は山口県内最高ランクの2つ星の観光名所として紹介されている。
熊谷美術館
山口県萩市今魚店町47
0838-25-5535
休館日 月曜日 水曜日~金曜日(祝日の場合は開館)
9:00~16:00 700円
熊谷家は、萩で問屋、金融、製塩業を営んでいた萩藩の御用商人で、萩藩7代藩主の毛利重就が藩の財政立て直しに着手した1754(宝暦4)年、力量を評価されて初代熊谷五右衛門芳充が抜擢され、御用金を調達し期待に応えた。年貢米の販売権を得た芳充は藩外の米も買い付けるなどして領内一の豪商となり、大坂の両替商で、大名貸を行っていた鴻池家や加島屋と同格となった。
芳充が50才の1768(明和5)年、萩の菊ヶ浜に近い今魚店町に新居を構えた。その後、6代まで御用商人として萩藩に仕え、明治以降も7代萬吉から11代伊織まで、250年間住み続け、現在に至っている。
熊谷家の3000坪(1万㎡)の敷地には、初代熊谷五右衛門が新築した主屋、離れ座敷、本蔵、宝蔵など13の蔵が立ち並ぶ(主屋、離れ、本蔵、宝蔵の4棟は国の重要文化財)。土蔵3棟を改造して展示室とした熊谷美術館は1965(昭和40)年に開館し、歴代の当主が蒐集した美術品を展示。
収蔵品は江戸時代を中心とする美術工芸品や民具、1400年代の水墨画家、雪舟をはじめとする書画屏風類、茶道具、香炉、硯箱、代々伝わる文書類など、約3000点に上る。
4代五右衛門義比がドイツ人医師のシーボルトから贈られた英国、ロルフ商会製のスクエアピアノは日本に残る最古のピアノとして有名。シーボルトが1823(文政6)年に持ち込んだもので、来日して200年を超えている。義比は文化の愛好者で、長崎に行き、シーボルトから膝と足の痛みの治療を受け、西洋事情を見聞。シーボルトが長崎郊外に開設した、診療所と医学や自然科学を教える鳴滝塾を支援し、高野長英、岡研介(鳴滝塾の初代塾長)など学者、医者、文人墨客を経済的に支えた。
茶道具では、樂焼、萩焼、唐津焼の茶碗、野々村仁清、尾形乾⼭、青木木米の作品、唐物や日本各地の陶磁器、⾹合、花器、風炉、釜、⽔指、茶⼊、棗、茶杓、菓⼦器などを所蔵している。
★石井茶碗美術館 閉館
山口県萩市南古萩町33-3
0838-22-1211
休館日 月曜日 1月6日~31日、6月、12月(展示替え期)
9:00~12:00 13:00~17:00 1000円
山口県萩市にある石井茶碗美術館は、茶碗の蒐集家として有名だった石井規源斎が約50年かけて集めた茶碗専門の美術館で、1969(昭和44)年に開館。江戸初期の珍しい古萩を中心に、萩焼の原点といわれている高麗茶碗や、瀬戸焼、伊万里焼、志野焼、唐津焼など日本各地の約130点の茶碗と茶道具約20点を展示していたが、閉館。
初代の坂高麗左衛門や三輪休雪の名碗などを収蔵していた。坂は、毛利輝元によって萩に連れてこられ、萩焼を創始した朝鮮人陶工で、2代藩主の毛利綱広から「高麗左衛門」の名を賜った。三輪休雪と共に萩藩の御用窯を務め、萩焼の本流を代々受け継いでいる。
福岡県
福岡市美術館
福岡県福岡市中央区大濠公園1-6
092-714-6051
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
9:30~17:30(入館は17:00まで)
7月~10月の金曜日と土曜日は9:30~20:00(入館は19:30まで) 200円
福岡市美術館
福岡市の都心部、水と緑に恵まれた大濠公園の中に、1979(昭和54)年、福岡市美術館が開館。福岡城跡、外交使節の接待用として平安時代に築かれた迎賓館の鴻臚館跡がある舞鶴公園に隣接しており、歴史、文化、観光の拠点となっている。
福岡市美術館は、重要文化財を含む茶道具や仏教美術、黒田清輝、青木繁、坂本繁二郎など九州出身の近代洋画家、ミロ、ダリ、ウォーホルなど20世紀の作家の作品、現代美術作品など、1万6000点超を蒐集しており、大規模改修を終え、2019年にリニューアルオープンした。
東邦電力(後に中部電力、関西電力、四国電力、九州電力に再編される)の経営に携わり、電力事業の再編で日本の発展に寄与した松永安左エ門は長崎県壱岐島の出身で、美術品蒐集家、茶人として知られ、耳庵の号を持つ。
北条早雲を祖とする後北条氏の時代も茶の湯が盛んだったため、「近代」を付け、小田原に居住した松永耳庵は近代小田原三茶人の1人。残りは、小田原に住み茶道を究め、三井物産の設立に関わった益田鈍翁(益田孝)と、中外商業新報社(日本経済新聞社の前身)や三越呉服店(現・三越伊勢丹)の社長だった野崎幻庵(野崎廣太)。
近代茶道の3人の偉人を「近代三茶人」と呼ぶが、益田鈍翁、松永耳庵に加え、生糸貿易で財を成し、富岡製糸場などの経営再建をした原三渓(原富太郎)の三茶人を指す。
松永コレクションは、小田原市にあった財団法人松永記念館が所蔵していたが、戦前に蒐集したものは東京国立博物館に、戦後に蒐集した茶道具や仏教美術など重要文化財20件を含む371点のコレクションは福岡市美術館に寄贈された。
福岡市美術館の松永コレクションには「猿投灰釉壺」「色絵吉野山図茶壺 野々村仁清作」「花籠図 尾形乾山作」(いずれも重要文化財)「志野宝珠香合」「高麗割高台茶碗 銘 下葉」「高麗雨漏茶碗」などがある。
福岡市美術館の茶道具には福岡藩初代藩主の黒田長政をはじめ黒田家伝来のものもあり、「唐物茶入 銘 博多文琳」「肩衝茶入 銘 源十郎」「織部茶入」「文琳記 小堀遠州筆」などを所蔵。
福岡東洋陶磁器美術館
福岡県福岡市城南区七隈8丁目7-42
092-861-0054
休館日 月曜日 祝日(敬老の日、文化の日は除く) 1・2月、7・8月(展示作品入れ替えのため)
10:00~17:00(入館は16:30まで) 800円
福岡市城南区にある私立総合大学、福岡大学に隣接する文教地区に、1999(平成11)年、福岡東洋陶磁美術館が開館。会計学の教授で、福岡大学の創立者として知られる溝口梅太郎の「福岡の学術文化を大いに発展させたい」という遺志が美術館の創設に繋がった。
梅太郎は高等教育の必要性を感じたが、学校を作る予算不足で賛同者は現れず、私財を投げ打ち借金をして福岡高等商業学校(現・福岡大学)を創立。借金返済のため事業を興し、返済に充てるという強い信念を持っていた。
梅太郎の息子で、西日本短期大学の学長を務めた溝口虎彦は、古代以降、アジアとの文化交流の拠点であった博多に、東洋古陶磁専門の美術館を誕生させたいと、半世紀をかけて蒐集したコレクションを公開。
茶の湯に造詣の深い虎彦は、中国、朝鮮、日本の貴重な鑑賞用陶磁、茶入、茶碗、水指、花入、香合、向付、火入、鉢などの茶陶を蒐集し、茶室「慈勝庵」の庵主として茶会を催した。『慈勝庵コレクション 茶陶と東洋陶磁名品展』という図録も発行。桃山時代の志野焼、織部焼などの茶陶の名品が多く、展示フロアの茶室でお茶会なども開催できる。
美術館のホームページの「所蔵品の一部解説」で茶入、茶碗、水指、花入、香合、向付などの作品を紹介している。
出光美術館 門司
福岡県北九州市門司区東港町2-3
093-332-0251
休館日 月曜日(祝日の場合は閉館) 年末年始
10:00~17:00(入館は16:30まで) 700円
出光興産の創業者、出光佐三とゆかりの深い門司港レトロ地区に、出光コレクションを展示する出光美術館(門司)が2000(平成12)年に開館。建物は大正期に建てられた出光興産の資材備蓄庫を改装・増築したもので、レトロな雰囲気で作品を鑑賞できる。
機械油を販売する出光商会を門司で設立し、国内有数の石油精製会社に育てた出光佐三は卓越した審美眼を持つ美術蒐集家でもあった。19歳の学生であった佐三は、当時あまり知られていなかった江戸時代の禅僧で画家の仙厓義梵の作品に出会い、父に頼んで入手。
これが出光コレクションの第1号で、中国陶磁や古唐津などに興味を持ち、日本屈指のコレクションを築き上げた。古美術を蒐集する一方で、陶芸家の板谷波山、画家で歌人の小杉放菴といった明治、大正、昭和の同時代の作家とも交流を深め、作品を蒐集した。
東京・丸の内にある出光美術館には茶室「朝夕菴」を設置しており、仙厓和尚の命日の10月7日に茶会を開催。仙厓が住職をしていた福岡県博多の聖福寺は臨済宗妙心寺派の寺院で、宋から茶種を持ち帰った明菴栄西の創建した日本最初の本格的な禅寺だ。
『喫茶養生記』を著わして日本に茶を広めた栄西ゆかりの聖福寺の住職、仙厓はユーモアに溢れ、洒脱な禅画を数多く残している。
宗像郡赤間村(現在の宗像市)出身の佐三は、故郷の宗像の発展に情熱を注ぎ、特に宗像神社(現・宗像大社)復興に尽力し、1962(昭和37)年から毎年10月17日、出光興産の主催で「献茶祭」を開催。
千利休を祖とする表千家の家元によって、宗像大社で茶の奉納が行われ、茶道関係者約600人が参加。この行事で、出光美術館の貴重な茶道具を使い、茶席が設けられる。佐三の「日本の文化を後世へ継承していきたい」という想いで始まり、現在も続いている。
出光美術館 門司では、日本の書画、中国と日本の陶磁器を中心に、テーマに沿った展覧会が年に5~6回行われ、出光コレクションを順次紹介し、出光佐三の生き様や事業の軌跡を伝える「出光創業史料室」も併設。
芦屋釜の里 芦屋釜の里資料館
福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿1558-3
093-223-5881
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日) 年末年始
9:30~17:00(入館は16:30まで) 300円 呈茶(抹茶と菓子)400円
芦屋釜の里は、季節の花と緑があふれる3000坪の日本庭園、芦屋釜の里資料館、芦屋釜復興工房、いつでも抹茶を楽しめる立礼席、大小の茶室などの施設を持つ。
芦屋釜は、南北朝時代の頃(14世紀半ば)から筑前国の芦屋津金屋(現在の福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜)で作られた茶の湯釜のこと。真形と呼ばれる端整な形と、胴部に表される優美な文様は京都の公家、貴人に好まれた。
芦屋釜の製作は江戸時代初期に途絶えたが、現代の茶席でも、芦屋釜は主役を務める存在で珍重されている。国指定の重要文化財の茶の湯釜9点のうち、芦屋釜が8点を占めている。
芦屋釜の里資料館は芸術性、技術力の高い芦屋釜の特色、歴史、茶の湯釡の製作工程などを展示物や映像で紹介。芦屋釜復興工房では、鋳物師たちが芦屋釜の復興を図るため、釜の製作、技術継承に取り組んでいる。
大茶室の「蘆庵」は庭園を一望できる25畳の茶室で、大寄せの茶会にも利用でき、露地、にじり口を備えた4畳半の茶室「吟風亭」もある。立礼席で抹茶と季節の干菓子を楽しめる。
佐賀県
佐賀県立九州陶磁文化館
佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙3100-1
0955-43-3681
休館日 月曜日(祝日の場合は翌日) 年末年始
9:00~17:00(入館は16:30まで) 無料 特別企画展は有料
肥前(佐賀県、長崎県)の陶磁器をはじめ、九州各地の陶磁器の文化遺産の保存と陶芸文化の発展のため作品、資料を蒐集、保存、展示するため1980(昭和55)年に開館。
九州陶磁の源流である中国、朝鮮の陶磁の年表や、日本の陶磁器の歴史、古伊万里とオランダ貿易の特色などを紹介。エントランスに陶器製のからくりオルゴール時計があり、30分ごとに動き出す。
柴田夫妻コレクション、蒲原コレクション、九州の古陶磁、白雨コレクション、唐津高取家の寄贈品、有田町の陶芸作家の青木龍山作品コレクション、唐津焼の人間国宝の中里逢庵作品コレクションなどがある。
柴田明彦・祐子夫妻が寄贈した「柴田夫妻コレクション」は17~18世紀、江戸時代に作られた有田焼(古伊万里)の代表的な作品と様式の変遷が分かるもので、寄贈された1万311点の中で約1000点を展示。
有田町出身の商社マンで、陶磁史の研究家であった蒲原権が有田町に寄贈した蒲原コレクションは、ヨーロッパの貴族を魅了した古伊万里などの陶磁器、資料を展示。ヨーロッパに輸出された有田焼が里帰りした形で、九州陶磁文化館の開館に合わせて有田町から寄託され、常設展示している。
白雨は蒲原信一郎の号で、高校時代から古美術蒐集を始め、竹中工務店に入社後は古美術コレクションの管理などを担い、茶の湯を趣味とした。遺族が444件925点の陶磁器類を寄贈。茶人だったため茶道具の陶磁器が多い。
九州各地の古陶磁のコーナーでは、佐賀県の古唐津、初期伊万里、古伊万里、柿右衛門、鍋島焼、長崎県の亀山焼、現川焼、平戸焼、福岡県の高取焼、上野焼、須恵焼、熊本県の網田焼、小代焼(小岱とも)、八代焼(高田)焼とも)、大分県の小鹿田焼、宮崎県の蓬莱山焼(丸山焼とも)、鹿児島県の龍門司焼、苗代川焼、沖縄県の壷屋焼などを紹介。
「暮らしを彩る」のコーナーは「酒」「煙草」「茶」「香」「化粧」「書」の6つのジャンルに分けられ、有田焼の食器、道具類が展示されており、館内の茶室「碟泉庵」は茶会や茶陶の展示などに使われる。
中里太郎右衛門陶房陳列館・御茶盌窯記念館
佐賀県唐津市町田3-6-29
0955-72-8171
休館日 水曜日 木曜日(祝日の場合は翌日休館) 年末年始
9:00~17:30 陳列館 国指定史跡 唐人町御茶盌窯 無料
9:00~17:00(入館は16:30まで)御茶盌窯記念館 400円
中里太郎右衛門陶房は初代中里又七から現在の14代中里太郎右衛門まで約430年の歴史を持つ窯元で、1615(元和元)年に唐津藩の御用窯となった。御茶盌窯(中里太郎右衛門陶房)は1734(享保19)年から唐津藩の御用窯として将軍家などへの献上品を焼くのに用いられた。この窯で焼かれたものは「献上唐津」と呼ばれ、抹茶碗、水指、花入などの茶陶や茶碗、大皿などが作られた。
陳列館には13代、14代の作品や工房の職人による唐津焼が展示販売され、工房の敷地内には5代中里喜平次が築窯した「国指定史跡 唐人町御茶盌窯」があり、自由に見学できる。
向かいにある御茶盌窯記念館は2020年に開館し、12代中里太郎右衛門(無庵)の150年前の旧宅をリノベーションし、中里家が蒐集した桃山時代の古唐津や唐津藩の御用窯で焼かれた献上唐津、歴代の太郎右衛門の代表作品を展示する。400年以上の歴史の中で変遷してきた唐津焼、中里家の歴史、中里家ゆかりの作品を紹介。
茶の世界では古くから「一井戸、二樂、三唐津」という茶の湯茶碗の品定めがされてきた。井戸茶碗は朝鮮半島で作られた高麗茶碗の一種で、高麗時代ではなく、李氏朝鮮時代の15~16世紀に焼かれたもの。「わび茶」の創始した村田珠光が活躍した頃は青磁や白磁の価値が高く、高麗茶碗は日常の雑器であったが、わびの美意識にかなう茶碗だと、日本の茶人に使用され、茶の湯の名品として人気が高まった。
「一樂、二萩、三唐津」と茶器を評価するフレーズもあるが、これは国産の焼物を対象にしたもの。いずれにも、千利休がプロデュースした樂焼と、唐津焼が入っている。粗い土を使った唐津焼は素朴な風合いと多彩な装飾技法が特徴で、強い主張を持たないため、お茶や料理、花などを引き立てる器として高い人気を誇った。
長崎県
波佐見町陶芸の館
長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2
0956-85-2290(波佐見町観光協会)
0956-85-2214
休館日 年末年始
9:00~17:00 無料
波佐見町陶芸の館 | 観光スポット | 【公式】長崎観光/旅行ポータルサイト ながさき旅ネット
波佐見やきもの公園にある「世界の窯広場」は、古代から近世にかけて世界を代表する窯12基を再現した世界でも珍しい野外博物館。最も古い「野焼き窯」を山上に配置し、東アジアでは中国、朝鮮、日本などの窯を、ヨーロッパ、中近東ではイギリス、トルコなどの窯が同寸大、あるいは3分の1で復元。ゴールデンウィークには県内外の人々で賑わう「波佐見陶器まつり」がやきもの公園で開催される。
公園の一角にある「波佐見町陶芸の館」の2階が歴史資料館になっており、400年近い波佐見焼の歴史と伝統、匠たちの技を紹介し、歴史的な磁器から現代の商品までを展示。
絵付師ロボットがリアルな表情と語りで波佐見焼について解説。「くらわんか碗」や「コンプラ瓶」など、波佐見焼の歴史的史料や波佐見焼の工程などを紹介する。波佐見では、かつて大坂と京都を結ぶ淀川で船遊びをしている客に、行商の船が「飯くらわんか」「酒くらわんか」などと声を掛け、物を売った時に使う茶椀や皿や徳利、海外輸出用の白い磁器の酒瓶のコンプラ瓶などの日用の磁器を生産していた。
コンプラの由来は、ポルトガル語で「仲買人」を意味するコンプラドール(comprador)の略称。1637(寛永14)年に起きた島原の乱後、江戸幕府はキリスト教と関連のあるポルトガル人を追放し、1642年にオランダ人商人を平戸から出島に移し、長崎の日本商人16人と貿易のための組合「金富良商社」(コンプラ社)を設立した。
日本から醤油や酒をコンプラ瓶に詰めて輸出し、海外からはオランダ東インド会社を通じて生糸、ラシャ(毛織物)、ギヤマン(ガラス製品)などを輸入。当時、堺産の醤油が主に輸出され、高級品として京都産の醤油も扱った。波佐見で焼かれていたコンプラ瓶は最盛期には年間40万本ほど作られていた。
歴史資料館では、当時の賑わいを描いた絵や道具類を展示し、ワラや縄を使って茶椀を梱包する手順を実物で紹介するなど、展示の仕方や見せ方にも工夫を凝らしている。1階の「くらわん館」は絵付け・ろくろ体験やショッピングが楽しめ、窯元や焼物の商社が30以上並ぶ波佐見焼最大級の観光物産館。波佐見町観光協会もあり、観光情報も入手できる。
焼物の伝統や文化が受け継がれてきた「肥前やきもの圏」は佐賀県と長崎県にまたがり、唐津、伊万里、武雄、嬉野、有田、波佐見、佐世保(三川内)、平戸の8つのエリアがあり、波佐見は有田の隣りのエリア。
佐賀県と長崎県の8つの市と町が「肥前やきもの圏」として日本遺産に指定され、ホームページには肥前陶磁器の特徴が紹介されている。
8つの市町と焼物名は、唐津市(唐津焼)、伊万里市(伊万里・鍋島焼)、武雄市(武雄焼)、嬉野市(肥前吉田焼・志田焼)、有田町(有田焼)、波佐見町(波佐見焼)、佐世保市(三川内焼)、平戸市(中野焼)。
大分県
日田市立小鹿田焼陶芸館
日田市大字鶴河内(源栄町)138-1
0973-29-2020
休館日 水曜日 年末年始
9:00~17:00 無料
小鹿田焼は、日田市の山あい、源栄町皿山地区で焼かれる陶器で、江戸幕府の直轄領(天領)であった1705(宝永2)年、日田の代官が領内の生活雑器を作るために窯を開かせた。
山を隔てた現在の小石原(福岡県朝倉郡)から陶工の柳瀬三右衛門を招き、柳瀬を招いた日田郡大鶴村の黒木十兵衛が資金を出し、小鹿田の坂本家が土地を提供。この3家が中心となって小鹿田焼が始まった。小石原焼は、16世紀末の桃山時代に渡来した朝鮮人陶工の技術の流れを汲む。
原料に、集落周辺で採取される、鉄分を多く含み、赤みがある土だけを使い、釉薬によってさまざまな形と文様を表現し、素朴さと温かみを出している。轆轤を回しながら、化粧土をつけた刷毛を小刻みに打ちつけて文様を付ける刷毛目、轆轤を回しながらL字型鉋を当てて表面を削る飛び鉋、化粧土や釉薬を一定の高さから垂れ流すようにかける流し掛けなどの技法を駆使して焼物を仕上げる。
こうした陶芸技法が1995(平成7)年に国の重要無形文化財に指定され、2008年には地区全体(約14ヘクタール)が「小鹿田焼の里」の名称で重要文化的景観に選定された。
1970年に建てられた日田市立小鹿田焼陶芸館が、2012年に建て替えられて開館。展示室には江戸時代から現在までの小鹿田焼の作品が展示され、小鹿田焼の歴史や特徴を学べる。
大分県の山間部で、ひっそりと作られていた陶器が脚光を浴びるきっかけとなったのが民藝運動だった。1926(大正15・昭和元)年に、美術研究家、思想家の柳宗悦と、陶芸家の濱田庄司、河井寛次郎、富本憲吉の4人が連名で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表し、民藝品のための美術館の開館と、無名の職人による美術工芸の美を発掘し、世の中に紹介しようという「民藝運動」が始まった。
運動の中心人物、柳は1931(昭和6)年、雑誌「工藝」に「日田の皿山」というレポートを書き、「この窯は北九州の古窯を知る者にとっては異常な興味をそそる。なぜならあの慶長頃から元禄にかけて旺盛を極めた朝鮮系の焼物が、今日ほとんど煙滅し去った時、ひとりこの窯ばかりは伝統を続けて今も煙を絶やさないからである」と記した。
後に『日田の皿山』という書籍を出版し、「世界一の民陶」と小鹿田焼を絶賛。日本民藝館の開館が実現し、民藝運動の高まりとともに、「誰からも省みられず貧しい歴史をつづけている」と記されていた小鹿田焼の名は全国へ広まっていく。
小鹿田焼陶芸館では大型の壺や皿、湯呑、急須、土瓶などの茶器や日常生活で使う皿などが展示され、小鹿田焼に関する映像を流している。
沖縄県
★那覇市立壺屋焼物博物館 休館中
沖縄県那覇市壺屋1-9-32
098-862-3761
休館日 月曜日(祝の日場合は開館) 年末年始
10:00~18:00(入館は17:30まで) 350円
琉球と呼ばれていた沖縄の土器、焼物の歴史は古く、およそ1万年前に作られた土器が発見されている。沖縄は中国、東南アジアとの貿易を行っていて、14世紀後半から酒甕や碗など多くの陶器を輸入し、1429年に「琉球王国」が誕生してからも朝鮮、タイ、ベトナム、日本から陶磁器を輸入。城の瓦などを中心に作られていた沖縄の焼物の質と技術が大きく向上した。
1609年、薩摩の島津藩が琉球を支配下に置き、1616年、薩摩から招聘した朝鮮人陶工が、琉球の湧田村(現・那覇市泉崎)に朝鮮式の製陶技法を伝え、現在のやちむんの基礎が築かれた。やちむんは琉球の言葉で「焼き物」を表し、「やち」は「焼き」、「むん」は「物」の意味。
琉球王国の中央政庁、首里王府(琉球王府ともいう)は工芸産業の振興策として、1682年、琉球内に分散していた知花、宝口、湧田といった複数の窯場を那覇市壺屋に統合。これが壺屋焼の始まりで、功績のあった陶工を士族に取り立てるなど、焼物技術の発展を後押しした。
壺屋焼は荒焼と上焼に分類され、釉薬をかけずに約1120度で焼き上げた焼物を荒焼、赤土に白土で化粧がけをしたり、釉薬をかけた焼物を上焼という。荒焼では酒甕や水甕、壺など大型の器を作り、上焼は食器、酒器、花器など日用品が中心で、壺屋焼の主流を占めている。
壺屋は、戦前は閑静な農村地帯だったが、戦後、人口が増えて市街地化し、1960年後半から登り窯による煙害が問題となり、登り窯にこだわる窯元は読谷村に工房を移転。読谷村座喜味に「やちむんの里」が生まれ、沖縄で初めて人間国宝となった陶芸家、金城次郎が1972年に壺屋から座喜味に窯を移したことを機に、陶工たちが集結し20ほどの工房になっている。
壺屋やちむん通りにある壺屋焼物博物館は、土器に始まって近年の壺屋焼に至る沖縄の焼物の歴史をひも解き、焼物の色や形、文様の特色、壷屋焼の技法、暮らしの中での使われ方、製作工程を紹介。壺屋焼の特徴的な作品、人間国宝の金城次郎など陶工の名作、沖縄で作られた食器、壺、シーサーなどの焼物を展示している。映像シアターでは、昔の壺屋の暮らしぶり、壺屋焼の技法、伝統を受け継ぐ陶工の思いを大スクリーンで知ることができる。
沖縄の茶文化は、15世紀頃、琉球王国と中国との間で行われた貿易を通じて伝わってきた。王族や貴族の間で茶の儀式が行われ、独自の茶の飲み方や茶会を開催。1879(明治12)年、沖縄県が設置され、琉球王国が消滅すると(琉球処分)、日本の茶文化の影響も受けながら、独自の茶文化を育み、多様化していく。
沖縄で定番のお茶は、さんぴん茶。「さんぴん」は琉球王国時代に中国から伝わったジャスミン茶の香片(シァンピェン)が転じたもの。さんぴん茶の起源は15世紀で、琉球の使者が明朝に派遣された際、1466年に茶葉を持ち帰ったとの記録が残っている。
さんぴん茶の普及は、琉球の陶器産業にも大きな影響を与え、さんぴん茶を美味しく、美しく楽しむための茶器の生産が盛んになり、香りを最大限に引き出す独特の形状の茶器が開発された。
沖縄には「ぶくぶく茶」という、煎り米を煮だした湯と茶湯を混ぜて泡立て、茶碗に盛って飲むお茶もあり、琉球王朝時代、賓客をもてなす際に提供されていた。茶道具として使われるのが大きな木製の器のぶくぶく鉢と、25センチほどの巨大な茶筅で、茶碗には沖縄陶器や琉球漆器が使われた。
沖縄では、お茶やお酒を通じて家族や友人、地域社会とのコミュニケーションを図ることが多い。集まっておしゃべりすることが楽しみで、「イチャリバ チョーデー」(出会えば兄弟)という言葉があるほど、お茶やお酒の席を大事にしている。壺屋焼物博物館はエレベーター改修工事のため2025年3月末まで休館。
*茶道関連のミュージアムを掲載していますが、漏れているミュージアムがあれば、ご連絡いただければ幸いです。茶碗、茶の湯釜などの茶道具のミュージアムも含まれています。
*記事を転載する場合は、以下のURLを記載してください。
茶道のミュージアムに行こう!
https://note.com/mzypzy189/n/nccf07f204090
