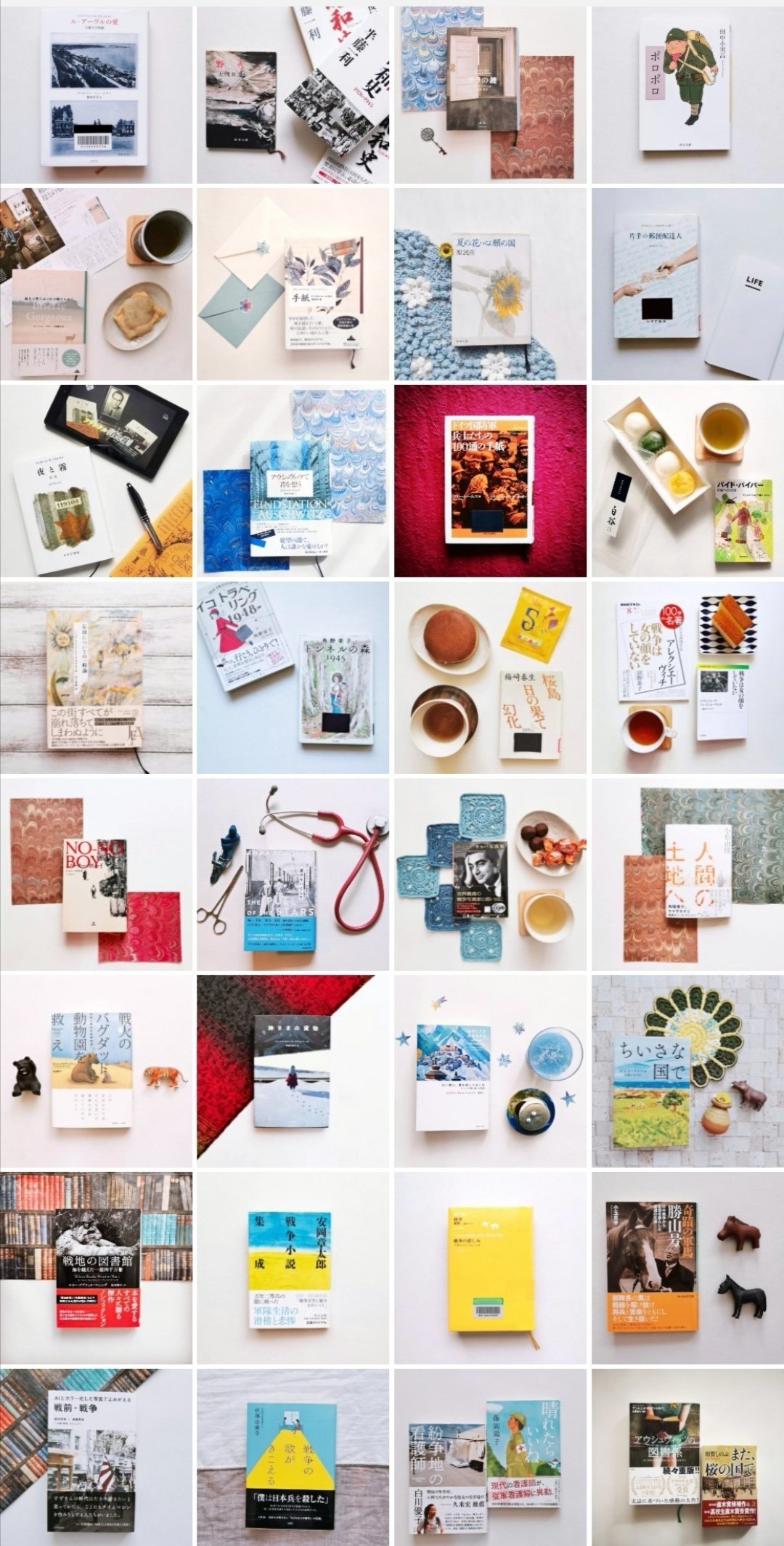わたしと戦争と文学と
窓を背にした図書室の隅、日も当たらない薄暗い本棚の下、私は煤けた床にしゃがんでいた。
一番下の棚には、大型の書籍が収められている。
ぎちぎちに詰まった本の群からハードカバーの花切れに爪を立て、ぎゅっぎゅっぎゅっと一冊抜き出す。
しましま模様の服を着た人物が写る白黒の表紙──アウシュヴィッツ強制収容所の写真集だった。
図書室はとても静かで、私以外に誰もない。
いや、もしかしたら他に誰かいたのかもしれないが、なんの音も、声も、気配も感じられなかった。
それほどまでにそれらの白黒写真は私をこの世界から隔離し、目を逸らそうにも頭をがっちりと固定されたかのように他の何ものも目に入らなくなっていた。
心臓が苦しいほどに速く、強く鳴っている。
誰かに見つかりはしないかと、背中で隠しながらページを捲りつづけた。
小学4年生だった。
この日から、図書室に行くと部屋の隅に「彼ら」を感じた。
木枠のようなベッドにぎゅうぎゅうに押し込められた骨と皮ばかりの男たち。
バラックと有刺鉄線の間に佇む女たちと子供。
刈り集められた藁のように積まれた髪の毛。
倉庫いっぱいの眼鏡と靴と骨の山と。
後ろめたいような何かもやもやしたものが私の深層にこの本の存在を隠し、度々この本を捲っていることを誰にも話すことができなかった。
彼らの姿は脳裏にべったりとこびりつき、その後何年経っても今もなお消えてはいない。
アウシュヴィッツを知ったこと、これが戦争文学やノンフィクションを読まずにはいられない私の原点になっている。
読む前の自分に戻ることはできないもの、それが戦争文学だと思う。
読むことも知ることも苦しい。
楽しんで読んだことなど一度もない。
自分でもなぜここまで戦争や紛争関連の本を手にしてしまうのか、正直明確に答えられるものはない。
ただ、とにかく知りたい。
何が起こったのかを、起きているのかを。
知って何ができるのか。
何もできない。
何もできないからまた苦しい。
だけど、読んでも読んでも、足りない。
どれだけ多くの声を集めても事実を並べても、この世界で長く広く根深く起こり続けている戦争を知り、その全ての悲しみを理解することなどできないから。
だから私は読み続けるしかない。
どこかの誰かの声を叫びを誰も聞く人がいなくなったとしたら、そこで世界は終わってしまうと思う。
だから私は読み続けるしかない。
明後日、2月24日でロシアのウクライナ侵攻から丸一年が経過する。
しかし、私はこの節目としての「一年」という言葉が嫌いだ。
同じく、8月15日に戦争を考えるということも嫌いだ。
何年続こうと、ある日「終戦です」と報じられようと、それは当事者たちにとっては区切りでもなんでもない。
戦いが終わっても、彼らの暮らしはそこで終わりではないから。
8月15日は始まりの日だと思っている。
この日と今は、一日も途切れることなく繋がっている。
だから私は読み続けるしかない。