
ハンナ・アレント『人間の条件』の言及されっぷりを眺めてみた #3
読みびとのまさきです。
ハンナ・アレントの『人間の条件』をテーマにしたこちらのシリーズ。まただいぶ間隔が空いてしまいましたが、なんとか11月中に書き上げたいと自分を奮い立たせ、最終回の#3をお届けしたいと思います。
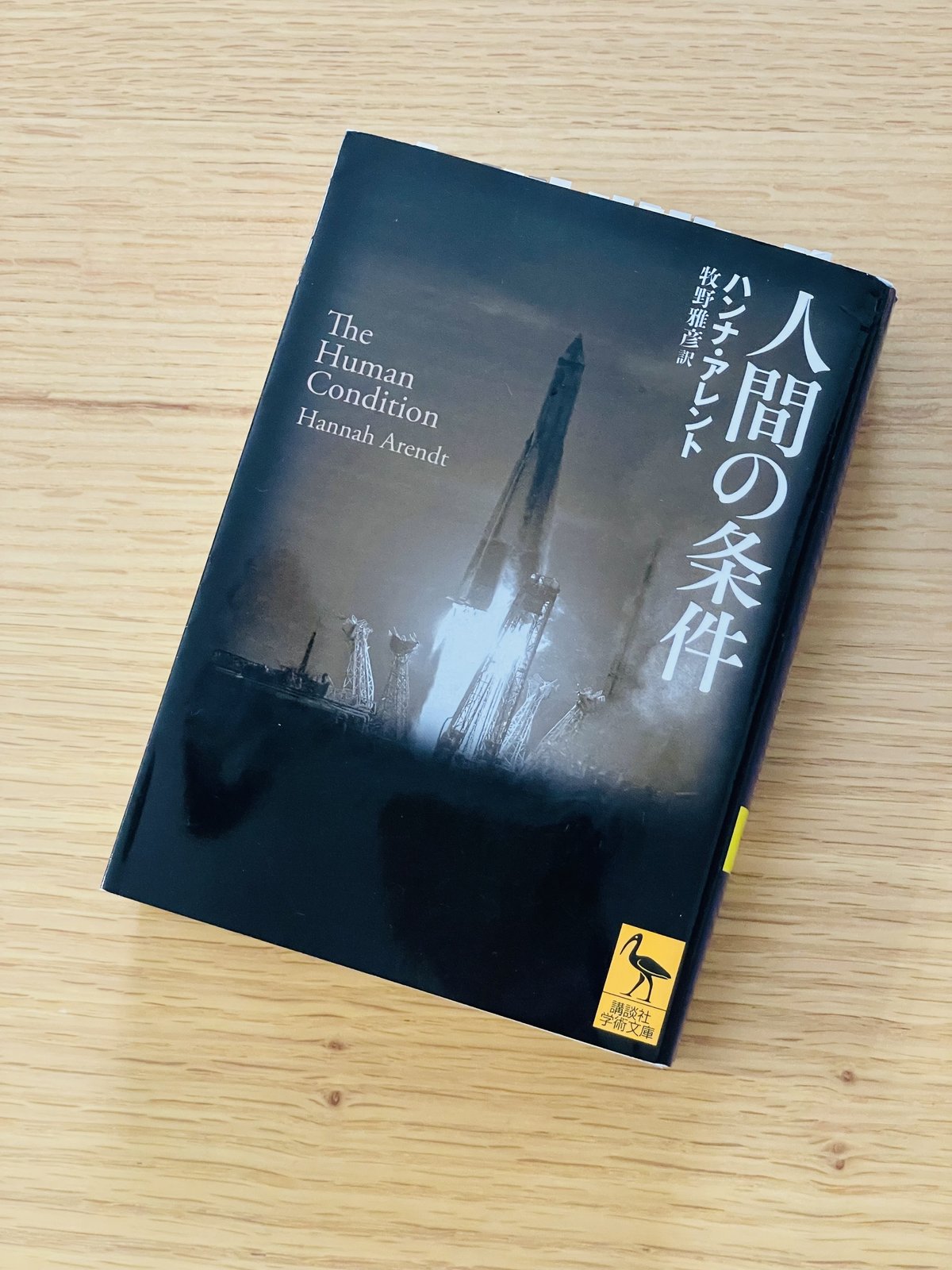
#1では、シリーズの書き出しと共に、國分功一郎さんの言及っぷりを眺めてみました。#2では、東浩紀さんの言及っぷりを眺め、その鋭さと深さを実感しました。
締めくくりとなる#3では、私が大好きな一冊、ジェニー・オデル『何もしない』での言及を概観したあと、自身の学びをまとめ、シリーズを閉じていきたいと思います。
◆ジェニー・オデル 『何もしない』と「出現の空間」
『人間の条件』をいつかちゃんと読みたいと思ったのは、ジェニー・オデル『何もしない』を読んだことがきっかけでした。

本の中で、アレントの考えとして「出現の空間」(『人間の条件』の訳本では「現れの空間」と訳されていることが多い)が紹介されており、この考え方にトキメキを感じずにはいられなかったのです。
ジェニー・オデルはアレントの思想をこのように紹介しています。
ソーシャルメディアには欠けているが、その後実際に人と会ったり、雑誌のようなより遅いメディアに接したりすれば見えてくるものが、ハンナ・アーレントが「出現の空間」と呼ぶものではないだろうか。アーレントにとって出現の空間とは、協力しあって意義ある行動や発言をする人たちの集合によって定義づけられる、デモクラシーの種となるものだ。
さらにオデルは主張を展開し、「出現の空間」のあるべき姿を指し示します。少し長いですが引用します。
その空間で私は見たり、聞いたりでき、また、その空間への投入度合いが同じ人たちから、見られ、聞かれる。得体の知れないツイッターの群衆とは違って、出現の空間は私の「理想のオーディエンス」だ。そこは私が話しかけられ、理解され、挑戦を受ける場所であり、そのためにその空間で私が言ったり、聞いたりすることに周知のコンテクストが与えられる。そのような遭遇の形態であれば、私も他の誰も、コンテクストを獲得したり、自分の発言を世論の最小公分母向けに包装し直したりするのに時間と労力を費やさなくてもいい。私たちは集まって、言いたいことを言いあい、行動に移すだけだ。
私はこの文章に、私たちが目指すべきコミュニティの姿がある気がしております。
これを読んで、「そう、こういうコミュニティが欲しいんだ、作りたいんだ」と思ったことをいまでもよく覚えており、ずっと自分の中で実現したいことの一つとして持っています。
私もいくつかのコミュニティに関わったり入ったりする中で、特に、「その空間への投入の度合いが同じ人たち」が集うことの重要性や、それによって生まれる「聞く・聞かれる」関係が、個に無理なく力を発揮させ、コミュニティをしなやかに育てることを実感しているからです。
この考え方の源泉が、ハンナ・アレントの『人間の条件』であることを知った時から、いつか読んでみようと心に決めたのです。
そして、この「出現の空間」について理解を深めるために、今度は『人間の条件』の該当箇所をを読み込んでみたいと思います。
まず、「出現の空間」を支える「権力」についてこのように書いてあります。
権力とは、公的空間、すなわち行為(=活動)し、語る人々が現れることができるような潜在的な空間を存在させ、持続させることのできる力である。
つまりここでも「持続性」が重要であることがわかります。いかに語り合いができる空間を持続可能なものにするか。そのために必要な力がある、それが「権力」であるとアレントは言うわけです。
権力と言うと、私なんかは、支配者のようなネガティブな印象を持ってしまうのですが、このように考えると、「権力」というのは、空間に集った人びとを包んでくれるような安心感のようなものであると言えそうです。
権力を生み出すために必要不可欠な物質的条件は、人々がともに生きることだけである。複数の人間が互いに近くに生活していて、行為(=活動)の潜在的可能性が常に存在しているところでのみ、権力は彼らとともに存続することができる。
目的のために、ただ集まろうとするのではなく、人が集まる中に潜在的に生まれる力が「権力」であり、それが暴力的な力になることを防ぎ、透明度の高い力としていかに守っていくか、そこが重要なのでしょう。
そして、「出現の空間」に身を置き、どこを目指すのか。アレントの考え方は次の一文に込められています。
普通に受け入れられているものを打破して尋常ならざるものに到達することにこそ、行為(=活動)というものの本質はある。
この一文は特に響きました。
「果たして、尋常ならざるものを為すことができるだろうか」と、つい力みがちにそう考えてしまいますが、まずは「出現の空間」に身を置き、自分の存在を確かなものにすることによってはじめて、「尋常ならざるもの」につながる何かが湧き起こるのだと思います。
そして、#2で取り上げた東浩紀さんが訂正してくれたように、「出現の空間」において、「活動」を支える開放性に加えて、「仕事」がもたらす持続性が必要であることも重要でしょう。自分が主に「仕事」と「活動」のどちらの役割を担っているときに自分らしさを感じるのか、改めて自分に問うていきたいです。
◆『人間の条件』のまとめ
ここまで、國分功一郎さん、東浩紀さん、そしてジェニー・オデルの3名の著作における『人間の条件』の言及っぷりを眺めてきました。
少し私なりに整理して、このシリーズを終えていきたいと思います。
『人間の条件』を初めて読んだときは、その重厚な内容に圧倒され、何をどう受け取っていいものか思考をまとめきれませんでしたが、こうして言及を眺めてきたことで、改めて受け取ったことは下記3点です。
「複数性」の概念は秀逸
「仕事」と「活動」はどちらも重要
「出現の空間」に身を置く
順番に見ていきたいと思います。
●複数性の概念は秀逸
「複数性」については、國分功一郎さんや東浩紀さんの言及で改めて理解を深めたところです。
なぜ政治が必要なのか。それは人と人がそれぞれ違うからです。当たり前のことですが、これをどれだけ意識できるかが日常で大きな違いを生み出すと感じます。
例えば、教育。
日本の義務教育は基本的には戦後に作られた仕組みです。その大きな特徴として、みんなで同じことを同じように学ぶ「学年学級制」があります。
私も当たり前のようにこの教育を受けてきましたが、ここに「複数性」の概念を入れると、もっと考えなければならないことが浮上してくるわけです。
そもそも、画一的に押し付けられる教育は、もうほぼ「労働」ですよね。授業の内容をどんな意味があるかもよくわからずにとにかく暗記して、いい点を取る。そんなことを小中高と続けていくわけです。もうこれは動物的な生、ゾーエーを送らされているようなもんです。
しかし、人間はそれぞれ違う。学びたい内容も理解する力も人それぞれなわけです。
その人間が集まって学ぶ意味とは何か。生きていくために必要な最低限の知識は何か。また個の特質に沿って進めていくべき内容は何か。そこをもっと突き詰めていかないと教育の未来はないのではないでしょうか。
このように教育だけでなく、ビジネスや地域コミュニティなど、いろいろな場面で、「複数性」を意識して、どんな共通理解を目指していくべきなのか、市民一人ひとりがどれだけ全体や公共に関心をもてるか、アレントに学ぶことはとても多いと感じます。
●「仕事」と「活動」はどちらも重要
『人間の条件』を読んで、浅い理解のままだと、とにかく「活動」が大事なんだという見解に落ち着いてしまうように思います。
しかし、東浩紀さんはこの考え方を丁寧に訂正してくれました。
アレントは、世界の持続を願ったわけです。その持続性を支えるのは、「仕事」による制作物です。
アレントは「労働」を否定しています。これはわかりやすいです。資本に働かされる人間の生を憂いているからこそ、「労働」ではなく「活動」を目指そうというわけです。
古代ギリシャに範を取る「活動」は、いわゆる政治参加を求めます。しかし、市民全員が政治を目指すというのはいささか強引ですし、そもそも不可能だと感じます。
そこで、「仕事」という役割があります。それは何かを残す(遺す)ということです。つまり「次世代への継承」ですね。
それは立派な町や建物など物理的な制作物でもいいですし、絵画や文学など芸術作品でもよい。また新しいサービスや仕組みといったソフトウェアでも良いわけです。
「労働」は自分の生存のために消費されるものを生産することですが、「仕事」は、世界の持続性のために自分が死んでも残るものを作ることです。
政治参加は難しくとも、子や孫が生きる世界が永遠であるように、今何を作り、残す(遺す)ことができるかを考えるのは、とても大切なのではないでしょうか。
●「出現の空間」に身を置く
ジェニー・オデルの『何もしない』の「出現の空間」の言及箇所を再読し、改めて、「出現の空間」に身を置く大切さを実感しました。
私は会社員を辞めて、フリーランス生活を始めて早5年にもなります。その間、孤独に1人で生きていたかというとそんなわけはなく、プロジェクトに加わったり、コミュニティを立ち上げたりもしています。
そして、今もなお、人が集って事をなすというのは、なかなかうまくいかないものだなと実感しています。
ジェニー・オデルの表現で刺さったのは、「空間への投入度合いが同じ人たちから、見られ、聞かれる」ことの大切さです。
投入度合いが同じになるようにコミュニティを築くのがとても難しい!
ただ、これが大切だと思うのです。そうじゃないと、私たちは常に周りの評価を気にしたり、誰かを操作しようとしたり、余計なことに時間と労力が割かれてしまいます。それでは、とてもじゃないけど大きな挑戦は果たせません。
だからこそ、自分の思いを素直に出せる空間、思いをお互いに承認し合える空間、そして失敗を恐れず挑戦を続けられる空間、そんなコミュニティに私も属したいですし、築いていきたいと思うのです。
以上、ハンナ・アレント『人間の条件』から受け取ったメッセージを私なりにまとめてみました。
こうしてみると、私たち日本人は、あまりにも受け身になりすぎていないでしょうか。アレントはそこに警鐘を鳴らしています。
それは戦後の社会がそうさせてきたのが大きいと思います。
「活動」や「仕事」にチャレンジにするには、知っておくべき教養が圧倒的に足りないのではないか、というのが私の認識です。
おそらくアレントの古典を読む人なんて、相当な物好きだと思います笑
高校生ぐらいでアレントを輪読して、どういう社会を築いていくべきかを対話する授業なんかがあってもいいと思いますし、大人こそアレントを読んで今の自分の働き方が、世界の持続に資するものになっているかどうか考える機会を作っても良いのではないかと感じます。
要するに、「みんなもっと本を読もうよ」というお誘いでこのテーマを締めたいと思います😄
長々とお付き合いいただき、ありがとうございました!
