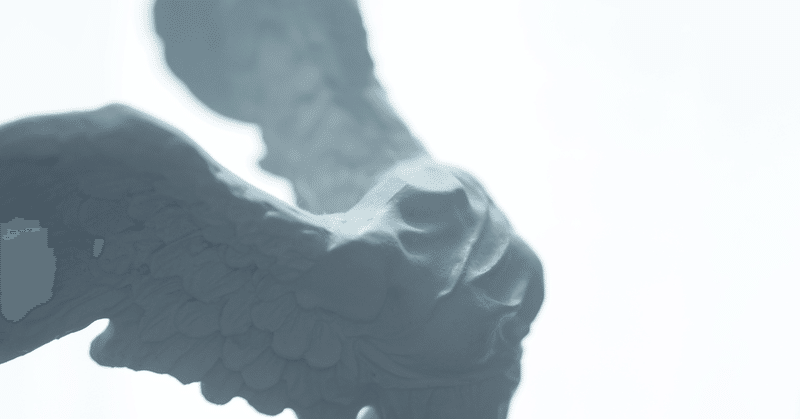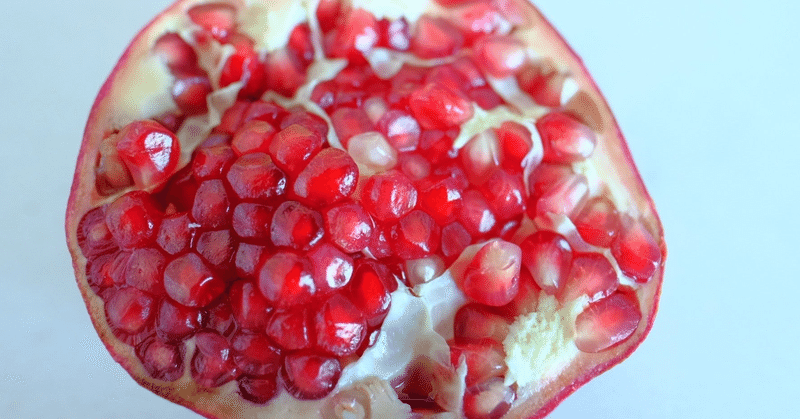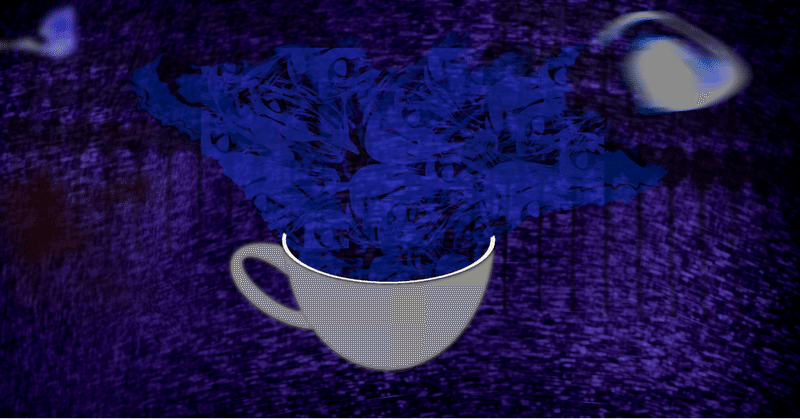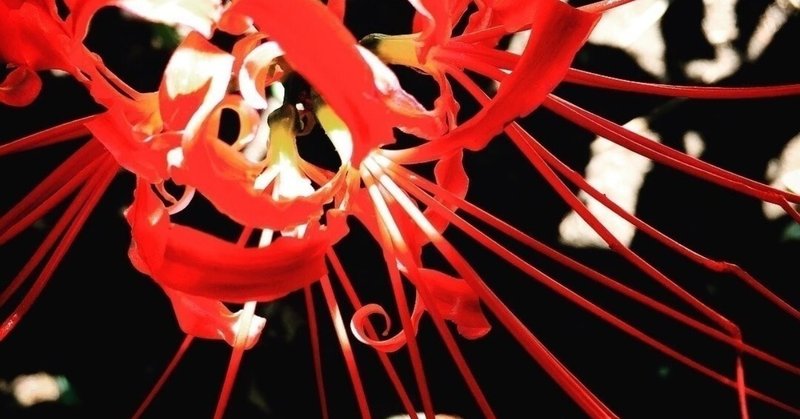#小説
「パープル・ヘイズ」の消えるとき
墓守からIDカードを受け取り、事務所を出た。朝から降り続いていた雨は勢いを増していた。会いに来ると、いつも雨なのは昔から変わらない。
休息日ということもあって、人影が広い墓場にまばらに見えた。花を供え、祈りをささげる人たちの前には空中に投影された故人のホログラムが浮かんでいる。それらは生前の記憶を再生する映像に過ぎないが、見る人を敬虔にする。ここに来れば、彼らに会えるのだ。
私は外套の襟を
掌編 「よもつへぐひ」
身体にはかみさんが宿っていて、切った爪のひとかけらだっておろそかにしちゃいかんのだって、ばあちゃんが言ってた。
出てきた鼻血を抑えながら、水道のとこに行くとイサナに見つかってしまった。
居ったん?
階段の上から見てたよ。
そいじゃなくて、兎。
冬の冷てえ水で手についた血を洗う。血がさっと溶けるみたいに流れていった。イサナは蛇口の上のコンクリに乗っかって、こっちを見下ろしながら、あんまし
「探偵(および真実)の不在」
書かれていないことは存在しないのなら、私はこう書かなければならない。
犯人は神崎である。
ここに死体がある。(ここ?)
神崎が見つけたとき、書斎は密室だった。(見つけたとき?)
新野の書斎には鍵がかかっていた。新野は机に突っ伏している状態で、ポケットには書斎の鍵が入っていた。書斎は部屋の壁一面を本棚で埋められており、窓はない。換気用のダクトがあり、扉のほかに出入りする場所はない。密室だ
掌編 「コーヒーが飲めない」
夢の中では、ハルおばさんは私と同い年の中学生だ。スカーフの曲がったセーラー服を着て、背中まである長い髪。髪は手入れをしていないからいつもボサボサ。綺麗な緋色の毛先は櫛を知らず、風も雨も枝葉だってくっつけて、ハルおばさんは無邪気に駆け回る。
犬か、こどもみたいに駆け回って、私を置いていくくせに、点みたいに遠くなるとこちらへ振り返って、大きく手を振る。
はやくおいで、ナズナ。
それでようやく、
掌編 「羽の機能について」
午前五時、目覚ましのアラームより先に目を覚ます。薄明の寝室に、時計の頭を叩いた音が歯痛のように響いた。シーツの衣擦れ、窓の外の鳥、そして耳鳴り。彼をそばやかす全ての音が神経に触れ、痺れる。
背後で寝息を立てる夫は、何時に帰ってきたのだろう。昨日、私がベッドに入ったのは午前一時だった。
青ざめた朝の光では、彼の顔色は判然としなかった。煮凝った夜気のゼラチンが、寝室を青く屈折させる。
寝室の扉
掌編 「あなたの物語」
その本は、ぼくが二番目に読んだ絵本でした。それは、朝焼けの空をことことと煮詰めたような、きれいな表紙の絵本でした。ぼくはその絵本が大好きで、絵本の端が、よれよれになって、擦り切れるまで、何度も何度も、読み返したものです。
だけど、その絵本には終わりがありませんでした。絵本の最期の頁《ページ》は、誰かに破り取られていたのです。
誰がこんなことをしたのだろう、と初めは思いました。けれど、今はそう
掌編 「pant-pant」
ブウウ――――――ンンン――――――ンンンと窓に取り付けた冷風機が唸る音で、俺は目を覚ました。冷風機が貴重な電力を音エネルギーに変換するために、部屋は涼しくならず、夏はいつまでも蒸し暑いままだった。
時計の針は夜中の二時を指している。腹にかけたタオルケットを剥ぐと、もわりと全身にかいた汗が臭いとなって、部屋に満ち満ちた。
ゴミ箱からは青臭い臭気が漂っている。獣臭さと言い換えてもいいかもしれな
掌編 「毒々しい金魚」
どん、と花火の音がして、ゆっくりと下りてきた緑の火花が落っこちた。お腹の底へ響く音がもう一度、どんと鳴ると、ガラスに入った氷がからんと高い音を立てて、崩れた。透明で、小さな氷山みたいな形をした氷の中に、今度は紫の火が灯って、サイダーみたいにぱちぱち弾けた。
ベランダへ落ちた花火の尻尾は、きらきらと風が泣くような声を出して、燃え尽きた。カーテンレールからぶら下がった、ハンガーには金魚柄の浴衣がか
掌編 「知的パラサイト」
それは、人類滅亡の合図だったのかもしれない。
ある日、あらゆる固定・携帯電話、スマートフォンに、世界同時に着信があった。発信元は不明。ただ、例外なしに、全人類へ着信が入った。
着信に出た人々は、ことごとく発狂した。運よく、電話に出られなかったか、あるいは、電話を取るのに遅れた人たちは、発狂し、暴徒と化した彼らの姿を見ることになった。
彼らは、口の端に泡を吹き、唐突に傍らにいる人間を襲った。
掌編 「ビルを喰うビルの街」
「このビルは、築何年でしたか?」
半袖のワイシャツを着た、クールビズルックの若者が、後ろを歩く腰の曲がった管理人へ振り向き、尋ねた。
髪の薄い老人は、わずかに白髪の残った頭を掻き、あー、と歯切れ悪く、言い淀んだ。それを見て、若者はすぐに付け加える。
「今、いる場所は、築何年のビルです?」
古ぼけたビルの通路は、かび臭い空気に満ちていた。ぼろぼろの内装は剥げかけており、指で触ると、荒い石の粒が
掌編 「こわれちゃった」
在原がマンションの中へ入った時、既に事は済んでいた。
「茜さん、またですか」
ワンルームのその部屋の、廊下には、点々と赤い血の跡が続き、廊下と部屋を隔てる扉のちょうど境の場所で、一人の男が倒れていた。
在原は土足のまま、部屋に上がり、スーツの内ポケットから、ビニールカバーを取り出して、靴にかぶせるように履かせた。
「茜さん?」
灯りの点いた部屋の方へ、彼は歩いていく。死におおせた男の死体を