
二十四節気の養生法【2025 小寒】
あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、1/5~1/19(大寒の前日)までの約2週間が小寒です。暦便覧には「冬至より一陽起こる故に陰気に逆らふ故、益々冷える也 」とあります。寒の入りで、立春の前日(節分)が寒の明け。この29日間が最も寒い時期ですが、三九天も今年は1/8~1/19でいよいよ寒さが厳しくなります。インフルエンザや風邪も流行っているようですので、くれぐれも風寒邪気に気をつけてお過ごしください。
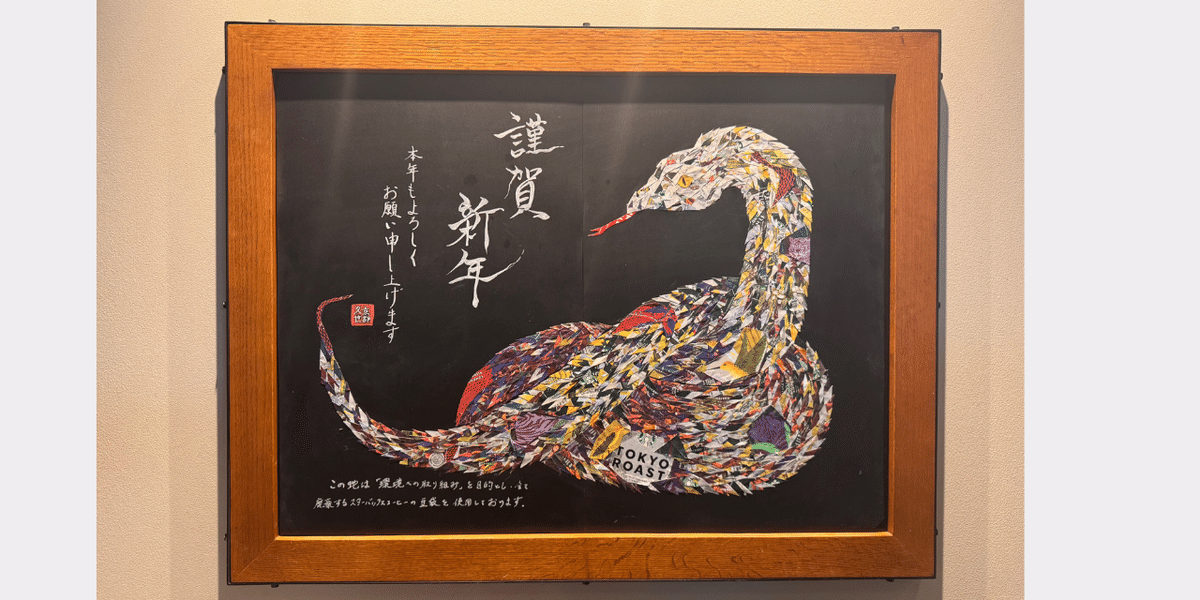
蛇の神様、三室戸寺 「宇賀神」の石像
今年は、乙巳歳ですね。宇治市の三室戸寺は巳(蛇)に縁のあるお寺とされ、普通は狛犬が祀られていますがこのお寺では本堂の前に狛蛇として体が蛇、頭が老翁で蓮に乗る姿をした「宇賀神」が祀られています。お寺に伝わる民話で、昔このあたりに蟹を助けた娘がいましたが、その父親が蛙を飲み込もうとしている蛇に娘を嫁にやるから蛙を放してやれと言って蛙を助けました。すると蛇が娘に嫁入りを迫りましたが、助けた蟹が蛇を退治したという伝承があり、この寺に娘が蛇の供養のために宇賀神の木像を奉納したと伝わります。木像は普段非公開ですが、お寺は狛蛇として宇賀神の石像を新設しました。蛇の尾には金運、翁のひげには健康長寿の御利益があるとされ、宇賀神は財運・金運の蛇神で、宇賀神を撫でると、財運(金運)・良運がつくといわれています。
こちらのお寺は花の寺として有名で、春はつつじやしゃくなげ、夏は紫陽花や蓮、また秋の紅葉も素晴らしいお寺です。ぜひまた花がきれいな頃にご案内したいと思います。日本には八百万の神様がいらっしゃいますが、本当にいろんな神様がいらっしゃるんですね。

私は今年も恒例の桃山御陵の明治天皇陵にお詣りしました。食っちゃ寝正月で運動不足を解消するためでもありますが、この石段は23段×10段の全部で230段有り、下から上まで上がると結構な運動になります。今年も途中休まず登り切れましたので安心しました。足腰や心肺機能のバロメーターに毎年登っています。

上まで登りきって振り返ると遠く宇治市内が一望に広がります。私がとても好きな景色のひとつで、この日も雲はありましたがお陽様が出てキラキラ光り穏やかなお天気で爽快な気分になりました。

そして、前方には明治天皇の陵墓があり、お正月三が日だけ柵が開けられ陵墓の目前まで行くことが許されます。白砂の上を歩いて陵墓に参詣しました。
この辺りは豊臣秀吉が建てた伏見城の敷地跡で、上の写真のあたりには昔は巨椋池という巨大な池が広がっていたそうです。
幕末の嘉永5年(1852年)に生まれ、寺田屋事件や鳥羽伏見の戦いなど坂本龍馬や幕末の志士たちが走った伏見に、幕末から文明開化の激動の明治時代を生きた明治天皇が眠っておられます。
また、歩いて5分ほどのところには平安京を開いたとされる桓武天皇柏原陵も祀られてあり、長い歴史の中でこの地に生まれて懸命に生きた人たちに思いが巡りますね。
2025年、人々が平安で穏やかな日々が過ごせますようお祈りいたしました。

小寒の養生法

暦って何…?
毎日、朝起きて今日は何日だっけ?何をする日だっけ?どこに行く日だっけ?なんて意識を呼び戻すのにひと苦労ですが、毎日毎日、当たり前のように今日が終わり、寝て起きたらまた明日が来ていますね。
では「暦」って何?誰がどうやって考えたの?って感じですが、どうも今のカレンダーでは季節感がピンときませんよね。今のカレンダーを基にしたいろいろな行事や「暦の上では○○」などと季節のことを言いますが、カレンダーの月日と合ってないような感じがしますね。今回は、このマガジンの名前自体を「二十四節気の養生法」としていますが、暦や旧暦、二十四節気などについて今さらながら考えてみたいと思います。
現代は毎日をグレゴリオ暦という暦(こよみ)で毎日を過ごしています。この暦は太陽暦を基にしており、1582年にローマ教皇グレゴリオ13世により導入されましたが、それまではユリウス暦が使われてきました。これはかの有名なローマの英雄ユリウス・カエサル(シーザー)がエジプトに遠征して紀元前45年にローマに持ち帰りました。エジプトでは毎年ナイル川の氾濫に悩まされていましたが、よくよく研究をすると毎年決まった時に氾濫することが分かってきました。さらに研究すると、朝、東の地平線から太陽が昇る直前におおいぬ座の一等星シリウスがヒライアカル・ライジングと言って太陽を伴って出る時があり、その約70日後にナイル川が氾濫することがわかり、さらに研究を続けると365日後にまた同じようにシリウスが太陽を伴って東の地平線から出ることが分かりました。これが地球が太陽の周りを一周する公転周期で、さらに研究を続けると365.25日という端数が出ることが分かり、4年に一度閏年を設けて調整されたそうです。2000年以上も前にそれが分かったっていうことがすごいですね!とても優秀な暦でそれ以来非常に長い間このユリウス暦が使われてきました。
ところが、実際に地球が太陽の周りを一周する公転の長さは、365.2425日だそうで、ユリウス暦(365.25日)だと1年で約11分長すぎることになるそうです。まぁ1年で11分ぐらいいいんじゃないと思いますが、400年ぐらいたつと3日ほどズレるそうで、ユリウス暦では春分の日を3/21と決め、キリスト教の復活祭は春分の日の後の最初の満月の後の日曜日と決められていましたが、カエサルがローマ帝国に持ち帰り採用してから1600年近くたった頃には春分が3/11ぐらいになり復活祭が出来なくなってしまったそうです。そのため1582年にローマ教皇により修正(ほぼ微調整)されたのがグレゴリオ暦で、これが今も使われている暦です。それにしても2000年以上も前にエジプトで作られた暦が、現代もほぼ原形で使われているって昔の人は本当にすごいですね!

太陰暦とは…?
一方、太陰暦は月の満ち欠けを基準とした暦で、新月(真っ暗闇)を1日(朔日=ついたち)とし、右側からだんだん光ってきて3日経つと右側が明るい三日月になり、さらに光る部分が大きくなって7~8日ごろに右半月になった時を上弦の月と言い、やがて14~15日には真ん丸い満月となり、徐々に右側から欠けてきて21~22日ごろに左半月になった時を下弦の月と言い、さらに欠けて左三日月になりやがて真っ暗闇の新月が訪れます。この月の満ち欠けの周期は29.5日で行われ、これをひと月と考え大の月を30日、小の月を29日として交互に組み合わせられました。カレンダーや時計が無かった時代に真っ暗が新月で1日、三日月が3日、満月が15日と暗い空の月の変化なので、誰にでもわかりやすいのが特徴で、この太陰暦はイスラム教ではヒジュラ暦と呼ばれ、現代も使われています。
また月の満ち欠けは、潮の干満にも大変影響しており、太陽と月と地球が一直線に並ぶ新月と満月は大潮、上弦、下限は小潮で、大潮の時は大漁になりやすいので漁師さんにとってはとても良い目安として活用されます。

では旧暦(太陰太陽暦)とは…?
しかしこの太陰暦も不都合なことがあり、29日を6回、30日を6回で合計すると354日となり、実際に地球が太陽の周りを一周すると365.2524日なので1年で11日(短く)ズレてしまいます。1年間だとたいしたことがないようですが、10年もすると110日(短く)ズレてしまい今以上に季節感とのズレが大きくなってしまいます。4か月近くもズレると暦では12月なのに、実際の気候は110日短い8月ごろの気候で、とても暑い12月ということになってしまいます。これでは漁師さんには都合が良くても、農家さんにはまったく使えない暦だということで、3年に1回閏月を設けて1年を13か月として調整しました。
…ここからが非常にわかりにくいポイントなんですが、その閏月はどうやって決まるのかと言いますと、二十四節気と太陰暦を組み合わせて決まります。
二十四節気は、太陽を観察してまず二至二分を見つけます。夏至、冬至、春分、秋分ですね。これは一年で一番昼が長い日が夏至で短い日が冬至、その中間点は春分と秋分で太陽は真東から出て真西に沈むので見つけられます。そして二至二分の中間点をそれぞれ立春、立夏、立秋、立冬として八等分します。こうして八節が完成します。

太陰暦の月の動きは12か月なので、太陽の動きも12に合わすと8の3倍なので一つを三等分すると8×3で24に分かれ、それに季節感のある名前を付けたのが二十四節気ということになります。太陽黄道で春分点を0度とし15度ずつ反時計周りします。二十四節気自体は太陽黄道を24等分して季節感のある名前を付けただけなので太陽暦とも言えます。

しかし地球が太陽を一周するのは平均365.24219日なのでやはりズレが生じます。この端数を4年に一度2月に1日増やして29日として調整されるのがいわゆる現在使われている閏年です。
そして太陰暦は、お月様の運行で一か月を決めますので、お月様の出ていない新月をその月の始まりの朔日(ついたち)とし、だいたい29.53日かけて満月になってまた新月に戻ります。二十四節気は月初めの節と月の中ごろの中気があり、次の月初めにまた節が来て中ごろに中気が来ます。そして二十四節気の中気と次の中気の間の平均は30.44日です。

そして、太陰太陽暦の決まり事として新月から次の新月までに含まれる中気によって名前が決められており、「雨水」という中気を含む月を「睦月」と言い現在の1月になります。次の「春分」という中気を含む月を「如月」という風に名前がついていくのですが、中気と中気の間が30.44日で新月と新月の間より長いため、微妙に中気が含まれない月が発生してしまうことがあります。この場合には前の月と同じ月の名前で閏一月や閏睦月、閏二月や閏如月など言って次の新月までを調整しました。ですので年によっては13か月あった年もあったのです。閏月は19年間で7回ぐらい、だいたい3年に1回ぐらいは起こったようで、3年に1度は13か月の年があったのです。
さらに、明治まで採用されていた天保暦では定気法が採用されており、これでは地球の公転が楕円形なので冬至のころは中気と中気の間が29.45日となり、新月と新月の間に中気が2つ含まれてしまうこともありました。そのため二至二分の2月、5月、8月、11月は固定し他の月で閏月を調整されていました。

このように、太陰太陽暦(旧暦)は基本的には月の満ち欠けによって一か月を決める太陰暦に、二十四節気の太陽暦を組み合わせて季節のズレを調整したもので、農暦とも言われ農作業のを行う目安としてとても有効に活用されてきたのです。そして、農作業以外にもそれに合わせていろいろな季節行事が行われるようになっていきました。
二十四節気とは…?
二十四節気は、今から3300年以上も前の紀元前1300年ごろの殷の時代には太陰太陽暦が使われていたことが甲骨文字の発見でわかっています。
二十四節気とは、太陽黄経0度を春分の日として起点とし地球から見た太陽の位置を角度で示したものを、その季節ごとに気候や自然現象などから季節をイメージしやすくわかりやすい名前を付けたもので、1か月に節気と中気が含まれ春夏秋冬の1つの季節を3か月とし、各季節に6つずつ配されます。現代私たちが使っているグレゴリオ暦(新暦)と太陰太陽暦(旧暦)では日付は異なりますが、地球から見た太陽の位置がこの角度を超えた時がそれぞれの節気になります。
太陰太陽暦での1月1日(春節)は、新月が朔日(ついたち)になるという決め事から、雨水の直前の新月の日が1月の最初の日(朔日)ということになり、毎年変わるのです。
天明八年(1788年)に出版された暦の解説書が「暦便覧」です。
春三月は立春から立夏の前日まで
立春 「春の気たつを以て也」
雨水 「陽気地上に発し、雪氷溶けて雨水となれば也」
驚蟄 「陽気地中にうごき、ちぢまる虫、穴をひらき出れば也」
春分 「日天の中を行て昼夜等分の時成也」
清明 「万物発して清浄明潔なれば、この芽はなにの草としれる也」
穀雨 「春雨降りて百穀を生化すれば也」
夏三月は立夏から立秋の前日まで
立夏 「夏のたつがゆえ也」
小満 「万物盈満すれば草木枝葉繁る」
芒種 「芒ある穀類、稼種する時なれば也」
夏至 「陽熱至極しまた日の長きのいたりたるを以て也」
小暑 「大暑来れる前なれば也」
大暑 「暑気いたりつまりたるゆへなれば也」
秋三月は立秋から立冬の前日まで
立秋 「初めて秋の気たつがゆへなれば也」
處暑 「陽気とどまりて、初めて退きやまんとすれば也」
白露 「陰気ようやく重なりて露こごりて白色となれば也」
秋分 「陰陽の中分なれば也」
寒露 「陰寒の気に合って、露結び凝らんとすれば也」
霜降 「つゆが陰気に結ばれて、霜となりて降るゆへ也」
冬三月は立冬から立春の前日まで
立冬 「冬の気立ち初めて、いよいよ冷ゆれば也」
小雪 「冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるがゆへ也」
大雪 「雪いよいよ降り重ねる折からなれば也」
冬至 「日南の限りを行て日の短きの至りなれば也」
小寒 「冬至より一陽起こるが故に陰気に逆らう故、益々冷ゆる也」
大寒 「冷ゆることの至りて甚だしきときなれば也」
中国から暦や二十四節気とともに伝わった生活の中での催事
五節供
人日の節供(1/7)古代中国では正月1日から鶏、狗(犬)、猪、羊、牛、馬順に今年一年の占いを立て、最後の7日に人の一年の運勢を占いました。
上巳の節供(3/3)桃の節句、ひな祭り、女の子の節供
端午の節供(5/5)菖蒲の節供、男の子の節供
七夕の節供(7/7)笹の節供、しちせき、
重陽の節供(9/9)菊の節供
の5つです。各節供については、その時期に改めて解説することにします。
五節供以外に雑節と呼ばれる暦日があります。暦が中国から伝わって以降に、日本の風土や文化に合わせて独自に追加され、中国にはない催事です。
土用 土旺用事の略で、立春・立夏・立秋・立冬の前18日間で、前の季節が終わり次の季節への変わり目となります。中国の古代思想五行説から来た考え方で、この期間は特に土の特性が強くなると考えます。
節分 節分はまさに季節の分かれ目で前の季節が終わる日です。ですから立春・立夏・立秋・立冬の前日すべてが節分なのですが、特に立春は1年の始まりとされるのでその前日は1年の終わりとして特に盛大に年越し行事として節分祭が行われるようになりました。
彼岸 春分の日と秋分の日をはさんだ前後3日間で合計7日間が彼岸になります。特に彼岸会と言われる仏教行事と結びつき、お墓参りをしたり先祖供養をする日として日本では定着しています。中国にはお彼岸という行事はないそうです。
社日 現代ではあまりなじみがなくなってきましたが、春分、秋分に最も近い戌の日で生まれた土地の産土神にお詣りする日とされ神社にお参りします。
八十八夜 立春から数えて88日目で「夏も近づく八十八夜」の童謡でご存じですね。例年5/1ごろで農作業の目安とされ、このころが最後の遅霜が降りるころとされます。
入梅 太陽黄経が60度となる日でだいたい6/10ごろで梅雨入りの目安の日です。日本は緯度が長いので地域による入梅時期はかなり差がありますね。
半夏生 太陽黄経が100度になる日でだいたい7/1ごろ。天地に邪気が満ち半夏という毒草が生ずる日と考えられ、昔は井戸に蓋をしたりこの日に収穫された野菜は食べないなどの風習があったそうです。半夏生までに田植えを終える農作業の目安の日とされ、またまただいたいの地域で梅雨明けごろとなり「半夏雨」と呼ばれる大雨洪水が起こりやすいころと考えられてきました。
二百十日、二百二十日 立春から数えて210日目と220日目、だいたい9/1ごろと9/11日ごろで、最も台風や嵐が襲来しやすいころとされ、農家や漁師の忌日とされてきました。
雑節についてもまたその時期が来たら改めて解説することにします。
今回は主に暦の部分が多くなってしまいました。もっと二十四節気の特徴や季節の行事、歳時記、言い伝えなども書きたかったのですが、非常に長くなってしまいます(それでなくても長いです)ので、また機会があればちょこちょこ書いていきたいと思います!
わかりやすく書きたいと思っていたのですが、やはり説明するのは難しいですね。
七草がゆ
まもなく1/7です。前回も書きましたが七草がゆと臘八粥を改めてご紹介します。今年は新暦の1/7と旧暦の12/8が同じ日になります。年末年始でお腹が疲れている人は、お好みのお粥でお腹を養生しましょう。
七草がゆは、せり、なずな、はこべ、はこぐさ、すずな、すずしろ、ほとけのざの春の七草を入れたお粥ですね。
七草がゆを食べるようになったのは室町時代あたりからだそうですが、七草囃子とともに邪気を追い払う行事として広まっていったそうです。
前日に七草を摘んで、神棚に供え7日の朝に七草囃子「七草なずな 唐土の鳥が 日本の土地に渡らぬ先に 七草なずな 手に摘み入れて ストトントントン」と唄いながら刻んでつくります。「唐土の鳥」は、中国の「 鬼車鳥(きしゃちょう)」と言われる頭が九つある奇怪な鳥で、夜になると飛び回り、人家に入ると凶事があり幼児に祟りをすると恐れられました。子どもが原因不明の病気になるのはこの鬼車鳥が空から邪気を落とすからだとされ、人日の節供のころに海を越えてやってくると恐れて、七草がゆを食べて邪気を追い払おうと考えたそうです。今ほど海外との交流が頻繁でなかったころは、疫病は海外から飛来する渡り鳥がもたらす、と考えられていたようで、疫病の禍を祓うために、祈りを込めて七草がゆを食べたのでしょうね。
七草がゆに入れる七草の性味と帰経、効能
[せり]
性味:涼、辛・甘、帰経:肺・肝・膀胱、効能:袪風湿、清熱、利湿、涼血止血、清胃滌熱、清熱解毒など
[なずな]
性味:涼、甘・淡、帰経:肝・脾、効能:涼肝止血、清熱利湿、清肺止咳、涼血止血、解毒、健脾胃・和中、平肝明目など
[はこべ]
性味:涼、微苦・甘、帰経:肝・大腸、効能:清熱解毒・消癰、清熱涼血、痔出血、清熱解暑、清肝瀉火、治肝積肥気、活血化瘀、補中益気など
[ははこぐさ]
性味:微寒、甘・淡、帰経:肺、効能:清熱、疏散風熱、去風明目、清肺止咳、止咳平喘、清熱利湿、清心安神、去風除湿、補血明目、平肝明目など
[すずな]
性味:平、辛・甘・苦、帰経:胃・肝、効能:消食導滞、下気寛中、行気除脹、通中益気、開胃、清熱解毒、解酒毒、利水解熱、清熱瀉火、散寒、温中益気など
[すずしろ]
性味:涼、辛・甘、帰経:脾・胃・肺・大腸、効能:清熱、清肺瀉熱、降逆下気、化痰熱、清熱解毒、行風気、涼血止血、清熱生津、消食導滞など
[ほとけのざ]
性味:平、苦、帰経:肺・胃・肝、効能:清熱解毒、消癰解毒、咽頭炎、乳腺炎、下血、発表透疹など
ご覧の通り七草のどの性質も平か寒涼ですね。温める物は一つもありません。つまり飲み過ぎ食べ過ぎで胃熱が溜まっているのを冷まして、消化を促進させる食材ばかりです。

臘八節(ラォバァジェ)
一方、台湾や中国など中華圏では、旧暦12/8(今年は1/7で偶然にも七草粥と同じ日ですね)は臘八節(ろうはちせつ)と言われるお祝いの日で、お釈迦様が悟りを開く前にあまりの苦行で死にそうになった時スジャータという娘が捧げた乳糜(ミルク粥)で体力が回復し、旧暦12/8に菩提樹の下で悟りを開いたということから、この日を「佛陀成道紀念日」や「法宝節」というようになり、お寺ではこの日を祝うため臘八粥(八寶粥)をお供えされ、参拝者にも臘八粥が振舞われ、この日を過ぎるといよいよ春節を迎える準備をはじめる大切な日だそうです。
一年で一番寒いこの時期にいただく臘八粥 (ろうはちがゆ)には、もち米、はと麦、緑豆、小豆、栗、ヤマ芋、ナツメ、蓮の実、百合、白きくらげ、竜眼、クルミ、氷砂糖などを入れて食べるそうです。
日本でも中国でも長い歴史に培われた食文化や伝統食がありますね。
八寶粥の作り方♪
材料(1人〜2人前)
小豆 50g
はと麦 50g
玄米 30g
蓮の実、枸杞の実、なつめ、黒豆など 適量
砂糖 50g
水 600cc
1.はと麦は硬い為事前に水をつけておきます。
2.あずきは、お鍋にたっぷりの水を入れ中火で一度沸騰させ、ザルに一度上げます。
3.”2”をまた鍋に戻しはと麦・玄米・水600ccを入れます。
4."3"に蓋をし中火でかけ、沸騰したら弱火にして50分ほど茹でます
5.50分後は火を止め砂糖を溶かして完成♪
八寶粥は中に入れるものに決まりはないので、お好みで白きくらげや緑豆などを入れてもいいですね♪

さて、今年は日本式の七草がゆか中華式の臘八粥(八寶粥)かどちらにしましょうか?
京都伝統中医学研究所の"小寒”におすすめの薬膳茶&薬膳食材"
1.「温陽補腎」の薬膳茶&食材
温陽を補い気血を巡らせるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、
薬膳茶では、からだを温める黒のお茶、なつめと生姜のチャイ、黒薔薇茶、気血巡茶など。
薬膳食材では、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、蓮の実、松の実、マイカイ花、桂花、茉莉花、紅花など。
薬膳火鍋紅白スープセット、手足冰凍鍋セット、冬の美薬膳鍋セット、四物鍋スープセットは、薬膳食材もセットになっているのでオススメです。
腎を補い働きを高めるオススメの薬膳茶&薬膳食材は、
薬膳茶では、肝腎かなめ茶、なつめ薬膳茶、なつめ竜眼茶、からだを温める黒のお茶など。
薬膳食材では、黒きくらげ、新彊なつめ、枸杞の実、竜眼、金針菜、紅花、マイカイ花など。
2.いろいろお豆のお汁粉セット…をお粥に!
薬膳スィーツ「いろいろお豆のお汁粉セット」の中身は「小豆・緑豆・金時豆・蓮の実・黒豆」の五種の豆類です。木火土金水の五色をバランスよく配合して五行周流。ココナツミルクで味付けて東南アジア風のスィーツとして人気がありますが、この季節はこれをそのまま「いろいろお豆のお粥」にもアレンジするのがオススメです。年末年始に飲み過ぎ食べ過ぎたという方は、ぜひお試しください。お腹の調子がグッと楽になりますよ。お好みで百合やヤマ芋、白きくらげなどを加えてもOK。
3.漢方入浴剤 ヨモギがたっぷり入った「ポカポカあたため乃湯」
この季節の養生にオススメの漢方入浴剤。ヨモギの香りが浴室いっぱいに広がり、香りに癒され芳香浴の効果も抜群です。ヨモギは昔から「婦人科の要薬」として血の道証改善に使われてきました。
中医学や薬膳の知恵を毎日のくらしに活かして、体質改善や病気の予防に役立てて下さい。
薬膳茶や薬膳食材などの商品は下記各ショップでお買い求めいただけます。
■薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店公式オンラインショップ
国際中医師がオリジナルブレンドした季節の薬膳茶や、厳選した安心安全の薬膳食材を専門に扱っています。ぜひご利用ください。
薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂公式オンラインショップ
特別プレゼント
「貴女の星の運勢先読み通信」無料プレゼント

ただいま薬膳茶&薬膳食材専門店 京都 楽楽堂 本店オンラインショップのLINE公式アカウントにお友達登録いただいた方で、ご希望者に彦阪泥舟社中と共同企画「貴女の星の運勢先読み通信」を無料でプレゼント。ご希望の方はLINEお友達登録の上、生年月日を記入してお申し込みください。
1月は、2025年一年間の貴女の本命星の運勢と中医学的養生法になります。今年も健やかに過ごすヒントを記載したPDFファイルをLINEでお届けします。
※継続配信は京都 楽楽堂本店のみのプレゼント企画です。下記QRコードを読み込んでお友達登録の上、生年月日と先読み通信配信希望と書いて送信してお申し込みください。

その他のオンラインショップ
■京都伝統中医学研究所 楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/iktcm/
■京都伝統中医学研究所 ヤフー店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/iktcm/
次回は、1月20日「大寒」ですね。一年で最も寒い三九天は1/8~1/16までです。しっかり温補腎陽の養生法でカラダを守ってください。
