
『個別最適な学びの足場を組む。』
タイトルを見て「どうせ流行り言葉(バズ・ワード)なんでしょ」「協働的な活動のほうが大事に決まってる」なんてご意見が聞こえてきそうです。
ましてや、帯に「みんな一緒、を手放す」なんて(編集者が)つけたもんだから「学校教育制度を否定する気か!」とお叱りを受けないかビクビクしながらも、やっぱり外せないキーワードだと考えてドカンと目に入るように大きく置いたわけです。
実は「どうせ流行り言葉(バズ・ワード)なんでしょ」に対する回答は、たしかに言葉としては新しいものですが、概念としては寺子屋や家庭教師以来の自然発生的で素朴な子育ての延長線上にあるものなんです。
「協働的な活動のほうが大事に決まってる」については、協働的な活動に力を入れている伝統校も「個」を非常に大切にしていたりします。
ここまではまあいいとして、なぜ「みんな一緒、を手放す」のか。やや説明が長くなりますが、おつき合いいただきたく。
日本の学校は、学習指導要領で定められた目標を達成するために必要な内容を、子どもたち全員に教えないといけません。それが子どもたちの社会を生き抜く力になると、限られた期間内に「教える」という使命を果たすには一斉画一的な(それも平均点周辺に合わせた)教育が効率がよいわけです。
一方で、学びの個性はみな違っていますから、本当に一人ひとりが生き抜く力を「身につける」ためには、それぞれの違いに合った「個別最適な学び」の視点がもっと必要になってきます。
多くの先生方は、その必要性をわかっていながらも、さまざまな制約があって極めてむずかしいと感じてるのではないでしょうか?
しかし歴史をたどれば、学校教育の限界に立ち向かっていく豊富な実践(「一人ひとりに合った教材・学習時間・方法などの柔軟な提供」と「自分の最適な学びを自力で計画・実行できる子どもの育成」)と、それを支える教育論がすでに存在してたことに気づきます。
本書は、そんな「個別最適な学びがむずかしい」と感じる先生方の疑問をとりあげ、著者が歴史的な理論や実践をもとに応えていくかたちで、読者が著者と対話しながら個別最適な学びに関する理解を深め、具体的な手立てにつなげられるような示唆を得ることのできる構成となっています。
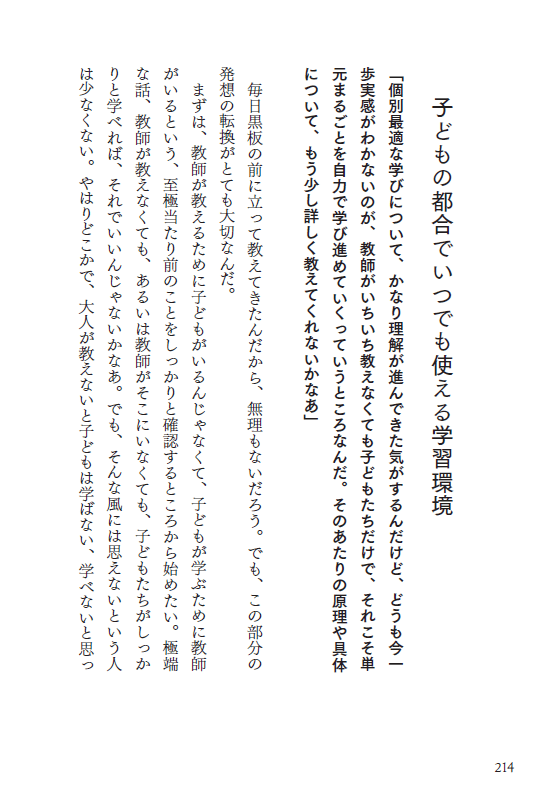
いま、国が主導するGIGAスクール構想によって学校に1人1台端末が整備され、個別最適な学びを進める追い風が吹いてるのは周知の事実です。
また世界的には、多様性を受け入れる包摂的な社会が目指されており、画一性を過度に要求されることとは逆行しています。
行き過ぎた一斉画一的な教育は同調圧力をもたらし、子どもたちの生きづらさをも生み出しかねない……そんな同調圧力の負の側面を解消するためにも個別最適な学びの視点は必要ですし、一人ひとりの違いが育つことでこそ、多様な他社と交わったときに新たな知恵が生まれるのではないでしょうか。
つまり個別最適な学びは、けっして協働的な活動を否定するものではありません! 冒頭のお叱りがあるとすれば、この点への引っ掛かりがあるのではないかと推測します。
すべての子どもは有能な学び手であり、適切な環境さえあれば、自ら環境にかかわり学んでいくものだと、著者は言います。そして自ら学び進めるたくましさが育つと、協働的な活動もいっそう活性化するようになるんです。
求められているのは、一人ひとりの背中をそっと押すこと。そのために、偏った「みんな一緒」を思い切って手放してみること。
そんな教育の転換点にあることを、個別最適な学びを切り口に、みんなで語り合ってみませんか? という思いでできた、帯のコピーでした。
この本は日本の教育の未来を、子ども「たち」のための教育から子ども「一人ひとり」のための教育に解像度をあげていくことができると思います。
学校の先生向けですが、教育に関心のある方全員に手にとっていただければうれしいです(少々むずかしい内容もありますが、やさしい語り口で写真もたくさんあり、読みやすいですよ!)。
も く じ
プロローグ
第1章 「令和の日本型学校教育」と個別最適な学び
百年以上の蓄積と今日的な意義を踏まえる
学習指導要領の着実な実施のための見直し
2017年版学習指導要領が目指す「学びの転換」
コロナショックで明らかになった課題
社会のあり方そのものの急激な変化
GIGAスクール構想と「未来の教室」
「個に応じた指導」を学習者視点から整理した概念
第2章 近代学校の特質と個別最適な学びの源流伝統的な子育ての習俗
欧米からの直輸入品
雀の学校
等級制から学年制へ
多様な形態の共存
モデルとしての軍隊と工場
新教育運動の二つの原理
特設学習時間
相補的で相互促進的な関係性
公開授業の不思議
第3章 学習研究の進展と個別最適な学び
みんな違って、みんないい
ティーチング・マシン
オペラント条件づけの原理を主体として飼いならす
知的CAI
AIドリル
テクノロジーの限界と教師の専門性
マスタリー・ラーニング
形成的評価と総括的評価の区別
ATI
教育を問い直す視点としてのATI的発想
第4章 指導の個別化と学習の個性化
はじまりは1971年
指導の個別化
学習の個性化
愛知県東浦町立緒川小学校の取り組み
はげみ学習
週間プログラムによる学習
オープン・タイム
バランスのとれたカラフルなカリキュラム
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する二つの行き方
第5章 学び方の得意と自己決定的学習
学ぶ領域の得意と学び方の得意
『大造じいさんとカルガモ』
そこを起点に伸びていく
学習における自己決定の充実
学習者の視点からの総点検
「個別最適化された学び」から「個別最適な学び」へ
順序選択学習
課題選択学習
課題設定学習
共通に学ぶべき内容における学習の個性化
履修主義と修得主義
単元内自由進度学習における速い子への対応
第6章 環境による教育と学習環境整備
子どもの都合でいつでも使える学習環境
すべての子どもは有能な学び手
指示や説明を文字情報でまとめて提供する
文脈情報の重要性
ICTの普及で一変した学習材の収集と提供
心ゆくまで見られる、触れられる環境整備
活動・体験コーナーの設置
マルチに機能する掲示
ティーチャー・プルーフ・カリキュラム
第7章 未来に向けて
最新のものより確実なものを
国内におけるその後の展開
海外の動向
あらためて2017年版学習指導要領と個別最適な学び
エピローグ
小社オンラインショップでもご購入いただけます
