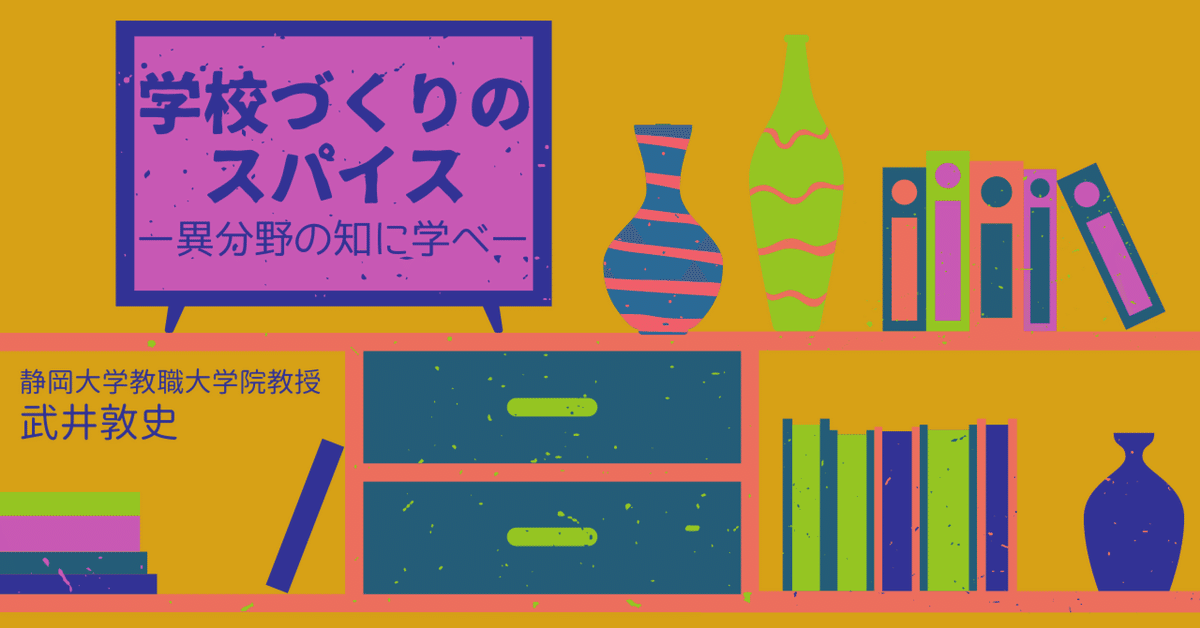
#43「複式簿記」思考を身につけよう~ 近藤哲朗ほか『「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図』より~|学校づくりのスパイス
ドイツの詩人ゲーテの文学作品に次のような一節が出てきます。
「複式簿記が商人にあたえてくれる利益は計り知れないほどだ。人間の精神が産んだ最高の発明の一つだね。立派な経営者は誰でも、経営に複式簿記を取り入れるべきなんだ」(ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代〈上〉』岩波書店、54 頁)。
複式簿記を学ぶ意義のある点については、学校経営者もその例外ではない、というのが今回の連載の結論です。今回は近藤哲朗、沖山誠、岩谷誠治『「お金の流れ」がたった1つの図法でぜんぶわかる 会計の地図』(ダイヤモンド社、2021年)を手がかりに、学校のマネジメントにも「複式簿記」の思考法を取り入れる必要について考えてみたいと思います。
複式簿記の考え方
大学教員は教育・研究のほかに、各種執筆活動や、講演・研修など活動の場が多岐にわたることが少なくありません。筆者も類例に漏れず、数年前から複式簿記で帳簿をつける羽目になったのですが、最初はよく分からないまま入門書をめくっていました。今でも年度末には、毎年「えーとこの勘定科目は何だったっけ」と思い出しながら会計ソフトの助けを借りてなんとか申告書を作成しています。
ところがこの本は圧倒的にわかりやすいのです。大学の事務室に書類不備でしょっちゅう叱られている事務オンチの筆者ですが、この本の説明はストンと腹に落ちます。しかも説明に際して使用しているのは、会計の解説書でよく使われる一枚の基本的な図だけです。
この本の説明(29~38頁)をもとに、会計の考え方を筆者なりに咀嚼したうえで、学校経営にも発想を対応させて説明してみましょう。下の図を見ながら読んでください。

まず、①出資金など組織に蓄えられているお金(「純資産」)と借りたお金(「負債」)が「資本」(事業の元手)になります。学校で言えば、教職員や教材、各種設備などが「純資産」に、学校外から得られた資源にあたる地域住民による活動支援などが「負債」に相当するでしょう。
そして企業はその資本を元手に商品・サービスをつくり「売上」を得ます(③)。このとき売上を得るのにかかったコストが「費用」(②)になります。学校なら費用にあたるのが教育活動に投入した時間や労力等のインプット、売上にあたるのが児童・生徒の学力向上等のアウトプットになります。
費用に対してより多くの売上を達成できれば、その分が利益となり次年度の純資産を増加させます(④)。逆に費用より売上が少なければ利益はマイナス(赤字)になり純資産を減らします(⑤)。学校で言えば通常の教育活動+αの効果(後述)です。
「資本」と「費用」の合計は「負債」「純資産」「売上」の合計に常に一致します。利益が上がって純資産が増えれば資本も増加して、次年度はより大きな推進力で事業を展開できるようになることを意味します。

+αが「資本」に替わる
このように会計のメタファーを使って教育を語ろうとすると、「学校の教育活動は会計のように数値化できるものばかりではない」というお叱りがすぐにでも聞こえてきそうです。そして確かにそのとおりなのですが、この思考法を身につけておくと、学校の経営もより明瞭に見えてくることがあります。
一例をあげましょう。2022年4月から「授業時数特例校」制度が導入されています。これは、ICTを活用するなどして学習指導要領の内容を適切に盛り込むこと等を条件に、学年ごとの各教科の標準授業時数を1割まで減らして教育課程を編成し、その分を教科等横断的な学習活動等に充てられるというものです。
たとえばオンライン講義やAIドリル等を用いて、従前の教育活動を実施するのに必要な組織コスト(費用)を削ることができれば、それによって利益に相当する「+αの効果」(たとえば教員のICT活用スキルやプロジェクト型学習のノウハウ)を高めることができます。そしてこれが次年度には学校の「資本」を増加させて、その分だけ教育活動へのインプットをさらに拡大させる余裕が生まれます。
このスキームをうまく活用できた自治体では、カリキュラムに余裕が生まれて次世代型の学習を進めることが可能になります。さらにノウハウも蓄積され働き方改革も進んで、教職員の意欲も高まり教員採用にも有利になるかもしれません。
ちなみに2022年度には、すでに18件28校がこの精度の導入を開始しています。
つまりこれは高利回りの預金のようなものです。だからこの仕組みをうまく使った学校(自治体)とそうでないところの間で格差が生じ、その格差が雪だるま式に拡大していくことも起こり得ます。一方で、様子見を決め込んで出遅れた自治体では収益体質は変わりません。
こうしたメカニズムは、費用と効果とを単純に比べる発想のみからでは、なかなか見えてはこないでしょう。
この本のおわりには本を著した動機について次のように語られています。「会計はあくまでレンズだ。その先に見ようとするものがなければ、意味をなさない。自分と社会のつながりを会計を通じてイメージできると、今よりも社会に対する解像度が上がり、自分がこれから何をすべきなのかが、少しずつ見えてくるはずだ」(196頁)。
学校教育を見るのにも、もちろんいろいろなレンズがあります。学校の中で仕事をしていると通常は教育の中身だけに視線が集まってしまいがちですが、時にはこのようにして、教育の資源とサービスの関係も俯瞰してみるとおもしろいのではないでしょうか。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
