
#23 アニミズムの復権~宇根豊『農本主義のすすめ』より~|学校づくりのスパイス
前回は、今後の世界の変化のなかで、大多数の個人が社会のなかでの経済的・軍事的有用性を失う一方で、個々の人間は主観的幸福感を求める傾向が強まるであろう、というハラリ氏の未来予測を紹介しました。今回は宇根豊氏の『農本主義のすすめ』(筑摩書房、2016年)をもとに、教育と「幸福」の関係について考えてみたいと思います。地方に移住して農業を志す若者が増えているというニュースを最近よく目にするようになりましたが、そうしたトレンドの背後にある人生観を考えるうえでも本書の提示する視点は示唆に富むものです。
「諸刃の剣」としての幸福追求
公教育の目標を表すキーワードとして、「成功」(success)に代わり「幸福」(well-being)が近年より頻繁に用いられるようになってきました。下の図は「OECD生徒の学習到達度調査」の報告書の表紙ですが、2015年からは生徒の「幸福度」の視点がとくに強調されるようになりました。この報告書のなかでは「近年、健康で豊かな人生を送るためには、収入や社会的地位といった社会経済的なアウトカムだけでは不十分であるという人々の認識の高まりが背景にはある」と指摘されています。

社会経済的成功から個人的幸福へとシフトする方向性は基本的にポジティブな変化であると筆者は考えます。近代学校という社会装置は産業社会のために発明され発展してきた制度ですが、人間は産業のために生きているわけではなく、人がよりよく生きるためにこそ教育を充実させたいと多くの人は考えているはずだからです。
けれども筆者は一方で、この方向性に手放しで賛同する気にもなれません。人間の幸福は社会が一方的に定義するものではないかもしれませんが、単に人が主観的に幸福と感じさえすればよい、というものでもないように思うからです。幸福感だけなら、教育のような骨の折れる作業を経ずとも、薬物投与やホルモン注射によってずっと簡単に達成されうるはずです。イギリスに「満足な豚より不満足なソクラテス」という格言がありますが、人間の幸福にとっては、その「深さ」が大切であり、深い幸福のためには現象の背後にある「何か」を想わずにはいられないのが人間ではないでしょうか?
この問題を「農」というテーマを題材に深く掘り下げて考えているのが、今回の宇根氏の著作です。宇根氏は本書では自身を「百姓」と称していますが、その教養の深さと透徹した論理性は秀逸というほかありません。
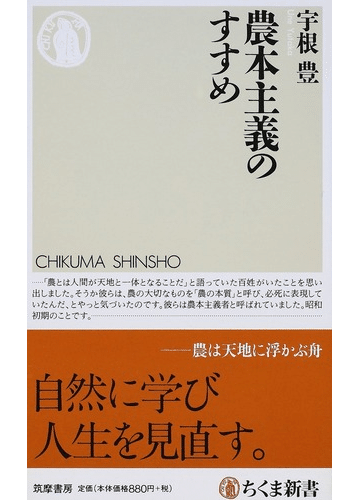
農本主義の視点
著作タイトルの「農本主義」とは、言うまでもなく「資本主義」との対比で用いられている言葉です。資本主義は世界の事物の価値を経済的価値に置き換えて人が所有することによって成立しています。だから資本主義だけを突き詰めていくと、世の中の価値をことごとく量化して、これを増大させ続けなければ社会が立ち行かなくなってしまいます。
これに対してこの本で語られている「農本主義」の考え方は、「農業を農に戻していくこと」(36頁)であると端的に語られています。いわゆる「農業」とは経済活動の手段として資本主義の一部として農作物を生産する働きのことですが、これに対して「農」は「農地(大地)を通して、天地自然に働きかけて、めぐみをいただくこと」(同)ととらえられています。この感覚を基礎に置いてみると「百姓の内からのまなざしでは、経済価値でははかれないものが世界の大半を占めるのに、なぜ農を『経済』で取り扱う風潮ばかりが強くなるのか」(88頁)と違和感が生じるといいます。
もちろん「農」もありのままの自然に手を加えることであり、人間の働きかけのなかには草木や虫などの生物を殺すことも含まれます。けれどもそうした命のやりとりも含めて「天地の中の生きものの生死は、天地の采配による自然な現象」(173頁)であるととらえるのが農本主義の発想のようです。
経済価値を基本尺度にして物事を測定し、所有して増やそうとするのではなく、人間を含めた生物はより大きな命(宇根氏はこれを「天地有情の共同体」と呼んでいます)の一部であり、そうした大きな命から自分の命も与えられているものなのだ、という「贈与」の感覚を基礎において世界をとらえ直そう、という考え方が農本主義の根底にはあるようです。
宇根氏は「天地自然の力を科学的に分析するのではなく、人知ではとらえられない『霊力』だと感じることも大切ではないでしょうか」(172頁)と語っていますが、こうした農本主義の考え方を一種のアニミズム(精霊信仰)であると片づけることは簡単です。
けれども農本主義をアニミズムというなら、人が「他人にも心がある」と考えることだって一種のアニミズムであることは否定できないはずです。私たちは自分だけでなく他人にも心があると信じていますが、他人の心の存在は、私たちにとって直接経験することも証明することもできないものだからです。逆に他人に心があると私たちが信じられるならば、それを他の動植物に拡大できない理由はありません。
身体を使う仕事を通じて個人の認知を超えた命の存在に触れようとする農本主義の価値観は、きっと多くの人の人生観を、より温かいものにするのではないでしょうか。そしてこの方向性は、芸術にも、ものづくりにも、そして教育という営みにも通底するものなのではないかと筆者は考えています。ハリウッド映画の「アバター」に象徴的に描かれているように、人の存在価値が有用性の次元でリスクにさらされている今日であるからこそ、命の存在をもとめる動きは、社会のさまざまな分野で今後さらに強まっていくはずです。
【Tips】
▼宇根氏は『うねゆたかの田んぼの絵本』という子ども向けの絵本も出しています。
(本稿は2018年度より雑誌『教職研修』誌上で連載された、同名の連載記事を一部加筆修正したものです。)
【著者経歴】
武井敦史(たけい・あつし) 静岡大学教職大学院教授。仕事では主に現職教員のリーダーシップ開発に取り組む。博士(教育学)。専門は教育経営学。日本学術研究会特別研究員、兵庫教育大学准教授、米国サンディエゴ大学、リッチモンド大学客員研究員等を経て現職。著書に『「ならず者」が学校を変える――場を活かした学校づくりのすすめ』(教育開発研究所、2017年)、『地場教育――此処から未来へ』(静岡新聞社、2021年)ほか多数。月刊『教職研修』では2013年度より連載を継続中。
