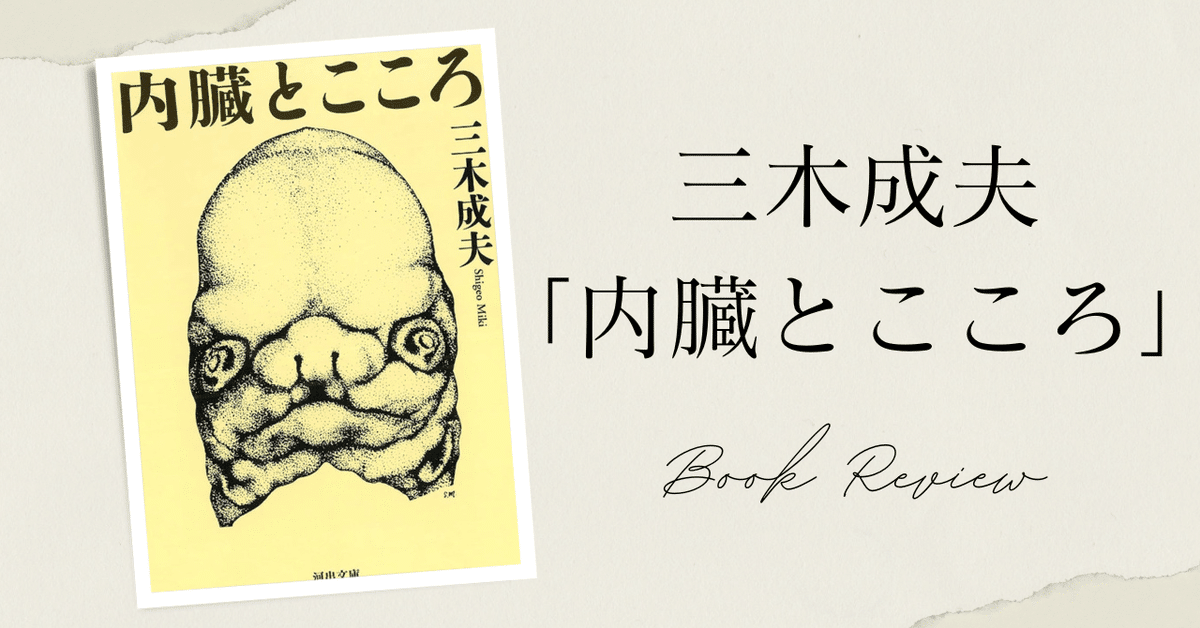
宇宙はわたしたちのからだのなかにある|【書評】三木成夫「内臓とこころ」
わたしの妻は、現在、妊娠6か月目を迎えたところなのですが、先日の妊婦健診ではじめて、「4Dエコー」なるものを使うことになりました。健診が終わったあと、わたしも、そのエコー写真をみせてもらいました。ところが、です。
これが、なんと形容したらよいものか。その写真をみても、いったい、どこが目でどこが口なのか(そもそもどこが顔なのか)、どこからが手でどこからが胴体なのか、まったく判別がつかないのです。

まるで無造作にこねくりまわされた粘土か何かのような、ボコボコとしたピンク色のかたまりがそこには写しだされ、しかしそれでいて、ふしぎな生命感をたたえている。妻もお医者さんのまえで、おもわず「グロいですね!」と漏らしてしまったということです。
ともあれ、来たるべき生命の誕生にむかって、日々、発見をあらたにしている夫婦ではあるのですが、ちょうどそんなおり、noteの読書感想コンテスト「#読書の秋2022」の推薦図書のなかに、ひときわ目をひく一冊をみつけたのでした。
それが本書「内臓とこころ」です。
お世辞にも「かわいい」とはいえない(むしろある種の「グロさ」を感じさせる)表紙をしているこの本は、どうやら、子どもの発育過程とこころの形成について書かれている(らしい)。
これまた、来るべき生命の誕生にそなえて、一読しておくにしくはなさそうだ……ということで、このたびの読書感想コンテストを奇貨として、手にとってみたというしだいでありました。

本書の著者は、解剖学者である三木成夫(1925-1987)。講演録にして処女作という、一風変わった一冊です。
本書を読み進めるにあたっては、まずふたつの用語をおさえておく必要があります。それが「体壁系」と「内臓系」。
解剖学の「か」の字もわからないわたしには、これらの用語さえ初耳なのですが、「体壁系」は、「手足や脳」といった感覚や運動にたずさわる器官をさしており、いっぽうの「内臓系」は、まさにからだの「内部に蔵された」器官、すなわち「はらわた」の部分にあたるとのこと。
そうして筆者は「内臓の復興」を訴えながら、「内臓感覚のなりたち」「内臓とこころ」「こころの形成」といったむずかしそうなテーマについて、快刀乱麻を断つごとく、あざやかに論を展開していくのです。
さて、ここであらためて、いま申しました「体壁系」と「内臓系」のそもそもの関係を考えてみなければならない。それは、生命の主人公は、あくまでも食と性を営む内臓系で、感覚と運動にたずさわる体壁系は、文字通り手足に過ぎない、ということです。つまり内臓系と体壁系は、〝本末〟の関係にあるわけです。ところが私どもの日常を振り返ってみますと、目に付きやすい体壁系にばかり注意が注がれ、いわば前端の顔しか見せない内臓系のほうは、ついおろそかにされているのが現状のようです。
本書の元本である「内臓のはたらきと子どものこころ」が築地書館から刊行されたのは、1982年。今からちょうど40年もまえのことになるわけですが、みなさん、いかがお感じになりますでしょうか。「目に付きやすい体壁系にばかり注意が注がれ」ている実態は、現代でもそう変わっていない(あるいはますます亢進している)とは思いませんか?
さて、本書は、わたしのような解剖学のまったくのド素人でも難なく読みとおせたわけですけれど、(読みやすい講演録だというのはもちろんのこと)その理由のひとつとして、筆者の「図式化」の明瞭さが挙げられるとわたしには感じられました。
筆者は「体壁系」と「内臓系」の対立を、それぞれ「頭脳」と「心臓」のそれに置き換えます。「頭脳」とは「あたま」のことであり、「心臓」とは「こころ」のことであり、そうして「内臓系」と「こころ」が接続されることによって、「内臓とこころ」という本書のタイトルにしめされたテーマが浮き彫りになるわけです。
さらにもうひとつ。本書をユニークなものにしているのは、筆者がわたしたちの生命活動を、宇宙的なスケールでとらえているところです。
筆者はこのように述べています、「宇宙リズムがもっとも純粋なかたちで宿るところが、この内臓系ではないか」。
つまるところ、内臓とこころは切っても切れない関係にあり、それは「宇宙リズム」によって条件づけられている。やや強引なまとめかたにはなりますが、本書の筆者の主張の根幹をひとことで表せば、そういうことになりそうです。
「宇宙リズム」ときくと、どことなくスピリチュアルな感じがしないでもない(しませんか?)。それでも、ふしぎと「きな臭さ」を感じさせないのが、この本のおもしろいところです。いわば筆者の「理性」と「感性」のさじ加減がうまいからで……と思っていたら、本書の解説で養老孟司も書いておりました。三木成夫は「情理」の「バランス」が「見事な人」であると。
あらためて問いましょう。
いったいわたしたちはいま、どれだけみずからの「内臓」を「はらわた」を労わって生活できているのでしょうか。そして「心臓」を、すなわち「こころ」を。
本書は子どもの発育について語りながらも、わたしたちおとなをふくめた人間ひとりひとりに、そうした大きな問いを差し向けつづけているかのようです。
最後に、本書の表紙の話にもどりますと、これ、実は、受胎38日目の胎児の顔、だそうです。このことは、「胎内にみる四億年前の世界」と題された、本書収録の「補論」に書かれているのですが、ここで、一点、けっして見落としてはならない記述があります。
この時期の胎児の顔を真正面から観察することは不可能です。そのためにはどうしても頸の部分を切断しなければならない。それはふつうの神経ではとてもできない相談ですが、まことにやむをえない。この決心が固まるまでに、いったいどれほどの月日が流れ去ったことか……。
いっけんさりげなく書き流されていますが、とても重要なことを筆者は語っているとわたしには読めます。
ねえ、みなさん。いったいどうして、わたしたちは、本やインターネットやアプリなどで、胎児の成長について知ることができるのでしょうか。つまり、受精卵が胎児となって、出産をむかえるまでのつぶさな経過について、正確に知ることができるのでしょうか。
それは、端的にいってしまえば、「人体実験」の積み重ねがあったから、にほかなりません。
医師である増﨑英明と、ノンフィクションライターである最相葉月が書いた「胎児のはなし」(ミシマ社)には、「子宮をとることが決まっている黒人に性交をさせて、一定時間を経過するごとに子宮や卵管を切って調べた」歴史について語られています。
いまだ謎多き胎児の世界。
羊水と闇につつまれたその原始の世界に思いをはせるとき、その探究の過程で無数のいのちの光が消えていったという事実を、わたしたちは忘れてはならないのだと思います。
いいなと思ったら応援しよう!

