
『KDDI—ライフスタイルを変える“au”の挑戦』調査ノートIT・通信業界シリーズ③全6話
こんにちは!
今回はauでおなじみのKDDIの回です。
そう言えば昔はセルラーだった様な……と思われた方、その辺りの答えがここに有ります!
【永久保存回】就活・転職にも役立つ『各業界』研究ノート🗒️👇
マーケティング基礎 SNS拡散編👇
『未来をつなぐテクノロジー—IT・通信業界の進化と展望』
①『IT・通信業界の細分化と代表企業—デジタル時代を支える巨人たち』
②『NTT—通信インフラを支える日本最大級の企業』
③『KDDI—ライフスタイルを変える“au”の挑戦』
④『楽天—ECから通信へ、挑戦するベンチャー魂』
⑤『富士通—ITソリューションで未来を創る総合IT企業』
⑥『IT・通信業界の未来—つながる社会のその先へ』
全6話でお届けします!
サイトマップはこちらから👇

KDDI—ライフスタイルを変える“au”の挑戦
私は「IT・通信業界シリーズ」の第3話として、KDDIを深掘りすることに決めた。前回、NTTを取り上げたときにも感じたのだけれど、通信キャリアというのは日本社会のインフラとしての側面がとても大きい。同時にITサービスや金融など、幅広い分野に事業を拡張している企業でもある。今回のKDDIは、なかでも「au」という携帯電話ブランドでおなじみだが、その背景にはKDDとDDI、さらには日本移動通信(IDO)など、いくつもの企業が合併して誕生した歴史がある。
私がKDDIに注目したのは、通信と生活を組み合わせた“ライフデザイン”戦略を掲げており、スマートフォンやIoT、金融サービス、さらにはエネルギー分野まで事業を広げている点が面白いからだ。かつては“第二電電(DDI)”という形でNTTの独占を崩すチャレンジャー的存在だったが、いまやKDDIは日本の通信市場でシェアを大きく握る1社として確固たる地位を築いている。「つなぐチカラで、くらしの変革」という理念がどう形になり、スマホ時代や5G以降の世界をどう見据えているのか——それを歴史、理念、功績、そして展望の4つの視点でまとめてみたいと思う。
そして今回も、私の部屋に住みつく“うさぎ先生”が鋭いツッコミや補足を加えてくれるはずだ。先生は謎の経緯でウサギの姿に変えられてしまった元大学教授で、マーケティングやAI、IT分野にも精通している。このシリーズではいつも私をサポートしてくれるありがたい存在で、製造業編やNTT編のときにも多くの洞察をくれた。今日もまた、私は会社から帰るなり「先生、KDDIについて徹底的に調べますよ!」とノートとPCを広げるのだった。

1. 歴史:KDDとDDIの合併からスタートし、モバイル市場で急成長
KDDIは2000年に発足した企業だが、その成り立ちは非常に複雑だ。元をたどれば、KDD(国際電信電話株式会社)とDDI(第二電電)、そしてIDO(日本移動通信)などが合併して誕生した。ここで少し歴史を振り返っておきたい。
1.1 KDD(国際電信電話株式会社)とは
戦後の日本で国際通信を担った企業がKDDだ。NTTの前身である電電公社は主に国内電話を扱っていたが、海外との電話・電報やデータ通信を独占していたのがKDDである。国策企業として設立された背景があり、国際通話の料金が非常に高かった時代に、海外通信サービスを独占していたのだ。
「それじゃあKDDが国際通信を完全に握っていたんですね」という私の問いかけに、先生は「そう。1970年代〜80年代は海外との電話といえばKDDしかなかった。民営化や自由化の流れのなかでKDDも変化が迫られ、やがてDDIなどと合併してKDDIの一部となる」と耳を動かしながら答えてくれた。
1.2 DDI(第二電電)というチャレンジャー
一方、DDIは国内長距離電話の競争を促進するために誕生した企業で、“第二電電”の名が示すように、NTTによる独占を崩すチャレンジャー的存在だった。1980年代後半から90年代にかけて、DDIはNTT長距離電話の対抗サービスを展開し、通話料金の引き下げを進める役割を担った。創設メンバーとして京セラの稲盛和夫氏などが名を連ねており、“稲盛流の経営”で注目を浴びたのもDDIの特徴だ。
「当時はNTTが絶対的に強かったけれど、DDIや日本テレコムなどが新規参入して、電話料金が下がり始めたんですよね。私の家でも市外電話のときに“マイライン”を設定する騒動があったり、ちょっとしたブームでした」と私は当時を思い出す。先生は「DDIの動きがなければ、NTTはあそこまで早く料金を引き下げたり、サービスを多様化したりしなかったかもしれない。競争原理の導入という意味で、大きな功績を残したんだ」と補足してくれる。
1.3 IDO(日本移動通信)と携帯電話
さらに、IDO(日本移動通信)はトヨタ自動車や東京電力などが出資して、アナログ携帯電話時代から移動体通信を提供していた企業で、関東〜東海地方を中心に事業を展開していた。NTTドコモが全国シェアを握るなか、IDOは独自のサービスで差別化を図っていた。そこにDDIが合流し、“IDO+DDI”が携帯電話のブランドとして“au”を立ち上げる流れへと進んでいく。
ここが面白いのだが、auというブランドが誕生した当初は「IDO地域+DDIセルラー地域」という具合に分かれていて、ロゴやサービスが統一されていなかった時期もある。私も「最初は関東でIDO、関西でDDIセルラー、みたいに名前が違っていてややこしかったイメージがあります」と記憶を辿る。先生は「そうだね。その後、全国共通ブランドとして“au”が正式に展開され、全国一体でサービスが提供されるようになった。これがKDDI発足への地固めと言える」と説明する。
1.4 KDDIの誕生
2000年、KDDとDDI、日本移動通信が合併して“KDDI”が誕生。国際通信(KDD)と国内長距離電話(DDI)、携帯電話(IDO・DDIセルラー)を一体化することで、総合通信サービスを提供できる企業へと進化する。その後、2001年にauブランドを正式に統一し、携帯電話市場で積極的な攻勢をかける。さらに2003年にツーカーを統合したり、2004年に旧・日本テレコムの一部を吸収したりと、合併・再編を続けて現在の形になっていった。
「こうしてみると、KDDIって歴史の中でいろんな企業を取り込んできたんですね。NTTと同じような国策系の色合いもありつつ、DDI時代のベンチャー気質もあるし、国際通信のKDDも持ってるなんて、本当に多様なルーツだ」と私が感想を漏らすと、先生は「そこがKDDIの面白いところさ。いくつもの企業文化が融合し、総合通信として一気に伸びた。NTTに比べると若い会社だけど、裏にはいろんな企業の歴史があるんだよ」と言って耳を立てた。私は改めて、「KDDIは第二電電の流れをくむチャレンジャー企業でありながら、いまや安定した大手キャリアの一角を担う存在なんだな」と納得する。
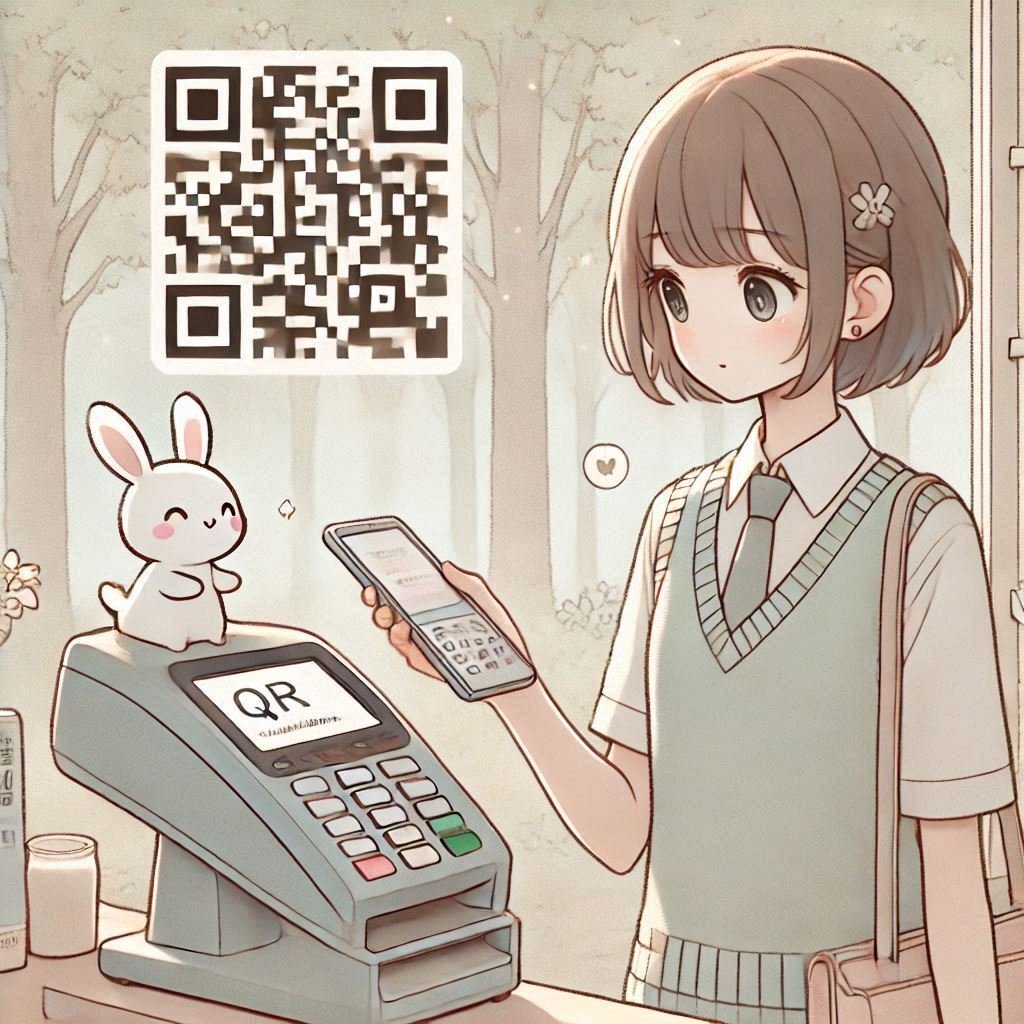
2. 理念:『つなぐチカラで、くらしの変革』を掲げる
ここから先は
最新記事を無料で提供していく為にも支援頂けますと幸いです。頂いた支援は資料や宣伝などクリエイターとしての活動費として使わせていただきます!
