
上手く記事を書くための6つの下準備
きちんとした記事を書くためには下準備が必要不可欠です。自分は何を読者に伝えたいのかが分かっていても、どうやって伝えるのかが分からないと、実際に書く所でつまずいてしまいます。
そうならないために、今回は効率良く質の高い記事を書く方法を6つ紹介していきます。
参考書籍
どんな文章、記事を書くにしても、書くための「下準備」が欠かせません。
下準備を行うと、何をしようか迷い、パソコンと睨めっこする時間が短縮されるので、効率が格段にアップします。
短時間で質の良い記事を書くためにはぜひ実践してみてください。
【超初心者向け】手わかりやすく面白い文章が3分でできる黄金レシピ

よく記事の構成は料理に例えられます。適当に材料を混ぜても美味しい料理は完成しません。
きちんとレシピ通りに手順を踏んで初めて、美味しい料理が完成するのです。記事を書くときのレシピは下記の通りです。
①その文章で何を伝えたいか(料理名を決める)
②まず書きたいことを箇条書きしてみる(材料を集めてくる)
③どういう流れがベストか考える(手順を考えながら調理)
④具体例などを入れながら肉づけしていく(味つけ)
⑤伝わる文章に味つけしていく(スパイス)
実際にやってみましょう。
【料理名】
「私が好きな牛丼チェーン店の特徴3つ」
【材料】
・素早く提供してくれるめ、空腹時にとても重宝する。
・値段が安いので、給料日前でも安心して足を運べる。
・自社で研究を続けたタレが絶品。
・最近値上がりが気になる。
・他のチェーン店にも魅力的な商品が出てきている。
【流れ】
①私が好きな牛丼チェーン店の特徴3つ
②特徴を3つ挙げる
③一方で、不満な点もある
④それでも私はチェーン店に通い続ける
文章の骨格が完成しました。あとは肉づけをしてスパイスを加えれば、記事が出来上がります。
タイトル:私が好きな牛丼チェーン店の特徴3つ
私が某牛丼チェーン店を愛して止まない牛丼娘である。まるで私が来るのをわかっていたかのように素早く提供される牛丼には、いつも驚かされる。
某チェーン店は、給料日前の私でさえも優しくしてくれる懐の広さがある。男だったら絶対に付き合っているレベルだ。
そして一番大事なのは牛丼の味。自社が10年かけて作り上げた秘伝のタレが乗った牛丼は絶品の一言ではとても言い表せない。舌が「もっとよこせ!」と言わんばかりに次々と口に運んでいってしまう。
ここまで賛頌ばかりしてきたが、もちろん不満な点はある。例えば、最近、牛丼の値上がりが増えていってる気がする。牛丼チェーン店の玉座に座っているからといって胡座をかき続けていると、いつか足元を掬われてしまうのではないかと心配になってしまう。
また他のチェーン店の躍進も気になる。ある店舗では牛丼だけでなく、お子様メニューやデザートを導入しているらしい。ファミリー層の獲得は、飲食をやる上でとても重要な戦略である。
しかし私はこれだけ不満があっても、某チェーン店に通い続ける予定だ。これはポケモンでサトシがピカチュウとずっと旅を続けるのと同じである。
私の人生において、某チェーン店は永遠の相棒の様な存在だからだ。「早い」「安い」「美味い」これだけ強いワザが揃っていれば、ポケモンマスターなんて容易いはずだ。
あらかじめ書きたい内容を整理して流れを書いておくだけでも、スムーズに文章が書けるようになります。
バズる記事が速く書ける5つの準備
こちらではより質の高い記事を書くために必要な5つの下準備について紹介していきます。
黄金レシピと違い、準備の数が多いですが、ここまで準備しておけば迷いなくきちんとした記事が出来上がるため、かえって効率の良い執筆が可能になります。
文章の目的地を決めるために、仮タイトルを付けておこう
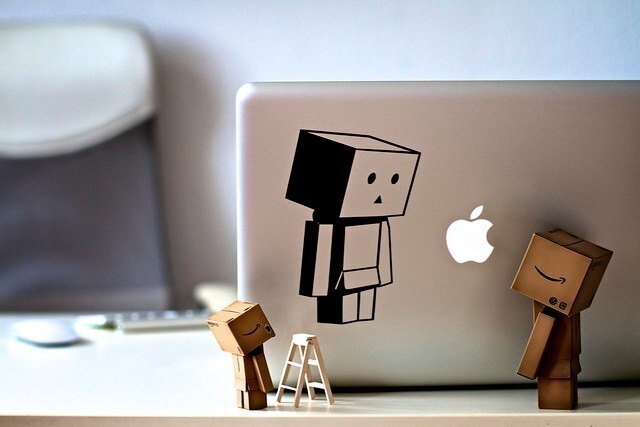
書きたいテーマが決まったら、仮でもいいのでタイトルを決めておくのがオススメです。
あらかじめ仮タイトルをつけておけば記事の内容が脱線するのを防ぐ効果があります。基本的に1つの記事につき、メッセージは1つに絞るものです。
仮タイトルがないと書いているうちに熱が入ってしまい、話が脱線してしまう恐れがあります。その状態で記事を書き上げてしまうと、読んだ人が余計なストレスを感じてしまうかもしれません。
読者のためにも、あらかじめ仮タイトルを作りテーマを1つに絞っておきましょう。こうすると、伝えたいメッセージが明確になるので、読者は迷わず読み進められます。
もちろんタイトルはあくまで「仮」なので、適当なものでOKです。本番用のタイトルは後からつけるようにしましょう。
5W1H整理法

書きたいテーマが決まり、仮タイトルをつけたら、文章を構成する「素材」を洗い出しましょう。
この時使えるのが「5W1H」を使った情報整理術です。
What(何)
When(いつ)
Where(どこで)
Who(誰)
Why(どうして)
How(どんな、いくら、それくらい)
例えば素敵なカフェで食べた美味しいチョコレートケーキをおすすめする記事を書きたいと思った場合、下記のように当てはめていきます。
What(何):チョコレートケーキ
When(いつ):今月から
Where(どこで):WOAカフェ(カフェの名前)
Who(誰):スイーツ好きの女性におすすめ
Why(どうして):チョコレートが濃厚で病みつきになるから
How(どんな、いくら、それくらい):コーヒーがついて500円とお得
書き始める前に自分が今どんな素材を持っているかを「5W1H整理法」の表に当てはめて書き出してみます。
もちろん最初から全てを埋める必要はありません。ただ表に当てはめられる情報が多いほど、記事の内容が充実し、説得力が増すようになります。
読者=ターゲットを設定する

「誰に向けて」書くかを定めておくと、文章の書き方が決まります。
ターゲットを意識すると選ぶ言葉や文章のテンションが変わっていくので、テーマが同じでも記事の雰囲気がガラッと変化します。
するとその記事に興味のあるターゲット層が集まりやすくなるため、アクセス数や「いいね」の数が伸びやすくなります。
設定する項目は以下の3つです。
①具体的な人物像(年齢、性別、職業、タイプ・志向)
②記事を読む目的
③読者心理
①に関しては他にも「趣味、価値観、悩み、職業」など、いくらでも掘り下げが可能です。掘り下げるほどターゲットが明確になるため、記事が読者に刺さりやすくなります。しかしあまりにも細かく設定すると記事を書く前に疲れてしまいます。あとこの段階で面倒になってしまい、記事を書くのが億劫になってしまいます。
ですのでターゲットは適度に設定することが大切です。
③の「読者心理」は「この記事を読む人は何に悩んでいるのか」を考える必要があります。自身がターゲットの気持ちになって考えるため、想像力が試される所でもあります。
簡単かつお手軽に読者に響くキーワードがわかる方法

「ターゲットは決まったけど、その人たちがどんなキーワードに反応するのかが、いまいちわからない」という人には以下の媒体を参考にしてみましょう。
ニュースアプリ
スマートニュースなどのニュースアプリを使うと、ネット好きの読者の動向が把握できます。
ニュースアプリを開いたら、タイトルをざっとでいいので閲覧します。その中でバズっている言葉や、いい表現だなと思ったのは、メモしたり、リンクを保存したりします。
こういったものはテンプレートにしておくことで、ここぞという時に役立ちます。
人気の雑誌
ターゲットに近しい雑誌、テーマが近い雑誌をみると記事を書く上での参考になります。
読者がどんなキーワードや見出しに興味を持っているのかを研究しましょう。また雑誌は沢山買うとお金がかかり、かさばるため、サブスクを使って読める環境を作っておくのがオススメです。
流行に敏感な20〜30代の女性「an・an」
ファッションに敏感な20〜30女性「MENS NON-NO」
美容に敏感な20〜30代の女性「美的」
庶民派の男性向け「週刊SPA!」
子育て中のママ「VERY」
流行に敏感な働く30〜40代の女性「InRed」
他には雑誌と連動したウェブメディアを利用するのもオススメです。
20-30代…「新R25」「マイナビニュース」「ハウコレ(女性)」
40-50代…「東洋経済オンライン」「NEWSポストセブン」「OTONA SALONE」
60代以上…「サライ.jp」「趣味人倶楽部」
「小見出し」=骨格を考える

小見出しは記事の構成としての役割があります。いい記事が書けるかどうかは、骨格とも呼べる小見出しが上手くできるかにかかっています。
まずはタイトル同様、仮でもいいので、小見出しを作っておきましょう。コツは仮にタイトルに対して、答えになっているかどうかです。
見出しが仮タイトルの答えになっていなければ、話が脱線すしてしまうか、読者が一目で記事の内容を判断できない恐れがあるので止めておきましょう。
例えば「私が好きな牛丼チェーン店の特徴3つ」という記事を書く場合
・私が牛丼にハマったきっかけ
・私は会社の休憩時間によく行く
・だから牛丼は最高
これでは小見出しが仮タイトルの答えになっていませんね。
・早い
・安い
・美味い
非常にシンプルですが、きちんとタイトルの答えになっています。最初はこれくらいシンプルでもいいので、ちゃんとした小見出しを作っておきましょう。
まとめ
✅タイトル→書きたいこと箇条書き→書く流れを決めて、骨格を作る。
✅骨格ができたら具体例を付け足したり、より伝わりやすい表現を加える。
✅文章の目的地を絞るために、書く前に仮でもいいのでタイトルを付けておこう。
✅5W1Hを使って文章の素材を整理しよう。
✅特定の人に届けるために、ターゲットをできる範囲で設定しよう。
✅ニュースアプリや雑誌を使って、読者に響くキーワードを設定しよう。
✅記事の構成を作るために、あらかじめ小見出しを考えておこう。
