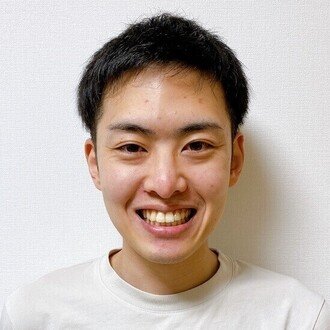【道化師の蝶】円城塔:着想はどこから来てどこに行くのか?
第146回芥川賞受賞された、円城塔さんの小説「道化師の蝶」の感想と考察を記載。
内容が難解で、自分の読解力が低かったからか、1回読んだだけでは、「着想について書かれているのかな?」というくらいで、サッパリ分からず、読み返して、ようやく少しは理解できたかできてないかという感じ。
純文学とも、ミステリとも、SFとも違う感じで、作品の構造自体が一種の言語遊戯を駆使しているとも言える。内容は難解なのだが、文章はサラサラと読めるという、言葉に形容し難い読後感があった。また、着想(アイデア)に関して、こんな見方があるのかと新鮮さもあった。
なお、ネタバレ含みますので、この記事は読了後に読むことをおすすめします。
あらすじ
人工言語である無活用ラテン語で記された小説『猫の下で読むに限る』。その正体不明の作家を追って、言葉は世界中を飛びまわる。帽子をすりぬける蝶が飛行機の中を舞うとき、「言葉」の網が振りかざされる。希代の多言語作家「友幸友幸」と、資産家A・A・エイブラムスの、言語をめぐって連環してゆく物語。
着想と言語化の関係は?
本作では、蝶と蝶を捕まえるための虫取り網が登場する。蝶は着想(アイデア)の比喩であり、虫取り網はアイデアを捕まえる行為を指している。
エイブラムス氏は、虫取り網を持って蝶を捕まえる(つまり着想を捕まえる)のを生業としているが、下記に記載があるように、悪い着想は網をすり抜けるので、良い着想(つまり、まだ誰も発見したことのない(と本人が思っている)アイデア)だけを網に引っ掛けて、それを実用化して事業として大成させようとしている。
「わたしの仕事というのはですな、こうして着想を捕まえて歩くことなのです。」
そして、網は文字であり、着想を捕まえるということは、言語化するということでもある。今や世に言語はたくさんあり、同じようなことを指していても言語間でニュアンスが異なることは多い。
まず、アイデアを言語に落とし込むという時点で、その言語の制約に我々は取り憑かれるわけで、その時点で自分が考えた内容を正確に表現するのは難しくなる。言葉が足りないということだ。さらに、言語間でニュアンスが異なることも多いので、同じ内容を言葉として伝えていたとしても、翻訳の過程で、本来の意図がそのまま伝わらないばかりか、言語間の差異によって新たに別の解釈が入り込んでしまうことで元のアイデアからはさらにかけ離れてしまう。
その網には文字たちが織り込まれている。でも小さな文字ではない。糸たちのなす脈絡が伸びて 捩じれて互いに絡み、表を見せて裏へと返る文字たちが、本来存在しない脈絡を摑む。そんな呪文だ。わたしは彼女が手にするその虫採り網を見た覚えがないが、その働きは明らかにわかる。
というわけで、本作では無活用ラテン語という人工言語が登場するのだが、これは稀代の多言語作家である友幸友幸(別の節では、着想として行動する)は、最初は、ありとあらゆる言語を学び、着想を記すのだが、言語化と言語間のニュアンスの違いによる着想の共有の限界を感じて、誰も使用しない言語であれば、そうした制約もないのではとの考えに至り、その例として無活用ラテン語が登場する。
アイデアは自分の頭の中で自由に発想している分には自由なのだが、、、
続きは、こちらで記載しています。
いいなと思ったら応援しよう!