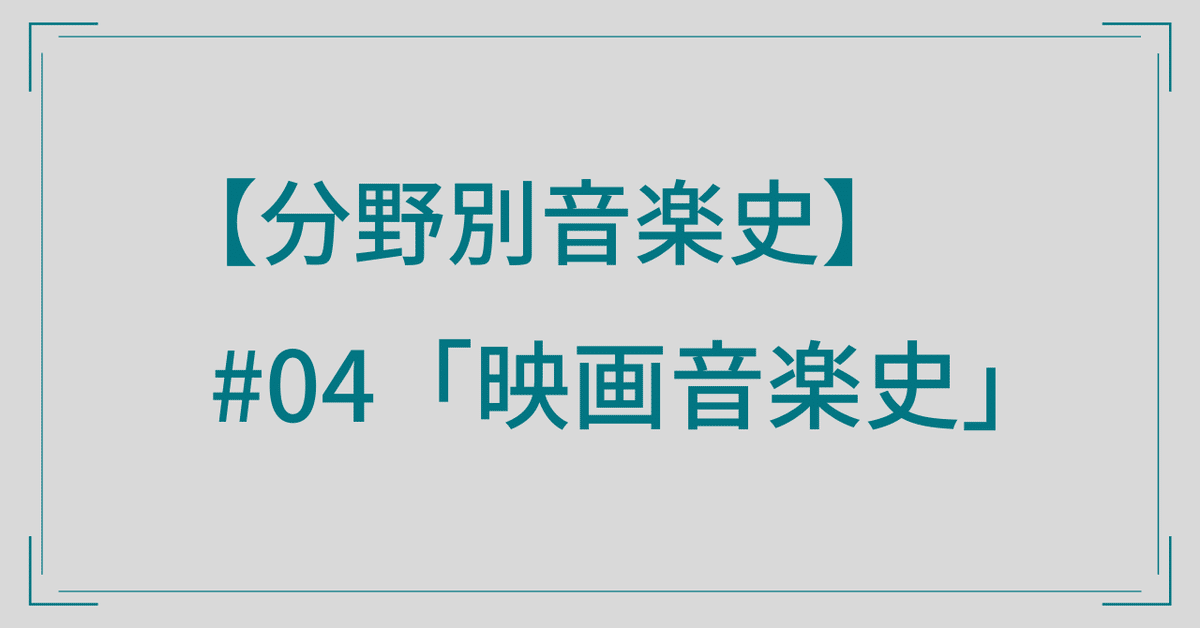
【分野別音楽史】#04「映画音楽史」
『分野別音楽史』のシリーズです。
良ければ是非シリーズ通してお読みください。
本シリーズのここまでの記事
#01-1「クラシック史」 (基本編)
#01-2「クラシック史」 (捉えなおし・前編)
#01-3「クラシック史」 (捉えなおし・中編)
#01-4「クラシック史」 (捉えなおし・後編)
#01-5 クラシックと関連したヨーロッパ音楽のもう1つの系譜
#02 「吹奏楽史」
#03-1 イギリスの大衆音楽史・ミュージックホールの系譜
#03-2 アメリカ民謡と劇場音楽・ミンストレルショーの系譜
#03-3 「ミュージカル史」
今回は「映画音楽史」です。映画音楽やテレビドラマの劇伴では、昔から現在まで絶えず豊かなオーケストラサウンドが用いられており、劇伴の存在は現代社会で普通に生活をしている(音楽にさほど興味のない)一般の人にとってシンフォニックな音楽を耳にする一番のきっかけである、とまで言えるほどではないでしょうか。
そして、現在「音楽」と言えばギター中心のバンドサウンドやシンセの打ち込みサウンドが主流である中で、オーケストラサウンドで作られた音楽はそれだけで「クラシック音楽」である、と思い込んでいる人も実は少なくないと思います。これはクラシックをよく知る人からすると否定したくなる感覚かもしれませんが、冷静に考えれば、それが「普通」の感覚でしょう。僕個人の感覚としても、本来、映画音楽はクラシック音楽に分類されてもしかるべき分野である、とさえ思っています。
歴史区分の知識・先入観を排除して聴くと、「映画音楽」という分野はクラシックのスタイルに非常に近いのに、どうしてクラシックに入らないのか?という問題意識と答えは、ここまでクラシック史の文脈においてさんざん書いてきましたが、改めて今度は映画音楽史サイドの流れを追うことで、論の補強としていきたいと思います。
過去記事には クラシック史とポピュラー史を一つにつなげた図解年表をPDFで配布していたり、ジャンルごとではなくジャンルを横断して同時代ごとに記事を書いた「メタ音楽史」の記事シリーズなどもあるので、そちらも良ければチェックしてみてくださいね。
◉普仏戦争と南北戦争後の情勢
まずは、ここまでの記事をもとに、映画が誕生する直前、19世紀後半の多岐に渡る音楽状況をもう一度整理しておきたいと思います。
ヨーロッパでは、1870~71年の普仏戦争(フランスvsプロイセンドイツ)を経て、それまで諸邦乱立状態だったドイツ圏がプロイセンによって統一され、「ドイツ帝国」が誕生。政治に加えて学問的な影響力も獲得し、18世紀までは実は劣勢だった音楽面でも「真面目で崇高な芸術」という方向性を武器に、ドイツ音楽が遂にヨーロッパのスタンダードへと成り上がったのでした。これによって現在まで続くクラシック音楽の価値観が決定し、19世紀がクラシック音楽の最盛期となります。
当時、ワーグナーとブラームスが鎬を削って美学的なクラシック芸術を発展させていっており、それに追従する形で各国にロマン派の作曲家たちも台頭。東欧の作曲家に対しては民族的な「国民楽派」である、というレッテルを貼ったりするなどして、ドイツこそが中心であり、それ以外が周辺である、ベートーヴェン由来の「ドイツ的」な芸術が「普遍的」であるという価値を植え付け、覇権を獲ることができたのです。
比較的娯楽音楽の性格を持っていたフランスでも、敗戦を機に「真面目な音楽」の文化を作ろう!と、サンサーンスやフォーレなどといったクラシカルな作曲家が登場しました。
他方で、オペラを庶民的にした「オペレッタ」はパリやウィーンで絶大な人気を博し、イギリスやアメリカへも渡っていきました。ワルツやポルカといったヨーロッパの都市文化の音楽は中南米へも伝わり、ラテン音楽の誕生の土壌となります。
イギリスではミュージックホールという劇場娯楽を中心に、トップダウン的な農村の文化(クラシック)とは異なる、都市型の労働者階級のためのポピュラー文化が台頭していきます。
アメリカでは、1861~65年の南北戦争を経て、ミンストレルショーから生まれたフォスターらの「アメリカ民謡」や、ギルモアやスーザらによるブラスバンドが身近な音楽として大人気の時代。さらに黒人奴隷制度が(名目上)廃止され、南部ではラグタイムやニューオーリンズジャズといった新しいリズムの音楽が産声を上げようとしていた時代。かたやニューヨークでは、ブロードウェイ劇場街が発達していき、ミンストレルショーから発展したヴォードビルやヴァラエティーショー、そしてヨーロッパ発のオペレッタといった劇場音楽からポップソングが産まれていくという新たな産業が始まろうとしていた時代です。
(※このような、クラシックとポピュラーの分岐点の真っ只中のような混沌としたタイミングで、日本では1868年に明治維新が起こっており「西洋音楽の流入」が起こります。日本が急速に価値観を大反転させて追い付こうとしていた「西洋音楽」の正体とは何だったのか?を知るためにも、この状況の整理は有用かと思います。)
さて、1870年代まで、人類の音楽の伝達方法としては、口承か楽譜かのどちらかでした。主に楽譜自体が作品として重要視されたのがクラシック音楽であり、それ以外の主に口承で伝えられる音楽が民俗音楽とされます。しかし、1870年代に、第3の伝達方法が登場します。アメリカの発明家トーマス・エジソンは1877年に蓄音機を発明したことにより、「音そのもの」が残されるようになったのです。
(はじめて録音されたのはエジソンの歌う「メリーさんの羊」であるというのは有名です。その後いくつかの録音が行われましたが、1889年にエジソンはブラームスに依頼し、ピアノ演奏を録音します。これが史上初のプロの演奏の録音だとされています。)
◉19世紀末~20世紀初頭 ―映画の誕生
19世紀は目まぐるしく科学技術が発達した時代で、19世紀初頭に写真が誕生して以来、画像を動かす試みも研究されていきました。
1877年に蓄音機を発明したエジソンは、「音」の次に「映像」に関心を向け、動画記録装置の研究を進めました。そして発明を完成させ、1891年に内輪向けに公開します。ヴォードビルやヴァラエティの芸人を呼んでは演し物を撮ったり、芝居の一場面、ボクシングの試合、ダンスなどを撮ったりしました。その後「キネトスコープ」として1893年に一般公開します(シカゴ万国博覧会に出展)。
この地点では、映像を見るには箱の中を覗き込む〈のぞき穴〉型だったため、多数に向け上映するということはできませんでした。エジソンはその後、他の発明に関心を移してしまいますが、そのあいだにヨーロッパでは、パリのリュミエール兄弟が1895年にスクリーン投影型の 「シネマトグラフ」の発明を成功させました。一般にこれが映画の起源だとされています。リュミエール兄弟は「工場の出口」など計10本の短編映画を商業公開しました。
初めは祭りや定期市など人の集まる場所で上映されるうち、さらに当時の市民の馴染みの場所だったミュージックホールやヴォードビル劇場の演し物の一つとして上映されるようになり、大人気となります。
やがてヴォードビルを真似て、店先をやっつけで改良したような上映ルームや、芝居小屋を無理やり押し広げたような即席ホールが次々と登場し、映画専門小屋として大ヒットします。こういった小屋は入場料が5セント(ニッケル硬貨)だったため、「ニッケルオデオン」と呼ばれ親しまれました。ニッケルオデオンは、貧しい庶民の社交場となり栄えました。
「音」に関して、一説によれば1895年からの5~6年間は本当に「音無し」だったといわれますが、別の説によれば、映画が生まれて2~3年で劇場では音を付けていたとも言われます。このあたりはハッキリしていないのですが、20世紀になると同時くらいに、どうやらサイレント映画に上映現場で音を付けることを試み始めたようです。ヴォードビルやミュージックホールといった場では「鳴り物」は必須でした。
そもそも演劇などにつく「付随音楽」は、古代ギリシャの劇音楽にその歴史を遡ることができますが、ルネサンス後のシェイクスピア劇などを経てバロック期に誕生したオペラやバレエなどもルーツといえるでしょう。クラシック音楽のロマン派への変化とともに、劇音楽も音楽の表現分野を広げると思われましたが、やがて「マトモ」に取り扱われなくなってしまいます。ドイツ美学の伝播に従って、音楽というものは「文学・演劇」に付随するものではなく、「音楽」という独立した中での「個」の主張として存在するべきだ、という風潮になってしまったのです。「道具としての付随物ではなく、音楽そのものの表現」というベートーヴェン由来のドイツ音楽美学は、ブラームス派とワーグナー派の両方の前提となりました。
そして、20世紀に入り、映画の時代が訪れたのです。クラシックの範疇である「オペラ」「オペレッタ」「楽劇」などはいずれも音楽表現と文学表現・劇そのものが一体で考えられる芸術であるので、映画の誕生により「映像」と「音楽」が一度分離したことによって、完全な「付随音楽・BGM」としての役割の音楽の歴史が、ここから始まったといえるでしょう。
初期の映画音楽のつけ方には、大きく2パターン存在しました。
①映画館ごとに、その場の音楽家が適当な音楽を現場でつけるパターン
②映画製作者側が専用の音楽(スコア)を用意したパターン
①映画館ごとに、その場の音楽家が適当な音楽を現場でつけるパターンでは、大半はピアノかオルガンで自己流で演奏され、一部のキュー・シートの指示には従ったものの、映像に合わせて自己のインスピレーション、音楽知識と技術を総動員して、即興での制作活動ともいえる演奏を行っていました。〈シネマオルガンの時代〉と言われ、「やってみよう」精神を盛んに、効果音を考えたり、スクリーンの裏でいろんな音を出してみたり、セリフをしゃべってみたり、とあらゆる方法が試され、その中でピアニストやオルガニストが大きく注目されました。
1909年にはトーマス・エジソン・カンパニーが自社の映画に「よく合う音楽」の楽譜を売り出したり、1913年にはオハイオ州の音楽出版社が「戦いのシーン」「ラヴシーン」などパターン化された音楽を用意した「Sam Fox Moving Picture Music」を売り出し、人気となりました。また、ドタバタコメディ全盛期の1910年代には、チャップリンなどの短編に対してラグタイムの音楽もよく演奏されていたようです。
②映画製作者側が専用の音楽(スコア)を用意したパターンでは、大型の劇場にフル・オーケストラが付き、既存のクラシック曲から書き下ろし曲までがスコアに揃えられ、それを演奏したそうです。選曲された作品としては、ロッシーニ、ベートーヴェン、ヴェルディ、ワーグナー、グリーグ、チャイコフスキー、サン・サーンスなどのクラシック曲から、フォスターなどのアメリカ民謡などまでを総動員して組み立てられました。
1908年のフランス映画「ギース公の暗殺」はサン・サーンスが映画のために音楽を担当しました。初期映画界はアメリカではなくフランスの存在感が強く、音楽としてもこの後の時代もしばらくフランスのクラシック作曲家が映画界に比較的積極的に関わることになります。
◉映画都市ハリウッドの形成と、トーキー映画の誕生
20世紀初頭の映画誕生当初は、届いたフィルムに対して上映劇場側が勝手に編集を行ってしまうのが当たり前でした。このような状況に対し、制作側が権限を持つことができるように契約がなされるようになります。そうして映画は権利ビジネスとして一大産業化していきました。映画製作会社を経営していた発明王エジソンも、数多くの訴訟を起こしていきます。さらにエジソンは、「ヴァイタグラフ」「バイオグラフ」「ルービン」などの大手企業のトラストを結成させ、モーション・ピクチャー・パテント・カンパニー(略称 MPPC =「映画特許会社」)を設立。「ザ・トラスト」「エジソン・トラスト」とも言われ、すべてがライセンス制となり、権利を管理下に置いて利益を吸収していくことに成功しました。
一方で、1910年頃からアメリカでは新規参上の会社が台頭し、勢いを持ち始めます。これに対し従来企業のエジソン・トラスト側は権益を守るために妨害を行っていきました。またそのころ、映画館は「いかがわしい場所」「ろくでもない場所」としてブルジョワ階級の目に留まるようになり、「学校や教会以外で若者が文化的な悪影響を受けるのは良くない」と、規制や取り締まりが断行されていきます。これに応じて映画業界も自主規制を進めていきますが、トラスト側からのトップダウン的な自主規制にニッケルオデオン系の人々はますます反発を深めてしまいました。
映画製作が困難になった反トラスト側の多くの映画人たちは難を逃れるため、そして新たな撮影場所を探し求め、新機軸を打ち出すために西海岸へと拠点を移しました。こうして映画都市ハリウッドが形成され始めます。ハリウッドはみるみる発展し、1920年代、ハリウッド映画はサイレント映画の全盛期となりました。このようなサイレント期の初期ハリウッド映画に対しても、上映場でのオーケストラやオルガン演奏によって音楽が付けられ、アメリカンオペレッタで活躍していたシグマンド・ロンバーグなど多くの作曲家が曲を書いて評判となりました。
フランス映画界では、オネゲル、サティ、ミヨーらが音楽を担当した作品が発表されたほか、パリで流行していたタンゴを取り入れた作品も登場します。
1923年には、ウォルト・ディズニーがディズニー・ブラザーズ・スタジオを設立し、アメリカンアニメーションの華やかな歴史がスタート。
さて、この段階まで、蓄音機やレコードというのは電気を使わずラッパ型の蓄音機に吹き込む「アコースティック録音」で、音質が貧弱でした。しかし、マイクを使った電気録音によるレコードの開発が進み、1925年、ビクター社が電気録音盤を初めて発売。
これにより、映画のリールと音楽のレコードを同期させる発想がうまれます(=ヴァイタフォン方式)。このような音声付きの映画作品は、サイレント映画に対して「トーキー映画」と呼ばれ、映画の中の一部でのトーキーや、短編トーキーなどで試行錯誤がなされました。そして1927年、世界初の長編トーキー映画「ジャズ・シンガー」が公開され、一大センセーションを巻き起こして大成功します。ここからトーキー時代の幕明けとなりました。音楽の担当は、当時のニューヨークの音楽産業の発信地ティン・パン・アレーのアーヴィング・バーリンが担当していました。
ところが、フィルムとレコードを同時再生するというこのヴァイタフォン方式は、映画館でフィルムが切れてしまっても音だけが鳴り続けたり、レコードの針飛びによっておかしくなったり、とトラブルが多発してしまい、上映館は疲弊してしまったため、映画のフィルムの左側に音も記録する「サウンドトラック方式」が間もなく開発され、そちらが今日の標準となりました。
このサウンドトラック方式を最大限活用したのがディズニーアニメでした。「ジャズ・シンガー」に遅れること1年、1928年「蒸気船ウィリー」が初のアニメーション・トーキーとして大ヒットします。
この作品は何を隠そうあのミッキーマウスのデビュー作です。実写での同時録音と違い、アニメではフィルムが完成してから音入れを行うことになったため、コマ数と音楽のテンポを計算によって一致させることが可能でした。これにより音楽と画面(ミッキーの身のこなし)が一体となり、ミッキーマウスのヒットの最大要因とまで言われています。階段を昇るときは弦楽器のピチカート、転んだときはグリッサンド、パンチの動きには銅鑼を鳴らす、など、効果音までも一体となってシンクロさせるこの手法を「ミッキーマウジング」と呼ぶまでになりました。
この作品では、昔のヴォードヴィル・ソング「スティームボート・ビル」を原案にして、「わらの中の七面鳥」「ヤンキー・ドゥードゥル」などのアメリカ民謡として親しまれているメロディを詰め込んでいます。その後もミッキーマウスシリーズにて楽曲は南北戦争の歌や愛国歌(ヤンキードゥードゥルなど)、民謡、子供の歌、クラシックなどが多く使われました。
こうして、映画のフィルムとシンクロする形で音楽が作られるようになり、こんにちのサウンドトラックに繋がる歴史がスタートしました。
1929年にはアカデミー賞、1932年にはヴェネチア国際映画祭も始まり、映画というものの文化的地位も向上していきました。
◉1930年代~ ハリウッド流サウンドトラックの確立
1930年代、ドイツではヒトラー・ナチス政権によってユダヤ人が迫害されていき、アメリカへ多くのユダヤ人作曲家が亡命していきました。
実はハリウッド映画産業やティン・パン・アレーの音楽産業はもともとからユダヤ人が中心となっていた業界だったのですが、ナチの台頭を受けてアメリカに渡ったユダヤ人作曲家たちによって、さらにここからハリウッド映画の音楽が発展し、その基礎がつくりあげられることになります。亡命作曲家のほとんどは、ウィーンでマーラーに師事していたか、その影響を受けていました。こうしてロマン派の手法は分野を変えて生き永らえ、継承されることになりました。
トーキー映画初期において、映画(セリフ)と音楽を簡単に結びつける方法としてはミュージカル的な手法が採用されていました。「ジャズ・シンガー」のあとしばらくはミュージカル映画が急増していました。そのような手法ではなく、正統な「BGM」としての映画音楽の芸術が確立するきっかけは、マックス・スタイナー(1888~1971)からでした。
マックス・スタイナーは、主人公や登場人物にひとつのテーマ(旋律)を与え、それを活用して展開する、というワーグナー流の「ライトモチーフ」の構想を思いついて作曲しました。プロデューサーはそれを評価し、セリフをしゃべっている最中でもその下に音楽を流すという手法を採用したのでした。そして、それまではセリフ、効果音、音楽はすべて同時録音だったのですが、別々に録音して1つにまとめればよいのだ、ということが発見され、1933年「キング・コング」で実現に至りました。
この発想は「アンダースコア」と呼ばれました。underscore = 傍線(アンダーライン)を引く、という意味だが、そこにscore(譜面)を引っかけた用語です。ワーグナー流の重厚なサウンドや、ドビュッシーのような浮遊感あるオーケストレーションが融合され、後期ロマン主義と印象主義の混合だとされました。状況説明的な音楽ではなく、登場人物や出来事それ自体に音楽テーマを与えるというパワーと、本格的なシンフォニックスコアのインパクトは絶大で、この方向性がハリウッドに長く君臨することとなりました。マックス・スタイナーは、ワーグナーからマーラーに至るドイツの伝統を独自に発展させ、映画音楽をドラマチックなシンフォニックスコアにした第一人者でした。
もう一人の功労者は、アルフレッド・ニューマン(1901~1970)です。マックス・スタイナーと共通する音楽スタイルで、さらに映像を意識した「ミッキーマウシング」や、流麗なアンサンブルが特徴です。
アルフレッド・ニューマンは、あの有名な「20世紀フォックスのスタジオ・ロゴのためのファンファーレ」を作曲したことでも知られています。
逆に、ミッキーマウシングを拒否し、映画の脚本を「オペラのリブレット(台本)」と見なして純芸術のオペラをつくるように作曲したのがコルンゴルト(1897~1957)です。ヨーロッパでマーラーやリヒャルト・シュトラウスから直接学んだ後期ロマン派的作風を、そのまま映画音楽に持ち込み、ハリウッド音楽に大きな影響を与えました。
コルンゴルトは映画音楽ではない純粋な芸術音楽の作曲も志向していたのですが、ご存じの通り当時の芸術音楽界は無調の前衛芸術の全盛期であり、ロマン派的作風は酷評の的だったうえ、映画音楽というもの自体が下等な芸術だとみなされていたため、コルンゴルトは「映画に魂を売った下等な作曲家」というレッテルを張られて、ウィーンの楽壇からは事実上抹殺されてしまいました。
シェーンベルクの登場によって既に「現代音楽」が最新の表現となってしまったクラシック創作界は調性音楽を過去のものと断じ、酷評していきます。このような考え方があったため、映画音楽文化はクラシックのロマン派を受け継いでいるにもかかわらず、クラシック音楽史に一切の記載が無いのです。
当時、小説を書くことよりも映画の脚本を書くほうが低俗な仕事だとされ、同様に映画音楽を書くことも低級な仕事だとされていました。バッハやベートーヴェンの伝統に属する自意識を持つクラシック作曲家たちは、「〇秒の○○な場面」という要求に応えたくなかったし、応えられなかったのです。
ちなみに、シェーンベルクのもとにも映画音楽制作の依頼が来たことはあったそうです。その際シェーンベルクは、「5万ドルと、スコアに何一つ手を入れないという絶対的保証」を要求したために実現しなかったといいます。
同じように、ストラヴィンスキーに映画音楽の依頼が舞い込んだ際には、「10万ドルと、1年間の作曲期間」を要求したために実現しなかったそうです。当時のクラシック作曲家の映画音楽(商業音楽)に対する考え方と拒否反応が伺える良い例だと思います。
このようなエピソードから、クラシックの「芸術至上主義」のドイツ的な本質というものが見えてきますし、それがアメリカへ学問的に「移植」されたことによって、その価値観がグローバルな音楽学のスタンダードに成ってしまったことがわかります。一方で、ソ連のプロコフィエフやフランス映画とフランスのクラシック作曲家は、好意的に映画音楽も手掛け、成功していました。
さて、ディズニーアニメのその後はというと、1929年からは短編アニメーションシリーズ「シリー・シンフォニー」が始まり、多数のクラシック曲の引用も行われました。ディズニーの初代音楽監督カール・スターリングは、音楽を出発点にしたシリーズを作りたかったようです。スタジオ・オーケストラによる豪華な管弦楽がディズニー映画を彩りました。
1937年には史上初のフルカラー長編アニメ「白雪姫」が大成功します。その後も「ピノキオ(1940)」「ファンタジア(1940)」などと続いていきました。
ディズニーアニメ音楽の特徴として、主題歌一曲だけが用意されているのではなく、場面場面に合わせて配慮された中で複数のヒットソングがたくさん用意されている贅沢さがあり、アニメーションという形を借りたミュージカル映画だと言えます。
当時の音楽状況を反映した興味深い作品として、「音楽の国(1935)」があります。「不協和音の海」に隔てられた「シンフォニーの国」と「ジャズの島」の2つの国の物語です。現実世界の音楽評論家や文化人の間でも論争となっていた「クラシック」と「ジャズ」。ロミオとジュリエット風に例えられたストーリーによって、争いの末、最終的に「ハーモニーの橋」が架けられ、2つの国に平和がもたらされる結末となり、互いに尊重し合うことが提唱されています。
◉ハリウッド映画の「黄金時代」
音楽の分野に限らず、第二次世界大戦中にはドイツやフランスからアメリカへ映画業界関係者が多数亡命したため、ハリウッドはさらに発展し、「黄金時代」を迎えました。1946年にはフランスでカンヌ国際映画祭も始まりました。
30年代以降、映画の発展と同じくしてスタイルが確立していったミュージカルでは、多くのポップソングがスタンダード曲になっていきましたが、映画の分野からも主題歌がヒットし、スタンダードとして残るようになったケースもありました。特にヴィクター・ヤングは数々の映画主題歌を提供し、ヒットを量産しました。「スタンダード曲」は、モダンジャズのセッション曲としても引用されていきました。
また、マーラーなどオーストリア・ウィーンのロマン派の本格的クラシックルーツを直接引き継いだといえるハリウッド映画のサウンドトラックも独自発展していきます。その作曲家としては、ヒューゴー・フリードホーファー、アレックス・ノース、バーナード・ハーマン、デイヴィッド・ラクシン、フランツ・ワックスマンらが牽引していました。
◉1940年代末~ 黄金時代の終焉
戦後のアメリカをはじめとした西側諸国では、共産主義国家の成立と冷戦の開始を背景に、共産主義者の追放運動が始まり、「赤狩り」と呼ばれました。その動きは映画業界にも大きく波及し、多くのアメリカ映画作家が追放されてしまいました。
さらに、「ビッグ5(パラマウント、MGM、20世紀FOX、ワーナー・ブラザーズ、RKO)」や「リトル3(ユニバーサル、コロンビア、ユナイテッドアーティスト)」と呼ばれていた主要映画制作会社8社すべてに、独占禁止法が適用されることになります。きっかけとなった訴訟はパラマウント訴訟と呼ばれ、これによって各社とも自社で抑えていた劇場網である映画館を手放さざるを得なくなり、メジャー各社は最大の収益源であった劇場を手放すことになってしまいます。「垂直統合システム」が崩壊し、興行側が自由に競争できるフリー・ブッキング制に移り、各社はB級映画のような軽い作品を制作する余裕が無くなってしまいました。
加えて、新しいメディアである「テレビ」が普及したため、映画の動員数が深刻に減少していきます。こうした状況に頭を悩ませた映画業界は、「テレビには真似のできない作品を作ろう」と、ワイドスクリーンを導入したり、大掛かりなセットや大量のスターを起用した大作主義で対抗しました。しかし、制作陣の疲弊や、本数の減少による新人監督の機会減少によって映画界はさらなる不調に陥ります。
こうして、「古典的ハリウッド」の黄金時代が終焉を迎えました。
そうした状況の真っ只中にあった映画界ですが、ミュージカル映画というジャンルは引き続き人気を保っており、「巴里のアメリカ人(1951)」「雨に唄えば(1952)」「バンド・ワゴン(1953)」などが名作として残っています。
ディズニーアニメでは、オムニバス形式の作品が続いていた中で、戦後はじめての長編作品として、「シンデレラ(1950)」が公開されます。この作品で初めて、ディズニーとしては外部からソングライターを雇うという選択をします。ウォルト・ディズニーは「ティン・パン・アレー」を訪れ、そこで出会った作家陣たちの力によって、「ビビディ・バビディ・ブー」のヒットに繋がったのでした。
その後も、「不思議な国のアリス(1951)」「ピーターパン(1953)」「眠れる森の美女(1959)」などから名曲が誕生しました。
これらの音楽は、もちろんクラシック音楽史には記載されるわけがないですし、かといってロック中心史観のポピュラー音楽史的にも「黒人音楽」に対する「商業的な白人のポップス」という位置づけによって「敵」となっていたために音楽史に記載されることは無く、たくさんの楽曲が残っているにもかかわらず歴史記述として一番目が向けられにくい分野だと思います。
フランス映画では、ジョルジュ・オーリックの音楽が重要となりました。通常、クラシック音楽史の記述では、戦前、エリック・サティに共感した「フランス六人組」のうちの1人としてひっそりと登場するオーリックですが、戦後は映画音楽の分野でポップスヒットを生み出していたのです。『赤い風車(1952)』『ローマの休日(1953)』『悲しみよこんにちは(1958)』などの音楽が特に知られ、『赤い風車』の主題歌「ムーラン・ルージュの歌」は特に世界的ヒットとなりました。
◉映画音楽は新たな「ポピュラー」化へ
ミュージカル映画の分野では、1950年代後半に上演された3大名作ミュージカル「マイ・フェア・レディ」「ウエスト・サイド・ストーリー」「サウンド・オブ・ミュージック」は、1960年代にすべて映画化され、その楽曲とともに世界的ヒットととなっていますが、このようにブロードウェイに原作を求めたものばかりになってしまいました。
さらに、1955年の映画「暴力教室」にて、ビル・ヘイリーによる主題歌「ロック・アラウンド・ザ・クロック」が一大センセーションを巻き起こし、「若者の反抗」の象徴としてとらえられるようになっていきました。ここからアメリカ音楽は若者文化が席巻し、一気にロックンロール旋風が巻き起こります。
ハリウッド映画の低調に加え、上記のような流れを持って1960年代に入り、映画音楽にも新たな潮流が生まれてきます。劇伴にもジャズやポップ・ロックのサウンドが導入されはじめたのです。そういった音楽を牽引した筆頭が、ヘンリー・マンシーニです。『ピンク・パンサー』シリーズや、TVシリーズの『ピーター・ガン』のテーマ曲が良く知られています。
ヘンリー・マンシーニは、主にオードリーヘップバーン作品を担当したことでも有名となり、『ティファニーで朝食を(1961)』の劇中歌「ムーン・リバー」はスタンダード曲となりました。
『酒とバラの日々(1962)』の同名テーマ曲も有名となり、多くのジャズミュージシャンやヴォーカリストが取り上げるスタンダード曲となりました。
ヘンリー・マンシーニにつづいて、劇伴やTVシリーズでのサウンドトラックは、クラシカルなもの一辺倒から脱却し、ジャンルを越えた試みがなされるようになります。それをもたらしたのは、ジャズシーンでアレンジャーなどとして活躍していたミュージシャンの映画音楽参入が要因のひとつとして挙げられます。
ジョン・バリーは地方のジャズ・バンドや軍楽隊を経てプロデューサー・アレンジャーとなり、1962年からの「007シリーズ」のテーマでインパクトを与えました。
クインシー・ジョーンズは、少年期にはレイ・チャールズとバンドを組んでいたり、バークリー音楽大学卒業後にはカウント・ベイシー、デューク・エリントン、サラ・ヴォーンといったジャズ界の大御所たちのアレンジを手がけたりといった活動をしていましたが、1960年代からはプロデューサーとしても活躍し始め、さらに映画音楽にも参入したのでした。この段階では映画『夜の大捜査線』などのサウンドトラックが評判となったのでした。(クインシー・ジョーンズはのちにマイケル・ジャクソンのプロデュースも手掛け、アメリカのポピュラー音楽界における著名な功労者の一人となります。)
ラロ・シフリンもジャズを出自として、サウンドトラックに影響をもたらしたミュージシャンです。1966年からのテレビシリーズ「スパイ大作戦( Mission: Impossible)」のテーマは非常に有名です。
70年代にもこの傾向が引き継がれ、デイヴ・グルーシンはフュージョンサウンドを映画音楽に持ち込みました。また、ビル・コンティは『ロッキー』で有名となります。
ディズニー映画では、1964年に『メリー・ポピンズ』という実写映画が作成され、劇中歌「チム・チム・チェリー」がヒットしました。しかし、1966年にウォルト・ディズニーが死去したことにより、ディズニー社はここから30年近くのあいだ、模索期に突入することとなります。
◉シンフォニックスコアの復権
このような風潮の中、1930年代~40年代のハリウッド映画初期に音楽おいて主流だった、マックス・スタイナーなどのクラシックのロマン派を直接引き継いだスタイルを、70年代に復権させた1人の人物があらわれます。それがジョン・ウィリアムズです。70年代初頭から注目され、1975年の『ジョーズ』の成功により、映画音楽界を代表する存在となりました。
その後『未知との遭遇('77)』『スターウォーズ('77)』『E.T.('82)』などの音楽で成功を続け、完全なるハリウッド流シンフォニックスコアの復権となりました。
(※繰り返しになりますが、このような19世紀ロマン派的な映画音楽は、もうクラシック音楽史に決して入ることはありません。この時代になると「ミニマルミュージック」や「電子音楽」といった実験的現代音楽が学問的な主流となり、それ以外の音楽は完全に問題外となっているのです。)
また、80年代に入ると、イギリスの映画『炎のランナー(1981)』ではギリシャの作曲家ヴァンゲリスによる音楽が、イタリアの映画『ニューシネマ・パラダイス(1988)』ではエンニオ・モリコーネによる音楽がヒットしました。
◉1990年代~ ディズニー新時代
さて、1966年にウォルト・ディズニーが死去して以来、長い模索期に入っていたディズニー映画ですが、華麗な復活を遂げることとなりました。
『リトル・マーメイド(1989)』『美女と野獣(1991)』『アラジン(1992)』『ライオン・キング(1994)』などで、音楽で新しさをアピールすることで人気を取り戻し、新時代を迎えることとなったのです。
これらの映画では、ハワード・ワシュマン作詞、アラン・メンケン作曲による楽曲が広くヒットしました。
◉21世紀~
2000年代に入るとディズニー映画では、『ターザン』や『ブラザー・ベア』で、元ジェネシスのフィル・コリンズが音楽を担当したことが注目すべきポイントです。また『リロ&スティッチ』では、エルヴィス・プレスリーの楽曲など既存曲の積極的使用が特徴となりました。
そのほか、劇伴の分野では、70年代末以降、ロマン派的なシンフォニックサウンドで第一線に立ち続けるジョン・ウィリアムズが、往年の『スターウォーズシリーズ』などを引き続き担当していたほか、00年代からは『ハリーポッターシリーズ』などでも大成功しました。さらに、映画音楽として非常に有名になった例としては、『パイレーツ・オブ・カリビアン』のハンス・ジマーも挙げられます。
2010年代では、ディズニーでの『塔の上のラプンツェル(2011)』や『アナと雪の女王(2013)』のヒットがトピックに挙げられるでしょう。
さらに、ミュージカル史でも触れたように、2010年代後半は『ララランド』('16)や『グレイテスト・ショーマン』('18)といったミュージカル映画がヒットしたことで、映画にとって音楽との関連性・重要性がまだまだ健在であることを示したでしょう。
