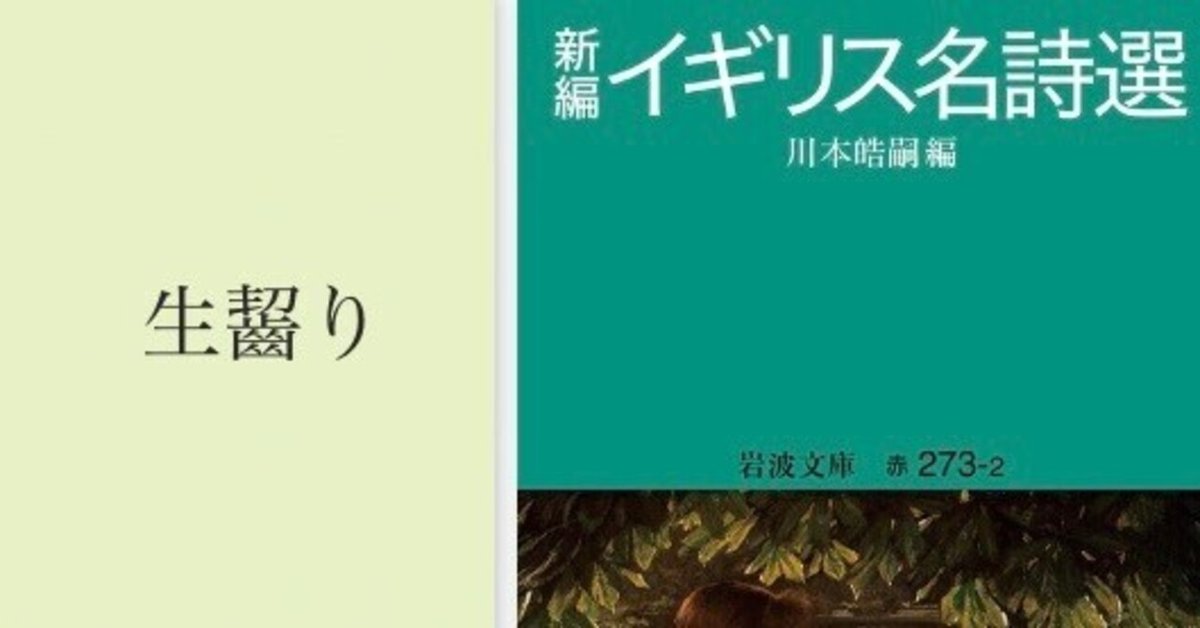
生齧り
急遽発生した待ち時間。二、三十分であれば、ぼーっとしてるだけでやり過ごせるが、一時間以上になるとそうはいかない。
そんなときどうするか。とっておきの方法がある、読書だ。結局いつもの読書かよ。そう、結局いつもの読書である。
*
知人から一時間遅れる、との連絡が入ったとき、私は高揚した。
待ち合わせ場所の近くに、未訪問の本屋があることに気づいて、どうしても覗いてみたいとうずうずしていたからだ。
店内を物色し、一冊選び、読書する。こうすれば一時間くらい余裕で潰せる。
こういう流れで本屋を訪ねると、普段は関心の外にある本が輝いて見えたりして、新しい出会いに結びつくことが多い。今回もそうなるといいなと胸が高鳴る。
最終的に購入にいたったのは、川本皓嗣編『新編 イギリス名詩選』(岩波文庫)。待ち時間を過ごすのに、これほど最適な一冊はない、間違いない。
*
待ち時間の間、目を通した範囲で、特に印象に残った一節を紹介したいと思う。
「自分など信用しないこと。自分の欠点を知るためには、
手伝ってもらうがいい、すべての友とーーすべての敵に。
生齧りの学問というのは危ないものだ。」
(アレグザンダー・ポープ:文、川本皓嗣編『新編 イギリス名詩選』岩波文庫、P111)
「初めて仰ぐ雲や山は、これが最後の雲や山かと見える。
だがやっとそこまで来ても、行く道はいよいよ遠く、
難儀は増す一方なのを
見てとって、人は身震いする。」
(アレグザンダー・ポープ:文、川本皓嗣編『新編 イギリス名詩選』岩波文庫、P113)
アレグザンダー・ポープというイギリスの詩人の作品から、二節引用した。
人によっては顔を顰めそうな内容だが、個人的にはグッとくる。この文章が印字された栞を自分で作り、本に挟んでおきたいくらい気に入った。
生齧りの学問が危ないというのは、まさにその通りで、人は学び始めの時期がもっとも自己過信に陥りやすい。
人は学べば学ぶほど、自信を失い、謙虚になっていくというのが私の持論だが、それは、どの学問領域の老練な研究者であっても、未だ解明できていないことを開陳し、自身の限界を隠さない姿勢を見せているからである。そういう研究者を目の前にしながら、構わず自信満々でいつづけるのは難しい。
そのことを自覚したとき、胸に到来してくるのが、上に引用した二つ目の文章、それが示す感覚。先に進めば進むほど、目的地が遠のいていくように感じるのだ。
こう考えると、「学ぶ」という行為には、多分に被虐性が含まれていると言えるかもしれない。
※※サポートのお願い※※
noteでは「クリエイターサポート機能」といって、100円・500円・自由金額の中から一つを選択して、投稿者を支援できるサービスがあります。「本ノ猪」をもし応援してくださる方がいれば、100円からでもご支援頂けると大変ありがたいです。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
