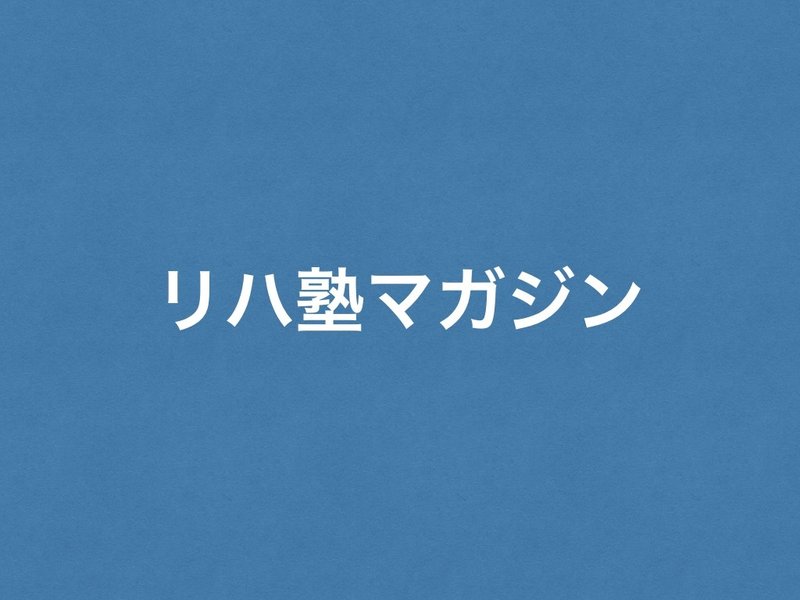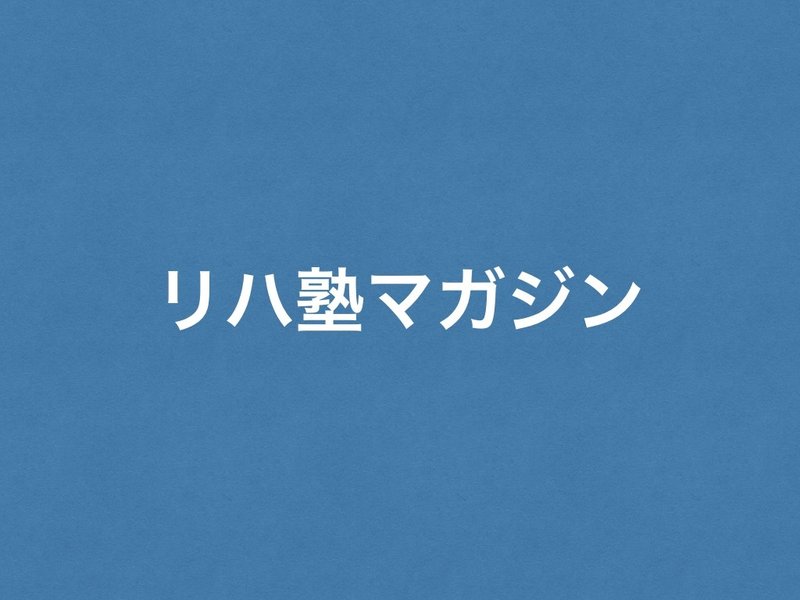筋力だけにフォーカスしてはいけない理由
リハ塾の松井です!
歩行や階段昇降、起居動作、各種ADL動作など、我々セラピストが一つのゴールとする動作において、関節がどの肢位でも適切な筋力を発揮できることが動作パフォーマンスにおいて重要です。
MMTは筋力の評価ですが、決まった肢位で評価しているので、例えその肢位でMMT5と判定されても、どんな場面でもその筋力を発揮できるとは限りません。
関節の動きは、屈曲/伸展、内転/外転、内旋/外旋と3軸の動きがあります。
理想は全ての方向、肢位においても劣ることなく筋力を発揮