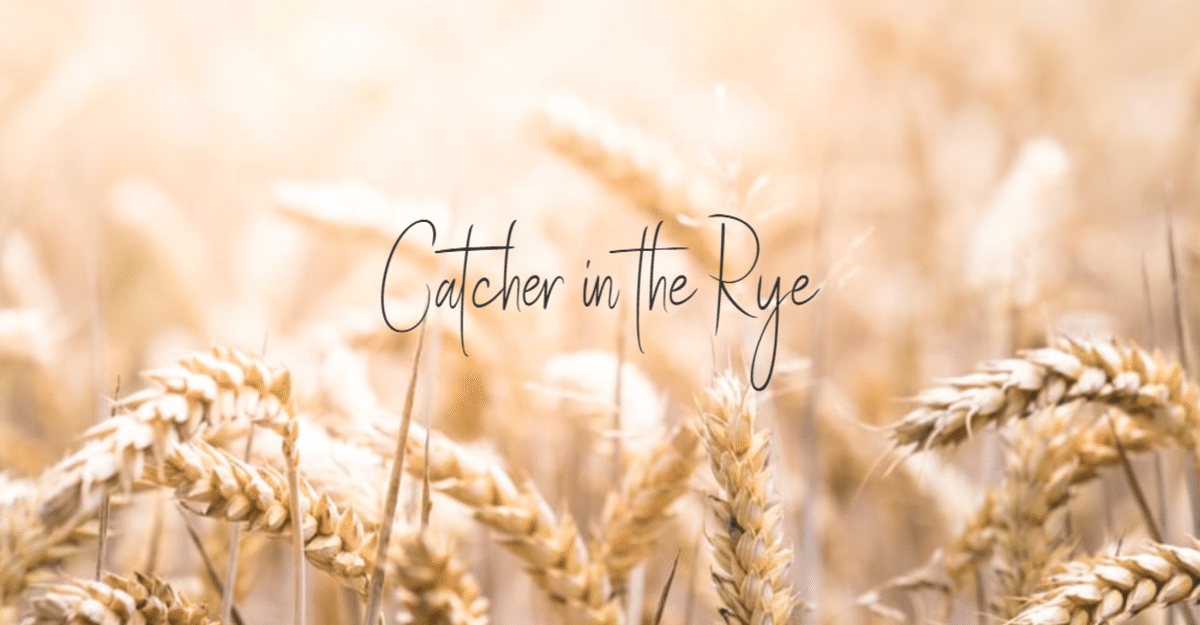
落ちるピーター・パン『キャッチャーインザライ』
今回のnoteでは、Catcher in the Rye (1951)『ライ麦畑でつかまえて』J・D・サリンジャーの作品を取り上げる。
I’m not sure what name of the song was that he was playing when I came in, but whatever it was, he was really stinking it up. He was putting all these dumb, show-offy ripples in high notes, and a lot of other very tricky stuff that gives me a pain in the ass.
おれが入ってきたとき彼が弾いていた曲の名前は定かじゃないが、なんだったかにせよ、甚だしく曲を腐らせていた。彼はそのまぬけな、ひけらかすような震音を高域で鳴らし、またそのやたらにこねくり回したテクはおれを苛つかせた(nite訳)。
個人的この作品は原文で読むのがベストだと思っている。なぜなら主人公ホールデンの特徴的な語りのリズムーーわざと乱暴な言葉を使いたがる未熟さ、聴衆あるいは世界に語りかけるような独特な「you」の使い方ーーは日本語に翻訳しきれないニュアンスを含んでいるからだ。ネット上ではこのひねくれものホールデンに対して嫌悪感を示したり、共感できないといった感想を必ず見かけるものだが、もっと深く味わってみれば、この本を読み進めるにつれ、ひねくれものの少年が愛おしくなってくるはず……そんな思いから、勢いでこの記事を書いてみた。
以下ネタバレ注意。文章の無断転載禁止(プロバイダー開示かけます)。
独り歩く少年
主人公ホールデン・コーフィールドは三日間に渡り巨大な都市New Yorkを彷徨歩く。
I 've lived in New York all my life, and I know Central Park like the back of my hand
New Yorkを知り尽くした上で、ときに注意深く、ときに夢遊病者のように街路を徘徊するホールデンは観察者としての目を持っている。
“[…]when somebody really wants to go, and even walks fast so ad to get there quicker, then it depresses hell out of me“
群衆を眺めるホールデン
目的を持って急ぐ人々を嫌悪しつつ、彼自身は“[…] I'm travelling incognito,”(Salinger 73)と自身を語り、匿名性を保持しようと試みる(彼は妄想の中でさえも秘匿しようとするI was concealing(Salinger 195))。偽名を多用し、“I didn't want anybody to notice me”(Salinger 195)と個人の特定を避ける彼の態度は、都市の在り方と近代的自我に着目したヴァルター・ベンヤミン(1892-1940)が考察した、遊歩者が群衆に紛れ、隠れ家を求める姿に重なる。
「長い時間あてどもなく街を彷徨った者はある陶酔感に襲われる。一歩ごとに、歩くこと自体が大きな力をもち始める。それに対して、立ち並ぶ商店の誘惑、ビストロや笑いかける女たちの誘惑はどんどん小さくなる。[…]禁欲的な動物のように、彼は、見知らぬ界隈を徘徊し、最後にはへとへとに疲れ果てて、自分の部屋に――彼にとってよそよそしいものに感じられ、冷ややかに迎え入れてくれる自分の部屋に――戻り、くずおれるように横になるのだ。」
ハシッシュの吸引になぞらえてBenjaminが語るこの「陶酔」は、ときに銃に撃たれたように装おい、まっすぐ歩けずに溺れるイメージに取り憑かれるホールデンの状態に似ている。実際彼は酒の有無にかかわらず「追憶としての陶酔」に常に酔った状態であるといえよう。
ところで、パサージュ論におけるキーワードの一つは「想起」だ。
博物館に入らずとも“I knew that whole museum routine like a book.”(Salinger 155)と細部を思い起こすことの出来るホールデンのまさに得意とするところである。ここで再びBenjaminを参照しよう。
「いうまでもなく、人にとって個人的であるようなかなり多くのものが、集団にとっては内的なものである。個人の内面には感覚、つまり病気だとか健康だという感じがあるように、集団の内面には建築やモード、いやそれどころか、空模様さえも含まれている。」
なるほどホールデンは天候にさえ弟の存在を連想している(150,153)し、リフレインされる“the sun wasn't out”という天候描写は、201ページにおいて弟アリーの墓参りの記憶と結びついていることが明らかになる(後述)。
「落ちる」こと
悪酔いし孤独感に苛まれたホールデンは最後の隠れ家を求めて冬園、セントラルパークにたどり着く。しかしそこで妹のために買ったレコードを落とし、湖に落ちかけるといった「fall」を経験した彼は家に帰ろうと決意する。
彼は既に語られた者、遺跡、記憶、古いものに郷愁を抱き、それらが「現在」に対して無力であることを憂いている。それは彼が過去に安らぎを見出す傾向を持っているからだ。そんな彼の性質は反抗的な家出少年らしからぬものであるが、この矛盾こそが、彼がどこか憎めない「人間らしさ」を持つキャラクターとたらしめている所以であり、同時に自身精神を追い詰める要因にもなった。彼は子供ながらにして既に失ったものを振り返り続ける回顧者なのである。
大人ぶって堕落したような(fall)行動を真似てみても、彼は自分の大切なものが死んで(fall)しまうことを極端に恐怖している。風化しない過去や死なない人間など存在しないにもかかわらず、だ。彼のそういった現実と向き合いたがらない危うい面はどこかピーター・パンの姿を想起させるーーーーもっともピーターパンは「落ちる」ことなく永遠に「飛び」続けるのであるが。
回帰すること
それでは何故、都市を歩きまわり家に帰ることを先延ばしにしようとしたホールデンは結局「home」へと回帰してしまうのか。この問いを考えるためにまずは彼が属する時代のコンテクストを参照したい。
帰還兵士の多くは、健全な雇用市場と将来に対する楽観的な展望に勇気づけられており、デート、結婚、家族を作ることに対し熱心な傾向にあった。1950年代に、男性の結婚年齢の中央値は24.3歳から22.6歳に、女性の場合は21.5歳から20.4歳に低下した。
サリンジャーについて論じられる際よく用いられるアメリカの社会情勢の話となるが、1948年から1953年の間でかの国は過去30年を上回る出生率を記録し、1954年には米国史上最大の1年間の人口増加を経験した。国の人口は1950年代に1億5170万人へ、そして1960年までには1億8,070万に増加した (Boucher 6)。また、1930年の大恐慌という困難を経験した戦後の親世代は子どもたちの生活を良くするために理想を体現しようとしたらしい(Hendricks 19)。この時代の概観を鑑みると、間違いなく本作品の主人公はその恩恵を享受しているといえるだろう。彼は裕福な家庭の息子であるだけでなく、自他ともに認めるnice(Salinger 14)な両親の子どもである。よってホールデン自身の「home」、「結婚」に対する考えも自身の常識に依拠した範疇を出ることはないと推測できる。
たとえば、ホールデンが性を意識するとき、そこには「結婚」という概念が立ち現れる。ホテルで娼婦と性交渉に及べば“[…] in case I ever get married or anything”(Salinger 121)の練習になるだろうと想定し、バルティモアでは少女たちが将来下らない男と結婚するのだろうと想像し気を滅入せる彼は、恋愛を経てからでないとsexyになれないことを自覚している節がある(191)。彼のデート相手サリーも「家庭home」に属する人間だ。またデートの際に彼女を泣かせてしまったホールデンが真っ先に恐れたのは彼女の家において権威を持つ父親である(173)。
“the queen of phonies”(Salinger 152)であるにもかかわらずサリーが結婚相手としてホールデンを惹きつけるのは、セックスアピールで彼の性的本能を刺激しているというよりむしろ一貫して主人公が執心する「home」を連想させる女性であるからに他ならない。ホールデンは“I felt like marrying her”(162)と、彼女との結婚を意識する。考える(think)ではなく無意識的に感じる(feel)のである。彼はこう感じた自分をcrazyだと留意するが、これは実のところ全くホールデンらしい思考の働きなのだ。一方サリーはホールデンの夢より現実的なプランを提示する(“[…] I mean after you go to college and all, and if we should get married and all.”(172)大学へ行ったりしてから……)。
西部への逃避を夢見ることでホールデン「家」への執着から離れようと試みた。しかし彼はその逃避先でも、美人と結婚し子どもを持ち安住しようとする。これは彼にとっての常識的な将来を西部に移植しただけであるといって良い。
“A room. Or a house. Or something you once lived on or something-you know”
という作文のテーマに対して野球のミットについて書いたホールデンは、「家」を「家にまつわる思い出」にすり替え事物としての住処に言及することを避けた。New Yorkでの放浪中固定電話へ電話を掛けることに躊躇や困難を覚えるのも、ホールデンが「家」を敷居として強く意識していることの表れである。「家」という敷居を境界線として捉えるならば、そこには当然内部と外部があると考えられる。内部を家庭、つまり「home」と仮定すれば、red hunting hatをかぶり、New Yorkという外部世界を歩く主人公はアウトサイダーであるといえるだろう。しかし、彼が心から求めてやまないもの、かつて失ってしまったものは彼の(記憶のなかの)homeのなかにしかもはや存在しえないのである。
永遠に失われるもの
都市を歩いているときでさえ言及、想起されるという点で、彼の弟アリーは物語のテクスト上最もホールデンに近しい存在といえる。彼が何故アウトサイダーホールデンに親和性を持つのかというと、死者として過去に住むアリーは「今」happening(Salinger 220)から永遠に除外されている者であるからだ。
アリーの死に対して感情を爆発させたホールデンが壊したのが窓であった“ […]I broke all the goddam windows with my fist, just for the hell of it”(Salinger 50)ことも興味深い。彼のこの行為は、家という「内側」から弟が「窓」の外へと去ってしまったことへの絶望を切ないほどに示している(そういえばピーターパンは窓から家を飛び出したのであった)。
今もなお「家」の内部に属する妹フィービーがアリーは死んだのよ、と宣言することでも明らかになるが、ホールデンの回想の中でも常にアリーは疎外され続ける存在として想起される(フェンスの外側にいる弟、墓地に置き去りにされる弟といった形で)。
私は個人的にCatcher in the Ryeで一番胸を衝かれたのは、ホールデンが雨の日の墓参りを回想するシーンだ。
It wasn’t too bad when the sun was out, but twice – twice – we were there when it started to rain. It was awful. It rained on his lousy tombstone, and it rained on the grass on his stomach. It rained all over the place. All the visitors that were visiting the cemetery started running like hell over to their cars. That’s what nearly drove me crazy. All the visitors could get in their cars and turn on their radios and all and then go someplace nice for dinner – everybody except Allie.
“ 太陽が照っているときはマシだけど、雨のときの墓参りは気が狂いそう(になる。雨が降り出すと皆車に戻りラジオを付けてどこか良い場所へディナーを食べに向かうんだーーーだだ一人アリーだけを残して( 202 nite)”
太陽が照っていない…(but the sun still wasn’t out…)というフレーズは実は何度も作中リフレインされている。16章においてはホールデンのアリーについての言及は目立たなかったが、こうした情景描写という細かい部分からも弟の死が常にホールデンの意識へ影を落としていることが確認できる。
続けて幾つかある回想の中でも、笑いすぎたアリーが椅子から落ちかけた、というシーンに注目してみよう。ここで強調すべきなのは、あくまで彼は落ちかけたjust about fell offのであって、落ちてしまった訳ではないという点である。Mr. Antoliniがホールデンの将来をfalling (Salinger 243) と表現し、彼の愛する妹フィービーが回転木馬から落ちてしまうことを心配したこと、
If they’re running and they don’t look where they’re going I have to come out from somewhere and catch them.
子供たちが落ちそうになれば僕がそれを受け止めるcatcherになろうと夢語ることから察せられるように、「落ちること」がすなわちホールデンにとっては子どもの成長、大人への参入を意味するのなら、この回想においてアリーは決して「落ちる」ことのない人物であることがこの場面で確認されていると解釈できる(飛び降り自殺したJames Castle(221)について直前で言及されるのは、彼のfragilさもホールデンがcatchすべきだったーーしかし救えなかったーー対象として記憶しているのではないだろうか)。
アリーはその死によって家庭内に回復しようがなく、そして「落ちる」べき肉体、bodyもない。よって彼は作品の中で唯一ホールデンが心配する必要のない子どもともいえるのである。
とすれば、ホールデンが物語の終盤で自らの存在が消失してしまうような恐怖に苛まれたときとっさにアリーに助けを求めたのも説明がつくだろう。
“I thought I'd just go down, down, down, and nobody'd see me again” .
この、都市に埋没し消えかけるという感覚にホールデンはdisappear(Salinger 257)することに心底恐怖し、下降することを拒絶することで彼の「home」への志向の揺るがなさを肯定してしまうのである。
第二次大戦後の精神的荒廃に晒されていた若者者たちは中産階級の物質主義を否定し、新しい価値を求めており、サリンジャーは反抗、狂気、放浪などの文脈で理解され1960 年代初頭には若者たちの反抗のバイブルとして、アメリカ文化にしっかりと根を下ろした
↑一般的に評価されるサリンジャー像
大人に敵意をしめす反抗的少年、アンチヒーローとして表象されてきたホールデンが、どこか憎めないキャラクターであるのは、彼の痛々しい喪失感、失われたものを追い求める直向きさが読者の心を捉えるからなのかもしれない。そうした、まるでいつかは弾けてしまうような泡の世界は先に挙げたような『ピーターパン』やカズオ・イシグロのテーマにも描かれてきた。
人によってはそれが幼いころの無邪気さであったり、夢であったり、自分の世界が壊れるはずがないという信じる盲目さだったりするのだろう。
If a body catch a body comin’ through the rye
わざと歌詞を間違えて歌う主人公のように、原題を直訳することなく意訳した「ライ麦畑でつかまえて」という言葉は、失ったものを追い求め、そのせいで自分が血を流していることにも気づかぬまま雨に打たれ続けているホールデン自身が無意識にだれかに「つかまえて」ほしいと願っていることを暗に示す言い得て妙な邦訳であるのかもしれない。

参考文献
Barash, David P, and Barash, Nanelle R. Madame Bovary's Ovaries: A Darwinian Look at Literature. New York: Delacorte Press, 2005.
Boucher, Diane. The 1950s American Home. Shire, 2013, pp.6-7.
Hendricks, Nancy. Daily Life in 1950s America. Greenwood Pub Group, 2019, pp.
Thomas, Lewis. The Fragile Species. Simon & Schuster, 1992.
Salinger, J, D. The Catcher in the Rye. Little, Brown and company. New York, 1951.
ヴァルター・ベンヤミン. 『都市の遊歩者』今村仁司 [ほか] 訳 東京 : 岩波書店, 1994.
ヴァルター・ベンヤミン「セントラルパーク」浅井健二郎編訳・久保哲司訳『近代の意味』
(ベンヤミン・コレクションⅠ)筑摩書房, 1995, pp. 357–415.
ヴァルター・ベンヤミン .ベンヤミン・コレクション3─記憶への旅. 浅井 健二郎 編訳 , 久
保 哲司 翻訳,ちくま学芸文芸,1997.
近森 高明. 「問われるストリート・エスノグラフィーの方法 : 都市の無意識を歩く作法 :
アレゴリーの力 : 遊歩と痕跡 : 都市の記憶を読む技法について」 国立民族学博
物館調査報告 巻80, 2009, 53-71.
都甲幸治 「サリンジャーにおける愛と死——『ライ麦畑でつかまえて』はアメリカでどう読まれてきたか」『文學界』2003, 317-22.
