
【宿題帳(自習用)】仮説の立て方

仮説の立てかたについて。
(作業)仮説というのは、学問にとっても、人生にとっても、とても大切なものだ。
モデルと言い換えてもいいが、とりあえずの推理・説明を考えて全体像を見直すのだ。
そして、違ったら仮説を直せばいい。
情報を相対化することによって、外観で物事を判断しなくなる。
丸谷才一の「思考のレッスン」には、このあたりのコツがよくまとめられている。
「思考のレッスン」(文春文庫)丸谷才一(著)
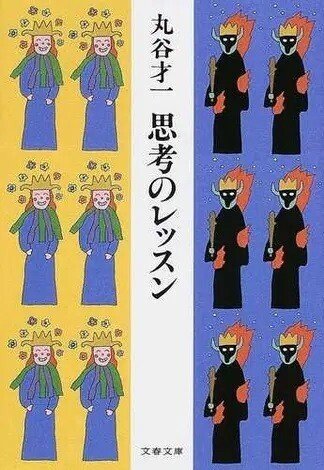
考える上で、まず大事なのは、問いかけである。
いかに「良い問」を立てるか、ということ。
「不思議だなあ」という気持ちから出た、かねがね持っている謎が大事である。
実際、古くからだと思っていたり、どこでもと思っている事柄が、自分の周りだけのことだったりする。
自分のなかに他者を作って、そのもう一人の自分に謎を突きつけて行くとよい。
謎を自分の心に銘記して、常になぜだろう、と問い続けることで謎を明確化、意識化することが大事。
そのために自分の中に「他者」を作って、その自分に謎をつきつけてゆくことだ。
「当たり前なんだ」とか、「昔からそうだったんだ」と、納得してはいけない。
他者の目、異文化の目で眺めることだ。
次に、「比較と分析」ということが非常に有効だ。
ある主題なり、対象なりの中で、特に、自分が関心を抱いている要素にこだわって分析してみる。
さらに、別のものと比較しながら分析すること。
そして、直感と想像力を使って仮説を立てること。
「仮説は大胆不敵に」、「あっと驚くようなものを立てるという芸術的奔放さが大事」という。
仮説を立てるには、「多様なものの中に、ある共通する型を発見する能力」が必要だと書いている。
その際に重要なことは、「見立て」であるとして、
古今和歌集の時代に発展した「見立て」…その意味と技法
和歌のレトリック~技法と鑑賞(3)見立て:その1
菅原道真や在原業平の和歌にみる見立ての役割
和歌のレトリック~技法と鑑賞(3)見立て:その2
次のようにいう。
同種のものが別の外観で存在することを発見する。
同類を見つけて同類項に入れる。
これは、他の言い方でいえば、「見立て」である。
「見立ての手法―日本的空間の読解」磯崎新(著)
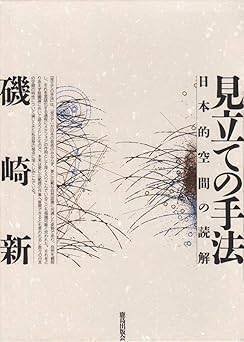
「見立て日本」(角川ソフィア文庫)松岡正剛(著)太田真三(写真)
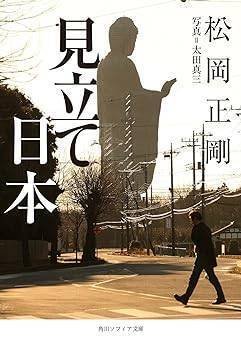
この「見立て」というのは、アナロジー(類推)ということで、元々は、「和歌・俳諧などで、ある物を別のものと仮にみなして表現すること。なぞらえること」だが、一見、かけ離れたところに、同じ構造を見抜くことである。
「神さまと日本人のあいだ―「見立て」にみる民族の感覚」(Fukutake Books)朱捷(著)
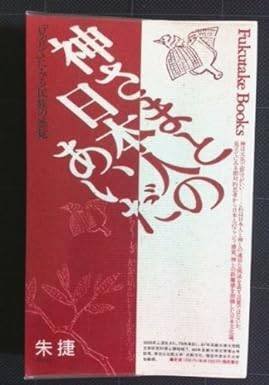
「見立てとうがち―躍動する詩心」(江戸川柳の美学)江口孝夫(著)

例えば、フロイトは、深層心理を説明するのに、氷山を思い浮かべたのかもしれないが、氷山を見て深層心理を発見したのかもしれない。
そうした発見というのは、実は、詩人の行為と似ている。
意味が定まった言葉から脱却して、全く新しい意味を発見するのが詩人だからだ。
「詩人たちの世紀―西脇順三郎とエズラ・パウンド」(大人の本棚)新倉俊一(著)
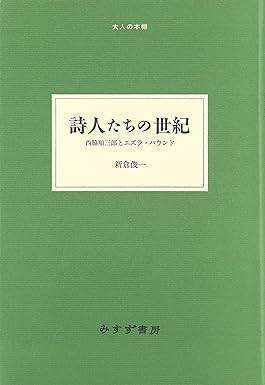
【参考文献】
「見立て」は、パロディと言い換えてもいい。
ジョームズ・ジョイスの「ユリシーズ」は、
「ユリシーズ〈1〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)
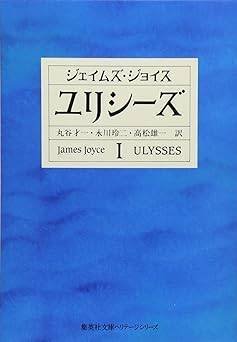
「ユリシーズ〈2〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)
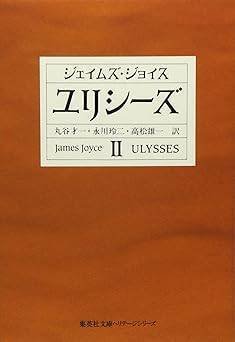
「ユリシーズ〈3〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)
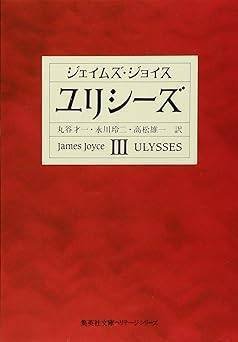
「ユリシーズ〈4〉」(集英社文庫)ジョイス,ジェイムズ(著)丸谷才一/永川玲二/高松雄一(訳)
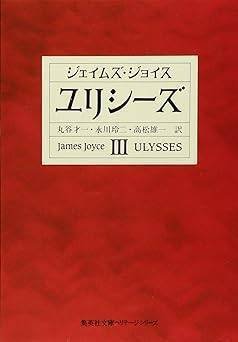
ホメロスの「オデュセイア」のパロディだし、
「オデュッセイア〈上〉」(岩波文庫)ホメロス(著)松平千秋(訳)
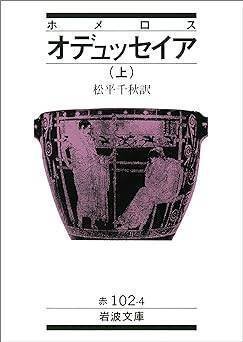
「オデュッセイア〈下〉」(岩波文庫)ホメロス(著)松平千秋(訳)
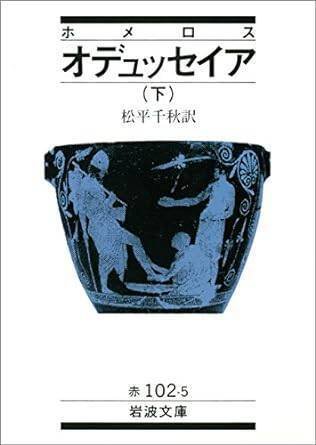
ニーチェの「ツァラトゥストラはかく語りき」は、
「ツァラトゥストラかく語りき」(河出文庫)ニーチェ,フリードリヒ・W.(著)佐々木中(訳)
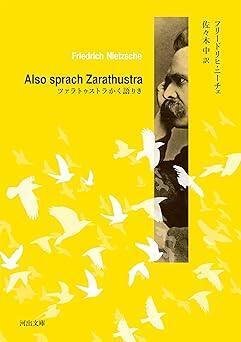
仏教の「如是我聞」から取っていて、
作品は、「新約聖書」、
「聖書 新共同訳 新約聖書」日本聖書協会(著, 編集)共同訳聖書実行委員会(訳)
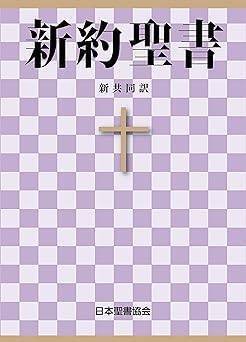
主人公は、ゾロアスター教の創始者のパロディになっている。
「ゾロアスター教」(講談社選書メチエ)青木健(著)
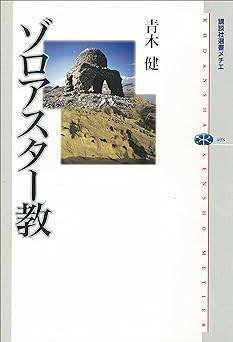
井上ひさしは、漱石のパロディで「ドン松五郎の生活」とか「吾輩は漱石である」など多くのパロディを書いている。
「ドン松五郎の生活」(新潮文庫)井上ひさし(著)
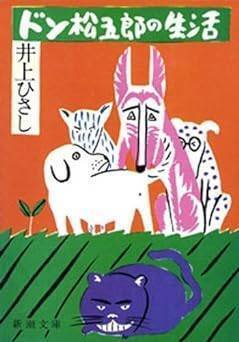
「吾輩は漱石である」(集英社文庫)井上ひさし(著)
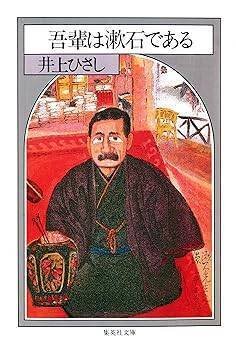
すべての作品は、過去の作品のパロディだ、ともいえるのである。
きれいな言葉で言えば、古典に現代的価値を見出しているのである。
型を発見したら、その型に対して、名前をつけること。
例えば、フロイトが、息子の母親に対する愛着を、「オイディプス・コンプレックス」と名づけたように。
名づけによって考えが整理されて、思考がさらに深まる。
「キーワード思考」と言い換えてもいいが、キーワードが生まれるのは、全く別な物を「見立て」る力があるからだ。
思考は、文章の形で規定される。
文章力がないと、考え方も精密さを欠く。
大ざっぱになったり、センチメンタルになったり、論理が乱暴になったり。
文章力と思考力は、ペアである。
「対話的な気持ちで書く」というのが書き方のコツだと。
自分の内部に甲乙2人がいて、いろんなことを語り合う。
考えるときには対話的に考える。
しかし、それを書くときには、普通の文章の書き方で書く。
書き出しに挨拶を書くな。
書き始めたら、前へむかって着実に進め。
中身が足りなかったら、考え直せ。
そして、パッと終れ。
「見立て」の達人は、昔、「見巧者」(みごうしゃ)といったが、達人はもちろん、丸谷才一だが、斎藤美奈子も鋭い。
「読者は踊る」のタイトルだけを見ているだけでも楽しい。
「読者は踊る―タレント本から聖書まで。話題の本253冊の読み方・読まれ方」斎藤美奈子(著)
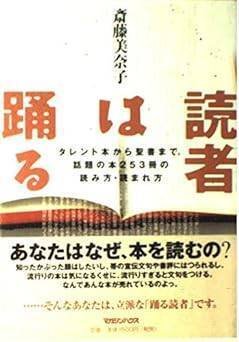
一部を抜き出すと・・・・・・
「消えゆく私小説の伝統はタレント本に継承されていた」
「字さえ書ければ、なるほど人はだれでも作家になれる」
「芥川賞は就職試験、選考委員会は『じじばば』の巣窟だった」
「女子高生ルポの商品価値はナマ写真ならぬナマ言説」
「汝、驚くなかれ。いまどきの聖書の日本語訳」
「死ぬまでやってなさい。全共闘二十五年目の同窓会」
「みんなひれ伏す『在日のアウトロー』という物語」
「〈すわ震災〉のチャンスを即興芸で語った人たち」
「哲学ブームの底にあるのは知的大衆のスケベ根性だ」
「学問は人の上に人を造る。超勉強法は疑似出世本だ」
「身内の自慢話が〈だれも悪くいわない本〉に化ける条件」
「近代史音痴の国で起こったお笑い歴史教科書論争」
「マニアなのかマヌケなのか。クラシック音楽批評の怪」
例えば、全共闘と暴走族を「見立て」て、次のようにいう。
「確かに、中国の簡体字で書いた立て看(立て看板)を書いていた全共闘とスプレーで漢字表記の落書きをする暴走族には同じ傾向がある。
団塊世代に批判的なのは、昭和30年代生まれの人が圧倒的に多い。
彼らは「全共闘には乗り遅れ、暴走族には早すぎた」世代だったりもするのだが、考えてみれば、全共闘と暴走族はひと皮むかなくても同質ではないだろうか。
両者の特質を列挙してみればわかることである。
反権力志向である
群れてあばれる
警察を当面の敵とする
スタイルを重視する
結束がゆるい
意外と思想がない
「族」は壁にスプレーで小むずかしい漢字は書くが、長じて作家や評論家となり「あの頃、僕たちは政治の季節のなかで・・・・・・」などと書いたりしないだけマシか。
斎藤には、この他にも、
「妊娠小説」、
「妊娠小説」(ちくま文庫)斎藤美奈子(著)
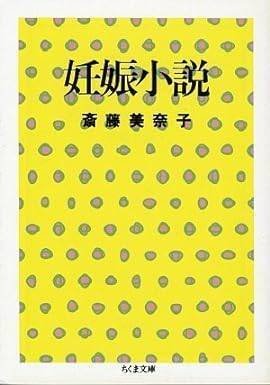
「紅一点論」、
「紅一点論―アニメ・特撮・伝記のヒロイン像」(ちくま文庫)斎藤美奈子(著)
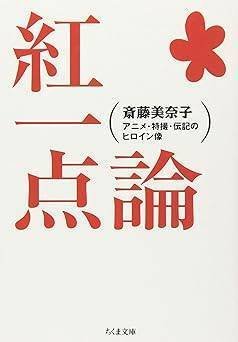
「文壇アイドル論」、
「文壇アイドル論」(文春文庫)斎藤美奈子(著)
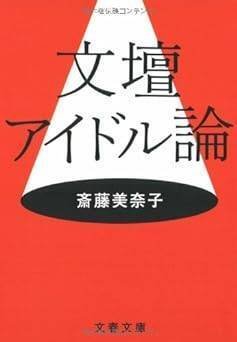
など面白い「見立て」がいっぱいだ。
【関連記事】
【雑考】垂直思考と水平思考
https://note.com/bax36410/n/nc041319885eb
【雑考】対位法的思考
https://note.com/bax36410/n/nef8c398b72cb
【雑考】複雑系思考法
https://note.com/bax36410/n/neaab25206650
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
https://note.com/bax36410/n/nad27a9739ea4
