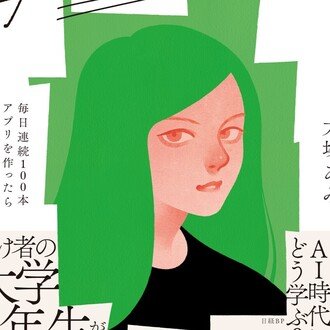誰でもできる100日の魔法| 100日チャレンジはなぜ100日なのか
副業で成功したい、資格を取らなきゃいけない、毎日の勉強が続かない…
――そんな経験はありませんか?
何度計画を立てても続けられず、途中であきらめてしまうことは、意思の弱さが問題なんだ。高学歴エリートみたいにはできないんだ。
私もこのように考えていました。
気づけば目標ばかりが増えて、どれも中途半端に終わってしまう。
そんな状況を打破するために効果的なのが「100日チャレンジ」です。
こで役立つのが、期限を区切ることで集中力と行動力を引き出す「100日チャレンジ」。
これをうまく活用すれば、理想に一歩ずつ近づけるはずです。
100日チャレンジは本になりました!↓
執筆エピソードはこちら!↓
1. 「100日」という時間の意味
まずは「100日」という期間そのものの意味について考えてみましょう。たとえば、創作や語学学習、あるいは資格試験の勉強など、成果が「可視化」されやすいものをイメージしてみてください。
1週間や2週間のスパンでは、目に見えて結果が出る前にモチベーションが途切れてしまうかもしれません。しかしながら、半年や1年といった長期スパンでは、ゴールにたどり着く前に飽きてしまったり、日常の忙しさに流されてしまいがちです。
それに対して、およそ3ヶ月ちょっとに当たる100日間は、気持ちを集中させるには十分な「緊張感」を保ちつつも、完走後の自分をイメージしやすいちょうどいい長さだと言われています。
たとえば英単語を覚えるなら「1日30個を100日続ければ3000語覚えられる」という具体的な数字が生まれますし、毎日何らかの作品(テキストでもイラストでも)を作るなら、100点の作品というわかりやすいゴールが設定できます。このように、100日は「ある程度まとまった成果物」を作り上げるのに向いた絶妙な時間設定といえるのです。
2. 続けるための仕組みづくりとしての「100日」
成果を出すためには、ただやみくもに「がんばる」だけでなく、継続できる仕組みを作ることが不可欠です。
人はモチベーションの波に左右されやすい生き物であるため、「気合」だけに頼ってしまうと、ちょっとしたトラブルや体調不良、スケジュールの変化であっという間にリズムが崩れてしまいます。
そこで役に立つのが、100日チャレンジのように「終わりが明確」な枠組みを用意する方法です。
大切なのは、先に“完了する日のイメージ”を設定しておくことです。
たとえば「この日までが勝負」と決めると、そこまでは自分の中でギアを上げて走るモードに入れますし、万が一ペースが乱れたときにも「あと○日だからもう少し頑張ろう」と心を立て直しやすくなります。
また「100日だけは集中して行う」と周囲に宣言することで、周りも理解しやすく、応援やサポートを得られる可能性が高まります。こうした仕組みづくりの観点でも、「期間が区切られている」ことには大きな意味があるのです。
私のチャレンジはこちら!
3. 「4ヶ月−2ヶ月ループ」の有効性
100日チャレンジを継続的に活用していくうえで、さらに有効なのは、「4ヶ月(約120日)−2ヶ月」のループを意図的に組み込む方法です。これは約4ヶ月間は高負荷の作業や学習に集中し、その後の2ヶ月間は負荷を下げて休養を優先するといったリズムをつくることを指します。
人は長期間にわたって高いテンションを維持し続けると、どこかで必ず心身の限界がきます。さらに、その後のモチベーションが大きく落ち込んでしまうと、回復に時間がかかり、結果的にパフォーマンスが下がってしまうケースも多いのです。
そこに「100日」という小さめの集中期間を挟むことで、思い切り力を出し切りやすくなります。そして、20日間で“成果を形にする期間”を設けたのち、残りの期間はペースを落としつつ、心身のリセットと新たなインプットに充てるわけです。
普通の人と同じペースで穏やかに仕事をしたり、あるいは思い切って海外旅行に行ってまったく別のことを楽しんだり。「高負荷のとき」と「負荷を下げるとき」を意図的に分けてあげることで、長い目で見た時の成長と健康のバランスを取れるようになります。
4. うまくいかないこともある—休むために生きるという視点
もっとも、こうした理想のリズムがいつも計画通りにいくわけではありません。
私は以前、本を書いた際、「100日以内に書き上げる」という目標を掲げました。最初は「100日あれば十分だろう。集中すれば一気に形にできるはずだ」と意気込んでいました。
ところが、蓋を開けてみると、執筆経験のなさから何度も書き直しを繰り返すことになり、気づけば半年以上も経過。企画段階から数えると、最終的には8ヶ月ほど費やしてしまったのです(こちらに全部書いてあります。)
それでも、11月末にはようやく原稿が完成し、「これでしばらくはゆっくり休める」と思っていたところ、12月には海外での講演の予定が入り、ヨーロッパへ飛ぶことになりました。
そこでようやく落ち着いて過ごせるようになり、せっかくならと3週間ほど旅行を満喫しました。
その時、「1月末まではしばらく仕事を抑えめにしてリラックスしよう」と思っていたのですが、ありがたいことに想定以上に仕事を頂き、12月中旬に帰国してからは暦に関係なく休む間もなく動き回る日々が続きました。
実は、本の執筆が終わったあと、私は燃え尽き症候群のような状態に陥っていました。最初の1週間はゲームや動画を見て過ごすだけで、「もう文章は書きたくないし、プログラムを見るのも嫌だ」というくらいモチベーションが下がっていたのです。しかし、ハンガリーでの講演を機に再びヨーロッパへ行き、ウィーンやブダペスト、コペンハーゲンなどを観光するうちに、徐々に精神的に回復していきました。
ヨーロッパでは英語が通じるので言語の壁は特に感じず、現地の知人も親切で色々なところに連れて行ってくれて、とても楽しい日々を過ごしました。
また、日本から地理的に遠い場所にいることで、いつものプレッシャーから解放され、不思議とストレスを感じにくかったのです。日々違う風景を楽しみ、体を動かしているうちに、「次の仕事をしたい」という気持ちが自然に戻ってきました。そして帰国する頃には、周囲の人から「元気になったね」と言われるほど回復していたのです。
私は、1ヶ月ほどのまとまった休みは確保するべきだと考えています。理想とはいえ、実際は仕事を優先してしまうことも多いのですが、きちんと休む重要性は変わりありません。
なぜなら、私自身は仕事のためではなく、遊ぶために生きているからです。
そしてこの生き方を実現するには、報酬や時間的自由を得るための交渉力が欠かせません。その交渉力を身につける手段の一つとして、私は「100日チャレンジ」を位置づけているのです。
おわりに
「100日チャレンジ」は、単なる目標達成メソッドのように見えますが、実は人生全体を俯瞰し「どのタイミングで集中し、どのタイミングで休むか」を戦略的に決定する方法でもあります。
スパンを短く設定するメリットは、目標が具体化しやすく達成感を得やすいこと。さらにその結果を定期的に積み重ねながら、自分の「休む権利」を守るための交渉力を高めていくことにもつながります。
無理なく継続できる仕組みを作り、大きな負荷をかける時期と休養する時期を明確に分ける。そして、遊びや旅行、プライベートの時間も満喫することで、次の100日に向けて新鮮なエネルギーをチャージする。
それが「誰でもできる100日の魔法」の本質ではないかと思っています。
よろしければ、はてなブックマークへの登録をお願いします。
いいなと思ったら応援しよう!