
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 22 植物や生き物の世話ができる その2
22 植物や生き物の世話ができる 【育て方】
「学校に進学すると何らかの動物の世話をしたり、植物を育てたりすることが必ずある」のですから、家庭でも、6歳までに動植物を飼育・栽培する経験をしておきましょう。
学校での意義と同じ様に次の5つが育ちます。特に、凸凹タイプの子どもは、2番と5番のために飼育栽培を経験させた方がいいです。
1. 豊かな感情、好奇心、思考力、表現力をはぐくむ
2. 自分以外の相手を思いやる心、他者とのコミュニケーション能力
育てる
3.豊かな人間形成の基礎を育てる
4.命の尊さを学べる
5.何かをやりとげる責任感を養える
子どもは、あまり植物を育てたいとはいいません。大抵は、「猫か犬か を飼いたい」ということが多いです。たまに、テレビとかの影響で「ハムスターを飼いたい」と言う子もいるようですが。
子どもは「飼いたい」と言ったのに、すく飽きてしまって世話をしなくなることがあります。特に、凸凹タイプの子どもにはそいう子が多いです。逆に言うと、それが特性です。好奇心が強く、興味が移りやすいのです。
習い事でも同じようなことが起こりますが、動物を飼うのはそれとは違いいます。習い事はやめれば終わりですが、動物は捨てるわけにはいきません。法律違反になるからです。
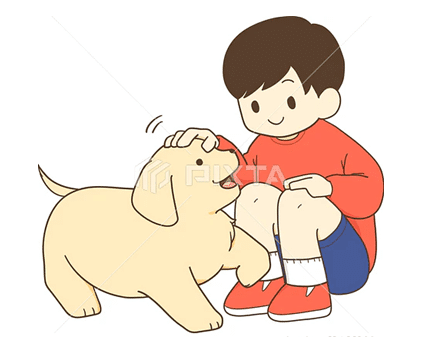
だから、飼う前によく話し合って「覚えて」で「世話をずっとする」ことの言質を取っておきましょう。できたら、紙に書いて貼っておくことをお勧めします。
その時の【セリフ】を書いておきます。
【セリフ】お母さんとこどもの「やりとり」を使っています。
母「犬を飼いたいんだね(「共感」)。」
子「そう。大ちゃんのとこに赤ちゃんが3匹生まれた。」
母「それを、大ちゃんがくれると言っているのね。」
子「そう、くれる。」
母「あなたは、犬が好きそうだもんね(「想像」)。」
子「犬、好き。」
母「では、正式にお願いしてください。」
子「どうしても、犬が飼いたいです(「すみません」)。」
母「『お願いします』も言ってください。」
子「お願いします。」
母「犬を飼うって大変なのよ。一度飼うと、犬が死ぬまで止められません
(「覚えて」)。分かった?1回言っておいて。」
子「死ぬまで飼います。」
母「それから、世話も大変よ。餌やりと散歩をしないといけません
(「覚えて」)。」
子「餌やり?散歩?」
母「そう。餌、つまりご飯を朝と夕方に2回あげること。毎日、散歩に連れ
て行ってあげること。」
子「さんぽってなぁーに。」
母「散歩はね、犬に運動させてあげるの。そうしないと、病気になるのよ
(「覚えて」)それから、おしっこやうんちをさせてあげるのよ。分から
なかったら、初めはママがついていってあげるけどね(「想像」)。」
子「ありがとう。」
母「さぁ、犬を飼ったら、あなたは何をするんですか?」
子「餌やりと散歩。」
母「大事なことだから、きちんと『です・ます』でいいましょう(「覚え
て」)。」
子「犬を飼ったら、餌やりと散歩をします。」
母「分かりました。ちゃんと守ってよ。ママ、覚えておくからね。そうだ、
あなたがするお仕事を、紙に書いてここに貼っておきましょう。毎日する
のよ。それでもいい?」
子「いいよ、ママ。」

最後に、犬や猫を飼うのを止めた方がいい場合を書きます。
・家族や子どもに犬や猫のアレルギーがある場合
➪近所の医者ですぐ調べてくれます
・子どもが感覚過敏で「ペットの死」を受け止められないで、トラ
ウマになるかもと判断した場合
・約束しても、子どもが「すぐ世話に飽きてしまう」と判断した場合
以上の3つの場合は、動物を買うのを諦めましょう。何か、植物の栽培を勧めたらいいでしょう。お薦めは、プランターで嫌いな野菜を育てることです。それを収穫して食べたら、たちまち野菜嫌いが治ります。
つまり、トマト嫌いはミニトマトを、ブロッコリー嫌いはブロッコリーを育てましょうということです。
いいなと思ったら応援しよう!

