
MBTI INFJが解説 MBTIとユング心理学はデマ?→統計学における質的データしか使ってない! 解説記事
ユング心理学やMBTIは、かなり強い批判のある理論です
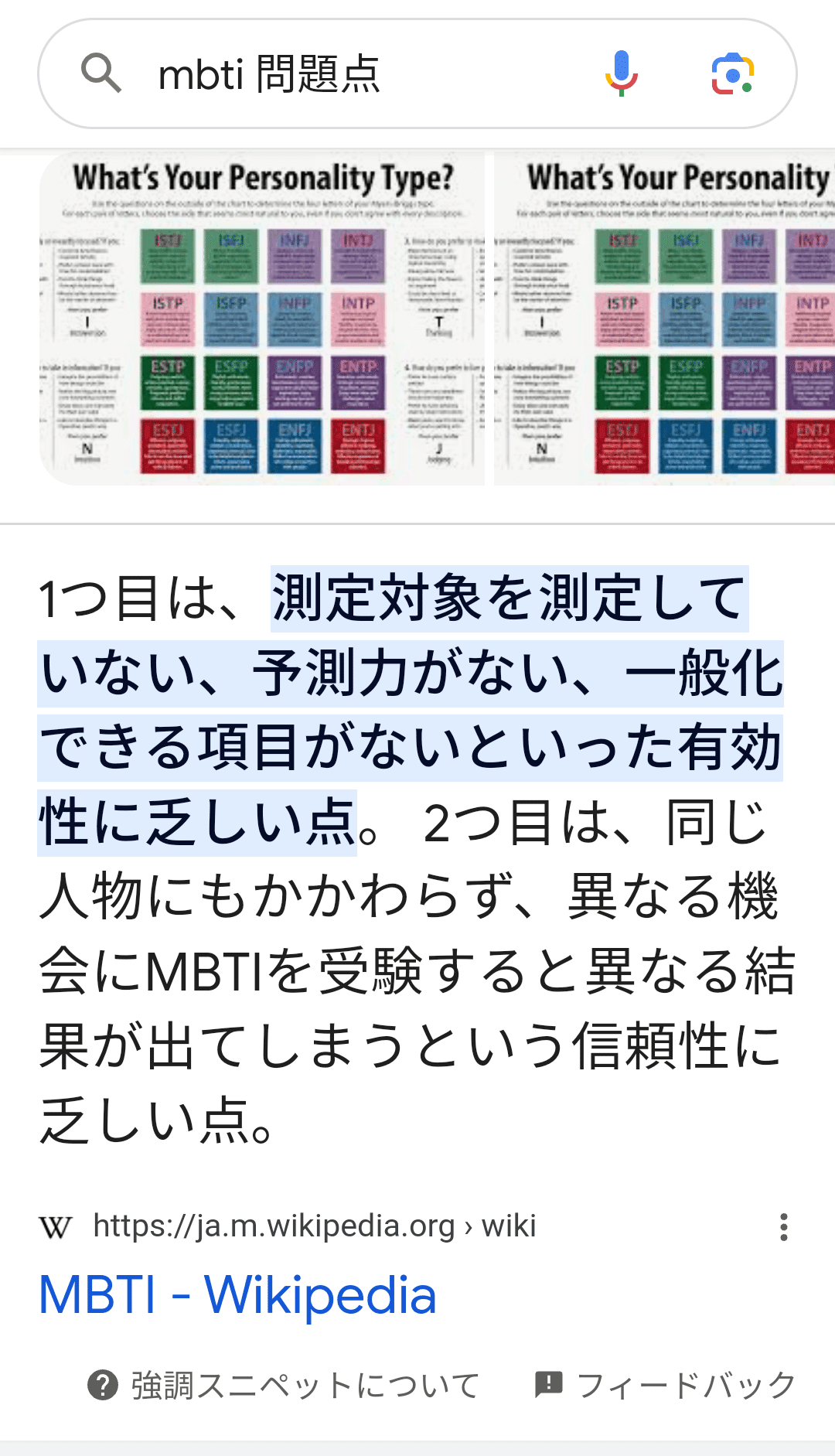
他には、この方の記事がわかりやすい
wikipediaにも批判の項目がある

私の考えは、次です
タイプ論はフィクションです。
統計学の、質的データと量的データの概念を当てはめて考えると、MBTIやユング心理学は質的データしか使っていない(名義尺度と順序尺度しかない)
しかし、差延を埋める努力をすれば、対人間攻略に使える概念道具になります。有用です
以下、解説
統計学用語の解説
質的データ、量的データ、名義尺度、順序尺度だけ分かれば、説明できます
※次のサイトから引用してます
まずデータの種類には大きく分けて(1)質的データ(Qualitative data)と(2)量的データ(Quantitative data)の2つがあります。
質的データとは、分類したり種類を区別したりするためのデータです。そのままでは足したり引いたりといった演算はできません。
これに対し量的データとは、数値として意味があるデータです。そのまま足したり引いたりの演算ができます。
名義尺度:「取引先名」や「製品名」など、分類のために区別はできても、順序はつけられないデータです。
順序尺度:「1位/2位/3位」、「優/良/可」、「Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ」など順位や成績の評価など順番に意味があるものです。区別ができ順序がつけられるデータです。
名義尺度は、分類のために利用されるデータ
順序尺度は、区別と順序がつけられるデータ
それでは解説。
タイプ論は、統計学における質的データのみを扱う。
タイプ論と統計学の概念同士の対応は以下の通り。
○名義尺度
→タイプ論の機能分類(思考型や感覚型とかのこと)
・種類の違いはあっても、能力に優劣なし。担当する役割が違うだけ
例→外向感情Feは他人の気持ちを読み取る機能。内向思考は論理を掘り下げる。外向思考は数値やデータを取り扱う機能
○順序尺度
→タイプ論における、主機能、補助機能、劣等機能の分類。
・機能の働きの得意不得意を比べている。苦手な機能も、鍛えることができる
・定義がゆるいから数値化できない。
MBTI、ユング心理学の曖昧さは、統計学の質的データしか使ってないせい。
量的データを一つも使っていない。
しかし、質的データだけでも、ある条件を満たせば、タイプ論は役立つ
1苦手な機能を鍛えて成長する
2理論の差延を埋めて検証する
3対人間攻略に使える
1 苦手な機能を鍛えて成長する
ユングのタイプ論は確か、統合性の高い円満な性格を目指すための理論のはず(ソースわからん、ごめん!)
私は、自分の苦手な機能を知って、そこを鍛えるやり方を考えて実践してる。
例えばこの記事を参考にしてる
ほとんどのMBTIポエマーたちは、性格診断をやるだけで、応用してない。
努力をせずに駄文を書き散らすだけ。
あなたの自分語りに価値があるんですか?刹那1しかないんじゃないですか?
生存者バイアスを加味しても、成功者の話を聞く方が有意義じゃないですか?(桜井政博さんのチャンネルや、初耳学の森岡毅の話の方が有意義すよ)
内心の安定、ユングの個性化は各自勝手にやることでしょう?
ncoさんの書いたこの傑作noteをぜひ見ていただきたいですね😊
2 理論の差延を埋めて検証する
差延はジャックデリダの用語ですけど、私はこう定義して使ってます
・差延を埋める=ズレを捉える、ズレを調べる
タイプ論、MBTIという理論を軸にして、実際の人間がどこまで理論に当てはまるか、どこに差延が発生しているのかを検証していくプロセスが全て。
要するに応用しましょうってことです
MBTI公式サイトにもプロセス大事って書いてる
MBTIは、受けられた人の利益を最優先に考えていますので、検査結果だけで人の性格を判断したり、診断することはありません。MBTIは、受けた本人が自分の検査結果をきっかけにしながら、一定の訓練を受けた有資格者のもとで、自分自身の理解を深めていくプロセスのほうを重視するメソッドです。
どのみち、統計学の定量的分析足りてないからフィクションだと思いますけどね。(ちゃんとした定量分析の論文はあるかもしれん、調べてないのでわからん)
個人的には、MBTIやユング心理学は、自己検証と応用を繰り返すだけで十分役立てられてるから、資格を取る意味がよくわからんです。
だからって軽んじる必要はないけどね
検証も応用もしないMBTIポエマーはもっと反省して🤗
3 対人間攻略に使える
他人の苦手な機能や能力の大雑把な推測ができる→対人攻略できる
この記事が詳しい
まとめ ユング心理学やMBTIのタイプ論って何なのさ?
タイプ論は器の大きさを測るざっくりした指標。
・性格に統合性があるかどうかを測る
・人間の能力傾向、能力の性質を測る
能力レベルを正確に測れるわけじゃない。タイプ論は質の指標の理論。
統計学における質的データで分析するもの
量的データを使わないなら、結局コレはフィクションなんですよ。
応用したら使える道具になるけどね
タイプ論を有効活用したいなら、プロセスを延々繰り返すしかないですね
・理論の構築
・差延を埋める努力
・理論の解体
・理論の純化、再構築
特に
○差延を埋める⇄理論の純化再構築
ココをやらないと価値がない
解説終わり!
オススメ記事です
