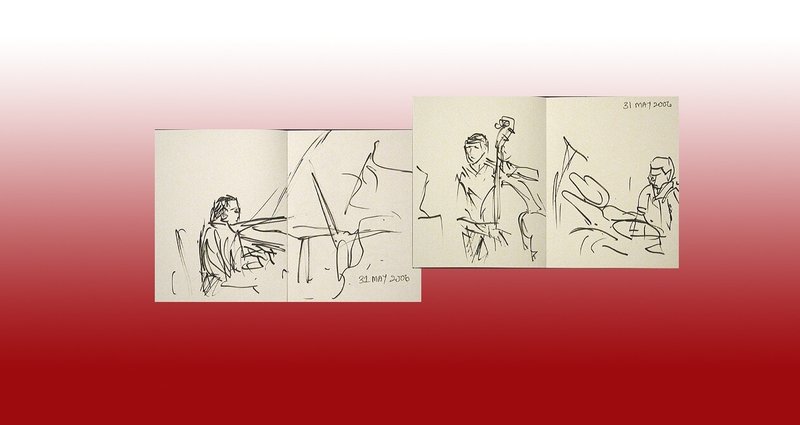記事一覧

China Girl by David Bowie
昨日まで中国に行っていた。大陸側、いわゆるメインランド・チャイナへははじめてだ。 10日間の日程、ずっと北京にいた。比較的低緯度の海に面した香港や台湾にくらべて、その気候や言葉以上に違いを感じたのはやはりその体制の違いか。いつも使っていたスマホのアプリはほとんどが使えず、持っていた書類が没収されることもあった。 中国からの帰国直後となった今月の21日の音楽、ややベタな選曲だけどデヴィッド・ボウイのこの曲を選ぶことにする。 ボウイがライブで語るように、このChina Girlは1970年代にイギー・ポップと一緒に書いた曲だ。 現代とはおおきく異なる当時の中国。その中国Chinaの名を冠した少女に対して、「青い瞳をあげよう(I'll give you eyes of blue)」、「世界征服を企む男をあげよう(I'll give you a man who wants to rule the world)」と尊大な妄言を吐く白人男の様は、現代では問題視されそうではある。この妄言や「雷鳴のごとき心臓の鼓動(I hear her heart beating as loud as thunder)」、「破裂する星(I saw the stars crashing down)」といった表現に、ドラッグの隠喩だとの説がある。そうしたダブルミーニングはロックの定番だから、きっとそうなのだろう。 ボウイがこの曲を書いた70年代、歌った80年代を経て、中国は世界の工場と呼ばれる経済大国になった。自由主義世界とは異なる価値観の、一党独裁の社会主義の大国になった。近年は、他国の情勢との連関もあって、不穏な危うさを感じさせる場面もある。 この曲が書かれた70年代なかば、デヴィッド・ボウイは東西冷戦の最前線のベルリンにいた。当時もすでに中国は社会主義陣営。チャイナ・ガールが否応なしに黙ってと言うところにも繋がってきそうだ。 And when I get excited My little China girl says Oh baby just shut your mouth She says, Shh... わたしたち日本はいちおう自由主義世界にいる。ここでどちらがどうというのは不毛だ。2016年のはじめに亡くなったボウイは冷戦下ですでに何かを予見していたのか。 中国から帰国してすぐ、ふとそんなことを考えてしまった。

The Times They Are A-Changin’ by Sinéad O’Connor
先日、地図について書いたときに最後に取り上げたボブ・ディランの名曲The Times They Are a-Changin’ (時代は変わる)。この曲は多くのシンガーにカバーされている。もともと変化に乏しい曲調のせいか、どれも歌詞のメッセージがはっきりと伝わってくる。 いつのものか不明だけど、昨年56歳で他界したシネイド・オコナーが歌うバージョンを見つけた。 先のnoteでは断片的に歌詞を引用していたけれど、じつは公開直前に削除した引用部分がある。描写が津波を連想させて、記事のテーマ的に不適切な感じがしたからだ。以下、その部分と拙訳を書いておく。 admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone 周りの水がどんどんと増してきて、 骨の髄まで浸ってしまうのを受け入れざるを得なくなる if your time to you is worth savin' then you better start swimmin' or you'll sink like a stone for the times they are a-changin' 自分の時代に救う価値があるなら いますぐ泳ぎだしたほうが良い さもなくば石のように沈むしかない 時代は変わるものだから この曲が発表された1964年にはまだ温暖化による海面上昇など想定されていなかったし、ディランがこの比喩で何を示唆していたのかわからない。しかしダーウィンの適者生存説のように、わたしたちも変化に適応していかなければならないことを歌っているのは明らかだ。 先日、突如わたしの使っていたMacBookが壊れてしまって、前回のnote更新はスマホからおこなった。このnoteも同じくスマホで書いていて、操作の勝手の違いがじつにまどろっこしく感じる。 いままでと同じように推敲しながら長文を書くのにはスマホからではかなりエネルギーが必要だ。たまたまパソコンが故障しただけなのだけど、なんだか自分の状況がこの曲でも歌われていることのような気がしないでもない。noteの書き方を変えるタイミングなのかもしれない。 いやいや、noteの書き方はほんのひとつのことにすぎない。身の回りから世間、政治、世界情勢と、あらためていろいろと変わり続けている。わたし自身こそアップデートが必要な時期が来ているようだ。 今日選んだ音楽映像のシネイドも、けっして幸せな形ではなかったけれど、変化し続けた生き様の表現者だった。