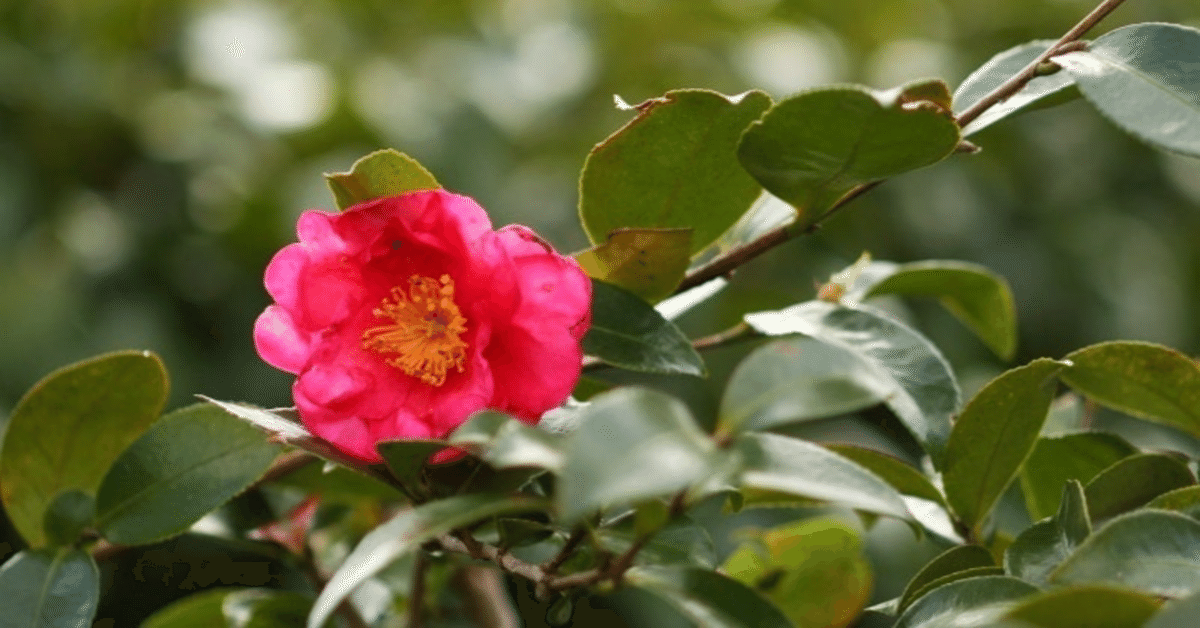
令和源氏物語 宇治の恋華 第八十一話
第八十一話 うしなった愛(十四)
弁の御許によってもたらされた知らせに薫は我が耳を疑いました。
あの美しい佳き人が病臥にあるとはどうしたことか?
公務も何もかもを忘れて宇治へ一路馬を駆る薫中納言の顔は青ざめております。
匂宮と姫君たちとの明るい未来を語り合っていたのはつい先日のことです。
きっとこの話を聞けば大君も生きる気力を奮い起こされるであろう、と早く愛しい姫にお会いしたい薫なのです。
宇治の山里には京よりもずっと早く冬が訪れており、梢には霜枯れた葉が色を失くし、馬が踏む草は乾いた音を立てております。
なんとわびしい。
やはりこのような場所では心細さも増すものよ。
気からの病でどうにかなってしまいそうではないか。
一刻も早く姫君たちを我が邸へお迎えしよう。
冴えた空気が頬を切るように鋭く吹き抜けますが、逸る君は意にも介しません。
見る間に宇治の山荘へと辿り着きました。
「大君さま、薫さまがお越しになられましたよ」
弁の御許が大君を励ましたが、ほんの少し頭を動かしたばかりで虚ろな表情を浮かべております。
「薫さまがお越しになりました」
もう一度御許が繰り返したことでその目に僅かな生気が宿ったように思われます。
「早く私を大君さまの元へ案内せぬか」
普段声を荒げない薫君の焦燥が大君への愛の深さかと女房たちには思われてなりません。
薫は大君の寝所に御簾を隔てた席に通されました。
「なんとも水臭いことよ。御簾を隔ててでは大君さまの御容態もわからぬではないか」
そう憤る薫に大君は優しげに声をかけました。
「薫さま、わたくしは今とてもやつれて見苦しいのですわ。女心と思ってお許しくださいまし。その代わりと言っては何ですが、わたくしの願いとして御簾の側までお寄りください。薫さまのお顔が見とうございます」
「そのような弱々しい御声でいらしてお労しい」
薫が御簾の側に寄ると透いたあちらの大君の様子もうっすらと窺えます。
「どうしてこのようなご様子になるまでお知らせくださらなんだ。私は何も知らずにいた自分を許せませんよ」
「突然にこのような状態になってしまいまして、わたくしも困惑しておりました」
この人を何とか励まして元気にして差し上げたいと強く願う薫はできる限りを尽くそうと決めました。
「弁、山の阿闍梨へは遣いを出したな?」
「はい。そろそろお越しになる頃合いかと」
「来られたらすぐに祈祷を始めていただくようお願いしなさい。私は片時もここを離れぬ」
そう毅然と言い放つ薫君が大君には誰よりも頼もしく思われるのです。
大君は近頃の物思い、行く末への不安から心休まる日などありませんでしたが、薫君が側にいられるだけで安心感を得られるようです。
薫はこの人のこと、匂宮と中君のことを気に病んで己の身を削っているのであろうと察しがつくのです。
「大君さまは何事も一人で抱え込もうとなさるのが悪い癖です。私も中君さまの行く末を心配する権利があるのですよ、後見なのですから。匂宮さまと先日話しましてね。中君さまを京にお迎えする準備をしていると伝えますと顔を輝かせておられました。頃合いを見て正式な妻として披露したいと思召されているのです。私はその真摯な姿勢にまことの愛を感じました。けして見捨てられることはありません。夫婦のことはその二人でしかわからぬ絆もあるでしょう。どうか大君さまは御心安くなさって下さい」
真実を語る強い視線に大君の心は溶かされてゆくようです。
「ありがとう、薫さま」
「これからはあなたの心配事を共に分かつと致しましょう。まずはお元気になっていただかなくてはなりませんね。中君ともども晴れて京へ移るのです。こんな山里ではよい薬師にも診ていただくこともできませんよ。まずは体も心も休めて回復されることです。よいですね」
「はい、わたくしなんだか安心して眠くなりましたわ」
「ではゆっくりお休みなさい。ここにずっとついていますからね」
「はい」
そうして大君はすうっと心地よい眠りに引き込まれてゆくのでした。
次のお話はこちら・・・
