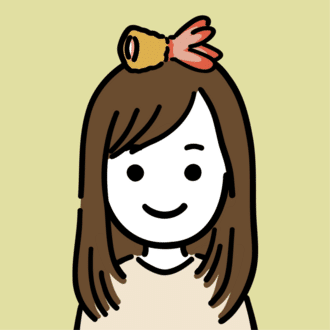わかる人にしかわからない?「具体と抽象」を読んで
気になっていた、こちらの本。
✅概要
永遠にかみ合わない議論、罵(ののし)り合う人と人。その根底にあるのは「具体=わかりやすさ」の弊害と、「抽象=知性」の危機。動物にはない人間の知性を支える頭脳的活動を「具体」と「抽象」という視点から読み解きます。
詳しくは本読んでほしいですが、おお!と思ったとこだけピックアップ。
✅わかる人にしかわからない
抽象度の高い概念は、見える人にしか見えない。(中略)
「わけのわからないことを言っている」と感じる人がいたとしたら、こんな風に考えるだけでも仕事のやり方や世の中の見方が変わってきます。「もしかしたら、私には見えていない抽象概念の話をしているのではないか」
「表面的なことではなく、そこから繋がっている本質的なことを語っているのではないか」
「わからない」と否定するのではなく、考え方を変える。これなるほどーーと思いました。
抽象画がいい例。
理解できずに否定してしまいがちだけど、このように考えたら、世界が広がって面白いかも。
✅なぜ「日本語」ではなく「国語」なのか
日常生活で言語として使うだけなら、「日常日本語会話」だけ学べば良い。
それをわざわざ時間をかけて、難解な長文を要約したり、自分の考えをまとめたりする練習をするのは、抽象と具体の往復運動という頭の体操のためなのです。
そこが「国語」という教科が、単に「英語」と同列の「日本語」でない決定的な違いといえます。
抽象と具体の往復運動だったって…知ってましたか?
これ学生時代から知ってたら、もっと意欲的に取り組めたのかな?🤔
いや、そんなことはないか笑
当時知ったとしても、「ふーん」程度で響かなかったと思います。
大人の今になって知るから、そうだったのか!と腑に落ちるんですかね。
✅感想
東大生が俯瞰の視点を持ってるとか、教授が何を言っているかわからないとか…
これらは「抽象概念」のレベルの違いだったんだなと。
この本を読んで、具体の世界に生きてるなーと反省したのですが、一つだけ抽象度が高く応用できてるかも?と感じることがあります。
それは「料理」です。
勝間さんがホットクックとヘルシオの料理本を出したとき、「もっとレシピ数を増やしてほしい」という声が多かった、と。
でも応用すれば、数少ないメニューでも展開していける。応用できない人は、どれだけ多くのレシピを載せたとしても、もっとレシピをくれ!となるよね…という話をしてました。
これに関しては、勝間さんの言うことが分かるんですよね。
塩分量の概念(総量の0.6%)と、蒸す、焼く、煮る等の代表メニューが各1つずつ把握できていれば、あとはなんとなく「こんな感じかな?」と感覚でできるようになりました。
結局、習慣なんですかね?
東大生(の多く)は普段から俯瞰の視点を持ってるから、抽象度が高い?
毎日料理してるから、個々のレシピがなくても抽象概念をとらえて応用できるようになったのかな?
ちなみに、どうすれば抽象化思考をうながすことができるのか?について。
多種多様な経験を積むことはもちろんですが、本を読んだり映画を見たり、芸術を鑑賞することによって実際には経験したことのない事を疑似経験することで、視野を広げることができます。
そうすれば、「一見異なるものの共通点を探す」ことができるようになり、やがてそれは無意識の癖のようになっていきます。
無意識の癖!
やっぱり習慣に近いものがあるんですかね?
ということで
本の解説はだいぶ端折ってしまったので、分かりにくい箇所もあったと思います。
興味ある方、面白いのでぜひ本読んでみてください!
ではでは。
いいなと思ったら応援しよう!