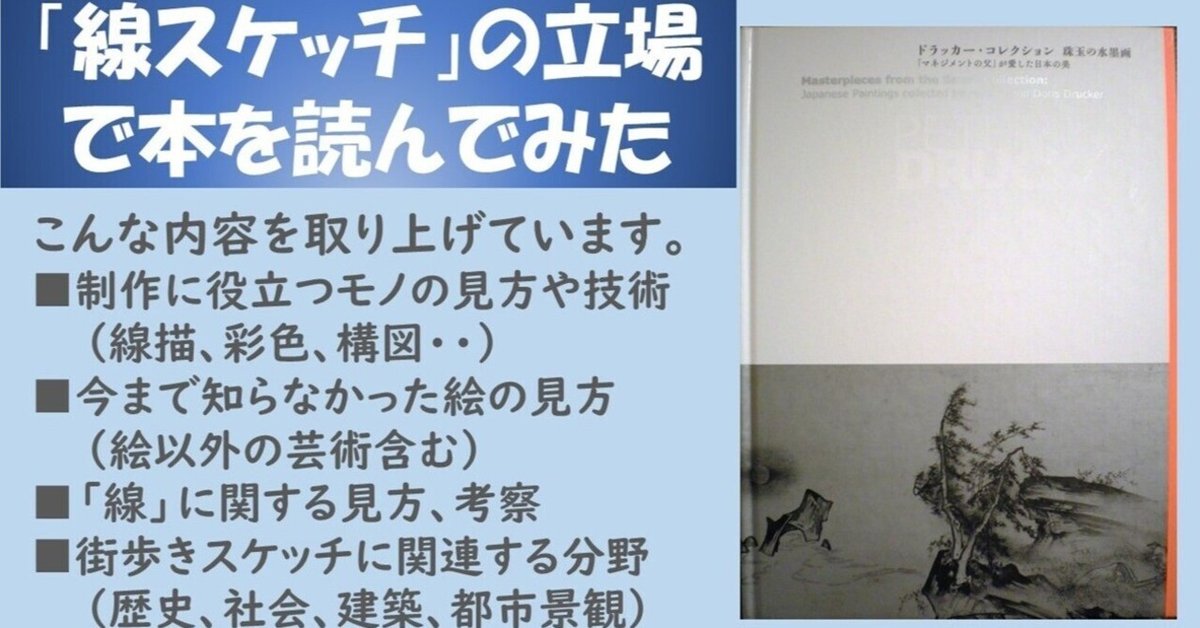
「ドラッカー・コレクション 珠玉の水墨画」千葉市美術館 美術出版(2015):西洋の知は日本美術の独自性をトポロジカル空間にあると見た!(その2)
(その1)から続く。
ドラッカーが語る日本の水墨画の独自性
日本美術へのラブレター
2015年の企画展の準備中に、1991年に執筆された未完の原稿がドラッカー家で発見され、上記小見出しの題名で本書の冒頭に掲載されました。
その中で、ドラッカーはコレクションを始めたきっかけと、1)日本美術は自分にとって何か、2)なぜ長年にわたって日本美術は新しい驚き、大きい感銘、喜びを自分に与え続けるのか、その二つの問に対する答えを簡潔に述べています。
要点を下に示します。
(1)日本美術には個性があるということ。一般に日本人はその”画一性”、また個人よりも”団体への帰属意識、組織化”が特徴と言われるが、日本の画家達はたいへんな個人主義者であり、特定の”絵画様式”が特定の”歴史区分”と結びつかないことが普通である。
(2)最初は琳派や狩野派に惹かれたが、室町の山水画に、その無限の多様性と深遠さ、その社会の価値の美的な表現と具現に親しむようになった。西洋美術と日本美術(室町水墨画)にある違いは観者のアプローチにある。前者では、芸術は鑑賞者に眺められるもの、見られるものだが後者は芸術は共に生きるためのもので、芸術は人の精神的環境になる。
ドラッカーは、日本の画家達は個人主義者だと言い切っています。特に江戸時代がそうだったと言うのですが、1960年代、1970年代に、海外はもちろん日本人も江戸時代の日本人画家達が個人主義者だとは誰も認識していなかったと思います。
もしあるとすれば、江戸末期から明治初期に見いだされ、独立した画家としてフランスで認められた浮世絵版画の北斎、広重、歌麿などの画家達に限られるでしょう。
「個人」が見えない日本人、組織に忠誠を尽くす日本人と現在でも通用する日本人像と対比させて、江戸時代の画家達の姿を講演の導入部で際立たせているのは、マネジメントの専門家であるドラッカーならではと思います。
もう一つの、西洋絵画と日本美術(室町水墨画)と何が違うのか、ドラッカーは、鑑賞者の立ち位置が違うと述べていますが、この点については、前回の島尾氏の水墨画入門書の最終記事で同様な趣旨を私は述べました。
注目したいのは、日本美術(室町水墨画)の場合は、芸術は共に生きるためのもの、精神的環境とまで言っていることで、これはドラッカー自身の生き方とその精神的支柱に関わる心からの言葉でしょう。
以下、彼の講演記録から、ドラッカーが挙げる具体的な日本美術の特徴と精神的環境を提供する理由を見ていくことにします。
(1)講演記録「ガイジンの見た日本美術」(1990年10月13日、於 根津美術館)松尾知子訳
ドラッカーは、根津美術館から講演要請を受けたときに、日本の聴衆に何を伝えようか、専門家でもないのに何が話せるだろうかと迷った末に、ある視点をテーマに選んだと講演の冒頭で話し出します。
それは、「自分に対して日本人及びアメリカの友人からいつも聞かれる二つの質問に関わる視点」です。二つ質問とは次の通りです:
●「ガイジンとして日本美術に何を見出すのですか?」
●「あなたにとって、他の国の美術と日本の美術とはどう違っているのですか?」
特に2番目の質問は、前回の記事を書くきっかけになった私の疑問、「日本の水墨画は中国と何が違うのか、特徴はあるのか」に直接対応しているので、西洋人の目でみた日本美術(室町水墨画)の特徴を知る大変貴重な講演記録と私は思いました。
それでは、早速各論を見てみましょう
■尾形光琳《蔦図(団扇)》
本作品のフリー画像がないため例示しませんが、団扇の代わりに扇面で、蔦の代わりに藤が描かれた、似た構図のメトロポリタン美術館所蔵の尾形光琳作《藤図(扇面)》をwikimedia commonsで見つけたので下に示します。

出典:wikimedia commons, public domain
以下にドラッカーの言葉を引用しますが、<蔦>を藤の<つる>に置き換えてお読みください。
(前略)この絵は基本的には抽象画であります。細い蔦が空間を仕切ると同時にそこにある種の空間を創りあげる、いわばノン・オブジェクティブ、非写実的な絵画なのです。葉の上下の空間がこれほどに深い感銘を与え、この絵を完全無欠にしているのです。この小さな扇面ほど余白を生き生きとさせ、それが絵の主題となっている他の抽象作品を知りません。そしてこれこそが、日本美術の特徴のひとつにほかなりません。
松尾知子訳、太字部分は筆者
ドラッカーは、収集を始めたごく初期に《蔦図》を購入しています。実は、尾形光琳の作品をもう一つ所有していますが、それは光琳らしさはあるものの、水墨画の花鳥図に近いものです。コレクションの中で琳派らしい作品はこの《蔦図》一点のみです。
ですからコレクションの主役である室町の水墨画ではなくこの作品から講演を始めるのは不思議な気がしますが、まだ日本美術が何か分からない初期であるからこそ、この琳派の作品の中にわけもなく惹かれた理由が潜んでいるのではないかと考えたのではないかと推測します。
実際「これこそが日本美術の特徴の一つ」と言い切るほど、この作品の日本美術のエッセンスに当時魅了されたのだと思います。
それは、写実的な蔦(藤)を描いているように見えながら実はそうではなく、光琳はある種の空間を創り上げていること、すなわち別の言葉では余白を生き生きとさせて、それが主題の抽象作品に仕上げていることだというのです。
しかし、ここでドラッカーはごく自然に「余白」という言葉を持ち出していることに、私は「おや!?」と軽い驚きを覚えました。
なぜなら、前回の記事『島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)。』4回シリーズの中でも幾たびか説明したように、「余白」の意味が西洋絵画と筆墨文化の水墨では異なるからです。
すなわち、西洋絵画では「余白」はただ未完成であることを示すのに対し、水墨では、「余白」は単なる空白ではなく、始めから絵画空間として存在していると。
もしドラッカーが購入当時そのような抽象空間の美に惹かれたのだとしたら、たとえ無意識だったとしても、欧米人の伝統的な感性と異なるものを持っていたことになります。
とは言え、アメリカでは、伝統的な西欧絵画に代わりジャクソン・ポロック、ウィレム・デ・クーニング、マーク・ロスコ等による抽象絵画が第二次大戦後隆盛になった状況を考慮すると、ドラッカーが購入を開始した1960年代の欧米人の空間把握の感性はもしかすると変わっていたのかもしれません。
ちなみに筆墨文化ではアクションペインティングや即興のパフォーマンスによる書画の抽象表現がはるか昔から知られていたので、現代抽象絵画は筆墨文化圏の人々には意外に受け入れられやすかったのではないでしょうか。
さてドラッカーは続けて西欧絵画と中国絵画の特徴と光琳の扇面と比較します。
ごく最近まで西欧絵画は叙景的でありました。中国絵画も独自の方法でありました。しかし、この光琳の扇面は叙述的描写ではなく、「デザインー意匠」なのです。(中略)デザインとは空間構成と関係するモノであり、デザインにおいては(中略)、常に最初に空間があり、そしてデザインによって余白を仕切られ、構築され、さらに限定されるのです。
松尾知子訳、太字部分は筆者
ここでドラッカーは先に引用した「空間創造」論をデザインと結びつけます。まず光琳の扇面は、叙景的な西欧絵画でも中国絵画の方法でもなく、「デザインー意匠」だと言います。そしてデザインの本質は空間構成と関係し、空間は、デザインによって余白を仕切られ限定されると見るのです。
しかし突然ドラッカーは「皆様はこれを日本が中国から学んだとおっしゃるかもしれません。」と私も含め誰もが考えそうな見方を提示します。
それは誰でも知るように日本の水墨画は、南宋の水墨画の輸入から始っており、しかも画家牧谿の著名な「柿図」を見れば誰もがそのように考えるだろうと、読者(ここでは聴衆)が言い出す前に自分自身が提示したわけです。

出典:wikimedia commons, public domain
しかしこのような見方を、ドラッカーはただちに否定します。
牧谿は中国人画家ではあるが、中国本国では高く評価されなかった。牧谿を評価したのは日本人であり、確かに「柿図」は、完璧なデザインであり、空間の処理を表しているが、尾形光琳の蔦図(藤図)は、日本人が評価した牧谿の柿図の直接の系譜に連なるものだからとその理由を述べます。
要は、デザイン感覚はもともと日本人が持ち合わせたものであり、たまたま中国人画家の牧谿の絵に、デザイン性を持つ様式を見出したのであって、中国人がもともとデザイン感覚をもっていたのではないというのでしょう。
さらに一歩踏み込んで、ドラッカーは独自の考え方で日本絵画の本質に迫ります。
まず「絵画は平面上に立体的な空間の虚構を創り出すもの」と定義し、その表現方法を、それぞれ西欧社会、中国の絵画に対して次のように対比します。
西欧世界の優れた絵画の伝統はこれを異なった方法で表現しております。ルネッサンス以来、今世紀に至るまでこれを直線的なパースペクティブ、すなわち幾何学によっておこなってきました。これに対し中国絵画は基本的にはアルジェブラティック、つまり代数的なものであります。中国絵画の理論は有名な、絵画の「三遠法」のような関係に基づくものであります。
松尾知子訳、太字部分は筆者
西欧絵画は幾何学、中国絵画を代数的と規定した後、日本絵画については次のように述べます。
ところが、日本の余白を構成するデザインはトポロジカル、すなわち位相幾何学的であります。18世紀に最初の展開を見せた数学の一分野である位相幾何学では、空間は「現実」であり、空間の構築はすなわち「視覚化」としてとらえられます。このことこそデザインが実際に試みることであり、光琳の扇面はそれを完成させるのです。
松尾知子訳、太字部分は筆者
西欧絵画が幾何学的というのは、線遠近法との関係でよく言われるので分かるとしても、中国絵画の「三遠法」は各種異論がある中、中国絵画が代数的と言われても分かりにくいところがあります。ここでは仮に一旦受け入れるとしても、さらにドラッカーの新しい日本絵画の見方、「トポロジカル」(位相幾何学的)ですが、そう言われても、突然近代数学用語が出てきたので、一般聴衆はキョトンとするばかりだったのではないでしょうか。
実はドラッカーは、この講演の4年前に、同じ根津美術館において水墨山水をテーマで講演を行っています。
次章でその講演記録を紹介しますが、そこでドラッカーは日本絵画の特徴が何故「トポロジカル」なのか、より具体的に解説していますので、そこであらためて紹介したいと思います。
(その3)に続く。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
