
記憶を嗅ぎ分けて。
視覚。聴覚。嗅覚。味覚。触覚。
人間の五感のうち、もっとも記憶に作用するのは嗅覚なのだそうだ。
いつか見た風景ではなく、懐かしい人の声でもなく、たとえば金木犀の香りが鼻をよぎった瞬間に、その人の記憶が紐解かれるのだという。
だからだろうか。
『アイダホ』(エミリー・ラスコヴィッチ 著 小竹由美子 訳 白水社)の主人公アンは、やたらと匂いを嗅ぐ。嗅ぎまくる。まるで執念深い猟犬のようだ。
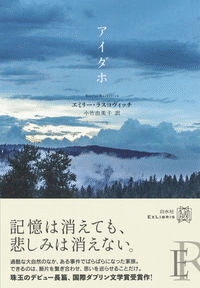
彼女の歳の離れた夫・ウエイドは、若年性認知症によって記憶を失いつつある。アンが匂いを嗅ぐのは、夫の以前の生活を思わせるものばかりだ。
トラックの運転席。クローゼットの棚から見つけた鹿皮の手袋。
そこから夏の気配だったり、幼い女の子の髪の匂いだったりを感じ取る。
いつか、ウエイドが嗅いだ匂いだ。ウエイドの記憶のどこかに、繋がっているであろう匂い。
アンは、ウエイドが過ごしたであろう日々を想像する。
何度も何度も繰り返せば、それがウエイドの記憶として積み重なっていくかのように。
匂いが呼び覚ます記憶は、個人的なものだ。同じ匂いを嗅いだからといって、記憶を共有することはできない。
アンが匂いから辿ったウエイドの記憶は、偽物だ。
アンが勝手に想像した、ウエイドが見たかもしれない景色。思ったかもしれないこと。ウエイド本人の中には存在しない記憶。
もちろん、アンにもわかっている。
しかし、アンには偽物の記憶を作り続けなければならない理由があるのだ。
結婚して8年になる二人のあいだには、どうしても分かち合えない秘密がある。
ウエイドの、前の家族のことだ。
前妻ジェニーと、二人の娘たち。
ウエイドは彼らについてほとんど話さない。だからアンも訊かない。
アンが彼らについて知っていることは、地元の人なら誰でも知っている。
ジェニーが幼い末娘をトラックの中で殺害したこと。
その現場を目撃した上の娘は森に逃げ込み、未だ行方不明であること。
ジェニーは今も刑に服しているということ。
認知症を患ってから、ウエイドは事件のことも、ジェニーや娘の存在すらも忘れてしまっているときがある。
それは、ウエイドにとって幸せなことなのだろうかとアンは思い悩む。
事件は確かに辛く痛ましい記憶でしかないだろう。しかし、それ以前の彼らは? 幸せな日々が全くなかったわけではないはずだ。ジェニーとの結婚生活、幼い娘二人の人生、その痕跡すべてを記憶の中から消し去っていいはずがないのではないか?
その葛藤から、アンは匂いを嗅ぐのである。そして、偽物の記憶を作るのである。ウエイドの代わりに、ジェニーと二人の娘を覚えていられるように。
なんという凄絶な愛なのだろう。
愛する人の愛した人たちを、自分の中でもう一度愛する。
偽物の記憶を作ってまで、追体験しようとする。家族になろうとする。
『アイダホ』には、感情的になるシーンがほとんどない。
とても淡々としている。事件の場面ですら、静かだ。
けれど、その根底を流れる愛は、渦をまくように力強く、激しい。
圧倒的な大自然を前にして、立ち尽くすことしかできないのと同じで『アイダホ』も、読後ただ茫然とするだけだ。
なんだかすごい本を読んだ気がする。
そんなふうに、いつか思い出す日がきっと来るはずだ。
いいなと思ったら応援しよう!

