
個を生かす教育を実現するための一手『松下村塾』に学ぶ和の教育観(中編)~わが国の伝統的な教育のかたちとは?~ー『日本人のこころ』7ー
こんばんは。高杉です。
日本人に「和の心」を取り戻すというスローガンのもと
『和だちプロジェクト』の代表として活動しています。
今年も2月11日が過ぎましたね!
我が国は、2024年で
皇紀2684年目を迎えました!
毎年思うのですが、
これは当たり前のことではなく、
これからも私たちがつないでいかないといけないことなのだと思うと
改めて気が引き締まりました。
和だちプロジェクトでは、
念願の紀元節をお祝いする和だち会を開催することができました!
これも、皆様のおかげです。
ありがとうございます!
引き続き、
毎週土曜日夜8時よりXスペースにて、
和だち会(和だちプロジェクト学習会)を実施していますので、
よろしくお願いいたします。
では、
本題の我が国の教育に目を向けていきましょう!
最後までお付き合いいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
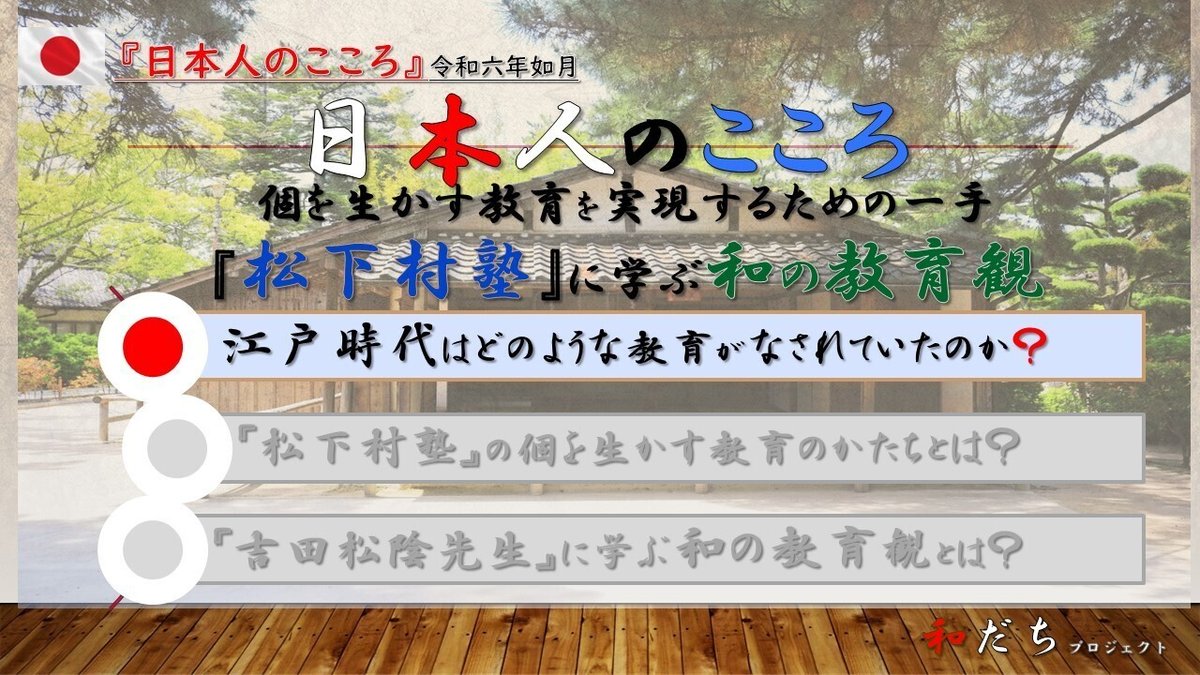
まずは、
『令和答申』でも書かれていたような
集団の中で個が埋没してしまうことになりかねない
正解主義や同町圧力といった問題がどのように生じてしまったのか?
江戸時代はどのような教育が行われていたのか?
について、
考えていきたいと思います。
1)現代の教育システムの限界とは?

わが国の義務教育は、
1872年に発布された「学制」によって始まりました。
我が国では、明治期に当たる近代に入ると
国民すべてに初等教育を施そうという考えが広がってきます。
問題は、
大勢の子供にどのように教育を施すのかということでした。
個別での指導は、子供の学習効率は高いが、
一人の教員が面倒を見ることができる人数には限界があり、
人件費面でどうにも採算が合わない。
そこで採用されたのが、
学級集団を相手にした「一斉指導」だったのです。
これにより、
一度に多くの子供が、
明治期には、80人を今と同じ広さの教室で学ぶようにすることにより、
安価に教育を行うことができる仕組みをつくったのです。
このように、
学級単位の「一斉指導」は、
学校運営の費用効率や教員による指導の効率を求める中で
編み出されました。
「一斉指導」は、
教育方法として優れていたから採用されたのではなく、
安上りであったから採用された仕組みなのです。

「一斉指導」は、
明治4(1871)年に来日したアメリカ人の外国人教師である
マリオン・スコットによって我が国に導入されました。
スコットは、
カリフォルニアの学校で使われていた教具一式を取り寄せ、
明治政府が教員養成のために東京に新設した官立師範学校に
当時のアメリカの教室をそのまま再現したのです。
授業は掛図を中心的な教材として、
あらかじめ決められてる一問一答式の問題を繰り返すというもので、
問答の内容をそのまま丸ごと復唱し、
暗記する注入主義的なものでした。
もちろん、
150年の時を経て、
今日では学級を基盤とした一斉指導も大いに改善されており、
知識の丸暗記でよしとするのではなく、深い意味理解を目指しており、
協働的な学びの要素を含むことがごく当たり前にもなっています。
しかし、
改善が進んできたとはいえ、
「一斉指導」は子供たちの間に存在する多様性をめぐって
原理的な問題を抱えています。
「一斉指導」がすべて悪とは言えないけれど、
個を生かす、個別最適という視点で見ていくと、
「一斉指導」だけでは、限界があると思うのです。
2)我が国の伝統的な教育のかたちとは?

そこでヒントになるモデルが、
我が国が伝統的に行っていた「寺子屋教育」「私塾での教育」
だと考えています。
寺子屋など近代以前の我が国の伝統的な教育方法においては、
たとえ大勢の子供が一つの部屋に居合わせても学習は個別的に進められ、
教材も一人一人違っていました。
ほとんどの時間、
子供たちは師匠がその子のために準備した教材を
各自のペースで自習をしていて、
それを一人一人順番に師匠が呼んでは、
少しの時間、個別に指導することが基本でした。

そもそも「寺子屋教育」は、
中世の「寺院教育」がもとになっていると言われています。
近世になると、
商品経済の発展に伴い庶民の生活に「読み・書き」能力が欠かせなくなり、民主の中から自然発生的に開設されるようになったと考えられています。
例えば、
農村では、農業技術の改良や新田の開発などにより、
生鮮性が高まり、種々の商品作物も栽培するようになると、
これまでの農業知識に加えて新しい知識の習得が
必要とされるようになります。
また、
商品経済が日本の津々浦々にまで浸透し、
契約書の作成や送り状などの書類作成が必要になってきます。
また、
訴状の作成など、
自分たちの生活を守るうえで文字学習は欠かせないものとなりました。
このようにして、
寺子屋が庶民の手によって創設されるようになったのです。
明治の中期に文部省は
旧藩時代の全国の藩校・郷校・寺子屋の調査を実施しました。
これに基づいて、『日本教育史資料』が刊行されましたが、
寺子屋の総数は1万5000余りと記録されています。
とりわけ19世紀に入り、幕末期には急激に増加しています。
人口比でみると、
数量的に現在の小学校に匹敵するほどの数があったのです。

「寺子屋」という名称が掲げられることはほとんどなく、
寺子屋は、一般的な呼称として用いられていたようです。
規模や経営者、教育内容などは、
その設立年代や地域によってかなり異なり、
城下町のような都市型の寺子屋においては、
経営者は武士が多く、単なる読み書きだけではなく、
『論語』や『孝経』などがテキストに用いられていることが
多かったようです。
人数は、100人から300人、
多いところでは600人近くの寺子を収容していた寺子屋もある
と記録されています。
農村や大阪のような商業都市になると、
兆人が経営する寺子屋が多く見られ、
10から20人、多いところで50人ほどの
寺子屋が多数を占めていたようです。
職業としての寺子屋が成立してからも
「教え」という行為は金銭に置き換えることができないという考え方から、
報酬としての「授業料」という形で寺子に金銭を要求することはなかったのです。
あくまでも、「お礼」として差し出されたとされています。
つまり、
寺子屋は、ボランティアで行われていたことが分かります。
江戸時代の日本は、まさに教育ボランティア大国だったのです。

寺子屋は、職業として成立しながらも、
「教え」が単なる文字の読み書き技術の授業にとどまらず、
「人としての学び」の伝統が学び手の側に存在していました。
寺子屋の学習形態は、
現在のように文部科学省という教育行政機関もなく、
また幕府や諸藩の規制も緩かったので、
地域や寺子屋の経営者によって多種多様でした。
維新前の江戸の寺子屋教育に関する調書
(『維新前東京市市立小学校教育法及維新法取調書』)によれば、
毎日の課業は「七ツ習ヒ」と称して、
「五ツ時」(現在の午前7時半ごろ)から
「八ツ時」(現在の午後2時半)までの7時間ほどが充てられていました。
寺子屋から帰宅する時間を「御八ツ」と呼び、
子供たちが空腹のまま帰宅して、
夕飯までの間に間食をとることを「おやつ」と呼ぶ習わしになりました。
全ての時間を授業に充てていたわけではなく、
女性であれば、午後から琴や三味線、裁縫などを学び、
男性の場合は、午後からそろばんを行う寺子屋もあったそうです。
休日は、毎月の一日と「五の日(5日、15日、25日)、
または6日に一度を基本としてありました。

近年、
学校での学習についていけない、
いわゆる「落ちこぼれ」が課題となっています。
「寺子屋教育」では、
基本的に「落ちこぼれ」という課題が起こりにくい学習形態が
とられていました。
寺子屋では、
基本的に子供たち同士がそれぞれの天神机を対面に位置して座り、
師匠は全員の寺子が見通せる場に位置していました。
つまり、
一斉授業を行っていないのです。
寺子の数が100人を超えても一斉授業という形態をとらないので、
子供一人一人の発達の度合いに応じた指導が可能になります。
こうした寺子屋の教育方法は、一見して経済効果が悪く、
「手間」(お金)と「暇」(時間)がかかるもののように見えますが、
一人一人異なる個性と能力をもった人間を教育することと、
均一な個性に仕上げるために一定の基準と目的を設定して、
一斉に授業することとは基本的に異なります。

寺子屋で使用されたテキストは、
一般に「往来物」と呼ばれています。
往来とは、
もともと一対の往来書簡を定型化してテキストに編集したもので、
平安時代の後期頃から登場したものです。
今日までで確認されている往来物は7000種類もあるのです。
農村地域では、
『農業往来』や『田舎往来』、『百姓往来』などがあり、
農地・農具の利用や穀物の栽培・耕作に関する、
農業労働に必要な知識や農民としての心構えなどのテキストが編まれました。
商業地域では、
商業に必要な用語で始まる『商売往来』や、
問屋の商業活動に必要な知識を中心に編纂された『問屋往来』などが刊行さ
れました。
漁村地域では、
漁業に要求される文字や知識に基づいて編纂された『浜辺小児教種(はまべしょうにおしえたね)』や『舟方往来』などがありました。
このように、
職業に関する往来物のほかに、目立つのは、
子供たちの生活圏から日本全国へと拡大する字名・村名・町名・国名などを内容とする『国尽』があります。
寺子屋のテキストとしての『往来物』は、
子供たちの生活を前提に編纂され、
しかも子供の興味と関心を引きつけるための最大努力と工夫がなされていま
した。
『往来物』を通して、
子供たちは自分たちの周りの社会を理解し、
将来の職業について学ぶのです。
寺子屋で活用された教材は、
徹底して生活中心主義と実用主義を貫いており、
庶民が「知りたい!」「知らせたい!」内容を自分たち自らの手でテキストとして編纂していたのです。
3)わたしたちが学ぶべき江戸の教育の知恵とは?

寺子屋の学習と現代の教育との大きな違いは、
試験に追い立てられ、
試験が子供たちの学校生活の中心となって緊張感を強いるということは
なかったということです。
なぜなら、
寺子屋では、卒業証書もなく、上級の学校に入学する準備も必要ではなく、
他人と競争して他人よりも良い成績をとらなければならないという必然性もなかったからです。
ただ個人の興味と生まれもった才能に任せて学んだ結果、
あるものは他人よりも学びの速度が速く、
学ぶことに強い関心を抱くことになったに過ぎないのです。
しかし、
寺子屋学習において、
試験に似たものがなかったと言えばそうでもありませんでした。
毎月一回、これまでに学習してきた手本を復習する「子さらい」と
一年に一回、一年間に学習してきた手本を暗書する「大さらい」が
行われました。
今でもこの名残で「おさらい」という言葉が残っていますよね。
すべての寺子屋で採用されていたものではありませんが、
「小さらい」も「大さらい」も、
子供たちを選別するためのものではなく、
個々の学習の到達度をみるという極めて教育的配慮の行き届いていたものなのです。

これまで、
江戸時代における我が国の伝統的な教育のかたちを見てきましたが、
ここから見えてくるものは何でしょう。
一昔前までは、
初等教育を終えただけで実社会に出ても「一人前」と呼ばれる大人が
たくさんいました。
これらの人々は、
それぞれの家庭で、地域社会で、労働の場であらゆる機会を通じて、
「一人前」になる教育を受けてきました。
家庭では、二世帯同居がふつうで
そこでの複雑な人間関係から生じるさまざまな対立・葛藤、
子供の誕生と子育て、
親しきものの老いや死の体験を通して子供は、実に様々なことを学び、そして成長してきました。
また、
地域社会の一員として、
子供から老人に至るまでそれぞれが果たさなければならない「務め」があり
ました。
小学校の高学年は、低学年の世話をしながら様々な地域の行事に参加し、
ある年齢に達すると青年団に属し、災害時には積極的に役割を果たしました。
家や社会が豊かな教育機能を有していて、
学び舎は、それを支える一部分にしか過ぎなかったのです。
学校に人間の教育をすべて詰め込もうとすること自体が問題なのです。
そして、
なによりも、
「教えること」よりも「学ぶこと」に主体をおく教育がなされていました。
学ぶ側に学びたいという意志と理由があって成立する教育の姿が
江戸時代にはあったのです。
これまでは、
江戸時代の「寺子屋教育」に主眼をおいてお話をしてきました。
先人の教育から私たちはまだまだ多くのことを学び取る必要がありますが、
あの明治時代を支えた我が国の伝統的な教育のかたちは幕末の「私塾」にも表れています。
次回は、
我が国の「私塾」での教育のかたちについて考えていきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国民一人一人が良心を持ち、
それを道標に自らが正直に、勤勉に、
かつお互いに思いやりをもって励めば、文化も経済も大いに発展し、
豊かで幸福な生活を実現できる。
極東の一小国が、明治・大正を通じて、
わずか半世紀で世界五大国の一角を担うという奇跡が実現したのは
この底力の結果です。
昭和の大東亜戦争では、
数十倍の経済力をもつ列強に対して何年も戦い抜きました。
その底力を恐れた列強は、
占領下において、教育勅語と修身教育を廃止させたのです。
戦前の修身教育で育った世代は、
その底力をもって戦後の経済復興を実現してくれました。
しかし、
その世代が引退し、戦後教育で育った世代が社会の中核になると、
経済もバブルから「失われた30年」という迷走を続けました。
道徳力が落ちれば、底力を失い、国力が衰え、政治も混迷します。

「国家百年の計は教育にあり」
という言葉があります。
教育とは、
家庭や学校、地域、職場など
あらゆる場であらゆる立場の国民が何らかのかたちで貢献することができる分野です。
教育を学校や文科省に丸投げするのではなく、
国民一人一人の取り組むべき責任があると考えるべきだと思います。
教育とは国家戦略。
『国民の修身』に代表されるように、
今の時代だからこそ、道徳教育の再興が日本復活の一手になる。
「戦前の教育は軍国主義だった」
などという批判がありますが、
実情を知っている人はどれほどいるのでしょうか。
江戸時代以前からの家庭や寺子屋、地域などによる教育伝統に根ざし、
明治以降の近代化努力を注いで形成してきた
我が国固有の教育伝統を見つめなおすことにより、
令和時代の我が国に
『日本人のこころ(和の精神)』を取り戻すための教育の在り方について
皆様と一緒に考えていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
